解説記事2007年02月12日 【会計基準解説】 改正企業会計基準適用指針第10号「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」の解説(2007年2月12日号・№198)
実務解説
改正企業会計基準適用指針第10号
「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」の解説
企業会計基準委員会 研究員 小堀一英
Ⅰ はじめに
企業会計基準委員会は、平成18年12月22日に、改正企業会計基準適用指針第10号「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(以下「改正適用指針」という。)を公表した。この改正適用指針は、平成18年5月に会社計算規則が施行されたことなどに伴い、平成17年12月に公表された企業会計基準適用指針第10号(以下「改正前適用指針」という。)を改正したものである。
本稿では、改正適用指針のうち今回の主な改正点について解説を行うとともに、公開草案から修正された点についても必要に応じ触れることとする。なお、文中意見にわたる部分は私見であることをあらかじめお断りしておく。
Ⅱ 共通支配下の取引等に関する会計処理
1 子会社が孫会社を吸収合併する場合等の会計処理
(1)子会社が孫会社を吸収合併する場合の会計処理(図表1)
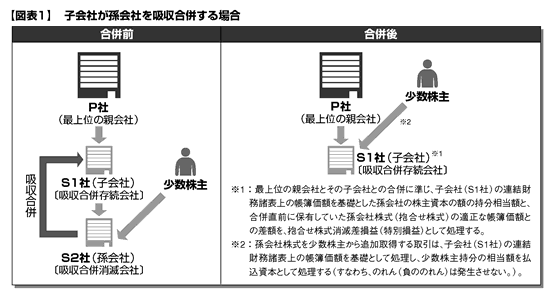
改正前適用指針では、企業集団の最上位の親会社が子会社を合併する場合の会計処理について定めていたが、改正適用指針では、企業集団の最上位の親会社以外の親会社を吸収合併存続会社としたその子会社(以下「孫会社」という。)との合併(企業集団の最上位の親会社から見た場合の、子会社と孫会社との合併)の会計処理について明らかにしている。
具体的には、子会社と孫会社の合併は、原則として、企業集団の最上位の親会社とその子会社との合併に準じて処理するものの、子会社が孫会社株式を少数株主から追加取得する取引は、企業結合会計基準にいうところの「少数株主との取引」としてではなく(第200項なお書き)(脚注1)、子会社にとっての連結財務諸表上の帳簿価額を基礎として会計処理することとされている(第206項(4)、第207項、[設例29-5])。
(2)親会社が子会社を吸収合併するにあたり、中間子会社に対価を支払う場合の会計処理
改正適用指針では、子会社が孫会社を吸収合併する場合の会計処理と併せて、親会社が子会社を吸収合併するにあたり、当該子会社の株式を保有する他の子会社(中間子会社)に合併の対価を交付する場合の取扱いも明らかにされた。
すなわち、親会社は、吸収合併した子会社の株主資本の額(脚注2)を、合併期日直前の持分比率に基づき、親会社持分相当額(親会社が直接保有する持分に相当する額)、少数株主持分相当額及び中間子会社持分相当額に按分し、そのうち中間子会社持分相当額については払込資本(資本金または資本剰余金)として処理する(第206項(3))。また、親会社持分相当額と少数株主持分相当額については、改正前適用指針と同様に、次のように処理する(第206項(2))。
・親会社持分相当額と、親会社が合併直前に保有していた子会社株式(抱合せ株式)の適正な帳簿価額との差額を、特別損益に計上する。
・少数株主持分相当額と、少数株主に交付した親会社株式の時価との差額を、のれんとして処理する。
2 子会社と他の子会社の合併における抱合せ株式の会計処理(図表2)

改正前適用指針では、同一の株主に支配されている子会社(いわゆる兄弟会社)同士の合併の会計処理については取り扱っていたものの、当該合併において吸収合併存続会社が吸収合併消滅会社の株式を有している場合の取扱いについて明確にしていなかったため、改正適用指針において明らかにされた。
すなわち、吸収合併存続会社が、吸収合併消滅会社の株式を「関連会社株式」または「その他有価証券」として保有している場合で、合併の対価として新株を発行したときの吸収合併存続会社の増加資本の会計処理は、次のいずれかの方法による(第247項(3)、第254項(3))。
① 吸収合併消滅会社の株主資本の額から当該抱合せ株式の適正な帳簿価額を控除した額を、払込資本の増加(当該差額がマイナスの場合にはその他利益剰余金の減少)として処理する。
② 吸収合併消滅会社の株主資本を引継いだ上で、抱合せ株式の適正な帳簿価額をその他資本剰余金から控除する。
3 完全親子会社関係にある組織再編において、対価が支払われない場合の会計処理
結合当事企業である各子会社が親会社に株式のすべてを保有されている場合(完全親子会社関係にある場合)における子会社同士の合併等では、実務上、親会社に合併等の対価が支払われないことがあるため、改正適用指針では、この場合における会計処理を明らかにした。なお、改正適用指針の公開草案では合併の場合の会計処理のみを定めていたが、その後に公表された会社計算規則において、会社分割の場合も同様の会計処理が認められることが明らかにされたため、改正適用指針では、会社分割の場合の会計処理についても定めている。
また、以下の会計処理は、組織再編の対価が支払われるか否かは企業集団の経済的実態には影響を与えないことが前提であるため、完全親子会社関係にある場合に限って適用されることに留意する必要がある(第437-2項)。
(1)完全親子会社関係にある場合における子会社同士の合併(図表3)
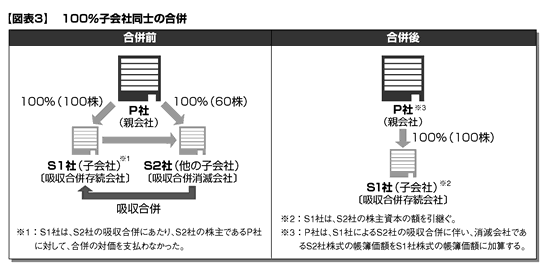
吸収合併存続会社の増加資本は、合併が共同支配企業の形成と判定された場合における「認められる会計処理」(吸収合併消滅会社の株主資本の項目を引継ぐ方法)に準じて処理する(第203-2項(1))。具体的には、会社法上、対価として株式を発行していないときは、資本金及び準備金を増加させることが適当ではないと解されるため、吸収合併消滅会社の資本金及び資本準備金はその他資本剰余金として引継ぎ、利益準備金はその他利益剰余金として引継ぐことになる。
なお、結合当事企業の株主である親会社は、吸収合併消滅会社の株式の帳簿価額を、吸収合併存続会社の株式の帳簿価額に加算することになる(第203-2項(1)なお書き)。
(2)会社分割の場合
① 親会社の事業を100%子会社に移転する場合
吸収分割会社である親会社は、分割型の会社分割における分割会社の処理に準じて、移転事業に係る資産及び負債の差額に相当する株主資本の額を変動させる(第203-2項(2)①)。なお、変動させる株主資本の内訳は、取締役会等の会社の意思決定機関において定められた額となる。
すなわち、親会社が100%子会社に事業を移転した場合に当該子会社から対価(子会社株式など)が支払われないと、親会社の個別財務諸表において株主資本が変動することになる。したがって、親会社が株主資本を変動させることなく100%子会社に事業を移転する場合には、移転した事業に見合う何らかの対価(子会社株式や現金などの財産)を、当該100%子会社から受取らなければならない点に留意が必要である(脚注3)。
また、吸収分割承継会社である子会社は、吸収分割会社である親会社で変動させた株主資本の額を、会社法の規定に基づき計上する。なお、吸収分割会社である親会社の株主は、なんら会計処理を要しないこととされている。
② 100%子会社の事業を他の100%子会社に移転する場合
吸収分割会社である100%子会社は、分割型の会社分割における分割会社の処理に準じて、移転事業に係る資産及び負債の差額に相当する株主資本の額を変動させる(第203-2項(2)②)。変動させる株主資本の内訳は、取締役会等の会社の意思決定機関において定められた額となる。
また、吸収分割承継会社である他の100%子会社は、吸収分割会社である子会社で変動させた株主資本の額を会社法の規定に基づき計上する。
なお、吸収分割会社である子会社の株主である親会社は、吸収分割会社の株式の帳簿価額から上記に従い算定された移転事業に係る資産及び負債の差額を減少させ、当該減少額を吸収分割承継会社の株式の帳簿価額に加算する。
③ 100%子会社の事業を親会社に移転する場合
吸収分割承継会社である親会社は、子会社が親会社に分割型の会社分割により事業を移転する場合の親会社の会計処理(第218項~第220項)に準じて処理する。
また、吸収分割会社である100%子会社は、子会社が親会社に分割型の会社分割により事業を移転する場合の子会社の会計処理(第221項)に準じて処理する(第203-2項(2)③)。
4 子会社が他の子会社に会社分割により事業を移転する場合の会計処理
改正前適用指針では、子会社が他の子会社に会社分割により事業を移転する場合の会計処理について示していなかったため、改正適用指針では、この場合の取扱いについて明らかにした(脚注4)。
具体的には、吸収分割会社である子会社は、個別財務諸表上及び連結財務諸表上、共通支配下の取引として、適正な帳簿価額を基礎とした会計処理を行うこととした(第254-2項、第254-3項、[設例11-4])。
なお、吸収分割会社である子会社の連結財務諸表上、当該会社分割に伴い持分変動差額が計上されることがあるが、これらを含む企業集団を支配している最上位の親会社と当該子会社の企業集団外の株主との取引である「少数株主との取引」には該当しないため、のれん(または負ののれん)は計上されない(第254-4項、[設例11-4])。
Ⅲ 株式交換及び株式移転に関する会計処理
1 株式移転設立完全親会社による子会社株式の取得原価の算定における簡便的な取扱い
改正前適用指針では、株式移転によって新設の完全親会社が取得する完全子会社(取得企業または旧親会社)の株式の取得原価は、株式移転日の前日における当該子会社の適正な帳簿価額による株主資本の額により算定することとされていた。しかしながら、合併の場合と異なり、株式移転の前日において株式移転完全子会社が決算を行い、当該子会社の適正な帳簿価額による株主資本の額を算定することは、実務上困難な場合が考えられる。
そこで、改正適用指針では、株式移転が取得または共通支配下の取引と判定された場合において、株式移転設立完全親会社が取得する株式移転完全子会社(取得企業または旧親会社)の株式の取得原価は、改正前適用指針の取扱いを原則としつつ、株式移転完全子会社の株式移転日の前日における適正な帳簿価額による株主資本の額と、直前の決算日に算定された当該金額との間に重要な差異がないと認められるときには、簡便的に、株式移転完全子会社の直前の決算日に算定された適正な帳簿価額による株主資本の額により算定することができるものとした(第121項(1)②、第239項(1)①イ)。
2 株式交換または株式移転において新株予約権付社債を承継する場合の会計処理
会社法では、株式交換または株式移転に際し、株式交換完全親会社等が株式交換完全子会社等から新株予約権付社債を承継することが可能とされているため、改正適用指針においても、その場合の株式交換完全親会社等及び株式交換完全子会社等の個別財務諸表上の会計処理について定めることとした。なお、以下では、株式移転を前提とした記載をするが、株式交換の場合の会計処理も、同様の考え方によることになる。
(1)株式移転設立完全親会社の会計処理
① 株式移転完全子会社の株式を株式移転完全子会社の適正な帳簿価額による株主資本の額により評価すべき場合
承継する新株予約権付社債を株式移転完全子会社で付されていた適正な帳簿価額により負債の部に計上するとともに、当該新株予約権付社債の承継の影響を考慮した株式移転完全子会社の株主資本相当額(税効果調整後)を、株式移転完全子会社の株式の取得原価に加算する(第118-2項、第121-2項(1)など)。
② 株式移転完全子会社の株式を時価で評価すべき場合
承継する新株予約権付社債を時価で評価したうえで負債の部に計上するとともに、同額を株式移転完全子会社の株式の取得原価に加算する(第110-2項、第121-2項(2))。
(2)株式移転完全子会社の会計処理
株式移転完全子会社は、新株予約権または新株予約権付社債に係る義務の履行を免れたため、株式移転設立完全親会社に承継された新株予約権付社債の額を利益に計上する(第115-2項、第118-3項、第123-2項など)。
なお、株式移転設立完全親会社と株式移転完全子会社が、株式移転に伴う新株予約権付社債の承継と同時に、債権債務関係を認識すべき契約を締結した場合には、株式移転設立完全親会社では債権を認識するとともに、同額を子会社株式の取得原価から控除し、一方の株式移転完全子会社では債務を認識するとともに、同額を新株予約権付社債の承継等に伴う利益から控除することが適当と考えられる(第404-2項ただし書き)。
3 株式交換または株式移転直前に子会社が自己株式を保有している場合の会計処理
会社法では、株式交換または株式移転に際し、株式交換完全親会社等は株式交換完全子会社等が保有する自己株式に株式交換等の対価を割当てる必要があるため、改正適用指針においても、株式交換等の対価として株式交換完全親会社等の株式が割当てられた場合の結合当事企業の会計処理を定めている。
(1)株式交換完全親会社等の会計処理
親会社が取得した子会社株式(子会社が保有していた自己株式)の取得原価は、時価により算定する(第238-2項、第241-2項)。
(2)株式交換完全子会社等の会計処理
子会社が自己株式と引換えに取得した親会社株式の取得原価は、親会社が付した子会社株式の取得原価を基礎として算定する。また、親会社株式の取得原価と自己株式の帳簿価額との差額は、自己株式処分差額としてその他資本剰余金に計上する(第238-3項、第241-3項)。
これらの取扱いは、①もともと、株式交換日または株式移転日に子会社が自己株式を保有するかどうか(株式交換日等の直前までに自己株式を消却するかどうか)は結合当事企業の意思で決められるものであるため、親会社と子会社との間で行う株式の交換は、当該株式交換または株式移転と一体の取引として捉える必要はなく、会計上は共通支配下の取引として処理する必然性はないこと、②子会社にとっては、資本控除されていた自己株式が親会社株式という資産に置き換わる(資本取引の対象から損益取引の対象に変わる)こととなり、新たに取得する親会社株式の時価を基礎として処理するほうが、その後の子会社の損益を適切に算定することができると考えられることによるものである(第447-3項)。
Ⅳ 自己株式に関する会計処理
企業結合に伴い自己株式が処分された場合の取扱いについて、会社計算規則の規定と整合性を図るため、また、企業会計基準第1号「自己株式及び準備金の額の減少等に関する会計基準」(以下「自己株式等会計基準」という。)が改正されたことなどにより、改正適用指針における自己株式に関する会計処理が改正されている。
1 取得と判定された場合において、取得企業が対価として自己株式を処分したときの会計処理
取得企業は、自己株式処分差額相当額(自己株式の処分の対価(時価)と帳簿価額の差額)を払込資本の増加(または減少)として処理し、当該払込資本の内訳項目(資本金、資本準備金またはその他資本剰余金)は、会社法の規定に基づき決定する(第80項、第112項など、[設例9])。
2 持分の結合と判定された場合において、結合企業が自己株式を対価として処分したときの会計処理
自己株式等会計基準の適用指針が改正されたことなどを踏まえ、結合企業は、吸収合併消滅会社の合併期日の前日の株主資本の構成をそのまま引継ぎ、処分した自己株式の帳簿価額をその他資本剰余金から控除することとされた(第135項、[設例16])。
3 持分の結合と判定された場合における自己株式の消却または消滅の会計処理
自己株式等会計基準の改正に伴い、結合企業が被結合企業の有する結合企業の株式(結合企業にとって自己株式となる。)の消却または消滅に対応して減額する株主資本項目をその他資本剰余金のみとし、吸収合併存続会社と吸収合併消滅会社のそれを区別せずに取扱う(第137項、第138項など、[設例16])。
Ⅴ その他の改正点
1 連結財務諸表原則を適用すべき企業結合に関する会計処理及び開示
企業結合に適用すべき会計基準には、企業結合に係る会計基準(適用対象は、合併、株式交換・株式移転、会社分割、事業譲渡・譲受、現物出資。以下「企業結合会計基準」という。)と連結財務諸表原則(適用対象は、現金を対価とした子会社株式の取得)があることから、連結財務諸表原則を適用すべき企業結合であっても、連結財務諸表原則に定めのない事項について企業結合会計基準の定めを適用して会計処理することが適当と考えられる場合には、企業結合会計基準の定めに準じて会計処理することができることを明らかにした(第31-2項)。ただし、企業結合会計基準の定めに準じて会計処理をした場合において、適用した会計処理に関連して、企業結合会計基準により一定の開示が求められているときは、当該定めに従い、必要な事項を開示するものとしている。
なお、企業結合会計基準の定めを適用して会計処理することが適当と考えられる場合であっても、企業結合会計基準の定めに準じて会計処理することが「できる」としたのは、企業結合会計基準一において、連結財務諸表原則に会計処理に関する定めがあるものについては企業結合会計基準の対象取引から除くこととされている点に配慮したためである。
また、連結財務諸表原則を適用すべき企業結合が行われた場合(上記のように、企業結合会計基準の定めを適用して会計処理した場合を除く。)であっても、企業結合会計基準で定められた注記事項を追加情報に準じて開示することを妨げるものではないことも明らかにされている(第31-2項、第310-2項、第316-2項)。
2 非適格合併等における税務上ののれんの税効果
平成18年度税制改正により、非適格合併等における税務上ののれん(資産調整勘定または差額負債調整勘定)に関する規定が定められたことから、改正適用指針においても、税務上ののれんの税効果に係る取扱いについて明らかにすることとした。
すなわち、税務上ののれんが認識される場合には、当該税務上ののれんの額を一時差異とみて、それに対する繰延税金資産または繰延税金負債を計上した上で、配分残余としての会計上ののれん(または負ののれん)を算定することに留意する必要があるものとされている(第72項、第378-2項)。
3 パーチェス法を適用した場合における株価の取扱い
企業結合が取得と判定され、市場価格のある取得企業等の株式が取得の対価として交付される場合、取得原価は、原則として、企業結合の合意公表日の直前数日間の株価により算定することになるが、当該株価には、終値のほか平均株価が含まれる旨が明記された(第38項(1))。
4 設例の改正
今回の改正にあたっては、以下の設例について改正(新設を含む。)を行っているため、改正適用指針の本文と併せて参照いただきたい。
〔設例5〕取得原価の算定―条件付取得対価の会計処理
〔設例9〕取得企業の増加資本の会計処理―新株の発行と自己株式の処分を併用した場合
〔設例11-4〕分離元企業の会計処理(受取対価:分離先企業の株式のみ)―分離先企業が新たに子会社となる場合―子会社が他の子会社に吸収分割により事業を移転する場合
〔設例16〕持分の結合―吸収合併存続会社の会計処理
〔設例23〕同一の株主(個人)により支配されている会社同士の合併の会計処理
〔設例25〕分割型の会社分割により子会社が親会社に事業を移転する場合の会計処理
〔設例29-5〕同一の株主(企業)により支配されている子会社同士の合併の会計処理―子会社とその子会社との合併(子会社と孫会社との合併)
Ⅵ 適用時期等
次の①から④の改正部分については、当該規則の改正が前提となるため、「会社法施行規則及び会社計算規則の一部を改正する省令」(平成18年法務省令第87号)により改正後の会社計算規則(平成18年法務省令第13号)が適用される組織再編から適用される。
① 完全親子会社関係にある組織再編において、対価が支払われない場合の会計処理(第203-2項)
② 子会社と孫会社の合併(第206項(4))
③ 孫会社から子会社への分割型の会社分割(第218項(4))
④ 子会社と他の子会社との合併における抱合せ株式の会計処理(第247項(3)及び第254項(3))
また、①から④を除く改正部分については、平成18年4月1日以後開始する事業年度から適用される。ただし、改正適用指針公表日前の組織再編(平成18年12月22日前に行われた組織再編)については、改正前の適用指針によることができることとされている。
(こぼり・かずひで)
脚注
1 企業結合会計基準に定める「少数株主との取引」に該当する場合、少数株主から追加取得する子会社株式の取得原価は、追加取得時における時価で算定することとなる。しかしながら、①子会社が孫会社株式を少数株主から取得する取引は、必ずしも親会社の立場からの外部取引とは考えられないこと、②企業結合会計基準では、親会社が自社の株式を対価として子会社株式を追加取得した場合であっても、それを時価で算定し追加的なのれんを計上してその後の利益に影響させる点については、将来の課題として残し、専ら現行の実務に与える混乱を最小にする観点から少数株主との取引が定められているため、その範囲はできるだけ限定的に解すべきと考えられることなどから、改正適用指針では「少数株主との取引」に該当しないものとして整理され、追加取得時における時価ではなく、連結財務諸表上の帳簿価額を基礎として会計処理するものとしたと考えられる。
2 親会社と子会社が合併する場合には、親会社の個別財務諸表では、原則として、適正な帳簿価額により資産及び負債を受入れるが、親会社が作成する連結財務諸表において、当該子会社の純資産等の帳簿価額を修正しているときは、個別財務諸表上も、連結財務諸表上の金額である修正後の帳簿価額(連結調整勘定を含む。)により資産及び負債を受入れる(企業結合会計基準注解(注16)、第207項)。
3 親会社の事業を100%子会社に移転し対価が支払われない場合に、移転事業に見合う金額の処理方法として、なぜ親会社の株主資本を変動させるかは直感的には理解しづらい。これは、対価として株式を発行していないときに、吸収分割会社において子会社株式を増減させること(及び吸収分割承継会社において資本金及び準備金を増加させること)が適当ではないこと、さりとて親会社において移転損益として処理することも適当ではないことから、消極的にもたらされたものと解される。また、これまでの適用指針(及び会社計算規則)の考え方との関係で整理すれば、当該会社分割は、①親会社が分割型の新設分割を行い、②同時に、100%子会社が当該新設分割承継会社を吸収合併したことと同じものと考えることもできる(なお、親会社の株主にとっては何も生じていないため、親会社の株主はなんら会計処理を要しないこととなる。)。
4 ただし、100%子会社間の会社分割であって、かつ、対価が支払われない場合には、3(2)②によることになる。
改正企業会計基準適用指針第10号
「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」の解説
企業会計基準委員会 研究員 小堀一英
Ⅰ はじめに
企業会計基準委員会は、平成18年12月22日に、改正企業会計基準適用指針第10号「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(以下「改正適用指針」という。)を公表した。この改正適用指針は、平成18年5月に会社計算規則が施行されたことなどに伴い、平成17年12月に公表された企業会計基準適用指針第10号(以下「改正前適用指針」という。)を改正したものである。
本稿では、改正適用指針のうち今回の主な改正点について解説を行うとともに、公開草案から修正された点についても必要に応じ触れることとする。なお、文中意見にわたる部分は私見であることをあらかじめお断りしておく。
Ⅱ 共通支配下の取引等に関する会計処理
1 子会社が孫会社を吸収合併する場合等の会計処理
(1)子会社が孫会社を吸収合併する場合の会計処理(図表1)
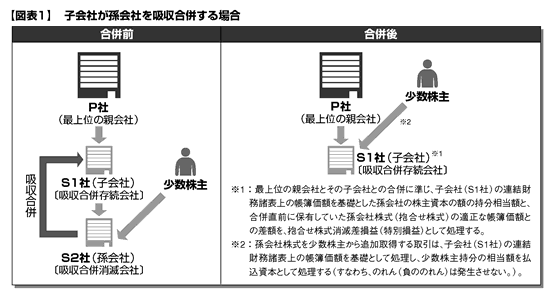
改正前適用指針では、企業集団の最上位の親会社が子会社を合併する場合の会計処理について定めていたが、改正適用指針では、企業集団の最上位の親会社以外の親会社を吸収合併存続会社としたその子会社(以下「孫会社」という。)との合併(企業集団の最上位の親会社から見た場合の、子会社と孫会社との合併)の会計処理について明らかにしている。
具体的には、子会社と孫会社の合併は、原則として、企業集団の最上位の親会社とその子会社との合併に準じて処理するものの、子会社が孫会社株式を少数株主から追加取得する取引は、企業結合会計基準にいうところの「少数株主との取引」としてではなく(第200項なお書き)(脚注1)、子会社にとっての連結財務諸表上の帳簿価額を基礎として会計処理することとされている(第206項(4)、第207項、[設例29-5])。
(2)親会社が子会社を吸収合併するにあたり、中間子会社に対価を支払う場合の会計処理
改正適用指針では、子会社が孫会社を吸収合併する場合の会計処理と併せて、親会社が子会社を吸収合併するにあたり、当該子会社の株式を保有する他の子会社(中間子会社)に合併の対価を交付する場合の取扱いも明らかにされた。
すなわち、親会社は、吸収合併した子会社の株主資本の額(脚注2)を、合併期日直前の持分比率に基づき、親会社持分相当額(親会社が直接保有する持分に相当する額)、少数株主持分相当額及び中間子会社持分相当額に按分し、そのうち中間子会社持分相当額については払込資本(資本金または資本剰余金)として処理する(第206項(3))。また、親会社持分相当額と少数株主持分相当額については、改正前適用指針と同様に、次のように処理する(第206項(2))。
・親会社持分相当額と、親会社が合併直前に保有していた子会社株式(抱合せ株式)の適正な帳簿価額との差額を、特別損益に計上する。
・少数株主持分相当額と、少数株主に交付した親会社株式の時価との差額を、のれんとして処理する。
2 子会社と他の子会社の合併における抱合せ株式の会計処理(図表2)

改正前適用指針では、同一の株主に支配されている子会社(いわゆる兄弟会社)同士の合併の会計処理については取り扱っていたものの、当該合併において吸収合併存続会社が吸収合併消滅会社の株式を有している場合の取扱いについて明確にしていなかったため、改正適用指針において明らかにされた。
すなわち、吸収合併存続会社が、吸収合併消滅会社の株式を「関連会社株式」または「その他有価証券」として保有している場合で、合併の対価として新株を発行したときの吸収合併存続会社の増加資本の会計処理は、次のいずれかの方法による(第247項(3)、第254項(3))。
① 吸収合併消滅会社の株主資本の額から当該抱合せ株式の適正な帳簿価額を控除した額を、払込資本の増加(当該差額がマイナスの場合にはその他利益剰余金の減少)として処理する。
② 吸収合併消滅会社の株主資本を引継いだ上で、抱合せ株式の適正な帳簿価額をその他資本剰余金から控除する。
3 完全親子会社関係にある組織再編において、対価が支払われない場合の会計処理
結合当事企業である各子会社が親会社に株式のすべてを保有されている場合(完全親子会社関係にある場合)における子会社同士の合併等では、実務上、親会社に合併等の対価が支払われないことがあるため、改正適用指針では、この場合における会計処理を明らかにした。なお、改正適用指針の公開草案では合併の場合の会計処理のみを定めていたが、その後に公表された会社計算規則において、会社分割の場合も同様の会計処理が認められることが明らかにされたため、改正適用指針では、会社分割の場合の会計処理についても定めている。
また、以下の会計処理は、組織再編の対価が支払われるか否かは企業集団の経済的実態には影響を与えないことが前提であるため、完全親子会社関係にある場合に限って適用されることに留意する必要がある(第437-2項)。
(1)完全親子会社関係にある場合における子会社同士の合併(図表3)
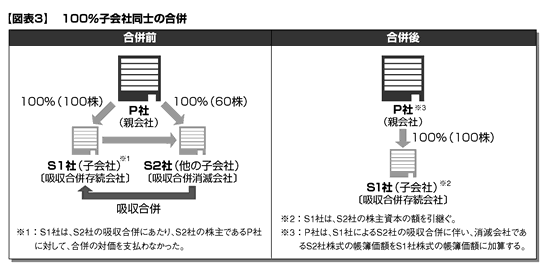
吸収合併存続会社の増加資本は、合併が共同支配企業の形成と判定された場合における「認められる会計処理」(吸収合併消滅会社の株主資本の項目を引継ぐ方法)に準じて処理する(第203-2項(1))。具体的には、会社法上、対価として株式を発行していないときは、資本金及び準備金を増加させることが適当ではないと解されるため、吸収合併消滅会社の資本金及び資本準備金はその他資本剰余金として引継ぎ、利益準備金はその他利益剰余金として引継ぐことになる。
なお、結合当事企業の株主である親会社は、吸収合併消滅会社の株式の帳簿価額を、吸収合併存続会社の株式の帳簿価額に加算することになる(第203-2項(1)なお書き)。
(2)会社分割の場合
① 親会社の事業を100%子会社に移転する場合
吸収分割会社である親会社は、分割型の会社分割における分割会社の処理に準じて、移転事業に係る資産及び負債の差額に相当する株主資本の額を変動させる(第203-2項(2)①)。なお、変動させる株主資本の内訳は、取締役会等の会社の意思決定機関において定められた額となる。
すなわち、親会社が100%子会社に事業を移転した場合に当該子会社から対価(子会社株式など)が支払われないと、親会社の個別財務諸表において株主資本が変動することになる。したがって、親会社が株主資本を変動させることなく100%子会社に事業を移転する場合には、移転した事業に見合う何らかの対価(子会社株式や現金などの財産)を、当該100%子会社から受取らなければならない点に留意が必要である(脚注3)。
また、吸収分割承継会社である子会社は、吸収分割会社である親会社で変動させた株主資本の額を、会社法の規定に基づき計上する。なお、吸収分割会社である親会社の株主は、なんら会計処理を要しないこととされている。
② 100%子会社の事業を他の100%子会社に移転する場合
吸収分割会社である100%子会社は、分割型の会社分割における分割会社の処理に準じて、移転事業に係る資産及び負債の差額に相当する株主資本の額を変動させる(第203-2項(2)②)。変動させる株主資本の内訳は、取締役会等の会社の意思決定機関において定められた額となる。
また、吸収分割承継会社である他の100%子会社は、吸収分割会社である子会社で変動させた株主資本の額を会社法の規定に基づき計上する。
なお、吸収分割会社である子会社の株主である親会社は、吸収分割会社の株式の帳簿価額から上記に従い算定された移転事業に係る資産及び負債の差額を減少させ、当該減少額を吸収分割承継会社の株式の帳簿価額に加算する。
③ 100%子会社の事業を親会社に移転する場合
吸収分割承継会社である親会社は、子会社が親会社に分割型の会社分割により事業を移転する場合の親会社の会計処理(第218項~第220項)に準じて処理する。
また、吸収分割会社である100%子会社は、子会社が親会社に分割型の会社分割により事業を移転する場合の子会社の会計処理(第221項)に準じて処理する(第203-2項(2)③)。
4 子会社が他の子会社に会社分割により事業を移転する場合の会計処理
改正前適用指針では、子会社が他の子会社に会社分割により事業を移転する場合の会計処理について示していなかったため、改正適用指針では、この場合の取扱いについて明らかにした(脚注4)。
具体的には、吸収分割会社である子会社は、個別財務諸表上及び連結財務諸表上、共通支配下の取引として、適正な帳簿価額を基礎とした会計処理を行うこととした(第254-2項、第254-3項、[設例11-4])。
なお、吸収分割会社である子会社の連結財務諸表上、当該会社分割に伴い持分変動差額が計上されることがあるが、これらを含む企業集団を支配している最上位の親会社と当該子会社の企業集団外の株主との取引である「少数株主との取引」には該当しないため、のれん(または負ののれん)は計上されない(第254-4項、[設例11-4])。
Ⅲ 株式交換及び株式移転に関する会計処理
1 株式移転設立完全親会社による子会社株式の取得原価の算定における簡便的な取扱い
改正前適用指針では、株式移転によって新設の完全親会社が取得する完全子会社(取得企業または旧親会社)の株式の取得原価は、株式移転日の前日における当該子会社の適正な帳簿価額による株主資本の額により算定することとされていた。しかしながら、合併の場合と異なり、株式移転の前日において株式移転完全子会社が決算を行い、当該子会社の適正な帳簿価額による株主資本の額を算定することは、実務上困難な場合が考えられる。
そこで、改正適用指針では、株式移転が取得または共通支配下の取引と判定された場合において、株式移転設立完全親会社が取得する株式移転完全子会社(取得企業または旧親会社)の株式の取得原価は、改正前適用指針の取扱いを原則としつつ、株式移転完全子会社の株式移転日の前日における適正な帳簿価額による株主資本の額と、直前の決算日に算定された当該金額との間に重要な差異がないと認められるときには、簡便的に、株式移転完全子会社の直前の決算日に算定された適正な帳簿価額による株主資本の額により算定することができるものとした(第121項(1)②、第239項(1)①イ)。
2 株式交換または株式移転において新株予約権付社債を承継する場合の会計処理
会社法では、株式交換または株式移転に際し、株式交換完全親会社等が株式交換完全子会社等から新株予約権付社債を承継することが可能とされているため、改正適用指針においても、その場合の株式交換完全親会社等及び株式交換完全子会社等の個別財務諸表上の会計処理について定めることとした。なお、以下では、株式移転を前提とした記載をするが、株式交換の場合の会計処理も、同様の考え方によることになる。
(1)株式移転設立完全親会社の会計処理
① 株式移転完全子会社の株式を株式移転完全子会社の適正な帳簿価額による株主資本の額により評価すべき場合
承継する新株予約権付社債を株式移転完全子会社で付されていた適正な帳簿価額により負債の部に計上するとともに、当該新株予約権付社債の承継の影響を考慮した株式移転完全子会社の株主資本相当額(税効果調整後)を、株式移転完全子会社の株式の取得原価に加算する(第118-2項、第121-2項(1)など)。
② 株式移転完全子会社の株式を時価で評価すべき場合
承継する新株予約権付社債を時価で評価したうえで負債の部に計上するとともに、同額を株式移転完全子会社の株式の取得原価に加算する(第110-2項、第121-2項(2))。
(2)株式移転完全子会社の会計処理
株式移転完全子会社は、新株予約権または新株予約権付社債に係る義務の履行を免れたため、株式移転設立完全親会社に承継された新株予約権付社債の額を利益に計上する(第115-2項、第118-3項、第123-2項など)。
なお、株式移転設立完全親会社と株式移転完全子会社が、株式移転に伴う新株予約権付社債の承継と同時に、債権債務関係を認識すべき契約を締結した場合には、株式移転設立完全親会社では債権を認識するとともに、同額を子会社株式の取得原価から控除し、一方の株式移転完全子会社では債務を認識するとともに、同額を新株予約権付社債の承継等に伴う利益から控除することが適当と考えられる(第404-2項ただし書き)。
3 株式交換または株式移転直前に子会社が自己株式を保有している場合の会計処理
会社法では、株式交換または株式移転に際し、株式交換完全親会社等は株式交換完全子会社等が保有する自己株式に株式交換等の対価を割当てる必要があるため、改正適用指針においても、株式交換等の対価として株式交換完全親会社等の株式が割当てられた場合の結合当事企業の会計処理を定めている。
(1)株式交換完全親会社等の会計処理
親会社が取得した子会社株式(子会社が保有していた自己株式)の取得原価は、時価により算定する(第238-2項、第241-2項)。
(2)株式交換完全子会社等の会計処理
子会社が自己株式と引換えに取得した親会社株式の取得原価は、親会社が付した子会社株式の取得原価を基礎として算定する。また、親会社株式の取得原価と自己株式の帳簿価額との差額は、自己株式処分差額としてその他資本剰余金に計上する(第238-3項、第241-3項)。
これらの取扱いは、①もともと、株式交換日または株式移転日に子会社が自己株式を保有するかどうか(株式交換日等の直前までに自己株式を消却するかどうか)は結合当事企業の意思で決められるものであるため、親会社と子会社との間で行う株式の交換は、当該株式交換または株式移転と一体の取引として捉える必要はなく、会計上は共通支配下の取引として処理する必然性はないこと、②子会社にとっては、資本控除されていた自己株式が親会社株式という資産に置き換わる(資本取引の対象から損益取引の対象に変わる)こととなり、新たに取得する親会社株式の時価を基礎として処理するほうが、その後の子会社の損益を適切に算定することができると考えられることによるものである(第447-3項)。
Ⅳ 自己株式に関する会計処理
企業結合に伴い自己株式が処分された場合の取扱いについて、会社計算規則の規定と整合性を図るため、また、企業会計基準第1号「自己株式及び準備金の額の減少等に関する会計基準」(以下「自己株式等会計基準」という。)が改正されたことなどにより、改正適用指針における自己株式に関する会計処理が改正されている。
1 取得と判定された場合において、取得企業が対価として自己株式を処分したときの会計処理
取得企業は、自己株式処分差額相当額(自己株式の処分の対価(時価)と帳簿価額の差額)を払込資本の増加(または減少)として処理し、当該払込資本の内訳項目(資本金、資本準備金またはその他資本剰余金)は、会社法の規定に基づき決定する(第80項、第112項など、[設例9])。
2 持分の結合と判定された場合において、結合企業が自己株式を対価として処分したときの会計処理
自己株式等会計基準の適用指針が改正されたことなどを踏まえ、結合企業は、吸収合併消滅会社の合併期日の前日の株主資本の構成をそのまま引継ぎ、処分した自己株式の帳簿価額をその他資本剰余金から控除することとされた(第135項、[設例16])。
3 持分の結合と判定された場合における自己株式の消却または消滅の会計処理
自己株式等会計基準の改正に伴い、結合企業が被結合企業の有する結合企業の株式(結合企業にとって自己株式となる。)の消却または消滅に対応して減額する株主資本項目をその他資本剰余金のみとし、吸収合併存続会社と吸収合併消滅会社のそれを区別せずに取扱う(第137項、第138項など、[設例16])。
Ⅴ その他の改正点
1 連結財務諸表原則を適用すべき企業結合に関する会計処理及び開示
企業結合に適用すべき会計基準には、企業結合に係る会計基準(適用対象は、合併、株式交換・株式移転、会社分割、事業譲渡・譲受、現物出資。以下「企業結合会計基準」という。)と連結財務諸表原則(適用対象は、現金を対価とした子会社株式の取得)があることから、連結財務諸表原則を適用すべき企業結合であっても、連結財務諸表原則に定めのない事項について企業結合会計基準の定めを適用して会計処理することが適当と考えられる場合には、企業結合会計基準の定めに準じて会計処理することができることを明らかにした(第31-2項)。ただし、企業結合会計基準の定めに準じて会計処理をした場合において、適用した会計処理に関連して、企業結合会計基準により一定の開示が求められているときは、当該定めに従い、必要な事項を開示するものとしている。
なお、企業結合会計基準の定めを適用して会計処理することが適当と考えられる場合であっても、企業結合会計基準の定めに準じて会計処理することが「できる」としたのは、企業結合会計基準一において、連結財務諸表原則に会計処理に関する定めがあるものについては企業結合会計基準の対象取引から除くこととされている点に配慮したためである。
また、連結財務諸表原則を適用すべき企業結合が行われた場合(上記のように、企業結合会計基準の定めを適用して会計処理した場合を除く。)であっても、企業結合会計基準で定められた注記事項を追加情報に準じて開示することを妨げるものではないことも明らかにされている(第31-2項、第310-2項、第316-2項)。
2 非適格合併等における税務上ののれんの税効果
平成18年度税制改正により、非適格合併等における税務上ののれん(資産調整勘定または差額負債調整勘定)に関する規定が定められたことから、改正適用指針においても、税務上ののれんの税効果に係る取扱いについて明らかにすることとした。
すなわち、税務上ののれんが認識される場合には、当該税務上ののれんの額を一時差異とみて、それに対する繰延税金資産または繰延税金負債を計上した上で、配分残余としての会計上ののれん(または負ののれん)を算定することに留意する必要があるものとされている(第72項、第378-2項)。
3 パーチェス法を適用した場合における株価の取扱い
企業結合が取得と判定され、市場価格のある取得企業等の株式が取得の対価として交付される場合、取得原価は、原則として、企業結合の合意公表日の直前数日間の株価により算定することになるが、当該株価には、終値のほか平均株価が含まれる旨が明記された(第38項(1))。
4 設例の改正
今回の改正にあたっては、以下の設例について改正(新設を含む。)を行っているため、改正適用指針の本文と併せて参照いただきたい。
〔設例5〕取得原価の算定―条件付取得対価の会計処理
〔設例9〕取得企業の増加資本の会計処理―新株の発行と自己株式の処分を併用した場合
〔設例11-4〕分離元企業の会計処理(受取対価:分離先企業の株式のみ)―分離先企業が新たに子会社となる場合―子会社が他の子会社に吸収分割により事業を移転する場合
〔設例16〕持分の結合―吸収合併存続会社の会計処理
〔設例23〕同一の株主(個人)により支配されている会社同士の合併の会計処理
〔設例25〕分割型の会社分割により子会社が親会社に事業を移転する場合の会計処理
〔設例29-5〕同一の株主(企業)により支配されている子会社同士の合併の会計処理―子会社とその子会社との合併(子会社と孫会社との合併)
Ⅵ 適用時期等
次の①から④の改正部分については、当該規則の改正が前提となるため、「会社法施行規則及び会社計算規則の一部を改正する省令」(平成18年法務省令第87号)により改正後の会社計算規則(平成18年法務省令第13号)が適用される組織再編から適用される。
① 完全親子会社関係にある組織再編において、対価が支払われない場合の会計処理(第203-2項)
② 子会社と孫会社の合併(第206項(4))
③ 孫会社から子会社への分割型の会社分割(第218項(4))
④ 子会社と他の子会社との合併における抱合せ株式の会計処理(第247項(3)及び第254項(3))
また、①から④を除く改正部分については、平成18年4月1日以後開始する事業年度から適用される。ただし、改正適用指針公表日前の組織再編(平成18年12月22日前に行われた組織再編)については、改正前の適用指針によることができることとされている。
(こぼり・かずひで)
脚注
1 企業結合会計基準に定める「少数株主との取引」に該当する場合、少数株主から追加取得する子会社株式の取得原価は、追加取得時における時価で算定することとなる。しかしながら、①子会社が孫会社株式を少数株主から取得する取引は、必ずしも親会社の立場からの外部取引とは考えられないこと、②企業結合会計基準では、親会社が自社の株式を対価として子会社株式を追加取得した場合であっても、それを時価で算定し追加的なのれんを計上してその後の利益に影響させる点については、将来の課題として残し、専ら現行の実務に与える混乱を最小にする観点から少数株主との取引が定められているため、その範囲はできるだけ限定的に解すべきと考えられることなどから、改正適用指針では「少数株主との取引」に該当しないものとして整理され、追加取得時における時価ではなく、連結財務諸表上の帳簿価額を基礎として会計処理するものとしたと考えられる。
2 親会社と子会社が合併する場合には、親会社の個別財務諸表では、原則として、適正な帳簿価額により資産及び負債を受入れるが、親会社が作成する連結財務諸表において、当該子会社の純資産等の帳簿価額を修正しているときは、個別財務諸表上も、連結財務諸表上の金額である修正後の帳簿価額(連結調整勘定を含む。)により資産及び負債を受入れる(企業結合会計基準注解(注16)、第207項)。
3 親会社の事業を100%子会社に移転し対価が支払われない場合に、移転事業に見合う金額の処理方法として、なぜ親会社の株主資本を変動させるかは直感的には理解しづらい。これは、対価として株式を発行していないときに、吸収分割会社において子会社株式を増減させること(及び吸収分割承継会社において資本金及び準備金を増加させること)が適当ではないこと、さりとて親会社において移転損益として処理することも適当ではないことから、消極的にもたらされたものと解される。また、これまでの適用指針(及び会社計算規則)の考え方との関係で整理すれば、当該会社分割は、①親会社が分割型の新設分割を行い、②同時に、100%子会社が当該新設分割承継会社を吸収合併したことと同じものと考えることもできる(なお、親会社の株主にとっては何も生じていないため、親会社の株主はなんら会計処理を要しないこととなる。)。
4 ただし、100%子会社間の会社分割であって、かつ、対価が支払われない場合には、3(2)②によることになる。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -

Copyright (C) 2019
SHINNIPPON-HOKI PUBLISHING CO.,LTD.




















