解説記事2007年04月09日 【制度解説】 減価償却制度見直しに係る税制、会計上の取扱い(2007年4月9日号・№206)
減価償却制度見直しに係る税制、会計上の取扱い
(社)日本経済団体連合会税制・会計グループ長 井上 隆
平成19年度税制改正では、大正7年の制度創設以来の大改革ともいわれる、減価償却制度の抜本的見直しが行われた。これにより、わが国の減価償却制度は米国や韓国などに比べても遜色のない制度となり、国際競争力の強化や設備投資の一層の促進に資することが期待される。本稿では、3月30日に公布された政省令によって明らかとなった新しい減価償却制度および企業会計上の取扱いについて概観する。なお、文中、意見にわたる部分については私見であることを予めお断りしておきたい。
Ⅰ 減価償却制度見直しの背景
企業の国際競争が一層熾烈さを増す中で、活動のインフラとなる制度の国際的な整合性が求められている。とりわけ、企業が国を選ぶ時代において、法人税制の整合性確保は不可欠であり、諸外国と比して、わが国が競争上不利な状況となっている大きな課題として、法人実効税率の引下げとともに減価償却制度の見直しの必要性が指摘されていた(図表1参照)。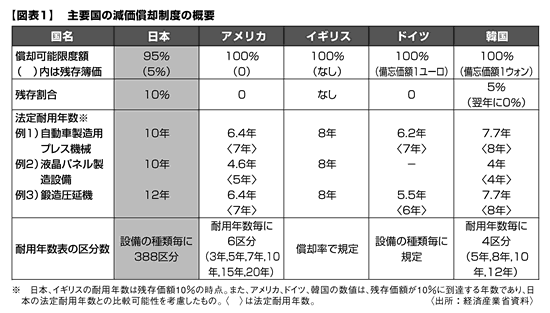 また、バブル崩壊後の長いトンネルを漸く抜け出したわが国が、急速に進む少子高齢化社会において、引き続き安定的な成長を遂げていくためには、設備投資を活性化させ生産性を向上させるなど、将来の成長への礎を築く必要があり、この点からも減価償却制度の早急な見直しが求められていた。
また、バブル崩壊後の長いトンネルを漸く抜け出したわが国が、急速に進む少子高齢化社会において、引き続き安定的な成長を遂げていくためには、設備投資を活性化させ生産性を向上させるなど、将来の成長への礎を築く必要があり、この点からも減価償却制度の早急な見直しが求められていた。
減価償却制度見直しの主要論点としては、①償却可能限度額(95%)の撤廃、②残存価額の撤廃、③償却カーブの見直し、④耐用年数の見直し、⑤償却資産に係る固定資産税の見直し、などが掲げられた。日本経団連をはじめとする産業界から、上記の各論点に対する強い働きかけもあり、昨年末の与党税制改正大綱(平成18年12月14日)では、以下の通り、減価償却の抜本的な見直しが明記されることとなった。
「わが国経済の持続的成長を実現するためには、設備投資を促進し、生産手段の新陳代謝を加速することにより、国際競争力の強化を図る必要がある。このような観点から、減価償却制度の抜本的見直しを行う。具体的には、主要国の中ではわが国においてのみ設けられている償却可能限度額(95%)を撤廃する。また、新規取得資産について法定耐用年数内に取得価額全額を償却できるよう制度を見直し、残存価額(10%)を廃止するとともに、250%定率法を導入し、償却率についても国際的に遜色のない水準に設定する。同時に、フラットパネルディスプレイ製造設備等、3設備の法定耐用年数について見直しを行う。なお、固定資産税の償却資産については、資産課税としての性格を踏まえ、現行の評価方法を維持する。」
すなわち、上記各論点のうち⑤の固定資産税の見直しを除き、①から④の論点については、今回の税制改正により抜本的な見直しが図られることとなった。固定資産税に関しては、減価償却制度が所得課税に係る費用配分手法であるのに対し、資産課税であることから今回の見直しの対象外とされたところである。しかし、長らく納税者負担の軽減の観点から両者の調整が図られてきた点、ならびに今回の減価償却制度の抜本見直しの基礎となった調査によれば償却資産の残存価値は限りなくゼロに近いことが明らかとなっており、5%の残存価額を維持することの合理的な理由が乏しい点を踏まえれば、将来的には、償却資産に係る固定資産税のあり方についても抜本的な見直しが不可欠となろう。
なお、耐用年数の短縮が行われた3設備とは、フラットパネルディスプレイ製造設備(10年を5年に短縮)のほか、フラットパネル用フィルム製造設備(10年を5年に短縮)、半導体用フォトレジスト製造設備(8年を5年に短縮)の3設備である。
Ⅱ 新たな減価償却制度の概要
1 新たな償却カーブの考え方
与党大綱に示された通り、今回の見直しでは、「法定耐用年数内に」「取得価額全額を(備忘価額1円まで)償却できる」こととされ、定率法に関しては、「250%定率法を導入」することとなった。
すなわち、従来、定額法、定率法とも95%の償却可能限度額に到達した後には償却はできないままになっていたが、今回の制度改正では、定額法に関しては耐用年数内で均等で、また、定率法に関しては250%定率法により耐用年数内で償却が行われる(図表2参照)。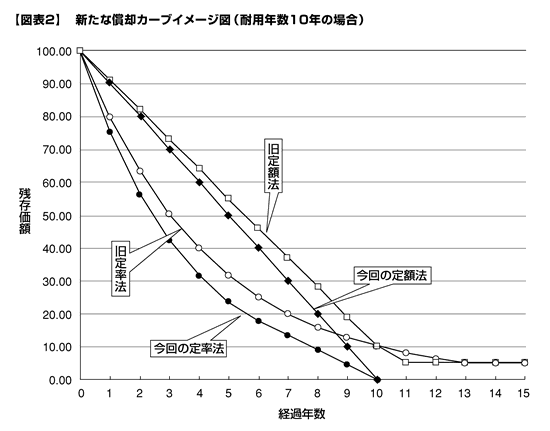
250%定率法とは、定額法で償却した場合の償却率(1/法定耐用年数)に対して2.5を乗じた数を定率法の償却率として計算する方法である。そして、法定耐用年数内に取得価額全額を償却できるように、償却額が一定の金額を下回ることとなったときに、償却方法を定額法に切り替えて減価償却費を計算することとされている。一定の金額とは、耐用年数から経過年数を控除した期間内に、その時の帳簿価額を均等償却すると仮定して計算した金額が基礎となる。これにより、償却額が毎年一定の割合で逓減する形で、耐用年数内での減価償却が行われることとなる。
2 具体的な取扱い
(1)旧制度との関係
新たな減価償却制度は、「平成19年4月1日以後に取得をされた減価償却資産」から適用される(法人税法施行令48条の2第1項)。適用は、事業年度ベースではなく、取得ベースであることに留意する必要がある。なお、3月31日以前に取得をした上で、4月1日以後に事業の用に供した減価償却資産については、適用は事業の用に供した日において当該減価償却資産の取得をしたものとみなして適用される(施行令附則11条2項)。
平成19年3月31日以前に取得をされた減価償却資産の償却の方法は、制度上、「旧定額法」、「旧定率法」と呼ばれることとなり(施行令48条の1第1項)、従来通りの償却限度額の計算が行われることとなる。そして、これらの旧制度を採用している減価償却資産につき、償却の額の累計額がその取得価額の100分の95(旧償却可能限度額)に達した場合には、翌事業年度からは、当該資産の取得価額から100分の95および備忘価額である1円を控除した金額を60(カ月)で除し、これに各事業年度の月数を乗じて計算した金額をもって償却限度額とみなすこととされている(施行令61条2項)。すなわち、旧償却可能限度額に達した減価償却資産については、翌事業年度から5年間の均等償却によって償却が可能となる。なお、均等償却の開始は翌事業年度から行われるため、たとえば、平成18年12月末終了事業年度において既に旧償却可能限度額に達した減価償却資産については、制度施行後の翌事業年度である平成20年12月末終了事業年度から均等償却が開始されることとなる。
また、耐用年数が短縮され新たに耐用年数表に加えられた3設備の新耐用年数は、平成19年4月1日以後に開始する事業年度から適用となるので、平成19年3月31日以前に取得をされた減価償却資産であっても、施行日以後の事業年度においては償却限度額の計算上、新たな耐用年数が適用される(耐用年数省令附則4)。
(2)定率法
定率法は、「減価償却資産の取得価額(既にした償却の額で各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額がある場合には、当該金額を控除した金額=未償却残額)にその償却費が毎年一定の割合で逓減するように当該資産の耐用年数に応じた償却率を乗じて計算した金額を各事業年度の償却限度額として償却する方法」であり(施行令48条の2第1項2号)、旧定率法と基本構造には何ら変化がない。但し、1(新たな償却カーブの考え方)で示した通り、耐用年数内で備忘価額まで償却を行うことができるよう、償却限度額が一定の金額を下回った時点から、別の償却率が用いられる(図表3参照)。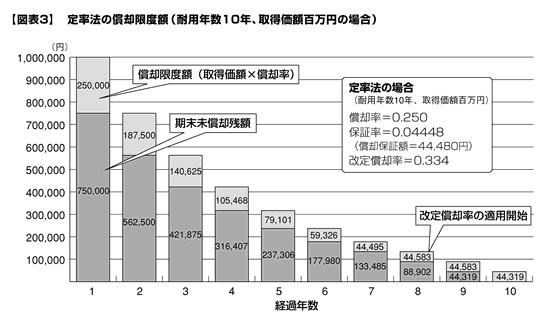
制度上、この一定の金額は「償却保証額」と呼ばれ、減価償却資産の取得価額に当該資産の耐用年数に応じた「保証率」を乗じて計算される。そして、償却額が「償却保証額」に満たないこととなった事業年度から、その後の償却費が毎年同一となるように、「改定取得価額」(満たないこととなった事業年度期首の未償却残額)に「改定償却率」を乗じた金額がそれ以後の各事業年度の償却限度額となり、備忘価額まで償却が行われることとなる。
これらの計算に必要な、「償却率」「保証率」「改定償却率」については、財務省令により耐用年数ごとに定められている(耐用年数省令別表第10)。
(3)定額法
残存価額が廃止されたことから、定額法については、「減価償却資産の取得価額にその償却費が毎年同一となるように当該資産の耐用年数に応じた償却率を乗じて計算した金額を各事業年度の償却限度額として償却する方法」となる(施行令48条の2第1項1号)。新たな償却率については耐用年数省令に定められている。
なお、建物については平成10年度税制改正により、定額法と定率法の選択制が廃止され定額法への一本化が図られていることから、平成10年3月31日以前に取得をされた建物については旧定額法と旧定率法の選択制、平成10年4月1日以後、平成19年3月31日以前に取得をされた建物については旧定額法、平成19年4月1日以後に取得をされた建物については定額法が適用されることとなる(施行令48条1項)。
(4)リース資産等
平成19年度税制改正では、リース会計基準の変更に伴い、平成20年4月1日以後に締結する契約所有権移転外ファイナンスリースは売買取引とみなされることとなった。これに伴い、当該リース資産については、リース期間定額法により減価償却が行われる。リース期間定額法とは、当該リース資産の取得価額をリース資産のリース期間の月数で除して計算した金額に当該事業年度におけるリース期間の月数を乗じて計算した金額を各事業年度の償却限度額として償却する方法である(施行令48条の2第1項6号)。
また、鉱業用減価償却資産等に係る生産高比例法に関しては、旧生産高比例法の計算に用いられていた残存価額を廃止して計算されることとなる。さらに、取替法の計算に関しては、取得価額の100分の50に達するまでの計算方法として旧定額法、旧定率法に加え、定額法、定率法が加えられた。
(5)資本的支出の取扱い
減価償却資産について支出する資本的支出については、その減価償却資産と種類および耐用年数を同じくする減価償却資産を新たに取得したものとして、別個に償却限度額の計算が行われる(施行令55条1項)。この計算は、元の減価償却資産の取得時期にかかわらず、資本的支出が平成19年4月1日以後に行われた場合すべてに適用される。
なお、旧減価償却の方法を採用している減価償却資産、すなわち、平成19年3月31日以前に取得をされた減価償却資産に対する資本的支出については、従来通りの方法で、取得価額に加算の上、旧減価償却方法により償却限度額の計算を行うことも可能である(施行令55条2項)。
資本的支出の取扱いとしては、実務負担を軽減する観点から、上記に加え2つの選択肢が用意されている(図表4参照)。第一は、定率法(すなわち平成19年4月1日以後に取得をされた減価償却資産に限られる)を採用しているときは、資本的支出があった事業年度の翌事業年度開始の時に、元の減価償却資産(「旧減価償却資産」という)の翌事業年度期首帳簿価額と新たに減価償却資産を取得したものとして扱われた資本的支出(「追加償却資産」という)の翌事業年度期首帳簿価額の合計額をもって、改めて一の減価償却資産を新たに取得したものとする方法である。これにより資本的支出の数が多数に及ぶ場合であっても、翌事業年度から常に一の減価償却資産を取得したものとして計算することが可能となる(施行令55条4項)。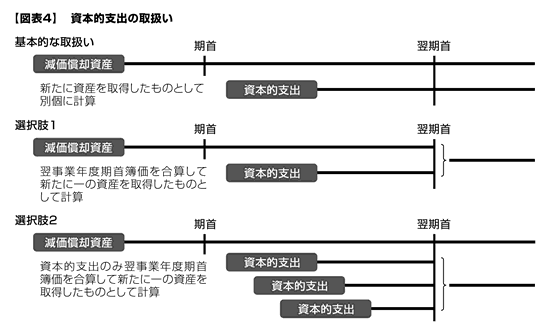
第二は、定率法を採用している複数の資本的支出があった事業年度の翌事業年度開始の時に、種類および耐用年数を同じくする資本的支出を合算し、元の減価償却資産とは別個に、改めて一の減価償却資産を新たに取得したものとする方法である。これにより、複数の資本的支出を翌事業年度から一括して処理することが可能となる(施行令55条5項)。
(6)届け出関係等
法人は申告書の提出期限までに、償却の方法を納税地の所轄税務署長に届け出なければならないが、平成19年3月31日以前に取得をされた減価償却資産について既に旧定額法、旧定率法、旧生産高比例法を選定している場合で、届け出を行わないときには、各々、定額法、定率法、生産高比例法を選定したものとみなされる(施行令51条3項)。
また、償却方法を変更しようとするときには、その新たな償却の方法を採用しようとする事業年度開始の日の前日までに、申請書を所轄税務署長に提出しなければならないが、施行日以後、最初に終了する事業年度においては、申告書の提出期限までに「届出書」を提出すれば、当該申請が行われ、かつ承認があったものとみなされる(施行令附則11条3項)。
Ⅲ 会計・監査上の取扱い
減価償却資産につきその償却費として損金の額に算入する金額は、当該事業年度においてその償却費として損金経理をした金額のうち、償却限度額に達するまでの金額である。いわゆる損金経理要件は、新しい減価償却制度の下でも不変であることから、会計上、とりわけ監査人による監査において、公正妥当な会計処理として取り扱われるか否かが重要となる。
日本公認会計士協会では、平成19年3月8日に公開草案「減価償却に関する当面の監査上の取扱い」を公表している。当該公開草案による、平成19年度税制改正による減価償却制度の見直しに関する監査上の取扱いは以下のとおりである。
1 減価償却の考え方
草案では、まず、「従来の会計実務において認められてきた減価償却方法については今後も容認できるとの立場を堅持しつつ、今回の税制改正に関する当面の監査上の取扱いを示す」こととしている。その上で、「多くの企業が法人税法に定められた耐用年数を用いており、また同様に残存価額の設定についても多くの企業が法人税法の規定にしたがっているのが現状である」とし、「法人税法に規定する普通償却限度額を正規の減価償却費として処理する場合においては、企業の状況に照らし、耐用年数又は残存価額に不合理と認められる事情のない限り、当面、監査上妥当なものとして取り扱うことができる」旨を示している。
2 平成19年度改正について
平成19年度改正に伴う監査上の取扱いとして、草案では、改正前後の定率法、(旧)定率法、定額法、(旧)定額法、の4通りの選択肢についてマトリックスを示し、各々、新規取得資産、既存資産の取扱いの整理を行っている(図表5参照)。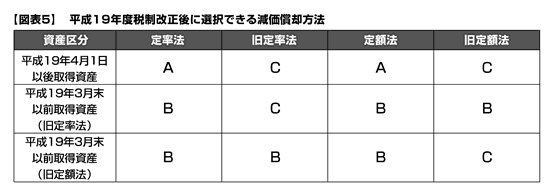 そして、「既存資産について従来の(旧)定率法を採用していた場合に、新規取得資産について(新)定率法を、あるいは、従来の(旧)定額法を採用していた場合に(新)定額法をそれぞれ採用する場合には、同一種類で同一用途の減価償却資産について、類似の減価償却方法を採用するものと認められるため、法令等の改正に伴う変更に準じた正当な理由による会計方針の変更として取り扱うものとする」こととされている(図表5Aのケース)。
そして、「既存資産について従来の(旧)定率法を採用していた場合に、新規取得資産について(新)定率法を、あるいは、従来の(旧)定額法を採用していた場合に(新)定額法をそれぞれ採用する場合には、同一種類で同一用途の減価償却資産について、類似の減価償却方法を採用するものと認められるため、法令等の改正に伴う変更に準じた正当な理由による会計方針の変更として取り扱うものとする」こととされている(図表5Aのケース)。
これ以外の変更(たとえば、(旧)定率法から(新)定額法への変更や、既存資産に(新)定額法や(新)定率法を適用する場合など)については、「会計方針の変更として取り扱うことになるが、単に法人税法の改正を理由とするだけでは正当な理由に該当せず、変更理由の合理性及び適時性に留意する必要がある」とされている(図表5Bのケース。なおCについては変更には当たらない)。
なお、既存資産について、(旧)償却可能限度額に達した減価償却資産を翌事業年度から5年間で均等償却することに関しても監査上妥当なものとして取り扱うこととされている。一方、5年間の均等償却ではなく、一括処理することに関しては、「減損会計基準の適用による減損損失が認められる等、合理的理由がある場合のみに容認される」ものとされている。
また、減価償却システムの変更に時間を要するなどの理由によって、適用初年度の中間財務諸表において新たな減価償却計算を行うことが困難な場合があることに配慮し、このような場合には、年度財務諸表において必要な注記が求められることとなる。 (いのうえ・たかし)
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -

Copyright (C) 2019
SHINNIPPON-HOKI PUBLISHING CO.,LTD.




















