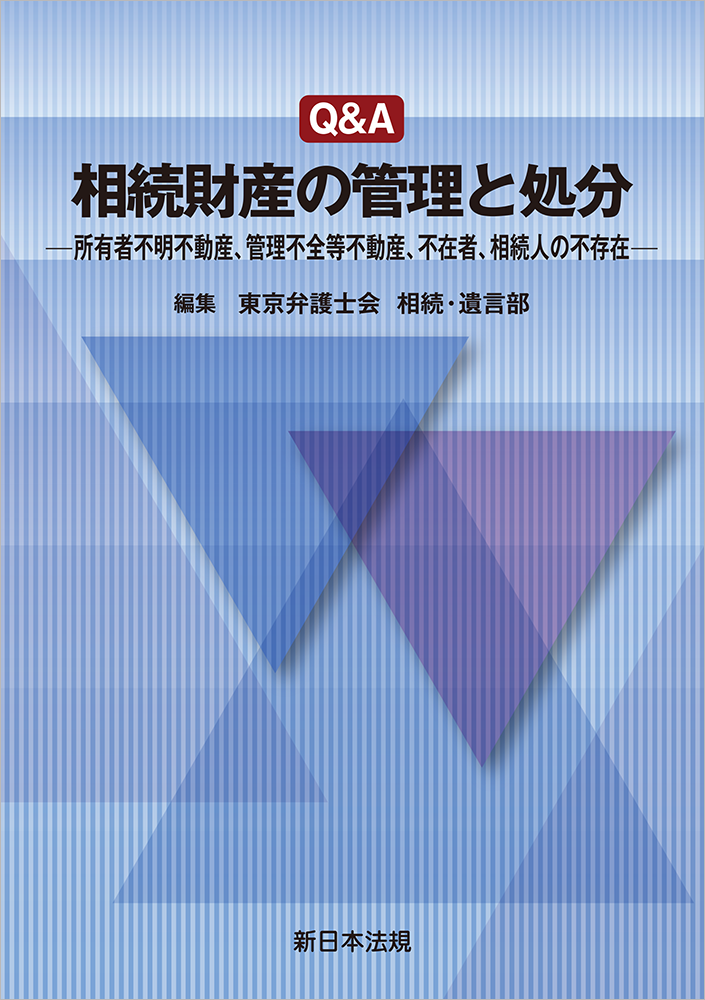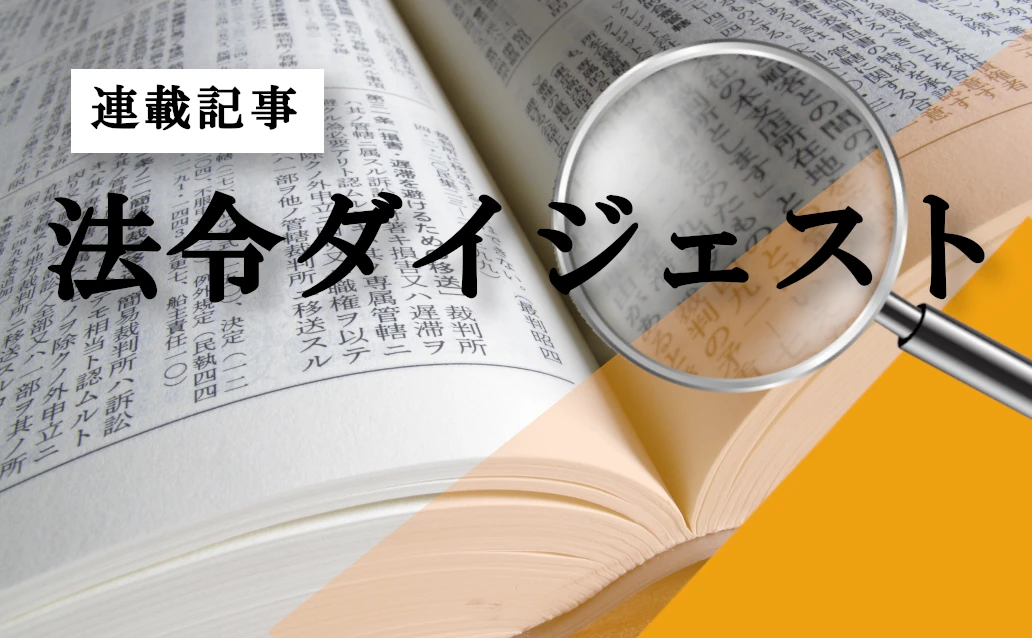解説記事2007年04月23日 【編集部解説】 減価償却の新別表と別表記載上の留意点(2007年4月23日号・№208)
実務解説
定率法の新別表は行不足じゃないの!?
減価償却の新別表と別表記載上の留意点
T&Amaster編集部 佐治俊夫
財務省は4月13日、法人税法施行規則の一部を改正する省令を定め、減価償却制度の抜本的な見直しに伴う新たな減価償却資産の償却額の計算に関する明細書(別表16(1)~別表16(5))の様式などを明らかにした(別表16(1)・別表16(2)の様式および記載要領は28~31頁に掲載)。減価償却費の明細書については、減価償却制度の見直しに伴い、平成19年4月1日以後終了事業年度から新別表が使用されることになる。そこで、本稿では、新別表の記載上の留意点を「別表16(2)旧定率法又は定率法による減価償却資産の償却額の計算に関する明細書」への記載例(27頁)を基にして明らかにしていきたい。
「別表16(2)旧定率法又は定率法による減価償却資産の償却額の計算に関する明細書」を下記の設例で記載例を作成していくと、定率法(250%定率法)を償却方法とする場合の期中事業供用資産の記載に若干の疑問が生じてくる。定率法では調整前償却額を計算することになるが、期中事業供用資産については月数按分で償却限度額を計算することになるため、償却保証額との大小判定が行われる調整前償却額とは別欄で月数按分後の償却限度額を表示しておくことが有用と考えられる。しかしながら、新別表には月数按分後の償却限度額の該当記載欄が設けられていないため、月数按分後の償却限度額をどの欄から記載すべきかに疑問が生じるというものである。この疑問は定率による償却から均等償却に移行するという定率法の特性に起因するものであり、期中事業供用資産の記載方法については、平成19年6月の法人税申告においても対応が迫られる。本誌では上記疑問点について当局に対応を確認しているところであるが、定率法の内容・記載方法を理解するうえでも、記載例は有用なものとなるだろう。
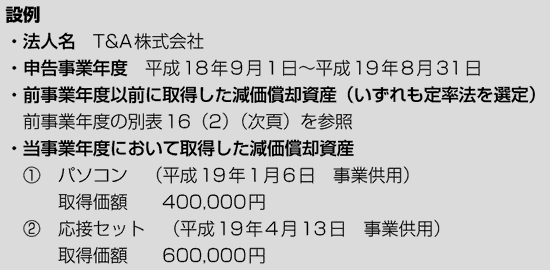
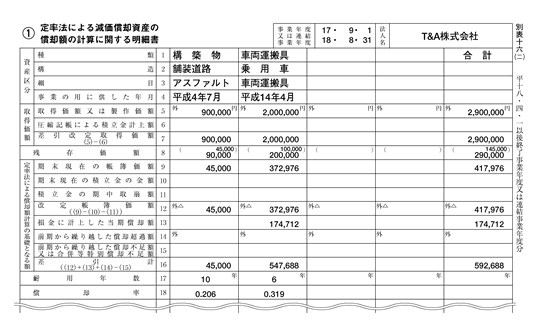
Ⅰ.新規取得減価償却資産を取得日で区分
(新)別表16(2)では、旧定率法による償却額と定率法による償却額の明細を1つの様式上に記載することが特徴となっている。すなわち、当期分の普通償却限度額等の計算では、「平成19年3月31日以前取得分(⇒旧定率法を適用)」と「平成19年4月1日以後取得分(⇒定率法を適用)」の計算欄が区分されて設けられている。
当事業年度の新規取得資産の減価償却方法は、事業年度ではなく取得日により区分して計算する(明細に記載する)ことになるので、設例では、②の減価償却資産(応接セット)だけが平成19年4月1日以後取得分に記載される。①の減価償却資産(パソコン)は新規取得資産には該当するものの、その取得日から平成19年3月31日以前取得分として記載される(旧定率法で償却限度額が計算される)。
①②の減価償却資産はいずれも期中取得資産であるため、それぞれの償却方法(①は旧定率法、②は定率法)により計算した償却限度額の計算では、月数按分計算が行われることになる(法令59①)。
Ⅱ.償却限度達成資産の均等償却は、施行日以後開始事業年度から
既存の減価償却資産のうち、構築物(アスファルト舗装)については、当事業年度の前事業年度までに、改正前法人税法施行令61条に規定されていた償却可能限度額までの償却が行われていた。減価償却制度の見直しでは、旧償却方法(旧定額法、旧定率法など)が適用される減価償却資産で当該事業年度の前事業年度までの各事業年度においてした償却の額の累積額が改正前法人税法施行令による償却可能限度額(有形減価償却資産である場合の取得価額×95%など)に達している場合には、償却後の帳簿価額から備忘価額(1円)等を控除した金額について5年間の均等償却額を当該各事業年度の償却限度額とみなす規定が設けられている(法令61②)。
しかし、当該法人税法施行令の規定は、施行日(平成19年4月1日)以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用することが規定されており(法令附則2、11)、設例の申告事業年度は、施行日をまたぐ事業年度に該当するものの、施行日以後に開始する事業年度には該当しないため、前事業年度までに償却可能限度額に達した資産についての、5年間の均等償却による償却限度額の計算(別表16(2)の「24」欄の記載)は設例の申告事業年度では行われない(T&A株式会社では、平成19年9月1日~平成20年8月31日の事業年度から償却可能限度額に達した減価償却資産の5年間の均等償却が行われる)。
Ⅲ.期中取得資産の償却限度額はどの欄で月数按分?
さて、平成19年4月1日以後に取得したことから定率法が適用される②の減価償却資産(応接セット)について、新別表への記載では、「事業年度の中途で事業の用に供した減価償却資産の償却限度額の特例(法令59)」(以下「月数按分」とする)をどの欄で表示することになるのかが別表の記載欄からは不明である。改正前の別表16(2)では、算出償却額(「19」欄)において、月数按分を反映させていた。改正前の定率法(⇒旧定率法)では、月数按分前の算出償却額を使用することはないため、算出償却額において月数按分後の数字を記載することに何らの問題は生じなかった。
新別表16(2)でこの欄(算出償却額)に対応するのは調整前償却額(「26」欄)ということになるが、定率法では、調整前償却額と償却保証額(「28」欄)の金額の大小を判定することになるため、調整前償却額(取得価額に償却率を乗じて計算した金額)では、月数按分を行う前の金額を記載することにならざるをえない。
反対に耐用年数8年の減価償却資産で調整前償却額に月数按分を反映させたとすると、定率法の償却率(0.313)×月数按分(事業の用に供した月数/当該事業年度の月数)が保証率を下回るような場合も生じてくる(1月の場合)。このような場合、別表上は調整前償却額(「26」)<償却保証額(「28」)ということになり、新規取得資産について、改定償却額(改定取得価額×改定償却率)が償却限度額となってしまう。これは明らかに不合理であって、政令の規定する償却方法とはいえない。政令は調整前償却額を取得価額に当該資産の耐用年数に応じた償却率を乗じて計算した金額(法令48条の2①二ロ)と規定しており、月数按分は、償却限度額の特例(法令59)として規定している。
政令の規定振りからすれば、月数按分を要する減価償却資産では、月数按分前の調整前償却額と月数按分後の償却限度額を区分しておく必要がある。しかも、新別表では、増加償却額(「32」欄))の計算の前に、月数按分による償却限度額を表示しておくことが求められるだろう。したがって、別表では調整前償却額の次欄に、月数按分を行う場合の算出償却額の欄を設けることが適切ではないかと考えられる。
なお、本稿では、調整前償却額(「26」欄)に月数按分後の償却限度額を付記することにして、以下の記載欄の金額に連絡させて記載例を作成している。
また、平成19年4月期決算で平成19年4月に減価償却資産を取得した場合には、月数按分が1/12となり、月数按分後の償却限度額が償却保証額を下回る事例が生じやすい。上記の疑問点については本誌が当局に記載方法の確認を行っており、記載方法は今後明らかにされると思われるが、別表記載上の留意点としてほしい。
(さじ・としお)
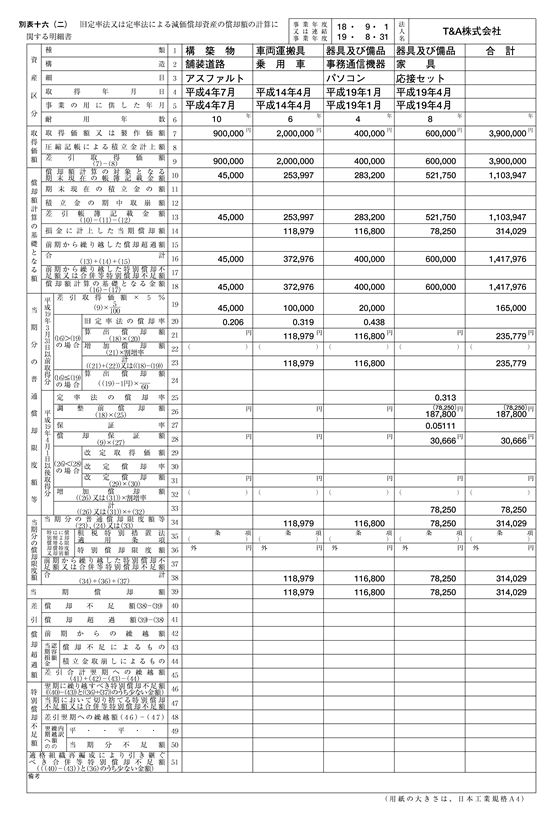
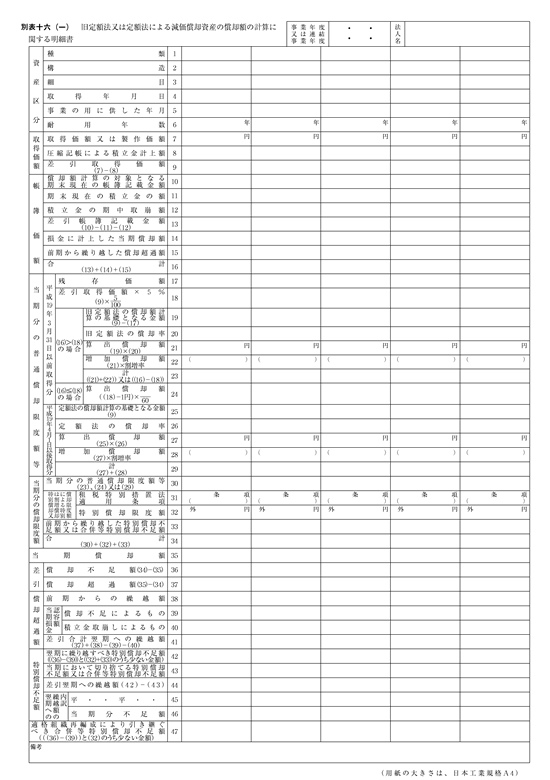
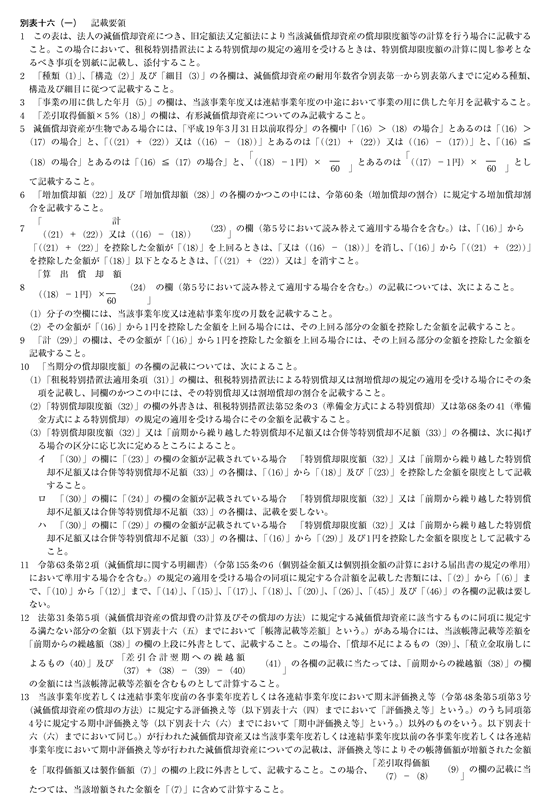
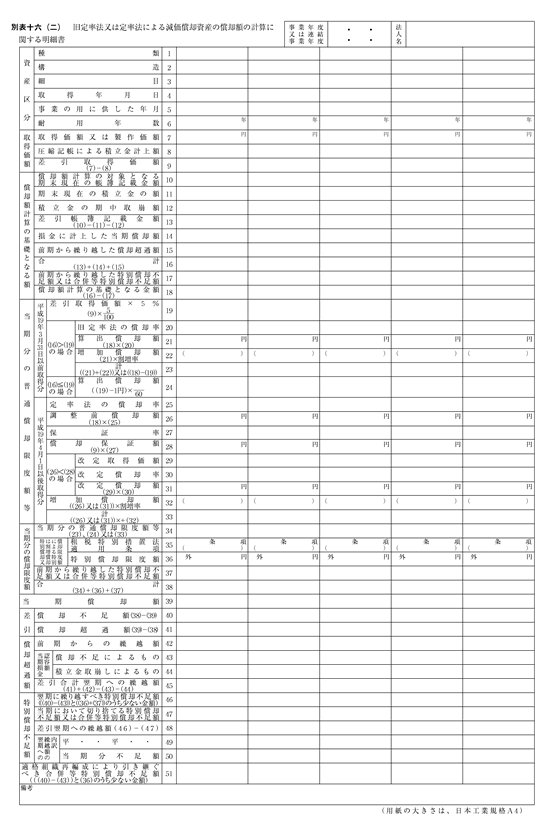
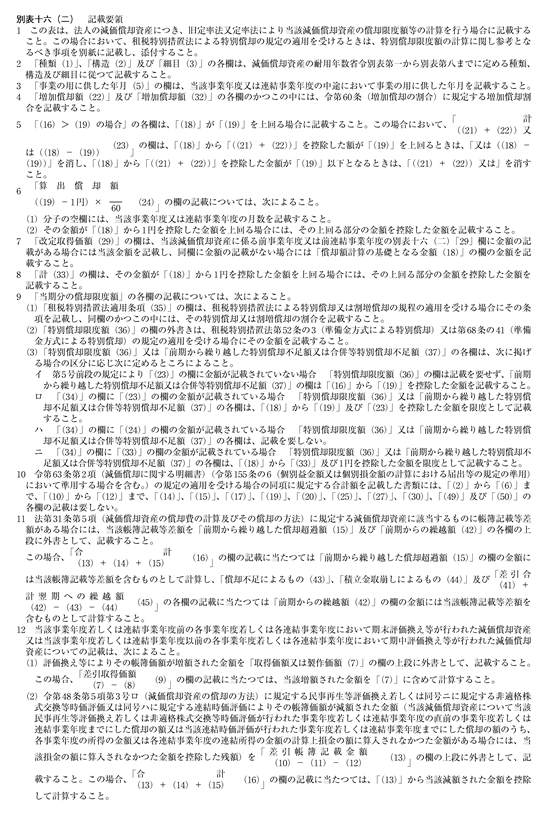
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -

Copyright (C) 2019
SHINNIPPON-HOKI PUBLISHING CO.,LTD.