解説記事2007年07月02日 【会計基準等解説】 「資産除去債務の会計処理に関する論点の整理」の解説(2007年7月2日号・№217)
実務解説
「資産除去債務の会計処理に関する論点の整理」の解説
企業会計基準委員会 研究員 玄蕃進吾
はじめに
企業会計基準委員会(ASBJ)は、平成19年5月30日に「資産除去債務の会計処理に関する論点の整理」(以下「本論点整理」という。)を公表した(脚注1)。ASBJでは、資産除去債務とこれに対応する除去費用をどのように会計処理するかについての検討を行っているが、今般、資産除去債務の会計処理についての論点やその周辺の論点について、一通りの検討が終了したことから、これを本論点整理として公表した。ASBJは今後、本論点整理に寄せられた意見も参考に資産除去債務の会計処理に関する会計基準等の取りまとめに向けた検討を続けていく予定である。
本稿では、本論点整理の概要について解説するが、文中の意見にわたる部分は筆者の私見である。
Ⅰ.本論点整理公表の経緯
我が国における現行の実務では、一般的に資産除去債務についての会計処理は行われておらず、また、米国会計基準や国際財務報告基準(IFRSs)といった国際的な会計基準で見られるような、資産除去債務を負債として計上するとともに、これに対応する除去費用を有形固定資産に計上する会計処理は行われていない。今般、ASBJは将来の負担を財務諸表に反映することは投資情報として役立つという指摘などから、資産除去債務の会計処理を検討プロジェクトとして取り上げている。
資産除去債務の会計処理については、テーマ協議会において直接的な提言が行われているわけではないが、固定資産会計については、短期のレベル1(比較的優先順位の高いグループ)の項目として、また、引当金の会計処理については、中長期のレベル2(比較的優先順位の高いグループであるレベル1以外のグループ)の項目とした提言がなされている。また、ASBJは平成16年9月以降、国際会計基準審議会(IASB)との間で、両会計基準のコンバージェンスに向けた作業を進めており、資産除去債務は、検討すべき項目の1つとして、共同プロジェクトの第3回会合(平成18年3月開催)において短期プロジェクト項目に追加されていた。
このような中、ASBJは平成18年7月に学識経験者を中心としたワーキング・グループを立ち上げて検討を開始するとともに、その後、平成18年11月に資産除去債務専門委員会を設置し、資産除去債務に関する論点についての検討を重ねている。今般、ASBJではこれまでの議論を本論点整理として公表し、今後、資産除去債務の会計処理に関する会計基準等の取りまとめに資するよう、広く意見を求めることとしている(脚注2)。
Ⅱ.各論点の解説
本論点整理では以下の9つの論点が、国際的な会計基準の取扱いや設例等とともに示されている。
1 資産除去債務の範囲【論点1】 本論点整理において資産除去債務の対象となる事象は、有形固定資産の解体、撤去等の処分及び原状回復であり、それには、有形固定資産が遊休状態にある場合は含まれないものとすることが考えられている。また、資産除去債務の発生原因としては、資産除去債務は有形固定資産の取得、建設、開発又は通常の稼動としての使用により生じるものであり、したがって、これらに該当しないもの、例えば、通常の稼動によるものではないもの及び有形固定資産の使用期間中に実施する汚染浄化等の環境修復や修繕は対象とはされていない。
さらに、資産除去債務の具体的な範囲としては、有形固定資産の除去に関連する債務を法令又は契約で要求される法律上の義務だけでなく、法律上の義務に準じるものも含まれると考えられている。ただし法律上の義務に準じるものとはいっても債務の決済を免れることがほとんどできない義務のようなものが想定されるため、その範囲に含まれるものはかなりの確実なレベルによるものであり、それは法令又は契約で要求される法律上の義務とほぼ同等の不可避的な支出が義務付けられているもののみが該当する。さらに、法律上の義務に準じるものとして具体的にどのようなケースが該当するか、また、実務上の観点から重要性の乏しいものや、金額を合理的に見積ることができないものは対象とはならないが、どの程度のものまで対象となるのかについては、今後、さらに検討するとされている。なお、企業が有形固定資産の解体、撤去等の処分をしなくてもペナルティーがないなど、有形固定資産の除去が企業の自発的な計画のみから生じる場合を資産除去債務の具体的範囲に加える必要はないと考えられている。
2 資産除去債務と対応する除去費用の会計処理【論点2】 資産除去債務とこれに係る除去費用については、大きく2つの考え方があり、それぞれに基づく会計処理が挙げられている。
1つは、有形固定資産の解体、撤去等の処分又は原状回復のサービス(除去サービス)を使用に応じて各期間で費用計上し、それに対応する金額を負債として認識する考え方に基づく会計処理(引当金処理)である。この引当金処理を行った場合には、資産除去債務の金額を注記事項として別途開示し、将来の負担を明示する必要があると考えられている。もう1つは、除去サービスに係る支払いが後日であっても、債務として負担している金額を負債計上し、同額を有形固定資産の取得原価に反映させる考え方に基づく会計処理(資産負債の両建処理)である。このような会計処理は、有形固定資産の取得に付随して生じる除去費用の未払いの債務を負債として計上するものであり、同時に、対応する除去費用を当該有形固定資産の取得原価に含めることで、当該資産への投資について回収すべき額を引き上げることを意味する。すなわち、有形固定資産の除去時に不可避的に生じる支出額を付随費用と同様に帳簿価額に加えた上で費用配分を行い、もって適切に回収ができないときには減損処理の対象とし、さらに、資産効率の観点からも有用と考えられる情報を提供するものである。また、このような考え方に基づく会計処理は、国際的な会計基準による会計処理とも整合し、資産除去債務の負債計上が不十分であるとする指摘にも対応するものと考えられている。
本論点整理では、さしあたり、引当金処理と資産負債の両建処理のいずれを採用するかの方向性を示していない。これは、資産除去債務の負債計上が不十分であるという指摘や国際的な会計基準とのコンバージェンスの観点も考慮すると資産負債の両建処理を採用すべきということになるが、資産負債の両建処理が費用計上の観点から引当金処理の結果と異なる可能性がありその影響を勘案すべきといった意見や、引当金計上の実績がある場合にも資産負債の両建処理を採用するか否かについて十分に議論すべきといった意見等を踏まえたことによるものである。
本論点整理では以下のように、資産除去債務と対応する除去費用について仮に資産負債の両建処理を採用するとした場合の論点(【論点3】から【論点9】)を掲げている。これは、資産負債の両建処理は我が国において新しい考え方によるものであるからであり、引当金処理と資産負債の両建処理のいずれを採用するかの結論は、本論点整理に対するコメント等も踏まえて決定することとされている。
3 資産除去債務の全額を負債として計上する理由【論点3】 有形固定資産の解体、撤去等の処分又は原状回復に要するサービスの支払いが、法律上の義務に基づく場合など、有形固定資産の除去時に不可避的に生じる場合があり、このような場合には債務として負担している金額を合理的に見積られることを条件に、資産除去債務の全額を負債として計上することが挙げられている。これについては、ファイナンス・リース取引の借手のように、資産除去債務の将来の支払金額が固定され、支払時期が確定している場合だけでなく、当該支払金額が固定されない場合又は支払時期が確定していない場合でも、法律上の義務に基づくなど、資産除去債務の範囲に該当する場合には、有形固定資産の除去サービスの支払いが不可避的に生じることとなる。
このため、本論点整理では、このような除去サービスの支払いが不可避的に生じる場合には、いずれの場合でも[図表1]のように割引前の将来キャッシュ・フローを見積り、割引後の金額(割引価値)で負債を計上することが考えられている。資産除去債務の将来の支払金額が固定されない場合又は支払時期が確定していない場合には、[図表2]のように将来キャッシュ・フローの見積額のうち、その時点までに発生していると認められる額をもって負債計上することも考えられるが、このような場合でも資産除去債務の全額を負債として計上するのは、環境問題を背景とした資産除去債務の早期認識に対する関心が高まりつつあることや、将来の負担を財務諸表に反映することは投資情報として役立つといった負債計上に対する情報ニーズにより一層対応できること等をその計上理由としている。
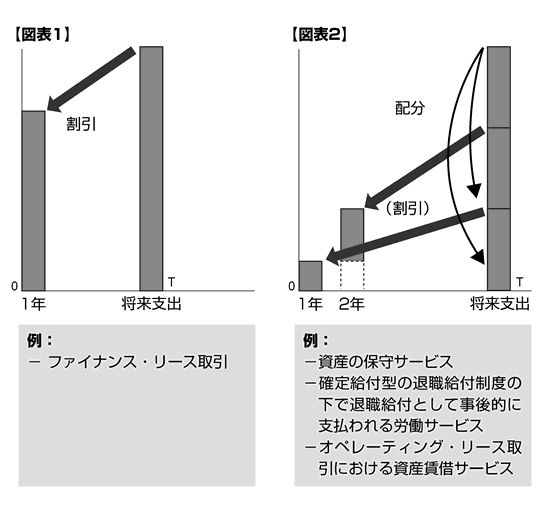
なお、本論点整理では、資産除去債務の両建処理と企業会計原則注解(注18)の引当金との関係について、資産除去債務の両建処理を行う場合には、いずれの場合でも当該引当金とは切り離して整理されている。また、本論点整理では、資産除去債務と類似の性格を有する修繕引当金との関係についても触れられているが、修繕引当金が負債性を有するかどうかという論点があることや、国際的な会計基準において資産除去債務の対象となる事象は明確に定められていることなどから、修繕については対象外とされている。
4 資産除去債務の負債としての計上時期【論点4】 本論点整理では、資産除去債務は、有形固定資産の取得、建設、開発又は使用により生じるものとされており、その発生時に負債として計上することが考えられている。ただし、当該負債の計上にあたっては、資産除去債務の金額を合理的に見積ることができることが必要となる。したがって、当該義務の金額を合理的に見積ることができない場合には負債を計上しないことになるが、当該義務の金額を合理的に見積ることができるようになったときに負債を計上することになる。なお、資産除去債務が発生しているにもかかわらず、当該義務の金額を合理的に見積ることができずに負債を計上していない場合には、別途開示を行う必要がある(Ⅱ.9【論点9】参照)。
また、資産除去債務が有形固定資産の稼動等にしたがって使用の都度発生する場合には、当該資産除去債務を各期において負債の増加分として区別して認識することになると考えられている。
5 資産除去債務に対応する除去費用の資産計上と費用配分【論点5】 資産負債の両建処理を採用した場合の資産計上の方法としては、資産除去債務に対応する除去費用を有形固定資産の取得に関する付随費用的な性格によるものとして、関連する有形固定資産の帳簿価額を増加させる方法によることが適当であると考えられている。また、これにより資産計上された金額は、減価償却を通じて、当該有形固定資産の耐用年数にわたり、規則的、合理的な方法によって各期に費用配分されることになる。なお、土地の原状回復等が法令又は契約で要求されている場合、当該除去費用を永続的な利用が前提とされている土地の一部とし、償却しないことは一般的に適当ではないとされている。また、資産除去債務の対象が複数の有形固定資産から構成される場合、資産除去債務に対応する除去費用を合理的な方法により按分し、それぞれの有形固定資産の帳簿価額に加える方法(按分法)だけでなく、当該複数の有形固定資産全体に対し一括して処理する方法(一括法)も認めるべきではないかと考えられている。一括法の場合、資産計上された金額は他の規則的、合理的な方法により毎期費用計上される。例えば、各資産の減価償却は除去費用を加える前の帳簿価額に基づいて行い、当該資産全体としての除去費用の資産計上額の減価償却は、除去の対象となる主たる資産(最も耐用年数の長い償却性の有形固定資産)の耐用年数に基づき行う方法が考えられる。いずれにしても、資産除去債務に対応する除去費用をどのように資産計上するか、また、資産計上された金額をどのように費用配分するかなどの論点については、引き続き検討することとされている。
さらに、資産除去債務が有形固定資産の稼動等、その使用の都度発生する場合(Ⅱ.4【論点4】参照)、費用配分の簡便的な方法として、除去費用を資産計上したのと同一の期間に、資産計上額と同一の金額を費用処理することも認められるとすることが検討されている。
6 資産除去債務の割引価値の算定における将来キャッシュ・フローの見積りと割引率の関係【論点6】
(1)将来キャッシュ・フローの見積りと割引率の算定において考慮すべき事項 将来キャッシュ・フローの見積金額には、生起しうる複数のキャッシュ・フローをそれぞれの確率で加重平均した金額(期待値)を用いることが考えられるが、割引価値の算定においては、将来キャッシュ・フローが見積値から乖離するリスクについて、将来キャッシュ・フローの見積りと割引率の算定のいずれかに反映させる必要がある。なお、一般的に、将来キャッシュ・フローが見積値から乖離するリスクは好まれないため、こうしたリスクを反映した場合には、反映しない場合に比べて、負債である資産除去債務の割引価値は大きくなる。また、割引率の算定において、債務者である企業自身の信用リスク、すなわち債務不履行のリスクを反映させるかどうかという論点もある。
(2)資産除去債務の割引価値 資産除去債務の割引価値としては、市場の評価を反映した割引価値(時価)による見方と、自己の評価を反映した支出の見積りの割引価値による見方が考えられている。
市場の評価を反映した割引価値(時価)による見方については、市場価格を観察することができる場合には、それに基づく価額を時価として用いることも考えられるが、通常、その市場価格を観察することはできない。したがって、市場価格に準ずるものとして、合理的に算定された価額を時価として用いることとし、市場の評価を反映して算定された割引価値を見積ることが考えられる。時価による場合、[図表3]の案1のように、一般的に市場の評価による将来キャッシュ・フローが見積値から乖離するリスクは将来キャッシュ・フローの見積りに反映され、割引率は無リスクの割引率に信用リスクを調整したものが用いられる。
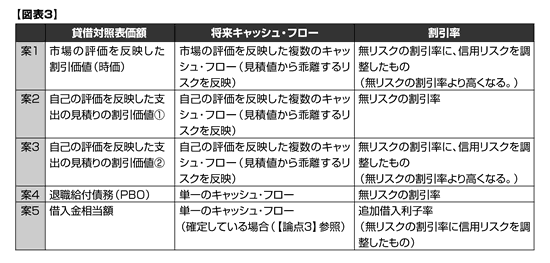
一方、自己の評価を反映した支出の見積りの割引価値による見方についても、自己の評価による将来キャッシュ・フローが見積値から乖離するリスクは、通常、将来キャッシュ・フローの見積りに反映される。この場合、割引率は、[図表3]の案2のように、無リスクの割引率が用いられる場合と、[図表3]の案3のように、無リスクの割引率に信用リスクを調整した場合が考えられる。なお、案3は、資産除去債務の市場が事実上、存在しない場合、資産除去債務の履行を行う者は自己以外に存在せず、負債の時価と実質的に相違しないことになることから、案1による見方に含めて検討することも考えられる。
この他、資産除去債務の割引価値としては、[図表3]の案4における退職給付債務のように、単一のキャッシュ・フローに基づき将来キャッシュ・フローを見積り、無リスクの割引率を用いて割引計算を行う見方や、[図表3]の案5におけるファイナンス・リースのように、単一のキャッシュ・フローに基づき将来キャッシュ・フローを見積り、追加借入利子率等を用いて割引計算を行う見方もあるが、これらの見方は、案1及び案2による見方に含めて検討することが適当と考えられている。
7 資産除去債務の負債計上後における将来キャッシュ・フローの見積り及び割引率の変更【論点7】 資産除去債務の見積りの変更から生じる調整を会計上、どのように処理するかについて本論点整理では、資産除去債務に係る負債及び関連する有形固定資産の取得原価に加減し、減価償却を通じて残存償却期間にわたり費用配分を行う方法(プロスペクティブ・アプローチ)により処理することが考えられている。これは、現行、我が国では見積りの変更について遡及して修正する会計基準等が整備されていないこと及び国際的な会計基準においては、将来に向かって修正する方法が採用されていることによるものである。なお、この場合、割引前の将来キャッシュ・フローの見積りの変更による調整額は、資産除去債務に係る負債の帳簿価額及び関連する有形固定資産の帳簿価額に加減して処理することになる。
一方、割引率の変更については、変更は行わず当初の割引率を用いる方法と、毎期、貸借対照表日現在で見直すことにより、その調整額を資産除去債務に係る負債の帳簿価額及び関連する有形固定資産の帳簿価額に加減して処理する方法の2つが挙げられているが、米国会計基準とIFRSsで会計処理が異なるなど、いずれの方法が適当かについては意見のあるところであり、引き続き検討することとされている。なお、時の経過による資産除去債務に係る負債の調整額は、その発生時の費用として処理することに留意する必要がある。
8 リース物件(賃借資産)における資産除去債務と対応する除去費用の処理【論点8】 ファイナンス・リース取引においては、通常、支払リース料に賃借資産を除去するための支出(残価保証等を含む。)が含まれており、借手が賃借資産の除去を行う義務を負うことはないため、この場合には、改めて借手は資産除去債務を計上する必要はなく、賃借資産の除去を行う義務を負う貸手が、資産除去債務の計上を考慮することになる。
一方、オペレーティング・リース取引の支払リース料に賃借資産の原状回復等に要する支出が含まれていない場合の賃借資産の原状回復等は、資産除去債務の対象となる事象に含まれないという見方と、当該事象に含まれるという見方がある。後者の見方は、オペレーティング・リース取引の対象となる賃借資産自体はオフバランス処理されるが、その使用によって関連する資産除去債務が生じることもあるという考え方によるものである。なお、後者の見方において借手が賃借に関連して敷金を支出している場合には、当該敷金と負債で計上される資産除去債務との関係から、現行の取得原価で認識されている敷金の処理に影響させるかどうかという論点もある。
9 資産除去債務と対応する除去費用に関する開示【論点9】 資産除去債務と対応する除去費用に関する開示については、国際的な会計基準における開示項目を参考に、次の項目の開示を求めるかどうか、引き続き検討することとされている。
(1)資産除去債務と関連する有形固定資産についての概要の開示 ① 債務の内容についての簡潔な説明及び支払が予測される時期
② 支払金額又は時期についての不確実性の内容
③ 将来の事象に関する重要な仮定
(2)資産除去債務を決済するために法的に制限された資産に関する情報の開示 例えば、減債基金のような資産の内容並びにその帳簿価額及び時価に関する情報など
(3)資産除去債務の帳簿価額に重要な変動があった場合の当該変動の原因別の内訳 ① 当期発生した金額
② 当期決済した金額
③ 当期戻し入れた未使用の金額
④ 時間の経過によって発生した期中増加額(利息費用相当額)
⑤ 将来キャッシュ・フローの見積りの変更による金額
⑥ 割引率の変更による影響額(割引率の変更を反映させる場合)
(4)資産除去債務を合理的に見積ることができず、負債として計上していない場合(Ⅱ.4【論点4】参照)にはその旨と理由の開示
Ⅲ.おわりに
ASBJでは、本論点整理に寄せられた意見も参考に、今後、資産除去債務の会計処理に関する会計基準等の取りまとめに向けた検討を続けていく予定である。なお、現時点では、平成19年末までに企業会計基準(案)及び同適用指針(案)の公開草案を公表することが予定されている。(げんば・しんご)
(脚注)
1 ASBJのホームページ(http://www.asb.or.jp/html/documents/summary_issue/aro/)を参照。
2 コメントの締切りは平成19年7月9日(月)である。
「資産除去債務の会計処理に関する論点の整理」の解説
企業会計基準委員会 研究員 玄蕃進吾
はじめに
企業会計基準委員会(ASBJ)は、平成19年5月30日に「資産除去債務の会計処理に関する論点の整理」(以下「本論点整理」という。)を公表した(脚注1)。ASBJでは、資産除去債務とこれに対応する除去費用をどのように会計処理するかについての検討を行っているが、今般、資産除去債務の会計処理についての論点やその周辺の論点について、一通りの検討が終了したことから、これを本論点整理として公表した。ASBJは今後、本論点整理に寄せられた意見も参考に資産除去債務の会計処理に関する会計基準等の取りまとめに向けた検討を続けていく予定である。
本稿では、本論点整理の概要について解説するが、文中の意見にわたる部分は筆者の私見である。
Ⅰ.本論点整理公表の経緯
我が国における現行の実務では、一般的に資産除去債務についての会計処理は行われておらず、また、米国会計基準や国際財務報告基準(IFRSs)といった国際的な会計基準で見られるような、資産除去債務を負債として計上するとともに、これに対応する除去費用を有形固定資産に計上する会計処理は行われていない。今般、ASBJは将来の負担を財務諸表に反映することは投資情報として役立つという指摘などから、資産除去債務の会計処理を検討プロジェクトとして取り上げている。
資産除去債務の会計処理については、テーマ協議会において直接的な提言が行われているわけではないが、固定資産会計については、短期のレベル1(比較的優先順位の高いグループ)の項目として、また、引当金の会計処理については、中長期のレベル2(比較的優先順位の高いグループであるレベル1以外のグループ)の項目とした提言がなされている。また、ASBJは平成16年9月以降、国際会計基準審議会(IASB)との間で、両会計基準のコンバージェンスに向けた作業を進めており、資産除去債務は、検討すべき項目の1つとして、共同プロジェクトの第3回会合(平成18年3月開催)において短期プロジェクト項目に追加されていた。
このような中、ASBJは平成18年7月に学識経験者を中心としたワーキング・グループを立ち上げて検討を開始するとともに、その後、平成18年11月に資産除去債務専門委員会を設置し、資産除去債務に関する論点についての検討を重ねている。今般、ASBJではこれまでの議論を本論点整理として公表し、今後、資産除去債務の会計処理に関する会計基準等の取りまとめに資するよう、広く意見を求めることとしている(脚注2)。
Ⅱ.各論点の解説
本論点整理では以下の9つの論点が、国際的な会計基準の取扱いや設例等とともに示されている。
1 資産除去債務の範囲【論点1】 本論点整理において資産除去債務の対象となる事象は、有形固定資産の解体、撤去等の処分及び原状回復であり、それには、有形固定資産が遊休状態にある場合は含まれないものとすることが考えられている。また、資産除去債務の発生原因としては、資産除去債務は有形固定資産の取得、建設、開発又は通常の稼動としての使用により生じるものであり、したがって、これらに該当しないもの、例えば、通常の稼動によるものではないもの及び有形固定資産の使用期間中に実施する汚染浄化等の環境修復や修繕は対象とはされていない。
さらに、資産除去債務の具体的な範囲としては、有形固定資産の除去に関連する債務を法令又は契約で要求される法律上の義務だけでなく、法律上の義務に準じるものも含まれると考えられている。ただし法律上の義務に準じるものとはいっても債務の決済を免れることがほとんどできない義務のようなものが想定されるため、その範囲に含まれるものはかなりの確実なレベルによるものであり、それは法令又は契約で要求される法律上の義務とほぼ同等の不可避的な支出が義務付けられているもののみが該当する。さらに、法律上の義務に準じるものとして具体的にどのようなケースが該当するか、また、実務上の観点から重要性の乏しいものや、金額を合理的に見積ることができないものは対象とはならないが、どの程度のものまで対象となるのかについては、今後、さらに検討するとされている。なお、企業が有形固定資産の解体、撤去等の処分をしなくてもペナルティーがないなど、有形固定資産の除去が企業の自発的な計画のみから生じる場合を資産除去債務の具体的範囲に加える必要はないと考えられている。
2 資産除去債務と対応する除去費用の会計処理【論点2】 資産除去債務とこれに係る除去費用については、大きく2つの考え方があり、それぞれに基づく会計処理が挙げられている。
1つは、有形固定資産の解体、撤去等の処分又は原状回復のサービス(除去サービス)を使用に応じて各期間で費用計上し、それに対応する金額を負債として認識する考え方に基づく会計処理(引当金処理)である。この引当金処理を行った場合には、資産除去債務の金額を注記事項として別途開示し、将来の負担を明示する必要があると考えられている。もう1つは、除去サービスに係る支払いが後日であっても、債務として負担している金額を負債計上し、同額を有形固定資産の取得原価に反映させる考え方に基づく会計処理(資産負債の両建処理)である。このような会計処理は、有形固定資産の取得に付随して生じる除去費用の未払いの債務を負債として計上するものであり、同時に、対応する除去費用を当該有形固定資産の取得原価に含めることで、当該資産への投資について回収すべき額を引き上げることを意味する。すなわち、有形固定資産の除去時に不可避的に生じる支出額を付随費用と同様に帳簿価額に加えた上で費用配分を行い、もって適切に回収ができないときには減損処理の対象とし、さらに、資産効率の観点からも有用と考えられる情報を提供するものである。また、このような考え方に基づく会計処理は、国際的な会計基準による会計処理とも整合し、資産除去債務の負債計上が不十分であるとする指摘にも対応するものと考えられている。
本論点整理では、さしあたり、引当金処理と資産負債の両建処理のいずれを採用するかの方向性を示していない。これは、資産除去債務の負債計上が不十分であるという指摘や国際的な会計基準とのコンバージェンスの観点も考慮すると資産負債の両建処理を採用すべきということになるが、資産負債の両建処理が費用計上の観点から引当金処理の結果と異なる可能性がありその影響を勘案すべきといった意見や、引当金計上の実績がある場合にも資産負債の両建処理を採用するか否かについて十分に議論すべきといった意見等を踏まえたことによるものである。
本論点整理では以下のように、資産除去債務と対応する除去費用について仮に資産負債の両建処理を採用するとした場合の論点(【論点3】から【論点9】)を掲げている。これは、資産負債の両建処理は我が国において新しい考え方によるものであるからであり、引当金処理と資産負債の両建処理のいずれを採用するかの結論は、本論点整理に対するコメント等も踏まえて決定することとされている。
3 資産除去債務の全額を負債として計上する理由【論点3】 有形固定資産の解体、撤去等の処分又は原状回復に要するサービスの支払いが、法律上の義務に基づく場合など、有形固定資産の除去時に不可避的に生じる場合があり、このような場合には債務として負担している金額を合理的に見積られることを条件に、資産除去債務の全額を負債として計上することが挙げられている。これについては、ファイナンス・リース取引の借手のように、資産除去債務の将来の支払金額が固定され、支払時期が確定している場合だけでなく、当該支払金額が固定されない場合又は支払時期が確定していない場合でも、法律上の義務に基づくなど、資産除去債務の範囲に該当する場合には、有形固定資産の除去サービスの支払いが不可避的に生じることとなる。
このため、本論点整理では、このような除去サービスの支払いが不可避的に生じる場合には、いずれの場合でも[図表1]のように割引前の将来キャッシュ・フローを見積り、割引後の金額(割引価値)で負債を計上することが考えられている。資産除去債務の将来の支払金額が固定されない場合又は支払時期が確定していない場合には、[図表2]のように将来キャッシュ・フローの見積額のうち、その時点までに発生していると認められる額をもって負債計上することも考えられるが、このような場合でも資産除去債務の全額を負債として計上するのは、環境問題を背景とした資産除去債務の早期認識に対する関心が高まりつつあることや、将来の負担を財務諸表に反映することは投資情報として役立つといった負債計上に対する情報ニーズにより一層対応できること等をその計上理由としている。
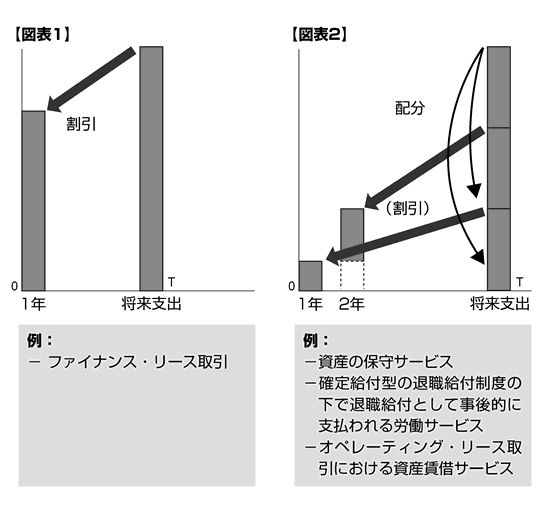
なお、本論点整理では、資産除去債務の両建処理と企業会計原則注解(注18)の引当金との関係について、資産除去債務の両建処理を行う場合には、いずれの場合でも当該引当金とは切り離して整理されている。また、本論点整理では、資産除去債務と類似の性格を有する修繕引当金との関係についても触れられているが、修繕引当金が負債性を有するかどうかという論点があることや、国際的な会計基準において資産除去債務の対象となる事象は明確に定められていることなどから、修繕については対象外とされている。
4 資産除去債務の負債としての計上時期【論点4】 本論点整理では、資産除去債務は、有形固定資産の取得、建設、開発又は使用により生じるものとされており、その発生時に負債として計上することが考えられている。ただし、当該負債の計上にあたっては、資産除去債務の金額を合理的に見積ることができることが必要となる。したがって、当該義務の金額を合理的に見積ることができない場合には負債を計上しないことになるが、当該義務の金額を合理的に見積ることができるようになったときに負債を計上することになる。なお、資産除去債務が発生しているにもかかわらず、当該義務の金額を合理的に見積ることができずに負債を計上していない場合には、別途開示を行う必要がある(Ⅱ.9【論点9】参照)。
また、資産除去債務が有形固定資産の稼動等にしたがって使用の都度発生する場合には、当該資産除去債務を各期において負債の増加分として区別して認識することになると考えられている。
5 資産除去債務に対応する除去費用の資産計上と費用配分【論点5】 資産負債の両建処理を採用した場合の資産計上の方法としては、資産除去債務に対応する除去費用を有形固定資産の取得に関する付随費用的な性格によるものとして、関連する有形固定資産の帳簿価額を増加させる方法によることが適当であると考えられている。また、これにより資産計上された金額は、減価償却を通じて、当該有形固定資産の耐用年数にわたり、規則的、合理的な方法によって各期に費用配分されることになる。なお、土地の原状回復等が法令又は契約で要求されている場合、当該除去費用を永続的な利用が前提とされている土地の一部とし、償却しないことは一般的に適当ではないとされている。また、資産除去債務の対象が複数の有形固定資産から構成される場合、資産除去債務に対応する除去費用を合理的な方法により按分し、それぞれの有形固定資産の帳簿価額に加える方法(按分法)だけでなく、当該複数の有形固定資産全体に対し一括して処理する方法(一括法)も認めるべきではないかと考えられている。一括法の場合、資産計上された金額は他の規則的、合理的な方法により毎期費用計上される。例えば、各資産の減価償却は除去費用を加える前の帳簿価額に基づいて行い、当該資産全体としての除去費用の資産計上額の減価償却は、除去の対象となる主たる資産(最も耐用年数の長い償却性の有形固定資産)の耐用年数に基づき行う方法が考えられる。いずれにしても、資産除去債務に対応する除去費用をどのように資産計上するか、また、資産計上された金額をどのように費用配分するかなどの論点については、引き続き検討することとされている。
さらに、資産除去債務が有形固定資産の稼動等、その使用の都度発生する場合(Ⅱ.4【論点4】参照)、費用配分の簡便的な方法として、除去費用を資産計上したのと同一の期間に、資産計上額と同一の金額を費用処理することも認められるとすることが検討されている。
6 資産除去債務の割引価値の算定における将来キャッシュ・フローの見積りと割引率の関係【論点6】
(1)将来キャッシュ・フローの見積りと割引率の算定において考慮すべき事項 将来キャッシュ・フローの見積金額には、生起しうる複数のキャッシュ・フローをそれぞれの確率で加重平均した金額(期待値)を用いることが考えられるが、割引価値の算定においては、将来キャッシュ・フローが見積値から乖離するリスクについて、将来キャッシュ・フローの見積りと割引率の算定のいずれかに反映させる必要がある。なお、一般的に、将来キャッシュ・フローが見積値から乖離するリスクは好まれないため、こうしたリスクを反映した場合には、反映しない場合に比べて、負債である資産除去債務の割引価値は大きくなる。また、割引率の算定において、債務者である企業自身の信用リスク、すなわち債務不履行のリスクを反映させるかどうかという論点もある。
(2)資産除去債務の割引価値 資産除去債務の割引価値としては、市場の評価を反映した割引価値(時価)による見方と、自己の評価を反映した支出の見積りの割引価値による見方が考えられている。
市場の評価を反映した割引価値(時価)による見方については、市場価格を観察することができる場合には、それに基づく価額を時価として用いることも考えられるが、通常、その市場価格を観察することはできない。したがって、市場価格に準ずるものとして、合理的に算定された価額を時価として用いることとし、市場の評価を反映して算定された割引価値を見積ることが考えられる。時価による場合、[図表3]の案1のように、一般的に市場の評価による将来キャッシュ・フローが見積値から乖離するリスクは将来キャッシュ・フローの見積りに反映され、割引率は無リスクの割引率に信用リスクを調整したものが用いられる。
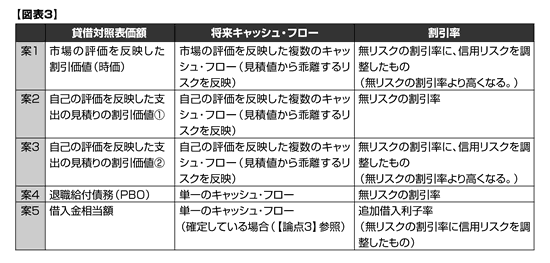
一方、自己の評価を反映した支出の見積りの割引価値による見方についても、自己の評価による将来キャッシュ・フローが見積値から乖離するリスクは、通常、将来キャッシュ・フローの見積りに反映される。この場合、割引率は、[図表3]の案2のように、無リスクの割引率が用いられる場合と、[図表3]の案3のように、無リスクの割引率に信用リスクを調整した場合が考えられる。なお、案3は、資産除去債務の市場が事実上、存在しない場合、資産除去債務の履行を行う者は自己以外に存在せず、負債の時価と実質的に相違しないことになることから、案1による見方に含めて検討することも考えられる。
この他、資産除去債務の割引価値としては、[図表3]の案4における退職給付債務のように、単一のキャッシュ・フローに基づき将来キャッシュ・フローを見積り、無リスクの割引率を用いて割引計算を行う見方や、[図表3]の案5におけるファイナンス・リースのように、単一のキャッシュ・フローに基づき将来キャッシュ・フローを見積り、追加借入利子率等を用いて割引計算を行う見方もあるが、これらの見方は、案1及び案2による見方に含めて検討することが適当と考えられている。
7 資産除去債務の負債計上後における将来キャッシュ・フローの見積り及び割引率の変更【論点7】 資産除去債務の見積りの変更から生じる調整を会計上、どのように処理するかについて本論点整理では、資産除去債務に係る負債及び関連する有形固定資産の取得原価に加減し、減価償却を通じて残存償却期間にわたり費用配分を行う方法(プロスペクティブ・アプローチ)により処理することが考えられている。これは、現行、我が国では見積りの変更について遡及して修正する会計基準等が整備されていないこと及び国際的な会計基準においては、将来に向かって修正する方法が採用されていることによるものである。なお、この場合、割引前の将来キャッシュ・フローの見積りの変更による調整額は、資産除去債務に係る負債の帳簿価額及び関連する有形固定資産の帳簿価額に加減して処理することになる。
一方、割引率の変更については、変更は行わず当初の割引率を用いる方法と、毎期、貸借対照表日現在で見直すことにより、その調整額を資産除去債務に係る負債の帳簿価額及び関連する有形固定資産の帳簿価額に加減して処理する方法の2つが挙げられているが、米国会計基準とIFRSsで会計処理が異なるなど、いずれの方法が適当かについては意見のあるところであり、引き続き検討することとされている。なお、時の経過による資産除去債務に係る負債の調整額は、その発生時の費用として処理することに留意する必要がある。
8 リース物件(賃借資産)における資産除去債務と対応する除去費用の処理【論点8】 ファイナンス・リース取引においては、通常、支払リース料に賃借資産を除去するための支出(残価保証等を含む。)が含まれており、借手が賃借資産の除去を行う義務を負うことはないため、この場合には、改めて借手は資産除去債務を計上する必要はなく、賃借資産の除去を行う義務を負う貸手が、資産除去債務の計上を考慮することになる。
一方、オペレーティング・リース取引の支払リース料に賃借資産の原状回復等に要する支出が含まれていない場合の賃借資産の原状回復等は、資産除去債務の対象となる事象に含まれないという見方と、当該事象に含まれるという見方がある。後者の見方は、オペレーティング・リース取引の対象となる賃借資産自体はオフバランス処理されるが、その使用によって関連する資産除去債務が生じることもあるという考え方によるものである。なお、後者の見方において借手が賃借に関連して敷金を支出している場合には、当該敷金と負債で計上される資産除去債務との関係から、現行の取得原価で認識されている敷金の処理に影響させるかどうかという論点もある。
9 資産除去債務と対応する除去費用に関する開示【論点9】 資産除去債務と対応する除去費用に関する開示については、国際的な会計基準における開示項目を参考に、次の項目の開示を求めるかどうか、引き続き検討することとされている。
(1)資産除去債務と関連する有形固定資産についての概要の開示 ① 債務の内容についての簡潔な説明及び支払が予測される時期
② 支払金額又は時期についての不確実性の内容
③ 将来の事象に関する重要な仮定
(2)資産除去債務を決済するために法的に制限された資産に関する情報の開示 例えば、減債基金のような資産の内容並びにその帳簿価額及び時価に関する情報など
(3)資産除去債務の帳簿価額に重要な変動があった場合の当該変動の原因別の内訳 ① 当期発生した金額
② 当期決済した金額
③ 当期戻し入れた未使用の金額
④ 時間の経過によって発生した期中増加額(利息費用相当額)
⑤ 将来キャッシュ・フローの見積りの変更による金額
⑥ 割引率の変更による影響額(割引率の変更を反映させる場合)
(4)資産除去債務を合理的に見積ることができず、負債として計上していない場合(Ⅱ.4【論点4】参照)にはその旨と理由の開示
Ⅲ.おわりに
ASBJでは、本論点整理に寄せられた意見も参考に、今後、資産除去債務の会計処理に関する会計基準等の取りまとめに向けた検討を続けていく予定である。なお、現時点では、平成19年末までに企業会計基準(案)及び同適用指針(案)の公開草案を公表することが予定されている。(げんば・しんご)
(脚注)
1 ASBJのホームページ(http://www.asb.or.jp/html/documents/summary_issue/aro/)を参照。
2 コメントの締切りは平成19年7月9日(月)である。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -

Copyright (C) 2019
SHINNIPPON-HOKI PUBLISHING CO.,LTD.





















