解説記事2007年09月10日 【編集部レポート】 ブルドックソース買収防衛策に係る裁判所決定を読み解く(3)(2007年9月10日号・№226)
ブルドックソース買収防衛策に係る裁判所決定を読み解く(3)
不公正発行に関する過去の判断を振り返る
text 編集部
前回(本誌225号20頁参照)までに、事件の経過や申立て時の主張をみながら、主要争点(図表1参照)の1つとなった「株主平等原則に違反するか」について、決定原文を参照する形で紹介したところである。今回は、買収防衛策としての本件新株予約権無償割当てが「『著しく不公正な方法により行われる場合』に該当するか」について各決定における判断を紹介する前に、最近の仮処分事件で「著しく不公正な方法」かどうかが争われたケースを振り返りながら、どのような規範のもとで各事件の判断がなされてきたのかをみてみたい。
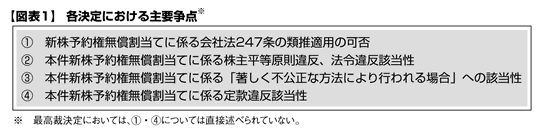
最近の主な仮処分事件 近時の企業買収事案の増加等を背景とし、いわゆる経営支配権の争奪を巡って、株式の買集めを行った者と発行会社との間で事件化するケースも増加した。特に平成16年から平成17年にかけては、会社側が対応策として採った手法に問題があるとして株主側がその差止めを求める事件が相次いだものといえよう(図表2参照)。
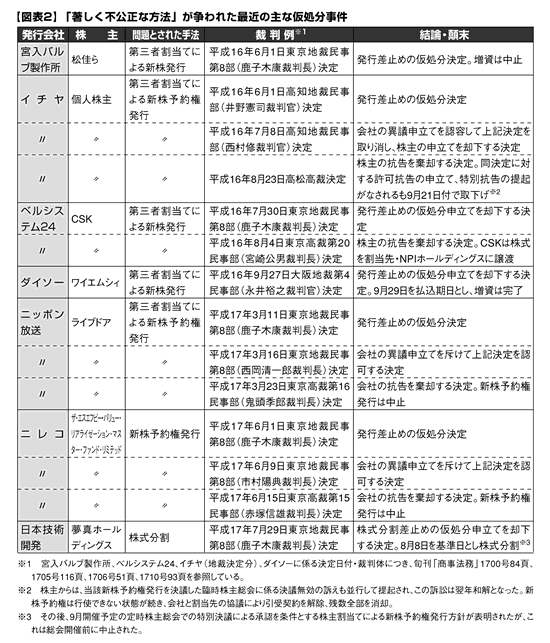
ここで取り上げたのは、会社側の手法が著しく不公正な方法によるものであるとする主張が争われた東京における5、大阪1、高知1の計7事件であるが、会社側の手法が裁判所に認容されず、結果として新株発行等の中止に追い込まれたのは、宮入バルブ製作所、ニッポン放送、ニレコの3事件にとどまる。
買収防衛策として明確に謳われた手法が判断されているのはニレコ事件以降で、ニレコにおいては、平成17年3月14日開催の取締役会で新株予約権の無償発行を内容とする「セキュリティ・プラン」の導入を決議。同日、「企業価値向上に向けた取組みについて(平成18年3月期の重点施策および株主割当による新株予約権の無償発行に関するお知らせ)」として公表された。
ニッポン放送事件における東京高裁平成17年3月23日決定に示された「経営支配権の維持・確保を主要な目的とする新株予約権の発行が許される特段の事情がある場合」(後掲・図表5の下段③参照)に準拠しながら、買収者および一定の関係者が発行済議決権付株式総数の20%を保有するに至った場合に、割当基準日(平成17年3月31日)以降に株式を取得した株主の持株比率を約3分の1に希釈するいわゆる事前警告型の買収防衛策で、申立株主の基準日時点での保有割合は約2.85%であった。
日本技術開発事件での申立株主は、平成17年7月21日時点で約6.83%を保有する筆頭株主。同年6月中に買増しを進め、同月24日には大量保有報告書を提出する5%超保有の株主となっていた。株主は7月7日、業務提携を申し入れたが、会社側は翌8日、「大規模買付行為への対応方針に関するお知らせ」を公表し、20%以上保有の株主を対象とし、「大規模買付ルールが遵守されなかった場合には、具体的な買付方法の如何にかかわらず、取締役会は、会社および株主全体の利益を守ることを目的として、株式分割、新株予約権の発行等、商法その他の法律および定款が認めるものを行使し、大規模買付行為に対抗する場合がある」旨を述べた。
株主は7月11日、同月20日からの公開買付け(TOB)の開始を公表。50%超取得を目指すもので、会社側は同日、大規模買付ルールに反すると発表した後、7月18日の取締役会決議により普通株式1株につき5株の割合で株式分割を行うことが決定、公表された。株主の主張によると、本件株式分割はTOBの実施を事実上困難にするというものであった。
買収防衛指針の策定 ニッポン放送事件高裁決定からニレコ事件地裁決定に至る間となる平成17年5月27日、「企業価値・株主共同の利益の確保又は向上のための買収防衛策に関する指針」(以下「指針」という)が経済産業省・法務省により共同策定されている。ここでは、「3原則」が示され、これに則した「平時導入・有事発動型」の防衛策の枠組も提示された(図表3参照)。
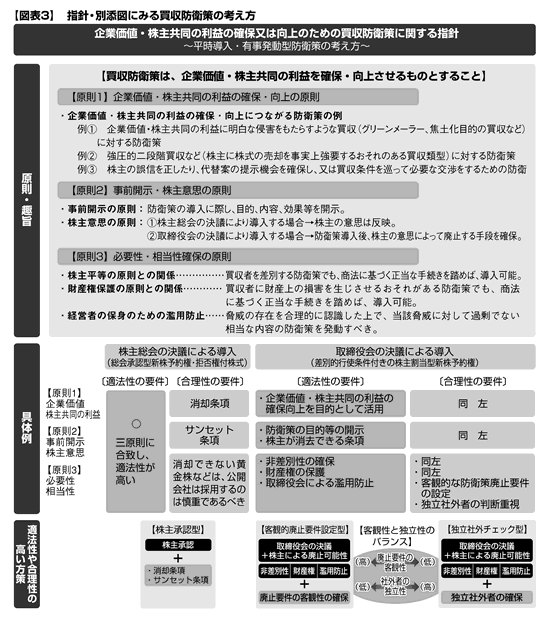
指針は、買収防衛策への関心の高まりを背景に、適法性および合理性が高い買収防衛策を提示することを目的とし、従来の判例・学説、このような買収防衛策の検討結果をまとめた企業価値研究会報告書、また、公表直前に示されたニッポン放送事件東京高裁決定をも踏まえて策定されたものである。
公表直後のニレコ事件東京地裁・東京高裁決定において、ここでの考え方が引用・参照されるなど、企業の行動規範としてはもとより、裁判規範としても一定の役割を担っている(当該指針自体について、買収防衛策に関する最新の状況や裁判所判断に基づき見直しが見込まれる状況にあるので留意されたい)。
指針では、たとえば原則3について、買収防衛策の適法性・合理性を確保するうえで弊害を防止することが不可欠であるとし、「株主平等の原則、財産権の保護、経営者の保身のための濫用防止等に配慮し、必要かつ相当な方法によるべきである」としている。
そのうえで許容される場合の具体例を提示し、たとえば、ブルドックソースのように「株主総会決議に基づいて買収防衛策として新株予約権等を発行するとき」は、①株主共同の利益を確保し、向上させるものであることが推認され(原則1参照)、②株主の意思に依拠し(原則2参照)、かつ、③取締役会の権限濫用のおそれのない必要かつ相当な方法によるものと推認される(原則3参照)と考えられるため、指針の示す3原則に合致し「公正な発行とされる可能性が高い」と述べていた。
なお、証券取引所や機関投資家の買収防衛策に係る基準等も上場・上場廃止、適示開示、株主総会での議案の賛否といった実務上、極めて重要なものであり、その一端を紹介しておきたい(図表4参照)。
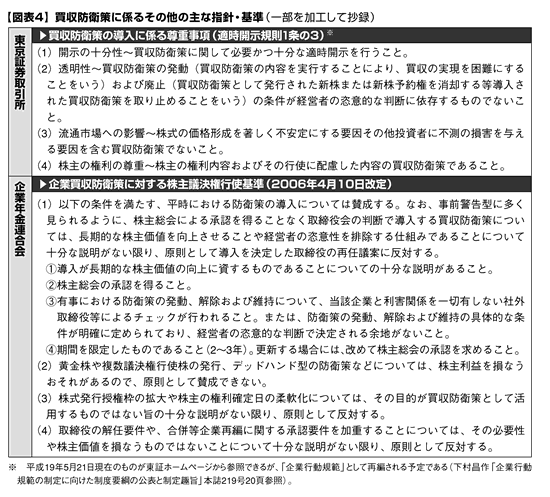
ニッポン放送事件等における判断 それでは、上記のような指針に直接の影響を及ぼしたニッポン放送事件、指針公表後に判断された明確な買収防衛策を巡るニレコ事件、日本技術開発事件について、裁判所の判断を振り返ってみたい。
ニッポン放送事件は、フジテレビジョン(以下「フジテレビ」という)がニッポン放送株式の全部取得を目指して始めたTOB中の平成17年2月21日までにライブドア側の普通株式の取得が37.85%に及ぶに至り、同月23日、ニッポン放送が「第三者割当による新株予約権発行のお知らせ」を公表。フジテレビのみへの新株予約権付与が明らかにされたことなどから、ライブドアが「著しく不公正な方法による発行である」などとして発行差止めを求めた事案である。
裁判所が各段階(図表2参照)で示した規範は図表5のとおりであるが、「経営支配権の維持・確保を主要な目的とする新株予約権の発行が許される特段の事情がある場合」を詳細に例示した東京高裁決定は、本件発行について、(ア)経営者が「自己又は第三者の個人的利益を図るために行ったものでないとはいえる」としながらも、(イ)「経営支配権に現に争いが生じている場面において」、(ウ)ライブドア側の持株比率を低下させ、経営者を支持し事実上の影響力を及ぼす特定の株主・フジテレビによる経営支配権の確保を目的とするものであると認定したうえで、ライブドアがニッポン放送の「事業や資産を食い物にするような目的で株式の敵対的買収を行っていることを認めるに足りる確たる資料はない」として「正当化する特段の事情」を認めなかった。
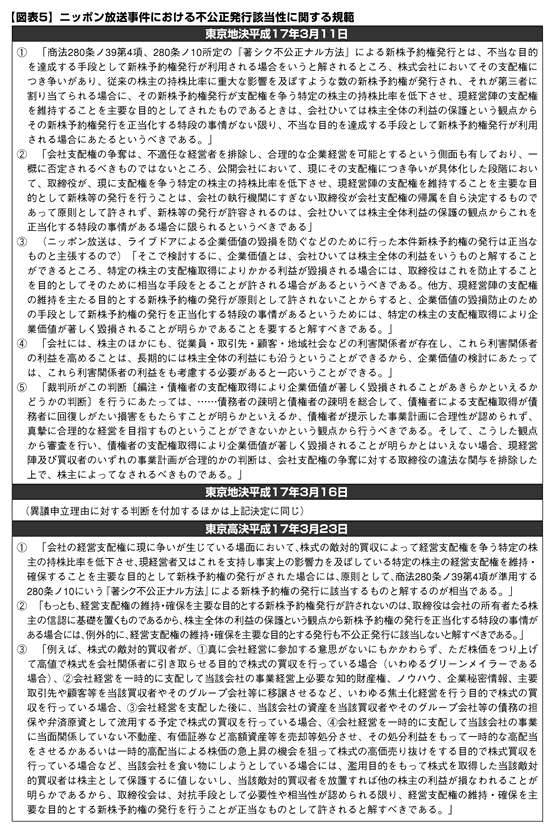
ニレコ事件で示された規範は図表6のとおり。取締役会決議による平時導入・有事発動型の買収防衛策について、6月1日の東京地裁決定は①~③を示し、初判断を行っている。本件では、①につきその仕組みがなく、②につき明確性を欠き、③につき不測の損害を与えるもので相当性を欠くと認定した。東京高裁決定は、この③に焦点をあてるものといえ、本件では「既存株主に受忍させるべきでない損害が生じるおそれがあるから、著しく不公正な方法による」としている。
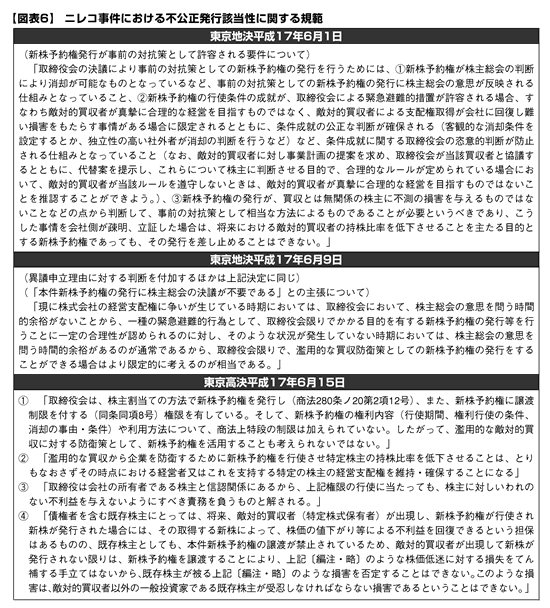
日本技術開発事件では、図表7のような規範が示されたうえ、ここで述べられる相当性について、本件では「直ちに相当性を欠き、取締役会がその権限を濫用したものとまでいうことはできない」とされたものである。
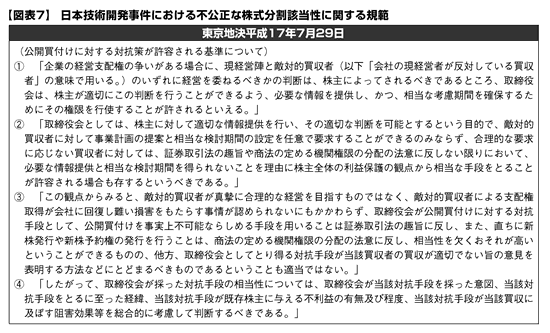
不公正発行に関する過去の判断を振り返る
text 編集部
前回(本誌225号20頁参照)までに、事件の経過や申立て時の主張をみながら、主要争点(図表1参照)の1つとなった「株主平等原則に違反するか」について、決定原文を参照する形で紹介したところである。今回は、買収防衛策としての本件新株予約権無償割当てが「『著しく不公正な方法により行われる場合』に該当するか」について各決定における判断を紹介する前に、最近の仮処分事件で「著しく不公正な方法」かどうかが争われたケースを振り返りながら、どのような規範のもとで各事件の判断がなされてきたのかをみてみたい。
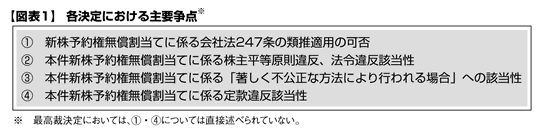
最近の主な仮処分事件 近時の企業買収事案の増加等を背景とし、いわゆる経営支配権の争奪を巡って、株式の買集めを行った者と発行会社との間で事件化するケースも増加した。特に平成16年から平成17年にかけては、会社側が対応策として採った手法に問題があるとして株主側がその差止めを求める事件が相次いだものといえよう(図表2参照)。
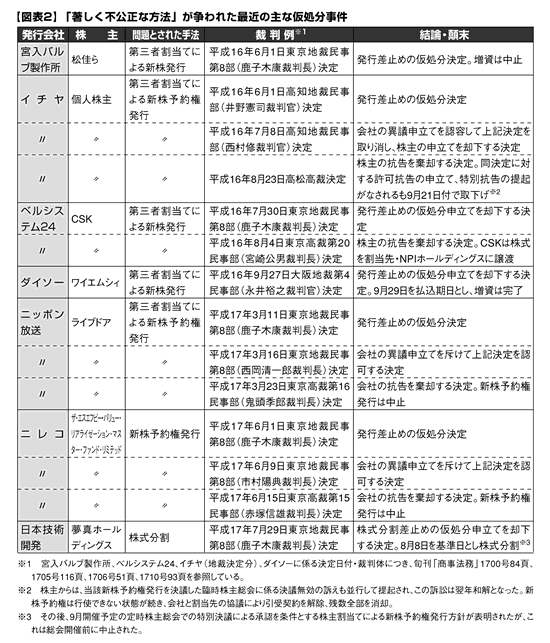
ここで取り上げたのは、会社側の手法が著しく不公正な方法によるものであるとする主張が争われた東京における5、大阪1、高知1の計7事件であるが、会社側の手法が裁判所に認容されず、結果として新株発行等の中止に追い込まれたのは、宮入バルブ製作所、ニッポン放送、ニレコの3事件にとどまる。
買収防衛策として明確に謳われた手法が判断されているのはニレコ事件以降で、ニレコにおいては、平成17年3月14日開催の取締役会で新株予約権の無償発行を内容とする「セキュリティ・プラン」の導入を決議。同日、「企業価値向上に向けた取組みについて(平成18年3月期の重点施策および株主割当による新株予約権の無償発行に関するお知らせ)」として公表された。
ニッポン放送事件における東京高裁平成17年3月23日決定に示された「経営支配権の維持・確保を主要な目的とする新株予約権の発行が許される特段の事情がある場合」(後掲・図表5の下段③参照)に準拠しながら、買収者および一定の関係者が発行済議決権付株式総数の20%を保有するに至った場合に、割当基準日(平成17年3月31日)以降に株式を取得した株主の持株比率を約3分の1に希釈するいわゆる事前警告型の買収防衛策で、申立株主の基準日時点での保有割合は約2.85%であった。
日本技術開発事件での申立株主は、平成17年7月21日時点で約6.83%を保有する筆頭株主。同年6月中に買増しを進め、同月24日には大量保有報告書を提出する5%超保有の株主となっていた。株主は7月7日、業務提携を申し入れたが、会社側は翌8日、「大規模買付行為への対応方針に関するお知らせ」を公表し、20%以上保有の株主を対象とし、「大規模買付ルールが遵守されなかった場合には、具体的な買付方法の如何にかかわらず、取締役会は、会社および株主全体の利益を守ることを目的として、株式分割、新株予約権の発行等、商法その他の法律および定款が認めるものを行使し、大規模買付行為に対抗する場合がある」旨を述べた。
株主は7月11日、同月20日からの公開買付け(TOB)の開始を公表。50%超取得を目指すもので、会社側は同日、大規模買付ルールに反すると発表した後、7月18日の取締役会決議により普通株式1株につき5株の割合で株式分割を行うことが決定、公表された。株主の主張によると、本件株式分割はTOBの実施を事実上困難にするというものであった。
買収防衛指針の策定 ニッポン放送事件高裁決定からニレコ事件地裁決定に至る間となる平成17年5月27日、「企業価値・株主共同の利益の確保又は向上のための買収防衛策に関する指針」(以下「指針」という)が経済産業省・法務省により共同策定されている。ここでは、「3原則」が示され、これに則した「平時導入・有事発動型」の防衛策の枠組も提示された(図表3参照)。
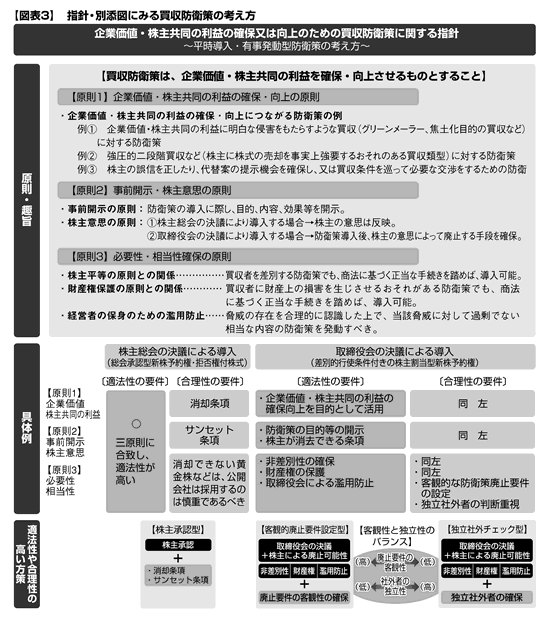
指針は、買収防衛策への関心の高まりを背景に、適法性および合理性が高い買収防衛策を提示することを目的とし、従来の判例・学説、このような買収防衛策の検討結果をまとめた企業価値研究会報告書、また、公表直前に示されたニッポン放送事件東京高裁決定をも踏まえて策定されたものである。
公表直後のニレコ事件東京地裁・東京高裁決定において、ここでの考え方が引用・参照されるなど、企業の行動規範としてはもとより、裁判規範としても一定の役割を担っている(当該指針自体について、買収防衛策に関する最新の状況や裁判所判断に基づき見直しが見込まれる状況にあるので留意されたい)。
指針では、たとえば原則3について、買収防衛策の適法性・合理性を確保するうえで弊害を防止することが不可欠であるとし、「株主平等の原則、財産権の保護、経営者の保身のための濫用防止等に配慮し、必要かつ相当な方法によるべきである」としている。
そのうえで許容される場合の具体例を提示し、たとえば、ブルドックソースのように「株主総会決議に基づいて買収防衛策として新株予約権等を発行するとき」は、①株主共同の利益を確保し、向上させるものであることが推認され(原則1参照)、②株主の意思に依拠し(原則2参照)、かつ、③取締役会の権限濫用のおそれのない必要かつ相当な方法によるものと推認される(原則3参照)と考えられるため、指針の示す3原則に合致し「公正な発行とされる可能性が高い」と述べていた。
なお、証券取引所や機関投資家の買収防衛策に係る基準等も上場・上場廃止、適示開示、株主総会での議案の賛否といった実務上、極めて重要なものであり、その一端を紹介しておきたい(図表4参照)。
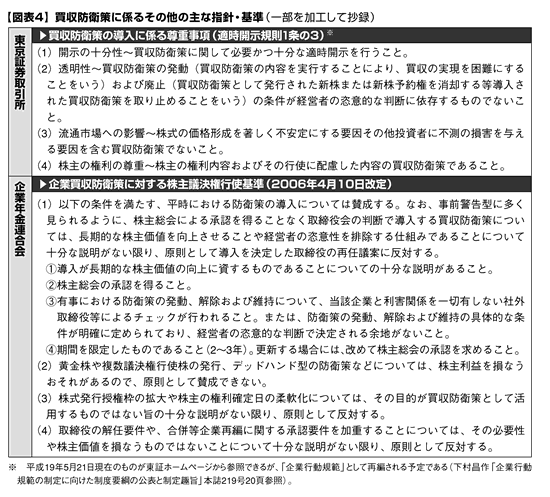
ニッポン放送事件等における判断 それでは、上記のような指針に直接の影響を及ぼしたニッポン放送事件、指針公表後に判断された明確な買収防衛策を巡るニレコ事件、日本技術開発事件について、裁判所の判断を振り返ってみたい。
ニッポン放送事件は、フジテレビジョン(以下「フジテレビ」という)がニッポン放送株式の全部取得を目指して始めたTOB中の平成17年2月21日までにライブドア側の普通株式の取得が37.85%に及ぶに至り、同月23日、ニッポン放送が「第三者割当による新株予約権発行のお知らせ」を公表。フジテレビのみへの新株予約権付与が明らかにされたことなどから、ライブドアが「著しく不公正な方法による発行である」などとして発行差止めを求めた事案である。
裁判所が各段階(図表2参照)で示した規範は図表5のとおりであるが、「経営支配権の維持・確保を主要な目的とする新株予約権の発行が許される特段の事情がある場合」を詳細に例示した東京高裁決定は、本件発行について、(ア)経営者が「自己又は第三者の個人的利益を図るために行ったものでないとはいえる」としながらも、(イ)「経営支配権に現に争いが生じている場面において」、(ウ)ライブドア側の持株比率を低下させ、経営者を支持し事実上の影響力を及ぼす特定の株主・フジテレビによる経営支配権の確保を目的とするものであると認定したうえで、ライブドアがニッポン放送の「事業や資産を食い物にするような目的で株式の敵対的買収を行っていることを認めるに足りる確たる資料はない」として「正当化する特段の事情」を認めなかった。
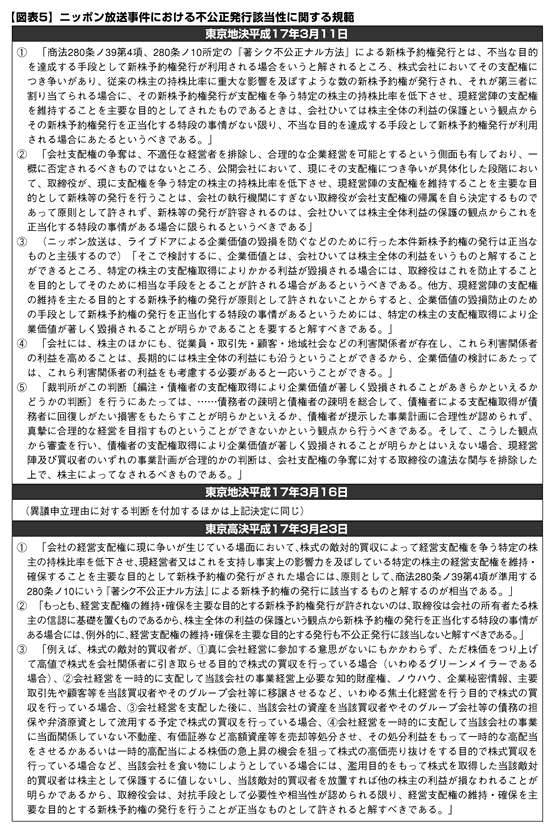
ニレコ事件で示された規範は図表6のとおり。取締役会決議による平時導入・有事発動型の買収防衛策について、6月1日の東京地裁決定は①~③を示し、初判断を行っている。本件では、①につきその仕組みがなく、②につき明確性を欠き、③につき不測の損害を与えるもので相当性を欠くと認定した。東京高裁決定は、この③に焦点をあてるものといえ、本件では「既存株主に受忍させるべきでない損害が生じるおそれがあるから、著しく不公正な方法による」としている。
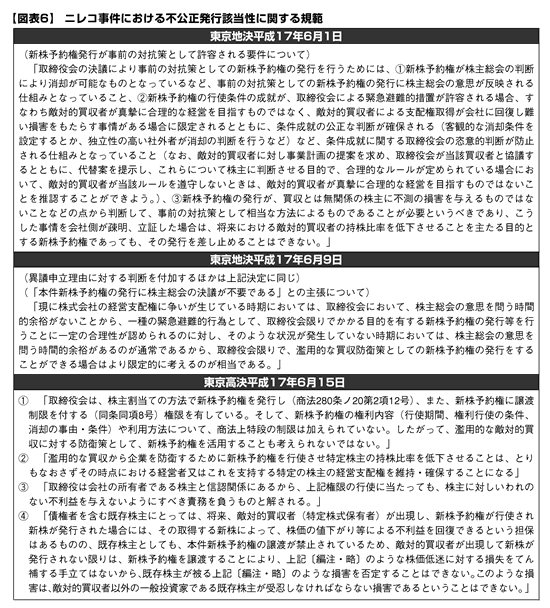
日本技術開発事件では、図表7のような規範が示されたうえ、ここで述べられる相当性について、本件では「直ちに相当性を欠き、取締役会がその権限を濫用したものとまでいうことはできない」とされたものである。
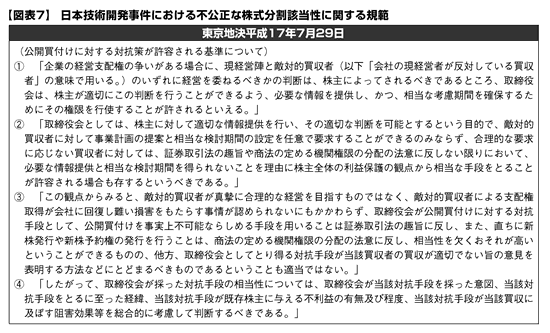
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -

Copyright (C) 2019
SHINNIPPON-HOKI PUBLISHING CO.,LTD.





















