解説記事2007年09月24日 【編集部解説】 自己株式に係る商法(会社法)・企業会計・税法上の取扱いの変遷について(上)(2007年9月24日号・№228)
解説
自己株式に係る商法(会社法)・企業会計・税法上の取扱いの変遷について(上)
text T&Amaster編集部 佐治俊夫
わが国の企業法制、企業会計、企業税制は、この十数年の間に大きな変革がなされてきた。国際社会との調整、バブル崩壊後の低迷した経済からの立直し、電子化等の著しい発展、会社経営の機動性・柔軟性などの向上などが要因として挙げられる。要因(理由付け)はともかくとして、そのあまりに大きな変革に対して、実務家は、戸惑いを隠せないでいた。
昨日まで学んでいた「取得原価主義」が「時価主義」重視に代わり、会社債権者保護を主たる目的とした「資本充実」の原則(「自己株式の取得・保有の禁止」)が度重なる改正で形骸化してきたことも一例といえるだろう。これらの変革は、法制、会計、税制の改正が一気呵成に実施される。社会のニーズに即した変革ともみられるが、制度の変革とは縁のない大多数の存在があった。すなわち、変革が行われたことに気付いてはいても、実感として受け止める必要がない大多数の存在である。
しかし、大がかりな変革では、いつかは制度が変わったことに直面せざるを得ない。例えていえば、「株主資本等変動計算書」の作成である。利益処分による配当も利益剰余金間の振替も縁のない会社は多数存在していたが、利益処分案(利益処分計算書)の作成は廃止され、株式会社は「株主資本等変動計算書」を作成することが義務付けられた。
本稿は、この十数年に大きく制度が変革されてきた項目について、その制度の変更の内容を法制、会計、税制にわたってレビューしよう(振り返ろう)とするものである。戸惑っているうちに、いつのまにか大きく制度が変革されてしまったと感じている実務家や、制度の変遷をもう一度確認しておきたいとする実務家の参考に資すれば幸いと考えている。
第1回の本稿においては、法制、会計、税制の取扱いが大きく見直されてきた自己株式の取扱いの変遷について、検証を試みることにする。
Ⅰ 平成6年商法改正前の自己株式の取扱い
1.商法上の取扱い 平成6年改正前の商法では、自己株式について、①株式消却のための取得、②合併または他の会社の営業全部の譲受けによるとき、③会社の権利の実行にあたりその目的を達成するために必要なとき、④株主の(商法上認められた)株式買取請求に応じて株式の買取りをするとき、(の4つの場合)を除いて自己株式の取得が禁止され(旧商法210条)、株式消却のための取得である場合には遅滞なく失効の手続をとり、その他の場合(上記②から④の場合)には、相当の時期に当該自己株式を処分しなければならない(旧商法211条)、と規定されていた。相当の時期の処分とはできるだけ早く処分することと解されていたが、何らかの事情により自己株式を保有したままの株式会社の例も少なからずあった。
POINT 商法は自己株式の取得・保有を原則禁止
2.会計上の取扱い 会計理論上では、自己株式の処理について、資本控除説と資産説とがある。自己株式の取得は実質的には資本の払戻しとみることができ、会計理論的には資本控除説がより理論的とされていた。昭和26年に公表された「商法と企業会計原則との調整に関する意見書」では、自己株式を資産の部に計上する代わりに、資本の部に控除の形式で表示することが提唱されていた。国際的な会計基準においても資本控除説による場合が多く、我が国では、個別財務諸表の作成においては資産説を採用しながら、アメリカの証券取引委員会が定めている会計規則の影響を色濃く受けている連結財務諸表規則(昭和51年に大蔵省令として制定)では、「連結会社及び持分法を適用した非連結子会社並びに関連会社が保有する連結財務諸表提出会社の株式は、資本に対する控除項目として連結貸借対照表の資本の部の末尾に記載しなければならない。」(連財規43条)と規定し、資本控除説によっている。
しかしながら、商法上の自己株式の取得・保有禁止規定などを論拠として、「株式会社の貸借対照表及び損益計算書に関する規則」(法務省令)および財務諸表規則(大蔵省令)が自己株式を流動資産として取り扱うこと規定(計規12条、財規18条)していたこともあって、制度会計(個別財務諸表の作成)では自己株式は流動資産として取り扱われていた。わが国の大多数の会社が個別財務諸表の作成で足りていることもあり、会計実務においては、資産説が大勢を占めていた。
また、自己株式が資産として会計実務上解されていたことを基因として、自己株式の帳簿価額は購入原価で行うものとされていた(自己株式の取得について原価法が採用されていた)。原価法に基づき購入原価で帳簿に記入し、処分(譲渡)が行われた場合には、自己株式売却損益を損益取引として認識していた(資本控除説の立場から、自己株式の売却益については、資本準備金に組み入れることが妥当とする意見もあったが、必ずしも会計実務に反映されるものとはならなかった)。
株式消却のための取得については、株式の消却が商法上の資本減少の規定に基づいて行われることから、株式会社の資本の減少に際し、減少資本金額と株式の払戻しに要した額との差額が減資差損益として認識されることになる。
POINT 会計実務は資産説で対応
3.税制上の取扱い 法人税法は、自己株式の取得について特段の規定を設けていなかった。すなわち、企業会計の立場と同じ立場に立つことが基本的なスタンスである。企業会計が自己株式の取得について、資産として取り扱い、自己株式売却損益を損益取引と認識していることからすれば、自己株式の取得および処分(譲渡)は、法人税法上の資本等取引には該当しないことになる。会計と税法が同じ立場をとることから、法人税申告書における申告調整を要することもなかった。
株式消却のための取得については、取得と消却は一体的な行為として、資本等取引に該当するものとされてきた。発行法人において損金・益金に該当することはないが、資本減少に際し、株主に支払う金銭その他の資産の時価の合計額が、その会社の資本等のうち、その支払の対象となった株式に係る部分の金額を超える場合、減資会社は株主に対して配当を支払ったものとみなされる。当該減資会社においては、みなし配当に係る源泉徴収義務等が発生し、当該株主はみなし配当等の計算を行うことになる。
POINT 税制と会計実務は一致
Ⅱ 平成13年商法改正前の取扱い
1.商法上の取扱い 自己株式の取得・保有の原則禁止については平成6年商法改正、平成9年の商法改正ならびに「株式の消却の手続に関する商法の特例に関する法律」(株式消却特例法)の制定およびその平成10年の改正(以下これらを「改正法」という)により、その規制が緩和されてきた。具体的には、①取締役・使用人に譲渡・交付するための取得(旧商法210条ノ2第1項)、②ストック・オプションの実行のための取得(旧商法210条ノ2第2項3号)、③定時総会の決議に基づく利益消却のための取得(旧商法212条ノ2第1項)、④株式の譲渡制限がある会社で譲渡先指定の請求があった場合に会社が買受人となる場合(旧商法210条5号)、⑤株式の譲渡制限がある会社で株主が死亡した場合に相続人との合意による買受け(旧商法210条の3第1項)、⑥株式消却特例法3条、3条の2、附則3条に基づく取得が、それぞれに取得の目的・手続・方法・財源などに規制が設けられてはいるものの、認められることになった。
POINT 自己株式の取得・保有原則禁止は緩和へ
2.会計上の取扱い 自己株式の取得規制が緩和されることになっても、計算書類規則12条の取扱いなどは見直されていないため、会計は、「資産説」の考え方を維持していた。日本公認会計士協会では、「改正法によって自己株式の取得に関する事由及び手続きが緩和されたことにより、今後、自己株式に係る取引の増加が予想されるため、従来の自己株式に係る会計実務を踏まえて、個別財務諸表上の会計処理及び表示方法を整理し、会計実務上の指針を提供することとした。」として、「自己株式の会計処理及び表示」を公表した。
そこでは、自己株式の会計処理および表示について、前頁のように基本的な取扱いが明らかにされている。
商法および株式消却特例法が利益消却のための取得・資本準備金による消却を認めたことで、「自己株式の会計処理及び表示」には、「利益による消却又は資本準備金による消却の事由により取得した自己株式の場合」について、上掲のようにその取扱いを明らかにしている。
POINT 会計は実務を踏まえた取扱いを明確化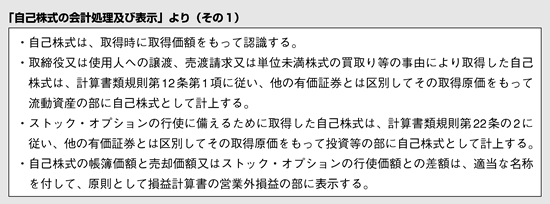
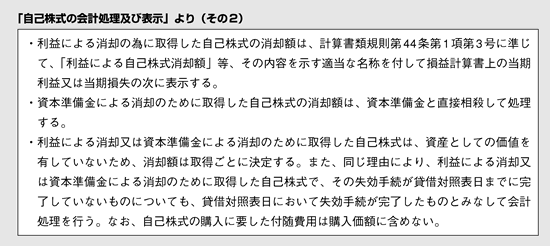
3.税制上の取扱い 改正法では、自己株式の取得・保有規制が緩和されてきたが、取締役・使用人に譲渡・交付するための取得(旧商法210条ノ2第1項)、ストック・オプションの実行のための取得(旧商法210条ノ2第2項3号)、定時総会の決議に基づく利益消却のための取得(旧商法212条ノ2第1項)、株式消却特例法3条、3条の2、附則3条に基づく取得では、公開会社にあっては、その取得方法が市場買付け、公開買付けに限るものと規定されていた。自己株式の取得については(特段に利益消却目的の取得においては)売却した株主において、みなし配当課税が生じる場合が多くなるが、市場取引においては売却株主が当該株式売却取引の相手方を知ることはその市場取引の仕組み上困難であり、みなし配当課税の適切な執行は困難であった。国税庁は平成6年10月31日付の個別照会への回答で、「定時総会の決議に基づく利益消却のための自己株式の取得」については、「みなし配当課税」の適用が行われない取扱いを明らかにした。
また、①上場会社等の利益消却のための公開買付けに応じた個人株主に対してみなし配当課税を適用しないこと、②発行会社が利益消却のための自己株式の買付け・消却を行った場合、その会社の残存株主(個人株主)に対するみなし配当課税を行わないこと、③発行会社が利益消却のための自己株式の買付け・消却を行った場合、その会社の残存株主(法人株主)は、みなし配当課税の適用(受取配当等の益金不算入規定の適用が受けられる)か、みなし配当の非課税規定の適用のいずれかを選択することができる、などを内容とした「租税特別措置法(令)」の改正が平成7年11月17日に公布・施行された。
POINT 株式市場に対応して税制はみなし配当課税の見直しに着手
Ⅲ平成13年商法改正での取扱い(金庫株の解禁)
1.商法上の取扱い 平成13年6月の商法改正では、自己株式の取得および保有が、「原則禁止」から財源規制などの一定の規制の下で認められることになった。すなわち、財源規制およびそれに関する手続規制ならびに株主平等原則に関連する規制を行うものの、自己株式の取得については一般的に許容することになった。平成13年改正前商法に規定されていた目的規制などが廃され、自己株式の相当の時期の処分義務も廃された(これにより自己株式を保有し続けることができるようになった)。
会計・税制との関連では、自己株式の取得と処分が分離されて取り扱われることになった。すなわち、自己株式の取得については、資本の払戻しの性格が明確化され、自己株式の処分(譲渡)については、新株の発行と実質的に同じ手続が要求されることになった。取得した自己株式については、そのまま消却するか、それを当面保有し続けておくかの選択が認められることになった。
POINT 金庫株が原則禁止から一般的許容に展開
2.会計上の取扱い 金庫株の解禁を踏まえ、企業会計基準委員会では、自己株式に関する会計処理を全面的に見直した「自己株式及び法定準備金の取崩等に関する会計基準」・「自己株式及び法定準備金の取崩等に関する会計基準適用指針」を平成14年2月21日に定めた。「自己株式及び法定準備金の取崩等に関する会計基準」では、下掲のように基本的な取扱いが明らかにされている。
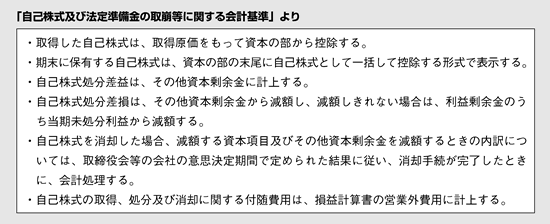
平成14年3月29日に公布された商法施行規則においても、「自己株式は資本の部に別に自己株式の部を設けて、控除する形式で記載し、又は記録しなければならない。」(69条4項)などと規定されることになった。
POINT 自己株式が資本控除説、自己株式取引が資本取引に
3.税制上の取扱い 平成13年6月の商法改正を踏まえ、法人税法では、平成14年4月1日以後に行う自己の株式の譲渡について、譲渡対価の額をその自己の株式の帳簿価額に相当する金額とする措置が講じられた(法人税法61条の2第5項)。この結果、自己の株式を譲渡した場合には、譲渡益または譲渡損の額は生じないことになる。また、自己の株式を譲渡した場合における譲渡対価の額からその自己の株式のその譲渡直前の帳簿価額を減算した金額を資本積立金額の増加額または減少額と規定した。
この他、会計は自己株式の取得に関する付随費用を営業外費用に計上することとしたが、法人税法は自己株式の取得を有価証券の取得として取り扱っているため、付随費用が取得価額を構成することになり、申告調整を要することになった。
POINT 税制は、自己株式を譲渡した場合に課税関係を生じさせない手当て さて、平成13年商法改正により、自己株式の取得・保有が一般的に許容されることになったが、この時点での税制上の取扱いを整理しておこう。
自己株式の取得については税制上は原則(みなし配当課税が適用される場合)と例外(みなし配当課税が適用されない場合)に区分される。
所得税法25条5項および法人税法24条5項は、自己株式の取得(証券取引所の開設する市場における購入による取得その他の政令で定める取得を除く。)により金銭その他の資産の交付を受けた場合において、みなし配当課税の適用があることを規定しており、所得税法施行令61条及び法人税法施行令23条3項にみなし配当課税が適用されない取得が限定列挙されている。限定列挙されている取得とは、市場における購入、組織再編時の承継取得(営業全部の譲受けなど)、単元未満株式・端株の買取請求権の規定による買取りである。
取得法人においては、原則による場合には、交付金銭等の額が取得資本等金額を超える部分の利益積立金額を減少させる(配当による社外流出とみなす)としており(法人税法2条18号カ)、例外による場合には利益積立金額は減少しない。
また、当該自己株式の税務上の取得価額は、原則による場合には、その購入の代価からみなし配当に伴う上記利益積立金減少額を減算した金額となり(法人税法施行令119条1項1号、例外の場合には、その購入の代価(付随費用を加算した金額)となる。
原則による自己株式の取得の場合には、会計上は取得原価をもって認識され、税務上は購入代価からみなし配当相当額を減算した額をもって取得価額とされることから、申告調整を要することになる。
譲渡した株主においては、原則による場合には、譲渡に係る対価の額からみなし配当相当額を控除した金額が譲渡対価の額とされ(措法37条の10第4項5号、法人税法61条の2第1項1号)、例外による場合には、みなし配当相当額は生じないため、調整計算は行われないことになる。(下に続く)(さじ・としお)
自己株式に係る商法(会社法)・企業会計・税法上の取扱いの変遷について(上)
text T&Amaster編集部 佐治俊夫
わが国の企業法制、企業会計、企業税制は、この十数年の間に大きな変革がなされてきた。国際社会との調整、バブル崩壊後の低迷した経済からの立直し、電子化等の著しい発展、会社経営の機動性・柔軟性などの向上などが要因として挙げられる。要因(理由付け)はともかくとして、そのあまりに大きな変革に対して、実務家は、戸惑いを隠せないでいた。
昨日まで学んでいた「取得原価主義」が「時価主義」重視に代わり、会社債権者保護を主たる目的とした「資本充実」の原則(「自己株式の取得・保有の禁止」)が度重なる改正で形骸化してきたことも一例といえるだろう。これらの変革は、法制、会計、税制の改正が一気呵成に実施される。社会のニーズに即した変革ともみられるが、制度の変革とは縁のない大多数の存在があった。すなわち、変革が行われたことに気付いてはいても、実感として受け止める必要がない大多数の存在である。
しかし、大がかりな変革では、いつかは制度が変わったことに直面せざるを得ない。例えていえば、「株主資本等変動計算書」の作成である。利益処分による配当も利益剰余金間の振替も縁のない会社は多数存在していたが、利益処分案(利益処分計算書)の作成は廃止され、株式会社は「株主資本等変動計算書」を作成することが義務付けられた。
本稿は、この十数年に大きく制度が変革されてきた項目について、その制度の変更の内容を法制、会計、税制にわたってレビューしよう(振り返ろう)とするものである。戸惑っているうちに、いつのまにか大きく制度が変革されてしまったと感じている実務家や、制度の変遷をもう一度確認しておきたいとする実務家の参考に資すれば幸いと考えている。
第1回の本稿においては、法制、会計、税制の取扱いが大きく見直されてきた自己株式の取扱いの変遷について、検証を試みることにする。
Ⅰ 平成6年商法改正前の自己株式の取扱い
1.商法上の取扱い 平成6年改正前の商法では、自己株式について、①株式消却のための取得、②合併または他の会社の営業全部の譲受けによるとき、③会社の権利の実行にあたりその目的を達成するために必要なとき、④株主の(商法上認められた)株式買取請求に応じて株式の買取りをするとき、(の4つの場合)を除いて自己株式の取得が禁止され(旧商法210条)、株式消却のための取得である場合には遅滞なく失効の手続をとり、その他の場合(上記②から④の場合)には、相当の時期に当該自己株式を処分しなければならない(旧商法211条)、と規定されていた。相当の時期の処分とはできるだけ早く処分することと解されていたが、何らかの事情により自己株式を保有したままの株式会社の例も少なからずあった。
POINT 商法は自己株式の取得・保有を原則禁止
2.会計上の取扱い 会計理論上では、自己株式の処理について、資本控除説と資産説とがある。自己株式の取得は実質的には資本の払戻しとみることができ、会計理論的には資本控除説がより理論的とされていた。昭和26年に公表された「商法と企業会計原則との調整に関する意見書」では、自己株式を資産の部に計上する代わりに、資本の部に控除の形式で表示することが提唱されていた。国際的な会計基準においても資本控除説による場合が多く、我が国では、個別財務諸表の作成においては資産説を採用しながら、アメリカの証券取引委員会が定めている会計規則の影響を色濃く受けている連結財務諸表規則(昭和51年に大蔵省令として制定)では、「連結会社及び持分法を適用した非連結子会社並びに関連会社が保有する連結財務諸表提出会社の株式は、資本に対する控除項目として連結貸借対照表の資本の部の末尾に記載しなければならない。」(連財規43条)と規定し、資本控除説によっている。
しかしながら、商法上の自己株式の取得・保有禁止規定などを論拠として、「株式会社の貸借対照表及び損益計算書に関する規則」(法務省令)および財務諸表規則(大蔵省令)が自己株式を流動資産として取り扱うこと規定(計規12条、財規18条)していたこともあって、制度会計(個別財務諸表の作成)では自己株式は流動資産として取り扱われていた。わが国の大多数の会社が個別財務諸表の作成で足りていることもあり、会計実務においては、資産説が大勢を占めていた。
また、自己株式が資産として会計実務上解されていたことを基因として、自己株式の帳簿価額は購入原価で行うものとされていた(自己株式の取得について原価法が採用されていた)。原価法に基づき購入原価で帳簿に記入し、処分(譲渡)が行われた場合には、自己株式売却損益を損益取引として認識していた(資本控除説の立場から、自己株式の売却益については、資本準備金に組み入れることが妥当とする意見もあったが、必ずしも会計実務に反映されるものとはならなかった)。
株式消却のための取得については、株式の消却が商法上の資本減少の規定に基づいて行われることから、株式会社の資本の減少に際し、減少資本金額と株式の払戻しに要した額との差額が減資差損益として認識されることになる。
POINT 会計実務は資産説で対応
3.税制上の取扱い 法人税法は、自己株式の取得について特段の規定を設けていなかった。すなわち、企業会計の立場と同じ立場に立つことが基本的なスタンスである。企業会計が自己株式の取得について、資産として取り扱い、自己株式売却損益を損益取引と認識していることからすれば、自己株式の取得および処分(譲渡)は、法人税法上の資本等取引には該当しないことになる。会計と税法が同じ立場をとることから、法人税申告書における申告調整を要することもなかった。
株式消却のための取得については、取得と消却は一体的な行為として、資本等取引に該当するものとされてきた。発行法人において損金・益金に該当することはないが、資本減少に際し、株主に支払う金銭その他の資産の時価の合計額が、その会社の資本等のうち、その支払の対象となった株式に係る部分の金額を超える場合、減資会社は株主に対して配当を支払ったものとみなされる。当該減資会社においては、みなし配当に係る源泉徴収義務等が発生し、当該株主はみなし配当等の計算を行うことになる。
POINT 税制と会計実務は一致
Ⅱ 平成13年商法改正前の取扱い
1.商法上の取扱い 自己株式の取得・保有の原則禁止については平成6年商法改正、平成9年の商法改正ならびに「株式の消却の手続に関する商法の特例に関する法律」(株式消却特例法)の制定およびその平成10年の改正(以下これらを「改正法」という)により、その規制が緩和されてきた。具体的には、①取締役・使用人に譲渡・交付するための取得(旧商法210条ノ2第1項)、②ストック・オプションの実行のための取得(旧商法210条ノ2第2項3号)、③定時総会の決議に基づく利益消却のための取得(旧商法212条ノ2第1項)、④株式の譲渡制限がある会社で譲渡先指定の請求があった場合に会社が買受人となる場合(旧商法210条5号)、⑤株式の譲渡制限がある会社で株主が死亡した場合に相続人との合意による買受け(旧商法210条の3第1項)、⑥株式消却特例法3条、3条の2、附則3条に基づく取得が、それぞれに取得の目的・手続・方法・財源などに規制が設けられてはいるものの、認められることになった。
POINT 自己株式の取得・保有原則禁止は緩和へ
2.会計上の取扱い 自己株式の取得規制が緩和されることになっても、計算書類規則12条の取扱いなどは見直されていないため、会計は、「資産説」の考え方を維持していた。日本公認会計士協会では、「改正法によって自己株式の取得に関する事由及び手続きが緩和されたことにより、今後、自己株式に係る取引の増加が予想されるため、従来の自己株式に係る会計実務を踏まえて、個別財務諸表上の会計処理及び表示方法を整理し、会計実務上の指針を提供することとした。」として、「自己株式の会計処理及び表示」を公表した。
そこでは、自己株式の会計処理および表示について、前頁のように基本的な取扱いが明らかにされている。
商法および株式消却特例法が利益消却のための取得・資本準備金による消却を認めたことで、「自己株式の会計処理及び表示」には、「利益による消却又は資本準備金による消却の事由により取得した自己株式の場合」について、上掲のようにその取扱いを明らかにしている。
POINT 会計は実務を踏まえた取扱いを明確化
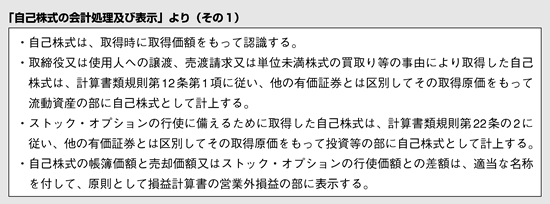
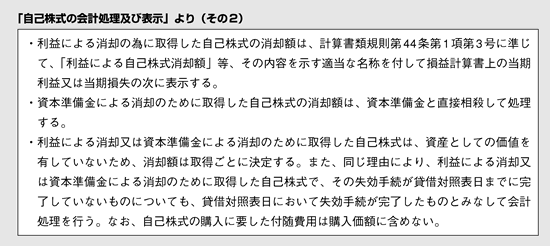
3.税制上の取扱い 改正法では、自己株式の取得・保有規制が緩和されてきたが、取締役・使用人に譲渡・交付するための取得(旧商法210条ノ2第1項)、ストック・オプションの実行のための取得(旧商法210条ノ2第2項3号)、定時総会の決議に基づく利益消却のための取得(旧商法212条ノ2第1項)、株式消却特例法3条、3条の2、附則3条に基づく取得では、公開会社にあっては、その取得方法が市場買付け、公開買付けに限るものと規定されていた。自己株式の取得については(特段に利益消却目的の取得においては)売却した株主において、みなし配当課税が生じる場合が多くなるが、市場取引においては売却株主が当該株式売却取引の相手方を知ることはその市場取引の仕組み上困難であり、みなし配当課税の適切な執行は困難であった。国税庁は平成6年10月31日付の個別照会への回答で、「定時総会の決議に基づく利益消却のための自己株式の取得」については、「みなし配当課税」の適用が行われない取扱いを明らかにした。
また、①上場会社等の利益消却のための公開買付けに応じた個人株主に対してみなし配当課税を適用しないこと、②発行会社が利益消却のための自己株式の買付け・消却を行った場合、その会社の残存株主(個人株主)に対するみなし配当課税を行わないこと、③発行会社が利益消却のための自己株式の買付け・消却を行った場合、その会社の残存株主(法人株主)は、みなし配当課税の適用(受取配当等の益金不算入規定の適用が受けられる)か、みなし配当の非課税規定の適用のいずれかを選択することができる、などを内容とした「租税特別措置法(令)」の改正が平成7年11月17日に公布・施行された。
POINT 株式市場に対応して税制はみなし配当課税の見直しに着手
Ⅲ平成13年商法改正での取扱い(金庫株の解禁)
1.商法上の取扱い 平成13年6月の商法改正では、自己株式の取得および保有が、「原則禁止」から財源規制などの一定の規制の下で認められることになった。すなわち、財源規制およびそれに関する手続規制ならびに株主平等原則に関連する規制を行うものの、自己株式の取得については一般的に許容することになった。平成13年改正前商法に規定されていた目的規制などが廃され、自己株式の相当の時期の処分義務も廃された(これにより自己株式を保有し続けることができるようになった)。
会計・税制との関連では、自己株式の取得と処分が分離されて取り扱われることになった。すなわち、自己株式の取得については、資本の払戻しの性格が明確化され、自己株式の処分(譲渡)については、新株の発行と実質的に同じ手続が要求されることになった。取得した自己株式については、そのまま消却するか、それを当面保有し続けておくかの選択が認められることになった。
POINT 金庫株が原則禁止から一般的許容に展開
2.会計上の取扱い 金庫株の解禁を踏まえ、企業会計基準委員会では、自己株式に関する会計処理を全面的に見直した「自己株式及び法定準備金の取崩等に関する会計基準」・「自己株式及び法定準備金の取崩等に関する会計基準適用指針」を平成14年2月21日に定めた。「自己株式及び法定準備金の取崩等に関する会計基準」では、下掲のように基本的な取扱いが明らかにされている。
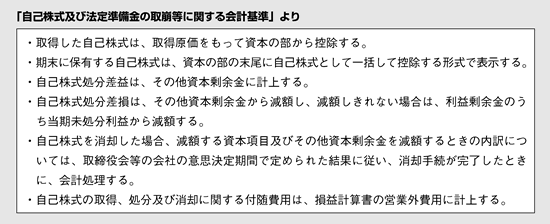
平成14年3月29日に公布された商法施行規則においても、「自己株式は資本の部に別に自己株式の部を設けて、控除する形式で記載し、又は記録しなければならない。」(69条4項)などと規定されることになった。
POINT 自己株式が資本控除説、自己株式取引が資本取引に
3.税制上の取扱い 平成13年6月の商法改正を踏まえ、法人税法では、平成14年4月1日以後に行う自己の株式の譲渡について、譲渡対価の額をその自己の株式の帳簿価額に相当する金額とする措置が講じられた(法人税法61条の2第5項)。この結果、自己の株式を譲渡した場合には、譲渡益または譲渡損の額は生じないことになる。また、自己の株式を譲渡した場合における譲渡対価の額からその自己の株式のその譲渡直前の帳簿価額を減算した金額を資本積立金額の増加額または減少額と規定した。
この他、会計は自己株式の取得に関する付随費用を営業外費用に計上することとしたが、法人税法は自己株式の取得を有価証券の取得として取り扱っているため、付随費用が取得価額を構成することになり、申告調整を要することになった。
POINT 税制は、自己株式を譲渡した場合に課税関係を生じさせない手当て さて、平成13年商法改正により、自己株式の取得・保有が一般的に許容されることになったが、この時点での税制上の取扱いを整理しておこう。
自己株式の取得については税制上は原則(みなし配当課税が適用される場合)と例外(みなし配当課税が適用されない場合)に区分される。
所得税法25条5項および法人税法24条5項は、自己株式の取得(証券取引所の開設する市場における購入による取得その他の政令で定める取得を除く。)により金銭その他の資産の交付を受けた場合において、みなし配当課税の適用があることを規定しており、所得税法施行令61条及び法人税法施行令23条3項にみなし配当課税が適用されない取得が限定列挙されている。限定列挙されている取得とは、市場における購入、組織再編時の承継取得(営業全部の譲受けなど)、単元未満株式・端株の買取請求権の規定による買取りである。
取得法人においては、原則による場合には、交付金銭等の額が取得資本等金額を超える部分の利益積立金額を減少させる(配当による社外流出とみなす)としており(法人税法2条18号カ)、例外による場合には利益積立金額は減少しない。
また、当該自己株式の税務上の取得価額は、原則による場合には、その購入の代価からみなし配当に伴う上記利益積立金減少額を減算した金額となり(法人税法施行令119条1項1号、例外の場合には、その購入の代価(付随費用を加算した金額)となる。
原則による自己株式の取得の場合には、会計上は取得原価をもって認識され、税務上は購入代価からみなし配当相当額を減算した額をもって取得価額とされることから、申告調整を要することになる。
譲渡した株主においては、原則による場合には、譲渡に係る対価の額からみなし配当相当額を控除した金額が譲渡対価の額とされ(措法37条の10第4項5号、法人税法61条の2第1項1号)、例外による場合には、みなし配当相当額は生じないため、調整計算は行われないことになる。(下に続く)(さじ・としお)
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -

Copyright (C) 2019
SHINNIPPON-HOKI PUBLISHING CO.,LTD.




















