解説記事2007年12月10日 【ニュース特集】 自由民主党税制調査会の税制改正審議をクローズアップ(2007年12月10日号・№238)
平成20年度税制改正の(政)審議項目はコレだ!
自由民主党税制調査会の税制改正審議をクローズアップ
平成20年度税制改正については、衆参のネジレ現象で税制改正の終着点が不透明なものとなっているが、自由民主党の税制調査会(津島雄二会長)は12月13日の自民党税制改正大綱決定を目途に、本格的な審議・検討を開始している。
本特集では、自民党税調の審議状況において、政策的問題として検討する重要項目(いわゆるマル政案件)の洗い出しと一次○×が行われたことから、自民党税調での審議状況および平成20年度税制改正における主なマル政案件の内容を取り上げる。
自民党の税制改正に係るスケジュール(想定) まずは、自由民主党の平成20年度税制改正に係るスケジュールを確認してみよう。下記図表1の自民党税調のスケジュールは自民党所属の全国会議員が出席することができる税調小委員会あるいは総会の予定スケジュールだが、小委員会が午後に開催されることが多いため、その日の午前中(あるいは小委員会の開催前)に自民党税調幹部が正副会長・顧問会議などを開催して議事整理を行っている。
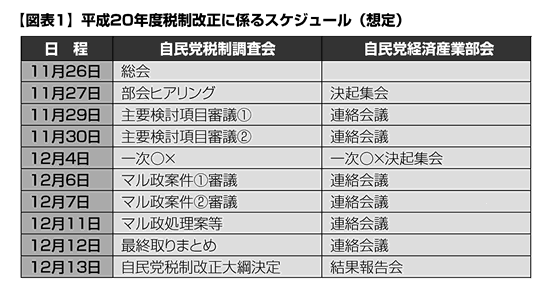
税調のスケジュールに対応する形で要望側(この例では、税制改正要望が多数項目に及ぶ自民党経済産業部会)が連絡会議・打合せ会を開催している。経済産業部会の場合には、連絡会議(決起集会)は昼食時に開催され、午前中に行われた正副会長・顧問会議での審議状況の報告や小委員会での発言事項などの調整が行われる。小委員会は多数の自民党国会議員が参加・発言するため、国会議員1人の発言回数は自ずと制限される。したがって、部会要望事項については、連絡会議などでの調整を行ったうえでのメリハリをつけた発言が行われることになる。小委員会で多くの議員から筋の通った主張が行われれば、その項目の取扱いも変わってくる。自民党税調においても、政治は数の影響を受けざるを得ない。
また、このほか、自民党税調幹部は公明党との与党協議や財政当局との調整を行うことになる。
電話帳・○×・マル政項目って何? 自民党税調では、主要検討項目の審議を行ったうえで、部会要望重点項目の一覧を作成し、各検討項目(マル政案件を除く)の方向性を明らかにする。この部会要望重点項目一覧は、国税関係・地方税関係・関税関係に分類されて作成されるが、この一覧は項目が多くて分厚くなるため、「電話帳」とも呼称されている。最終的には電話帳に記載されたすべての部会要望項目に何らかの結論付けをすることになる。
電話帳に記載の各項目には○△×などの振分け記号が付されており、○であれば税制改正要望が受け入れられることになり、×であればお断りということだ。業界団体などの関係者は、電話帳の○×を見て一喜一憂し、×であれば、さらに要望して△(検討項目)や○となるための陳情を行うことになる。一次の判断で×とされた項目についても、小委員会等の審議で△(検討し、後日報告する)に判断が変更されたり、△△(長期検討とする)に変更されて、翌年度以降の改正に望みをつなぐこともある。
振分け記号のなかでも重要視されているのが、(政)(マル政)である。(政)は、政策的問題として検討するということだが、税制改正の主要検討項目は、(政)として審議されることが通例となっている。
これが平成20年度税制改正の(政)だ 自民党税調で○となった主な事項について、その内容を紹介しよう。
1.生命保険料控除制度の見直し 生命保険料控除制度については、①現行制度(生命保険料控除・個人年金保険料控除)を遺族・老後・医療・介護保障への多様なニーズおよび多様化・複合化した生命保険商品に対応した簡素でわかりやすい汎用的な自助努力を支援する制度(新たな生命保険料控除)に改組すること(図表2参照)や、②公的社会保障制度を補完する医療・介護・年金の各分野における保険商品の重点的な普及の充実・拡大のための自助努力を支援する制度を創設すること(図表3参照)、③民間介護保険の加入者の支払保険料に対し、現行の生命保険料控除とは別枠の所得控除を創設することが、要望されていてマル政となった。
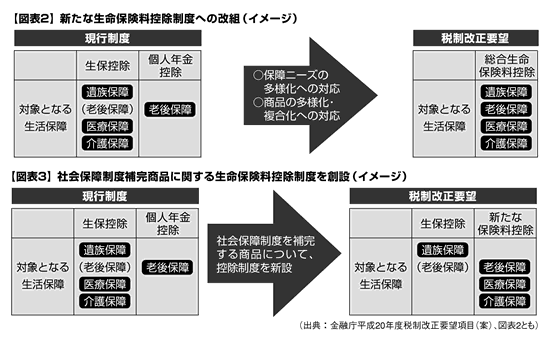
また、かねてより、所得税の各種控除のあり方を議論すべきという意見もあり、特に個人住民税については速やかに整理すべきとの指摘があり、この指摘も併せてマル政になっている。すなわち、生命保険料控除については、拡充・縮小両方向の検討が行われる。
2.寄附税制の拡充 寄附税制では、所得税について①控除限度額(総所得×30%-5,000円)の引上げ、②控除限度額の繰越控除制度の創設、③控除対象額の足切り(5,000円)の撤廃、法人税について、寄附金の損金算入枠の拡大が要望され、マル政になった。
3.証券税制 今号スコープ(40頁)参照。
4.エンジェル税制の拡充 エンジェル税制については、投資時点において投資額をその年の他の株式譲渡益から控除する措置が恒久措置として設けられているが、①投資時点での税額控除制度とすること、②株式取得・損失発生時点の優遇措置の対象所得の範囲を金融所得に拡大すること等が要望され、マル政になった。
5.省エネ改修促進税制の創設 地球温暖化防止に向けて家庭部門のCO2排出量の削減を図るため、既存住宅において一定の省エネ改修(窓の二重サッシ化や壁の断熱化等)を行った場合について、①所得税で省エネ改修費用の10%(上限20万円)を税額控除する特例措置、②固定資産税を3年間1/2に減額する特例措置が要望され、マル政になった。
6.農林水産業と商工業との連携等を促進するための税制措置 農林水産業と商工業との連携等を図り、地域の活力を引き出すような事業活動を行う者の取組みを支援するため、①「農商工連携等計画」の承認を受けた事業者で、同計画に沿った機械・装置の設備投資を行う者についての特別償却制度(または税額控除制度)を創設し、②既存の企業立地促進税制の対象業種に農林水産業と関連の高い業種を追加すること・設備の投資規模要件の引下げ・特別償却率の引上げにより拡充することが要望され、マル政になった。
7.トン数標準税制の導入 外航海運業においては、激しい国際競争のなかにあるが、欧米、韓国等において、みなし利益課税のトン数標準税制が導入された結果、わが国の外航海運事業者は競争条件が不均衡な状態に置かれている。その結果、日本籍船・日本人船員は、極端に減少している。このような事態に対応するため、外航海運市場において世界標準ともいうべきトン数標準税制(船舶のトン数をから算定されるみなし利益に法人税を課税する税制)を創設することが要望され、マル政になった。
8.研究開発税制の延長・拡充 研究開発税制については、①増加額に係る税額控除制度の延長、②税額控除額の上限(法人税額の20%の引上げ)、③繰越税額控除限度超過額の繰越期間(現行1年間)の延長が要望され、マル政になった。
9.情報基盤強化税制の延長・拡充 情報基盤強化税制の適用期限の延長のほか、①部門間・企業間で分断されている情報システムを連携するソフトウェアの対象資産への追加、②インターネット経由で情報処理を行うサービス(SaaS・ASP)の適用対象への追加、③中小企業者等にかかるソフトウェアの取得価額要件(現行年間300万円)の緩和が要望され、マル政になった。
10.人材投資促進税の延長・拡充 人材投資促進税制の適用期限の延長のほか、①中小企業を対象として、教育訓練費の増減に関わらず、教育費の総額の一定割合を税額控除する制度の拡充、②技能承継のための教育訓練費を支援対象に追加が要望され、マル政になった。
11.事業承継税制の抜本拡充 ①一定の事業継続・雇用確保を要件として非上場株式等事業用資産の相続税の80%以上の軽減措置を導入すること、②営業権を始めとする非上場株式の評価について事情の変更等を踏まえた所要の見直しを行うことが要望され、マル政になった。
12.土地税制(登録免許税の特例措置)の延長 ①土地の売買による所有権の移転登記に係る登録免許税の特例(本則20/1,000⇒10/1,000)等の延長、②JリートおよびSPCに係る登録免許税の延長が要望され、マル政になった。
13.道路特定財源の延長 道路特定財源諸税(揮発油税・自動車重量税・軽油引取税・自動車取得税・地方道路譲与税)の暫定税率の適用期限の10年間延長やその用途(道路整備への充当あるいは環境保全に配慮すること)について要望され、その取扱いがマル政になった。
14.公益法人制度改革に伴う税制上の整備 公益法人制度改革に伴い、現行の公益法人は、公益社団(財団)・一般社団(財団)に区分される。①公益社団(財団)に係る税制、一般社団(財団)に係る税制、③新制度への移行に係る税制の措置などの整備が要望され、マル政になった。
15.社会医療法人に係る非課税措置等の創設 地域において確保が困難な医療を担う社会医療法人について、①医療保健業の法人税非課税と収益業務への軽減税率(22%)の適用、②社会医療法人に寄附した者の寄附優遇措置(寄附金控除・相続税非課税・損金算入)が要望され、マル政になった。
16.認定NPO法人税制の拡充 ①認定要件の緩和(パブリック・サポートテストの要件緩和など)、②申請手続の負担軽減・簡素化、③閲覧情報範囲の見直し、④公益法人制度改革に伴う寄附金税制拡充の適用が要望され、マル政になった。
17.事前照会に対する文書回答手続の改善 ①対象となる取引について、現行は「実際に行われた又は確実に行われる取引」に限定しているが、将来行う予定の取引で個別具体的な資料の提示が可能なものを対象に追加すること、②公表範囲、非公表期間について、現行は「事前照会者名、照会内容及び回答内容が一定期間後公表される。」ことになっているが、照会者を特定する情報は原則非公表とするとともに、照会内容等についての照会者からの申し出に基づく非公表期間を延期すること、③回答期限について、現行は「原則3か月以内に行うよう努める。」としているが、「原則3か月以内の極力早期に回答を行うよう努める。」と見直すことが要望され、マル政になった。
18.公的年金からの特別徴収の早急な導入 公的年金から個人住民税の特別徴収を行うことについては、平成21年度を目途に導入ができるように準備を進めるとされているが、収納事務の効率化が図れる特別徴収の早急な導入が要望され、マル政になった。
19.ふるさと納税制度の導入 いわゆる「ふるさと納税制度」を導入するための個人住民税における寄附金税制(所得控除)の抜本的拡充が要望され、マル政になった。総務省が設置したふるさと納税研究会(島田晴雄座長)では、税額控除方式をとることとし、所得税と合わせて適用下限額(5,000円)を超える額の全額を控除する制度設計を行っている。
20.法人住民税・法人事業税の充実確保・地方消費税の充実による偏在性の少ない地方税体系の構築 税源偏在度が大きいとされる地方法人2税のあり方・税源偏在度が小さいとされる地方消費税のあり方について、マル政になった。
増田総務相は、偏在度の小さい地方消費税と偏在度の大きい地方法人2税との(国と地方との)税源交換を提案したが、額賀財務相の理解は得られていない。また、地方税の偏在是正措置として、偏在度の大きい法人事業税の一部を新税を設けて移管し、人口などを基準に自治体に再分配するしくみが検討されている。
21.超長期住宅(200年住宅)に係る税額の減額措置の創設 耐久性、耐震性および可変性を備えた質の高い住宅の供給および適切な維持管理等による住宅の長寿命化を推進するため、一定の基準に適合する認定住宅に係る登録免許税・固定資産税・不動産取得税の軽減特例措置の創設が要望され、マル政になった。
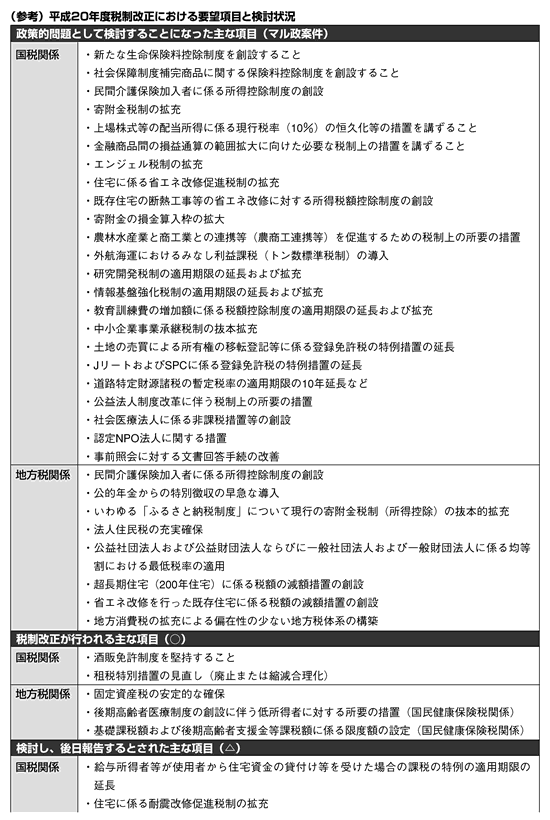
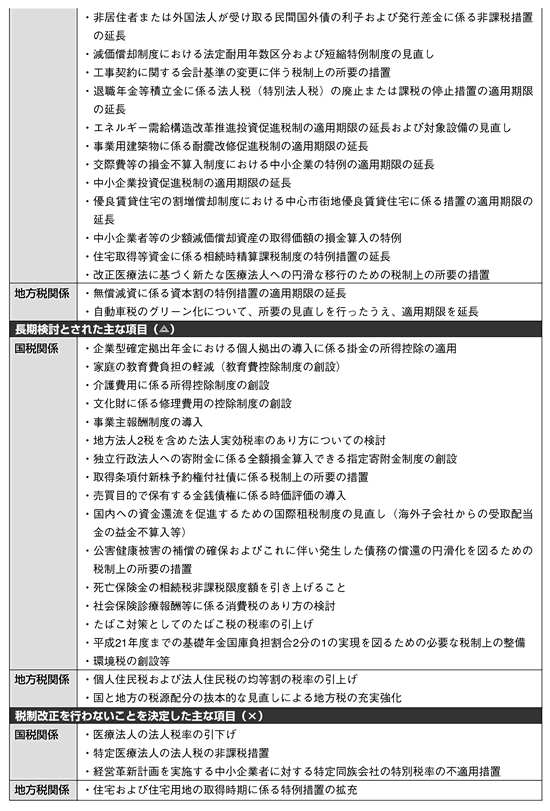
自由民主党税制調査会の税制改正審議をクローズアップ
平成20年度税制改正については、衆参のネジレ現象で税制改正の終着点が不透明なものとなっているが、自由民主党の税制調査会(津島雄二会長)は12月13日の自民党税制改正大綱決定を目途に、本格的な審議・検討を開始している。
本特集では、自民党税調の審議状況において、政策的問題として検討する重要項目(いわゆるマル政案件)の洗い出しと一次○×が行われたことから、自民党税調での審議状況および平成20年度税制改正における主なマル政案件の内容を取り上げる。
自民党の税制改正に係るスケジュール(想定) まずは、自由民主党の平成20年度税制改正に係るスケジュールを確認してみよう。下記図表1の自民党税調のスケジュールは自民党所属の全国会議員が出席することができる税調小委員会あるいは総会の予定スケジュールだが、小委員会が午後に開催されることが多いため、その日の午前中(あるいは小委員会の開催前)に自民党税調幹部が正副会長・顧問会議などを開催して議事整理を行っている。
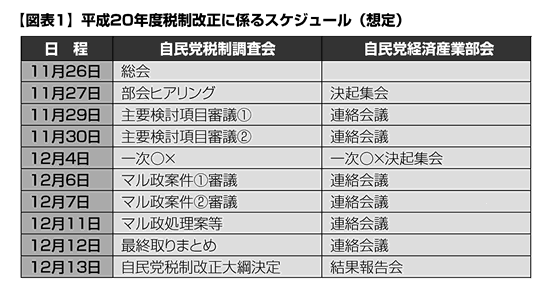
税調のスケジュールに対応する形で要望側(この例では、税制改正要望が多数項目に及ぶ自民党経済産業部会)が連絡会議・打合せ会を開催している。経済産業部会の場合には、連絡会議(決起集会)は昼食時に開催され、午前中に行われた正副会長・顧問会議での審議状況の報告や小委員会での発言事項などの調整が行われる。小委員会は多数の自民党国会議員が参加・発言するため、国会議員1人の発言回数は自ずと制限される。したがって、部会要望事項については、連絡会議などでの調整を行ったうえでのメリハリをつけた発言が行われることになる。小委員会で多くの議員から筋の通った主張が行われれば、その項目の取扱いも変わってくる。自民党税調においても、政治は数の影響を受けざるを得ない。
また、このほか、自民党税調幹部は公明党との与党協議や財政当局との調整を行うことになる。
電話帳・○×・マル政項目って何? 自民党税調では、主要検討項目の審議を行ったうえで、部会要望重点項目の一覧を作成し、各検討項目(マル政案件を除く)の方向性を明らかにする。この部会要望重点項目一覧は、国税関係・地方税関係・関税関係に分類されて作成されるが、この一覧は項目が多くて分厚くなるため、「電話帳」とも呼称されている。最終的には電話帳に記載されたすべての部会要望項目に何らかの結論付けをすることになる。
電話帳に記載の各項目には○△×などの振分け記号が付されており、○であれば税制改正要望が受け入れられることになり、×であればお断りということだ。業界団体などの関係者は、電話帳の○×を見て一喜一憂し、×であれば、さらに要望して△(検討項目)や○となるための陳情を行うことになる。一次の判断で×とされた項目についても、小委員会等の審議で△(検討し、後日報告する)に判断が変更されたり、△△(長期検討とする)に変更されて、翌年度以降の改正に望みをつなぐこともある。
振分け記号のなかでも重要視されているのが、(政)(マル政)である。(政)は、政策的問題として検討するということだが、税制改正の主要検討項目は、(政)として審議されることが通例となっている。
これが平成20年度税制改正の(政)だ 自民党税調で○となった主な事項について、その内容を紹介しよう。
1.生命保険料控除制度の見直し 生命保険料控除制度については、①現行制度(生命保険料控除・個人年金保険料控除)を遺族・老後・医療・介護保障への多様なニーズおよび多様化・複合化した生命保険商品に対応した簡素でわかりやすい汎用的な自助努力を支援する制度(新たな生命保険料控除)に改組すること(図表2参照)や、②公的社会保障制度を補完する医療・介護・年金の各分野における保険商品の重点的な普及の充実・拡大のための自助努力を支援する制度を創設すること(図表3参照)、③民間介護保険の加入者の支払保険料に対し、現行の生命保険料控除とは別枠の所得控除を創設することが、要望されていてマル政となった。
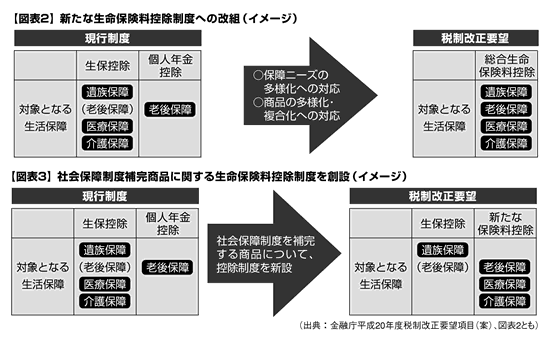
また、かねてより、所得税の各種控除のあり方を議論すべきという意見もあり、特に個人住民税については速やかに整理すべきとの指摘があり、この指摘も併せてマル政になっている。すなわち、生命保険料控除については、拡充・縮小両方向の検討が行われる。
2.寄附税制の拡充 寄附税制では、所得税について①控除限度額(総所得×30%-5,000円)の引上げ、②控除限度額の繰越控除制度の創設、③控除対象額の足切り(5,000円)の撤廃、法人税について、寄附金の損金算入枠の拡大が要望され、マル政になった。
3.証券税制 今号スコープ(40頁)参照。
4.エンジェル税制の拡充 エンジェル税制については、投資時点において投資額をその年の他の株式譲渡益から控除する措置が恒久措置として設けられているが、①投資時点での税額控除制度とすること、②株式取得・損失発生時点の優遇措置の対象所得の範囲を金融所得に拡大すること等が要望され、マル政になった。
5.省エネ改修促進税制の創設 地球温暖化防止に向けて家庭部門のCO2排出量の削減を図るため、既存住宅において一定の省エネ改修(窓の二重サッシ化や壁の断熱化等)を行った場合について、①所得税で省エネ改修費用の10%(上限20万円)を税額控除する特例措置、②固定資産税を3年間1/2に減額する特例措置が要望され、マル政になった。
6.農林水産業と商工業との連携等を促進するための税制措置 農林水産業と商工業との連携等を図り、地域の活力を引き出すような事業活動を行う者の取組みを支援するため、①「農商工連携等計画」の承認を受けた事業者で、同計画に沿った機械・装置の設備投資を行う者についての特別償却制度(または税額控除制度)を創設し、②既存の企業立地促進税制の対象業種に農林水産業と関連の高い業種を追加すること・設備の投資規模要件の引下げ・特別償却率の引上げにより拡充することが要望され、マル政になった。
7.トン数標準税制の導入 外航海運業においては、激しい国際競争のなかにあるが、欧米、韓国等において、みなし利益課税のトン数標準税制が導入された結果、わが国の外航海運事業者は競争条件が不均衡な状態に置かれている。その結果、日本籍船・日本人船員は、極端に減少している。このような事態に対応するため、外航海運市場において世界標準ともいうべきトン数標準税制(船舶のトン数をから算定されるみなし利益に法人税を課税する税制)を創設することが要望され、マル政になった。
8.研究開発税制の延長・拡充 研究開発税制については、①増加額に係る税額控除制度の延長、②税額控除額の上限(法人税額の20%の引上げ)、③繰越税額控除限度超過額の繰越期間(現行1年間)の延長が要望され、マル政になった。
9.情報基盤強化税制の延長・拡充 情報基盤強化税制の適用期限の延長のほか、①部門間・企業間で分断されている情報システムを連携するソフトウェアの対象資産への追加、②インターネット経由で情報処理を行うサービス(SaaS・ASP)の適用対象への追加、③中小企業者等にかかるソフトウェアの取得価額要件(現行年間300万円)の緩和が要望され、マル政になった。
10.人材投資促進税の延長・拡充 人材投資促進税制の適用期限の延長のほか、①中小企業を対象として、教育訓練費の増減に関わらず、教育費の総額の一定割合を税額控除する制度の拡充、②技能承継のための教育訓練費を支援対象に追加が要望され、マル政になった。
11.事業承継税制の抜本拡充 ①一定の事業継続・雇用確保を要件として非上場株式等事業用資産の相続税の80%以上の軽減措置を導入すること、②営業権を始めとする非上場株式の評価について事情の変更等を踏まえた所要の見直しを行うことが要望され、マル政になった。
12.土地税制(登録免許税の特例措置)の延長 ①土地の売買による所有権の移転登記に係る登録免許税の特例(本則20/1,000⇒10/1,000)等の延長、②JリートおよびSPCに係る登録免許税の延長が要望され、マル政になった。
13.道路特定財源の延長 道路特定財源諸税(揮発油税・自動車重量税・軽油引取税・自動車取得税・地方道路譲与税)の暫定税率の適用期限の10年間延長やその用途(道路整備への充当あるいは環境保全に配慮すること)について要望され、その取扱いがマル政になった。
14.公益法人制度改革に伴う税制上の整備 公益法人制度改革に伴い、現行の公益法人は、公益社団(財団)・一般社団(財団)に区分される。①公益社団(財団)に係る税制、一般社団(財団)に係る税制、③新制度への移行に係る税制の措置などの整備が要望され、マル政になった。
15.社会医療法人に係る非課税措置等の創設 地域において確保が困難な医療を担う社会医療法人について、①医療保健業の法人税非課税と収益業務への軽減税率(22%)の適用、②社会医療法人に寄附した者の寄附優遇措置(寄附金控除・相続税非課税・損金算入)が要望され、マル政になった。
16.認定NPO法人税制の拡充 ①認定要件の緩和(パブリック・サポートテストの要件緩和など)、②申請手続の負担軽減・簡素化、③閲覧情報範囲の見直し、④公益法人制度改革に伴う寄附金税制拡充の適用が要望され、マル政になった。
17.事前照会に対する文書回答手続の改善 ①対象となる取引について、現行は「実際に行われた又は確実に行われる取引」に限定しているが、将来行う予定の取引で個別具体的な資料の提示が可能なものを対象に追加すること、②公表範囲、非公表期間について、現行は「事前照会者名、照会内容及び回答内容が一定期間後公表される。」ことになっているが、照会者を特定する情報は原則非公表とするとともに、照会内容等についての照会者からの申し出に基づく非公表期間を延期すること、③回答期限について、現行は「原則3か月以内に行うよう努める。」としているが、「原則3か月以内の極力早期に回答を行うよう努める。」と見直すことが要望され、マル政になった。
18.公的年金からの特別徴収の早急な導入 公的年金から個人住民税の特別徴収を行うことについては、平成21年度を目途に導入ができるように準備を進めるとされているが、収納事務の効率化が図れる特別徴収の早急な導入が要望され、マル政になった。
19.ふるさと納税制度の導入 いわゆる「ふるさと納税制度」を導入するための個人住民税における寄附金税制(所得控除)の抜本的拡充が要望され、マル政になった。総務省が設置したふるさと納税研究会(島田晴雄座長)では、税額控除方式をとることとし、所得税と合わせて適用下限額(5,000円)を超える額の全額を控除する制度設計を行っている。
20.法人住民税・法人事業税の充実確保・地方消費税の充実による偏在性の少ない地方税体系の構築 税源偏在度が大きいとされる地方法人2税のあり方・税源偏在度が小さいとされる地方消費税のあり方について、マル政になった。
増田総務相は、偏在度の小さい地方消費税と偏在度の大きい地方法人2税との(国と地方との)税源交換を提案したが、額賀財務相の理解は得られていない。また、地方税の偏在是正措置として、偏在度の大きい法人事業税の一部を新税を設けて移管し、人口などを基準に自治体に再分配するしくみが検討されている。
21.超長期住宅(200年住宅)に係る税額の減額措置の創設 耐久性、耐震性および可変性を備えた質の高い住宅の供給および適切な維持管理等による住宅の長寿命化を推進するため、一定の基準に適合する認定住宅に係る登録免許税・固定資産税・不動産取得税の軽減特例措置の創設が要望され、マル政になった。
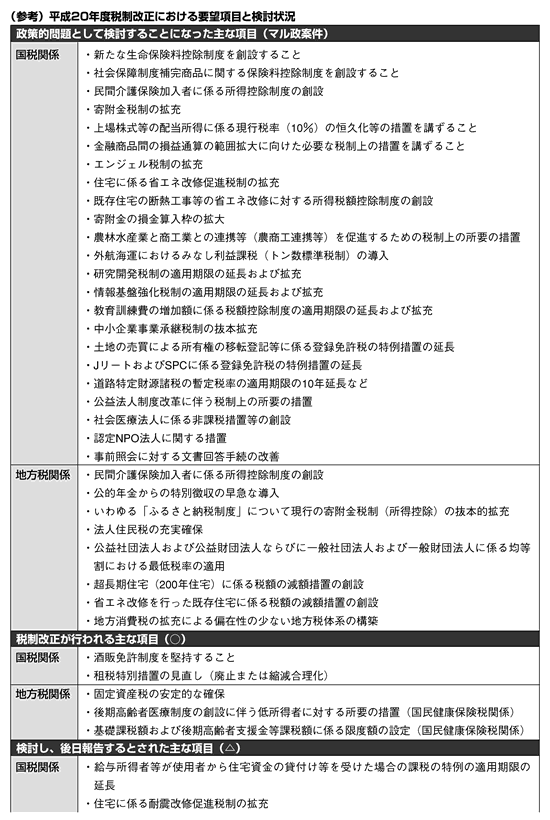
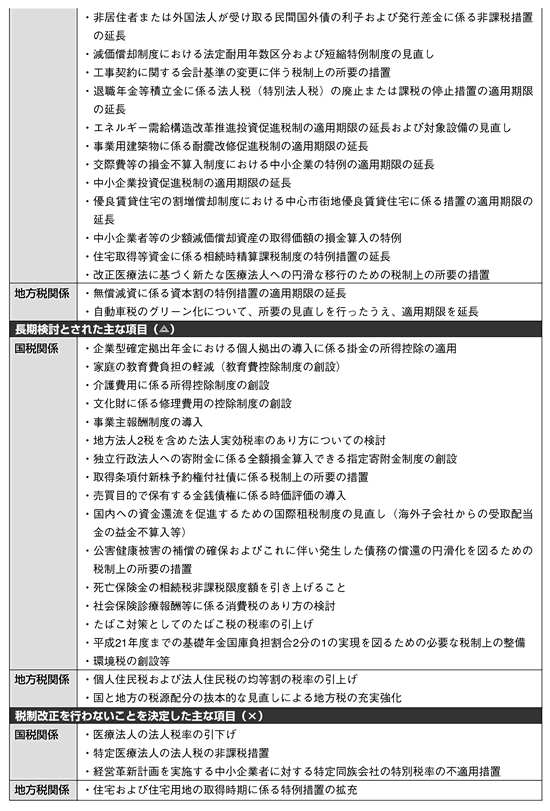
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -























