解説記事2007年12月17日 【ニュース特集】 早出し!「法定耐用年数改正」に関するQ&A(2007年12月17日号・№239)
平成20年度税制改正最新情報
早出し!「法定耐用年数改正」に関するQ&A
去る12月13日、与党から平成20年度税制改正大綱が公表された。衆参のねじれ現象下で全体的に改正内容が小粒といわれるなかにあって、“歴史的”な大改正であり、かつ税負担、実務への影響も大きいのが、法定耐用年数の改正だ。
平成20年度税制改正により、法定耐用年数省令「別表2」(機械及び装置の耐用年数表)は従来の390区分から55区分へと大幅に簡素化されることになる(今号6頁表参照。本稿では単に「別表2」という)。これに伴い、実務上の論点もいくつか浮上している。本特集では、現時点で判明している事項をQA形式にまとめた。
Q 要するに何が変わるの?
A 平成20年度税制改正で最も大きく変わるのが、別表2です。現行制度上、別表2には、「機械及び装置」の耐用年数が390区分に渡って細かく規定されていますが、平成20年度税制改正により、これが55区分に簡素化(大括り化)されます。
といっても、単に耐用年数の区分が減っただけではありません。今回の改正のポイントは、これまでは「設備ごと」に定められていた耐用年数が、「業種ごと」の区分により定められる点です。
したがって、理屈のうえでは、1つの会社内で複数の異なる業種に係る事業が営まれており、それぞれの事業において同一種の設備が用いられている場合には、これら1つの会社内の同一種の設備であっても「複数」の異なる耐用年数が適用されることがあり得ると考えられます。
Q 新しい別表2はどうやって読むの?
A 「業種ごと」に耐用年数が定められる別表2においては、1つの業種区分において複数の耐用年数が並んでいる場合がありますが、そのうち1番下にある「その他の設備」の耐用年数がその業種における「原則的」な耐用年数になります(図1参照)。
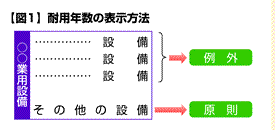
それ以外のものは、「例外」として位置付けられ、たとえば、19年度税制改正で耐用年数が短縮されたフラットパネルディスプレイ製造設備は、耐用年数が原則8年の「電子部品・デバイス・電子回路製造業用設備」に属するものの、同設備の耐用年数は個別に5年と定められます。
Q 別表2以外は変わらない?
A 今回の改正は別表2が中心となりますが、その他でも一部別表の統廃合が行われます。具体的には、別表7(農業用の減価償却資産)が別表1(建物、構築物、車両、器具・備品等)に吸収されるほか、別表5(汚染処理用の減価償却資産)と別表6(ばい煙処理用の減価償却資産)が統合され、「公害防止用減価償却資産」に関する新しい別表となります(図2参照)。
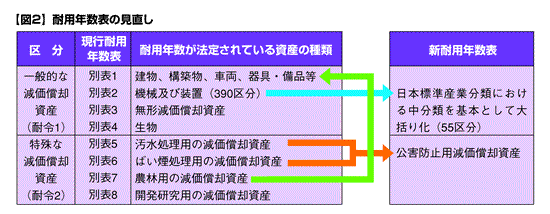
Q 今回の税制改正で耐用年数は短くなるのですか?
A 今回の改正では「減価償却資産の使用実態を踏まえて」法定耐用年数の見直しを図ったとのことであり、大部分のものは短くなるか、変わりませんが、一部は従来より長くなるものもあるようです。
Q 新しい法定耐用年数はいつから適用されますか?
A 平成20年4月1日以後に開始する事業年度から適用されることになります。
平成19年度税制改正における減価償却方法の改正(250%定率法の導入等)では、平成19年4月1日以後に「事業供用」していることが適用要件の1つとなっていましたが、今回の法定耐用年数の見直しでは、取得日や事業供用日に関係なく、法定耐用年数が改正されるすべての減価償却資産に対し、「平成20年4月1日以後に開始する事業年度」において、新たな償却率が適用されることになります。
Q 旧定額・旧定率法適用資産にも新耐用年数の適用あり?
A 適用されます。上記のとおり、新法定耐用年数は新規取得設備のみならず、既存設備に対しても適用されることになるため、減価償却資産に対し新旧定額法・新旧定率法のいずれが適用されているかは問われません。
Q 税法基準に基づく新たな償却率を会計上も適用したら問題あり?
A 監査上の問題が生じる可能性があります。平成19年度税制改正における新減価償却制度導入に伴って償却方法を変更する場合(旧定額法→250%定率法、旧定率法→新定額法)、会計上は、償却方法の変更について合理的な理由が求められました(日本公認会計士協会「減価償却に関する当面の監査上の取扱い」を参照(http://www.hp.jicpa.or.jp/specialized_field/81_1.html))。
同様の問題は、今回の法定耐用年数改正による償却率の変更においても起こる可能性があるといえます。
Q 耐用年数通達はどうなる?
A 別表2において、これまで「設備ごと」に定めていた耐用年数が「業種ごと」に分けて定められたことで、個別の設備についての詳細な定義に関する記述は改廃される可能性があります。
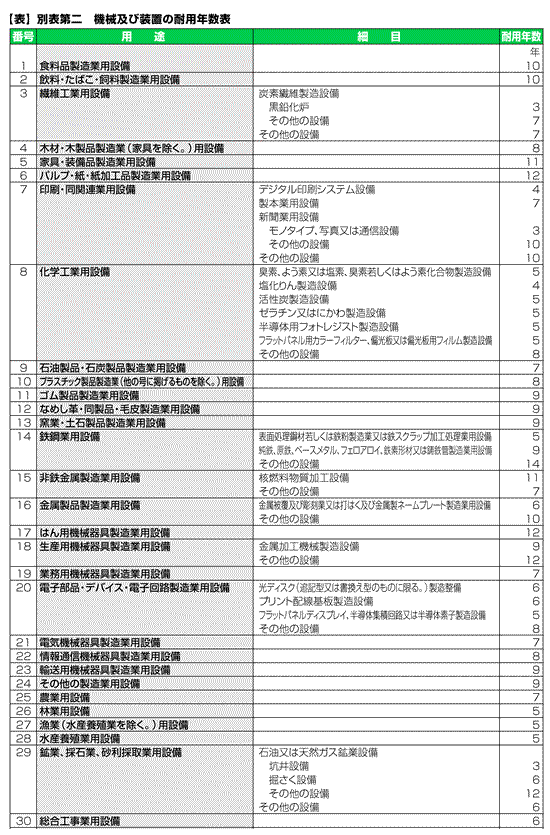
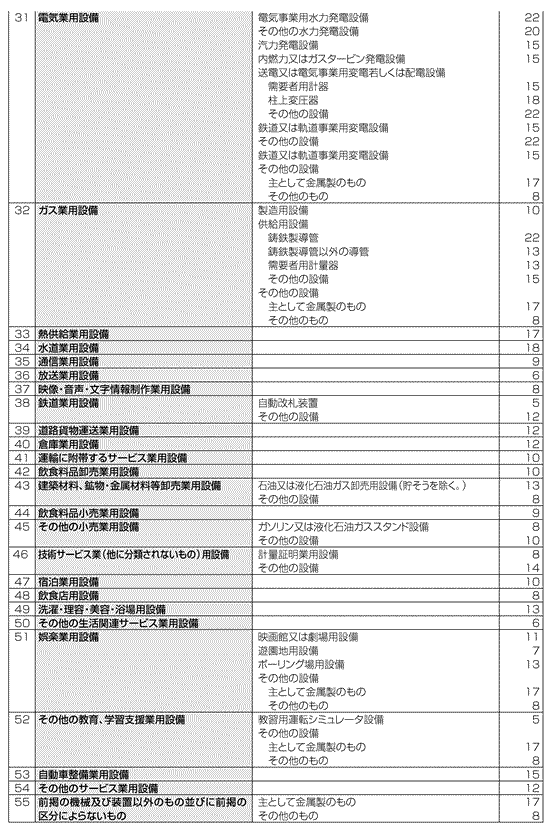
早出し!「法定耐用年数改正」に関するQ&A
去る12月13日、与党から平成20年度税制改正大綱が公表された。衆参のねじれ現象下で全体的に改正内容が小粒といわれるなかにあって、“歴史的”な大改正であり、かつ税負担、実務への影響も大きいのが、法定耐用年数の改正だ。
平成20年度税制改正により、法定耐用年数省令「別表2」(機械及び装置の耐用年数表)は従来の390区分から55区分へと大幅に簡素化されることになる(今号6頁表参照。本稿では単に「別表2」という)。これに伴い、実務上の論点もいくつか浮上している。本特集では、現時点で判明している事項をQA形式にまとめた。
Q 要するに何が変わるの?
A 平成20年度税制改正で最も大きく変わるのが、別表2です。現行制度上、別表2には、「機械及び装置」の耐用年数が390区分に渡って細かく規定されていますが、平成20年度税制改正により、これが55区分に簡素化(大括り化)されます。
といっても、単に耐用年数の区分が減っただけではありません。今回の改正のポイントは、これまでは「設備ごと」に定められていた耐用年数が、「業種ごと」の区分により定められる点です。
したがって、理屈のうえでは、1つの会社内で複数の異なる業種に係る事業が営まれており、それぞれの事業において同一種の設備が用いられている場合には、これら1つの会社内の同一種の設備であっても「複数」の異なる耐用年数が適用されることがあり得ると考えられます。
Q 新しい別表2はどうやって読むの?
A 「業種ごと」に耐用年数が定められる別表2においては、1つの業種区分において複数の耐用年数が並んでいる場合がありますが、そのうち1番下にある「その他の設備」の耐用年数がその業種における「原則的」な耐用年数になります(図1参照)。
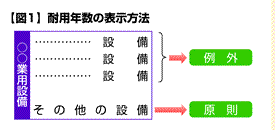
それ以外のものは、「例外」として位置付けられ、たとえば、19年度税制改正で耐用年数が短縮されたフラットパネルディスプレイ製造設備は、耐用年数が原則8年の「電子部品・デバイス・電子回路製造業用設備」に属するものの、同設備の耐用年数は個別に5年と定められます。
Q 別表2以外は変わらない?
A 今回の改正は別表2が中心となりますが、その他でも一部別表の統廃合が行われます。具体的には、別表7(農業用の減価償却資産)が別表1(建物、構築物、車両、器具・備品等)に吸収されるほか、別表5(汚染処理用の減価償却資産)と別表6(ばい煙処理用の減価償却資産)が統合され、「公害防止用減価償却資産」に関する新しい別表となります(図2参照)。
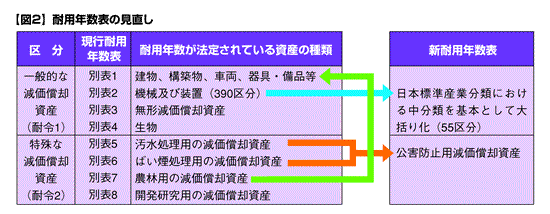
Q 今回の税制改正で耐用年数は短くなるのですか?
A 今回の改正では「減価償却資産の使用実態を踏まえて」法定耐用年数の見直しを図ったとのことであり、大部分のものは短くなるか、変わりませんが、一部は従来より長くなるものもあるようです。
Q 新しい法定耐用年数はいつから適用されますか?
A 平成20年4月1日以後に開始する事業年度から適用されることになります。
平成19年度税制改正における減価償却方法の改正(250%定率法の導入等)では、平成19年4月1日以後に「事業供用」していることが適用要件の1つとなっていましたが、今回の法定耐用年数の見直しでは、取得日や事業供用日に関係なく、法定耐用年数が改正されるすべての減価償却資産に対し、「平成20年4月1日以後に開始する事業年度」において、新たな償却率が適用されることになります。
Q 旧定額・旧定率法適用資産にも新耐用年数の適用あり?
A 適用されます。上記のとおり、新法定耐用年数は新規取得設備のみならず、既存設備に対しても適用されることになるため、減価償却資産に対し新旧定額法・新旧定率法のいずれが適用されているかは問われません。
Q 税法基準に基づく新たな償却率を会計上も適用したら問題あり?
A 監査上の問題が生じる可能性があります。平成19年度税制改正における新減価償却制度導入に伴って償却方法を変更する場合(旧定額法→250%定率法、旧定率法→新定額法)、会計上は、償却方法の変更について合理的な理由が求められました(日本公認会計士協会「減価償却に関する当面の監査上の取扱い」を参照(http://www.hp.jicpa.or.jp/specialized_field/81_1.html))。
同様の問題は、今回の法定耐用年数改正による償却率の変更においても起こる可能性があるといえます。
Q 耐用年数通達はどうなる?
A 別表2において、これまで「設備ごと」に定めていた耐用年数が「業種ごと」に分けて定められたことで、個別の設備についての詳細な定義に関する記述は改廃される可能性があります。
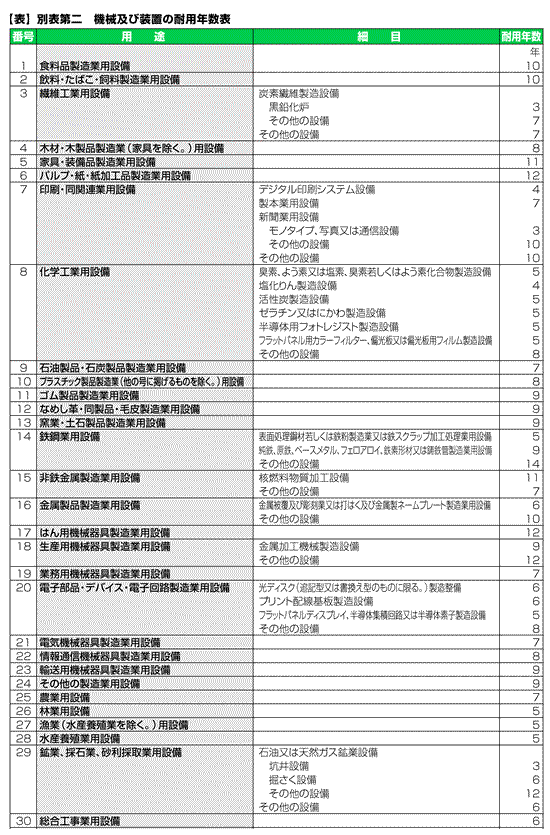
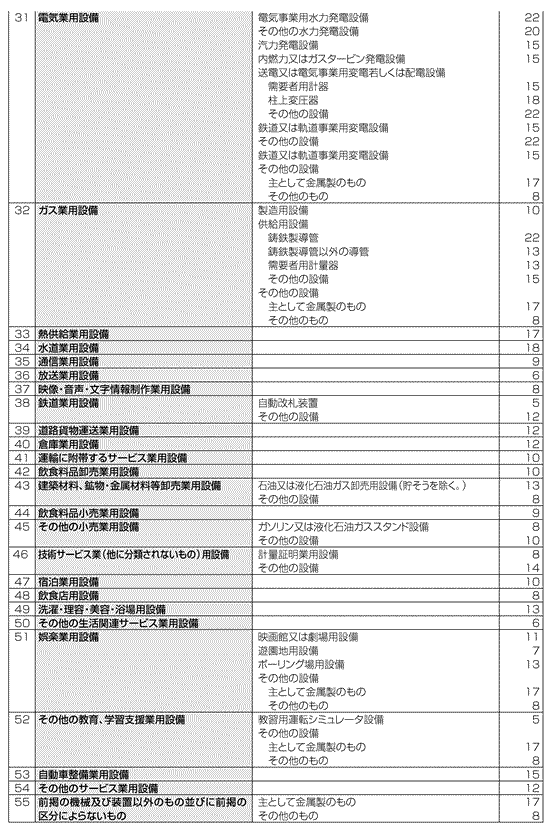
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -

Copyright (C) 2019
SHINNIPPON-HOKI PUBLISHING CO.,LTD.




















