解説記事2007年12月24日 【会計基準等解説】 改正企業会計基準適用指針第10号「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」の解説(2007年12月24日号・№240)
実務解説
改正企業会計基準適用指針第10号
「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」の解説
企業会計基準委員会 研究員 小林正和
Ⅰ.はじめに
企業会計基準委員会では、平成19年11月15日に改正企業会計基準適用指針第10号「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(以下「改正適用指針」という。)1を公表している。これは、平成18年12月22日に、企業会計基準適用指針第10号「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」が改正されたところであるが、会社法の施行日から1年間適用除外とされていた合併等対価の柔軟化に関する規定が平成19年5月に施行されたことに伴い、いわゆる三角合併などについて、これまで明らかにされていなかった当該企業結合が取得に該当しない場合の会計処理について検討する必要が生じているものと考えられることなどから、所要の改正を行ったものである。
本稿では、改正適用指針の概要を解説するが、文中の意見にわたる部分は筆者の私見であることをあらかじめお断りしておく。また、特段記載のない限り、本稿における項番号は、改正適用指針の項番号を指す。
Ⅱ.主な改正点
1 子会社が親会社株式を交付した場合(いわゆる三角合併などの場合)の会計処理(共通支配下の取引に該当する場合)(図1参照)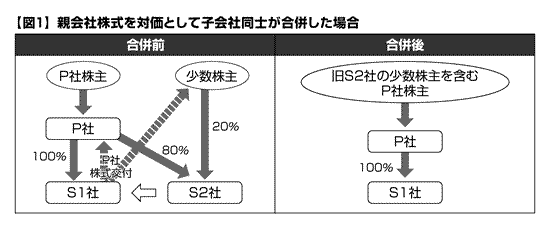
共通支配下の取引の場合2(ここでは、同一の株主に支配されている子会社同士を想定)において、子会社が親会社株式を対価として他の子会社と合併する場合の会計処理について、以下のとおり追加的に定められた(第243項から第245項参照)。なお、合併対価が、親会社株式のみではなく、親会社株式及び吸収合併存続会社の株式の場合についても、同様に、第251項から第253項に示されている。
(1)子会社(吸収合併存続会社)の個別財務諸表上の処理(第243項(1)参照) 吸収合併存続会社である子会社3は、吸収合併消滅会社である他の子会社から受け入れる資産及び負債を合併期日の前日に付された適正な帳簿価額により計上する。また、吸収合併消滅会社の株主資本の額と交付した親会社株式の適正な帳簿価額との差額をのれん(又は負ののれん)として計上する。
(2)親会社の個別財務諸表上の処理(第244項ただし書き参照) 親会社は、保有していた吸収合併消滅会社(子会社)の株式の適正な帳簿価額を、これと引き換えに取得した株式(自己株式)の取得原価として算定する。これは「自己株式及び準備金の額の減少等に関する会計基準の適用指針」第7項による。
(3)親会社の連結財務諸表上の処理(第245項なお書き参照) 企業集団からみると、親会社が合併の対価として自己株式を処分する取引と同様に考えることができるため、親会社の連結財務諸表上、少数株主に交付した自己株式の時価と適正な帳簿価額との差額は、資本取引として自己株式処分差額に振り替える。このため、上記(1)における連結子会社ののれんに係る会計処理を取り消した後、あらためて少数株主に交付した自己株式の時価と減少する少数株主持分との差額は、追加取得に係るのれんとして計上することとなる。
2 親会社が子会社を株式交換完全子会社とする場合等の会計処理(中間子会社がある場合)
(1)親会社が子会社を株式交換完全子会社とする場合(第236-4項及び図2参照)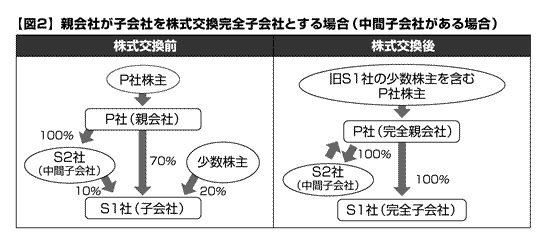
親会社(株式交換完全親会社)が、中間子会社から株式交換完全子会社株式を追加取得するときの会計処理については、株式交換完全子会社の適正な帳簿価額による株主資本の額に株式交換日の前日の持分比率を乗じて中間子会社持分相当額を取得原価として算定するとともに、その額を払込資本(資本金又は資本剰余金)として処理することが明記された。これは吸収合併の場合(第206項参照)と同様である。
中間子会社における会計処理については、保有していた株式交換完全子会社株式の適正な帳簿価額を、これと引き換えに取得した株式交換完全親会社の取得原価として算定する。
(2)親会社と子会社が株式移転設立完全親会社を設立する場合(第239項(1)なお書き参照) (1)の場合と同様に、株式移転設立完全親会社が、中間子会社から株式移転完全子会社株式(旧子会社株式)を追加取得するときの会計処理については、当該旧子会社株式の適正な帳簿価額による株主資本の額に当該旧子会社株式の株式移転日の前日の持分比率を乗じて中間子会社持分相当額を取得原価として算定するとともに、その額を払込資本(資本金又は資本剰余金)として処理することが明記された。
(3)子会社がその子会社(孫会社)を株式交換完全子会社とする場合(第236-5項参照) 子会社が、株式交換完全子会社株式(孫会社株式)を追加取得するときの会計処理については、最上位の親会社と子会社の株主との取引ではないため、前述の中間子会社に対価を支払う場合における中間子会社持分相当額に準じて算定することが明記された。すなわち、当該孫会社の株主資本の額に株式交換日の前日の持分比率を乗じた持分相当額を取得原価として算定するとともに、その額を払込資本(資本金又は資本剰余金)として処理する。
3 その他 (1)取得に直接要した支出額として自社の株式又は新株予約権を交付した場合(第48項また書き参照)
「ストック・オプション等に関する会計基準」第14項及び第15項において、財貨又はサービスの対価として自社株式オプションを付与する取引の会計処理が定められていることから、企業結合に直接要した支出額として自社の株式又は新株予約権を交付した場合についても、当該定めに準じて測定することが明記された。
(2)吸収合併存続会社が新株予約権を交付する場合等(第50項及び第361項参照) 取得と判定された吸収合併において、①吸収合併消滅会社の株主に対して新株予約権を交付した場合の会計処理については、原則として当該新株予約権の交換条件を決定した時の時価に基づき、取得の対価とされ、②吸収合併消滅会社の新株予約権者に対して新株予約権又は現金を交付した場合の会計処理については、原則として合併期日の時価に基づき4、取得に直接要した支出額に準じて取得原価に含めることとなる。
例えば、吸収合併消滅会社の従業員等に報酬として新株予約権(ストック・オプション)を付与していたため、これと引き換えに吸収合併存続会社の新株予約権を付与した場合、合併期日の時価に基づき取得原価に含め、貸借対照表の純資産の部に新株予約権として計上されるものと考えられる。したがって、合併期日から権利確定日までの期間に対応する部分は、未だ吸収合併消滅会社の貸借対照表上、新株予約権とされてはおらず、これと引き換えに吸収合併存続会社の新株予約権を付与していないため、その部分は当該期間の労働や業務執行等のサービスの対価として、期間の経過に応じて費用及び新株予約権として計上されることとなるものと考えられる。
なお、取得と判定された株式交換及び株式移転の場合についても、同様になる(第110-2項、第121-2項(2)及び第404-2項参照)。
(3)共通支配下の取引において自己株式を処分する場合(第203項(1)なお書き参照) 自己株式の処分の対価を、適正な帳簿価額を基礎として会計処理する場合において、①払込資本とする処理を適用するときは、自己株式の帳簿価額を控除した額を払込資本として処理すること、②吸収合併消滅会社の株主資本をそのまま引き継ぐ処理又は分割型の会社分割において株主資本の内訳を適切に配分した額をもって計上する処理を適用するときは、自己株式の帳簿価額をその他資本剰余金から控除して会計処理することが明記された。
(4)子会社が他の子会社に分割型の会社分割により事業を移転する場合(第203-2項(2)②及び第257項参照) 親会社(株主)の会計処理については、実質的に、保有していた吸収分割会社株式と引き換えに、吸収分割承継会社の株式を受け取ったものとみなして、被結合企業の株主に係る会計処理(第294項から第296項参照)に準じて処理することと整理された。
(5)親会社が子会社を吸収合併する場合(中間子会社がある場合)(第206項(3)なお書き参照) 中間子会社における会計処理は、保有していた子会社(吸収合併消滅会社)の株式の適正な帳簿価額を、これと引き換えに取得した親会社株式の取得原価として算定することが明記された。
(6)親会社と子会社が株式移転設立完全親会社を設立する場合(第239-4項及び設例28参照) 株式移転完全子会社(旧親会社)の会計処理については、保有していた株式移転完全子会社(旧子会社)の株式移転直前の適正な帳簿価額を、これと引き換えに取得した株式移転設立完全親会社の株式の取得原価として計上することが本文中に明記された。
(7)共通支配下の取引における分割型の会社分割5において、吸収分割承継会社が吸収分割会社で計上されていた株主資本の内訳を適切に配分した額をもって計上する場合(第409項(3)参照) この場合には、吸収分割会社は、受け取った吸収分割承継会社の株式の取得原価に、これに係る繰延税金資産又は繰延税金負債を加減した額により、株主資本を変動させることが明記された。例えば、適正な帳簿価額50(税務上の簿価70)の事業資産を移転した場合、吸収分割会社は、当該事業資産及びこれに係る繰延税金資産8((70-50)×実効税率40%)を減少させ、吸収分割承継会社に引き継ぐこととなるため、吸収分割承継会社の株主資本は58(=50+8)増加するものと考えられる。これは、吸収分割承継会社の株主資本の増加額58と吸収分割会社が変動させた株主資本の額とは一致する必要がある(第234項(2)ただし書き参照)ためである。
(8)共通支配下において現金のみを対価として子会社株式だけを受け取る場合(第448項参照) 共通支配下において、現金等の財産を対価として子会社株式を受け取る場合のうち、現金のみを対価として子会社株式だけを受け取る場合には、これまでの実務上の取扱いに照らして、個別財務諸表上、金融商品会計基準に従って会計処理されるため、のれん(又は負ののれん)が生じないことが明記された。なお、連結財務諸表上は、投資と資本の相殺消去により、のれん(又は負ののれん)を計上することになる。
4 適用時期等 今回の改正はこれまで明らかにされていなかった取扱いを明確にすることが主眼であり、実務において一定の準備期間が必要と考えられたことなどから、平成20年4月1日以後の組織再編について適用することとした。ただし、改正日(平成19年11月15日)以後終了する事業年度内のいずれの組織再編からも早期適用することができることとした(第331-2項参照)。
(こばやし・まさかず)
脚注
1 改正適用指針については、企業会計基準委員会(ASBJ)のホームページ(http://www.asb.or.jp/)を参照のこと。
2 取得の場合の会計処理については、第82項を参照のこと。
3 まず初めに、子会社が親会社株式を取得することになるが、ここでは当該親会社株式が取得されていることが前提とされている。
4 測定については、取得した識別可能資産及び負債の時価と同様に考える立場を明らかにしたものと考えられる。
5 このような場合として、親会社が子会社に(第234項(2)ただし書き)、子会社が他の子会社に(第256項)、あるいは単独にて新設子会社に(第264項)、それぞれ分割型の会社分割をした場合が挙げられている。
改正企業会計基準適用指針第10号
「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」の解説
企業会計基準委員会 研究員 小林正和
Ⅰ.はじめに
企業会計基準委員会では、平成19年11月15日に改正企業会計基準適用指針第10号「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(以下「改正適用指針」という。)1を公表している。これは、平成18年12月22日に、企業会計基準適用指針第10号「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」が改正されたところであるが、会社法の施行日から1年間適用除外とされていた合併等対価の柔軟化に関する規定が平成19年5月に施行されたことに伴い、いわゆる三角合併などについて、これまで明らかにされていなかった当該企業結合が取得に該当しない場合の会計処理について検討する必要が生じているものと考えられることなどから、所要の改正を行ったものである。
本稿では、改正適用指針の概要を解説するが、文中の意見にわたる部分は筆者の私見であることをあらかじめお断りしておく。また、特段記載のない限り、本稿における項番号は、改正適用指針の項番号を指す。
Ⅱ.主な改正点
1 子会社が親会社株式を交付した場合(いわゆる三角合併などの場合)の会計処理(共通支配下の取引に該当する場合)(図1参照)
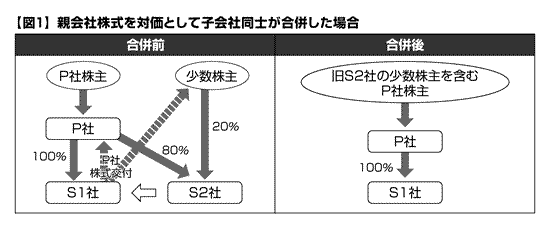
共通支配下の取引の場合2(ここでは、同一の株主に支配されている子会社同士を想定)において、子会社が親会社株式を対価として他の子会社と合併する場合の会計処理について、以下のとおり追加的に定められた(第243項から第245項参照)。なお、合併対価が、親会社株式のみではなく、親会社株式及び吸収合併存続会社の株式の場合についても、同様に、第251項から第253項に示されている。
(1)子会社(吸収合併存続会社)の個別財務諸表上の処理(第243項(1)参照) 吸収合併存続会社である子会社3は、吸収合併消滅会社である他の子会社から受け入れる資産及び負債を合併期日の前日に付された適正な帳簿価額により計上する。また、吸収合併消滅会社の株主資本の額と交付した親会社株式の適正な帳簿価額との差額をのれん(又は負ののれん)として計上する。
(2)親会社の個別財務諸表上の処理(第244項ただし書き参照) 親会社は、保有していた吸収合併消滅会社(子会社)の株式の適正な帳簿価額を、これと引き換えに取得した株式(自己株式)の取得原価として算定する。これは「自己株式及び準備金の額の減少等に関する会計基準の適用指針」第7項による。
(3)親会社の連結財務諸表上の処理(第245項なお書き参照) 企業集団からみると、親会社が合併の対価として自己株式を処分する取引と同様に考えることができるため、親会社の連結財務諸表上、少数株主に交付した自己株式の時価と適正な帳簿価額との差額は、資本取引として自己株式処分差額に振り替える。このため、上記(1)における連結子会社ののれんに係る会計処理を取り消した後、あらためて少数株主に交付した自己株式の時価と減少する少数株主持分との差額は、追加取得に係るのれんとして計上することとなる。
2 親会社が子会社を株式交換完全子会社とする場合等の会計処理(中間子会社がある場合)
(1)親会社が子会社を株式交換完全子会社とする場合(第236-4項及び図2参照)
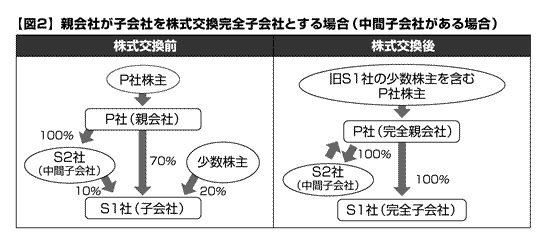
親会社(株式交換完全親会社)が、中間子会社から株式交換完全子会社株式を追加取得するときの会計処理については、株式交換完全子会社の適正な帳簿価額による株主資本の額に株式交換日の前日の持分比率を乗じて中間子会社持分相当額を取得原価として算定するとともに、その額を払込資本(資本金又は資本剰余金)として処理することが明記された。これは吸収合併の場合(第206項参照)と同様である。
中間子会社における会計処理については、保有していた株式交換完全子会社株式の適正な帳簿価額を、これと引き換えに取得した株式交換完全親会社の取得原価として算定する。
(2)親会社と子会社が株式移転設立完全親会社を設立する場合(第239項(1)なお書き参照) (1)の場合と同様に、株式移転設立完全親会社が、中間子会社から株式移転完全子会社株式(旧子会社株式)を追加取得するときの会計処理については、当該旧子会社株式の適正な帳簿価額による株主資本の額に当該旧子会社株式の株式移転日の前日の持分比率を乗じて中間子会社持分相当額を取得原価として算定するとともに、その額を払込資本(資本金又は資本剰余金)として処理することが明記された。
(3)子会社がその子会社(孫会社)を株式交換完全子会社とする場合(第236-5項参照) 子会社が、株式交換完全子会社株式(孫会社株式)を追加取得するときの会計処理については、最上位の親会社と子会社の株主との取引ではないため、前述の中間子会社に対価を支払う場合における中間子会社持分相当額に準じて算定することが明記された。すなわち、当該孫会社の株主資本の額に株式交換日の前日の持分比率を乗じた持分相当額を取得原価として算定するとともに、その額を払込資本(資本金又は資本剰余金)として処理する。
3 その他 (1)取得に直接要した支出額として自社の株式又は新株予約権を交付した場合(第48項また書き参照)
「ストック・オプション等に関する会計基準」第14項及び第15項において、財貨又はサービスの対価として自社株式オプションを付与する取引の会計処理が定められていることから、企業結合に直接要した支出額として自社の株式又は新株予約権を交付した場合についても、当該定めに準じて測定することが明記された。
(2)吸収合併存続会社が新株予約権を交付する場合等(第50項及び第361項参照) 取得と判定された吸収合併において、①吸収合併消滅会社の株主に対して新株予約権を交付した場合の会計処理については、原則として当該新株予約権の交換条件を決定した時の時価に基づき、取得の対価とされ、②吸収合併消滅会社の新株予約権者に対して新株予約権又は現金を交付した場合の会計処理については、原則として合併期日の時価に基づき4、取得に直接要した支出額に準じて取得原価に含めることとなる。
例えば、吸収合併消滅会社の従業員等に報酬として新株予約権(ストック・オプション)を付与していたため、これと引き換えに吸収合併存続会社の新株予約権を付与した場合、合併期日の時価に基づき取得原価に含め、貸借対照表の純資産の部に新株予約権として計上されるものと考えられる。したがって、合併期日から権利確定日までの期間に対応する部分は、未だ吸収合併消滅会社の貸借対照表上、新株予約権とされてはおらず、これと引き換えに吸収合併存続会社の新株予約権を付与していないため、その部分は当該期間の労働や業務執行等のサービスの対価として、期間の経過に応じて費用及び新株予約権として計上されることとなるものと考えられる。
なお、取得と判定された株式交換及び株式移転の場合についても、同様になる(第110-2項、第121-2項(2)及び第404-2項参照)。
(3)共通支配下の取引において自己株式を処分する場合(第203項(1)なお書き参照) 自己株式の処分の対価を、適正な帳簿価額を基礎として会計処理する場合において、①払込資本とする処理を適用するときは、自己株式の帳簿価額を控除した額を払込資本として処理すること、②吸収合併消滅会社の株主資本をそのまま引き継ぐ処理又は分割型の会社分割において株主資本の内訳を適切に配分した額をもって計上する処理を適用するときは、自己株式の帳簿価額をその他資本剰余金から控除して会計処理することが明記された。
(4)子会社が他の子会社に分割型の会社分割により事業を移転する場合(第203-2項(2)②及び第257項参照) 親会社(株主)の会計処理については、実質的に、保有していた吸収分割会社株式と引き換えに、吸収分割承継会社の株式を受け取ったものとみなして、被結合企業の株主に係る会計処理(第294項から第296項参照)に準じて処理することと整理された。
(5)親会社が子会社を吸収合併する場合(中間子会社がある場合)(第206項(3)なお書き参照) 中間子会社における会計処理は、保有していた子会社(吸収合併消滅会社)の株式の適正な帳簿価額を、これと引き換えに取得した親会社株式の取得原価として算定することが明記された。
(6)親会社と子会社が株式移転設立完全親会社を設立する場合(第239-4項及び設例28参照) 株式移転完全子会社(旧親会社)の会計処理については、保有していた株式移転完全子会社(旧子会社)の株式移転直前の適正な帳簿価額を、これと引き換えに取得した株式移転設立完全親会社の株式の取得原価として計上することが本文中に明記された。
(7)共通支配下の取引における分割型の会社分割5において、吸収分割承継会社が吸収分割会社で計上されていた株主資本の内訳を適切に配分した額をもって計上する場合(第409項(3)参照) この場合には、吸収分割会社は、受け取った吸収分割承継会社の株式の取得原価に、これに係る繰延税金資産又は繰延税金負債を加減した額により、株主資本を変動させることが明記された。例えば、適正な帳簿価額50(税務上の簿価70)の事業資産を移転した場合、吸収分割会社は、当該事業資産及びこれに係る繰延税金資産8((70-50)×実効税率40%)を減少させ、吸収分割承継会社に引き継ぐこととなるため、吸収分割承継会社の株主資本は58(=50+8)増加するものと考えられる。これは、吸収分割承継会社の株主資本の増加額58と吸収分割会社が変動させた株主資本の額とは一致する必要がある(第234項(2)ただし書き参照)ためである。
(8)共通支配下において現金のみを対価として子会社株式だけを受け取る場合(第448項参照) 共通支配下において、現金等の財産を対価として子会社株式を受け取る場合のうち、現金のみを対価として子会社株式だけを受け取る場合には、これまでの実務上の取扱いに照らして、個別財務諸表上、金融商品会計基準に従って会計処理されるため、のれん(又は負ののれん)が生じないことが明記された。なお、連結財務諸表上は、投資と資本の相殺消去により、のれん(又は負ののれん)を計上することになる。
4 適用時期等 今回の改正はこれまで明らかにされていなかった取扱いを明確にすることが主眼であり、実務において一定の準備期間が必要と考えられたことなどから、平成20年4月1日以後の組織再編について適用することとした。ただし、改正日(平成19年11月15日)以後終了する事業年度内のいずれの組織再編からも早期適用することができることとした(第331-2項参照)。
(こばやし・まさかず)
脚注
1 改正適用指針については、企業会計基準委員会(ASBJ)のホームページ(http://www.asb.or.jp/)を参照のこと。
2 取得の場合の会計処理については、第82項を参照のこと。
3 まず初めに、子会社が親会社株式を取得することになるが、ここでは当該親会社株式が取得されていることが前提とされている。
4 測定については、取得した識別可能資産及び負債の時価と同様に考える立場を明らかにしたものと考えられる。
5 このような場合として、親会社が子会社に(第234項(2)ただし書き)、子会社が他の子会社に(第256項)、あるいは単独にて新設子会社に(第264項)、それぞれ分割型の会社分割をした場合が挙げられている。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -

Copyright (C) 2019
SHINNIPPON-HOKI PUBLISHING CO.,LTD.




















