コラム2008年04月28日 【編集部レポート】 外為法27条による審査と投資中止勧告に至る経緯(2008年4月28日号・№256)
外為法27条による審査と投資中止勧告に至る経緯
政府による初の中止勧告は何を根拠として行われたか
text 編集部
経済協力開発機構(OECD)がわが国の潜在成長率の引上げに関し、『対日経済審査報告書2008年版』において「低迷が続いているサービス部門の生産性の伸びを反転することが不可欠である」としたうえで、「競争強化のためには対日直接投資を阻む障壁ならびに海外投資家の投資意欲を削ぐ製品市場の規制を撤廃することが重要である」と述べてから約1週間を経過した4月16日、電源開発への追加投資方針を外国為替及び外国貿易法(外為法)に基づき届け出ていたザ・チルドレンズ・インベストメント・ファンド(TCI)に対して、財務大臣および経済産業大臣から「本件届出に係る対内直接投資を中止すること」を内容とする勧告がなされた。
外為法における対内直接投資等の事前届出制度 財務大臣・経済産業大臣による勧告は、「外為法27条(対内直接投資等の届出及び変更勧告等)」に基づき、同条1項に定める対内直接投資等の事前届出制度の対象となる投資が行われるに際し、
① 「国の安全を損ない」、
② 「公の秩序の維持を妨げ」、もしくは
③ 「公衆の安全の保護に支障を来す」
ことになること、または、
④ 「我が国経済の円滑な運営に著しい悪影響を及ぼす」
ことになることといった事態を生ずるおそれがある対内直接投資等に該当しないかどうかを見極める審査の結果を受けてなされたものである(同条3項・5項)(その手続等について、図表1参照)。
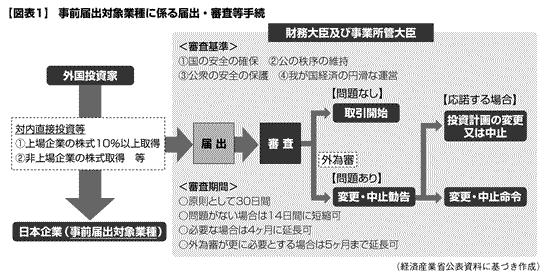
審査および勧告は、「財務大臣及び事業所管大臣は、第3項の規定により対内直接投資等を行つてはならない期間を延長した場合において、同項の規定による審査をした結果、第1項の規定による届出に係る対内直接投資等が国の安全等に係る対内直接投資等に該当すると認めるときは、関税・外国為替等審議会の意見を聴いて、当該対内直接投資等の届出をしたものに対し、……内容の変更又は中止を勧告することができる」(同条5項)とする手順にのっとり、今回のケースでは、財務大臣および経済産業大臣が「関税・外国為替等審議会外国為替等分科会外資特別部会」(部会長:吉野直行慶應義塾大学経済学部教授。メンバーについて、図表2参照)の意見を踏まえて行われている。
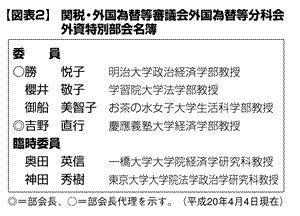
関税・外国為替等審議会(会長:中山信弘弁護士)は、当時の中央省庁等改革に伴って、従来の関税率審議会と外国為替等審議会の機能を引き継ぐものとして平成13年1月6日に発足し、同月23日に第1回総会を開催した財務大臣等の諮問機関である。発足当初から関税分科会および外国為替等分科会を擁し、現在の構成メンバーは産業界・金融界等の各関係者、証券関係者、消費者代表、大学教授、弁護士、メディア関係者等からなるが、意見を提示した外国為替等分科会外資特別部会のメンバーは大学教授のみから構成されていることとなる。
外資特別部会の意見 外資特別部会は勧告の前日にあたる4月15日、TCIからのヒアリングも経たうえで5項目からなる次のような意見を述べた(編注・以下では要旨を収載)。
① 対内直接投資の積極的導入は極めて重要であり、わが国企業の健全なコーポレート・ガバナンスの発展を促す効果もあるところ、わが国への直接投資はここ3年間の約760件の事前届出案件も含めてすべて認められてきており、このような開放された市場は今後とも維持されなければならないこと
② 一方で投資活動の結果として公の秩序の維持が妨げられるようなことがあってはならず、こうした懸念には適切に対応する必要があるのであって、このような観点から、国民生活にとって必要不可欠なインフラである電気事業については、多くの国において「OECD資本移動自由化コード」に基づく対内直接投資規制の対象分野とし(編注・図表3の「1.国際ルールに整合的な措置」等を参照)、または国等が保有する事業とすることにより、電気の長期的・安定的供給の確保が図られていること
③ 電源開発は、総亘長2,400kmに及ぶ送電線や東日本・西日本の電力融通を行う周波数変換所等を保有し、長期的な設備投資を行うことでわが国の電力の安定供給を支え、また、国の原子力・核燃料サイクル政策にとり重要な大間原子力発電所の建設計画等を予定していること
④ TCIによる電源開発の株式追加取得が行われた場合、その主要株主としての行動によっては、これまでTCIから示された諸提案をもってしても送電線を始めとする基幹設備に係る計画・運用・維持、国の原子力・核燃料サイクル政策の実施に不測の影響が及ぶ可能性を否定できないこと
⑤ 以上から、本件投資によって公の秩序の維持が妨げられるおそれがあると認められ、よって、政府において適切な対応が取られることを求めること
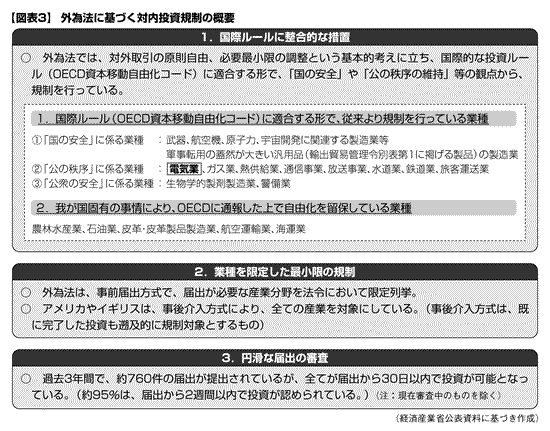
TCIはいかなる主張・対応をしていたか 今回の勧告の発端となる事前届出は今年1月15日、ザ・チルドレンズ・インベストメント・マスターファンド(TCIファンド。代表者:クリストファー・ホーン取締役)が行っており、届出日において電源開発の発行済株式の9.9%を保有していたところ、この届出に基づき追加取得する株数の上限を10.1%(既保有分と合わせて20%)と設定する届出がなされた。
続いてTCIは、1月16日の報道発表により、外資による電源開発への投資により国家安全保障に関する懸念が生じる旨の平成19年12月中の経済産業大臣発言を踏まえ、また、電源開発の事業のどの側面が懸念を惹起するのか明示するよう求めるTCIの要請に対して政府が基準や指針を示すことは国家安全保障の見地からできない旨の経済産業省の対応を明らかにしたうえで、「日本政府が抱いていると思われる懸念を払拭するため」とし、①取得株数の上限を20%に設定、②原子力発電所や送電線設備の運営に関し株主総会が行われる場合の、当該決議における追加取得株式に係る議決権の不行使を表明した。
さらに4月15日には、TCIが上記申出に違反しないことを法的に担保できるか確証が得られないとする政府の懸念への「新提案」として、③追加取得株式の信託銀行等第三者への信託、信託契約における議決権凍結、④TCIによる大間原子力発電所への影響排除のため、同発電所を政府が支配し電源開発が少数株主となる別会社に譲渡し、運営は契約に基づき電源開発が引き続き行うといった2つのスキームを提案。株式の追加取得が「原子力発電所や送電線設備に一切影響を与えるものではなく、したがって、『国の安全』や『公の秩序』を脅かさない」ことを強調したうえで、「日本国民の皆様と政府にわかっていただくためであれば、必要かつ適切なあらゆる措置を採らせていただく所存です」と最大限とも評価できる譲歩姿勢を示していた。
TCIファンドは、昨年6月27日に開催された電源開発の株主総会における第4号議案「剰余金の配当の件」について、3月9日付で「期末30円配当を100円とすべき」とする増配提案を行った株主。増配提案が当該総会決議で否決された後の昨年12月には、経営改善提案としての「J-Power(電源開発株式会社)による企業価値創造のためのビジネスプラン」や11月22日付の電源開発社長宛の書簡を公表し、一方、これに伴って電源開発側も、この提案等に対する会社としての考え方を公表するなどのやりとりが行われていた。
政府による勧告 財務大臣・経済産業大臣は4月16日、TCIファンドによる株式追加取得の中止を勧告した。勧告では、電源開発の沿革、わが国電力供給システムにおける位置付けを説明したうえで、電気事業がOECD・資本移動自由化コード3条に規定する「公の秩序の維持」の観点から届出業種として指定されていることを前提に、本件審査において、TCIファンドによる株式取得が、
(a)基幹設備の計画・運用・維持にいかなる影響を及ぼし、
(b)それらを通じて電気の安定供給や原子力・核燃料サイクルに関するわが国の政策にいかなる影響を与え、
(c)わが国の公の秩序の維持を妨げるおそれがあるか
という観点から検討されたことが掲げられている。
この場合に焦点となる「公の秩序の維持を妨げるおそれの認定」については、図表4のように示されている。これらの結果として、①TCIファンドによる投資方針、これまでの投資行動から判断すると、本件届出に係る対内直接投資は電源開発の経営に一定の影響を及ぼす可能性がある、②株式の追加取得、これに伴う株主権の行使を通じて電源開発の経営や基幹設備に係る計画・運用・維持に影響を及ぼし、それらを通じて電気の安定供給や原子力・核燃料サイクルに関するわが国の政策に影響を与えるおそれは十分に払拭できない、③TCIファンドから示された提案によっては、電気の安定供給や原子力・核燃料サイクルに関するわが国の政策に影響を与えるおそれが払拭できないことが認定され、中止勧告に至ったものである。
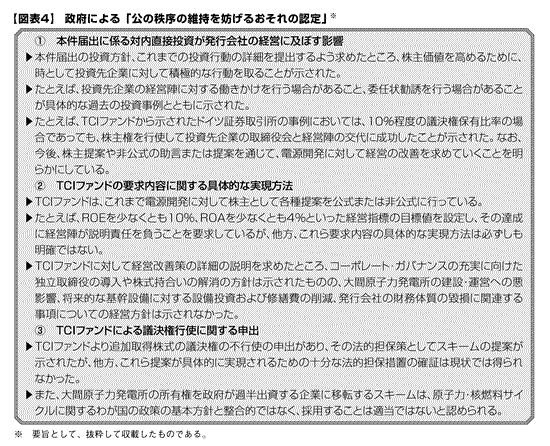
中止勧告に伴っては、「日本政府の対日直接投資促進の姿勢は不変」と題する財務大臣・経済産業大臣談話が公表されており、このなかで、①電気事業について、OECD諸国においても、OECDへの通知により外資規制を行っている国が11カ国、国等が保有している国が18カ国、うち重複している国が6カ国、特段の対応のない国が7カ国となっていることを説明するとともに、②審査が累次にわたるTCIからのヒアリングを含めて行われ、その結果、公の秩序の維持を妨げるおそれが払拭できないと認められることから、関税・外国為替等審議会の意見を聴いたうえで中止勧告することとしたもので、これが外為法に基づき実施された初めての勧告であることに敷衍、③対内直接投資の促進はわが国の政策の基本方針であり、外為法のもとでは本件以外の届出はすべて法令で定められた30日以内の審査期間で投資が認められており、うち約95%は2週間以内で認められていることを強調し、④「なお」としながら、電源開発に対し、株主との真摯な対話のなかで株主への説明責任を果たしていくことの必要性、事業の公益性を勘案した株主への還元のあり方について株主の理解と納得が得られるような努力を要請した。
勧告後のTCIの動き 外為法27条7項によると、勧告を受けた者は勧告日から起算して10日以内に「財務大臣及び事業所管大臣に対し、当該勧告を応諾するかしないかを通知しなければならない」とされており、本件の場合の諾否期限は4月25日。今号刊行時にはTCI側の対応も明らかにされているはずであるが、仮にTCI側がこの通知をしなかった場合、または当該勧告を応諾しない旨の通知をした場合には、財務大臣および経済産業大臣は、TCIファンドに対し、当該対内直接投資の中止を命令することができる(外為法27条10項)(図表1参照)。
TCIは中止勧告が出された翌4月17日、東京都内で記者会見を開き、同日、電源開発に対して5項目の株主提案を行ったことを発表。その内容は、①株式持合いを含む株式投資が2007年3月末現在で680億円にも上るところ、定款上、これを50億円に制限、②現状、社外取締役が皆無であるところ、定款上、最低3名の社外取締役の枠を設定、③期末配当を1株につき90円(中間配当と合わせて年間120円)とする、④これよりは低額の配当を適切と考える株主のため、この額を50円(同様に年間80円)とする、⑤自己株式取得枠を総額700億円設定することを求めるものとなっている。
TCIは、これらの提案が会社提案として採用されることを「心から願っています」とし、採用されない場合、来るべき定時株主総会における社長の再任に反対する意向を表明している。
政府による初の中止勧告は何を根拠として行われたか
text 編集部
経済協力開発機構(OECD)がわが国の潜在成長率の引上げに関し、『対日経済審査報告書2008年版』において「低迷が続いているサービス部門の生産性の伸びを反転することが不可欠である」としたうえで、「競争強化のためには対日直接投資を阻む障壁ならびに海外投資家の投資意欲を削ぐ製品市場の規制を撤廃することが重要である」と述べてから約1週間を経過した4月16日、電源開発への追加投資方針を外国為替及び外国貿易法(外為法)に基づき届け出ていたザ・チルドレンズ・インベストメント・ファンド(TCI)に対して、財務大臣および経済産業大臣から「本件届出に係る対内直接投資を中止すること」を内容とする勧告がなされた。
外為法における対内直接投資等の事前届出制度 財務大臣・経済産業大臣による勧告は、「外為法27条(対内直接投資等の届出及び変更勧告等)」に基づき、同条1項に定める対内直接投資等の事前届出制度の対象となる投資が行われるに際し、
① 「国の安全を損ない」、
② 「公の秩序の維持を妨げ」、もしくは
③ 「公衆の安全の保護に支障を来す」
ことになること、または、
④ 「我が国経済の円滑な運営に著しい悪影響を及ぼす」
ことになることといった事態を生ずるおそれがある対内直接投資等に該当しないかどうかを見極める審査の結果を受けてなされたものである(同条3項・5項)(その手続等について、図表1参照)。
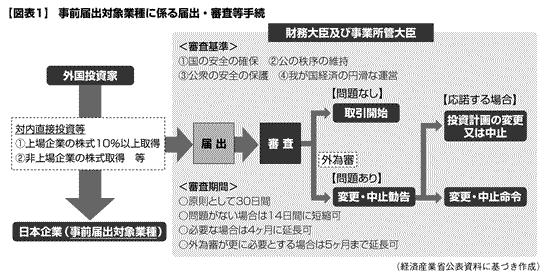
審査および勧告は、「財務大臣及び事業所管大臣は、第3項の規定により対内直接投資等を行つてはならない期間を延長した場合において、同項の規定による審査をした結果、第1項の規定による届出に係る対内直接投資等が国の安全等に係る対内直接投資等に該当すると認めるときは、関税・外国為替等審議会の意見を聴いて、当該対内直接投資等の届出をしたものに対し、……内容の変更又は中止を勧告することができる」(同条5項)とする手順にのっとり、今回のケースでは、財務大臣および経済産業大臣が「関税・外国為替等審議会外国為替等分科会外資特別部会」(部会長:吉野直行慶應義塾大学経済学部教授。メンバーについて、図表2参照)の意見を踏まえて行われている。
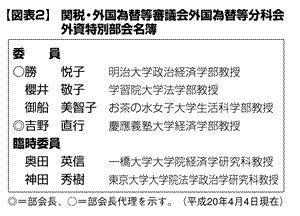
関税・外国為替等審議会(会長:中山信弘弁護士)は、当時の中央省庁等改革に伴って、従来の関税率審議会と外国為替等審議会の機能を引き継ぐものとして平成13年1月6日に発足し、同月23日に第1回総会を開催した財務大臣等の諮問機関である。発足当初から関税分科会および外国為替等分科会を擁し、現在の構成メンバーは産業界・金融界等の各関係者、証券関係者、消費者代表、大学教授、弁護士、メディア関係者等からなるが、意見を提示した外国為替等分科会外資特別部会のメンバーは大学教授のみから構成されていることとなる。
外資特別部会の意見 外資特別部会は勧告の前日にあたる4月15日、TCIからのヒアリングも経たうえで5項目からなる次のような意見を述べた(編注・以下では要旨を収載)。
① 対内直接投資の積極的導入は極めて重要であり、わが国企業の健全なコーポレート・ガバナンスの発展を促す効果もあるところ、わが国への直接投資はここ3年間の約760件の事前届出案件も含めてすべて認められてきており、このような開放された市場は今後とも維持されなければならないこと
② 一方で投資活動の結果として公の秩序の維持が妨げられるようなことがあってはならず、こうした懸念には適切に対応する必要があるのであって、このような観点から、国民生活にとって必要不可欠なインフラである電気事業については、多くの国において「OECD資本移動自由化コード」に基づく対内直接投資規制の対象分野とし(編注・図表3の「1.国際ルールに整合的な措置」等を参照)、または国等が保有する事業とすることにより、電気の長期的・安定的供給の確保が図られていること
③ 電源開発は、総亘長2,400kmに及ぶ送電線や東日本・西日本の電力融通を行う周波数変換所等を保有し、長期的な設備投資を行うことでわが国の電力の安定供給を支え、また、国の原子力・核燃料サイクル政策にとり重要な大間原子力発電所の建設計画等を予定していること
④ TCIによる電源開発の株式追加取得が行われた場合、その主要株主としての行動によっては、これまでTCIから示された諸提案をもってしても送電線を始めとする基幹設備に係る計画・運用・維持、国の原子力・核燃料サイクル政策の実施に不測の影響が及ぶ可能性を否定できないこと
⑤ 以上から、本件投資によって公の秩序の維持が妨げられるおそれがあると認められ、よって、政府において適切な対応が取られることを求めること
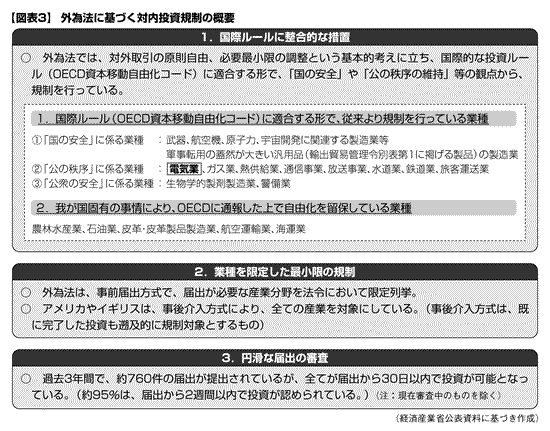
TCIはいかなる主張・対応をしていたか 今回の勧告の発端となる事前届出は今年1月15日、ザ・チルドレンズ・インベストメント・マスターファンド(TCIファンド。代表者:クリストファー・ホーン取締役)が行っており、届出日において電源開発の発行済株式の9.9%を保有していたところ、この届出に基づき追加取得する株数の上限を10.1%(既保有分と合わせて20%)と設定する届出がなされた。
続いてTCIは、1月16日の報道発表により、外資による電源開発への投資により国家安全保障に関する懸念が生じる旨の平成19年12月中の経済産業大臣発言を踏まえ、また、電源開発の事業のどの側面が懸念を惹起するのか明示するよう求めるTCIの要請に対して政府が基準や指針を示すことは国家安全保障の見地からできない旨の経済産業省の対応を明らかにしたうえで、「日本政府が抱いていると思われる懸念を払拭するため」とし、①取得株数の上限を20%に設定、②原子力発電所や送電線設備の運営に関し株主総会が行われる場合の、当該決議における追加取得株式に係る議決権の不行使を表明した。
さらに4月15日には、TCIが上記申出に違反しないことを法的に担保できるか確証が得られないとする政府の懸念への「新提案」として、③追加取得株式の信託銀行等第三者への信託、信託契約における議決権凍結、④TCIによる大間原子力発電所への影響排除のため、同発電所を政府が支配し電源開発が少数株主となる別会社に譲渡し、運営は契約に基づき電源開発が引き続き行うといった2つのスキームを提案。株式の追加取得が「原子力発電所や送電線設備に一切影響を与えるものではなく、したがって、『国の安全』や『公の秩序』を脅かさない」ことを強調したうえで、「日本国民の皆様と政府にわかっていただくためであれば、必要かつ適切なあらゆる措置を採らせていただく所存です」と最大限とも評価できる譲歩姿勢を示していた。
TCIファンドは、昨年6月27日に開催された電源開発の株主総会における第4号議案「剰余金の配当の件」について、3月9日付で「期末30円配当を100円とすべき」とする増配提案を行った株主。増配提案が当該総会決議で否決された後の昨年12月には、経営改善提案としての「J-Power(電源開発株式会社)による企業価値創造のためのビジネスプラン」や11月22日付の電源開発社長宛の書簡を公表し、一方、これに伴って電源開発側も、この提案等に対する会社としての考え方を公表するなどのやりとりが行われていた。
政府による勧告 財務大臣・経済産業大臣は4月16日、TCIファンドによる株式追加取得の中止を勧告した。勧告では、電源開発の沿革、わが国電力供給システムにおける位置付けを説明したうえで、電気事業がOECD・資本移動自由化コード3条に規定する「公の秩序の維持」の観点から届出業種として指定されていることを前提に、本件審査において、TCIファンドによる株式取得が、
(a)基幹設備の計画・運用・維持にいかなる影響を及ぼし、
(b)それらを通じて電気の安定供給や原子力・核燃料サイクルに関するわが国の政策にいかなる影響を与え、
(c)わが国の公の秩序の維持を妨げるおそれがあるか
という観点から検討されたことが掲げられている。
この場合に焦点となる「公の秩序の維持を妨げるおそれの認定」については、図表4のように示されている。これらの結果として、①TCIファンドによる投資方針、これまでの投資行動から判断すると、本件届出に係る対内直接投資は電源開発の経営に一定の影響を及ぼす可能性がある、②株式の追加取得、これに伴う株主権の行使を通じて電源開発の経営や基幹設備に係る計画・運用・維持に影響を及ぼし、それらを通じて電気の安定供給や原子力・核燃料サイクルに関するわが国の政策に影響を与えるおそれは十分に払拭できない、③TCIファンドから示された提案によっては、電気の安定供給や原子力・核燃料サイクルに関するわが国の政策に影響を与えるおそれが払拭できないことが認定され、中止勧告に至ったものである。
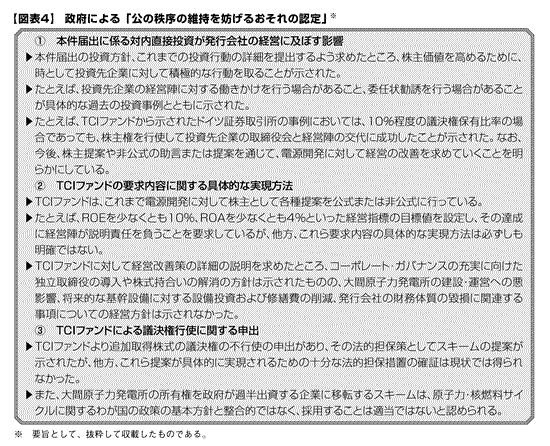
中止勧告に伴っては、「日本政府の対日直接投資促進の姿勢は不変」と題する財務大臣・経済産業大臣談話が公表されており、このなかで、①電気事業について、OECD諸国においても、OECDへの通知により外資規制を行っている国が11カ国、国等が保有している国が18カ国、うち重複している国が6カ国、特段の対応のない国が7カ国となっていることを説明するとともに、②審査が累次にわたるTCIからのヒアリングを含めて行われ、その結果、公の秩序の維持を妨げるおそれが払拭できないと認められることから、関税・外国為替等審議会の意見を聴いたうえで中止勧告することとしたもので、これが外為法に基づき実施された初めての勧告であることに敷衍、③対内直接投資の促進はわが国の政策の基本方針であり、外為法のもとでは本件以外の届出はすべて法令で定められた30日以内の審査期間で投資が認められており、うち約95%は2週間以内で認められていることを強調し、④「なお」としながら、電源開発に対し、株主との真摯な対話のなかで株主への説明責任を果たしていくことの必要性、事業の公益性を勘案した株主への還元のあり方について株主の理解と納得が得られるような努力を要請した。
勧告後のTCIの動き 外為法27条7項によると、勧告を受けた者は勧告日から起算して10日以内に「財務大臣及び事業所管大臣に対し、当該勧告を応諾するかしないかを通知しなければならない」とされており、本件の場合の諾否期限は4月25日。今号刊行時にはTCI側の対応も明らかにされているはずであるが、仮にTCI側がこの通知をしなかった場合、または当該勧告を応諾しない旨の通知をした場合には、財務大臣および経済産業大臣は、TCIファンドに対し、当該対内直接投資の中止を命令することができる(外為法27条10項)(図表1参照)。
TCIは中止勧告が出された翌4月17日、東京都内で記者会見を開き、同日、電源開発に対して5項目の株主提案を行ったことを発表。その内容は、①株式持合いを含む株式投資が2007年3月末現在で680億円にも上るところ、定款上、これを50億円に制限、②現状、社外取締役が皆無であるところ、定款上、最低3名の社外取締役の枠を設定、③期末配当を1株につき90円(中間配当と合わせて年間120円)とする、④これよりは低額の配当を適切と考える株主のため、この額を50円(同様に年間80円)とする、⑤自己株式取得枠を総額700億円設定することを求めるものとなっている。
TCIは、これらの提案が会社提案として採用されることを「心から願っています」とし、採用されない場合、来るべき定時株主総会における社長の再任に反対する意向を表明している。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -

Copyright (C) 2019
SHINNIPPON-HOKI PUBLISHING CO.,LTD.





















