解説記事2008年06月02日 【会計基準等解説】 資産除去債務に関する会計基準等について(2008年6月2日号・№260)
実務解説
資産除去債務に関する会計基準等について
企業会計基準委員会 主任研究員 荻原正佳
Ⅰ.はじめに
企業会計基準委員会(ASBJ)は、企業会計基準第18号「資産除去債務に関する会計基準」(以下「会計基準」という。)及び企業会計基準適用指針第22号「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」(以下「適用指針」という。)を平成20年3月31日付で公表した。
本稿では、会計基準及び適用指針の概要を紹介するが、意見にわたる部分は私見であることを予めお断りしておく。
Ⅱ.資産除去債務の会計処理の基本的な考え方
資産除去債務の会計処理の基本的な考え方は、「有形固定資産の除去に伴う支出の不可避的な義務(資産除去債務)が存在する場合に、それを負債に計上し、その発生時における現在価値を当該有形固定資産の帳簿価額に加えて、減価償却を通じて各期に費用配分するとともに、その現在価値と割引前の将来支出金額との差額を時の経過による調整額として費用計上していく会計処理」と要約できる。
例えば、有形固定資産の取得時に資産除去債務が発生し、20年後に100の支出が見込まれているものとする。この場合、割引率を4%とすると支出見込額の現在価値は約46となる。これが資産除去債務の当初計上額となるとともに、有形固定資産の帳簿価額に加算されることになる。資産サイドでは、この当初に計上された金額46が減価償却を通じて期間配分される一方、負債サイドでは、支出見込額100との差額54(100-46)が「時の経過による資産除去債務の調整額」として各期に費用計上され、現在価値の増加に従って負債が増額されていくことになる(図参照)。
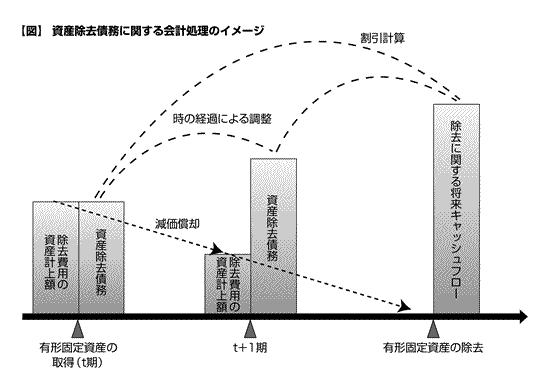
同様の会計処理を採用している国際的な会計基準(脚注1)とのコンバージェンスが、ASBJが資産除去債務をプロジェクト項目として取り上げた契機の一つとなっている。このような会計処理は、不可避的な義務は負債として認識する必要があるという考え方に基づくものといえる。
Ⅲ.適用範囲
会計基準の適用対象となるのは、「資産除去債務」の定義を満たす法律上の義務及びそれに準ずるものである。
「資産除去債務」とは、有形固定資産の取得、建設、開発又は通常の使用によって生じ、当該有形固定資産の除去に関して法令又は契約で要求される法律上の義務及びそれに準ずるものをいう。この場合の法律上の義務及びそれに準ずるものには、有形固定資産を除去する義務のほか、有形固定資産の除去そのものは義務でなくとも、有形固定資産を除去する際に当該有形固定資産に使用されている有害物質等を法律等の要求による特別の方法で除去するという義務も含まれる(基準第3項(1))。
会計基準では、資産除去債務は有形固定資産の取得、建設、開発又は通常の使用により生じるものとしている。通常の使用とは、有形固定資産を意図した目的のために正常に稼働させることをいう。有形固定資産を除去する義務が、不適切な操業等の異常な原因によって発生した場合には、資産除去債務として使用期間にわたって費用配分すべきものではなく、引当金の計上や、「固定資産の減損に係る会計基準」の適用対象とすべきものと考えられる(基準第26項)。
なお、本会計基準でいう有形固定資産には、財務諸表等規則において有形固定資産に区分される資産のほか、それに準ずる有形の資産も含む。したがって、建設仮勘定やリース資産のほか、財務諸表等規則において「投資その他の資産」に分類されている投資不動産などについても、資産除去債務が存在している場合には、会計基準の対象となる(基準第23項)。
有形固定資産の「除去」とは、有形固定資産を用役提供から除外することをいう(一時的に除外する場合を除く)。除去の具体的な態様には、売却、廃棄、リサイクルその他の方法による処分等が含まれるが、企業が自ら使用を継続する転用や用途変更は含まれない。また、有形固定資産が遊休状態になることは除去に該当しない(基準第3項(2))。
資産除去債務の典型な事例として、原子力発電施設の解体に伴う債務が挙げられることが多い。有形固定資産を除去する義務としては、そのほかに、例えば、定期借地権契約で賃借した土地の上に建設した建物等を除去する義務、鉱山等の原状回復義務、賃借建物の原状回復義務などが考えられる。また、有害物質等を特別の方法で除去する義務としては、アスベストやPCBの除去の義務などが該当しうるものと考えられる。
資産除去債務は、あくまで有形固定資産の除去に関連するものが対象であるため、資産の使用開始前から将来の支出が予想されるものであっても、有形固定資産の使用期間中に実施する環境修復や修繕は対象とはならない(基準第24項)。
本会計基準では、法律上の義務に準ずるものとは、債務の履行を免れることがほぼ不可能な義務を指し、法令又は契約で要求される法律上の義務とほぼ同等の不可避的な義務が該当するとしている。具体的には、法律上の解釈により当事者間での清算が要請される義務に加え、過去の判例や行政当局の通達等のうち、法律上の義務とほぼ同等の不可避的な支出が義務付けられるものが該当すると考えられる。したがって、有形固定資産の除去が企業の自発的な計画のみによって行われる場合は、法律上の義務に準ずるものには該当しない(基準第28項)。
Ⅳ.資産除去債務の会計処理
1.資産除去債務の負債計上 資産除去債務は、有形固定資産の取得、建設、開発又は通常の使用によって発生した時に負債として計上する(基準第4項)。
資産除去債務の発生時に、当該債務の金額を合理的に見積ることができない場合には、これを計上せず、当該債務額を合理的に見積ることができるようになった時点で負債として計上する。その場合の負債の計上の処理は、第10項及び第11項に準じる(基準第5項)。
資産除去債務を合理的に見積ることができない場合とは、決算日現在入手可能なすべての証拠を勘案し、最善の見積りを行ってもなお、合理的に金額を算定できない場合をいう。このような場合には、基準第16項(5)に定める開示が必要である(指針第2項)。
資産除去債務を負債に計上する会計処理としては、本会計基準で採用している資産負債の両建処理を行う方法のほか、有形固定資産の除去に係る用役の費消を当該有形固定資産の使用に応じて各期間に費用配分し、それに対応する金額を負債として認識する考え方(引当金処理)もある。引当金処理は、有形固定資産に対応する除去費用が当該有形固定資産の使用に応じて各期に適切な形で費用配分されるという点では、資産負債の両建処理と同様であり、また、資産負債の両建処理の場合に計上される借方項目の資産性を疑問視する観点からは、引当金処理を採用した上で資産除去債務の金額等を注記情報として開示するほうが適切ではないかとの見方もあった。
しかしながら、引当金処理では有形固定資産の除去に必要な金額が貸借対照表に計上されないことから、資産除去債務の負債計上が不十分であるという意見がある。また、資産負債の両建処理は、除去費用を有形固定資産の取得原価に含めることで、有形固定資産に対応する除去費用が減価償却を通じて当該有形固定資産の使用に応じて各期に費用配分されるため、損益計算の観点からは引当金処理を包摂するものといえる。さらに、資産負債の両建処理は、国際的な会計基準とのコンバージェンスにも資するものであるため、本会計基準では、資産負債の両建処理を求めることとした(会計基準第32項から第34項まで)。
2.資産除去債務の算定 資産除去債務はそれが発生したときに、有形固定資産の除去に関する割引前の将来キャッシュ・フローを見積り、割引後の金額(割引価値)で算定する(基準第6項)。
(1)将来支出の見積り 割引前の将来キャッシュ・フローは、合理的で説明可能な仮定及び予測に基づく自己の支出見積りによる。その見積金額は、生起する可能性の最も高い単一の金額又は生起しうる複数の将来キャッシュ・フローをそれぞれの確率で加重平均した金額とする。将来キャッシュ・フローには、有形固定資産の除去に係る作業のために直接要する支出のほか、処分に至るまでの支出(例えば、保管や管理のための支出)も含める(基準第6項(1))。
割引前の将来キャッシュ・フローの見積りは、次のような情報を基礎として行うこととしている(指針第3項)。
イ.対象となる有形固定資産の除去に必要な平均的な処理作業に対する価格の見積り
ロ.対象となる有形固定資産を取得した際に、取引価額から控除された当該資産に係る除去費用の算定の基礎となった数値
ハ.過去において類似の資産について発生した除去費用の実績
ニ.当該有形固定資産への投資の意思決定を行う際に見積られた除去費用
ホ.有形固定資産の除去に係るサービス(除去サービス)を行う業者など第三者からの情報
これらにより見積られた金額に、インフレ率や見積値から乖離するリスクを反映させ、また、合理的で説明可能な仮定及び予測に基づき、技術革新などによる影響額を見積ることができる場合には、これを反映させる。
(2)割引率 割引率は、貨幣の時間価値を反映した無リスクの税引前の利率とする(基準第6項(2))。
米国会計基準のように信用リスクを反映させた割引率を用いるべきだとする考え方もあるが、会計基準では、明示的な金利キャッシュ・フローを含まない債務である資産除去債務については、退職給付会計と同様に無リスクの割引率を用いるのが整合的と考えられること、同一内容の債務について信用リスクの高い企業のほうが、負債計上額が少なくなる結果となるのは財政状態を適切に示さないと考えられることなどから、無リスクの割引率を用いることとしている(基準第40項)。
3.資産除去債務に対応する除去費用の資産計上と費用配分
(1)原則的な考え方 資産除去債務を負債として計上した時に、当該負債の計上額と同額を、関連する有形固定資産の帳簿価額に加える。これを、減価償却を通じて、当該有形固定資産の残存耐用年数にわたり、各期に費用配分する(基準第7項)。
本会計基準では、この負債計上額に対応する資産計上額を「資産除去債務に対応する除去費用」と呼んでいる。その性格は、有形固定資産の取得に関する付随費用と同様のものと説明されている。すなわち、有形固定資産の除去時に不可避的に生じる支出額を付随費用と同様に取得原価に加えて当該資産への投資について回収すべき額を引き上げた上で、その費用配分を行い、さらに資産効率の観点からも有用と考えられる情報を提供するものであると考えられている(基準第41項)。
資産除去債務に対応する金額を有形固定資産の取得原価に含めて計上する場合、実務上の負担を勘案すると、関連する有形固定資産と区分して別の資産として管理することは妨げられないが、その場合でも、財務諸表上は有形固定資産として表示する必要がある(基準第42項)。
なお、会計基準適用後の減損会計基準の適用にあたり、資産除去債務が負債に計上されている場合には、除去費用部分の影響を二重に認識しないようにするため、将来キャッシュ・フローの見積りに除去費用部分を含めない(基準第43項)。
(2)資産除去債務が使用の都度発生する場合 資産除去債務が有形固定資産の稼働等に従って、使用の都度発生する場合には、資産除去債務に対応する除去費用を各期においてそれぞれ資産計上し、関連する有形固定資産の残存耐用年数にわたり、各期に費用配分する。なお、この場合には、上記の処理のほか、除去費用をいったん資産に計上し、当該計上時期と同一の期間に、資産計上額と同一の金額を費用処理することもできる(基準第8項)。
なお、通常、資産除去債務は有形固定資産の取得、建設または開発の時点で発生するものであり、このように使用の都度発生する場合は極めて例外的であると考えられる(基準第46項)。
(3)時の経過による資産除去債務の調整額 時の経過による資産除去債務の調整額は、その発生時の費用として処理する。当該調整額は、期首の負債の帳簿価額に当初負債計上時の割引率を乗じて算定する(基準第9項)。この調整額は、退職給付会計における利息費用と同様の性格を有するものと考えられている(基準第48項)。
なお、資産除去債務の割引率については、国際財務報告基準(脚注2)では毎期見直すこととされているが、本会計基準では、米国会計基準と同様に、変更を行わずに負債計上時の割引率を用いることとしている。これは、他の負債の取扱いとの整合性や、関連する有形固定資産について減価償却という費用配分が行われることとの整合性を考慮したものである(基準第49項)。
(4)資産除去債務の対象が複数の有形固定資産から構成される場合 資産除去債務の対象が複数の有形固定資産から構成され、そのうち一部の資産は全体の除去以前により短い周期で除去される場合も想定される。この短い周期で除去される資産について除去の義務がなければ資産除去債務には該当しないが、主たる資産について資産除去債務があり、主たる資産の除去に伴い全体が同時に除去される場合には、その際の除去費用は資産除去債務に付随するものと見て、全体を一括して資産除去債務の見積りを行い、対応する除去費用を主たる資産の帳簿価額に加えることとしている(指針第6項)。
このとき、主たる資産を除去するまでの間に行われる、より短い周期で実施される資産の除去及び再取得に係る支出は資産除去債務の対象とせず、主たる資産の除去と同時に行われる資産の除去に係る支出は対象となる(指針第24項)。
なお、個々の資産が除去に係る法的義務等を有する時は、当該複数の有形固定資産に対し、一括して資産除去債務を見積るのではなく、個々の有形固定資産について見積り、対応する除去費用を個々の有形固定資産の帳簿価額に加える必要がある(指針第25項)。
(5)特別の法令等により除去に係る費用を適切に計上する方法がある場合 特別の法令等により、有形固定資産の除去に係るサービス(除去サービス)の費消を当該有形固定資産の使用に応じて各期間で適切に費用計上する方法がある場合には、当該費用計上方法を用いることができる。ただし、この場合でも、会計基準の定めに基づき、当該有形固定資産の資産除去債務を負債に計上し、これに対応する除去費用を関連する有形固定資産の帳簿価額に加える方法で資産として計上しなければならない。また、当該費用の計上方法については、注記する必要がある(指針第8項)。
この取扱いは、原子力発電施設の解体費用について解体引当金を計上している電力業界などが主な対象として想定されているが、費用計上方法が会計上合理的であることが適用の条件となる。
(6)建物等賃借契約に関連して敷金を支出している場合 賃借建物等について有形固定資産(内部造作等)の除去などの原状回復の義務がある場合、資産除去債務に該当するが、当該賃借契約に関連する敷金が資産計上されているときは、資産除去債務の負債計上及び対応する除去費用の資産計上に代えて、当該敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、そのうち当期の負担に属する金額を費用に計上する方法によることができる(指針第9項)。資産除去債務とそれに対応する除去費用の会計処理と敷金の会計処理は、本来別個に行うべきものと考えられるが、建物等の賃借契約に関連する資産除去債務については、実務上の負担に対する考慮から、このような処理方法が認められている(指針第27項)。
なお、敷金について上記の処理を行う場合には、適用初年度の期首において、当該敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額のうち前期以前の負担に属する金額を、当期の損失(原則として特別損失)として計上する(指針第15項)。
4.資産除去債務の見積りの変更
(1)割引前将来キャッシュ・フローの見積りの変更 割引前の将来キャッシュ・フローに重要な見積りの変更が生じた場合の当該見積りの変更による調整額は、資産除去債務の帳簿価額及び関連する有形固定資産の帳簿価額に加減して処理する。資産除去債務が法令の改正等により新たに発生した場合も、見積りの変更と同様に取り扱う(基準第10項)。
この方法(プロスペクティブ・アプローチ)は、見積りの変更の影響を残存耐用年数にわたり費用配分することになるが、国際財務報告基準及び米国基準でも同様の方法が採用されている。
(2)割引前将来キャッシュ・フローの見積りの変更による調整額に適用する割引率 割引前の将来キャッシュ・フローに重要な見積りの変更が生じ、当該キャッシュ・フローが増加する場合、その時点の割引率を適用する。これに対し、当該キャッシュ・フローが減少する場合には、負債計上時の割引率を適用する。なお、過去に割引前の将来キャッシュ・フローの見積りに増加があった場合で、減少部分に適用すべき割引率を特定できないときは、加重平均した割引率を適用する(基準第11項)。
この取扱いは米国会計基準と同様である。
Ⅴ.開 示
1.貸借対照表上の開示 資産除去債務は、貸借対照表日後1年以内にその履行が見込まれる場合を除き、固定負債の区分に資産除去債務等の適切な科目名で表示する。貸借対照表日後1年以内に資産除去債務の履行が見込まれる場合には、流動負債の区分に表示する(基準第12項)。
2.損益計算書上の表示
(1)資産計上された除去費用の費用配分額 資産計上された資産除去債務に対応する除去費用に係る費用配分額は、関連する有形固定資産の減価償却費と同じ区分に含めて計上する(基準第13項)。
(2)時の経過による資産除去債務の調整額 時の経過による資産除去債務の調整額は、関連する有形固定資産の減価償却費と同じ区分に含めて計上する(基準第14項)。
国際財務報告基準では財務費用としているが、米国基準では営業費用としている。本会計基準では、実際の資金調達活動による費用ではないことや、退職給付会計における利息費用との類似性等を考慮して、関連する有形固定資産の減価償却費と同じ区分とした。
(3)決済時の差額 資産除去債務残高と資産除去債務の決済のために実際に支払われた額との差額は、原則として、当該資産除去債務に対応する除去費用に係る費用配分額と同じ区分に含めて計上する(基準第15項)。
3.注記事項 資産除去債務の会計処理に関連して、重要性が乏しい場合を除き、次の事項を注記するものとしている(基準第16項)。なお、多数の有形固定資産について資産除去債務が生じている場合には、有形固定資産の種類や場所等に基づいて、下記の注記をまとめて記載することができる(指針第10項)。
① 資産除去債務の内容についての簡潔な説明(資産除去債務の発生原因となっている法的規制又は契約等の概要を簡潔に記載)
② 支出発生までの見込期間、適用した割引率等の前提条件
③ 資産除去債務の総額の期中における増減内容
④ 資産除去債務の見積りを変更したときは、その変更の概要及び影響額
⑤ 資産除去債務は発生しているが、その債務を合理的に見積ることができないため、貸借対照表に資産除去債務を計上していない場合には、当該資産除去債務の概要、合理的に見積ることができない旨及びその理由(①「資産除去債務の内容についての簡潔な説明」と関連付けて記載する)
4.資産除去債務のキャッシュ・フロー計算書上の取扱い 資産除去債務を実際に履行した場合、その支出額についてはキャッシュ・フロー計算書上「投資活動によるキャッシュ・フロー」の項目として取り扱う。また、重要な資産除去債務を計上した時は、キャッシュ・フロー計算書に「重要な非資金取引」としての注記が必要となる(指針第12項、第13項)。
5.四半期財務諸表における注記 企業会計基準第12号「四半期財務諸表に関する会計基準(以下「四半期会計基準」という。)第19項(21)及び第25項(20)で定める「財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適切に判断するために重要なその他の事項」として、資産除去債務が前年度末と比較して著しく変動している場合には、その簡潔な説明及び変動額の内訳を記載することが考えられる。なお、会計基準の適用開始による資産除去債務の変動については、その影響が重要であれば、「重要な会計処理の原則及び手続についての変更」(四半期会計基準第19項(2)及び第25項(1))として注記を行うこととなる(指針第30項)。
Ⅵ.適用時期等
1.適用時期 本会計基準は、平成22年4月1日以後開始する事業年度から適用する。ただし、平成22年3月31日以前に開始する事業年度から適用することができる(基準第17項)。
本会計基準の適用は、会計基準の変更に伴う会計方針の変更として取り扱う(基準第20項)。
2.適用初年度における期首残高の算定 適用初年度の期首残高は次のように算定し、両者の差額は適用初年度の損益とし、原則として特別損失に計上する(基準第18項)。
① 適用初年度の期首における既存資産に関連する資産除去債務は、適用初年度の期首日時点における割引前将来キャッシュ・フローの見積り及び割引率により計算する。
② 適用初年度の期首における既存資産の帳簿価額に含まれる除去費用は、資産除去債務の発生時点における割引前将来キャッシュ・フローの見積り及び割引率が、適用初年度の期首時点と同一であったものとみなして計算した金額から、その後の減価償却額に相当する金額を控除した金額とする。
なお、適用初年度の期首における既存資産に関連する資産除去債務について引当金を計上していた場合、資産除去債務及び関連する有形固定資産の期首残高は上記①及び②に従って算定するが、前期末の引当金の残高を資産除去債務の一部として引き継ぐ(基準第19項)。
上述のような算定方法は、キャッチアップ方式の考え方によるものである。将来キャッシュ・フローの見積りの変更と同様にプロスペクティブ方式を採用する考え方も検討の対象とされた。しかし、適用初年度においては、使用開始後相当の期間を経過した有形固定資産が対象となることが多いことから、プロスペクティブ方式では資産の残高が回収可能価額を大きく上回る結果となる可能性が大きくなる。それに対応するために減損損失の認識の要否の検討を要求することとした場合、検討対象となる資産が多数にのぼり実務上過大な負担となるおそれがあることなどを考慮した結果、キャッチアップ方式がより適切と判断されたものである(基準第62項)。
キャッチアップ方式の採用により生じる期首差額の取扱いに関しては、将来の一定期間にわたって費用処理する方法や、適用初年度の期首剰余金の調整項目とする方法も検討の対象とされた。しかしながら、前者については、減損会計基準適用時にこれを容認しなかった経緯との整合性、後者については、過年度財務諸表への会計基準の遡及適用の考え方が我が国では未だ導入されていないこととの整合性の観点などから、いずれも適切でないと判断された(基準第63項)。(おぎわら・まさよし)
脚注
1 国際財務報告基準ではIAS第37号「引当金、偶発負債及び偶発資産」及びIAS第16号「有形固定資産」、米国会計基準ではSFAS第143号「資産除去債務に関する会計処理」で規定されている。
2 IFRIC第1号「廃棄、復旧及びそれらに類似の負債の変動」が解釈指針として示されている。
資産除去債務に関する会計基準等について
企業会計基準委員会 主任研究員 荻原正佳
Ⅰ.はじめに
企業会計基準委員会(ASBJ)は、企業会計基準第18号「資産除去債務に関する会計基準」(以下「会計基準」という。)及び企業会計基準適用指針第22号「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」(以下「適用指針」という。)を平成20年3月31日付で公表した。
本稿では、会計基準及び適用指針の概要を紹介するが、意見にわたる部分は私見であることを予めお断りしておく。
Ⅱ.資産除去債務の会計処理の基本的な考え方
資産除去債務の会計処理の基本的な考え方は、「有形固定資産の除去に伴う支出の不可避的な義務(資産除去債務)が存在する場合に、それを負債に計上し、その発生時における現在価値を当該有形固定資産の帳簿価額に加えて、減価償却を通じて各期に費用配分するとともに、その現在価値と割引前の将来支出金額との差額を時の経過による調整額として費用計上していく会計処理」と要約できる。
例えば、有形固定資産の取得時に資産除去債務が発生し、20年後に100の支出が見込まれているものとする。この場合、割引率を4%とすると支出見込額の現在価値は約46となる。これが資産除去債務の当初計上額となるとともに、有形固定資産の帳簿価額に加算されることになる。資産サイドでは、この当初に計上された金額46が減価償却を通じて期間配分される一方、負債サイドでは、支出見込額100との差額54(100-46)が「時の経過による資産除去債務の調整額」として各期に費用計上され、現在価値の増加に従って負債が増額されていくことになる(図参照)。
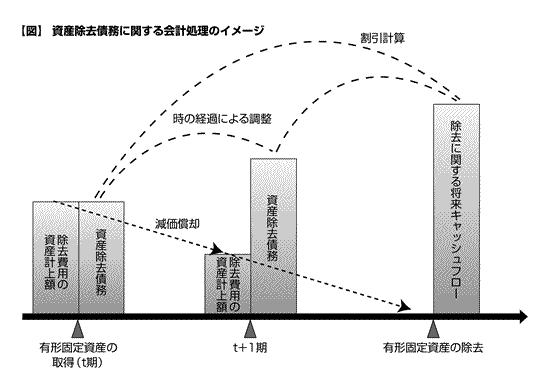
同様の会計処理を採用している国際的な会計基準(脚注1)とのコンバージェンスが、ASBJが資産除去債務をプロジェクト項目として取り上げた契機の一つとなっている。このような会計処理は、不可避的な義務は負債として認識する必要があるという考え方に基づくものといえる。
Ⅲ.適用範囲
会計基準の適用対象となるのは、「資産除去債務」の定義を満たす法律上の義務及びそれに準ずるものである。
「資産除去債務」とは、有形固定資産の取得、建設、開発又は通常の使用によって生じ、当該有形固定資産の除去に関して法令又は契約で要求される法律上の義務及びそれに準ずるものをいう。この場合の法律上の義務及びそれに準ずるものには、有形固定資産を除去する義務のほか、有形固定資産の除去そのものは義務でなくとも、有形固定資産を除去する際に当該有形固定資産に使用されている有害物質等を法律等の要求による特別の方法で除去するという義務も含まれる(基準第3項(1))。
会計基準では、資産除去債務は有形固定資産の取得、建設、開発又は通常の使用により生じるものとしている。通常の使用とは、有形固定資産を意図した目的のために正常に稼働させることをいう。有形固定資産を除去する義務が、不適切な操業等の異常な原因によって発生した場合には、資産除去債務として使用期間にわたって費用配分すべきものではなく、引当金の計上や、「固定資産の減損に係る会計基準」の適用対象とすべきものと考えられる(基準第26項)。
なお、本会計基準でいう有形固定資産には、財務諸表等規則において有形固定資産に区分される資産のほか、それに準ずる有形の資産も含む。したがって、建設仮勘定やリース資産のほか、財務諸表等規則において「投資その他の資産」に分類されている投資不動産などについても、資産除去債務が存在している場合には、会計基準の対象となる(基準第23項)。
有形固定資産の「除去」とは、有形固定資産を用役提供から除外することをいう(一時的に除外する場合を除く)。除去の具体的な態様には、売却、廃棄、リサイクルその他の方法による処分等が含まれるが、企業が自ら使用を継続する転用や用途変更は含まれない。また、有形固定資産が遊休状態になることは除去に該当しない(基準第3項(2))。
資産除去債務の典型な事例として、原子力発電施設の解体に伴う債務が挙げられることが多い。有形固定資産を除去する義務としては、そのほかに、例えば、定期借地権契約で賃借した土地の上に建設した建物等を除去する義務、鉱山等の原状回復義務、賃借建物の原状回復義務などが考えられる。また、有害物質等を特別の方法で除去する義務としては、アスベストやPCBの除去の義務などが該当しうるものと考えられる。
資産除去債務は、あくまで有形固定資産の除去に関連するものが対象であるため、資産の使用開始前から将来の支出が予想されるものであっても、有形固定資産の使用期間中に実施する環境修復や修繕は対象とはならない(基準第24項)。
本会計基準では、法律上の義務に準ずるものとは、債務の履行を免れることがほぼ不可能な義務を指し、法令又は契約で要求される法律上の義務とほぼ同等の不可避的な義務が該当するとしている。具体的には、法律上の解釈により当事者間での清算が要請される義務に加え、過去の判例や行政当局の通達等のうち、法律上の義務とほぼ同等の不可避的な支出が義務付けられるものが該当すると考えられる。したがって、有形固定資産の除去が企業の自発的な計画のみによって行われる場合は、法律上の義務に準ずるものには該当しない(基準第28項)。
Ⅳ.資産除去債務の会計処理
1.資産除去債務の負債計上 資産除去債務は、有形固定資産の取得、建設、開発又は通常の使用によって発生した時に負債として計上する(基準第4項)。
資産除去債務の発生時に、当該債務の金額を合理的に見積ることができない場合には、これを計上せず、当該債務額を合理的に見積ることができるようになった時点で負債として計上する。その場合の負債の計上の処理は、第10項及び第11項に準じる(基準第5項)。
資産除去債務を合理的に見積ることができない場合とは、決算日現在入手可能なすべての証拠を勘案し、最善の見積りを行ってもなお、合理的に金額を算定できない場合をいう。このような場合には、基準第16項(5)に定める開示が必要である(指針第2項)。
資産除去債務を負債に計上する会計処理としては、本会計基準で採用している資産負債の両建処理を行う方法のほか、有形固定資産の除去に係る用役の費消を当該有形固定資産の使用に応じて各期間に費用配分し、それに対応する金額を負債として認識する考え方(引当金処理)もある。引当金処理は、有形固定資産に対応する除去費用が当該有形固定資産の使用に応じて各期に適切な形で費用配分されるという点では、資産負債の両建処理と同様であり、また、資産負債の両建処理の場合に計上される借方項目の資産性を疑問視する観点からは、引当金処理を採用した上で資産除去債務の金額等を注記情報として開示するほうが適切ではないかとの見方もあった。
しかしながら、引当金処理では有形固定資産の除去に必要な金額が貸借対照表に計上されないことから、資産除去債務の負債計上が不十分であるという意見がある。また、資産負債の両建処理は、除去費用を有形固定資産の取得原価に含めることで、有形固定資産に対応する除去費用が減価償却を通じて当該有形固定資産の使用に応じて各期に費用配分されるため、損益計算の観点からは引当金処理を包摂するものといえる。さらに、資産負債の両建処理は、国際的な会計基準とのコンバージェンスにも資するものであるため、本会計基準では、資産負債の両建処理を求めることとした(会計基準第32項から第34項まで)。
2.資産除去債務の算定 資産除去債務はそれが発生したときに、有形固定資産の除去に関する割引前の将来キャッシュ・フローを見積り、割引後の金額(割引価値)で算定する(基準第6項)。
(1)将来支出の見積り 割引前の将来キャッシュ・フローは、合理的で説明可能な仮定及び予測に基づく自己の支出見積りによる。その見積金額は、生起する可能性の最も高い単一の金額又は生起しうる複数の将来キャッシュ・フローをそれぞれの確率で加重平均した金額とする。将来キャッシュ・フローには、有形固定資産の除去に係る作業のために直接要する支出のほか、処分に至るまでの支出(例えば、保管や管理のための支出)も含める(基準第6項(1))。
割引前の将来キャッシュ・フローの見積りは、次のような情報を基礎として行うこととしている(指針第3項)。
イ.対象となる有形固定資産の除去に必要な平均的な処理作業に対する価格の見積り
ロ.対象となる有形固定資産を取得した際に、取引価額から控除された当該資産に係る除去費用の算定の基礎となった数値
ハ.過去において類似の資産について発生した除去費用の実績
ニ.当該有形固定資産への投資の意思決定を行う際に見積られた除去費用
ホ.有形固定資産の除去に係るサービス(除去サービス)を行う業者など第三者からの情報
これらにより見積られた金額に、インフレ率や見積値から乖離するリスクを反映させ、また、合理的で説明可能な仮定及び予測に基づき、技術革新などによる影響額を見積ることができる場合には、これを反映させる。
(2)割引率 割引率は、貨幣の時間価値を反映した無リスクの税引前の利率とする(基準第6項(2))。
米国会計基準のように信用リスクを反映させた割引率を用いるべきだとする考え方もあるが、会計基準では、明示的な金利キャッシュ・フローを含まない債務である資産除去債務については、退職給付会計と同様に無リスクの割引率を用いるのが整合的と考えられること、同一内容の債務について信用リスクの高い企業のほうが、負債計上額が少なくなる結果となるのは財政状態を適切に示さないと考えられることなどから、無リスクの割引率を用いることとしている(基準第40項)。
3.資産除去債務に対応する除去費用の資産計上と費用配分
(1)原則的な考え方 資産除去債務を負債として計上した時に、当該負債の計上額と同額を、関連する有形固定資産の帳簿価額に加える。これを、減価償却を通じて、当該有形固定資産の残存耐用年数にわたり、各期に費用配分する(基準第7項)。
本会計基準では、この負債計上額に対応する資産計上額を「資産除去債務に対応する除去費用」と呼んでいる。その性格は、有形固定資産の取得に関する付随費用と同様のものと説明されている。すなわち、有形固定資産の除去時に不可避的に生じる支出額を付随費用と同様に取得原価に加えて当該資産への投資について回収すべき額を引き上げた上で、その費用配分を行い、さらに資産効率の観点からも有用と考えられる情報を提供するものであると考えられている(基準第41項)。
資産除去債務に対応する金額を有形固定資産の取得原価に含めて計上する場合、実務上の負担を勘案すると、関連する有形固定資産と区分して別の資産として管理することは妨げられないが、その場合でも、財務諸表上は有形固定資産として表示する必要がある(基準第42項)。
なお、会計基準適用後の減損会計基準の適用にあたり、資産除去債務が負債に計上されている場合には、除去費用部分の影響を二重に認識しないようにするため、将来キャッシュ・フローの見積りに除去費用部分を含めない(基準第43項)。
(2)資産除去債務が使用の都度発生する場合 資産除去債務が有形固定資産の稼働等に従って、使用の都度発生する場合には、資産除去債務に対応する除去費用を各期においてそれぞれ資産計上し、関連する有形固定資産の残存耐用年数にわたり、各期に費用配分する。なお、この場合には、上記の処理のほか、除去費用をいったん資産に計上し、当該計上時期と同一の期間に、資産計上額と同一の金額を費用処理することもできる(基準第8項)。
なお、通常、資産除去債務は有形固定資産の取得、建設または開発の時点で発生するものであり、このように使用の都度発生する場合は極めて例外的であると考えられる(基準第46項)。
(3)時の経過による資産除去債務の調整額 時の経過による資産除去債務の調整額は、その発生時の費用として処理する。当該調整額は、期首の負債の帳簿価額に当初負債計上時の割引率を乗じて算定する(基準第9項)。この調整額は、退職給付会計における利息費用と同様の性格を有するものと考えられている(基準第48項)。
なお、資産除去債務の割引率については、国際財務報告基準(脚注2)では毎期見直すこととされているが、本会計基準では、米国会計基準と同様に、変更を行わずに負債計上時の割引率を用いることとしている。これは、他の負債の取扱いとの整合性や、関連する有形固定資産について減価償却という費用配分が行われることとの整合性を考慮したものである(基準第49項)。
(4)資産除去債務の対象が複数の有形固定資産から構成される場合 資産除去債務の対象が複数の有形固定資産から構成され、そのうち一部の資産は全体の除去以前により短い周期で除去される場合も想定される。この短い周期で除去される資産について除去の義務がなければ資産除去債務には該当しないが、主たる資産について資産除去債務があり、主たる資産の除去に伴い全体が同時に除去される場合には、その際の除去費用は資産除去債務に付随するものと見て、全体を一括して資産除去債務の見積りを行い、対応する除去費用を主たる資産の帳簿価額に加えることとしている(指針第6項)。
このとき、主たる資産を除去するまでの間に行われる、より短い周期で実施される資産の除去及び再取得に係る支出は資産除去債務の対象とせず、主たる資産の除去と同時に行われる資産の除去に係る支出は対象となる(指針第24項)。
なお、個々の資産が除去に係る法的義務等を有する時は、当該複数の有形固定資産に対し、一括して資産除去債務を見積るのではなく、個々の有形固定資産について見積り、対応する除去費用を個々の有形固定資産の帳簿価額に加える必要がある(指針第25項)。
(5)特別の法令等により除去に係る費用を適切に計上する方法がある場合 特別の法令等により、有形固定資産の除去に係るサービス(除去サービス)の費消を当該有形固定資産の使用に応じて各期間で適切に費用計上する方法がある場合には、当該費用計上方法を用いることができる。ただし、この場合でも、会計基準の定めに基づき、当該有形固定資産の資産除去債務を負債に計上し、これに対応する除去費用を関連する有形固定資産の帳簿価額に加える方法で資産として計上しなければならない。また、当該費用の計上方法については、注記する必要がある(指針第8項)。
この取扱いは、原子力発電施設の解体費用について解体引当金を計上している電力業界などが主な対象として想定されているが、費用計上方法が会計上合理的であることが適用の条件となる。
(6)建物等賃借契約に関連して敷金を支出している場合 賃借建物等について有形固定資産(内部造作等)の除去などの原状回復の義務がある場合、資産除去債務に該当するが、当該賃借契約に関連する敷金が資産計上されているときは、資産除去債務の負債計上及び対応する除去費用の資産計上に代えて、当該敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、そのうち当期の負担に属する金額を費用に計上する方法によることができる(指針第9項)。資産除去債務とそれに対応する除去費用の会計処理と敷金の会計処理は、本来別個に行うべきものと考えられるが、建物等の賃借契約に関連する資産除去債務については、実務上の負担に対する考慮から、このような処理方法が認められている(指針第27項)。
なお、敷金について上記の処理を行う場合には、適用初年度の期首において、当該敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額のうち前期以前の負担に属する金額を、当期の損失(原則として特別損失)として計上する(指針第15項)。
4.資産除去債務の見積りの変更
(1)割引前将来キャッシュ・フローの見積りの変更 割引前の将来キャッシュ・フローに重要な見積りの変更が生じた場合の当該見積りの変更による調整額は、資産除去債務の帳簿価額及び関連する有形固定資産の帳簿価額に加減して処理する。資産除去債務が法令の改正等により新たに発生した場合も、見積りの変更と同様に取り扱う(基準第10項)。
この方法(プロスペクティブ・アプローチ)は、見積りの変更の影響を残存耐用年数にわたり費用配分することになるが、国際財務報告基準及び米国基準でも同様の方法が採用されている。
(2)割引前将来キャッシュ・フローの見積りの変更による調整額に適用する割引率 割引前の将来キャッシュ・フローに重要な見積りの変更が生じ、当該キャッシュ・フローが増加する場合、その時点の割引率を適用する。これに対し、当該キャッシュ・フローが減少する場合には、負債計上時の割引率を適用する。なお、過去に割引前の将来キャッシュ・フローの見積りに増加があった場合で、減少部分に適用すべき割引率を特定できないときは、加重平均した割引率を適用する(基準第11項)。
この取扱いは米国会計基準と同様である。
Ⅴ.開 示
1.貸借対照表上の開示 資産除去債務は、貸借対照表日後1年以内にその履行が見込まれる場合を除き、固定負債の区分に資産除去債務等の適切な科目名で表示する。貸借対照表日後1年以内に資産除去債務の履行が見込まれる場合には、流動負債の区分に表示する(基準第12項)。
2.損益計算書上の表示
(1)資産計上された除去費用の費用配分額 資産計上された資産除去債務に対応する除去費用に係る費用配分額は、関連する有形固定資産の減価償却費と同じ区分に含めて計上する(基準第13項)。
(2)時の経過による資産除去債務の調整額 時の経過による資産除去債務の調整額は、関連する有形固定資産の減価償却費と同じ区分に含めて計上する(基準第14項)。
国際財務報告基準では財務費用としているが、米国基準では営業費用としている。本会計基準では、実際の資金調達活動による費用ではないことや、退職給付会計における利息費用との類似性等を考慮して、関連する有形固定資産の減価償却費と同じ区分とした。
(3)決済時の差額 資産除去債務残高と資産除去債務の決済のために実際に支払われた額との差額は、原則として、当該資産除去債務に対応する除去費用に係る費用配分額と同じ区分に含めて計上する(基準第15項)。
3.注記事項 資産除去債務の会計処理に関連して、重要性が乏しい場合を除き、次の事項を注記するものとしている(基準第16項)。なお、多数の有形固定資産について資産除去債務が生じている場合には、有形固定資産の種類や場所等に基づいて、下記の注記をまとめて記載することができる(指針第10項)。
① 資産除去債務の内容についての簡潔な説明(資産除去債務の発生原因となっている法的規制又は契約等の概要を簡潔に記載)
② 支出発生までの見込期間、適用した割引率等の前提条件
③ 資産除去債務の総額の期中における増減内容
④ 資産除去債務の見積りを変更したときは、その変更の概要及び影響額
⑤ 資産除去債務は発生しているが、その債務を合理的に見積ることができないため、貸借対照表に資産除去債務を計上していない場合には、当該資産除去債務の概要、合理的に見積ることができない旨及びその理由(①「資産除去債務の内容についての簡潔な説明」と関連付けて記載する)
4.資産除去債務のキャッシュ・フロー計算書上の取扱い 資産除去債務を実際に履行した場合、その支出額についてはキャッシュ・フロー計算書上「投資活動によるキャッシュ・フロー」の項目として取り扱う。また、重要な資産除去債務を計上した時は、キャッシュ・フロー計算書に「重要な非資金取引」としての注記が必要となる(指針第12項、第13項)。
5.四半期財務諸表における注記 企業会計基準第12号「四半期財務諸表に関する会計基準(以下「四半期会計基準」という。)第19項(21)及び第25項(20)で定める「財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適切に判断するために重要なその他の事項」として、資産除去債務が前年度末と比較して著しく変動している場合には、その簡潔な説明及び変動額の内訳を記載することが考えられる。なお、会計基準の適用開始による資産除去債務の変動については、その影響が重要であれば、「重要な会計処理の原則及び手続についての変更」(四半期会計基準第19項(2)及び第25項(1))として注記を行うこととなる(指針第30項)。
Ⅵ.適用時期等
1.適用時期 本会計基準は、平成22年4月1日以後開始する事業年度から適用する。ただし、平成22年3月31日以前に開始する事業年度から適用することができる(基準第17項)。
本会計基準の適用は、会計基準の変更に伴う会計方針の変更として取り扱う(基準第20項)。
2.適用初年度における期首残高の算定 適用初年度の期首残高は次のように算定し、両者の差額は適用初年度の損益とし、原則として特別損失に計上する(基準第18項)。
① 適用初年度の期首における既存資産に関連する資産除去債務は、適用初年度の期首日時点における割引前将来キャッシュ・フローの見積り及び割引率により計算する。
② 適用初年度の期首における既存資産の帳簿価額に含まれる除去費用は、資産除去債務の発生時点における割引前将来キャッシュ・フローの見積り及び割引率が、適用初年度の期首時点と同一であったものとみなして計算した金額から、その後の減価償却額に相当する金額を控除した金額とする。
なお、適用初年度の期首における既存資産に関連する資産除去債務について引当金を計上していた場合、資産除去債務及び関連する有形固定資産の期首残高は上記①及び②に従って算定するが、前期末の引当金の残高を資産除去債務の一部として引き継ぐ(基準第19項)。
上述のような算定方法は、キャッチアップ方式の考え方によるものである。将来キャッシュ・フローの見積りの変更と同様にプロスペクティブ方式を採用する考え方も検討の対象とされた。しかし、適用初年度においては、使用開始後相当の期間を経過した有形固定資産が対象となることが多いことから、プロスペクティブ方式では資産の残高が回収可能価額を大きく上回る結果となる可能性が大きくなる。それに対応するために減損損失の認識の要否の検討を要求することとした場合、検討対象となる資産が多数にのぼり実務上過大な負担となるおそれがあることなどを考慮した結果、キャッチアップ方式がより適切と判断されたものである(基準第62項)。
キャッチアップ方式の採用により生じる期首差額の取扱いに関しては、将来の一定期間にわたって費用処理する方法や、適用初年度の期首剰余金の調整項目とする方法も検討の対象とされた。しかしながら、前者については、減損会計基準適用時にこれを容認しなかった経緯との整合性、後者については、過年度財務諸表への会計基準の遡及適用の考え方が我が国では未だ導入されていないこととの整合性の観点などから、いずれも適切でないと判断された(基準第63項)。(おぎわら・まさよし)
脚注
1 国際財務報告基準ではIAS第37号「引当金、偶発負債及び偶発資産」及びIAS第16号「有形固定資産」、米国会計基準ではSFAS第143号「資産除去債務に関する会計処理」で規定されている。
2 IFRIC第1号「廃棄、復旧及びそれらに類似の負債の変動」が解釈指針として示されている。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -

Copyright (C) 2019
SHINNIPPON-HOKI PUBLISHING CO.,LTD.





















