解説記事2008年06月16日 【会計基準等解説】 企業会計基準適用指針第22号「連結財務諸表における子会社及び関連会社の範囲の決定に関する適用指針」について(2008年6月16日号・№262)
実務解説
企業会計基準適用指針第22号
「連結財務諸表における子会社及び関連会社の範囲の決定に関する適用指針」について
企業会計基準委員会 専門研究員 二宮正裕
Ⅰ.はじめに
企業会計基準委員会(ASBJ)では、平成20年5月13日に、企業会計基準適用指針第22号「連結財務諸表における子会社及び関連会社の範囲の決定に関する適用指針」(以下「本適用指針」という。)を公表している(脚注1)。本適用指針は、平成20年1月24日に公開草案を公表し、これに対して寄せられたコメントも参考に審議を行い、公表されたものである。本稿では、本適用指針の概要を紹介するが、文中の意見にわたる部分は筆者の私見であることをあらかじめお断りしておく。なお、特に断りがない限り、参照項は本適用指針の項番号を指す。
Ⅱ.本適用指針の位置付け
1 経 緯 平成9年6月に、企業会計審議会は「連結財務諸表制度の見直しに関する意見書」(以下「連結意見書」という。)を公表し、従来の個別情報を中心とする開示から連結情報を中心とする開示に転換を図ることを提言するとともに、連結情報充実の観点から改訂した「連結財務諸表原則」(以下「連結原則」という。)を公表した。さらに、同審議会は、平成10年10月に、子会社及び関連会社の範囲を整理した「連結財務諸表制度における子会社及び関連会社の範囲の見直しに係る具体的な取扱い」(以下「子会社等の範囲の見直しに係る具体的な取扱い」という。)を公表し、子会社及び関連会社の判定基準についての具体的な取扱いを示している。
連結原則及び子会社等の範囲の見直しに係る具体的な取扱いにおいては、議決権の所有割合以外の要素を加味した支配力基準を導入し、他の会社等の財務及び営業又は事業の方針を決定する機関を支配しているかどうかという観点から子会社の判定を行うこととし、また、影響力基準を導入し、他の会社等の財務及び営業又は事業の方針決定に対して重要な影響を与えることができるかどうかという観点から関連会社の判定を行うこととしている。
連結原則及び子会社等の範囲の見直しに係る具体的な取扱いを踏まえて、これまで子会社及び関連会社の範囲の決定に関しては、日本公認会計士協会監査委員会報告第60号「連結財務諸表における子会社及び関連会社の範囲の決定に関する監査上の取扱い」(以下「監査委員会報告第60号」という。)が実務上の指針として用いられてきた。
2 本適用指針の目的 ASBJでは、会社法の施行への対応や早期に取扱いの明確化が必要と考えられるものがあることから、監査委員会報告第60号のうち会計上の取扱いに関する部分について、基本的にその内容を引き継いだ上で、本適用指針を公表した。すなわち、本適用指針は、子会社及び関連会社の範囲について、連結原則及び子会社等の範囲の見直しに係る具体的な取扱いを適用する際の指針を定めることを目的としている。
Ⅲ.本適用指針の概要
以下では、監査委員会報告第60号の取扱いと異なる定めをした箇所を中心に示すこととする。
1 議決権の所有割合の算定(4項) 本適用指針では、監査委員会報告第60号の考え方を踏襲し、他の会社が子会社又は関連会社に該当するかどうかの判定において用いられる他の会社の議決権の所有割合は、原則として、次の算式によって算定するものとしている。
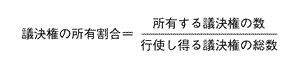
この際、「行使し得る議決権の総数」についても、従来と同様に、株主総会において行使し得るものと認められている総株主の議決権の数としている。また、会社法への対応により表現が改正されているが、これまでと同様に、以下の株式に係る議決権については、いずれも行使し得る議決権の総数には含まれないこととしている(5項)。
① 自己株式
② 完全無議決権株式(株主総会のすべての事項について議決権を行使することができない株式)
③ 会社法308条1項による相互保有株式
審議の過程では、一部の議案のみに議決権を有する議決権制限株式の取扱いについて、保有する議決権の内容により所有割合の算定に含めるかどうかを別途判断することも検討されたが、実質的な支配力又は影響力の判定は、議決権の所有割合のみで行うものはないことから、本適用指針では従来どおり、当該株式を所有割合の算定に含めることとしたとしている(36項)。
2 他の会社等の意思決定機関を支配していないこと等が明らかであると認められる場合の明確化(16項(4)及び24項)
(1)経 緯 連結原則第三 一 2及び子会社等の範囲の見直しに係る具体的な取扱い 一 3ただし書きでは、他の会社等の意思決定機関を支配していることに該当する要件を満たしていても、「財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて他の会社等の意思決定機関を支配していないことが明らかであると認められる場合」、当該他の会社等は子会社に該当しないものとしている。これに該当する場合の例として、従来、監査委員会報告第60号2(6)⑤及び⑥並びに3(4)①及び②で示されていた取扱いについては、その範囲や理由が明確ではないという指摘があった。特に、ベンチャーキャピタル条項などと呼ばれることもある監査委員会報告第60号2(6)⑥及び3(4)②は、監査上、留意すべき事項として示されていたこともあり、解釈が一様ではないという見方もあった。このため、本適用指針では、この考え方を整理し、該当する場合を具体的に示すこととした。
すなわち、本適用指針では、この取扱いは、ベンチャーキャピタルなどの投資企業が投資育成や事業再生を図りキャピタルゲイン獲得を目的とする営業取引として、又は銀行などの金融機関が債権の円滑な回収を目的とする営業取引として、当該他の会社の株式を所有し、当該営業取引のために議決権を行使していても、一定の場合には、当該他の会社の株主総会を支配する意図はないと判断することを想定していたものと解し、当該営業取引のために議決権を行使していても、投資先である他の会社等と連結グループとみなされるような運営がなされておらず、他の会社等の意思決定機関を支配する意図はないと判断できるような場合について、具体的に示すこととしたとしている(41項)。
(2)本適用指針での整理 本適用指針16項(4)では、ベンチャーキャピタルなどの投資企業(投資先の事業そのものによる成果ではなく、売却による成果を期待して投資価値の向上を目的とする業務を専ら行う会社等)が投資育成や事業再生を図りキャピタルゲイン獲得を目的とする営業取引として、又は銀行などの金融機関が債権の円滑な回収を目的とする営業取引として、他の会社等の株式や出資を有している場合には、子会社等の範囲の見直しに係る具体的な取扱い 一 3にいう他の会社等の意思決定機関を支配していることに該当する要件を満たしていても、次のすべてを満たすようなとき(ただし、当該他の会社等の株主総会その他これに準ずる機関を支配する意図が明確であると認められる場合を除く(脚注2)。)には、財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて他の会社等の意思決定機関を支配していないことが明らかであると認められ、子会社には該当しないことを示した。なお、本適用指針24項では関連会社の判定(他の会社等に重要な影響を与えることができないことが明らかであると認められる場合)についても、同様の定めを置いている。
① 売却等により他の会社等の議決権の大部分を所有しないこととなる合理的な計画があること まず、本適用指針では、この点について、関連会社の判定(24項)とともに整理しているため、「大部分を所有しないこと」については、売却等により、一義的には関連会社にあたらない程度にまで当該他の会社等の議決権を所有しないこととなる必要があるものと考えられるとしている。また、営業取引として他の会社等の株式や出資を有していることが前提とされていることから、当該営業取引の性質に見合う売却等の方法や時期その他の事項を考慮した計画の合理性が必要となるとしている。
② 当該他の会社等との間で、当該営業取引として行っている投資又は融資以外の取引がほとんどないこと ここでいう投資は、前述した営業取引として有している他の会社等の株式や出資を指し、融資は、金融機関が債権の円滑な回収を目的とする営業取引として他の会社等の株式や出資を有している場合における当該債権を指す。本適用指針では、そのような営業取引が独立して行われており、それ以外の取引がない場合には、他の会社等の意思決定機関を支配していることに該当する要件を満たすように投資企業が当該他の会社等の株式や出資を有していても、それはキャピタルゲイン獲得を目的とする営業取引としてのものにすぎず、また、金融機関が当該他の会社等の債権と株式や出資を有していても、それは当該債権の円滑な回収を目的とする営業取引としてのものにすぎないものと考えられるとしている。
③ 当該他の会社等は、自己の事業を単に移転したり自己に代わって行うものとはみなせないこと 公開草案では、「当該他の会社等の事業の種類は、自己の事業の種類と明らかに異なるものであること」としていたが、寄せられたコメント等を踏まえ、本適用指針では、新設分割や自己が主体となって他の会社等を設立したりすることにより、当該他の会社等において単に事業を移転したり自己に代わって行うものとみなせるような場合には、営業取引としてではなく、自己と一体になった運営がなされる可能性が高いため、この点を強調することが適切と考え修正したものとしている。
④ 当該他の会社等との間に、シナジー効果も連携関係も見込まれないこと 本適用指針では、他の要件ととともに、このような要件も満たす場合には、投資先である他の会社等とは別々に運営され、他の会社等の意思決定機関を支配する意図はないと判断できるものと考えられるとしている。また、シナジー効果も連携関係も見込まれない場合には、当該他の会社等を連結の対象としないこととしても、連結財務諸表に重要な影響を及ぼす見込がないため、その弊害も少ないものと考えられる。
さらに、本適用指針では、これらに加えて、以下も必要であるとしている。
⑤ 当該他の会社等の株式や出資を有している投資企業や金融機関は、実質的な営業活動を行っている会社等であること 投資先である他の会社等と連結グループとみなされるような運営がなされておらず、他の会社等の意思決定機関を支配する意図はないと判断できるような場合は、本来、出資者は必ずしも投資企業や金融機関に限られないが、出資者たる企業を制限しないと恣意的な適用のおそれがあること及び一般的には投資企業や金融機関と考えられることから、本適用指針では、監査委員会報告第60号と同様に、出資者を限定しているものとしている(43項)。
また、当該出資者は、営業取引として行っているものであるため、本適用指針では、実質的な営業活動を行っている会社等であることが必要であるとし、実質的な営業活動を行っているかどうかは、第三者からの資金拠出が多くなされているかどうか、複数の投資先へ幅広く投資を行っているかどうかなどの観点から判断され、法人格や物的施設の有無のみによって判断されるものではないと考えられるとしている(43項)。
⑥ 当該投資企業や金融機関が含まれる企業集団に関する連結財務諸表にあっては、当該企業集団内の他の連結会社(親会社及びその連結子会社)においても上記②から④の事項を満たすこと 監査委員会報告第60号による監査上の取扱いでは、企業集団内に投資企業や金融機関がある場合の考え方も明確ではないという指摘があったため、前述したように、本適用指針では、投資企業等が実質的な営業活動を行っている会社等であり、その企業自体が上記①から④の事項を満たしており、投資先を支配していないと判断されたときには、企業集団自体が投資企業等に該当する必要はないものとした。これは、投資企業等が投資先を支配していないと判断された結果を、当該投資企業等の親会社の連結財務諸表上、受け入れても恣意的な適用のおそれは少ないと考えられたことによる。この際、当該親会社の連結財務諸表上、自己のみならず企業集団として投資先を支配していないことが明らかであると認められる必要があるため、自己と投資先である他の会社等との関係は、当該親会社及びその連結子会社と当該他の会社等との関係においても同様に取り扱うことが適当であるものとした(44項)。すなわち、本適用指針では、投資先との関係において、上記②から④の事項を満たす必要があることとしたとしている。
本適用指針では、さらに、投資先である他の会社等がさらに別の他の会社等に投資を行っている場合など、いわゆる多層構造にある場合等の取扱いも示している(45項)。
a)垂直的な投資関係
最初の投資先である他の会社等及びその投資先である別の他の会社等について、子会社等の範囲の見直しに係る具体的な取扱い一3にいう他の会社等の意思決定機関を支配していることに該当する事項を満たしていても、本適用指針では、上記で示した事項を満たしていれば、当該他の会社等は、それぞれ子会社に該当しないことにあたるものと考えられるとされている(脚注3)。
b)並行的な投資関係
企業集団内の複数の連結会社(親会社及び連結子会社)が、投資先である他の会社等に対してそれぞれ投資を行っており、各連結会社単独では子会社等の範囲の見直しに係る具体的な取扱い一3にいう他の会社等の意思決定機関を支配していることに該当する要件を満たしていないが、企業集団としてはこれを満たしている場合でも、当該連結会社及び当該企業集団内の連結会社が上記の事項を満たしていれば、連結財務諸表上、子会社に該当しないことにあたるものと考えられるとされている。
(3)他の会社等の意思決定機関を支配していないことが明らかであると認められる場合の会計処理等 本適用指針46項及び50項では、上記(2)を満たすことにより、他の会社等の意思決定機関を支配していないことが明らかであると認められる場合、又は、子会社以外の他の会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないことが明らかであると認められる場合、当該他の会社等に対する投資は企業会計基準第10号「金融商品に関する会計基準」及びその具体的な指針に従って取り扱われることとなるとしている。
また、法令等により連結財務諸表に係る注記を行うこととなる場合(例えば、他の会社等の議決権の過半数を自己の計算において所有しているにもかかわらず、当該他の会社等を子会社としなかった場合の当該他の会社等の名称や子会社としなかった理由など)には、当該法令等に従って開示を行うこととなるとしている。具体的には、連結財務諸表規則13条2項3号及び3項4号による注記が行われることとなるものと考えられる。
3 利害関係者の判断を著しく誤らせるおそれがあるため連結の範囲に含めない子会社及び持分法を適用しない関連会社
(1)利害関係者の判断を著しく誤らせるおそれがあるため連結の範囲に含めない子会社 連結原則 第三 一 4(2)では、子会社のうち、連結することにより利害関係者の判断を著しく誤らせるおそれのある会社等は、連結の範囲に含めないものとしている。一般に、それは限定的であると考えられており、本適用指針では、新たに現行の実務等を考慮した具体例が示されている(19項及び47項)(脚注4)。
(2)利害関係者の判断を著しく誤らせるおそれがあるため持分法を適用しない関連会社 連結原則等では、利害関係者の判断を著しく誤らせるおそれのあるため持分法を適用しない関連会社を示していないが、連結財務諸表規則では、これを示しているため、本適用指針では、子会社の場合と同様に、持分法を適用することにより利害関係者の判断を著しく誤らせるおそれのある関連会社(非連結子会社を含む。)に対する投資については、持分法を適用しないことを明示し、現行の連結財務諸表規則における取扱いと整合させることとした(26項及び52項)。
4 海外の子会社等が連結財務諸表を作成している場合の連結子会社及び持分法適用関連会社の範囲 平成18年5月に公表された実務対応報告第18号「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」により、監査委員会報告第60号8の定めは適用されないこととなるため、本適用指針には、当該取扱いは示されていない。
5 適用時期等 公開草案では、平成20年4月1日以後開始する連結会計年度から適用するものとしていたが、適用にあたっては実務上の受入準備が必要であることを考慮して、本適用指針は、平成20年10月1日以後開始する連結会計年度から適用するものとしている(30項)。ただし、平成20年9月30日以前に開始する連結会計年度から適用することができるとされており、この場合には期首から適用することに留意する必要があるため、例えば、平成20年4月1日以後開始する連結会計年度から適用することもできるが、この場合にも、第1四半期の四半期連結財務諸表から適用することとなる(54項)。また、本適用指針の定めを適用することにより、これまでの会計処理と異なることとなる場合には、会計基準の変更に伴う会計方針の変更として取り扱うとされている(31項)。(にのみや・まさひろ)
脚注 1 ASBJのホームページ(http://www.asb.or.jp/html/documents/docs/VC-hanni/VC-hanni.pdf)参照。
2 このただし書きは、本適用指針の検討にあたり、具体的な状況を限定的に示しているものの、依然として弊害の懸念も指摘されていることから、確認のため、当該他の会社等の株主総会その他これに準ずる機関を支配する意図が明確である場合には、子会社にあたることを示すこととしたものである(42項)。
3 なお、最初の投資先である他の会社等が、投資企業や金融機関が行う「自己の事業を単に移転したり自己に代わって行うものとはみなせない」に該当しない場合には、上記③を満たしておらず、営業取引としてではなく自己と一体になった運営がなされる可能性が高いため、当該他の会社等を支配していないとは言えず子会社となることに留意する必要があるとされている(45項)。
ただし、子会社と判断された最初の投資先である他の会社等が(さらに、その投資先と合併等が予定されているなどのために)、支配が一時的であると認められる会社等であれば、連結の範囲に含めないものとなり(18項)、投資企業は(最初の投資先である他の会社等とその投資先との合併等により)、別の他の会社等である投資先の株式を有することが見込まれるため、第16項(4)を満たすものである限り、当該投資先について子会社に該当しないと判断されるものと考えられる。
4 もっとも、この具体例は、実務対応報告第20号「投資事業組合に対する支配力基準及び影響力基準の適用に関する実務上の取扱い」Q5のAで示されているものである。
企業会計基準適用指針第22号
「連結財務諸表における子会社及び関連会社の範囲の決定に関する適用指針」について
企業会計基準委員会 専門研究員 二宮正裕
Ⅰ.はじめに
企業会計基準委員会(ASBJ)では、平成20年5月13日に、企業会計基準適用指針第22号「連結財務諸表における子会社及び関連会社の範囲の決定に関する適用指針」(以下「本適用指針」という。)を公表している(脚注1)。本適用指針は、平成20年1月24日に公開草案を公表し、これに対して寄せられたコメントも参考に審議を行い、公表されたものである。本稿では、本適用指針の概要を紹介するが、文中の意見にわたる部分は筆者の私見であることをあらかじめお断りしておく。なお、特に断りがない限り、参照項は本適用指針の項番号を指す。
Ⅱ.本適用指針の位置付け
1 経 緯 平成9年6月に、企業会計審議会は「連結財務諸表制度の見直しに関する意見書」(以下「連結意見書」という。)を公表し、従来の個別情報を中心とする開示から連結情報を中心とする開示に転換を図ることを提言するとともに、連結情報充実の観点から改訂した「連結財務諸表原則」(以下「連結原則」という。)を公表した。さらに、同審議会は、平成10年10月に、子会社及び関連会社の範囲を整理した「連結財務諸表制度における子会社及び関連会社の範囲の見直しに係る具体的な取扱い」(以下「子会社等の範囲の見直しに係る具体的な取扱い」という。)を公表し、子会社及び関連会社の判定基準についての具体的な取扱いを示している。
連結原則及び子会社等の範囲の見直しに係る具体的な取扱いにおいては、議決権の所有割合以外の要素を加味した支配力基準を導入し、他の会社等の財務及び営業又は事業の方針を決定する機関を支配しているかどうかという観点から子会社の判定を行うこととし、また、影響力基準を導入し、他の会社等の財務及び営業又は事業の方針決定に対して重要な影響を与えることができるかどうかという観点から関連会社の判定を行うこととしている。
連結原則及び子会社等の範囲の見直しに係る具体的な取扱いを踏まえて、これまで子会社及び関連会社の範囲の決定に関しては、日本公認会計士協会監査委員会報告第60号「連結財務諸表における子会社及び関連会社の範囲の決定に関する監査上の取扱い」(以下「監査委員会報告第60号」という。)が実務上の指針として用いられてきた。
2 本適用指針の目的 ASBJでは、会社法の施行への対応や早期に取扱いの明確化が必要と考えられるものがあることから、監査委員会報告第60号のうち会計上の取扱いに関する部分について、基本的にその内容を引き継いだ上で、本適用指針を公表した。すなわち、本適用指針は、子会社及び関連会社の範囲について、連結原則及び子会社等の範囲の見直しに係る具体的な取扱いを適用する際の指針を定めることを目的としている。
Ⅲ.本適用指針の概要
以下では、監査委員会報告第60号の取扱いと異なる定めをした箇所を中心に示すこととする。
1 議決権の所有割合の算定(4項) 本適用指針では、監査委員会報告第60号の考え方を踏襲し、他の会社が子会社又は関連会社に該当するかどうかの判定において用いられる他の会社の議決権の所有割合は、原則として、次の算式によって算定するものとしている。
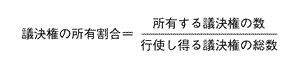
この際、「行使し得る議決権の総数」についても、従来と同様に、株主総会において行使し得るものと認められている総株主の議決権の数としている。また、会社法への対応により表現が改正されているが、これまでと同様に、以下の株式に係る議決権については、いずれも行使し得る議決権の総数には含まれないこととしている(5項)。
① 自己株式
② 完全無議決権株式(株主総会のすべての事項について議決権を行使することができない株式)
③ 会社法308条1項による相互保有株式
審議の過程では、一部の議案のみに議決権を有する議決権制限株式の取扱いについて、保有する議決権の内容により所有割合の算定に含めるかどうかを別途判断することも検討されたが、実質的な支配力又は影響力の判定は、議決権の所有割合のみで行うものはないことから、本適用指針では従来どおり、当該株式を所有割合の算定に含めることとしたとしている(36項)。
2 他の会社等の意思決定機関を支配していないこと等が明らかであると認められる場合の明確化(16項(4)及び24項)
(1)経 緯 連結原則第三 一 2及び子会社等の範囲の見直しに係る具体的な取扱い 一 3ただし書きでは、他の会社等の意思決定機関を支配していることに該当する要件を満たしていても、「財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて他の会社等の意思決定機関を支配していないことが明らかであると認められる場合」、当該他の会社等は子会社に該当しないものとしている。これに該当する場合の例として、従来、監査委員会報告第60号2(6)⑤及び⑥並びに3(4)①及び②で示されていた取扱いについては、その範囲や理由が明確ではないという指摘があった。特に、ベンチャーキャピタル条項などと呼ばれることもある監査委員会報告第60号2(6)⑥及び3(4)②は、監査上、留意すべき事項として示されていたこともあり、解釈が一様ではないという見方もあった。このため、本適用指針では、この考え方を整理し、該当する場合を具体的に示すこととした。
すなわち、本適用指針では、この取扱いは、ベンチャーキャピタルなどの投資企業が投資育成や事業再生を図りキャピタルゲイン獲得を目的とする営業取引として、又は銀行などの金融機関が債権の円滑な回収を目的とする営業取引として、当該他の会社の株式を所有し、当該営業取引のために議決権を行使していても、一定の場合には、当該他の会社の株主総会を支配する意図はないと判断することを想定していたものと解し、当該営業取引のために議決権を行使していても、投資先である他の会社等と連結グループとみなされるような運営がなされておらず、他の会社等の意思決定機関を支配する意図はないと判断できるような場合について、具体的に示すこととしたとしている(41項)。
(2)本適用指針での整理 本適用指針16項(4)では、ベンチャーキャピタルなどの投資企業(投資先の事業そのものによる成果ではなく、売却による成果を期待して投資価値の向上を目的とする業務を専ら行う会社等)が投資育成や事業再生を図りキャピタルゲイン獲得を目的とする営業取引として、又は銀行などの金融機関が債権の円滑な回収を目的とする営業取引として、他の会社等の株式や出資を有している場合には、子会社等の範囲の見直しに係る具体的な取扱い 一 3にいう他の会社等の意思決定機関を支配していることに該当する要件を満たしていても、次のすべてを満たすようなとき(ただし、当該他の会社等の株主総会その他これに準ずる機関を支配する意図が明確であると認められる場合を除く(脚注2)。)には、財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて他の会社等の意思決定機関を支配していないことが明らかであると認められ、子会社には該当しないことを示した。なお、本適用指針24項では関連会社の判定(他の会社等に重要な影響を与えることができないことが明らかであると認められる場合)についても、同様の定めを置いている。
① 売却等により他の会社等の議決権の大部分を所有しないこととなる合理的な計画があること まず、本適用指針では、この点について、関連会社の判定(24項)とともに整理しているため、「大部分を所有しないこと」については、売却等により、一義的には関連会社にあたらない程度にまで当該他の会社等の議決権を所有しないこととなる必要があるものと考えられるとしている。また、営業取引として他の会社等の株式や出資を有していることが前提とされていることから、当該営業取引の性質に見合う売却等の方法や時期その他の事項を考慮した計画の合理性が必要となるとしている。
② 当該他の会社等との間で、当該営業取引として行っている投資又は融資以外の取引がほとんどないこと ここでいう投資は、前述した営業取引として有している他の会社等の株式や出資を指し、融資は、金融機関が債権の円滑な回収を目的とする営業取引として他の会社等の株式や出資を有している場合における当該債権を指す。本適用指針では、そのような営業取引が独立して行われており、それ以外の取引がない場合には、他の会社等の意思決定機関を支配していることに該当する要件を満たすように投資企業が当該他の会社等の株式や出資を有していても、それはキャピタルゲイン獲得を目的とする営業取引としてのものにすぎず、また、金融機関が当該他の会社等の債権と株式や出資を有していても、それは当該債権の円滑な回収を目的とする営業取引としてのものにすぎないものと考えられるとしている。
③ 当該他の会社等は、自己の事業を単に移転したり自己に代わって行うものとはみなせないこと 公開草案では、「当該他の会社等の事業の種類は、自己の事業の種類と明らかに異なるものであること」としていたが、寄せられたコメント等を踏まえ、本適用指針では、新設分割や自己が主体となって他の会社等を設立したりすることにより、当該他の会社等において単に事業を移転したり自己に代わって行うものとみなせるような場合には、営業取引としてではなく、自己と一体になった運営がなされる可能性が高いため、この点を強調することが適切と考え修正したものとしている。
④ 当該他の会社等との間に、シナジー効果も連携関係も見込まれないこと 本適用指針では、他の要件ととともに、このような要件も満たす場合には、投資先である他の会社等とは別々に運営され、他の会社等の意思決定機関を支配する意図はないと判断できるものと考えられるとしている。また、シナジー効果も連携関係も見込まれない場合には、当該他の会社等を連結の対象としないこととしても、連結財務諸表に重要な影響を及ぼす見込がないため、その弊害も少ないものと考えられる。
さらに、本適用指針では、これらに加えて、以下も必要であるとしている。
⑤ 当該他の会社等の株式や出資を有している投資企業や金融機関は、実質的な営業活動を行っている会社等であること 投資先である他の会社等と連結グループとみなされるような運営がなされておらず、他の会社等の意思決定機関を支配する意図はないと判断できるような場合は、本来、出資者は必ずしも投資企業や金融機関に限られないが、出資者たる企業を制限しないと恣意的な適用のおそれがあること及び一般的には投資企業や金融機関と考えられることから、本適用指針では、監査委員会報告第60号と同様に、出資者を限定しているものとしている(43項)。
また、当該出資者は、営業取引として行っているものであるため、本適用指針では、実質的な営業活動を行っている会社等であることが必要であるとし、実質的な営業活動を行っているかどうかは、第三者からの資金拠出が多くなされているかどうか、複数の投資先へ幅広く投資を行っているかどうかなどの観点から判断され、法人格や物的施設の有無のみによって判断されるものではないと考えられるとしている(43項)。
⑥ 当該投資企業や金融機関が含まれる企業集団に関する連結財務諸表にあっては、当該企業集団内の他の連結会社(親会社及びその連結子会社)においても上記②から④の事項を満たすこと 監査委員会報告第60号による監査上の取扱いでは、企業集団内に投資企業や金融機関がある場合の考え方も明確ではないという指摘があったため、前述したように、本適用指針では、投資企業等が実質的な営業活動を行っている会社等であり、その企業自体が上記①から④の事項を満たしており、投資先を支配していないと判断されたときには、企業集団自体が投資企業等に該当する必要はないものとした。これは、投資企業等が投資先を支配していないと判断された結果を、当該投資企業等の親会社の連結財務諸表上、受け入れても恣意的な適用のおそれは少ないと考えられたことによる。この際、当該親会社の連結財務諸表上、自己のみならず企業集団として投資先を支配していないことが明らかであると認められる必要があるため、自己と投資先である他の会社等との関係は、当該親会社及びその連結子会社と当該他の会社等との関係においても同様に取り扱うことが適当であるものとした(44項)。すなわち、本適用指針では、投資先との関係において、上記②から④の事項を満たす必要があることとしたとしている。
本適用指針では、さらに、投資先である他の会社等がさらに別の他の会社等に投資を行っている場合など、いわゆる多層構造にある場合等の取扱いも示している(45項)。
a)垂直的な投資関係
最初の投資先である他の会社等及びその投資先である別の他の会社等について、子会社等の範囲の見直しに係る具体的な取扱い一3にいう他の会社等の意思決定機関を支配していることに該当する事項を満たしていても、本適用指針では、上記で示した事項を満たしていれば、当該他の会社等は、それぞれ子会社に該当しないことにあたるものと考えられるとされている(脚注3)。
b)並行的な投資関係
企業集団内の複数の連結会社(親会社及び連結子会社)が、投資先である他の会社等に対してそれぞれ投資を行っており、各連結会社単独では子会社等の範囲の見直しに係る具体的な取扱い一3にいう他の会社等の意思決定機関を支配していることに該当する要件を満たしていないが、企業集団としてはこれを満たしている場合でも、当該連結会社及び当該企業集団内の連結会社が上記の事項を満たしていれば、連結財務諸表上、子会社に該当しないことにあたるものと考えられるとされている。
(3)他の会社等の意思決定機関を支配していないことが明らかであると認められる場合の会計処理等 本適用指針46項及び50項では、上記(2)を満たすことにより、他の会社等の意思決定機関を支配していないことが明らかであると認められる場合、又は、子会社以外の他の会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないことが明らかであると認められる場合、当該他の会社等に対する投資は企業会計基準第10号「金融商品に関する会計基準」及びその具体的な指針に従って取り扱われることとなるとしている。
また、法令等により連結財務諸表に係る注記を行うこととなる場合(例えば、他の会社等の議決権の過半数を自己の計算において所有しているにもかかわらず、当該他の会社等を子会社としなかった場合の当該他の会社等の名称や子会社としなかった理由など)には、当該法令等に従って開示を行うこととなるとしている。具体的には、連結財務諸表規則13条2項3号及び3項4号による注記が行われることとなるものと考えられる。
3 利害関係者の判断を著しく誤らせるおそれがあるため連結の範囲に含めない子会社及び持分法を適用しない関連会社
(1)利害関係者の判断を著しく誤らせるおそれがあるため連結の範囲に含めない子会社 連結原則 第三 一 4(2)では、子会社のうち、連結することにより利害関係者の判断を著しく誤らせるおそれのある会社等は、連結の範囲に含めないものとしている。一般に、それは限定的であると考えられており、本適用指針では、新たに現行の実務等を考慮した具体例が示されている(19項及び47項)(脚注4)。
(2)利害関係者の判断を著しく誤らせるおそれがあるため持分法を適用しない関連会社 連結原則等では、利害関係者の判断を著しく誤らせるおそれのあるため持分法を適用しない関連会社を示していないが、連結財務諸表規則では、これを示しているため、本適用指針では、子会社の場合と同様に、持分法を適用することにより利害関係者の判断を著しく誤らせるおそれのある関連会社(非連結子会社を含む。)に対する投資については、持分法を適用しないことを明示し、現行の連結財務諸表規則における取扱いと整合させることとした(26項及び52項)。
4 海外の子会社等が連結財務諸表を作成している場合の連結子会社及び持分法適用関連会社の範囲 平成18年5月に公表された実務対応報告第18号「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」により、監査委員会報告第60号8の定めは適用されないこととなるため、本適用指針には、当該取扱いは示されていない。
5 適用時期等 公開草案では、平成20年4月1日以後開始する連結会計年度から適用するものとしていたが、適用にあたっては実務上の受入準備が必要であることを考慮して、本適用指針は、平成20年10月1日以後開始する連結会計年度から適用するものとしている(30項)。ただし、平成20年9月30日以前に開始する連結会計年度から適用することができるとされており、この場合には期首から適用することに留意する必要があるため、例えば、平成20年4月1日以後開始する連結会計年度から適用することもできるが、この場合にも、第1四半期の四半期連結財務諸表から適用することとなる(54項)。また、本適用指針の定めを適用することにより、これまでの会計処理と異なることとなる場合には、会計基準の変更に伴う会計方針の変更として取り扱うとされている(31項)。(にのみや・まさひろ)
脚注 1 ASBJのホームページ(http://www.asb.or.jp/html/documents/docs/VC-hanni/VC-hanni.pdf)参照。
2 このただし書きは、本適用指針の検討にあたり、具体的な状況を限定的に示しているものの、依然として弊害の懸念も指摘されていることから、確認のため、当該他の会社等の株主総会その他これに準ずる機関を支配する意図が明確である場合には、子会社にあたることを示すこととしたものである(42項)。
3 なお、最初の投資先である他の会社等が、投資企業や金融機関が行う「自己の事業を単に移転したり自己に代わって行うものとはみなせない」に該当しない場合には、上記③を満たしておらず、営業取引としてではなく自己と一体になった運営がなされる可能性が高いため、当該他の会社等を支配していないとは言えず子会社となることに留意する必要があるとされている(45項)。
ただし、子会社と判断された最初の投資先である他の会社等が(さらに、その投資先と合併等が予定されているなどのために)、支配が一時的であると認められる会社等であれば、連結の範囲に含めないものとなり(18項)、投資企業は(最初の投資先である他の会社等とその投資先との合併等により)、別の他の会社等である投資先の株式を有することが見込まれるため、第16項(4)を満たすものである限り、当該投資先について子会社に該当しないと判断されるものと考えられる。
4 もっとも、この具体例は、実務対応報告第20号「投資事業組合に対する支配力基準及び影響力基準の適用に関する実務上の取扱い」Q5のAで示されているものである。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -

Copyright (C) 2019
SHINNIPPON-HOKI PUBLISHING CO.,LTD.





















