解説記事2008年06月23日 【会計基準等解説】 「中小企業の会計に関する指針(平成20年度版)」について(2008年6月23日号・№263)
実務解説
「中小企業の会計に関する指針(平成20年度版)」について
企業会計基準委員会 専門研究員 中條恵美
Ⅰ はじめに
日本公認会計士協会、日本税理士会連合会、日本商工会議所、企業会計基準委員会が主体となって設置された「中小企業の会計指針作成検討委員会」は、平成20年5月2日に、「中小企業の会計に関する指針(平成20年度版)」(以下、「中小企業会計指針」という。)を公表した。
本稿では、本年度の改正のポイントを紹介する。なお、文中における意見に関する部分については私見であることをあらかじめ申し添える。
Ⅱ 改正のポイント
今回の改正では、平成20年4月1日以後開始する事業年度から原則適用される企業会計基準第9号「棚卸資産の評価に関する会計基準」(以下、「棚卸資産会計基準」という。)及び同13号「リース取引に関する会計基準」(以下、「リース会計基準」という。)に対応した会計処理の見直しが行われたほか、法人税法の改正及び金融商品取引法の施行等を踏まえた所要の修正が行われている。なお、これは平成20年1月に公表された公開草案に対して寄せられた意見を検討し、公表されたものであるが、公開草案から内容に係る修正は行われていない。
1.棚卸資産の評価基準 これまで、棚卸資産の評価については、原価法と低価法の選択適用が認められてきたが、棚卸資産会計基準の適用後は、通常の販売目的(販売するための製造目的を含む。)で保有する棚卸資産について、収益性が低下した場合には、当該正味売却価額をもって貸借対照表価額としなければならない。これに対応して、中小会計指針では、次のように改正が行われている(前頁「27.棚卸資産の評価基準」参照)。
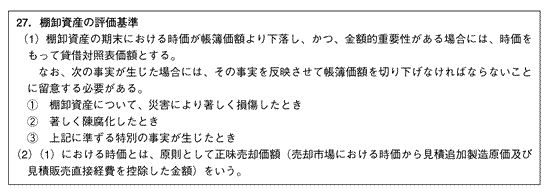
(1)通常の販売目的で保有する棚卸資産の会計処理 第27項(1)では、棚卸資産会計基準と同様に、棚卸資産の収益性が低下した場合には、帳簿価額を正味売却価額まで切り下げることが求められているが、中小企業の負担に配慮し、簿価切下額に金額的重要性がある場合を除き、これまでの会計処理(従来の原価法)も認められることとなる。
ただし、金額的重要性がある場合に該当しないため、従来の原価法と同様の会計処理を行う場合であっても、①から③の品質低下や陳腐化などに対応する簿価切下げは行わなければならないため、第27項(1)のなお書きが注意的に記載されている。
(2)開 示 簿価切下額の損益計算書上の表示に関しては、棚卸資産会計基準の内容とほぼ同様であるが、簿価切下額の注記又は内訳表示に関しては、表示することが望ましいとして中小企業に対する簡便的な取扱いが示されている(上記「29.損益計算書上の表示及び注記」参照)。
また、個別注記表において、棚卸資産会計基準の適用に伴い会計方針の記載例が改正されているが(記載例1参照)、下線のとおり、収益性の低下に基づく簿価切下げは、低価法として扱われていないことに留意が必要である。
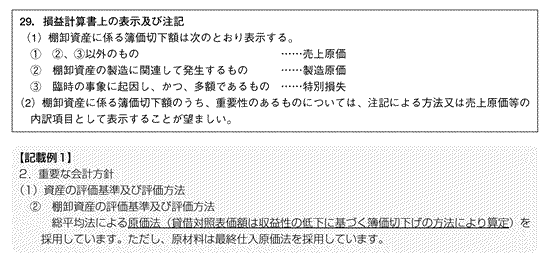
2.リース取引 リース会計基準の公表により、ファイナンス・リース取引のうち所有権移転外ファイナンス・リース取引(次頁「74-2.所有権移転外ファイナンス・リース取引」参照)について、これまで一定の注記を要件として認められていた通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理(以下「賃貸借処理」という。)が廃止され、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理(以下「売買処理」という。)に一本化された。この際、中小企業への負担に配慮し、従来の賃貸借処理を引き続き認めることを求める意見が多く寄せられたため、中小企業会計指針では、これを中心に検討が行われ、所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る借手側の取扱いについて改正が行われた(次頁「74-3.所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る借手の会計処理」「74-4.所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る借手の注記」参照)。
74-2.所有権移転外ファイナンス・リース取引 リース取引とは、特定の物件の所有者である貸手が、その物件の借手に対し、リース期間にわたりこれを使用収益する権利を与え、借手は、リース料を貸手に支払う取引をいう。
リース契約に基づくリース期間の中途において契約を解除することができないリース取引又はこれに準ずるリース取引で、借手が、契約に基づきリース物件からもたらされる経済的利益を実質的に享受することができ、かつ、リース物件の使用に伴って生じるコストを実質的に負担することとなるリース取引をファイナンス・リース取引といい、このうち、リース契約上の諸条件に照らしてリース物件の所有権が借手に移転すると認められるもの以外の取引を所有権移転外ファイナンス・リース取引という。
74-3.所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る借手の会計処理 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る借手は、通常の売買取引に係る方法に準じて会計処理を行う。ただし、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うことができる。
なお、法人税法上は、すべての所有権移転外リース取引は売買として取り扱われ、賃借人がリース料(賃借料)として経理をした場合においても、その金額は償却費として経理をしたものとされることに留意する。
74-4.所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る借手の注記 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る借手は、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行った場合には、未経過リース料を注記する。
ただし、重要性がないリース取引については、注記を省略することができる。
(1)所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る借手側の会計処理及び注記 第74-3項では、所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る借手について、リース会計基準と同様、売買処理を行うとしているが、ただし書き以下で、第74-4項の注記を要件に、従来どおり、賃貸借処理を行うことができるとしている。これは、前述のとおり、中小企業への過度の負担に配慮し、引き続き賃貸借処理を認める一方で、未経過リース料の注記を求めることで、オフバランスとなったリース資産及びリース債務に関する情報を補完し、中小企業の会計情報の利用者にとって有用な情報を提供しようとするものである。この場合の注記例については、個別注記表の記載例で下記のとおり示されている(記載例2参照)。
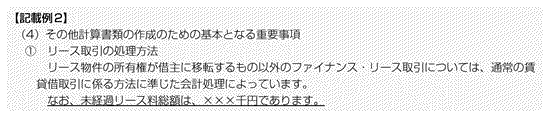
なお、注記を省略することができる重要性がないリース取引については、中小企業会計指針の公開草案に対して、「リース取引に関する会計基準の適用指針」第35項の少額リース資産及び短期のリース取引に関する簡便的な取扱いにおける、いわゆる300百万円基準のような具体的な金額基準を定めるべきであるという意見があった。検討の結果、中小企業会計指針の方針として、会計処理について具体的な金額基準を示すことなく、個々の企業の判断に委ねているため、リース取引についても金額基準は示されなかったが、これは、重要性に関してリース会計基準より厳しい取扱いを想定するものではなく、未経過リース料が中小企業にとって重要性があるかどうかを実態に応じて判断するという意味であると考えられる。
(2)(1)以外のリース取引に係る会計処理 中小企業会計指針でのリース取引に関する取扱いは、いずれも所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る借手側の会計処理であり、所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る貸手側の会計処理や、所有権移転ファイナンス・リース取引などの取扱いについては、特に示されていない。
中小企業会計指針では、中小企業が計算書類を作成するに当たり拠ることが望ましい会計処理を網羅的に示すことは、およそ不可能であるとして、特に中小企業において必要と考えられるものについて、重点的に言及している。したがって、中小企業会計指針に記載のない項目の会計処理に当たっては、上記の「本指針の作成に当たっての方針」に示された考え方に基づくことが求められている(第8項)。
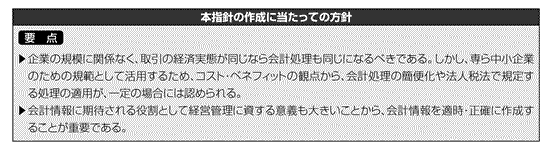
これにより、(1)以外のリース取引は、原則として、リース会計基準に従うこととなるが、コスト・ベネフィットの観点から、一定の場合には会計処理の簡便化が認められ得ると考えられる。
3.その他の改正 平成19年度の税制改正による税法上の減価償却制度の見直しに伴って、平成20年3月期に減価償却方法の変更を行う企業が想定されたことから、個別注記表の記載例において、会計方針の変更の記載例が追加されている(記載例3参照)。
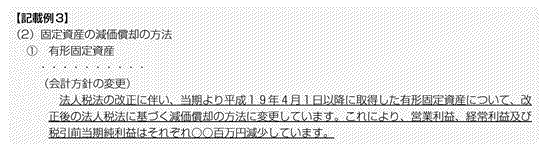
4.おわりに 中小企業会計指針は、その指針としての性格から、適用時期が示されていない。今年度の改正は、平成20年度からの会計基準等の適用に合わせて改正が行われているが、これらの会計基準は早期適用も認められていることから、法令等に適用時期について別途定めのある事項を除き、指針公表後に作成される計算書類から本指針によることができると考えられる。
(ちゅうじょう・えみ)
「中小企業の会計に関する指針(平成20年度版)」について
企業会計基準委員会 専門研究員 中條恵美
Ⅰ はじめに
日本公認会計士協会、日本税理士会連合会、日本商工会議所、企業会計基準委員会が主体となって設置された「中小企業の会計指針作成検討委員会」は、平成20年5月2日に、「中小企業の会計に関する指針(平成20年度版)」(以下、「中小企業会計指針」という。)を公表した。
本稿では、本年度の改正のポイントを紹介する。なお、文中における意見に関する部分については私見であることをあらかじめ申し添える。
Ⅱ 改正のポイント
今回の改正では、平成20年4月1日以後開始する事業年度から原則適用される企業会計基準第9号「棚卸資産の評価に関する会計基準」(以下、「棚卸資産会計基準」という。)及び同13号「リース取引に関する会計基準」(以下、「リース会計基準」という。)に対応した会計処理の見直しが行われたほか、法人税法の改正及び金融商品取引法の施行等を踏まえた所要の修正が行われている。なお、これは平成20年1月に公表された公開草案に対して寄せられた意見を検討し、公表されたものであるが、公開草案から内容に係る修正は行われていない。
1.棚卸資産の評価基準 これまで、棚卸資産の評価については、原価法と低価法の選択適用が認められてきたが、棚卸資産会計基準の適用後は、通常の販売目的(販売するための製造目的を含む。)で保有する棚卸資産について、収益性が低下した場合には、当該正味売却価額をもって貸借対照表価額としなければならない。これに対応して、中小会計指針では、次のように改正が行われている(前頁「27.棚卸資産の評価基準」参照)。
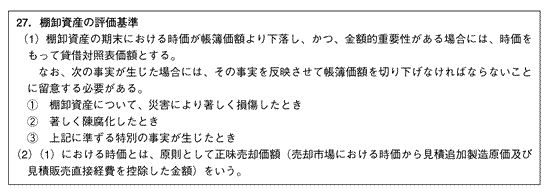
(1)通常の販売目的で保有する棚卸資産の会計処理 第27項(1)では、棚卸資産会計基準と同様に、棚卸資産の収益性が低下した場合には、帳簿価額を正味売却価額まで切り下げることが求められているが、中小企業の負担に配慮し、簿価切下額に金額的重要性がある場合を除き、これまでの会計処理(従来の原価法)も認められることとなる。
ただし、金額的重要性がある場合に該当しないため、従来の原価法と同様の会計処理を行う場合であっても、①から③の品質低下や陳腐化などに対応する簿価切下げは行わなければならないため、第27項(1)のなお書きが注意的に記載されている。
(2)開 示 簿価切下額の損益計算書上の表示に関しては、棚卸資産会計基準の内容とほぼ同様であるが、簿価切下額の注記又は内訳表示に関しては、表示することが望ましいとして中小企業に対する簡便的な取扱いが示されている(上記「29.損益計算書上の表示及び注記」参照)。
また、個別注記表において、棚卸資産会計基準の適用に伴い会計方針の記載例が改正されているが(記載例1参照)、下線のとおり、収益性の低下に基づく簿価切下げは、低価法として扱われていないことに留意が必要である。
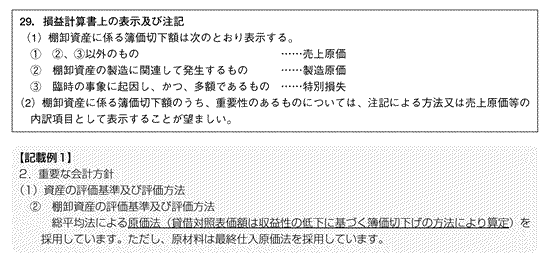
2.リース取引 リース会計基準の公表により、ファイナンス・リース取引のうち所有権移転外ファイナンス・リース取引(次頁「74-2.所有権移転外ファイナンス・リース取引」参照)について、これまで一定の注記を要件として認められていた通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理(以下「賃貸借処理」という。)が廃止され、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理(以下「売買処理」という。)に一本化された。この際、中小企業への負担に配慮し、従来の賃貸借処理を引き続き認めることを求める意見が多く寄せられたため、中小企業会計指針では、これを中心に検討が行われ、所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る借手側の取扱いについて改正が行われた(次頁「74-3.所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る借手の会計処理」「74-4.所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る借手の注記」参照)。
74-2.所有権移転外ファイナンス・リース取引 リース取引とは、特定の物件の所有者である貸手が、その物件の借手に対し、リース期間にわたりこれを使用収益する権利を与え、借手は、リース料を貸手に支払う取引をいう。
リース契約に基づくリース期間の中途において契約を解除することができないリース取引又はこれに準ずるリース取引で、借手が、契約に基づきリース物件からもたらされる経済的利益を実質的に享受することができ、かつ、リース物件の使用に伴って生じるコストを実質的に負担することとなるリース取引をファイナンス・リース取引といい、このうち、リース契約上の諸条件に照らしてリース物件の所有権が借手に移転すると認められるもの以外の取引を所有権移転外ファイナンス・リース取引という。
74-3.所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る借手の会計処理 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る借手は、通常の売買取引に係る方法に準じて会計処理を行う。ただし、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うことができる。
なお、法人税法上は、すべての所有権移転外リース取引は売買として取り扱われ、賃借人がリース料(賃借料)として経理をした場合においても、その金額は償却費として経理をしたものとされることに留意する。
74-4.所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る借手の注記 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る借手は、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行った場合には、未経過リース料を注記する。
ただし、重要性がないリース取引については、注記を省略することができる。
(1)所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る借手側の会計処理及び注記 第74-3項では、所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る借手について、リース会計基準と同様、売買処理を行うとしているが、ただし書き以下で、第74-4項の注記を要件に、従来どおり、賃貸借処理を行うことができるとしている。これは、前述のとおり、中小企業への過度の負担に配慮し、引き続き賃貸借処理を認める一方で、未経過リース料の注記を求めることで、オフバランスとなったリース資産及びリース債務に関する情報を補完し、中小企業の会計情報の利用者にとって有用な情報を提供しようとするものである。この場合の注記例については、個別注記表の記載例で下記のとおり示されている(記載例2参照)。
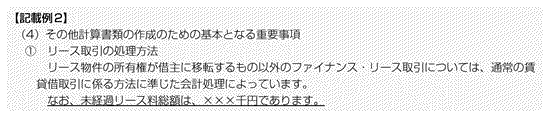
なお、注記を省略することができる重要性がないリース取引については、中小企業会計指針の公開草案に対して、「リース取引に関する会計基準の適用指針」第35項の少額リース資産及び短期のリース取引に関する簡便的な取扱いにおける、いわゆる300百万円基準のような具体的な金額基準を定めるべきであるという意見があった。検討の結果、中小企業会計指針の方針として、会計処理について具体的な金額基準を示すことなく、個々の企業の判断に委ねているため、リース取引についても金額基準は示されなかったが、これは、重要性に関してリース会計基準より厳しい取扱いを想定するものではなく、未経過リース料が中小企業にとって重要性があるかどうかを実態に応じて判断するという意味であると考えられる。
(2)(1)以外のリース取引に係る会計処理 中小企業会計指針でのリース取引に関する取扱いは、いずれも所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る借手側の会計処理であり、所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る貸手側の会計処理や、所有権移転ファイナンス・リース取引などの取扱いについては、特に示されていない。
中小企業会計指針では、中小企業が計算書類を作成するに当たり拠ることが望ましい会計処理を網羅的に示すことは、およそ不可能であるとして、特に中小企業において必要と考えられるものについて、重点的に言及している。したがって、中小企業会計指針に記載のない項目の会計処理に当たっては、上記の「本指針の作成に当たっての方針」に示された考え方に基づくことが求められている(第8項)。
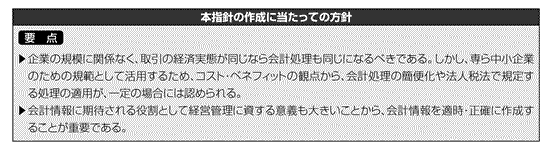
これにより、(1)以外のリース取引は、原則として、リース会計基準に従うこととなるが、コスト・ベネフィットの観点から、一定の場合には会計処理の簡便化が認められ得ると考えられる。
3.その他の改正 平成19年度の税制改正による税法上の減価償却制度の見直しに伴って、平成20年3月期に減価償却方法の変更を行う企業が想定されたことから、個別注記表の記載例において、会計方針の変更の記載例が追加されている(記載例3参照)。
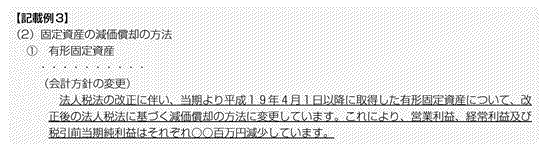
4.おわりに 中小企業会計指針は、その指針としての性格から、適用時期が示されていない。今年度の改正は、平成20年度からの会計基準等の適用に合わせて改正が行われているが、これらの会計基準は早期適用も認められていることから、法令等に適用時期について別途定めのある事項を除き、指針公表後に作成される計算書類から本指針によることができると考えられる。
(ちゅうじょう・えみ)
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -

Copyright (C) 2019
SHINNIPPON-HOKI PUBLISHING CO.,LTD.





















