解説記事2008年07月21日 【ニュース特集】 農商工等連携関連2法の概要と支援制度を読み解く(2008年7月21日号・№267)
平成20年7月21日施行!
農商工等連携関連2法の概要と支援制度を読み解く
「中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律」および「企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の一部を改正する法律」(いわゆる農商工等連携関連2法)が5月23日に公布された。前者は、農林水産業と商業・工業等との産業間連携を強化して地域経済を活性化するため、認定事業者等に対し、設備投資等に係る税制支援、事業資金の貸付け等に係る金融支援などを行うもので、平成20年7月21日から施行される。また、後者は、農林水産関連産業集積の活性化に関する取組みについて、追加的に税制等の支援措置を講じるもの。施行日は平成20年8月22日の予定となっている。今回の特集では、農商工等連携関連2法の概要と支援措置を紹介する。
農商工等連携促進法の概要 「中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律」(以下、農商工等連携促進法)は、中小企業者と農林漁業者とが連携し、それぞれの経営資源を有効活用し、新商品や新役務の開発等を行う場合に、金融支援や税制支援等を講じている。
具体的には、中小企業者および農林漁業者が共同して作成した農商工等連携事業に係る計画(農商工等連携事業計画)について、主務大臣の認定を受ける必要がある(図1参照)。
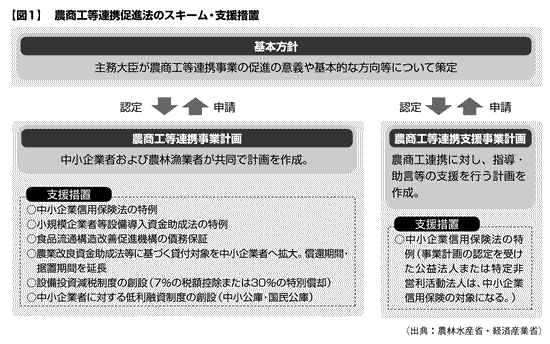
農商工等連携事業計画については、農商工等連携事業の目標、内容、同事業を実施するために必要な資金の額や調達方法を記載することが求められている。主務大臣の認定を受けた場合には、中小企業信用保険法の特例や課税の特例などを受けることができる(表参照)。
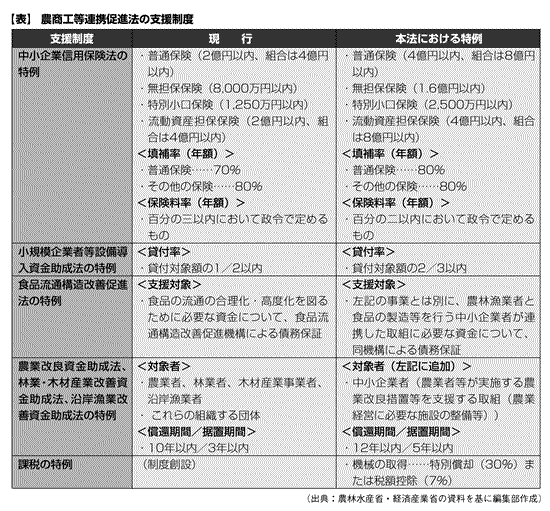 なお、課税の特例の対象に関しては、農商工等連携事業計画に記載された農商工等連携事業の内容に従って取得または製作をする機械および装置となり、取得価額の30%の特別償却と7%の税額控除との選択適用となる(措法42条の7第1項7号等)。
なお、課税の特例の対象に関しては、農商工等連携事業計画に記載された農商工等連携事業の内容に従って取得または製作をする機械および装置となり、取得価額の30%の特別償却と7%の税額控除との選択適用となる(措法42条の7第1項7号等)。
公益法人やNPO法人でも特例の対象に また、中小企業者だけでなく、一定の要件を満たす公益法人またはNPO法人も対象となる。公益法人またはNPO法人が農商工等連携に対して、交流会の開催、指導・助言等の支援を行う計画(農商工等連携支援事業計画)を作成し、主務大臣の認定を受けた場合には、公益法人やNPO法人であっても、中小企業信用保険法の特例の対象になる。
一定の要件を満たす公益法人とは、出資金額または拠出金額の2分の1以上が中小企業者によるものとされ、一般社団・財団法人法施行(平成20年12月1日)後は、一般社団法人の場合は、議決権の2分の1以上を中小企業者が有しているもの。また、一般財団法人の場合は、設立時に拠出された財産価額の2分の1以上が中小企業者により拠出されているものとされる。
NPO法人に関しては、表決権の2分の1以上を中小企業者が有しているものが要件となる。
農商工等連携促進法施行令等が公布 なお、7月18日には、「中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律施行令」のほか、同法の施行期日を平成20年7月21日と定める政令が公布されている。また、中小企業信用保険法の特例である農商工等連携事業関連保証に係る保険料率などが定められている。
企業立地促進法の一部改正の概要 「企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の一部を改正する法律」(以下、企業立地促進法)は、産業集積が地域経済の活性化に果す役割の重要性を鑑み、企業立地の促進等による地域における産業集積の形成や活性化のために地方公共団体が行う取組みを支援するもの。
企業立地等を重点的に促進すべき区域(集積区域)において企業立地または事業高度化を行うとする事業者については、「企業立地計画」または「事業高度化計画」を作成し、都道府県知事の承認を受ければ、課税の特例や金融面の支援措置を受けることができる(図2参照)。平成19年6月11日から施行されている。
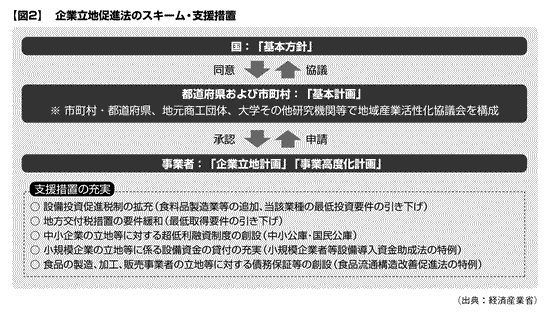
今回の一部改正では、農林水産関連産業集積の活性化に関する取組みを対象とし、支援措置を講じることにしたものだ。施行日は平成20年8月22日が予定されている。
税制措置の対象に農林漁業関連業種を追加 企業立地促進法に係る税制措置については、特別償却制度(機械装置15%、建物等8%)が手当てされているが、この対象業種として、農林漁業関連業種を追加するとともに、投資規模要件を大幅に引き下げている(措法44条の2第1項等)。
農林漁業関連業種については、食料品製造業、飲料・たばこ・飼料製造業、木材・木製品製造業、家具・装備品製造業、パルプ・紙・紙加工業品製造業、プラスチック製品製造業、ゴム製品製造業、各種商品卸売業、飲食料品卸売業、木材・竹材卸売業、農業用機械器具卸売業、農業用機械器具卸売業、家具・建具卸売業となっている。
機械装置は4,000万円以上 また、投資規模要件については、従来の農林漁業関連業種以外の業種(企業立地促進法19条1項)は、機械装置3億円以上(単価1,000万円以上)、建物等5億円以上とされている。
しかし、農林漁業関係業種に関しては、機械装置4,000万円以上(単価500万円以上)、建物等5,000万円以上に大幅に引き下げられている(図3参照)。
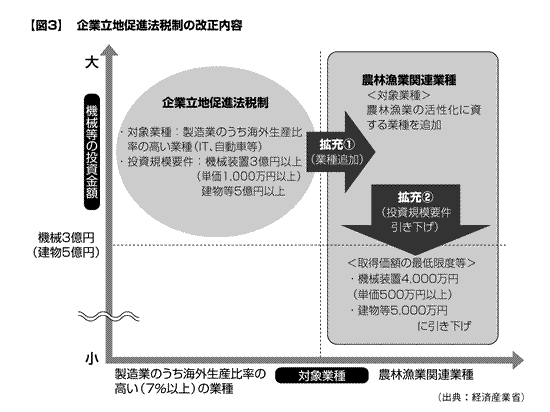
金融支援も措置 そのほか、金融支援として、①中小企業の企業立地等に対する超低利の融資制度の創設(中小企業が承認企業立地計画または承認事業高度化計画に従って行う企業立地または事業高度化のために必要な設備資金に対して、政府系金融機関(中小公庫・国民公庫)による超低利の融資制度を創設する)、②小規模企業の企業立地等に係る設備資金の貸付の充実(小規模企業者が承認企業立地計画または承認事業高度化計画に従った設備の設置等に対し、都道府県貸与機関が行う設備資金貸付について、貸付割合の上限を1/2以内から2/3以内へ引き上げる措置を講じる)、③食品の製造、加工、販売事業者の立地等に対する債務保証等の創設(食品の製造、加工、販売の事業者が承認企業立地計画または承認事業高度化計画に従って行う企業立地または事業高度化のために必要な資金の借入等に対し、(財)食品流通構造改善促進機構が債務保証等を行うことができる措置を講じる)を手当てしている。
農商工等連携関連2法の概要と支援制度を読み解く
「中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律」および「企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の一部を改正する法律」(いわゆる農商工等連携関連2法)が5月23日に公布された。前者は、農林水産業と商業・工業等との産業間連携を強化して地域経済を活性化するため、認定事業者等に対し、設備投資等に係る税制支援、事業資金の貸付け等に係る金融支援などを行うもので、平成20年7月21日から施行される。また、後者は、農林水産関連産業集積の活性化に関する取組みについて、追加的に税制等の支援措置を講じるもの。施行日は平成20年8月22日の予定となっている。今回の特集では、農商工等連携関連2法の概要と支援措置を紹介する。
農商工等連携促進法の概要 「中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律」(以下、農商工等連携促進法)は、中小企業者と農林漁業者とが連携し、それぞれの経営資源を有効活用し、新商品や新役務の開発等を行う場合に、金融支援や税制支援等を講じている。
具体的には、中小企業者および農林漁業者が共同して作成した農商工等連携事業に係る計画(農商工等連携事業計画)について、主務大臣の認定を受ける必要がある(図1参照)。
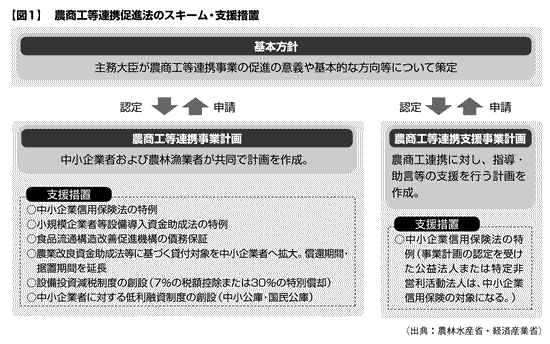
農商工等連携事業計画については、農商工等連携事業の目標、内容、同事業を実施するために必要な資金の額や調達方法を記載することが求められている。主務大臣の認定を受けた場合には、中小企業信用保険法の特例や課税の特例などを受けることができる(表参照)。
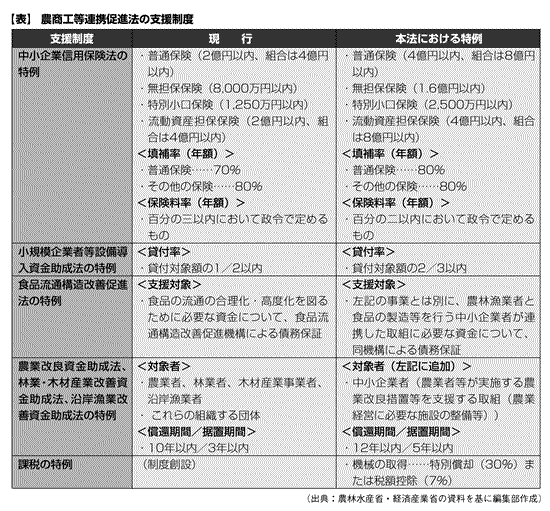 なお、課税の特例の対象に関しては、農商工等連携事業計画に記載された農商工等連携事業の内容に従って取得または製作をする機械および装置となり、取得価額の30%の特別償却と7%の税額控除との選択適用となる(措法42条の7第1項7号等)。
なお、課税の特例の対象に関しては、農商工等連携事業計画に記載された農商工等連携事業の内容に従って取得または製作をする機械および装置となり、取得価額の30%の特別償却と7%の税額控除との選択適用となる(措法42条の7第1項7号等)。公益法人やNPO法人でも特例の対象に また、中小企業者だけでなく、一定の要件を満たす公益法人またはNPO法人も対象となる。公益法人またはNPO法人が農商工等連携に対して、交流会の開催、指導・助言等の支援を行う計画(農商工等連携支援事業計画)を作成し、主務大臣の認定を受けた場合には、公益法人やNPO法人であっても、中小企業信用保険法の特例の対象になる。
一定の要件を満たす公益法人とは、出資金額または拠出金額の2分の1以上が中小企業者によるものとされ、一般社団・財団法人法施行(平成20年12月1日)後は、一般社団法人の場合は、議決権の2分の1以上を中小企業者が有しているもの。また、一般財団法人の場合は、設立時に拠出された財産価額の2分の1以上が中小企業者により拠出されているものとされる。
NPO法人に関しては、表決権の2分の1以上を中小企業者が有しているものが要件となる。
農商工等連携促進法施行令等が公布 なお、7月18日には、「中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律施行令」のほか、同法の施行期日を平成20年7月21日と定める政令が公布されている。また、中小企業信用保険法の特例である農商工等連携事業関連保証に係る保険料率などが定められている。
企業立地促進法の一部改正の概要 「企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の一部を改正する法律」(以下、企業立地促進法)は、産業集積が地域経済の活性化に果す役割の重要性を鑑み、企業立地の促進等による地域における産業集積の形成や活性化のために地方公共団体が行う取組みを支援するもの。
企業立地等を重点的に促進すべき区域(集積区域)において企業立地または事業高度化を行うとする事業者については、「企業立地計画」または「事業高度化計画」を作成し、都道府県知事の承認を受ければ、課税の特例や金融面の支援措置を受けることができる(図2参照)。平成19年6月11日から施行されている。
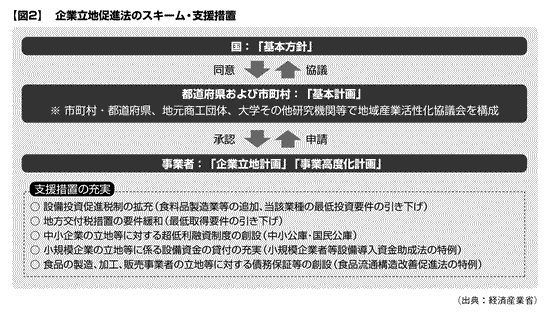
今回の一部改正では、農林水産関連産業集積の活性化に関する取組みを対象とし、支援措置を講じることにしたものだ。施行日は平成20年8月22日が予定されている。
税制措置の対象に農林漁業関連業種を追加 企業立地促進法に係る税制措置については、特別償却制度(機械装置15%、建物等8%)が手当てされているが、この対象業種として、農林漁業関連業種を追加するとともに、投資規模要件を大幅に引き下げている(措法44条の2第1項等)。
農林漁業関連業種については、食料品製造業、飲料・たばこ・飼料製造業、木材・木製品製造業、家具・装備品製造業、パルプ・紙・紙加工業品製造業、プラスチック製品製造業、ゴム製品製造業、各種商品卸売業、飲食料品卸売業、木材・竹材卸売業、農業用機械器具卸売業、農業用機械器具卸売業、家具・建具卸売業となっている。
機械装置は4,000万円以上 また、投資規模要件については、従来の農林漁業関連業種以外の業種(企業立地促進法19条1項)は、機械装置3億円以上(単価1,000万円以上)、建物等5億円以上とされている。
しかし、農林漁業関係業種に関しては、機械装置4,000万円以上(単価500万円以上)、建物等5,000万円以上に大幅に引き下げられている(図3参照)。
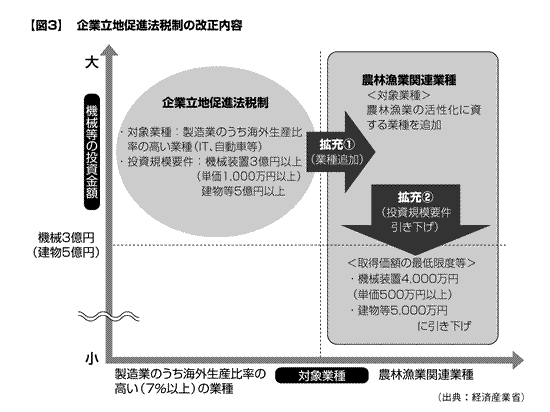
金融支援も措置 そのほか、金融支援として、①中小企業の企業立地等に対する超低利の融資制度の創設(中小企業が承認企業立地計画または承認事業高度化計画に従って行う企業立地または事業高度化のために必要な設備資金に対して、政府系金融機関(中小公庫・国民公庫)による超低利の融資制度を創設する)、②小規模企業の企業立地等に係る設備資金の貸付の充実(小規模企業者が承認企業立地計画または承認事業高度化計画に従った設備の設置等に対し、都道府県貸与機関が行う設備資金貸付について、貸付割合の上限を1/2以内から2/3以内へ引き上げる措置を講じる)、③食品の製造、加工、販売事業者の立地等に対する債務保証等の創設(食品の製造、加工、販売の事業者が承認企業立地計画または承認事業高度化計画に従って行う企業立地または事業高度化のために必要な資金の借入等に対し、(財)食品流通構造改善促進機構が債務保証等を行うことができる措置を講じる)を手当てしている。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -

Copyright (C) 2019
SHINNIPPON-HOKI PUBLISHING CO.,LTD.




















