解説記事2008年08月04日 【ニュース特集】 無償取引等への寄附金課税や「役務提供」の範囲などが焦点(2008年8月4日号・№269)
「移転価格事務運営要領」(事務運営指針)改正案の論点
無償取引等への寄附金課税や「役務提供」の範囲などが焦点
国税庁は現在、「移転価格事務運営要領」(事務運営指針)の見直しを進めている。同要領の改正案は6月5日~7月4日までパブリックコメントに付されていたが、その内容に対しては、企業側からの注文も多い。
たとえば、国内法人と海外の子法人の間で行われる無償取引等への「寄附金課税」だ。これについて、企業側は「相互協議を経ることなく課税を行えるようにするもの」として警戒感を強めている。また、企業側がこれまで「株主活動」と考えていたものが「役務提供」とされ、移転価格税制の対象に取り込まれることなども懸念している。
本特集では、「移転価格事務運営要領」(事務運営指針)の改正案の論点を整理する。
1 移転価格事務運営要領見直しで、「役務提供」の範囲が広く? 移転価格税制の対象となる「役務提供」があったかどうかは、国際課税においてしばしば問題となるところだが、今回の移転価格事務運営要領の改正案では、親会社から子会社に対する役務提供があったかどうかの判断を、「親会社の子会社に対する行為が当該子会社にとって経済的又は商業的価値を有するものかどうか」により行うこととし、具体的な基準として下記の2つを掲げている(事務運営要領改正案2-9(1))。
ただ、OECDガイドライン7.6によると、親会社から子会社等への役務提供が価値を持つかどうかの判断は、「独立企業がその活動に対して進んで対価を支払う」かどうかが分かれ道とされている。
そこで企業側も、このOECDガイドライン7.6にのっとり、「子会社が自らその活動を対価を支払って受けるかどうか行うか」により、移転価格税制の対象となる「役務提供」に該当するかどうかを判断するべきだと主張している。
たとえば、親会社が自らの財務政策に基づいて、子会社に対し資金運用に関する役務提供を行うケースがあるが、このような役務提供は、子会社が自ら望んだものとはいえないことから、親会社から子会社に対する役務提供には該当しないとしている。
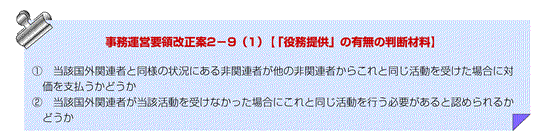
2 グロ-バルな広告宣伝費は「役務提供」に当たるか 事務運営要領改正案2-9(1)では、「役務提供」に該当するかどうかの判断の対象になり得るものとして、次頁のようなものを挙げているが、企業側には、「広告宣伝」のうちグローバルな広告宣伝費については、役務提供の対象とすべきではないとの意見がある。これは、グローバルな広告宣伝は、親会社自身のブランド向上のために行われるものであるためだ。
一方、子会社の独自製品や、子会社がある国の国内市場向けに独自に行う広告宣伝を親会社が行った場合には「役務提供」と判断され得ることについては異論はないようだ。
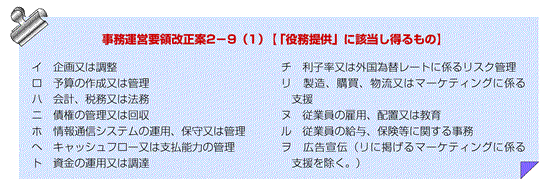
3「株主活動」or「役務提供」? 「役務提供」に関するもう1つの論点が、「株主活動」との区分だ。
移転価格税制においては、親会社から海外の子会社に対する何らかの行動が、「株主活動」に当たるのか「役務提供」に当たるのか、その区分が難しいケースが少なくない。「株主活動」に該当すれば、移転価格税制の適用対象外となるが、親会社が「株主」として子会社に何か注文をつけたつもりでも、それが課税当局から「役務提供」とみられることが少なくない。
この点、移転価格事務運営要領の改正案では、親会社の子会社に対する株主活動の具体的例として、下記の2つを挙げている。
これに対し企業側からは、親会社の子会社に対する株主活動の範囲は広いことから、改正案のような限定的な例示は「範囲が狭すぎる」との意見が出ている。少なくとも、稟議手続(審査、決定手続や、子会社に対するその結果の通知など)やコーポレートガバナンス活動(株主が投資した会社の活動を監視し、法令等の遵守を可能とする株主支配)については、子会社に対する親会社の投資の保全活動であることとし、移転価格事務運営要領のなかでこれらが「株主活動」である旨を明示するべきだとの声があがっている。
また、改正案では、親会社が子会社に対して行う「経営管理」について、「親会社の子会社等に対する投資の保全を目的とする活動が、当該子会社等の経営管理に係るものである場合には、当該活動は役務の提供に該当することに留意する」との規定が盛り込まれている(同指針2-9(4)なお書き)。これに対し企業側は、このように「経営管理=役務提供」と決め付けてしまうと、「株主行動」として行われる“経営状況の管理”まで移転価格税制の対象となりかねない点に強い懸念を持っている。このため、移転価格税制の対象は、本来は子会社が行うべき経営管理を親会社が代行するようなケースに限定するよう求める声がある。
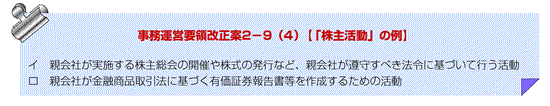
4 寄附金課税で、相互協議が不要に? 国内の親法人が海外の子法人に対し無償取引等を行った場合には、移転価格税制が適用されることが考えられる。ただ、移転価格税制を適用する場合には、相互協議による国際的な二重課税の調整が必要になる。
一方、今回示されている「移転価格事務運営要領」(事務運営指針)の一部改正案では、国内の親法人と海外の子法人間での無償取引等を租税特別措置法66条の4第3項の「寄附金課税」の対象とするとの規定が新設されている(事務運営要領改正案2-19)。
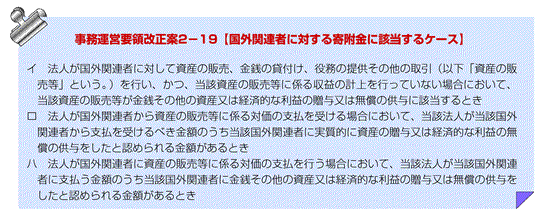
具体的には、上記のような取引を寄附金課税の対象にするとしている。
これに対し企業側は、寄附金課税の対象になると、移転価格税制の枠組みから外れて相互協議の対象外となり、二重課税状態を排除する途が閉ざされてしまうことに強い懸念を示している。
さらに、租税特別措置法66条の4第1項と第3項との適用関係が明確でないとして、その明確化を求める声があがっている。具体的には、税特別措置法66条の4第3項の規定は租税特別措置法66条の4第1項の規定が適用できない場合に限って適用されるべきであり、できる限り租税特別措置法66条の4第1項の適用を検討すべきとし、改正案2-19については、「課税当局が相互協議を経ることなく課税を行えるようにするもの」と指摘する声もあがっている。
5 事前確認申請期限の前倒しで、事実関係が未確定のまま申請? 「移転価格事務運営要領」(事務運営指針)の一部改正案5-2では、事前確認申請期限を、現行の確認対象事業年度のうち「最初の事業年度に係る確定申告書の提出期限」から「最初の事業年度開始の日の前日」へと前倒しすることが提示されている(図参照)。
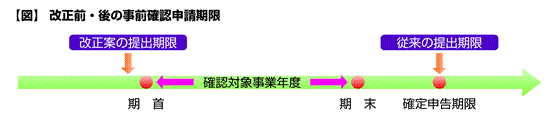
ただ、確認対象事業年度前に申請が求められることになると、確認対象事業年度において生じる事実関係が未確定の状態のまま申請を行うことになりかねない。このため、企業側は、結局後になって申請内容の大幅な修正を行わざるをえなくなることを懸念、改正に反対の姿勢を示している。
また、アメリカやイギリスなどの諸外国においては、現行の日本の規定同様、「確認対象事業年度の申告期限」を事前確認申請期限としているケースが多い。このため、仮に改正案どおりに日本における申請期限が「最初の事業年度開始の日の前日」とされた場合には、これらの諸外国との間で、事前確認申請の時期がずれることになり、諸外国から修正を求められたり、確認申請内容について関係国では確認が得られないといった事態も懸念されている。
無償取引等への寄附金課税や「役務提供」の範囲などが焦点
国税庁は現在、「移転価格事務運営要領」(事務運営指針)の見直しを進めている。同要領の改正案は6月5日~7月4日までパブリックコメントに付されていたが、その内容に対しては、企業側からの注文も多い。
たとえば、国内法人と海外の子法人の間で行われる無償取引等への「寄附金課税」だ。これについて、企業側は「相互協議を経ることなく課税を行えるようにするもの」として警戒感を強めている。また、企業側がこれまで「株主活動」と考えていたものが「役務提供」とされ、移転価格税制の対象に取り込まれることなども懸念している。
本特集では、「移転価格事務運営要領」(事務運営指針)の改正案の論点を整理する。
1 移転価格事務運営要領見直しで、「役務提供」の範囲が広く? 移転価格税制の対象となる「役務提供」があったかどうかは、国際課税においてしばしば問題となるところだが、今回の移転価格事務運営要領の改正案では、親会社から子会社に対する役務提供があったかどうかの判断を、「親会社の子会社に対する行為が当該子会社にとって経済的又は商業的価値を有するものかどうか」により行うこととし、具体的な基準として下記の2つを掲げている(事務運営要領改正案2-9(1))。
ただ、OECDガイドライン7.6によると、親会社から子会社等への役務提供が価値を持つかどうかの判断は、「独立企業がその活動に対して進んで対価を支払う」かどうかが分かれ道とされている。
そこで企業側も、このOECDガイドライン7.6にのっとり、「子会社が自らその活動を対価を支払って受けるかどうか行うか」により、移転価格税制の対象となる「役務提供」に該当するかどうかを判断するべきだと主張している。
たとえば、親会社が自らの財務政策に基づいて、子会社に対し資金運用に関する役務提供を行うケースがあるが、このような役務提供は、子会社が自ら望んだものとはいえないことから、親会社から子会社に対する役務提供には該当しないとしている。
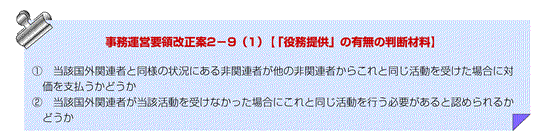
2 グロ-バルな広告宣伝費は「役務提供」に当たるか 事務運営要領改正案2-9(1)では、「役務提供」に該当するかどうかの判断の対象になり得るものとして、次頁のようなものを挙げているが、企業側には、「広告宣伝」のうちグローバルな広告宣伝費については、役務提供の対象とすべきではないとの意見がある。これは、グローバルな広告宣伝は、親会社自身のブランド向上のために行われるものであるためだ。
一方、子会社の独自製品や、子会社がある国の国内市場向けに独自に行う広告宣伝を親会社が行った場合には「役務提供」と判断され得ることについては異論はないようだ。
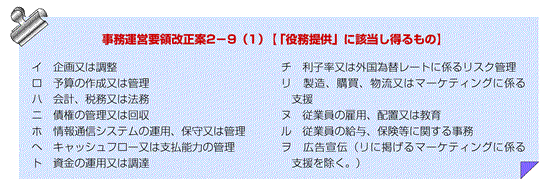
3「株主活動」or「役務提供」? 「役務提供」に関するもう1つの論点が、「株主活動」との区分だ。
移転価格税制においては、親会社から海外の子会社に対する何らかの行動が、「株主活動」に当たるのか「役務提供」に当たるのか、その区分が難しいケースが少なくない。「株主活動」に該当すれば、移転価格税制の適用対象外となるが、親会社が「株主」として子会社に何か注文をつけたつもりでも、それが課税当局から「役務提供」とみられることが少なくない。
この点、移転価格事務運営要領の改正案では、親会社の子会社に対する株主活動の具体的例として、下記の2つを挙げている。
これに対し企業側からは、親会社の子会社に対する株主活動の範囲は広いことから、改正案のような限定的な例示は「範囲が狭すぎる」との意見が出ている。少なくとも、稟議手続(審査、決定手続や、子会社に対するその結果の通知など)やコーポレートガバナンス活動(株主が投資した会社の活動を監視し、法令等の遵守を可能とする株主支配)については、子会社に対する親会社の投資の保全活動であることとし、移転価格事務運営要領のなかでこれらが「株主活動」である旨を明示するべきだとの声があがっている。
また、改正案では、親会社が子会社に対して行う「経営管理」について、「親会社の子会社等に対する投資の保全を目的とする活動が、当該子会社等の経営管理に係るものである場合には、当該活動は役務の提供に該当することに留意する」との規定が盛り込まれている(同指針2-9(4)なお書き)。これに対し企業側は、このように「経営管理=役務提供」と決め付けてしまうと、「株主行動」として行われる“経営状況の管理”まで移転価格税制の対象となりかねない点に強い懸念を持っている。このため、移転価格税制の対象は、本来は子会社が行うべき経営管理を親会社が代行するようなケースに限定するよう求める声がある。
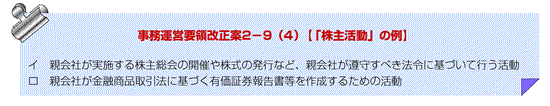
4 寄附金課税で、相互協議が不要に? 国内の親法人が海外の子法人に対し無償取引等を行った場合には、移転価格税制が適用されることが考えられる。ただ、移転価格税制を適用する場合には、相互協議による国際的な二重課税の調整が必要になる。
一方、今回示されている「移転価格事務運営要領」(事務運営指針)の一部改正案では、国内の親法人と海外の子法人間での無償取引等を租税特別措置法66条の4第3項の「寄附金課税」の対象とするとの規定が新設されている(事務運営要領改正案2-19)。
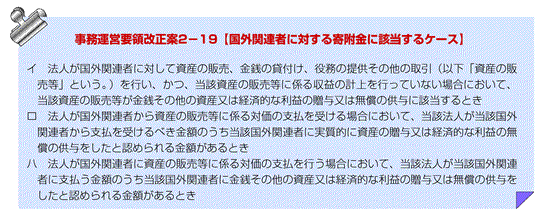
具体的には、上記のような取引を寄附金課税の対象にするとしている。
これに対し企業側は、寄附金課税の対象になると、移転価格税制の枠組みから外れて相互協議の対象外となり、二重課税状態を排除する途が閉ざされてしまうことに強い懸念を示している。
さらに、租税特別措置法66条の4第1項と第3項との適用関係が明確でないとして、その明確化を求める声があがっている。具体的には、税特別措置法66条の4第3項の規定は租税特別措置法66条の4第1項の規定が適用できない場合に限って適用されるべきであり、できる限り租税特別措置法66条の4第1項の適用を検討すべきとし、改正案2-19については、「課税当局が相互協議を経ることなく課税を行えるようにするもの」と指摘する声もあがっている。
5 事前確認申請期限の前倒しで、事実関係が未確定のまま申請? 「移転価格事務運営要領」(事務運営指針)の一部改正案5-2では、事前確認申請期限を、現行の確認対象事業年度のうち「最初の事業年度に係る確定申告書の提出期限」から「最初の事業年度開始の日の前日」へと前倒しすることが提示されている(図参照)。
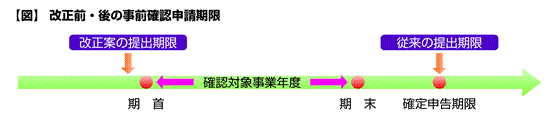
ただ、確認対象事業年度前に申請が求められることになると、確認対象事業年度において生じる事実関係が未確定の状態のまま申請を行うことになりかねない。このため、企業側は、結局後になって申請内容の大幅な修正を行わざるをえなくなることを懸念、改正に反対の姿勢を示している。
また、アメリカやイギリスなどの諸外国においては、現行の日本の規定同様、「確認対象事業年度の申告期限」を事前確認申請期限としているケースが多い。このため、仮に改正案どおりに日本における申請期限が「最初の事業年度開始の日の前日」とされた場合には、これらの諸外国との間で、事前確認申請の時期がずれることになり、諸外国から修正を求められたり、確認申請内容について関係国では確認が得られないといった事態も懸念されている。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -

Copyright (C) 2019
SHINNIPPON-HOKI PUBLISHING CO.,LTD.




















