解説記事2008年10月20日 【巻頭特集】 インサイダー取引の未然防止と東証COMLECの取組み(2008年10月20日号・№279)
巻頭特集
「未然防止」のための留意点を改めて確認する
インサイダー取引の未然防止と東証COMLECの取組み
東京証券取引所自主規制法人 売買審査部総務・企画・取引相談グループ調査役 吉松和彦
インサイダー取引は、これを防止しようとする法改正が過去度々行われてきているものの、依然として跡を絶たない。証券取引法の平成16年改正(平成16年法律第97号)で課徴金制度が導入され、事案の公表とともに会社間の契約当事者によるもの、報道機関職員によるもの、監査法人の公認会計士によるものなど様々な類型の違反行為が浮彫りにされるなか(本誌267号8頁参照)、違反の認識が希薄なケースも散見される。課徴金制度についてさらなる法改正(268号13頁等参照)が実現し、施行を控えた今、本稿では、近時開催された「上場会社コンプライアンス・フォーラム(東京)」での識者・市場関係者の指摘等を踏まえ、東証COMLECの取組みと「未然防止」の観点を中心とする対応をまとめていただいた。 (編集部)
Ⅰ はじめに
東京証券取引所自主規制法人(以下「当法人」という)は、昨年秋に金融商品取引法が施行され、自主規制業務に関する組織体制の法的枠組みが整備されたことに伴い、これまでの自主規制業務を市場運営からより独立したものとすべく、昨年11月に新たに自主規制法人として業務を開始した。
また、これまでの自主規制業務をさらに実効性あるものとするため、「自主規制機能強化プログラム(R+:アールプラス)」を策定し、そこに掲げる「市場の公正性・信頼性の一層の向上」の基本方針のもと、各種施策に取り組んでいる。
このような施策の1つとして、当法人は本年6月、上場会社や取引参加者を始めとする市場関係者のコンプライアンス支援をより一層強化するため、専門機関として「東証Rコンプライアンス研修センター(東証COMLEC:コムレック)」を設置し、活動を開始したところである。
本稿では、最近、市場関係者においてインサイダー取引に対する関心が高まっていることを踏まえ、当法人のインサイダー取引に対する取組みおよび東証COMLECを通じた新たな取組みなどを紹介するとともに、先般開催された「上場会社コンプライアンス・フォーラム(東京)」等において指摘のあった上場会社におけるインサイダー取引の未然防止上の留意点を紹介することとする。
なお、文中意見にわたる部分は筆者の個人的見解であることをお断りしておく。
Ⅱ 東証自主規制法人の市場監視業務と東証COMLECを通じた新たな取組み
1 東証自主規制法人の市場監視業務 当法人は、金融商品取引法で定められた自主規制業務の1つとして売買審査と呼ばれる市場監視業務を行っており、具体的には、市場監視部門である売買審査部が日々の売買動向を監視し、インサイダー取引や相場操縦等の不公正取引の有無を調査している。
この売買審査は、相場動向や上場会社の公表情報を基に初動的な分析を行う「調査」と、その結果を踏まえ、委託者の属性や重要事実の決定経緯に関する情報等、さらに詳細な情報を加えて分析を行う「審査」の2段階で実施され、審査結果についてはすべて証券取引等監視委員会に報告される。
実際の調査・審査の状況は図表1のとおりであるが、特徴的なのはその件数の多さである。当法人では、東証市場の全上場株式等の売買データを毎日売買審査システムにかけて相場操縦のおそれのある行為を抽出するとともに、インサイダー取引規制上の重要事実が公表された銘柄についてもすべて調査の対象にするなど、網羅的な市場監視に取り組んでいる(証券取引等監視委員会等の体制強化、同委員会による審査等件数について、図表2・図表3および後述Ⅳ1参照)。
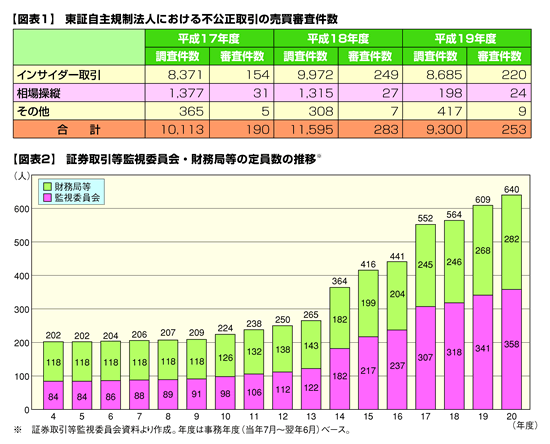
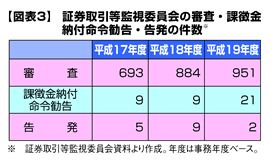
2 東証COMLECを通じた新たな取組み 証券市場の健全性を確保するためには、先の売買審査を通じた事後的な法令違反行為の摘発はもとより、そもそも法令違反行為を起こさせないための未然防止が重要である。当法人は、このような法令違反の未然防止についても自主規制機関に期待される機能の1つであると認識しており、この分野の活動に従前にも増して積極的に取り組んでいる。その中心となるのが東証COMLECを通じた教育・啓発活動である。
東証COMLECの活動は大きく3つの柱からなる(図表4参照)。まず1つめに、各種コンプライアンス関連セミナー等の開催および社内研修への講師派遣がある。当法人では、常日頃からインサイダー取引を始めとするコンプライアンス関連の問合せ・相談を数多く受けており、そのような経験・知識を有する専門のスタッフを東証COMLECの講師として提供している。
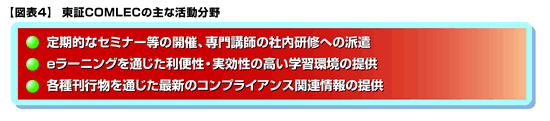
次に、eラーニングを用いた研修環境の提供である。eラーニングは社内研修手段の1つとして多くの企業・団体において利用されており、インサイダー取引規制などの全役職員に必要な研修ツールとしても大変有用である。このため、当法人では、各社の研修システムへのコンテンツ提供や受講企業の代わりにデータ処理を行うASPサービス(脚注1)等を通じて利便性・実効性の高い学習環境を提供している。
そして最後の柱は、各種刊行物の提供である。インサイダー取引に関連するものとしては『こんぷらくんのインサイダー取引規制Q&A』が各社の研修資料としても活用されており、これらの刊行物に法令改正の内容や注意すべきポイント等をタイムリーに盛り込むことで、より多くの方が常に最新の情報を知ることができるようにしている。
当法人としては、従前から行っている市場監視を引き続き行うとともに、これら東証COMLECによる教育・啓発活動を通じて、法令違反行為の摘発とその未然防止の両面から市場の健全性の確保に努めていく考えである。
より多くの市場関係者のコンプライアンス支援を進めていく観点から利用対象を制限していないため、東証上場会社・取引参加者以外のすべての市場関係者においても有効に活用いただければ幸いである。
Ⅲ 上場会社におけるインサイダー取引の未然防止上の留意点
東証COMLECの教育・啓発活動の一環として、去る9月10日、東京都内(渋谷公会堂)で上場会社・取引参加者等の役職員を対象とした「上場会社コンプライアンス・フォーラム(東京)」が開催された。
本フォーラムでは、昨今のインサイダー取引事件の増加を踏まえ、上場会社としてインサイダー取引にどのように立ち向かうべきか、どのようなポイントに注意すべきかなどを、証券取引等監視委員会や企業法務に詳しい弁護士の講演と有識者によるパネルディスカッションで紹介した。今後、大阪(11月7日)、札幌(12月11日)、名古屋(1月26日)等でも同様のフォーラムを開催する予定である(脚注2)。
以下では、先般のフォーラムなどを通じて、当法人が上場会社等の市場関係者に指摘したインサイダー取引の未然防止上の留意点を紹介することとする。
1 上場会社におけるインサイダー取引の未然防止の必要性 そもそも、なぜ上場会社が役職員個人のインサイダー取引を防止する必要があるのか。この点、個人の犯罪をどの程度組織的な管理で防止できるかについては議論のあるところであるが、当法人としては、次のような認識のもと、上場会社に役職員のインサイダー取引の未然防止の徹底を求めているところである。
まず、経営上のリスク管理の観点である。自社の役職員からインサイダー取引が発生した場合、それが会社名とともに報道されることにより、会社の信用やブランドイメージが傷つき、経営に重大な影響を受ける、あるいは株価にまで影響が及ぶ可能性が考えられる。このため、上場会社においては、自社の経営上のリスク管理の一環として、インサイダー取引の未然防止に努めることが求められる。
また、証券市場の一員としての観点にも留意いただきたい。上場会社は証券市場における投資対象そのものであるとともに、会社情報の出し手として証券市場を支える重要な責務を担っている。このため、より一段高いレベルで市場の健全性の確保に関わることが期待される。
インサイダー取引は、個人の犯罪ではあるものの、それが社会に与える影響は非常に大きい。一個人、一企業の問題ではなく、証券市場全体の信頼性の低下にもつながる問題である。上場会社においては、企業の経営上の問題として、そしてわが国資本市場経済を支える重要な担い手としてこの問題に積極的に取り組むことが求められる。
2 経営トップ自らによる関与の必要性 インサイダー取引の未然防止を徹底するためには、経営トップ自らがこの問題の深刻さ・重要さをよく認識し、全社的な取組みとして対応する必要があることにも留意いただきたい。
特に、この問題を考える場合には、会社としての情報管理や開示のあり方といった極めて重要な政策判断が求められることや、場合によっては人事管理政策までを含めた対応が必要となることから、経営トップ自らが全社的な経営課題の1つとして推進していくことが必要である。
3 適切な法令認識の必要性 最近の課徴金事案では、上場会社が自己株式取得を行う際に、意図せずインサイダー取引規制に抵触した「うっかり型」のインサイダー取引が多くみられる。その多くは、単純な法令の認識不足による場合が多いが、インサイダー取引は形式犯であり、悪意がなかった、法令を知らなかったでは済まされないことから、十分な注意が必要である。
なお、このような法令の認識不足の典型的なケースとしては、重要事実の認識時期が適切でなかった、軽微基準のない重要事実をそれと認1識していなかったなどの理由によるものが多い。
また、自己株式取得の際だけでなく、役職員個人の株式売買の際に事前届出等を受ける担当部署が正しく「信号機」として判断できるようにするためにも、上場会社においては、改めて法令の適切な理解に努めるとともに、社内の確認体制の整備が必要である。
当法人では、全国の上場会社を対象としたインサイダー取引の未然防止に関するアンケート調査報告書(脚注3)のなかで、各社の取組状況とともに、規制について誤解の多いポイントや体制整備上の留意点等を紹介している。上場会社においては、ぜひご一読いただき、今後の体制整備の参考としていただきたい。
4 インサイダー取引防止規程の整備 役職員がインサイダー取引を起こさぬようにするためには、日々の業務のなかで具体的に何に注意し、何を行う(行わない)べきかを解りやすく明示しておくことが重要である。このため、上場会社においては、役職員が重要な情報に触れた際に、それをどのように扱うべきか、自社株売買等を行う際にはどのような確認や手続が必要かなどを社内規程として定めておくことが求められる。これがいわゆるインサイダー取引防止規程(内部者取引管理規程)であり、体制整備の基礎となるものである。
そして、規程制定後も、それが形骸化することのないよう、継続的に役職員に周知徹底するとともに、内容の更新や運用の改善に努めることが求められる。
なお、前述のアンケート調査によると、規程整備済みの上場会社が全体の89.8%に達する結果となっているが、規程整備済みの上場会社においても「インサイダー取引を禁止する」として概念のみを記載し、具体的な手続を何も定めていない会社が少なくないことから、未対応の上場会社においては、ぜひ今後の課題として検討いただきたい。
5 情報管理・売買管理体制の整備 インサイダー取引防止規程の制定とともに、それを適切に運用していくための体制整備が求められる。特に情報管理と売買管理の両面からの体制整備が求められるが、その際には決して無理のない仕組みとなるよう、注意が必要である。
なお、具体的な情報管理の方法としては、情報の報告・伝達手段、ルート、範囲の明確化など、不必要な情報の拡散を防ぐ観点と、積極的な情報へのアクセスに対する防御の観点の両面から検討することが大切である。
売買管理の方法については、前出のアンケート調査から7割を超える上場会社が役職員の自社株売買等の前に確認を要する「許可型」の手続を採用しているとの結果となっており、また、一定期間の売買禁止や役員による売買の全面禁止など外形的に厳格な売買管理体制が整備される傾向が高いようであるが、実際の売買管理には限界があることや、売買の過剰な制限は役職員個人の財産権を侵害することにもつながることから、上場会社においては、過度に保守的になり過ぎぬよう、リスクに応じた制度設計が必要である。
6 役職員に対する継続的な教育・研修 構築した社内体制を適切に機能させるためには、それを担う役職員1人ひとりの高いコンプライアンス意識と法令等に対する正しい知識や理解が必要である。
上場会社においては、役職員に対して継続的に法令・社内規程等の内容を周知徹底するとともに、インサイダー取引を組織の一員として積極的に防止しようとする前向きな意識の醸成に努めることが求められる。
また、重要事実を含む情報には、決算に関する情報だけでなく業務の現場で発生するものもあることから、財務部門などの一部の役職員に対してのみ研修を行うのではなく、すべての役職員に対して適切な研修を行うことが重要である。
この点、現実問題として各企業の研修担当者は、役職員が各地に点在している、工場や販売等の業務が停止できない、研修用のインフラ(パソコン、インターネット等)が十分にないなど様々な制約のなかで研修方法や頻度を考えなくてはならず、各社とも非常に苦労していることと思われるが、東証COMLECでは、こうした際の研修方法の相談についても各社の状況に応じた提案を行っていることから、気軽に相談いただければ幸いである(脚注4)。
Ⅳ インサイダー取引に対する証券界の取組み
これまで当法人の取組みおよび上場会社における未然防止上の留意点等について述べてきたが、証券界では、このほかにも多くの取組みがなされていることから、ここでその概要を紹介することとしたい。
1 証券取引等監視委員会の動向 わが国の市場監視体制は、証券取引等監視委員会、取引所・証券業協会からなる自主規制機関、市場仲介者である証券会社の3者により構成されている。
このうち、最近インサイダー取引が数多く摘発されるようになった要因として、証券取引等監視委員会の体制が大幅に強化されてきたことが挙げられる。前掲・図表3のとおり最近10年間で急速に人員体制が強化されており、また、課徴金制度の導入により機動的な法執行体制が整ったことも最近の摘発件数の増加に大きく寄与している(前掲・図表4参照)。
また、証券取引等監視委員会は、これまでの流通市場の監視に加え、企業の不適切なファイナンス等の発行市場までを含めた包括的な市場監視を行う方針であり、近く予定されている課徴金制度の強化および検査・調査の範囲・対象の拡大とともに、着実に監視体制を強化させている。
2 新たなインフラの整備 一方、証券会社等の市場仲介者を通じた取組みも行われている。具体的には、平成18年3月に金融庁に設置された「証券会社の市場仲介機能等に関する懇談会」の報告を踏まえ、日本証券業協会、証券会社、取引所により具体的な方策が検討され、大きく2つの市場監視に関するインフラが整備されることとなっている。
その1つが「内部者情報システム」である。これは、上場会社役職員によるインサイダー取引を未然防止するため、売買の前に委託者の会社関係者への該当の有無を確認する「内部者登録制度」の実効性を高めるために導入されるもので、上場会社が適切に自社役職員の情報を登録することにより、証券会社における事前チェック機能が高まり、自社の役職員によるインサイダー取引をより確実に防止できるというものである。
そして、もう1つのインフラが、当局、自主規制機関、証券会社を守秘性の高いネットワークで結び、安全で迅速な市場監視を可能とする「コンプライアンスWAN」であり、それぞれ来年春の稼動に向けて準備が進められているところである。
証券界では、このほかにも各種の検討が進められており、これまで以上に実効性の高い市場監視体制が構築されることが期待されているところである。
Ⅴ おわりに
最近の証券市場における投資家層の拡大や上場会社の自己株式取得機会の増加などに伴い、上場会社がインサイダー取引のリスクを強く意識する場面がこれまで以上に増えており、既に多くの上場会社が未然防止策を講じ始めている。
ただし、インサイダー取引は、決して上場会社だけの問題ではなく、証券市場を利用するすべての関係者に関わる問題であり、弁護士・会計士等の証券市場のゲートキーパーや上場会社と資本・取引関係のある未上場会社のほか、社会的信用を強く求められている組織・団体等においても、それぞれがリスクに応じて前向きに取り組んでいくことが必要である。
当法人としても、市場監視や東証COMLECの活動を通じて、これらすべての市場関係者のコンプライアンスを支援すべく積極的に取り組んでいく考えである。
上場会社を含むすべての市場関係者においては、インサイダー取引防止の趣旨をご理解いただき、引き続き、未然防止に向けて取り組んでいただければ幸いである。
(よしまつ・かずひこ)
脚注
1 ASP(Application Service Provider)サービスとは、利用者の代わりにアプリケーション・プログラムや処理情報をデータセンターで管理し、これをインターネット等を通じて利用者に提供するサービスのことである。
2 上場会社コンプライアンス・フォーラムの情報については、東証自主規制法人のホームページ http://www.tse.or.jp/sr/comlec/seminar.html に東京開催分の発言概要・資料等を掲載予定であり、http://www.tse.or.jp/sr/comlec/comp_forum.html に大阪開催の開催概要を掲載している(登録締切りは11月5日)。
3 「全国上場会社内部者取引管理アンケート調査報告書(平成19年5月公表)」の詳細は、東証自主規制法人ホームページ http://www.tse.or.jp/sr/unfair/houkoku.html を参照されたい。
4 東証COMLECの相談窓口は、電話:03-3665-2769、メール:COMLEC@tse.or.jpとなっている。
「未然防止」のための留意点を改めて確認する
インサイダー取引の未然防止と東証COMLECの取組み
東京証券取引所自主規制法人 売買審査部総務・企画・取引相談グループ調査役 吉松和彦
インサイダー取引は、これを防止しようとする法改正が過去度々行われてきているものの、依然として跡を絶たない。証券取引法の平成16年改正(平成16年法律第97号)で課徴金制度が導入され、事案の公表とともに会社間の契約当事者によるもの、報道機関職員によるもの、監査法人の公認会計士によるものなど様々な類型の違反行為が浮彫りにされるなか(本誌267号8頁参照)、違反の認識が希薄なケースも散見される。課徴金制度についてさらなる法改正(268号13頁等参照)が実現し、施行を控えた今、本稿では、近時開催された「上場会社コンプライアンス・フォーラム(東京)」での識者・市場関係者の指摘等を踏まえ、東証COMLECの取組みと「未然防止」の観点を中心とする対応をまとめていただいた。 (編集部)
Ⅰ はじめに
東京証券取引所自主規制法人(以下「当法人」という)は、昨年秋に金融商品取引法が施行され、自主規制業務に関する組織体制の法的枠組みが整備されたことに伴い、これまでの自主規制業務を市場運営からより独立したものとすべく、昨年11月に新たに自主規制法人として業務を開始した。
また、これまでの自主規制業務をさらに実効性あるものとするため、「自主規制機能強化プログラム(R+:アールプラス)」を策定し、そこに掲げる「市場の公正性・信頼性の一層の向上」の基本方針のもと、各種施策に取り組んでいる。
このような施策の1つとして、当法人は本年6月、上場会社や取引参加者を始めとする市場関係者のコンプライアンス支援をより一層強化するため、専門機関として「東証Rコンプライアンス研修センター(東証COMLEC:コムレック)」を設置し、活動を開始したところである。
本稿では、最近、市場関係者においてインサイダー取引に対する関心が高まっていることを踏まえ、当法人のインサイダー取引に対する取組みおよび東証COMLECを通じた新たな取組みなどを紹介するとともに、先般開催された「上場会社コンプライアンス・フォーラム(東京)」等において指摘のあった上場会社におけるインサイダー取引の未然防止上の留意点を紹介することとする。
なお、文中意見にわたる部分は筆者の個人的見解であることをお断りしておく。
Ⅱ 東証自主規制法人の市場監視業務と東証COMLECを通じた新たな取組み
1 東証自主規制法人の市場監視業務 当法人は、金融商品取引法で定められた自主規制業務の1つとして売買審査と呼ばれる市場監視業務を行っており、具体的には、市場監視部門である売買審査部が日々の売買動向を監視し、インサイダー取引や相場操縦等の不公正取引の有無を調査している。
この売買審査は、相場動向や上場会社の公表情報を基に初動的な分析を行う「調査」と、その結果を踏まえ、委託者の属性や重要事実の決定経緯に関する情報等、さらに詳細な情報を加えて分析を行う「審査」の2段階で実施され、審査結果についてはすべて証券取引等監視委員会に報告される。
実際の調査・審査の状況は図表1のとおりであるが、特徴的なのはその件数の多さである。当法人では、東証市場の全上場株式等の売買データを毎日売買審査システムにかけて相場操縦のおそれのある行為を抽出するとともに、インサイダー取引規制上の重要事実が公表された銘柄についてもすべて調査の対象にするなど、網羅的な市場監視に取り組んでいる(証券取引等監視委員会等の体制強化、同委員会による審査等件数について、図表2・図表3および後述Ⅳ1参照)。
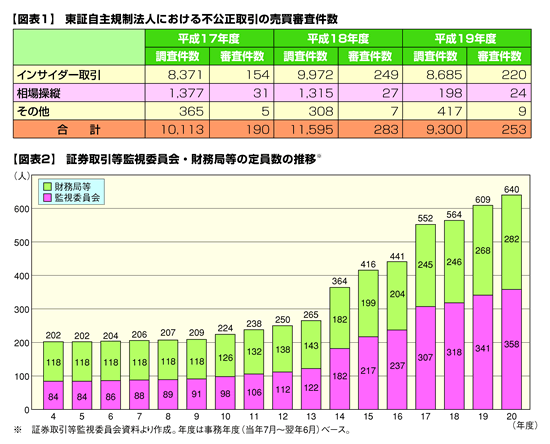
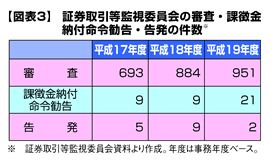
2 東証COMLECを通じた新たな取組み 証券市場の健全性を確保するためには、先の売買審査を通じた事後的な法令違反行為の摘発はもとより、そもそも法令違反行為を起こさせないための未然防止が重要である。当法人は、このような法令違反の未然防止についても自主規制機関に期待される機能の1つであると認識しており、この分野の活動に従前にも増して積極的に取り組んでいる。その中心となるのが東証COMLECを通じた教育・啓発活動である。
東証COMLECの活動は大きく3つの柱からなる(図表4参照)。まず1つめに、各種コンプライアンス関連セミナー等の開催および社内研修への講師派遣がある。当法人では、常日頃からインサイダー取引を始めとするコンプライアンス関連の問合せ・相談を数多く受けており、そのような経験・知識を有する専門のスタッフを東証COMLECの講師として提供している。
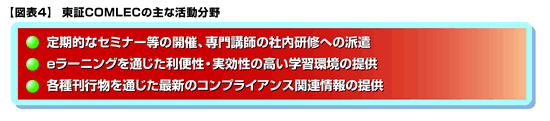
次に、eラーニングを用いた研修環境の提供である。eラーニングは社内研修手段の1つとして多くの企業・団体において利用されており、インサイダー取引規制などの全役職員に必要な研修ツールとしても大変有用である。このため、当法人では、各社の研修システムへのコンテンツ提供や受講企業の代わりにデータ処理を行うASPサービス(脚注1)等を通じて利便性・実効性の高い学習環境を提供している。
そして最後の柱は、各種刊行物の提供である。インサイダー取引に関連するものとしては『こんぷらくんのインサイダー取引規制Q&A』が各社の研修資料としても活用されており、これらの刊行物に法令改正の内容や注意すべきポイント等をタイムリーに盛り込むことで、より多くの方が常に最新の情報を知ることができるようにしている。
当法人としては、従前から行っている市場監視を引き続き行うとともに、これら東証COMLECによる教育・啓発活動を通じて、法令違反行為の摘発とその未然防止の両面から市場の健全性の確保に努めていく考えである。
より多くの市場関係者のコンプライアンス支援を進めていく観点から利用対象を制限していないため、東証上場会社・取引参加者以外のすべての市場関係者においても有効に活用いただければ幸いである。
Ⅲ 上場会社におけるインサイダー取引の未然防止上の留意点
東証COMLECの教育・啓発活動の一環として、去る9月10日、東京都内(渋谷公会堂)で上場会社・取引参加者等の役職員を対象とした「上場会社コンプライアンス・フォーラム(東京)」が開催された。
本フォーラムでは、昨今のインサイダー取引事件の増加を踏まえ、上場会社としてインサイダー取引にどのように立ち向かうべきか、どのようなポイントに注意すべきかなどを、証券取引等監視委員会や企業法務に詳しい弁護士の講演と有識者によるパネルディスカッションで紹介した。今後、大阪(11月7日)、札幌(12月11日)、名古屋(1月26日)等でも同様のフォーラムを開催する予定である(脚注2)。
以下では、先般のフォーラムなどを通じて、当法人が上場会社等の市場関係者に指摘したインサイダー取引の未然防止上の留意点を紹介することとする。
1 上場会社におけるインサイダー取引の未然防止の必要性 そもそも、なぜ上場会社が役職員個人のインサイダー取引を防止する必要があるのか。この点、個人の犯罪をどの程度組織的な管理で防止できるかについては議論のあるところであるが、当法人としては、次のような認識のもと、上場会社に役職員のインサイダー取引の未然防止の徹底を求めているところである。
まず、経営上のリスク管理の観点である。自社の役職員からインサイダー取引が発生した場合、それが会社名とともに報道されることにより、会社の信用やブランドイメージが傷つき、経営に重大な影響を受ける、あるいは株価にまで影響が及ぶ可能性が考えられる。このため、上場会社においては、自社の経営上のリスク管理の一環として、インサイダー取引の未然防止に努めることが求められる。
また、証券市場の一員としての観点にも留意いただきたい。上場会社は証券市場における投資対象そのものであるとともに、会社情報の出し手として証券市場を支える重要な責務を担っている。このため、より一段高いレベルで市場の健全性の確保に関わることが期待される。
インサイダー取引は、個人の犯罪ではあるものの、それが社会に与える影響は非常に大きい。一個人、一企業の問題ではなく、証券市場全体の信頼性の低下にもつながる問題である。上場会社においては、企業の経営上の問題として、そしてわが国資本市場経済を支える重要な担い手としてこの問題に積極的に取り組むことが求められる。
2 経営トップ自らによる関与の必要性 インサイダー取引の未然防止を徹底するためには、経営トップ自らがこの問題の深刻さ・重要さをよく認識し、全社的な取組みとして対応する必要があることにも留意いただきたい。
特に、この問題を考える場合には、会社としての情報管理や開示のあり方といった極めて重要な政策判断が求められることや、場合によっては人事管理政策までを含めた対応が必要となることから、経営トップ自らが全社的な経営課題の1つとして推進していくことが必要である。
3 適切な法令認識の必要性 最近の課徴金事案では、上場会社が自己株式取得を行う際に、意図せずインサイダー取引規制に抵触した「うっかり型」のインサイダー取引が多くみられる。その多くは、単純な法令の認識不足による場合が多いが、インサイダー取引は形式犯であり、悪意がなかった、法令を知らなかったでは済まされないことから、十分な注意が必要である。
なお、このような法令の認識不足の典型的なケースとしては、重要事実の認識時期が適切でなかった、軽微基準のない重要事実をそれと認1識していなかったなどの理由によるものが多い。
また、自己株式取得の際だけでなく、役職員個人の株式売買の際に事前届出等を受ける担当部署が正しく「信号機」として判断できるようにするためにも、上場会社においては、改めて法令の適切な理解に努めるとともに、社内の確認体制の整備が必要である。
当法人では、全国の上場会社を対象としたインサイダー取引の未然防止に関するアンケート調査報告書(脚注3)のなかで、各社の取組状況とともに、規制について誤解の多いポイントや体制整備上の留意点等を紹介している。上場会社においては、ぜひご一読いただき、今後の体制整備の参考としていただきたい。
4 インサイダー取引防止規程の整備 役職員がインサイダー取引を起こさぬようにするためには、日々の業務のなかで具体的に何に注意し、何を行う(行わない)べきかを解りやすく明示しておくことが重要である。このため、上場会社においては、役職員が重要な情報に触れた際に、それをどのように扱うべきか、自社株売買等を行う際にはどのような確認や手続が必要かなどを社内規程として定めておくことが求められる。これがいわゆるインサイダー取引防止規程(内部者取引管理規程)であり、体制整備の基礎となるものである。
そして、規程制定後も、それが形骸化することのないよう、継続的に役職員に周知徹底するとともに、内容の更新や運用の改善に努めることが求められる。
なお、前述のアンケート調査によると、規程整備済みの上場会社が全体の89.8%に達する結果となっているが、規程整備済みの上場会社においても「インサイダー取引を禁止する」として概念のみを記載し、具体的な手続を何も定めていない会社が少なくないことから、未対応の上場会社においては、ぜひ今後の課題として検討いただきたい。
5 情報管理・売買管理体制の整備 インサイダー取引防止規程の制定とともに、それを適切に運用していくための体制整備が求められる。特に情報管理と売買管理の両面からの体制整備が求められるが、その際には決して無理のない仕組みとなるよう、注意が必要である。
なお、具体的な情報管理の方法としては、情報の報告・伝達手段、ルート、範囲の明確化など、不必要な情報の拡散を防ぐ観点と、積極的な情報へのアクセスに対する防御の観点の両面から検討することが大切である。
売買管理の方法については、前出のアンケート調査から7割を超える上場会社が役職員の自社株売買等の前に確認を要する「許可型」の手続を採用しているとの結果となっており、また、一定期間の売買禁止や役員による売買の全面禁止など外形的に厳格な売買管理体制が整備される傾向が高いようであるが、実際の売買管理には限界があることや、売買の過剰な制限は役職員個人の財産権を侵害することにもつながることから、上場会社においては、過度に保守的になり過ぎぬよう、リスクに応じた制度設計が必要である。
6 役職員に対する継続的な教育・研修 構築した社内体制を適切に機能させるためには、それを担う役職員1人ひとりの高いコンプライアンス意識と法令等に対する正しい知識や理解が必要である。
上場会社においては、役職員に対して継続的に法令・社内規程等の内容を周知徹底するとともに、インサイダー取引を組織の一員として積極的に防止しようとする前向きな意識の醸成に努めることが求められる。
また、重要事実を含む情報には、決算に関する情報だけでなく業務の現場で発生するものもあることから、財務部門などの一部の役職員に対してのみ研修を行うのではなく、すべての役職員に対して適切な研修を行うことが重要である。
この点、現実問題として各企業の研修担当者は、役職員が各地に点在している、工場や販売等の業務が停止できない、研修用のインフラ(パソコン、インターネット等)が十分にないなど様々な制約のなかで研修方法や頻度を考えなくてはならず、各社とも非常に苦労していることと思われるが、東証COMLECでは、こうした際の研修方法の相談についても各社の状況に応じた提案を行っていることから、気軽に相談いただければ幸いである(脚注4)。
Ⅳ インサイダー取引に対する証券界の取組み
これまで当法人の取組みおよび上場会社における未然防止上の留意点等について述べてきたが、証券界では、このほかにも多くの取組みがなされていることから、ここでその概要を紹介することとしたい。
1 証券取引等監視委員会の動向 わが国の市場監視体制は、証券取引等監視委員会、取引所・証券業協会からなる自主規制機関、市場仲介者である証券会社の3者により構成されている。
このうち、最近インサイダー取引が数多く摘発されるようになった要因として、証券取引等監視委員会の体制が大幅に強化されてきたことが挙げられる。前掲・図表3のとおり最近10年間で急速に人員体制が強化されており、また、課徴金制度の導入により機動的な法執行体制が整ったことも最近の摘発件数の増加に大きく寄与している(前掲・図表4参照)。
また、証券取引等監視委員会は、これまでの流通市場の監視に加え、企業の不適切なファイナンス等の発行市場までを含めた包括的な市場監視を行う方針であり、近く予定されている課徴金制度の強化および検査・調査の範囲・対象の拡大とともに、着実に監視体制を強化させている。
2 新たなインフラの整備 一方、証券会社等の市場仲介者を通じた取組みも行われている。具体的には、平成18年3月に金融庁に設置された「証券会社の市場仲介機能等に関する懇談会」の報告を踏まえ、日本証券業協会、証券会社、取引所により具体的な方策が検討され、大きく2つの市場監視に関するインフラが整備されることとなっている。
その1つが「内部者情報システム」である。これは、上場会社役職員によるインサイダー取引を未然防止するため、売買の前に委託者の会社関係者への該当の有無を確認する「内部者登録制度」の実効性を高めるために導入されるもので、上場会社が適切に自社役職員の情報を登録することにより、証券会社における事前チェック機能が高まり、自社の役職員によるインサイダー取引をより確実に防止できるというものである。
そして、もう1つのインフラが、当局、自主規制機関、証券会社を守秘性の高いネットワークで結び、安全で迅速な市場監視を可能とする「コンプライアンスWAN」であり、それぞれ来年春の稼動に向けて準備が進められているところである。
証券界では、このほかにも各種の検討が進められており、これまで以上に実効性の高い市場監視体制が構築されることが期待されているところである。
Ⅴ おわりに
最近の証券市場における投資家層の拡大や上場会社の自己株式取得機会の増加などに伴い、上場会社がインサイダー取引のリスクを強く意識する場面がこれまで以上に増えており、既に多くの上場会社が未然防止策を講じ始めている。
ただし、インサイダー取引は、決して上場会社だけの問題ではなく、証券市場を利用するすべての関係者に関わる問題であり、弁護士・会計士等の証券市場のゲートキーパーや上場会社と資本・取引関係のある未上場会社のほか、社会的信用を強く求められている組織・団体等においても、それぞれがリスクに応じて前向きに取り組んでいくことが必要である。
当法人としても、市場監視や東証COMLECの活動を通じて、これらすべての市場関係者のコンプライアンスを支援すべく積極的に取り組んでいく考えである。
上場会社を含むすべての市場関係者においては、インサイダー取引防止の趣旨をご理解いただき、引き続き、未然防止に向けて取り組んでいただければ幸いである。
(よしまつ・かずひこ)
脚注
1 ASP(Application Service Provider)サービスとは、利用者の代わりにアプリケーション・プログラムや処理情報をデータセンターで管理し、これをインターネット等を通じて利用者に提供するサービスのことである。
2 上場会社コンプライアンス・フォーラムの情報については、東証自主規制法人のホームページ http://www.tse.or.jp/sr/comlec/seminar.html に東京開催分の発言概要・資料等を掲載予定であり、http://www.tse.or.jp/sr/comlec/comp_forum.html に大阪開催の開催概要を掲載している(登録締切りは11月5日)。
3 「全国上場会社内部者取引管理アンケート調査報告書(平成19年5月公表)」の詳細は、東証自主規制法人ホームページ http://www.tse.or.jp/sr/unfair/houkoku.html を参照されたい。
4 東証COMLECの相談窓口は、電話:03-3665-2769、メール:COMLEC@tse.or.jpとなっている。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -

Copyright (C) 2019
SHINNIPPON-HOKI PUBLISHING CO.,LTD.




















