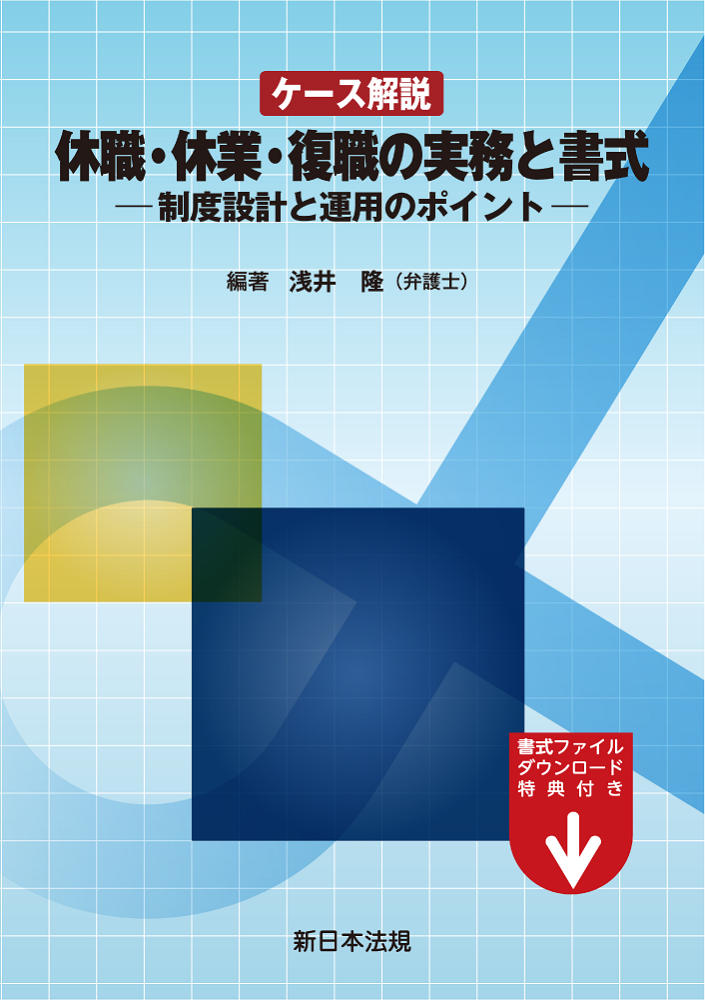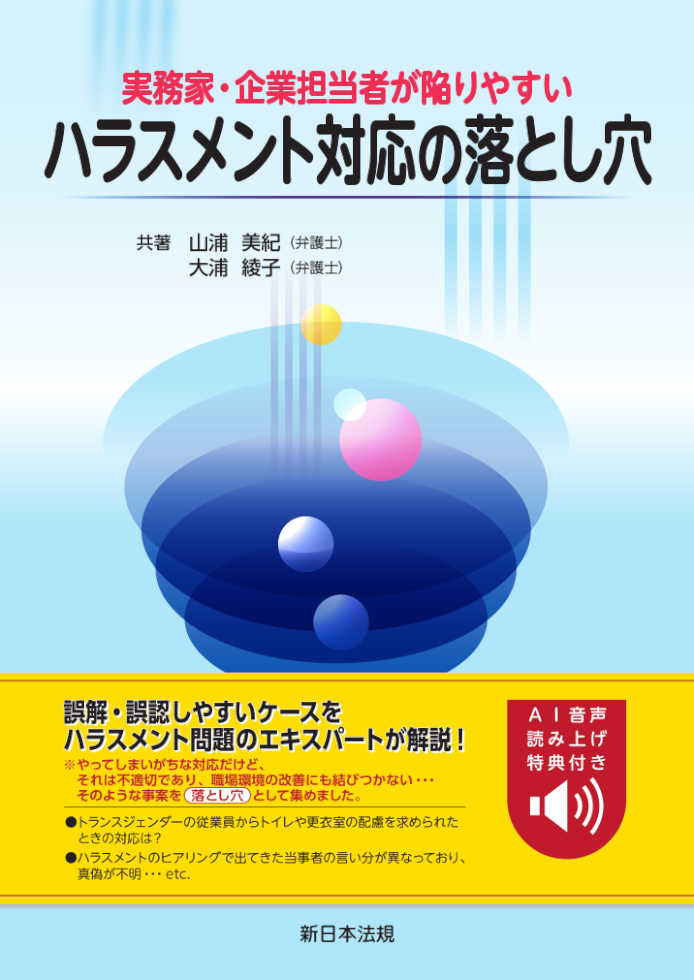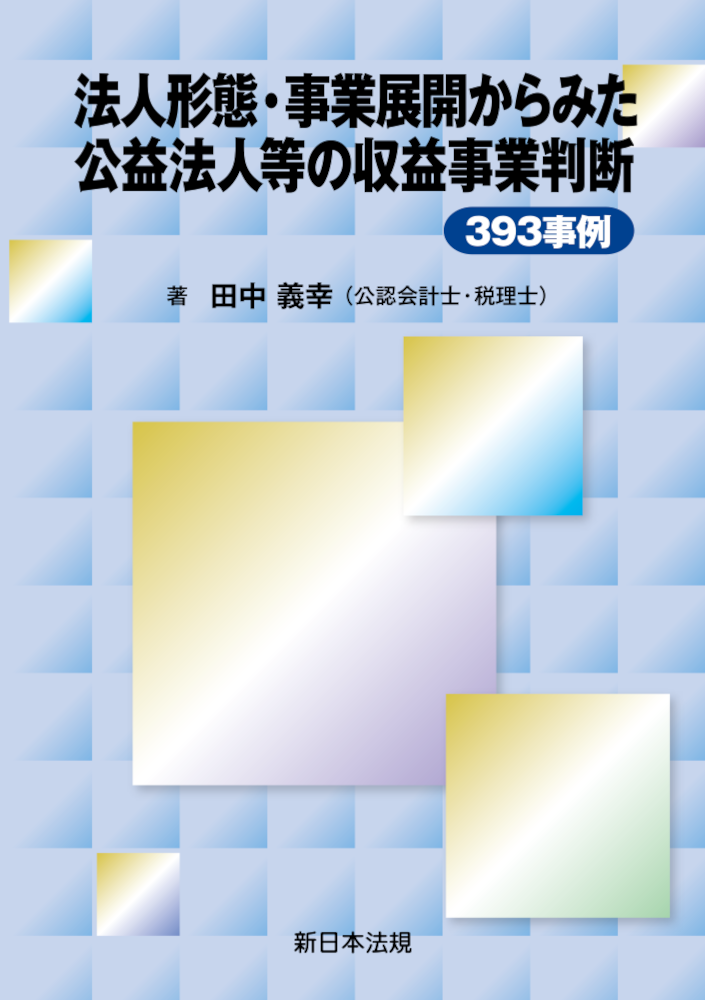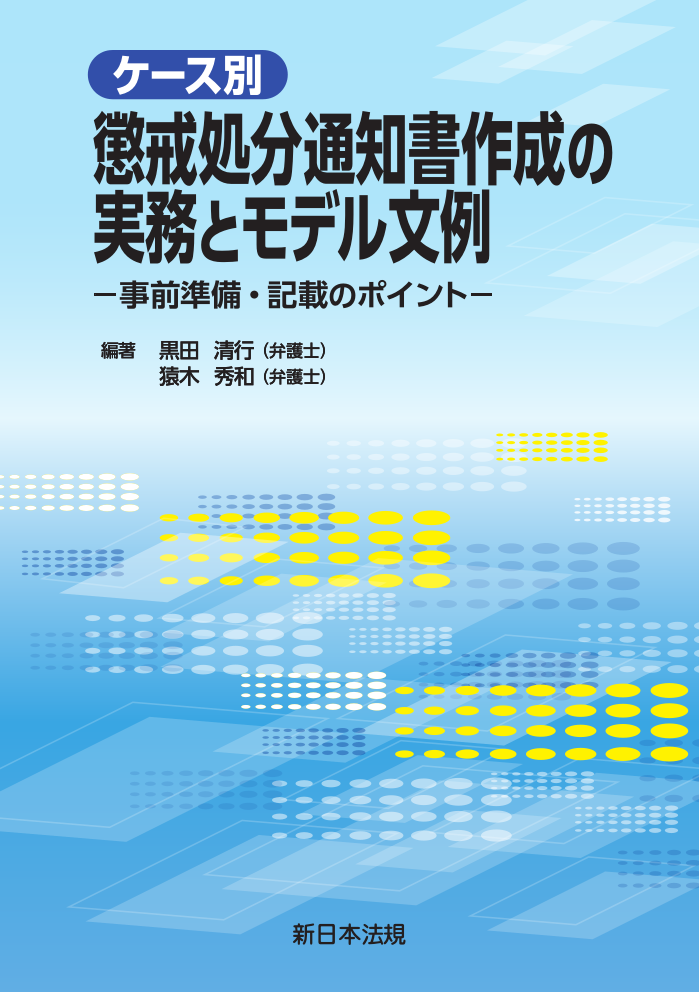解説記事2009年04月06日 【ニュース特集】 耐用年数は、基本原則+“4つの基準”で判定可能(2009年4月6日号・№301)
決定版・これでもう迷わない! 耐用年数判定
耐用年数は、基本原則+“4つの基準”で判定可能
平成20年度税制改正における耐用年数の“大括り化”後、3月決算法人が初めての確定申告を迎えるが、いまだ改正後の耐用年数の選定に迷う法人も少なくないようだ。
耐用年数の大括り化の趣旨はいうまでもなく耐用年数の簡素化にあり、むしろ、以前よりも耐用年数判定はシンプルになったといえる。それにもかかわらず耐用年数の判定に迷うのは、個別設備に着目したこれまでの耐用年数判定からの頭の切替えができていないことが一因にあるものと思われる。
本特集では、シンプルかつ正確に耐用年数判定を行う方法を、国税庁が本年1月23日に公表した改正耐用年数通達を踏まえながら、解説したい。
「法人ごとに一種類の耐用年数のみが適用される」という誤解 平成20年度税制改正における耐用年数改正では、別表2においてこれまで「設備ごと」に定められていた耐用年数が「業種ごと」に分けて定められた。
これに伴って広がっていたのが、「法人が保有する設備に対しては、一律にその法人の業種に係る耐用年数が適用される」という誤解。食品メーカーを例にとると、保有する設備にはすべて「食料品製造業用設備」に係る耐用年数である10年が適用されるというものだ。
この点については、課税当局側も「間違い」であることを明言しているので注意したいところだ。すなわち、一の法人内でも、異なる耐用年数の設備が存在し得るということである。
特に、複数の異なる製品を製造する大手メーカー等においては、その傾向が強い。一方、単一あるいは類似製品のみを製造する小規模メーカー等では、結果として、保有するすべての設備に対し、法人の業種と同じ業種に係る耐用年数が適用されるケースも多いだろう(図1参照)。

耐用年数の判定方法
原則的な判定方法 では、耐用年数大括り化後の耐用年数の判定方法を具体的に見てみよう。
まず、耐用年数判定の“大原則”として頭に入れておきたいのが、耐用年数通達1-4-2だ。同通達は、耐用年数の判定は、「設備ごと」に当該設備の使用状況を見て、「いずれの業種用の設備として使用しているか」により判定を行うこととしている。
たとえば、総合電機メーカーで、「電球」「電子部品」「電池」を作っていたとしよう。この場合、まず日本標準産業分類の小分類を見て、それぞれに該当する業種を確認する。次に、それが別表2に掲げる業種(日本標準産業分類の中分類に掲げる業種)のどれに当てはまるかを確認、耐用年数を判定することになる(図2参照)。

なお、別表2における業種の判定に際しては、耐用年数通達・付表8を使うと便利だ。付表8では、日本標準産業分類の小分類と別表2の業種(日本標準産業分類の中分類)の対応関係が示されており、さらに、小分類をブレークダウンした例も掲載されているので、耐用年数を判定するにあたっては必携といえよう(下記、付表8の一部抜粋参照)。

このような判定方法によれば、総合家電メーカーのように、いろいろな種類の製品を製造している場合、図2の通り、通常は異なる耐用年数の設備が出てくることになる。
中間製品が生じる場合の判定方法 製造業等においては、設備によって中間生産物が出るケースがあるが、耐用年数通達1-4-3では、その設備がどの業種用の設備として使用されているかを判定するにあたっては、あくまで「最終製品」に基づいて判定することとしている。
たとえば、電機メーカーにおいて、「液晶TV」という最終製品を製造する設備を有していたとしよう。液晶TVの製造過程では、「フラットパネル・ディスプレイ」や「フラットパネル・カラーフィルター」といった中間製品が生じることになるが、耐用年数通達1-4-3によれば、当該設備は、あくまで「液晶TV」という最終製品を作るための設備として、耐用年数を判定することになる。具体的には、耐用年数省令別表2「情報通信機械器具製造業用設備」として、8年の耐用年数が適用されることになろう。
しかし、中間製品である「フラットパネル・ディスプレイ」や「フラットパネル・カラーフィルター」を自社の液晶TVには組み込まず、他社に販売するケースも見られるところだ。このような場合について、耐用年数通達1-4-4では、最終製品に係る設備を構成する中間製品に係る設備の規模が「相当程度」である場合には、最終製品ではなく、中間製品に係る業種により耐用年数を判定することとしている。したがって、「フラットパネル・ディスプレイ」には、耐用年数省令別表2「電子部品、デバイス又は電子回路製造業用設備」の「フラットパネルディスプレイ」として耐用年数5年、「フラットパネル・カラーフィルター」には、耐用年数省令別表2「化学工業用設備」の「フラットパネル用カラーフィルター」として耐用年数5年が適用されることになる。
問題はここでいう「相当程度」の定義だ。通達では、「相当程度」の例示として「総生産量等に占める割合がおおむね50%超」「工程に占める割合がおおむね50%超」の2つの例示を行っているが、課税当局は、必ずしもこの2つの例示には限定せず、「設備の大きさや金額など様々な判断要素があることから、法人において実態に即した合理的な判断基準があれば、それを尊重する」とコメントしている。たとえば、中間製品の見た目の大きさや、あるいは、中間製品の製造に必要な高額な最新設備が組み込まれているといったことも判断基準になり得るという。
また、「おおむね50%」については文字通り「おおよそ」であれば足り、詳細な計算は不要であるとしている。

自家用設備がある場合の判定方法 上記の「中間製品」は従来から耐用年数通達に存在した概念であるが、これに対し、今回の改正耐用年数通達により新たに作られた概念が「自家用設備」だ。
耐用年数通達1-4-5では、ある設備から生ずる最終製品(A)を専ら用いて他の最終製品(B)が生産される場合には、その設備は、AではなくBに係る業種により耐用年数を判定することとしている。
たとえば、自動車メーカーで、自動車の製造ライン用に発電設備を有している場合、この発電設備が「自家用設備」に該当することになる。この場合、発電設備はあくまで自動車の製造ライン用に用いられるものであることから、「発電設備」として耐用年数を判定するのではなく、「輸送用機械器具製造業用設備」として、耐用年数を判定することになる(図3参照)。
 ただし、自家用設備に該当するためには、発電設備が「専ら」自動車の製造ライン用に使用されていることが条件となる。仮に、発電設備により生じた電気を主に外部販売しているとすれば、発電設備は自家用設備ではなく、「内燃力又はガスタービン発電設備」として15年の耐用年数が適用されることになろう。
ただし、自家用設備に該当するためには、発電設備が「専ら」自動車の製造ライン用に使用されていることが条件となる。仮に、発電設備により生じた電気を主に外部販売しているとすれば、発電設備は自家用設備ではなく、「内燃力又はガスタービン発電設備」として15年の耐用年数が適用されることになろう。
なお、ここでいう「専ら」についても、数値基準は不要とのことである。
複合的なサービスを提供している場合の判定方法 サービス業には複数のサービスが包含されているケースが少なくない。
たとえば、ホテル業においては、クリーニング設備や浴場設備はホテルの宿泊者に対するサービスの一部を構成し、ホテル業とは不可分なものになっているといえる。
このようなケースについて改正耐用年数通達1-4-6では、「それぞれの設備から生ずる役務の提供が複合して一の役務の提供を構成する場合」には、当該一の役務の提供に係る業種用の設備の耐用年数を適用することとしている(図4参照)。
 ただし、宿泊客以外も利用可能なホテル内のレストランの厨房用の機械および装置については、「飲食店業用設備」として、耐用年数8年が適用されることになる(耐通2-8-5)。
ただし、宿泊客以外も利用可能なホテル内のレストランの厨房用の機械および装置については、「飲食店業用設備」として、耐用年数8年が適用されることになる(耐通2-8-5)。
これに対し、平成20年7月に国税庁より明らかにされた「耐用年数等の見直し(平成20年度税制改正)に関するQ&A」のうち、Q6「設備の種類の具体的判定例」には、自動車部品製造業者が工場に有する「従業員の給食のため厨房設備」の耐用年数判定について、「その構成や使用状況が、通常の飲食店業用の設備と同様であることから、別表第2の『48 飲食店業用設備』に該当し、8年の耐用年数が適用される」との記述がある。
しかし、自動車部品製造業者にとっての「厨房施設」は、ホテル業にとってのクリーニング設備や浴場設備とは異なり、自動車部品製造業の一部を構成しているものとはいえない。したがって、自動車部品製造業とは切り離して、「48 飲食店業用設備」を適用した方が理にかなっているものと考えられ、改正耐用年数通達1-4-6には当てはまらないことになる。
COLUMN
中間製品と自家用設備から生じる製品 中間製品、自家用設備から生じる製品は、ともに最終製品の一部を構成、あるいは最終製品の完成に貢献することから、一見、両者は区別が付きづらい。しかし、中間製品は、あくまで最終製品を製造する生産設備によって生じるのに対し、自家用設備から生じる製品は、最終製品を製造する生産設備とは全く別の設備から生じる点が異なっている。
COLUMN
耐用年数通達に「旧耐用年数」が掲載されている理由 耐用年数の大括り化に伴い、390区分もあった旧耐用年数省令別表2はもはや無用の長物となったようにも見えるが、耐用年数通達には、なぜか旧耐用年数表別表2が付表10として掲載されている。これは、耐用年数の短縮や増加償却の申請に配慮したもの。すわなち、当該設備が耐用年数短縮や増加償却の対象となるかを判断するに際しては、「●●業種 ●年」といった大ざっぱな耐用年数ではなく、やはり設備ごとに耐用年数を検証することが必要になるだろうとの想定のもと、旧別表2を残したものである。
耐用年数は、基本原則+“4つの基準”で判定可能
平成20年度税制改正における耐用年数の“大括り化”後、3月決算法人が初めての確定申告を迎えるが、いまだ改正後の耐用年数の選定に迷う法人も少なくないようだ。
耐用年数の大括り化の趣旨はいうまでもなく耐用年数の簡素化にあり、むしろ、以前よりも耐用年数判定はシンプルになったといえる。それにもかかわらず耐用年数の判定に迷うのは、個別設備に着目したこれまでの耐用年数判定からの頭の切替えができていないことが一因にあるものと思われる。
本特集では、シンプルかつ正確に耐用年数判定を行う方法を、国税庁が本年1月23日に公表した改正耐用年数通達を踏まえながら、解説したい。
「法人ごとに一種類の耐用年数のみが適用される」という誤解 平成20年度税制改正における耐用年数改正では、別表2においてこれまで「設備ごと」に定められていた耐用年数が「業種ごと」に分けて定められた。
これに伴って広がっていたのが、「法人が保有する設備に対しては、一律にその法人の業種に係る耐用年数が適用される」という誤解。食品メーカーを例にとると、保有する設備にはすべて「食料品製造業用設備」に係る耐用年数である10年が適用されるというものだ。
この点については、課税当局側も「間違い」であることを明言しているので注意したいところだ。すなわち、一の法人内でも、異なる耐用年数の設備が存在し得るということである。
特に、複数の異なる製品を製造する大手メーカー等においては、その傾向が強い。一方、単一あるいは類似製品のみを製造する小規模メーカー等では、結果として、保有するすべての設備に対し、法人の業種と同じ業種に係る耐用年数が適用されるケースも多いだろう(図1参照)。

耐用年数の判定方法
原則的な判定方法 では、耐用年数大括り化後の耐用年数の判定方法を具体的に見てみよう。
まず、耐用年数判定の“大原則”として頭に入れておきたいのが、耐用年数通達1-4-2だ。同通達は、耐用年数の判定は、「設備ごと」に当該設備の使用状況を見て、「いずれの業種用の設備として使用しているか」により判定を行うこととしている。
たとえば、総合電機メーカーで、「電球」「電子部品」「電池」を作っていたとしよう。この場合、まず日本標準産業分類の小分類を見て、それぞれに該当する業種を確認する。次に、それが別表2に掲げる業種(日本標準産業分類の中分類に掲げる業種)のどれに当てはまるかを確認、耐用年数を判定することになる(図2参照)。

なお、別表2における業種の判定に際しては、耐用年数通達・付表8を使うと便利だ。付表8では、日本標準産業分類の小分類と別表2の業種(日本標準産業分類の中分類)の対応関係が示されており、さらに、小分類をブレークダウンした例も掲載されているので、耐用年数を判定するにあたっては必携といえよう(下記、付表8の一部抜粋参照)。

このような判定方法によれば、総合家電メーカーのように、いろいろな種類の製品を製造している場合、図2の通り、通常は異なる耐用年数の設備が出てくることになる。
中間製品が生じる場合の判定方法 製造業等においては、設備によって中間生産物が出るケースがあるが、耐用年数通達1-4-3では、その設備がどの業種用の設備として使用されているかを判定するにあたっては、あくまで「最終製品」に基づいて判定することとしている。
たとえば、電機メーカーにおいて、「液晶TV」という最終製品を製造する設備を有していたとしよう。液晶TVの製造過程では、「フラットパネル・ディスプレイ」や「フラットパネル・カラーフィルター」といった中間製品が生じることになるが、耐用年数通達1-4-3によれば、当該設備は、あくまで「液晶TV」という最終製品を作るための設備として、耐用年数を判定することになる。具体的には、耐用年数省令別表2「情報通信機械器具製造業用設備」として、8年の耐用年数が適用されることになろう。
しかし、中間製品である「フラットパネル・ディスプレイ」や「フラットパネル・カラーフィルター」を自社の液晶TVには組み込まず、他社に販売するケースも見られるところだ。このような場合について、耐用年数通達1-4-4では、最終製品に係る設備を構成する中間製品に係る設備の規模が「相当程度」である場合には、最終製品ではなく、中間製品に係る業種により耐用年数を判定することとしている。したがって、「フラットパネル・ディスプレイ」には、耐用年数省令別表2「電子部品、デバイス又は電子回路製造業用設備」の「フラットパネルディスプレイ」として耐用年数5年、「フラットパネル・カラーフィルター」には、耐用年数省令別表2「化学工業用設備」の「フラットパネル用カラーフィルター」として耐用年数5年が適用されることになる。
問題はここでいう「相当程度」の定義だ。通達では、「相当程度」の例示として「総生産量等に占める割合がおおむね50%超」「工程に占める割合がおおむね50%超」の2つの例示を行っているが、課税当局は、必ずしもこの2つの例示には限定せず、「設備の大きさや金額など様々な判断要素があることから、法人において実態に即した合理的な判断基準があれば、それを尊重する」とコメントしている。たとえば、中間製品の見た目の大きさや、あるいは、中間製品の製造に必要な高額な最新設備が組み込まれているといったことも判断基準になり得るという。
また、「おおむね50%」については文字通り「おおよそ」であれば足り、詳細な計算は不要であるとしている。

自家用設備がある場合の判定方法 上記の「中間製品」は従来から耐用年数通達に存在した概念であるが、これに対し、今回の改正耐用年数通達により新たに作られた概念が「自家用設備」だ。
耐用年数通達1-4-5では、ある設備から生ずる最終製品(A)を専ら用いて他の最終製品(B)が生産される場合には、その設備は、AではなくBに係る業種により耐用年数を判定することとしている。
たとえば、自動車メーカーで、自動車の製造ライン用に発電設備を有している場合、この発電設備が「自家用設備」に該当することになる。この場合、発電設備はあくまで自動車の製造ライン用に用いられるものであることから、「発電設備」として耐用年数を判定するのではなく、「輸送用機械器具製造業用設備」として、耐用年数を判定することになる(図3参照)。
 ただし、自家用設備に該当するためには、発電設備が「専ら」自動車の製造ライン用に使用されていることが条件となる。仮に、発電設備により生じた電気を主に外部販売しているとすれば、発電設備は自家用設備ではなく、「内燃力又はガスタービン発電設備」として15年の耐用年数が適用されることになろう。
ただし、自家用設備に該当するためには、発電設備が「専ら」自動車の製造ライン用に使用されていることが条件となる。仮に、発電設備により生じた電気を主に外部販売しているとすれば、発電設備は自家用設備ではなく、「内燃力又はガスタービン発電設備」として15年の耐用年数が適用されることになろう。なお、ここでいう「専ら」についても、数値基準は不要とのことである。
複合的なサービスを提供している場合の判定方法 サービス業には複数のサービスが包含されているケースが少なくない。
たとえば、ホテル業においては、クリーニング設備や浴場設備はホテルの宿泊者に対するサービスの一部を構成し、ホテル業とは不可分なものになっているといえる。
このようなケースについて改正耐用年数通達1-4-6では、「それぞれの設備から生ずる役務の提供が複合して一の役務の提供を構成する場合」には、当該一の役務の提供に係る業種用の設備の耐用年数を適用することとしている(図4参照)。
 ただし、宿泊客以外も利用可能なホテル内のレストランの厨房用の機械および装置については、「飲食店業用設備」として、耐用年数8年が適用されることになる(耐通2-8-5)。
ただし、宿泊客以外も利用可能なホテル内のレストランの厨房用の機械および装置については、「飲食店業用設備」として、耐用年数8年が適用されることになる(耐通2-8-5)。これに対し、平成20年7月に国税庁より明らかにされた「耐用年数等の見直し(平成20年度税制改正)に関するQ&A」のうち、Q6「設備の種類の具体的判定例」には、自動車部品製造業者が工場に有する「従業員の給食のため厨房設備」の耐用年数判定について、「その構成や使用状況が、通常の飲食店業用の設備と同様であることから、別表第2の『48 飲食店業用設備』に該当し、8年の耐用年数が適用される」との記述がある。
しかし、自動車部品製造業者にとっての「厨房施設」は、ホテル業にとってのクリーニング設備や浴場設備とは異なり、自動車部品製造業の一部を構成しているものとはいえない。したがって、自動車部品製造業とは切り離して、「48 飲食店業用設備」を適用した方が理にかなっているものと考えられ、改正耐用年数通達1-4-6には当てはまらないことになる。
COLUMN
中間製品と自家用設備から生じる製品 中間製品、自家用設備から生じる製品は、ともに最終製品の一部を構成、あるいは最終製品の完成に貢献することから、一見、両者は区別が付きづらい。しかし、中間製品は、あくまで最終製品を製造する生産設備によって生じるのに対し、自家用設備から生じる製品は、最終製品を製造する生産設備とは全く別の設備から生じる点が異なっている。
COLUMN
耐用年数通達に「旧耐用年数」が掲載されている理由 耐用年数の大括り化に伴い、390区分もあった旧耐用年数省令別表2はもはや無用の長物となったようにも見えるが、耐用年数通達には、なぜか旧耐用年数表別表2が付表10として掲載されている。これは、耐用年数の短縮や増加償却の申請に配慮したもの。すわなち、当該設備が耐用年数短縮や増加償却の対象となるかを判断するに際しては、「●●業種 ●年」といった大ざっぱな耐用年数ではなく、やはり設備ごとに耐用年数を検証することが必要になるだろうとの想定のもと、旧別表2を残したものである。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -

Copyright (C) 2019
SHINNIPPON-HOKI PUBLISHING CO.,LTD.