解説記事2009年04月27日 【制度解説】 「継続企業の前提に関する注記」に係る財務諸表等規則等の改正の要点(2009年4月27日号・№304)
解説
「継続企業の前提に関する注記」に係る財務諸表等規則等の改正の要点
金融庁総務企画局企業開示課主任企業会計専門官 平松 朗
金融庁総務企画局企業開示課企業会計第一係 山下祐士
Ⅰ.はじめに
今般、企業会計審議会から「監査基準の改訂に関する意見書」(平成21年4月9日付)が公表され、継続企業(ゴーイング・コンサーン)の前提の注記に関する監査基準の改訂が行われるとともに、4月20日付で「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」(平成21年内閣府令第27号)が公布され、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(以下「財務諸表等規則」という)および「企業内容等の開示に関する内閣府令」(以下「開示府令」という)など内閣府令等関係規定についても改正が行われた。
この背景には、本年2月に行われた企業会計審議会企画調整部会からの「我が国における国際会計基準の取扱いについて(中間報告)(案)」の公表がある。
わが国企業に対する国際会計基準(IFRS)の任意適用が早ければ平成22(2010)年3月期にも想定されるなか、鋭意、会計基準のコンバージェンスが進められているが、IFRSにおいては、継続企業の前提の注記が会計基準として定められている。IFRSで財務報告をする会社が現実化することを踏まえると、開示内容を整合させないとわが国会計基準で財務報告をする会社との間で比較しにくい状況が生じるため、整合させるための検討が必要であると考えられた。
また、監査基準の分野でも、国際会計士連盟(IFAC)の国際監査・保証基準審議会(IAASB)により明瞭性プロジェクト(クラリティ・プロジェクト)が進められてきたが、わが国がクラリティ・プロジェクトに対応していくなかで、継続企業の前提の注記がわが国監査基準と国際監査基準(ISA)との差異として指摘されていた。
さらに、継続企業の前提の注記に関するわが国実務では、債務超過や連続営業損失など一定の事象や状況が存在する場合に形式的に注記を求める傾向にあり、国際的な実務と必ずしも整合的でないとの指摘もある。
こうしたことから、今般、投資者に対してより有用な情報を提供し、また、国際的な開示・監査基準や実務との整合性を確保する観点から、一定の事象や状況が存在する場合であって、経営者等の対応策等を勘案してもなお「継続企業の前提に重要な不確実性」がある場合に限って、継続企業の前提に関する注記を求めるよう監査基準や内閣府令が改正されたものである。加えて、有価証券報告書におけるいわゆるリスク情報やMD&A情報についても、それらを充実させるための改正が行われた。
これら一連の改正事項は、基本的に平成21年3月31日以後終了する事業年度から適用される。
以下では、改正の概要を解説することとするが、文中意見にわたる部分は私見であることをあらかじめ申し添える。
Ⅱ.財務諸表等規則等の改正
1.「継続企業の前提に関する注記」の導入
(1)導入の経緯 「継続企業の前提に関する注記」は、財務諸表等規則の平成14年10月18日付の改正の際に新設されたものである。
この改正は、平成14年1月25日付で「監査基準の改訂に関する意見書」が企業会計審議会から公表されたことを受けて行われた。この意見書により監査基準は全面的に改訂されたが、そのなかで、企業が将来にわたって事業活動を継続するとの前提(継続企業の前提)に関する重要な疑義に対する監査人の対応が新たに定められた。同意見書においては、継続企業の前提に関する事項を財務諸表において注記することが提言されている。
継続企業の前提に関する注記については、国際会計基準(IAS)(脚注1)のように会計基準においてその注記内容が定められているものがある。他方、米国においては、会計基準は定められておらず、監査基準に基づく開示・監査実務が行われている(脚注2)。
わが国においては、企業会計審議会の議論の過程で、開示の基準は会計基準ではなく法令により手当てされることになり、結局、財務諸表等規則等で規定されることとなった。
(2)旧規定の内容 旧規定は、「貸借対照表日において、債務超過等財務指標の悪化の傾向、重要な債務の不履行等財政破綻の可能性その他会社が将来にわたつて事業を継続するとの前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況が存在する場合」に財務諸表に継続企業の前提に関する注記を行うこととされた(財務諸表等規則旧8条の27)。
また、「重要な疑義を抱かせる事象又は状況」を具体的にするために、監査基準の改訂に関する意見書の前文を参考に、「『財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則』の取扱いに関する留意事項について」(以下「財規ガイドライン」という)が設けられた。
財務諸表等規則および財規ガイドラインに規定された事象や状況を整理すると、次のようになる。
①債務超過、②重要な債務の不履行、③売上高の著しい減少、④継続的な営業損失の発生、⑤継続的な営業キャッシュ・フローのマイナス、⑥重要な債務の返済の困難性、⑦新たな資金調達が困難な状況、⑧取引先からの与信の拒絶、⑨事業の継続に不可欠な重要な資産の毀損または喪失もしくは権利の失効、⑩重要な市場または取引先の喪失、⑪巨額の損害賠償の履行、⑫法令等に基づく事業の制約等。
また、旧規定においては、注記内容として次の4号が列記されていた(財務諸表等規則旧8条の27)。
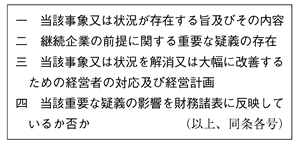 なお、旧第4号においては、「当該重要な疑義の影響を財務諸表に反映しているか否か」が開示事項とされているが、日本公認会計士協会監査委員会報告第74号「継続企業の前提に関する開示について」においては、「財務諸表は継続企業を前提として作成されており、当該重要な疑義の影響を財務諸表に反映していない」旨を注記することとされていた。
なお、旧第4号においては、「当該重要な疑義の影響を財務諸表に反映しているか否か」が開示事項とされているが、日本公認会計士協会監査委員会報告第74号「継続企業の前提に関する開示について」においては、「財務諸表は継続企業を前提として作成されており、当該重要な疑義の影響を財務諸表に反映していない」旨を注記することとされていた。
(3)日本公認会計士協会の対応 日本公認会計士協会は、旧規定公布の直後、平成14年11月6日付で上記・監査委員会報告第74号を公表しており、これが実質的に開示実務のよりどころとなっていた。
同報告は、「単独で又は複合して継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況」として、図表1に掲げる20項目を列挙しているが、これらの項目が継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象または状況であり、「当該事象又は状況の解消又は大幅な改善に重要な不確実性が残るために、継続企業の前提に関する重要な疑義が認められるか否かを、総合的に判断する必要がある」とされており、重要な不確実性の存否を、疑義の存否に係らしめていた。
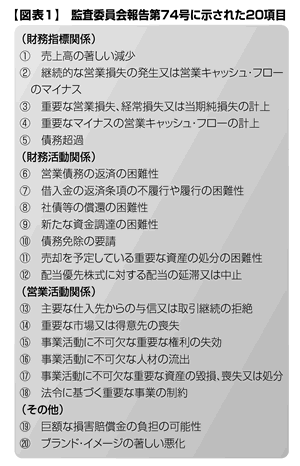 同報告によれば、これらの事象または状況が貸借対照表日後に解消または大幅に改善した場合もしくは当該事象または状況が変化した場合には、その旨および経緯を注記に含めて記載することが必要とされた。
同報告によれば、これらの事象または状況が貸借対照表日後に解消または大幅に改善した場合もしくは当該事象または状況が変化した場合には、その旨および経緯を注記に含めて記載することが必要とされた。
また、貸借対照表日後に事象または状況が発生した場合には、後発事象として開示されることとされていた。
2.今回の改正内容 「継続企業の前提に関する注記」に関する規定は、平成21年4月20日付の財務諸表等規則等の改正により大幅に修正された(財務諸表等規則新8条の27等参照)。
上述のように、これまでは「継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況」があるか否かという、いわば形式的な基準によって、継続企業の前提に関する注記の要否が判断される実務が行われる傾向にあった。
たとえば、貸借対照表日において債務超過や重要な債務の不履行のみならず、継続的な営業損失の発生や重要な営業損失の計上といった事象や状況が認められれば、ほぼ自動的に重要な疑義を抱かせる事象や状況が存在するものとして、注記が求められる実務が行われていたところである。
昨年秋以降の世界的な景気の後退もあり、企業業績が急激に悪化したため、かなりの数の注記が行われるようになった。金融機関との間で、注記が付されていないことが融資条件になっているケースがあることから、形式的な発想で注記を付けることの問題点が一層クローズ・アップされたきらいもある。
また、注記がされたうえで、監査報告書を作成する際に、監査人が経営者の対応や経営計画の合理性を検討し、最終的に監査人による意見が表明されるという仕組みになっているが、今回の改正では、国際会計基準や国際監査基準などに合わせ、このようなプロセスを見直すこととした(図表2参照)。
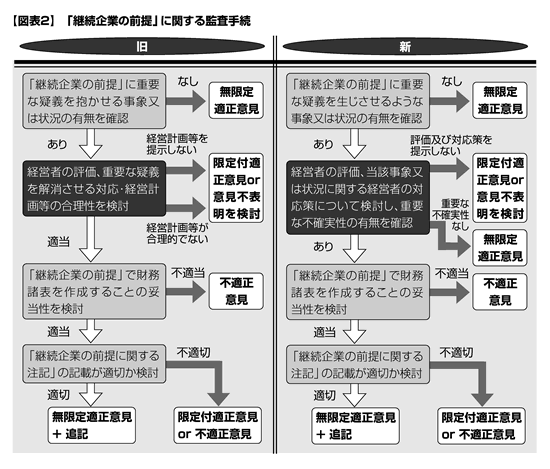 具体的には、「継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況」が認められる場合は、まず、経営者がその事象や状況を解消し、または改善するための対応策を検討、評価することになる。そして、このような対応策を講じてもなお継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められるときに注記が必要となる(図表3参照)。
具体的には、「継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況」が認められる場合は、まず、経営者がその事象や状況を解消し、または改善するための対応策を検討、評価することになる。そして、このような対応策を講じてもなお継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められるときに注記が必要となる(図表3参照)。
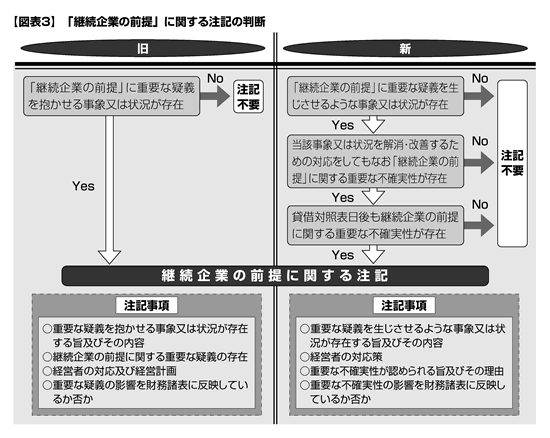 条文(財務諸表等規則8条の27)に沿って説明すると、この改正により、まず、形式的な実務を招きやすい「債務超過等財務指標の悪化の傾向、重要な債務の不履行等財政破綻の可能性」という例示部分を削除した。
条文(財務諸表等規則8条の27)に沿って説明すると、この改正により、まず、形式的な実務を招きやすい「債務超過等財務指標の悪化の傾向、重要な債務の不履行等財政破綻の可能性」という例示部分を削除した。
また、「……事象又は状況が存在する場合であつて、当該事象又は状況を解消し、又は改善するための対応をしてもなお継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められるときは……」という文言を挿入し、新しいプロセスの考え方を具体的に条文化している。
さらに、「ただし、貸借対照表日後において、当該重要な不確実性が認められなくなつた場合は、注記することを要しない。」というただし書を設けている。
これは、貸借対照表日後において重要な不確実性が認められなくなった場合には、むしろ注記をしない方が有用な情報になる面があるという考え方に基づく。
また、貸借対照表日後に新たな事象または状況に起因する重要な不確実性が認められた場合には、重要な後発事象の注記としての検討が行われることになる(財規ガイドライン8の27-5、日本公認会計士協会監査・保証実務委員会報告第76号参照)。
財務諸表等規則8条の27第1号から第4号までの注記の内容も「重要な疑義」から「重要な不確実性」に改正され、実務のプロセスに合わせて、各号の順番も改正され、旧第2号と旧第3号の順番が入れ替えられた。
財規ガイドラインについても、財務諸表等規則に応じた用語等の改正が行われたほか、「総合的かつ実質的に判断を行うものとし、……事象又は状況が存在するか否かといった画一的な判断を行うことのないよう留意する」旨の規定が新設された(財規ガイドライン8の27-3)。
Ⅲ.開示府令の改正
財務諸表等規則等の改正と同時に開示府令等の改正が行われた。
開示府令第2号様式(有価証券届出書)の記載上の注意の(33)および(36)が改正され、b項が追加・挿入されている(他の有価証券届出書および有価証券報告書の様式では、基本的に第2号様式の記載上の注意の(33)および(36)に準じて記載することとされているため、各様式についても同様の改正となる)。
1.「事業等のリスク」等の開示 「事業等のリスク」の開示は、平成15年3月31日に公布され、同年4月1日より施行された開示府令の改正に際して導入され、有価証券報告書については施行日以後開始する事業年度に係るものから適用されたので、3月決算会社については平成16年3月期の有価証券報告書から適用された。
この平成15年改正により、「事業の内容」「経理の状況」等に関する事項のうち、投資判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事象などリスク情報の記載を求め、また、「財政状態及び経営成績の分析」(MD&A)として経営者による財政・経営成績の分析についての記載を求めることとされた。
今回の改正では、「事業等のリスク」(リスク情報)の記載上の注意として、継続企業の前提に「重要な疑義を生じさせるような事象又は状況その他提出会社の経営に重要な影響を及ぼす事象(重要事象等)が存在する場合」には、その旨、その内容を具体的に、かつ投資者にわかりやすく記載することとする規定が新設された。
また、「財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析」(MD&A)の記載上の注意として、リスク情報として重要事象等を記載した場合には、「当該重要事象等についての分析・検討内容及び当該重要事象等を解消し、又は改善するための対応策を具体的に」記載することを求める規定が新設された(図表4参照)。
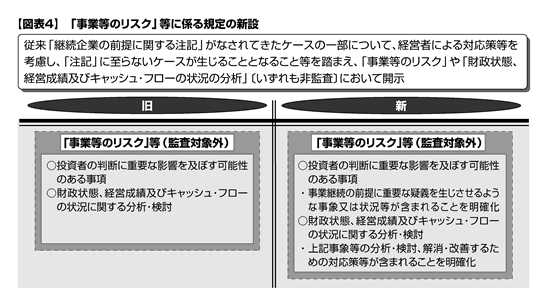 2.個別ガイドラインの改正等
2.個別ガイドラインの改正等
(1)「事業等のリスク」に関する取扱いガイドラインの改正 これらの改正に併せて、企業内容等開示ガイドラインの個別ガイドラインである「『事業等のリスク』に関する取扱いガイドライン」が改正されている。
重要事象等に関しては、その会社の経営への影響も含めて具体的な内容を記載することとされた。このうち、継続企業の前提に「重要な疑義を生じさせるような事象又は状況」が生じた場合に、その内容が確実に記載されるよう、監査委員会報告第74号の「4継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事業又は状況」を参考に例示列挙された次の事象または状況(図表1参照)が単独でまたは複合的に生ずることによってこれに該当し得る旨が示された。ただし、「事業等のリスク」の記載にあたっては、これらの例示にとらわれることなく、積極的に記載することが望まれるところである。
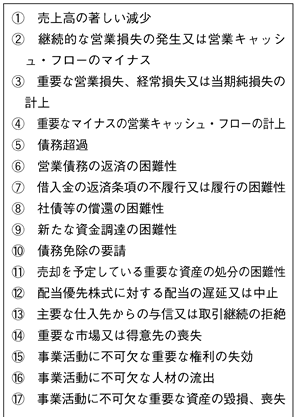
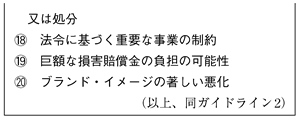 (2)「財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析」に関する取扱いガイドラインの新設
さらに、個別ガイドラインのⅡとして「『財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析』に関する取扱いガイドライン」が新設された。
(2)「財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析」に関する取扱いガイドラインの新設
さらに、個別ガイドラインのⅡとして「『財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析』に関する取扱いガイドライン」が新設された。
すなわち、「当該重要事象等を解消し、又は改善するための対応策」については、提出会社の「財務の健全性に悪影響を及ぼしている、又は及ぼし得る要因に関して経営者が講じている、又は講じる予定の対応策の具体的な内容(実施時期、実現可能性の程度、金額等を含む。)」を記載することとされている。
また、対応策の例としては、①資産の処分に関する計画、②資金調達の計画、③債務免除の計画、④その他が挙げられている。対応策の例は、監査基準委員会報告書第22号「継続企業の前提に関する監査人の検討」を参考にしており、「その他」が付け加えられている。
このような開示府令等の改正の方向も、リスク情報等が充実している欧米の開示事例を範にしており、投資者保護上も望ましいものと考えられる。
Ⅳ.監査基準の改訂
監査基準についても、企業会計審議会から平成21年4月9日付で公表された「監査基準の改訂に関する意見書」により、上述の考え方に沿って継続企業の前提に関する監査基準の改訂が行われている。
改訂監査基準の前文では、「監査人は、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在すると判断した場合には、当該事象又は状況に関して合理的な期間について経営者が行った評価及び対応策について検討したうえで、なお継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められるか否かを確かめなければならない」とされ、また、監査報告書についても「継続企業の前提に関する重要な不確実性」が認められるときの財務諸表の記載に関して意見を表明することとされた(脚注3)。
これに従い、日本公認会計士協会の関係する実務指針(監査委員会報告第74号、監査基準委員会報告書第22号等)も見直されている(これについては、別途の解説が行われるかと思われる)。
監査基準改訂の意義等詳細は、監査基準の専門家による解説を参照いただきたいが、1点だけ付言すると、今回は、「合理性」という用語が、制定当初の一応の合理性という意味ではなく経済的な合理性というような想定外のリジッドな意味に受け取られる傾向が強かったので、改訂監査基準上、極力「合理性」という用語を使用しないこととされた。
たとえば、実施基準の「三 監査の実施」の「経営計画等の合理性を検討」するという部分が「対応策について検討」というように改訂されている。
また、報告基準においても、経営者が「合理的な経営計画等を提示しないときには」意見不表明を検討するという文言が、「評価及び対応策を示さないときには、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められるか否かを確かめる十分かつ適切な監査証拠を入手できないことがあるため」と改訂されており、経営者から合理的な経営計画が示されない場合に、直ちに意見不表明とするような実務については見直しを求めている。
Ⅴ.おわりに
以上に述べたような一連の改正により、有価証券報告書における「事業等のリスク」および「財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析」と財務諸表における継続企業の前提の注記とを一体として、経営上のリスクを開示することになる。
また、継続企業の前提の注記については、改訂監査基準による監査手続が行われることにより注記内容の確度が向上し、もって、一層投資者保護が図られることになると思われる。
これらの改正は、平成21年3月期決算から適用される(脚注4)。関係者には、検討する時間は短期間であろうとは思うが、以上のような改正の趣旨を汲み取っていただき、積極的な取組みをお願いしたい。
なお、中間監査基準および四半期レビュー基準についても、企業会計審議会において改訂を検討することが改訂監査基準の前文において明記されており、これに応じて四半期財務諸表等規則・中間財務諸表等規則等の改正も予定されていることを付言しておく。
(ひらまつ・あきら/やました・ゆうじ)
脚注
1 国際会計基準第1号第25項においては、「継続企業」として、「財務諸表を作成するに際して、経営者は継続企業として存続する能力があるかどうかを検討しなければならない。……経営者がこの検討を行う際に、当該企業の継続企業としての存続能力に対して重大な疑問を生じさせるような事象又は状態に関する重要な不確定事項を発見したときは、その不確定事項を開示しなければならない。……」と規定されている。
2 米国財務会計基準審議会(FASB)は、昨年10月9日付で公開草案「ゴーイング・コンサーン」を公表している。公開草案第7項において開示内容が定められているが、注記の要否の部分については、IASとほぼ同文である。記載事項は、①企業の継続能力に疑義を生じさせる事象または状況、②当該事象または状況の影響、③経営者の当該事象または状況の重大性の評価および緩和の要素、④事業の中断可能性、⑤経営者の不確実性の影響の緩和への改善策および企業の継続能力に対する重大な疑義を緩和するための対応策、⑥資産額の回収可能性または分類、負債の額または分類とされている。
3 「監査基準の改訂について」(平成21年4月9日・企業会計審議会)においては、「継続企業の前提に関する注記の開示を規定している財務諸表等規則等やその監査を規定する監査基準において、一定の事象や状況が存在すれば直ちに継続企業の前提に関する注記及び追記情報の記載を要するとの規定となっているとの理解がなされ、一定の事実の存在により画一的に当該注記を行う実務となっているとの指摘がある。また、それらの規定や実務は国際的な基準とも必ずしも整合的でないとも指摘されている。」との記述がある。
4 開示府令の改正規定の適用は、次のとおりである。
(1)有価証券報告書:平成21年3月31日に終了する事業年度に係るものから適用される。
(2)有価証券届出書
① 有価証券報告書の提出会社が提出するもの:(1)の有価証券報告書の提出後に提出する有価証券届出書から適用される。
② ①以外のもの:平成21年7月1日以後提出するものから適用される。
「継続企業の前提に関する注記」に係る財務諸表等規則等の改正の要点
金融庁総務企画局企業開示課主任企業会計専門官 平松 朗
金融庁総務企画局企業開示課企業会計第一係 山下祐士
Ⅰ.はじめに
今般、企業会計審議会から「監査基準の改訂に関する意見書」(平成21年4月9日付)が公表され、継続企業(ゴーイング・コンサーン)の前提の注記に関する監査基準の改訂が行われるとともに、4月20日付で「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」(平成21年内閣府令第27号)が公布され、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(以下「財務諸表等規則」という)および「企業内容等の開示に関する内閣府令」(以下「開示府令」という)など内閣府令等関係規定についても改正が行われた。
この背景には、本年2月に行われた企業会計審議会企画調整部会からの「我が国における国際会計基準の取扱いについて(中間報告)(案)」の公表がある。
わが国企業に対する国際会計基準(IFRS)の任意適用が早ければ平成22(2010)年3月期にも想定されるなか、鋭意、会計基準のコンバージェンスが進められているが、IFRSにおいては、継続企業の前提の注記が会計基準として定められている。IFRSで財務報告をする会社が現実化することを踏まえると、開示内容を整合させないとわが国会計基準で財務報告をする会社との間で比較しにくい状況が生じるため、整合させるための検討が必要であると考えられた。
また、監査基準の分野でも、国際会計士連盟(IFAC)の国際監査・保証基準審議会(IAASB)により明瞭性プロジェクト(クラリティ・プロジェクト)が進められてきたが、わが国がクラリティ・プロジェクトに対応していくなかで、継続企業の前提の注記がわが国監査基準と国際監査基準(ISA)との差異として指摘されていた。
さらに、継続企業の前提の注記に関するわが国実務では、債務超過や連続営業損失など一定の事象や状況が存在する場合に形式的に注記を求める傾向にあり、国際的な実務と必ずしも整合的でないとの指摘もある。
こうしたことから、今般、投資者に対してより有用な情報を提供し、また、国際的な開示・監査基準や実務との整合性を確保する観点から、一定の事象や状況が存在する場合であって、経営者等の対応策等を勘案してもなお「継続企業の前提に重要な不確実性」がある場合に限って、継続企業の前提に関する注記を求めるよう監査基準や内閣府令が改正されたものである。加えて、有価証券報告書におけるいわゆるリスク情報やMD&A情報についても、それらを充実させるための改正が行われた。
これら一連の改正事項は、基本的に平成21年3月31日以後終了する事業年度から適用される。
以下では、改正の概要を解説することとするが、文中意見にわたる部分は私見であることをあらかじめ申し添える。
Ⅱ.財務諸表等規則等の改正
1.「継続企業の前提に関する注記」の導入
(1)導入の経緯 「継続企業の前提に関する注記」は、財務諸表等規則の平成14年10月18日付の改正の際に新設されたものである。
この改正は、平成14年1月25日付で「監査基準の改訂に関する意見書」が企業会計審議会から公表されたことを受けて行われた。この意見書により監査基準は全面的に改訂されたが、そのなかで、企業が将来にわたって事業活動を継続するとの前提(継続企業の前提)に関する重要な疑義に対する監査人の対応が新たに定められた。同意見書においては、継続企業の前提に関する事項を財務諸表において注記することが提言されている。
継続企業の前提に関する注記については、国際会計基準(IAS)(脚注1)のように会計基準においてその注記内容が定められているものがある。他方、米国においては、会計基準は定められておらず、監査基準に基づく開示・監査実務が行われている(脚注2)。
わが国においては、企業会計審議会の議論の過程で、開示の基準は会計基準ではなく法令により手当てされることになり、結局、財務諸表等規則等で規定されることとなった。
(2)旧規定の内容 旧規定は、「貸借対照表日において、債務超過等財務指標の悪化の傾向、重要な債務の不履行等財政破綻の可能性その他会社が将来にわたつて事業を継続するとの前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況が存在する場合」に財務諸表に継続企業の前提に関する注記を行うこととされた(財務諸表等規則旧8条の27)。
また、「重要な疑義を抱かせる事象又は状況」を具体的にするために、監査基準の改訂に関する意見書の前文を参考に、「『財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則』の取扱いに関する留意事項について」(以下「財規ガイドライン」という)が設けられた。
財務諸表等規則および財規ガイドラインに規定された事象や状況を整理すると、次のようになる。
①債務超過、②重要な債務の不履行、③売上高の著しい減少、④継続的な営業損失の発生、⑤継続的な営業キャッシュ・フローのマイナス、⑥重要な債務の返済の困難性、⑦新たな資金調達が困難な状況、⑧取引先からの与信の拒絶、⑨事業の継続に不可欠な重要な資産の毀損または喪失もしくは権利の失効、⑩重要な市場または取引先の喪失、⑪巨額の損害賠償の履行、⑫法令等に基づく事業の制約等。
また、旧規定においては、注記内容として次の4号が列記されていた(財務諸表等規則旧8条の27)。
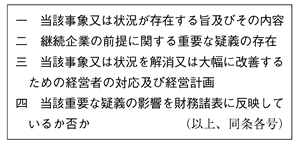 なお、旧第4号においては、「当該重要な疑義の影響を財務諸表に反映しているか否か」が開示事項とされているが、日本公認会計士協会監査委員会報告第74号「継続企業の前提に関する開示について」においては、「財務諸表は継続企業を前提として作成されており、当該重要な疑義の影響を財務諸表に反映していない」旨を注記することとされていた。
なお、旧第4号においては、「当該重要な疑義の影響を財務諸表に反映しているか否か」が開示事項とされているが、日本公認会計士協会監査委員会報告第74号「継続企業の前提に関する開示について」においては、「財務諸表は継続企業を前提として作成されており、当該重要な疑義の影響を財務諸表に反映していない」旨を注記することとされていた。(3)日本公認会計士協会の対応 日本公認会計士協会は、旧規定公布の直後、平成14年11月6日付で上記・監査委員会報告第74号を公表しており、これが実質的に開示実務のよりどころとなっていた。
同報告は、「単独で又は複合して継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況」として、図表1に掲げる20項目を列挙しているが、これらの項目が継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象または状況であり、「当該事象又は状況の解消又は大幅な改善に重要な不確実性が残るために、継続企業の前提に関する重要な疑義が認められるか否かを、総合的に判断する必要がある」とされており、重要な不確実性の存否を、疑義の存否に係らしめていた。
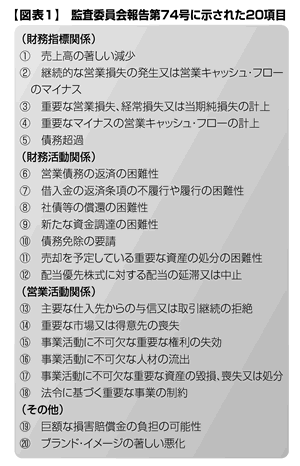 同報告によれば、これらの事象または状況が貸借対照表日後に解消または大幅に改善した場合もしくは当該事象または状況が変化した場合には、その旨および経緯を注記に含めて記載することが必要とされた。
同報告によれば、これらの事象または状況が貸借対照表日後に解消または大幅に改善した場合もしくは当該事象または状況が変化した場合には、その旨および経緯を注記に含めて記載することが必要とされた。また、貸借対照表日後に事象または状況が発生した場合には、後発事象として開示されることとされていた。
2.今回の改正内容 「継続企業の前提に関する注記」に関する規定は、平成21年4月20日付の財務諸表等規則等の改正により大幅に修正された(財務諸表等規則新8条の27等参照)。
上述のように、これまでは「継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況」があるか否かという、いわば形式的な基準によって、継続企業の前提に関する注記の要否が判断される実務が行われる傾向にあった。
たとえば、貸借対照表日において債務超過や重要な債務の不履行のみならず、継続的な営業損失の発生や重要な営業損失の計上といった事象や状況が認められれば、ほぼ自動的に重要な疑義を抱かせる事象や状況が存在するものとして、注記が求められる実務が行われていたところである。
昨年秋以降の世界的な景気の後退もあり、企業業績が急激に悪化したため、かなりの数の注記が行われるようになった。金融機関との間で、注記が付されていないことが融資条件になっているケースがあることから、形式的な発想で注記を付けることの問題点が一層クローズ・アップされたきらいもある。
また、注記がされたうえで、監査報告書を作成する際に、監査人が経営者の対応や経営計画の合理性を検討し、最終的に監査人による意見が表明されるという仕組みになっているが、今回の改正では、国際会計基準や国際監査基準などに合わせ、このようなプロセスを見直すこととした(図表2参照)。
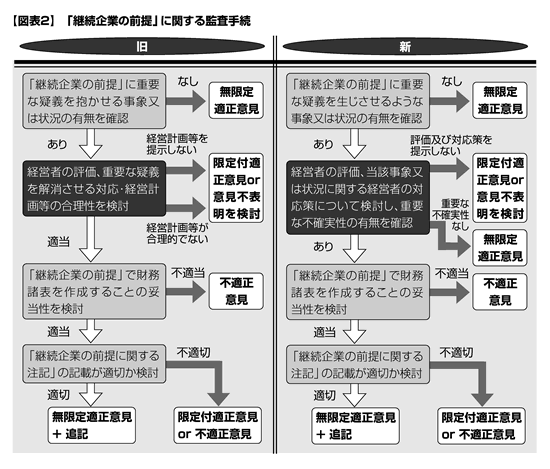 具体的には、「継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況」が認められる場合は、まず、経営者がその事象や状況を解消し、または改善するための対応策を検討、評価することになる。そして、このような対応策を講じてもなお継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められるときに注記が必要となる(図表3参照)。
具体的には、「継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況」が認められる場合は、まず、経営者がその事象や状況を解消し、または改善するための対応策を検討、評価することになる。そして、このような対応策を講じてもなお継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められるときに注記が必要となる(図表3参照)。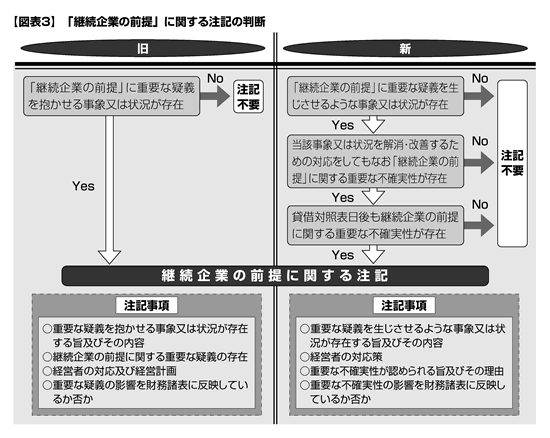 条文(財務諸表等規則8条の27)に沿って説明すると、この改正により、まず、形式的な実務を招きやすい「債務超過等財務指標の悪化の傾向、重要な債務の不履行等財政破綻の可能性」という例示部分を削除した。
条文(財務諸表等規則8条の27)に沿って説明すると、この改正により、まず、形式的な実務を招きやすい「債務超過等財務指標の悪化の傾向、重要な債務の不履行等財政破綻の可能性」という例示部分を削除した。また、「……事象又は状況が存在する場合であつて、当該事象又は状況を解消し、又は改善するための対応をしてもなお継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められるときは……」という文言を挿入し、新しいプロセスの考え方を具体的に条文化している。
さらに、「ただし、貸借対照表日後において、当該重要な不確実性が認められなくなつた場合は、注記することを要しない。」というただし書を設けている。
これは、貸借対照表日後において重要な不確実性が認められなくなった場合には、むしろ注記をしない方が有用な情報になる面があるという考え方に基づく。
また、貸借対照表日後に新たな事象または状況に起因する重要な不確実性が認められた場合には、重要な後発事象の注記としての検討が行われることになる(財規ガイドライン8の27-5、日本公認会計士協会監査・保証実務委員会報告第76号参照)。
財務諸表等規則8条の27第1号から第4号までの注記の内容も「重要な疑義」から「重要な不確実性」に改正され、実務のプロセスに合わせて、各号の順番も改正され、旧第2号と旧第3号の順番が入れ替えられた。
財規ガイドラインについても、財務諸表等規則に応じた用語等の改正が行われたほか、「総合的かつ実質的に判断を行うものとし、……事象又は状況が存在するか否かといった画一的な判断を行うことのないよう留意する」旨の規定が新設された(財規ガイドライン8の27-3)。
Ⅲ.開示府令の改正
財務諸表等規則等の改正と同時に開示府令等の改正が行われた。
開示府令第2号様式(有価証券届出書)の記載上の注意の(33)および(36)が改正され、b項が追加・挿入されている(他の有価証券届出書および有価証券報告書の様式では、基本的に第2号様式の記載上の注意の(33)および(36)に準じて記載することとされているため、各様式についても同様の改正となる)。
1.「事業等のリスク」等の開示 「事業等のリスク」の開示は、平成15年3月31日に公布され、同年4月1日より施行された開示府令の改正に際して導入され、有価証券報告書については施行日以後開始する事業年度に係るものから適用されたので、3月決算会社については平成16年3月期の有価証券報告書から適用された。
この平成15年改正により、「事業の内容」「経理の状況」等に関する事項のうち、投資判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事象などリスク情報の記載を求め、また、「財政状態及び経営成績の分析」(MD&A)として経営者による財政・経営成績の分析についての記載を求めることとされた。
今回の改正では、「事業等のリスク」(リスク情報)の記載上の注意として、継続企業の前提に「重要な疑義を生じさせるような事象又は状況その他提出会社の経営に重要な影響を及ぼす事象(重要事象等)が存在する場合」には、その旨、その内容を具体的に、かつ投資者にわかりやすく記載することとする規定が新設された。
また、「財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析」(MD&A)の記載上の注意として、リスク情報として重要事象等を記載した場合には、「当該重要事象等についての分析・検討内容及び当該重要事象等を解消し、又は改善するための対応策を具体的に」記載することを求める規定が新設された(図表4参照)。
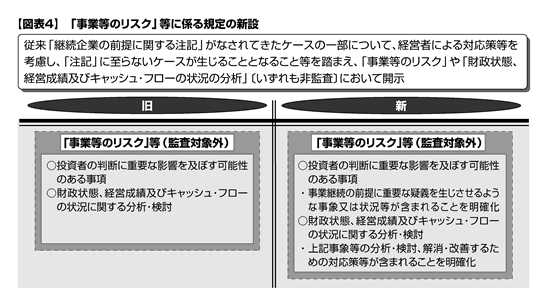 2.個別ガイドラインの改正等
2.個別ガイドラインの改正等(1)「事業等のリスク」に関する取扱いガイドラインの改正 これらの改正に併せて、企業内容等開示ガイドラインの個別ガイドラインである「『事業等のリスク』に関する取扱いガイドライン」が改正されている。
重要事象等に関しては、その会社の経営への影響も含めて具体的な内容を記載することとされた。このうち、継続企業の前提に「重要な疑義を生じさせるような事象又は状況」が生じた場合に、その内容が確実に記載されるよう、監査委員会報告第74号の「4継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事業又は状況」を参考に例示列挙された次の事象または状況(図表1参照)が単独でまたは複合的に生ずることによってこれに該当し得る旨が示された。ただし、「事業等のリスク」の記載にあたっては、これらの例示にとらわれることなく、積極的に記載することが望まれるところである。
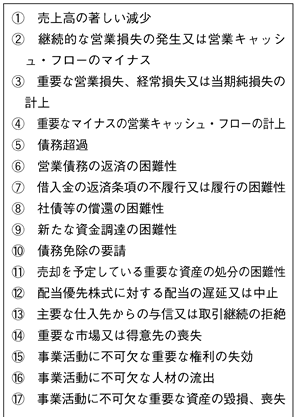
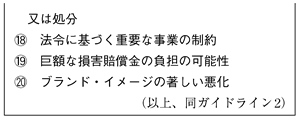 (2)「財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析」に関する取扱いガイドラインの新設
さらに、個別ガイドラインのⅡとして「『財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析』に関する取扱いガイドライン」が新設された。
(2)「財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析」に関する取扱いガイドラインの新設
さらに、個別ガイドラインのⅡとして「『財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析』に関する取扱いガイドライン」が新設された。すなわち、「当該重要事象等を解消し、又は改善するための対応策」については、提出会社の「財務の健全性に悪影響を及ぼしている、又は及ぼし得る要因に関して経営者が講じている、又は講じる予定の対応策の具体的な内容(実施時期、実現可能性の程度、金額等を含む。)」を記載することとされている。
また、対応策の例としては、①資産の処分に関する計画、②資金調達の計画、③債務免除の計画、④その他が挙げられている。対応策の例は、監査基準委員会報告書第22号「継続企業の前提に関する監査人の検討」を参考にしており、「その他」が付け加えられている。
このような開示府令等の改正の方向も、リスク情報等が充実している欧米の開示事例を範にしており、投資者保護上も望ましいものと考えられる。
Ⅳ.監査基準の改訂
監査基準についても、企業会計審議会から平成21年4月9日付で公表された「監査基準の改訂に関する意見書」により、上述の考え方に沿って継続企業の前提に関する監査基準の改訂が行われている。
改訂監査基準の前文では、「監査人は、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在すると判断した場合には、当該事象又は状況に関して合理的な期間について経営者が行った評価及び対応策について検討したうえで、なお継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められるか否かを確かめなければならない」とされ、また、監査報告書についても「継続企業の前提に関する重要な不確実性」が認められるときの財務諸表の記載に関して意見を表明することとされた(脚注3)。
これに従い、日本公認会計士協会の関係する実務指針(監査委員会報告第74号、監査基準委員会報告書第22号等)も見直されている(これについては、別途の解説が行われるかと思われる)。
監査基準改訂の意義等詳細は、監査基準の専門家による解説を参照いただきたいが、1点だけ付言すると、今回は、「合理性」という用語が、制定当初の一応の合理性という意味ではなく経済的な合理性というような想定外のリジッドな意味に受け取られる傾向が強かったので、改訂監査基準上、極力「合理性」という用語を使用しないこととされた。
たとえば、実施基準の「三 監査の実施」の「経営計画等の合理性を検討」するという部分が「対応策について検討」というように改訂されている。
また、報告基準においても、経営者が「合理的な経営計画等を提示しないときには」意見不表明を検討するという文言が、「評価及び対応策を示さないときには、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められるか否かを確かめる十分かつ適切な監査証拠を入手できないことがあるため」と改訂されており、経営者から合理的な経営計画が示されない場合に、直ちに意見不表明とするような実務については見直しを求めている。
Ⅴ.おわりに
以上に述べたような一連の改正により、有価証券報告書における「事業等のリスク」および「財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析」と財務諸表における継続企業の前提の注記とを一体として、経営上のリスクを開示することになる。
また、継続企業の前提の注記については、改訂監査基準による監査手続が行われることにより注記内容の確度が向上し、もって、一層投資者保護が図られることになると思われる。
これらの改正は、平成21年3月期決算から適用される(脚注4)。関係者には、検討する時間は短期間であろうとは思うが、以上のような改正の趣旨を汲み取っていただき、積極的な取組みをお願いしたい。
なお、中間監査基準および四半期レビュー基準についても、企業会計審議会において改訂を検討することが改訂監査基準の前文において明記されており、これに応じて四半期財務諸表等規則・中間財務諸表等規則等の改正も予定されていることを付言しておく。
(ひらまつ・あきら/やました・ゆうじ)
脚注
1 国際会計基準第1号第25項においては、「継続企業」として、「財務諸表を作成するに際して、経営者は継続企業として存続する能力があるかどうかを検討しなければならない。……経営者がこの検討を行う際に、当該企業の継続企業としての存続能力に対して重大な疑問を生じさせるような事象又は状態に関する重要な不確定事項を発見したときは、その不確定事項を開示しなければならない。……」と規定されている。
2 米国財務会計基準審議会(FASB)は、昨年10月9日付で公開草案「ゴーイング・コンサーン」を公表している。公開草案第7項において開示内容が定められているが、注記の要否の部分については、IASとほぼ同文である。記載事項は、①企業の継続能力に疑義を生じさせる事象または状況、②当該事象または状況の影響、③経営者の当該事象または状況の重大性の評価および緩和の要素、④事業の中断可能性、⑤経営者の不確実性の影響の緩和への改善策および企業の継続能力に対する重大な疑義を緩和するための対応策、⑥資産額の回収可能性または分類、負債の額または分類とされている。
3 「監査基準の改訂について」(平成21年4月9日・企業会計審議会)においては、「継続企業の前提に関する注記の開示を規定している財務諸表等規則等やその監査を規定する監査基準において、一定の事象や状況が存在すれば直ちに継続企業の前提に関する注記及び追記情報の記載を要するとの規定となっているとの理解がなされ、一定の事実の存在により画一的に当該注記を行う実務となっているとの指摘がある。また、それらの規定や実務は国際的な基準とも必ずしも整合的でないとも指摘されている。」との記述がある。
4 開示府令の改正規定の適用は、次のとおりである。
(1)有価証券報告書:平成21年3月31日に終了する事業年度に係るものから適用される。
(2)有価証券届出書
① 有価証券報告書の提出会社が提出するもの:(1)の有価証券報告書の提出後に提出する有価証券届出書から適用される。
② ①以外のもの:平成21年7月1日以後提出するものから適用される。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -

Copyright (C) 2019
SHINNIPPON-HOKI PUBLISHING CO.,LTD.





















