解説記事2009年05月04日 【ニュース特集】 出向負担金に係る合理性と寄附金認定の境界線を探る(2009年5月4日号・№305)
当局による否認事例を基に検証
出向負担金に係る合理性と寄附金認定の境界線を探る
企業が経営上の理由から、従業員の解雇回避などを目的にグループ会社に出向させるケースも多いと思われる。その際、出向元法人が出向者に対する給与等を負担し、寄附金と認定されずに損金算入するためには、その負担することに合理的な理由が必要となる。
今回の特集では、税務当局が出向元法人の出向負担金を寄付金認定した事例を基に、出向負担金に係る合理的な理由と寄附金認定の境界線を検証する。
出向元法人が給与負担する場合の取扱い 出向元法人が出向者に対する給与等を負担する場合、その負担することに、給与較差の補てんなどの合理的な理由があれば、出向者に対する給与等の支給として、負担金を損金算入することが可能だ。なお、給与較差の補てんに関しては、法基通9-2-47(出向者に対する給与の較差補てん)に定められている。また、給与の較差補てんのほか、出向元法人が出向者の給与等を負担する合理的な理由として、たとえば、出向者の出向先法人での勤務が出向元法人への労務提供を包含している場合、出向者の労務提供の反対給付として出向元法人に特別な経済的利益が認められる場合などが挙げられる(左掲参照)。
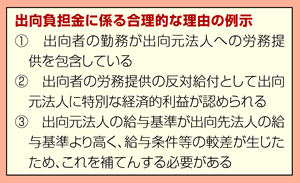
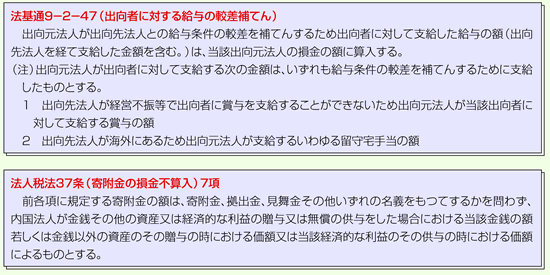 合理的な理由がない場合、寄附金認定のリスク
一方、上記のような出向負担金に係る合理的な理由が存在しない場合、その負担金については、出向元法人から出向先法人に対する贈与とされ、寄附金(法法37条7項)に該当すると判断されることになる。
合理的な理由がない場合、寄附金認定のリスク
一方、上記のような出向負担金に係る合理的な理由が存在しない場合、その負担金については、出向元法人から出向先法人に対する贈与とされ、寄附金(法法37条7項)に該当すると判断されることになる。
雇用調整等を目的として子会社への出向を実施 ここで、出向元法人が負担した子会社出向社員の給与について、税務当局がその負担に合理性を認めず、寄附金と認定した事例を紹介する。
問題となったのは、X法人(電気工事、電気通信工事、土木工事、塗装工事等の請負、企画、設計、管理業務)が平成16年3月期~平成18年3月期に損金の額に算入した、X社の子会社(Y社)への出向社員に係る給与についてである。
Y社は、不動産の売買、賃貸およびそれらの仲介、管理等を主な業務とし、不動産事業部、ビルサービス事業部、保険事業部、総務部等を有しており、各地に営業所も有していた。
X社から子会社Y社への出向実施に関する経緯は、以下のとおり。
X社は、就業規則により、業務上必要な場合には、社員、特別社員および嘱託に社外出向を命じることができる。そして、X社は、営業工事部門の業績が大幅に悪化したことから、業績回復を図るため、営業工事部門および事務部門を中心とした要員の流動化(出向)を実施することを計画。そのなかでX社は、要員の流動化について、ローコスト体質の向上とともに、「社員の雇用を守る」という最大目標の維持のため、支店等との調整を行ったうえで、実施に移した。
組織再編成により工事部門に出向者が発生 一方、Y社はX社のOBの受入れ会社として存続してきたが、上記のX社のグループ法人を含めた組織再編成により営業所に工事部門を設置し、X社などから電気工事等を受注することになった。そのため、Y社では、不動産事業部、ビルサービス事業部、保険事業部、総務部等へのX社社員の出向に加えて、平成14年5月以降に、営業所に新たに設置された工事部門にもX社からの出向者が発生した。
なお、Y社の平成16年3月期~平成18年3月期におけるX社からの受注工事金額およびY社独自の営業に基づく受注工事金額については、図表1のとおり。
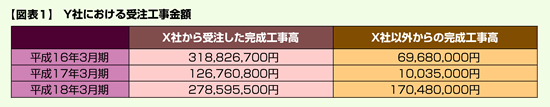
「出向覚書」では、出向先法人の給与負担額を50%に
協定書に、X社の業務に従事する旨の特約事項の記載なし 出向負担金と寄附金の関係で重要となる出向契約の内容を確認しておこう。
X社は、Y社との間に、平成11年4月11日付で、X社からY社に出向させる社員の取扱いに関する協定書(出向協定書)を締結しており、出向社員の給与については、X社の規程によりX社が支給するとしている。そして、出向社員が出向中にX社の業務に従事する旨の特約事項の記載はない。
X社は「出向覚書」において、X社がY社から受領する出向者に係る月額のY社の給与負担額に関して、出向者の平均年齢(50歳)を標準とするX社の使用人の年間給与等の支給額とY社の社員の年間給与等支給額の比率がおおむね2:1となることから、一部の出向者を除いて、出向時における出向社員に関するX社給与等の額の50%相当額をY社からの給与負担額とした。
なお、X社とY社との間の出向の概要および協定書の要旨は、図表2を参照。
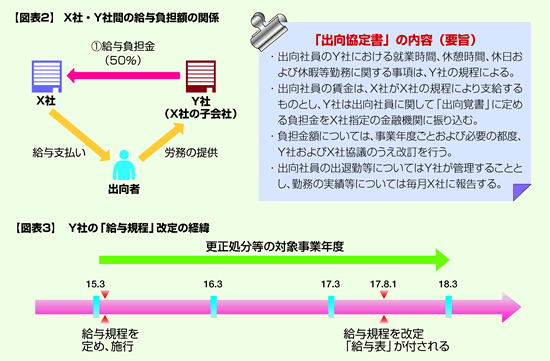
給与規定の改定前は、「給与表」存在せず 給与較差の補てんに関する合理的な理由の有無の判定においては、給与規程の内容も重要な要素となる。
X社は、昭和56年6月1日に社員の給与に関する給与規程を定め、施行している。一方、Y社は、平成15年4月1日に社員の給与に関する給与規程を定めて施行したが、その後、平成17年8月に給与規程を改定。改定後の給与規程には、社員の年齢に対応する年齢給と成績に対応する成績給を組み合わせた給与表が付されている(図表3参照)。
なお、Y社の平成16年3月期~平成18年3月期におけるX社からの出向社員以外の社員は、X社を退職後に雇用された再雇用者、派遣会社からの従業員およびパート等から構成されており、Y社の給与規程の給与表を適用するプロパー社員はいない。
当局、経済的利益の無償の供与と認定 こうした状況において、X社は出向者に対するX社の給与負担額(支払額とY社負担額との差額)、平成16年3月期~平成18年3月期の法人税の所得金額の計算上、給与等の額に含めて計算した。これに対して、税務当局はX社が給与負担金を負担したことについて、X社がY社に対する債権の一部を放棄したものであり、経済的利益の供与と認定し、法人税の更正処分等を行った。税務当局は、認定の主な理由として、①出向社員はY社で専ら勤務しており、給与は労務の対価であることから、出向社員給与は、その全額をYが負担すべきものである、②X社からY社への出向が出向社員の雇用回避等を行うための合理的な理由にもよるものだとしても、そのことが直ちにX社が給与負担額を負担する合理的な理由とはならないこと、③出向によりX社にとってビルの修繕工事等の受注機会が拡大したとしても、それはYの業務から結果的、反射的に生じただけであることなどを挙げている。
審査請求では、審判所が更正処分等を適法と判断 上記のX社・Y社間の出向に係る税務当局の更正処分に対しては、X社から審査請求がなされ、国税不服審判所は裁決(東裁(法・諸)平20第112号)で、X社には給与負担額を負担する合理的理由があるとは認められないとして、当局の更正処分等を適法と判断している。
審判所の裁決では、まず出向負担について、判断法人の使用人が他の法人に出向した場合、その出向者は、たとえ出向元法人との間に雇用関係が維持されていたとしても、その労務は出向先法人に対して提供されるものであることから、その労務に対する対価である給与等については、原則として、出向先法人が負担することになるとしている。
そして、出向元法人が出向者に対する給与等を負担することに合理的な理由がある場合、その負担金は寄附金には該当しないことになるとし、その合理的な理由として、前述(4頁参照)の3項目を例示し、X社とY社の間の出向に係るX社の出向負担金に、合理的な理由があるか否かを判断している。以下、その具体的な内容を確認していく。
経済的合理性等について X社は、審査請求において、X社からY社への出向は、①X社における雇用調整、Y社における労働力の補完、X社の組織の再編成、X社とY社との連携強化等を主な目的としていること、②X社には、人件費の負担軽減、人材流出の防止、Y社が行うビルメンテナンス業務を通じてX社のビル修繕工事等の受注機会の拡大が期待できるメリットがあること、③Y社には、事業規模および事業範囲を拡大するなか、能力・経験のある人材確保、新規事業に関するノウハウの取得メリットがあることから、X社の給与負担額を50%としたものであり、そこにX社による給与負担に経済的合理性があると主張した。
しかし、審判所は、前述の合理性の基準に照らし、その出向が雇用調整を目的に行われるものであっても、それは、出向社員がY社で提供する労務の反対給付となるものではないと指摘。また、Y社が行うビルメンテナンス業務を通じてX社のビル修繕工事等の受注機会の拡大が期待できるメリットは否定できないものの、それはあくまでも期待であり、出向社員の労務提供の反対給付としてX社に特別な経済的利益を与えているとみることはできないと判断した。
給与較差について X社とY社との間に給与較差が存在するか否かについて、X社は、出向後も出向者とX社の間に雇用関係が継続しており、出向者に対して雇用契約に基づき出向前と同様の給与を支払う義務を負っており、また、出向者の労務が専らY社に提供されているとしても、X社がY社に対し、出向者に出向前と同様の給与を支払うことを強制することは、特別の合意がない限り不可能であることから、X社が給与を負担することは、その金額が社会通念上不当な場合を除いて、法的合理性を有していると主張した。
これに対して審判所は、次の事実からX社・Y社間に給与較差があるものと認められないとした。①Y社の平成16年3月期~平成18年3月期の社員の多くがX社からの出向社員であり、X社からの出向者以外の社員は、X社を退職した再雇用者、派遣会社からの従業員およびパート等から構成され、Y社の給与規程における給与表を適用するプロパー社員はいないこと、②給与条件の較差の基本となる給与表の存在が、平成17年7月31日まで確認できず、その給与表が適用となる新規プロパー社員が平成18年4月1日から採用されていることから、上記各事業年度において、給与表は実効性のあるものとは認められないこと。
出向社員の勤務内容等について 出向者の勤務が出向元法人への労務提供を包含しているか否かについて、審判所は、X社とY社との間の出向協定書には、出向社員が出向中、X社の業務に従事するなどと特約事項がなく、出向した工事担当者は、工事の施工管理業務等を遂行する能力を有していること、工事担当者のY社への出向に伴い、Y社に完成工事高が発生するとともに、Y社はX社からの受注工事以外の工事も行っていることを認定。
また、工事担当者がX社の指示に基づいて業務を行っている実態、X社の外注工事でX社の社員が現場で工事担当者に指示することがあっても、それはX社に責任施工する元請業者としての責任があることから不自然なことではなく、その指示をもってX社が出向者に雇用者としての立場で指揮命令しているとみることは相当ではないとした。
そして、X社が給与等の支給目的以外に工事担当者の活動を日々管理していた事実も認められず、X社が工事担当者を特別な指揮管理下に置いていたとみることはできないとして、出向した工事担当者のY社での勤務は、X社への労務提供を包含しているものではなく、Y社の事業本来の業務を行っていたと判断した。
出向負担金に係る合理性と寄附金認定の境界線を探る
企業が経営上の理由から、従業員の解雇回避などを目的にグループ会社に出向させるケースも多いと思われる。その際、出向元法人が出向者に対する給与等を負担し、寄附金と認定されずに損金算入するためには、その負担することに合理的な理由が必要となる。
今回の特集では、税務当局が出向元法人の出向負担金を寄付金認定した事例を基に、出向負担金に係る合理的な理由と寄附金認定の境界線を検証する。
出向元法人が給与負担する場合の取扱い 出向元法人が出向者に対する給与等を負担する場合、その負担することに、給与較差の補てんなどの合理的な理由があれば、出向者に対する給与等の支給として、負担金を損金算入することが可能だ。なお、給与較差の補てんに関しては、法基通9-2-47(出向者に対する給与の較差補てん)に定められている。また、給与の較差補てんのほか、出向元法人が出向者の給与等を負担する合理的な理由として、たとえば、出向者の出向先法人での勤務が出向元法人への労務提供を包含している場合、出向者の労務提供の反対給付として出向元法人に特別な経済的利益が認められる場合などが挙げられる(左掲参照)。
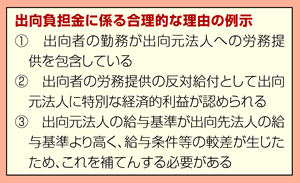
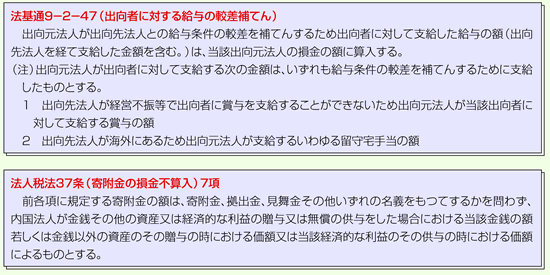 合理的な理由がない場合、寄附金認定のリスク
一方、上記のような出向負担金に係る合理的な理由が存在しない場合、その負担金については、出向元法人から出向先法人に対する贈与とされ、寄附金(法法37条7項)に該当すると判断されることになる。
合理的な理由がない場合、寄附金認定のリスク
一方、上記のような出向負担金に係る合理的な理由が存在しない場合、その負担金については、出向元法人から出向先法人に対する贈与とされ、寄附金(法法37条7項)に該当すると判断されることになる。雇用調整等を目的として子会社への出向を実施 ここで、出向元法人が負担した子会社出向社員の給与について、税務当局がその負担に合理性を認めず、寄附金と認定した事例を紹介する。
問題となったのは、X法人(電気工事、電気通信工事、土木工事、塗装工事等の請負、企画、設計、管理業務)が平成16年3月期~平成18年3月期に損金の額に算入した、X社の子会社(Y社)への出向社員に係る給与についてである。
Y社は、不動産の売買、賃貸およびそれらの仲介、管理等を主な業務とし、不動産事業部、ビルサービス事業部、保険事業部、総務部等を有しており、各地に営業所も有していた。
X社から子会社Y社への出向実施に関する経緯は、以下のとおり。
X社は、就業規則により、業務上必要な場合には、社員、特別社員および嘱託に社外出向を命じることができる。そして、X社は、営業工事部門の業績が大幅に悪化したことから、業績回復を図るため、営業工事部門および事務部門を中心とした要員の流動化(出向)を実施することを計画。そのなかでX社は、要員の流動化について、ローコスト体質の向上とともに、「社員の雇用を守る」という最大目標の維持のため、支店等との調整を行ったうえで、実施に移した。
組織再編成により工事部門に出向者が発生 一方、Y社はX社のOBの受入れ会社として存続してきたが、上記のX社のグループ法人を含めた組織再編成により営業所に工事部門を設置し、X社などから電気工事等を受注することになった。そのため、Y社では、不動産事業部、ビルサービス事業部、保険事業部、総務部等へのX社社員の出向に加えて、平成14年5月以降に、営業所に新たに設置された工事部門にもX社からの出向者が発生した。
なお、Y社の平成16年3月期~平成18年3月期におけるX社からの受注工事金額およびY社独自の営業に基づく受注工事金額については、図表1のとおり。
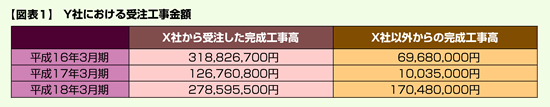
「出向覚書」では、出向先法人の給与負担額を50%に
協定書に、X社の業務に従事する旨の特約事項の記載なし 出向負担金と寄附金の関係で重要となる出向契約の内容を確認しておこう。
X社は、Y社との間に、平成11年4月11日付で、X社からY社に出向させる社員の取扱いに関する協定書(出向協定書)を締結しており、出向社員の給与については、X社の規程によりX社が支給するとしている。そして、出向社員が出向中にX社の業務に従事する旨の特約事項の記載はない。
X社は「出向覚書」において、X社がY社から受領する出向者に係る月額のY社の給与負担額に関して、出向者の平均年齢(50歳)を標準とするX社の使用人の年間給与等の支給額とY社の社員の年間給与等支給額の比率がおおむね2:1となることから、一部の出向者を除いて、出向時における出向社員に関するX社給与等の額の50%相当額をY社からの給与負担額とした。
なお、X社とY社との間の出向の概要および協定書の要旨は、図表2を参照。
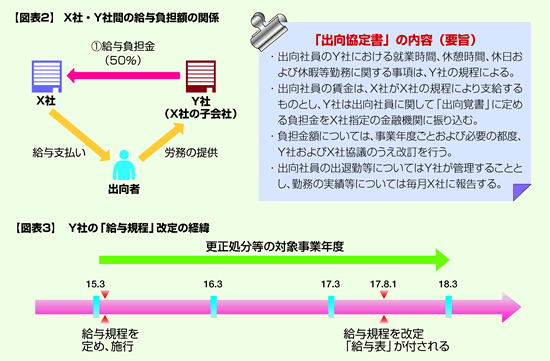
給与規定の改定前は、「給与表」存在せず 給与較差の補てんに関する合理的な理由の有無の判定においては、給与規程の内容も重要な要素となる。
X社は、昭和56年6月1日に社員の給与に関する給与規程を定め、施行している。一方、Y社は、平成15年4月1日に社員の給与に関する給与規程を定めて施行したが、その後、平成17年8月に給与規程を改定。改定後の給与規程には、社員の年齢に対応する年齢給と成績に対応する成績給を組み合わせた給与表が付されている(図表3参照)。
なお、Y社の平成16年3月期~平成18年3月期におけるX社からの出向社員以外の社員は、X社を退職後に雇用された再雇用者、派遣会社からの従業員およびパート等から構成されており、Y社の給与規程の給与表を適用するプロパー社員はいない。
当局、経済的利益の無償の供与と認定 こうした状況において、X社は出向者に対するX社の給与負担額(支払額とY社負担額との差額)、平成16年3月期~平成18年3月期の法人税の所得金額の計算上、給与等の額に含めて計算した。これに対して、税務当局はX社が給与負担金を負担したことについて、X社がY社に対する債権の一部を放棄したものであり、経済的利益の供与と認定し、法人税の更正処分等を行った。税務当局は、認定の主な理由として、①出向社員はY社で専ら勤務しており、給与は労務の対価であることから、出向社員給与は、その全額をYが負担すべきものである、②X社からY社への出向が出向社員の雇用回避等を行うための合理的な理由にもよるものだとしても、そのことが直ちにX社が給与負担額を負担する合理的な理由とはならないこと、③出向によりX社にとってビルの修繕工事等の受注機会が拡大したとしても、それはYの業務から結果的、反射的に生じただけであることなどを挙げている。
審査請求では、審判所が更正処分等を適法と判断 上記のX社・Y社間の出向に係る税務当局の更正処分に対しては、X社から審査請求がなされ、国税不服審判所は裁決(東裁(法・諸)平20第112号)で、X社には給与負担額を負担する合理的理由があるとは認められないとして、当局の更正処分等を適法と判断している。
審判所の裁決では、まず出向負担について、判断法人の使用人が他の法人に出向した場合、その出向者は、たとえ出向元法人との間に雇用関係が維持されていたとしても、その労務は出向先法人に対して提供されるものであることから、その労務に対する対価である給与等については、原則として、出向先法人が負担することになるとしている。
そして、出向元法人が出向者に対する給与等を負担することに合理的な理由がある場合、その負担金は寄附金には該当しないことになるとし、その合理的な理由として、前述(4頁参照)の3項目を例示し、X社とY社の間の出向に係るX社の出向負担金に、合理的な理由があるか否かを判断している。以下、その具体的な内容を確認していく。
経済的合理性等について X社は、審査請求において、X社からY社への出向は、①X社における雇用調整、Y社における労働力の補完、X社の組織の再編成、X社とY社との連携強化等を主な目的としていること、②X社には、人件費の負担軽減、人材流出の防止、Y社が行うビルメンテナンス業務を通じてX社のビル修繕工事等の受注機会の拡大が期待できるメリットがあること、③Y社には、事業規模および事業範囲を拡大するなか、能力・経験のある人材確保、新規事業に関するノウハウの取得メリットがあることから、X社の給与負担額を50%としたものであり、そこにX社による給与負担に経済的合理性があると主張した。
しかし、審判所は、前述の合理性の基準に照らし、その出向が雇用調整を目的に行われるものであっても、それは、出向社員がY社で提供する労務の反対給付となるものではないと指摘。また、Y社が行うビルメンテナンス業務を通じてX社のビル修繕工事等の受注機会の拡大が期待できるメリットは否定できないものの、それはあくまでも期待であり、出向社員の労務提供の反対給付としてX社に特別な経済的利益を与えているとみることはできないと判断した。
給与較差について X社とY社との間に給与較差が存在するか否かについて、X社は、出向後も出向者とX社の間に雇用関係が継続しており、出向者に対して雇用契約に基づき出向前と同様の給与を支払う義務を負っており、また、出向者の労務が専らY社に提供されているとしても、X社がY社に対し、出向者に出向前と同様の給与を支払うことを強制することは、特別の合意がない限り不可能であることから、X社が給与を負担することは、その金額が社会通念上不当な場合を除いて、法的合理性を有していると主張した。
これに対して審判所は、次の事実からX社・Y社間に給与較差があるものと認められないとした。①Y社の平成16年3月期~平成18年3月期の社員の多くがX社からの出向社員であり、X社からの出向者以外の社員は、X社を退職した再雇用者、派遣会社からの従業員およびパート等から構成され、Y社の給与規程における給与表を適用するプロパー社員はいないこと、②給与条件の較差の基本となる給与表の存在が、平成17年7月31日まで確認できず、その給与表が適用となる新規プロパー社員が平成18年4月1日から採用されていることから、上記各事業年度において、給与表は実効性のあるものとは認められないこと。
出向社員の勤務内容等について 出向者の勤務が出向元法人への労務提供を包含しているか否かについて、審判所は、X社とY社との間の出向協定書には、出向社員が出向中、X社の業務に従事するなどと特約事項がなく、出向した工事担当者は、工事の施工管理業務等を遂行する能力を有していること、工事担当者のY社への出向に伴い、Y社に完成工事高が発生するとともに、Y社はX社からの受注工事以外の工事も行っていることを認定。
また、工事担当者がX社の指示に基づいて業務を行っている実態、X社の外注工事でX社の社員が現場で工事担当者に指示することがあっても、それはX社に責任施工する元請業者としての責任があることから不自然なことではなく、その指示をもってX社が出向者に雇用者としての立場で指揮命令しているとみることは相当ではないとした。
そして、X社が給与等の支給目的以外に工事担当者の活動を日々管理していた事実も認められず、X社が工事担当者を特別な指揮管理下に置いていたとみることはできないとして、出向した工事担当者のY社での勤務は、X社への労務提供を包含しているものではなく、Y社の事業本来の業務を行っていたと判断した。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -

Copyright (C) 2019
SHINNIPPON-HOKI PUBLISHING CO.,LTD.




















