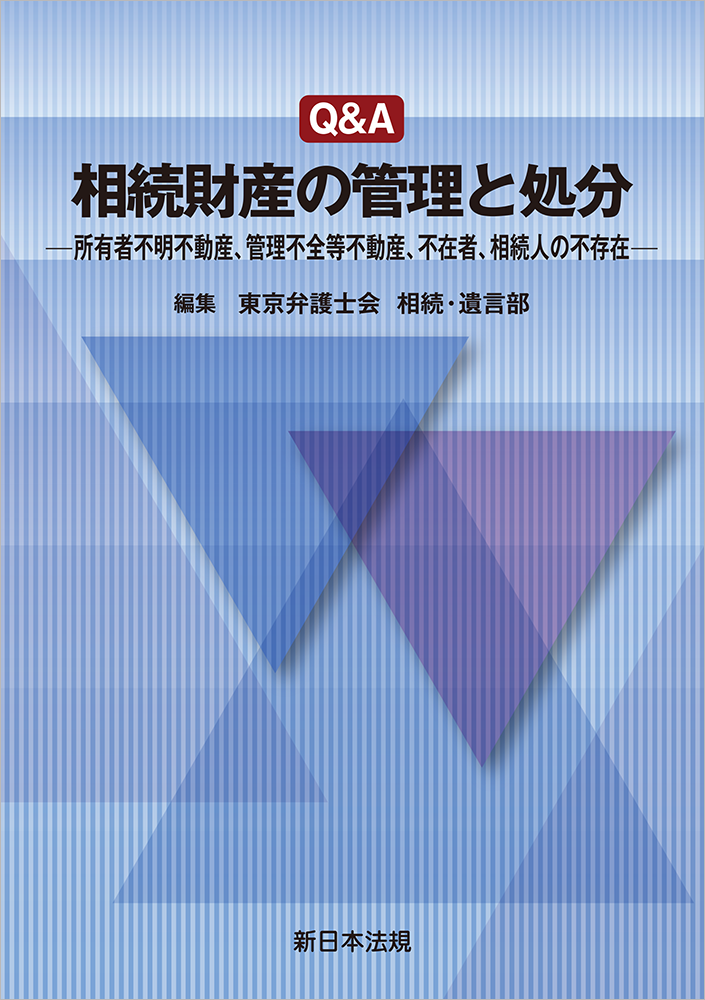解説記事2009年06月01日 【ニュース特集】 無対価による債務超過の子会社の合併等と寄附金課税(2009年6月1日号・№308)
税制適格再編でも債務消滅損益が発生?
無対価による債務超過の子会社の合併等と寄附金課税
景気低迷のなか、債務超過に陥った子会社の合併等を考える企業は少なくないようだ。
ただ、実務家の一部からは、債務超過の子会社を合併等する場合において、包括否認規定の適用や事実認定により、寄附金課税(および債務消滅益に対する課税)を懸念する声も聞かれる。
本特集では、この問題について検証を行った。
1 景気低迷と会社法が背景に 債務超過に陥った子会社の合併等を検討する動きの背景には、景気低迷のほか、会社法により、債務超過の子会社を無対価により合併等することが可能になったことがある。
商法では、資本充実の原則や債権者保護への抵触から、債務超過会社の合併等は「簿価」による場合のみ認め、時価による債務超過会社の合併等は禁止していた。
一方、会社法では、会社の財産の評価は当事会社の判断に委ねるべきであることや、債権者も異議手続によって保護されていることからこれを認め、さらにこれを対価なし(すなわち、被合併法人等の株主に対し、何も資産を交付しない)で実現可能とした。
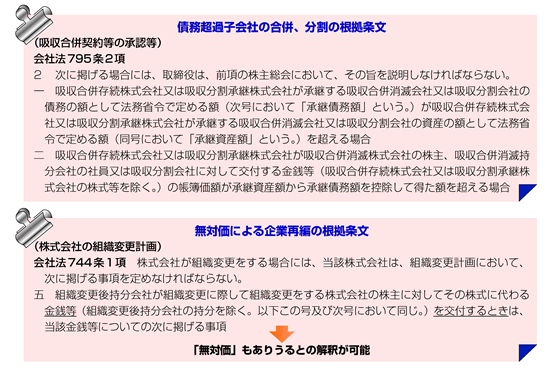
2 無条件に認めれば、親会社の純資産が“無償”で子会社に移転する恐れを指摘する声も このように、債務超過に陥った子会社の合併等は会社法上は可能となったものの、実務家のなかには、税務上、事実認定や包括否認規定の適用による寄附金課税を受けるリスクを指摘する向きもある。
基本的に、無対価(株式の交付の省略)による図1~5のような企業再編においては、合併(親)法人株式以外の資産もしくは分割承継(親)法人株式以外の資産が交付されていないことから、原則として適格再編(法人税法2条12号の8、12号の11)に該当することになる(いずれも、企業再編後の完全支配関係の継続が要件)。
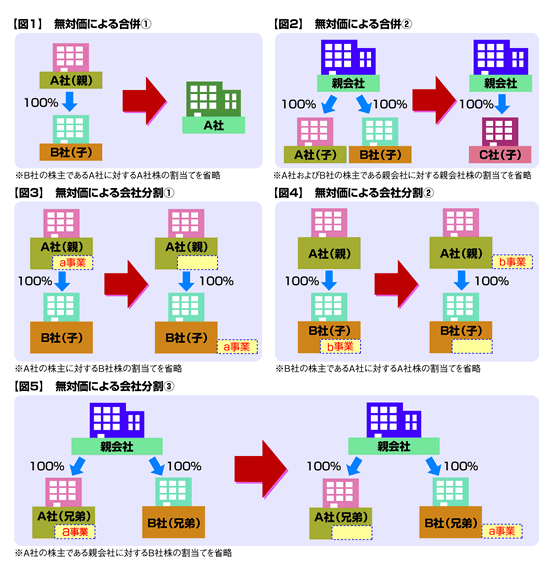 しかし、一部の実務家からは、このような無対価による債務超過の子会社の合併等について、これが無条件に認められるとなれば、親会社の純資産を事実上「無償」で子会社に移転するようなことができてしまうに等しいことから、寄附金課税の問題が生じる可能性があると指摘する声があがっている。
しかし、一部の実務家からは、このような無対価による債務超過の子会社の合併等について、これが無条件に認められるとなれば、親会社の純資産を事実上「無償」で子会社に移転するようなことができてしまうに等しいことから、寄附金課税の問題が生じる可能性があると指摘する声があがっている。
すなわち、無対価による債務超過の子会社の合併等を行うことについて経済合理性、経営上の必要性がない場合には、事実認定や包括否認規定(法人税法132条の2)の適用により、親会社においては寄附金課税、子会社においては債務消滅益が認識されるというものだ。
適格合併等であれば、債務消滅益や債務引受損失は発生しないと理解している向きも多いだろうが、上記の考え方においては、非適格合併等のケース同様、適格合併等においても、合併等直前の事業年度において債務消滅益や債務引受損失を認識したうえで、合併法人等においては、債務消滅益を反映した被合併法人等の株主資本を引き継ぐことになるとされる(図6の仕訳参照)。
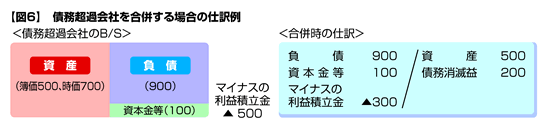
3 「営業権」に関する論点の延長線上に では、実際のところ、包括否認規定等が適用される可能性はどの程度であろうか。
この点を検証するにあたっては、営業権の事例も1つの参考にはなろう。
債務超過会社について「営業権」を認識し、それなりの金額で買収した場合には、税務上、寄附金課税の問題が発生しうる。しかし、そもそも被買収会社の評価、特に事業の評価は主観的な要素を排除できず、たとえば買収会社が被買収会社について、「取引先等との関係」など数字に表れにくい価値を認めたり、「シナジーがある」「経営トップが変われば利益を生む可能性が高い」といった主張のもと、被買収会社の価値を財務上の価値よりも高く評価した場合(すなわち「営業権」の存在を認めた場合)には、課税当局としてもこれを覆すのは容易ではないのが実情だ。
無対価による債務超過の子会社の合併等もこの延長線上にある話といってよいだろう。
すなわち、無対価による債務超過の子会社の合併等については、事実認定や包括否認規定の適用がないとは言い切れないものの(特に法人税法132条の2の文理解釈上は、包括否認規定の適用がないとは言い切れないであろう)、事実上、その適用にはかなりの困難が伴うと考えられる(図7参照)。
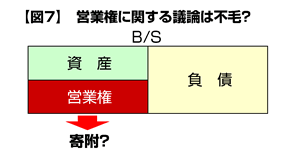
もっとも、営業権の例で触れたように、「適用にかなりの困難が伴う」のは、無対価による債務超過の子会社の合併、分割について経営的、経済合理的な理由が存在すれば、それを課税当局が覆すのは容易ではないからにほかならず、形式上、税制適格であれば、目的の如何に関わらず否認を受けないということではない点に留意したいところだ。
言い換えれば、無対価による債務超過の子会社の合併等においては、少なくともその経営的、経済合理的な理由を持っておくことは、寄附金課税等を回避するための前提条件となろう。
無対価による債務超過の子会社の合併等と寄附金課税
景気低迷のなか、債務超過に陥った子会社の合併等を考える企業は少なくないようだ。
ただ、実務家の一部からは、債務超過の子会社を合併等する場合において、包括否認規定の適用や事実認定により、寄附金課税(および債務消滅益に対する課税)を懸念する声も聞かれる。
本特集では、この問題について検証を行った。
1 景気低迷と会社法が背景に 債務超過に陥った子会社の合併等を検討する動きの背景には、景気低迷のほか、会社法により、債務超過の子会社を無対価により合併等することが可能になったことがある。
商法では、資本充実の原則や債権者保護への抵触から、債務超過会社の合併等は「簿価」による場合のみ認め、時価による債務超過会社の合併等は禁止していた。
一方、会社法では、会社の財産の評価は当事会社の判断に委ねるべきであることや、債権者も異議手続によって保護されていることからこれを認め、さらにこれを対価なし(すなわち、被合併法人等の株主に対し、何も資産を交付しない)で実現可能とした。
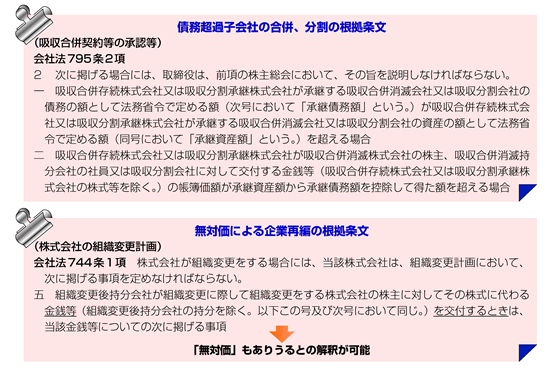
2 無条件に認めれば、親会社の純資産が“無償”で子会社に移転する恐れを指摘する声も このように、債務超過に陥った子会社の合併等は会社法上は可能となったものの、実務家のなかには、税務上、事実認定や包括否認規定の適用による寄附金課税を受けるリスクを指摘する向きもある。
基本的に、無対価(株式の交付の省略)による図1~5のような企業再編においては、合併(親)法人株式以外の資産もしくは分割承継(親)法人株式以外の資産が交付されていないことから、原則として適格再編(法人税法2条12号の8、12号の11)に該当することになる(いずれも、企業再編後の完全支配関係の継続が要件)。
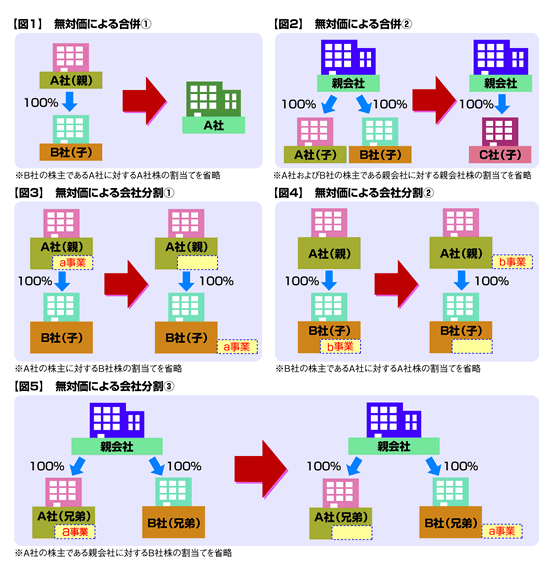 しかし、一部の実務家からは、このような無対価による債務超過の子会社の合併等について、これが無条件に認められるとなれば、親会社の純資産を事実上「無償」で子会社に移転するようなことができてしまうに等しいことから、寄附金課税の問題が生じる可能性があると指摘する声があがっている。
しかし、一部の実務家からは、このような無対価による債務超過の子会社の合併等について、これが無条件に認められるとなれば、親会社の純資産を事実上「無償」で子会社に移転するようなことができてしまうに等しいことから、寄附金課税の問題が生じる可能性があると指摘する声があがっている。すなわち、無対価による債務超過の子会社の合併等を行うことについて経済合理性、経営上の必要性がない場合には、事実認定や包括否認規定(法人税法132条の2)の適用により、親会社においては寄附金課税、子会社においては債務消滅益が認識されるというものだ。
適格合併等であれば、債務消滅益や債務引受損失は発生しないと理解している向きも多いだろうが、上記の考え方においては、非適格合併等のケース同様、適格合併等においても、合併等直前の事業年度において債務消滅益や債務引受損失を認識したうえで、合併法人等においては、債務消滅益を反映した被合併法人等の株主資本を引き継ぐことになるとされる(図6の仕訳参照)。
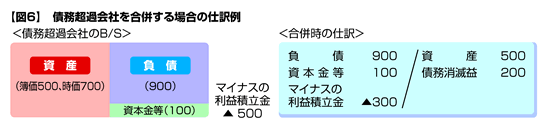
3 「営業権」に関する論点の延長線上に では、実際のところ、包括否認規定等が適用される可能性はどの程度であろうか。
この点を検証するにあたっては、営業権の事例も1つの参考にはなろう。
債務超過会社について「営業権」を認識し、それなりの金額で買収した場合には、税務上、寄附金課税の問題が発生しうる。しかし、そもそも被買収会社の評価、特に事業の評価は主観的な要素を排除できず、たとえば買収会社が被買収会社について、「取引先等との関係」など数字に表れにくい価値を認めたり、「シナジーがある」「経営トップが変われば利益を生む可能性が高い」といった主張のもと、被買収会社の価値を財務上の価値よりも高く評価した場合(すなわち「営業権」の存在を認めた場合)には、課税当局としてもこれを覆すのは容易ではないのが実情だ。
無対価による債務超過の子会社の合併等もこの延長線上にある話といってよいだろう。
すなわち、無対価による債務超過の子会社の合併等については、事実認定や包括否認規定の適用がないとは言い切れないものの(特に法人税法132条の2の文理解釈上は、包括否認規定の適用がないとは言い切れないであろう)、事実上、その適用にはかなりの困難が伴うと考えられる(図7参照)。
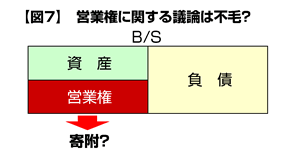
もっとも、営業権の例で触れたように、「適用にかなりの困難が伴う」のは、無対価による債務超過の子会社の合併、分割について経営的、経済合理的な理由が存在すれば、それを課税当局が覆すのは容易ではないからにほかならず、形式上、税制適格であれば、目的の如何に関わらず否認を受けないということではない点に留意したいところだ。
言い換えれば、無対価による債務超過の子会社の合併等においては、少なくともその経営的、経済合理的な理由を持っておくことは、寄附金課税等を回避するための前提条件となろう。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -

Copyright (C) 2019
SHINNIPPON-HOKI PUBLISHING CO.,LTD.