解説記事2009年06月08日 【ニュース特集】 DES・自己株式の譲渡に債務消滅益の認定(2009年6月8日号・№309)
DES・自己株式の譲渡に債務消滅益の認定
東京地方裁判所民事第2部(岩井伸晃裁判長)は4月28日、DES(債務の株式への転化)および自己株式の譲渡について債務消滅益が生ずるか否かなどが争点となっていた事案について、いずれも、「債権と債務の混同により消滅したが、混同による債務の消滅自体は資本等取引には該当せず、損益取引に該当すると解されるので、これに基づく経済的利益につき債務消滅益を認定することは違法ではない。」などと判示して、債務消滅益を認定しての課税処分を容認した(本誌308号10頁参照)。
事業再生の手法としてDESが喧伝され、あるいは、東京地方裁判所の商事部が券面額説を採ることを明らかにして以来、DESに伴う債務消滅益の認定課税については、さまざまな議論が行われてきた。また、自己株式の取引が資本等取引と整理されて以来、自己株式の取引に伴う債務消滅益や受贈益への認定課税についても同様であり、法人税法22条2項および5項の解釈論にも波及する。
本判決に対しては、原告が控訴しており、確定したものとはなっていないが、課税庁の取組みおよび本事案についての司法判断は、注目しておくべきものだろう。
本事案におけるDESについての債務消滅益 本事案において、債務者会社(原告)と密接な関係を有する債権者会社は、外国銀行から額面4億3044万2435円の債務者会社あて債権を代金1億6200万円で取得した。その後、債務者会社と債権者会社は、債務者が普通株式80万株(1株の発行価額538円(資本に組み入れない金額38円))を発行し、債権者が4億3040万円の債権を現物出資することによりこの新株を引き受けることを合意して、債権者への第三者割当による増資が行われた。
債務者は、現物出資を受けるに当たり、東京地方裁判所に検査役の選任を請求し、検査役は、同裁判所に対し調査報告書を提出し、現物出資を行う法人(債権者)の存在および現物出資の目的である債権の存在が認められ、その目的の価額は額面どおり4億3040万円をくだらないので、これに対して1株の発行価額を538円とする新株発行会社(債務者)の株式80万株を割り当てることは妥当である旨の報告をした。債務者は上記のDESにより上記のような経理処理を行った。
国は、債務者と債権者との関係は、本件増資前において「同一者による支配関係」があり、本件増資後において「同一者による支配関係」が継続する関係に該当すると認められることから、適格現物出資に該当し、被現物出資法人である債務者の本件債権の取得価額は現物出資法人である債権者の本件現物出資の直前の帳簿価格に相当する1億6200万円と認められるので、当該混同によって消滅した債権の額面額4億3044万2435円のうち、本件債権の取得価額1億6200万円を超える部分の2億6844万2435円については、債務消滅益として益金の額に算入することになるとして、課税処分を行った。
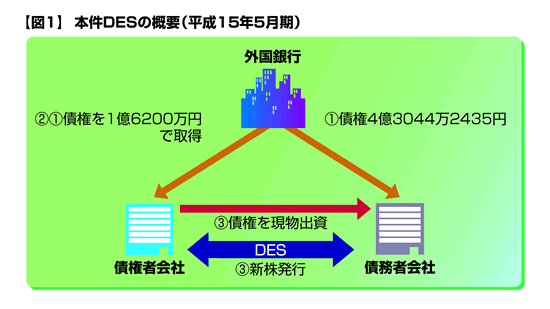
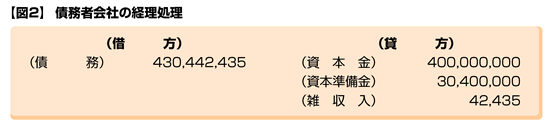
本事案における自己株式の譲渡についての債務消滅益 本事案において、債務者会社(原告)と密接な関係を有する債権者会社は、外国銀行から額面4億6931万0500円の債務者会社あて債権を代金2億5663万2756円で取得した。その後、債務者会社は債権者会社に債務の弁済として1億4461万0500円支払ったため、債権の残額は、3億2470万円となった。債務者は、自己株式34万株(帳簿価額3億2470万円)を債権者に譲渡し、その対価として、本件債権(3億2470万円)を取得した。
国は、本件債権の取得価額は直近の取引価額等からみて1億1202万2256円(2億5663万2756円-1億4461万0500円)と認められるので、当該混同によって消滅した債権の額面額3億2470万円のうち、本件債権の取得価額1億1202万2256円を超える部分の2億1267万7744円については、債務消滅益として法人税法22条の規定により、益金の額に算入することになるとして、課税処分を行った。
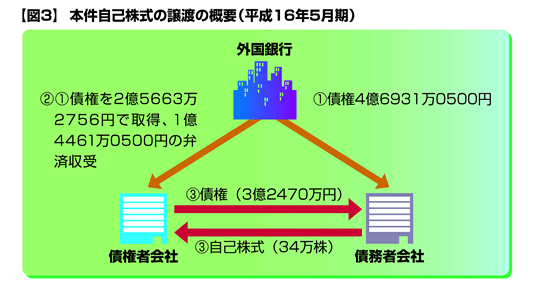
「DES・自己株式取引は非課税」は幻想か 本件訴訟における2つの争点について原告の主張および裁判所の判断は下表のとおりである。本件は納税者側が控訴しており、確定したものではないが、(資本等取引とされてきた)DESや自己株式の処分について、損益取引を認定して課税処分が行われたこと、裁判所が課税庁の判断を受け入れたことは、課税実務への影響も少なくないものといえるだろう。
原告の主張 | 裁判所の判断 | |
| 本件DESについて債務消滅益が生ずるか否か | (1)DESは1個の取引行為として資本等取引に該当するので、DESによって債務が消滅しても債務消滅益は発生しない。 (2)当社の処理は、券面額説の実務によっており(東京地裁商事部において選任された検査役も券面額で評価する旨の調査報告書を提出しており)、債務消滅益は計上されない。課税実務においても、税法上DESに関する明確な規定はなく、民商法上借用された現物出資として扱われたが、債務者法人に関しては、資本等取引として、債務消滅益が計上されることはなく、課税関係は発生しないとされてきた。法人税法の平成18年改正により、DESにおいて券面額での処理が認められなくなったと解されているが、これはそれまでの処理を立法により変更したものであり、平成15年2月28日に行われた本件DESには、平成18年改正後の法人税法は遡及的には適用されない。 (3)DESを行うに当たっては、現物出資の形式を借用し、債務(負債)を出資できると擬制してきたのであり、DESによって移転するのは資産ではなく、自己の債務であるから、法人税法が規定する現物出資に該当せず、法人税法等の関連法令の適用はない。 (4)DESを現物出資と混同に分解しなければならないという必要性はなく、当事者の意思に反してそのように分解し得る許容性の根拠や契機は民商法等には何ら存在しない。 (5)混同は事実であって取引ではないので、損益取引には該当しない。 (6)DESの場合、被現物出資法人は資産または資産及び負債を取得しておらず、自己の負債の移転がされたにすぎないから、法人税法62条の4第1項の適用はない。 | (1)本件DESは、現行法制上、①現物出資による債権者から債務者への本件債権の移転、②本件債権とこれに対応する債務の混同による消滅および③本件新株発行および新株引受けという複数の各段階の過程で構成される複合的な行為であるから、これらをもって一の取引行為とみることはできない。また、上記①の現物出資および同③の新株発行の過程においては、資本等の金額の増減があるので、これらは資本等取引に当たると認められるものの、上記②の混同の過程においては、資本等の金額の増減は発生しないので、資本等取引に該当するとは認められない。本件債務免除益の認定は、平成18年改正後の法人税法の遡及適用によるものではない。平成18年改正前に課税当局によって一般的な税務上の取扱いが示されたことを認めるに足りる証拠はない。 |
| 本件自己株式の譲渡について債務消滅益が生ずるか否か | (1)自己株式の処分は損益の発生しない資本等取引であり、本件取引が資本等取引に該当する以上、また、本件取引当時および本件取引を含む事業年度分の法人税確定申告当時、他に別段の定めがない以上、自己株式の処分について債務消滅益を認定することは違法である。 (2)処分行政庁が、債権の取得価額を1億1202万2256円であると認定したのは、原告の財務内容を考慮しない何ら根拠のないものであり、その認定は違法である。被告の主張に基づけば、本件自己株式の時価は1株あたり329円となり(34万株で1億1202万2256円)、全く時価からかけ離れた低額すぎる価額である。本件自己株式の譲渡取引当時、原告は財務体質を改善させ、自己の債務を全額支払うに足りる十分な能力があったことは、本件自己株式の譲渡取引当時の貸借対照表に照らしても明らかであって、その重要な証左として、原告が本件自己株式の譲渡取引直前の平成15年11月28日、○○銀行から5億円にものぼる融資を受けた事実があり、名実ともに譲渡の対価は3億2470万円であった。 (3)契約は両当事者の合意により決せられるものであり、これは、民商法の大原則である。譲渡契約における譲渡対価の額は、当事者の合意により定まるものであり、譲渡対価の額は本件自己株式の簿価である3億2470万円である。 (4)自己株式の譲渡の対価が債権の時価であるとしても、財産評価基本通達によれば、本件債権は券面額である3億2470万円と評価されることになる。 (5)被告は、民商法上、本件自己株式の譲渡取引、すなわち、1つの取引を、何らの根拠なく譲渡金額は別異の金額であるとした上で、独自の解釈に基づき「仕訳」という会計処理上のテクニカルな方法により2つに分解し、1つの部分は資本等取引でありその余の部分は損益取引であるとするが、これは、明らかに、公正妥当な会計処理の原則に反し、法人税法22条4項に反する。 | (1)本件自己株式の譲渡およびその対価としての本件債権の譲受けそのものは資本等取引であるが、混同による債務の消滅自体は資本等取引には該当せず、損益取引に該当すると解されるので、これに基づく経済的利益につき債務消滅益を認定することは違法ではない。 |
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -























