解説記事2009年07月13日 【制度解説】 課徴金制度・企業結合規制の見直しに係る独占禁止法の改正の要点(2009年7月13日号・№314)
解説
課徴金制度・企業結合規制の見直しに係る独占禁止法の改正の要点
前公正取引委員会事務総局経済取引局総務課企画室室長補佐 小俣栄一郎
前公正取引委員会事務総局経済取引局企業結合課主査 松風宏幸
Ⅰ.はじめに
1 本稿の位置付け 「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律」(以下「平成21年改正法」という)が平成21年6月3日、第171回通常国会において成立した。6月10日、平成21年法律第51号として公布されている。
本稿では、平成21年改正法、特に課徴金制度に係る改正および企業結合規制における届出制度の見直しの概略を紹介する。いずれも公布日から1年内の政令指定日に施行される。
なお、文中意見にわたる部分は筆者らの個人的見解であることを予めお断りしておく。
2 改正の主な内容および経緯 本改正の主な項目は、(ⅰ)排除型私的独占に対する課徴金導入、(ⅱ)不公正な取引方法の一部の行為類型の法定化および課徴金の導入、(ⅲ)主導的地位にある事業者に対する課徴金割増算定率の導入、(ⅳ)課徴金減免制度の適用事業者数の拡大、(ⅴ)課徴金減免共同申請制度の導入、(ⅵ)命令の名宛人に係る規定の整備、(ⅶ)企業結合規制に関する改正等ならびに(ⅷ)刑事罰の引上げおよび(ⅸ)損害賠償における求意見制度に係る改正である。
このうち、(ⅰ)~(ⅶ)の改正項目は、平成20年改正法案として国会へ提出したものであるが、審議されることなく廃案となったところ、今般成立した平成21年改正法案は、平成20年改正法案に(ⅷ)および(ⅸ)の改正項目を追加したものである。
なお、平成20年改正法案附則において検討することとされていた審判制度の見直しについては、平成21年改正法附則において引き続き検討していく旨が規定されている。
Ⅱ.課徴金制度等の見直し(表1参照)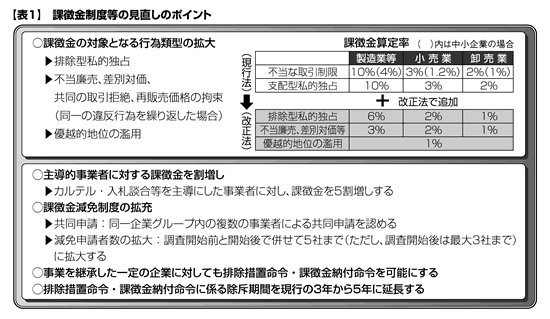
1 課徴金対象範囲の拡大
(1)排除型私的独占に対する課徴金の導入
① 導入の趣旨 排除型私的独占は、不当な取引制限や支配型私的独占と同様に競争を実質的に制限する行為であり、競争秩序に与える影響は大きく、また違反行為が排除されたとしても、その後、直ちに市場への再参入が起こり、競争が迅速に回復することが期待できないことも多い。
したがって、違反行為に対する抑止力を確保する必要性が高いといえることから、課徴金の対象として新たに排除型私的独占も加えられた(7条の2第4項)。
なお、課徴金の対象となるのは、支配型私的独占と同様、供給に係る排除型私的独占に限られる。
② 課徴金の算定 排除型私的独占に対する課徴金の算定においては、違反行為が始まった日(始期)から違反行為がなくなった日(終期)までの期間(違反行為期間。ただし、3年間を上限とする)における違反の対象となった商品に係る売上額を基礎額とし、これに所定の算定率を乗じた金額が課徴金の額となる。
排除型私的独占により形成される競争制限状態にある市場は、その成立ちが人為的であるか否かに違いがあるものの、市場において独占的地位にある事業者が存在するという点で独寡占市場に近似しているといえる。
そこで、独寡占市場における事業者の売上高営業利益率を参考として、製造業等を営む事業者に対する算定率は6%とされている(製造業等を営む事業者の場合。小売業:2%、卸売業:1%)。
(2)不公正な取引方法の行為類型の法定化と課徴金制度の導入
① 不公正な取引方法の法律上の明確化 現行一般指定で規定されている違反行為のうち、不公正な取引方法として原則違法となる違反行為であって課徴金の対象としても事業活動に過度に萎縮を招くこととはならないと考えられるものまたは抑止力を強化すべきとの要請が非常に強かったものとして、共同の取引拒絶(一般指定1項)、差別対価(同3項)、不当廉売(同6項前段)および再販売価格の拘束(同12項)(以下「4類型」という)ならびに優越的地位の濫用(同14項)が、次のとおり全部または一部が法律上規定されたうえで、新たに課徴金の対象となる(2条9項1号~5号)。
一方、課徴金の対象とはならない不公正な取引方法については、同項6号に基づき、引き続き公正取引委員会が指定することとなる。
(a)共同の取引拒絶(2条9項1号)
一般指定の共同の取引拒絶のうち、課徴金の対象となるのは供給に係るもののみとなり、購入に係るものは除外される。
これは、共同の取引拒絶は私的独占の予防的規制であるところ、その購入に係るものは課徴金の対象とされていないこと(7条の2第4項)に合わせたものである。
(b)差別対価(2条9項2号)
同じ「価格」という競争手段を用いて行われる違反行為である不当廉売にならい、「継続して」および「他の事業者の事業活動を困難にさせるおそれ」を要件とし、違法性がより強い行為に限定して課徴金の対象としている。
また、共同の取引拒絶と同様に、供給に係るものが課徴金の対象となり、購入に係るものは含まれない。
(c)不当廉売(2条9項3号)
一般指定6項前段部分、すなわち、「正当な理由がないのに、商品又は役務をその供給に要する費用を著しく下回る対価で継続して供給し、他の事業者の事業活動を困難にするおそれがある場合」が課徴金の対象となる。
(d)再販売価格の拘束(2条9項4号)
一般指定12項で規定する同一の行為が課徴金の対象となる。
(e)優越的地位の濫用(2条9項5号)
一般指定14項のうち、5号(役員選任への不当干渉)を除く1号~4号の行為が課徴金の対象となる。
ただし、3号および4号に該当する行為の実体規定は、明確化をしたうえで2条9項5号ハに掲げられている。
② 4類型に係る課徴金賦課要件および額の算定(20条の2~20条の5)
(a)課徴金賦課要件(10年以内の繰返し等)
4類型は、10年以内に同種の行為を繰り返した場合に課徴金の対象となる。
不公正な取引方法は、その法益侵害の程度が「公正な競争を阻害するおそれ」であり、また、事業者の日常の取引活動と密接に関連する行為類型であることも踏まえ、事業者の正当な事業活動を過度に萎縮させることのないよう、繰返しがあったときのみ対象とする制度としている。
「繰返し」であるか否かは、調査開始日(立入検査日。これが行われない場合には課徴金納付命令の事前通知を受けた日)を起算日として、遡って10年以内に同一類型の違反行為について処分(排除措置命令または課徴金納付命令(確定しているものに限る))または違法宣言審決があったことで判断する。
(b)4類型に対する課徴金の算定方法および算定率
4類型に対する課徴金の算定においては、違反行為期間における違反対象商品等の売上額が算定の基礎となる。
また、算定率については、過去の事案における違反行為者の売上高営業利益率を踏まえ、抑止に必要な水準となるよう3%(製造業等を営む事業者の場合。小売業:2%、卸売業者:1%)とされ、中小企業等の事業者規模別算定率の適用はない。
③ 優越的地位の濫用に対する課徴金の算定方法および算定率(20条の6)
(a)課徴金賦課要件(継続性)
優越的地位の濫用は、2条9項5号に掲げる行為をしただけではなく、それを「継続してするものに限り」課徴金の対象となる。
「継続してする」の要件は、事案ごとに判断されるが、たとえば、一定期間従業員を派遣させる、定期的・継続的に不当に協賛金を収受する、恒常的に不当な返品を繰り返すなどがこれに該当する。
なお、上記4類型と異なり、10年以内の繰返しは要件とされていない。
(b)課徴金の算定方法および算定率
優越的地位の濫用に対する課徴金の基礎は、違反行為を開始した日からそれが終了した日までの期間(違反行為期間。上限は3年間)における、当該行為の相手方との間の取引額となる。
また、違反行為者は取引の相手方に対して商品等を供給する立場にある場合と需要する立場が考えられるところ、「取引額」は、違反事業者が前者である場合には相手方への「売上額」、後者である場合には相手方からの「購入額」となる。
また、算定率は、過去の違反行為における事案を参考に1%となる。
なお、中小企業等の事業者規模別の算定率、業種別算定率に係る規定はない。
2 課徴金制度に関する他の改正
(1)主導的役割を果たした事業者に対する課徴金算定率の割増し 共同行為であるカルテル、入札談合において、「幹事」など主導的な役割を果たす事業者は、その形成を容易にし、またそれを維持・継続することを可能ならしめているといえる。このような「主導的役割」を果たそうとする事業者の出現を抑止して、カルテル等の発生を防止し、またはその自壊を促すために、そのような事業者に対する課徴金を5割増すこととしている(7条の2第8項)。
この割増率は、不当な取引制限についてのみ適用され、他の行為類型には適用はない(同項柱書)。
関与の具体的形態は、7条の2第8項1号~3号に規定されている。
主導的地位にある事業者が繰返し加算(同条7項)の要件にも該当する場合には、算定率は20%(製造業等・大企業)となる(同条9項)。また、主導的事業者には、早期離脱による軽減率の適用はない(同条6項ただし書)。
(2)課徴金減免制度の改正
① 減免申請者数の拡大 旧法における課徴金減免制度では、減免申請が認められるのは最大3社までとされていたが、今回の改正により最大5社までとなった(7条の2第11項3号)。減免率は4、5番目ともに30%となる。
ただし、「最大5社」が認められるのは、調査開始日の前後により条件が異なる。
まず、調査開始前の減免申請については、最大5社まで認められる。なお、4、5番目の申請者が減免を受けるには、「公正取引委員会によって把握されていない事実に係る」情報を報告することが求められる(未知性の要件)。
次いで、調査開始後の申請については、調査前の申請者が5社未満である場合には、調査開始後の公正取引委員会規則で定める一定の期日までに、最大3社までの範囲で調査開始の前後を通して合計5社まで申請が可能となる(同条12項)。
調査開始後の申請に係る情報については、引き続き未知性の要件が求められる。
② グループ内企業による共同申請制度の導入 (a)概 要
旧法における課徴金減免制度での申請は、単独の事業者としてしか認められていなかった。しかしながら、近年、企業グループ全体での法令遵守の徹底が重要視されるようになってきており、一の企業グループ内で違法行為の有無に係る内部調査を行った結果、当該企業グループ内における複数の事業者が同一の違反行為に関与したとみられる事実が発見されることがある。
このような場合に、当該同一グループ企業における複数の事業者が同時に申請したときには、複数の「枠」が一挙に埋まってしまうこととなり、公正取引委員会が得ることとなる情報が限られることとなる。この結果、本来期待される事件の迅速処理が達成できなくなるおそれがある。
この問題を解消するため、同一企業グループ内における複数の事業者が、一定の要件を満たす場合には共同申請を認め、共同申請者に同一の順位を割り当てることとする(7条の2第13項)。
共同申請が認められるのは、(ⅰ)報告および資料提出をしたときに子会社等の関係にあることが必要である(同項1号)。また、(ⅱ)共同申請者が違反行為をしている全期間にわたり、子会社等の関係にあることが必要である(同項2号)。
これらの要件は、違反行為期間中またはその終了後、共同行為者の株式を取得して子会社等の関係を作り出すなど、共同申請を認める趣旨に反する申請を認めない趣旨である。
ただし、違反行為者が子会社等の関係にある者に、違反行為に係る事業を事業譲渡または会社分割により承継させ、承継の前後を通じて継続的に違反行為が行われていた場合には、被承継人と承継人は共同申請ができる(同項3号イ)。
また、共同行為をした事業者のうちの一部の者が他の事業者に譲渡または会社分割により承継させ、承継の前後を通じて継続的に違反行為が行われていた場合も、共同で申請できる(同項3号ロ)。
(b)共同申請の効果
上述の要件を満たす複数の事業者が共同申請を行った場合には、減免申請の順位、申請事業者数に関しては1つの事業者として数えられ、減免の効果を付与される。
したがって、調査開始前に子会社等の関係にある3社が3番目に共同申請した場合には、当該3社はいずれも調査開始前順位3番の効果を付与されることになり、また、その後2社(2グループ)まで申請が可能である(7条の2第13項柱書後段)。
一方、共同申請者のなかに1社でも、(ⅰ)虚偽報告、(ⅱ)要請された報告等の不提出または(ⅲ)他の事業者に対する違反行為の強要等の欠格事由がある場合には、共同申請者全部について、減免が認められなくなる(同条17項)。
Ⅲ.企業結合規制の見直し(表2参照)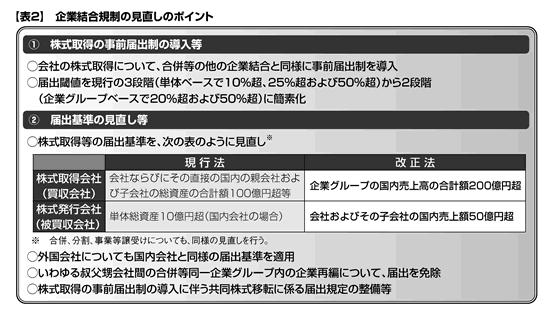
1 企業結合規制の見直しの背景等 従来の独占禁止法においては、株式取得については、海外の主要国と異なり事後報告制となっていたため、公正取引委員会への事前届出義務がなく、企業結合審査における海外競争当局との協力が行いにくい等の状況が生じていた。
また、わが国市場に与える影響の大きさからみて、本来であれば届出が行われるべきであるような企業結合が、従来の独占禁止法における届出基準では届出の対象となっていない状況もみられたことから、株式取得に係る事前届出制の導入や届出基準を見直すことなどを内容とした企業結合規制の見直しが行われることとなった。
2 企業結合規制の見直しの概要 今般の企業結合規制の見直しは、大きく(ⅰ)会社の株式取得についての事前届出制の導入、届出基準の見直し等、(ⅱ)合併、分割および事業等の譲受けについての届出基準の見直し、届出免除範囲の拡大、(ⅲ)共同株式移転についての規定の整備、(ⅳ)その他の4つに分けられる。
(1)会社の株式取得についての事前届出制の導入、届出基準の見直し等
① 事前届出制の導入、届出基準の見直し (a)事前届出制の導入(10条2項、8項等)
合併、分割等と同様の事前届出制を株式取得についても導入することとした。
届出受理の日から30日を経過するまでは、待機期間としてその届出に係る株式の取得は禁止されることになる。
(b)届出基準の変更(10条2項)
法改正後の事前届出制においては、株式取得会社の属する企業結合集団(株式取得会社の「最終親会社」(株式取得会社の親会社のうち他の親会社の子会社になっていない会社)とその子会社からなるグループのことをいう。子会社および親会社については、会社法等と同様に実質基準を用いる予定である)の国内売上高合計額(企業結合集団に属する会社等の国内売上高(国内で供給された商品および役務の価額の最終事業年度における合計額として公正取引委員会規則で定めるもの)を合計した額)が200億円超となるような株式取得会社が(なお、現行の株式取得会社の単体規模要件(総資産20億円超)は廃止された)、株式発行会社およびその子会社の国内売上高を合計した額が50億円超となるような株式発行会社の株式の取得をしようとする場合に届出義務が課せられる(具体的な金額は政令で定められる予定である)。
(c)届出閾値の簡素化(10条2項)
法改正後の事前届出制のもとでは、従来の3段階から届出閾値を簡素化し、株式取得会社の属する企業結合集団で株式発行会社の議決権を保有する割合が20%、50%を超える2段階に届出義務が課せられる(具体的な数値は政令で定められる予定である)。
(d)届出免除等(10条2項ただし書、10条3項・4項)
法改正後の事前届出制のもとでは、予め届出を行うことが困難である場合として公正取引委員会規則で定める場合について、届出免除とされる。
また、法改正後の事前届出制のもとでは、届出閾値の算定において、銀行や保険会社が株式を取得または所有する議決権(同業の会社の株式を取得または所有する場合を除く)等を除外し、他方、金銭または有価証券の信託に係る株式に係る議決権で、自らが委託者もしくは受益者としてその行使について受託者に指図を行うことができるもの等を含むものとしている。
なお、たとえば、株式発行会社が自己株式の取得をしたことにより株式取得会社の所有する議決権の割合が増加するケースは届出の対象外である。
(e)内外無差別の届出基準(10条2項)
従来の事後報告制のもとでは、株式発行会社が外国会社である場合には、その国内の営業所等の売上高が10億円を超えることを届出基準としていたが、法改正後の事前届出制のもとでは、外国会社であっても国内の会社と同様の届出基準を用いることとしている。
② 組合を通じた株式取得についてのみなし規定の整備(10条5項)
法改正後の事前届出制のもとでは、会社の子会社となっている法人格のない組合(任意組合、投資事業有限責任組合等)を通じて株式の取得をしようとする場合について、当該組合の直接の親会社が株式を取得しようとするものとみなし、その親会社が届出義務を負うことになる。
(2)合併、分割および事業等の譲受けについての届出基準の見直し、届出免除範囲の拡大
① 届出基準の見直し(15条2項、15条の2第2項・3項、16条2項)
合併および分割については、株式取得の届出基準と同様に、原則として、企業結合集団の国内売上高合計額が200億円を超える会社と企業結合集団の国内売上高合計額が50億円を超える会社が合併および分割をしようとする場合に届出義務が課せられることになる(具体的な金額は政令で定められる予定である)。
ただし、重要部分承継に係る分割については、承継の対象部分に係る国内売上高が100億円または30億円が届出基準となる(具体的な金額は政令で定められる予定である)。
また、事業等の譲受けについては、企業結合集団の国内売上高合計額が200億円を超える会社が、単体の国内売上高が30億円を超える会社の事業の全部を譲り受けようとする場合等に届出義務が課せられることになる(具体的な金額は政令で定められる予定である)。
② 届出免除範囲の拡大(15条2項ただし書、15条の2第2項ただし書・3項ただし書、16条2項ただし書)
法改正後は、合併、分割および事業等の譲受けをしようとするすべての当事会社が同一の企業結合集団に属する場合は届出を免除することとし、届出免除範囲を拡大することとした。
③ 内外無差別の届出基準(15条2項、15条の2第2項・3項、16条2項)
株式取得と同様、法改正後は、外国会社であっても国内の会社と同様の届出基準を用いることとしている。
(3)共同株式移転についての規定の整備
① 規定の趣旨 現行法では、共同株式移転(2以上の会社が持株会社を設立し、株式移転を行うことにより、当該持株会社の子会社となること)については10条に基づき規制が行われてきた。
法改正により、株式取得について事前届出制が導入されたが、仮に、企業結合審査の結果として公正取引委員会が競争上問題のあるような共同株式移転であると判断した場合であっても、持株会社はまだ設立されておらず、排除措置を命ぜられるべき会社が存在しないという事態が生じる。
また、株式取得に係る届出書の提出義務を負うべき持株会社が、届出の時点ではまだ設立されていないことから、事前届出が行われない状況になる。
このため、法改正によって、新たに共同株式移転について実体規定および届出規定等を整備することとしたものである。
② 規定の概要(15条の3)
合併等と同様の実体規定および届出規定を整備している。
届出については、共同株式移転をしようとする会社のうち、ある会社の属する企業結合集団の国内売上高合計額が200億円を超え、かつ、他のある会社の国内売上高合計額が50億円を超える場合に届出義務が生じることになる(具体的な金額は政令で定められる予定である)。
(4)その他 17条の2(排除措置)、18条(合併等の無効の訴え)、91条(株式保有、役員兼任等の制限禁止違反の罪)等について、株式取得に係る事前届出制の導入や共同株式移転に係る規定の整備等に伴い、所要の規定の整理を行っている。
(おまた・えいいちろう/まつかぜ・ひろゆき)
課徴金制度・企業結合規制の見直しに係る独占禁止法の改正の要点
前公正取引委員会事務総局経済取引局総務課企画室室長補佐 小俣栄一郎
前公正取引委員会事務総局経済取引局企業結合課主査 松風宏幸
Ⅰ.はじめに
1 本稿の位置付け 「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律」(以下「平成21年改正法」という)が平成21年6月3日、第171回通常国会において成立した。6月10日、平成21年法律第51号として公布されている。
本稿では、平成21年改正法、特に課徴金制度に係る改正および企業結合規制における届出制度の見直しの概略を紹介する。いずれも公布日から1年内の政令指定日に施行される。
なお、文中意見にわたる部分は筆者らの個人的見解であることを予めお断りしておく。
2 改正の主な内容および経緯 本改正の主な項目は、(ⅰ)排除型私的独占に対する課徴金導入、(ⅱ)不公正な取引方法の一部の行為類型の法定化および課徴金の導入、(ⅲ)主導的地位にある事業者に対する課徴金割増算定率の導入、(ⅳ)課徴金減免制度の適用事業者数の拡大、(ⅴ)課徴金減免共同申請制度の導入、(ⅵ)命令の名宛人に係る規定の整備、(ⅶ)企業結合規制に関する改正等ならびに(ⅷ)刑事罰の引上げおよび(ⅸ)損害賠償における求意見制度に係る改正である。
このうち、(ⅰ)~(ⅶ)の改正項目は、平成20年改正法案として国会へ提出したものであるが、審議されることなく廃案となったところ、今般成立した平成21年改正法案は、平成20年改正法案に(ⅷ)および(ⅸ)の改正項目を追加したものである。
なお、平成20年改正法案附則において検討することとされていた審判制度の見直しについては、平成21年改正法附則において引き続き検討していく旨が規定されている。
Ⅱ.課徴金制度等の見直し(表1参照)
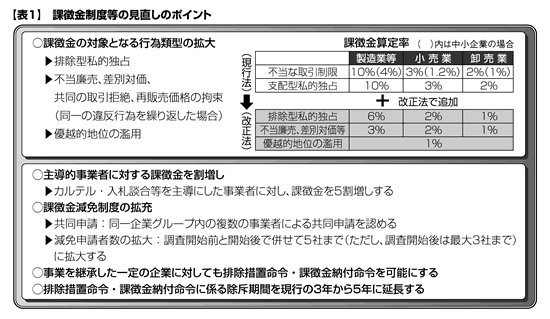
1 課徴金対象範囲の拡大
(1)排除型私的独占に対する課徴金の導入
① 導入の趣旨 排除型私的独占は、不当な取引制限や支配型私的独占と同様に競争を実質的に制限する行為であり、競争秩序に与える影響は大きく、また違反行為が排除されたとしても、その後、直ちに市場への再参入が起こり、競争が迅速に回復することが期待できないことも多い。
したがって、違反行為に対する抑止力を確保する必要性が高いといえることから、課徴金の対象として新たに排除型私的独占も加えられた(7条の2第4項)。
なお、課徴金の対象となるのは、支配型私的独占と同様、供給に係る排除型私的独占に限られる。
② 課徴金の算定 排除型私的独占に対する課徴金の算定においては、違反行為が始まった日(始期)から違反行為がなくなった日(終期)までの期間(違反行為期間。ただし、3年間を上限とする)における違反の対象となった商品に係る売上額を基礎額とし、これに所定の算定率を乗じた金額が課徴金の額となる。
排除型私的独占により形成される競争制限状態にある市場は、その成立ちが人為的であるか否かに違いがあるものの、市場において独占的地位にある事業者が存在するという点で独寡占市場に近似しているといえる。
そこで、独寡占市場における事業者の売上高営業利益率を参考として、製造業等を営む事業者に対する算定率は6%とされている(製造業等を営む事業者の場合。小売業:2%、卸売業:1%)。
(2)不公正な取引方法の行為類型の法定化と課徴金制度の導入
① 不公正な取引方法の法律上の明確化 現行一般指定で規定されている違反行為のうち、不公正な取引方法として原則違法となる違反行為であって課徴金の対象としても事業活動に過度に萎縮を招くこととはならないと考えられるものまたは抑止力を強化すべきとの要請が非常に強かったものとして、共同の取引拒絶(一般指定1項)、差別対価(同3項)、不当廉売(同6項前段)および再販売価格の拘束(同12項)(以下「4類型」という)ならびに優越的地位の濫用(同14項)が、次のとおり全部または一部が法律上規定されたうえで、新たに課徴金の対象となる(2条9項1号~5号)。
一方、課徴金の対象とはならない不公正な取引方法については、同項6号に基づき、引き続き公正取引委員会が指定することとなる。
(a)共同の取引拒絶(2条9項1号)
一般指定の共同の取引拒絶のうち、課徴金の対象となるのは供給に係るもののみとなり、購入に係るものは除外される。
これは、共同の取引拒絶は私的独占の予防的規制であるところ、その購入に係るものは課徴金の対象とされていないこと(7条の2第4項)に合わせたものである。
(b)差別対価(2条9項2号)
同じ「価格」という競争手段を用いて行われる違反行為である不当廉売にならい、「継続して」および「他の事業者の事業活動を困難にさせるおそれ」を要件とし、違法性がより強い行為に限定して課徴金の対象としている。
また、共同の取引拒絶と同様に、供給に係るものが課徴金の対象となり、購入に係るものは含まれない。
(c)不当廉売(2条9項3号)
一般指定6項前段部分、すなわち、「正当な理由がないのに、商品又は役務をその供給に要する費用を著しく下回る対価で継続して供給し、他の事業者の事業活動を困難にするおそれがある場合」が課徴金の対象となる。
(d)再販売価格の拘束(2条9項4号)
一般指定12項で規定する同一の行為が課徴金の対象となる。
(e)優越的地位の濫用(2条9項5号)
一般指定14項のうち、5号(役員選任への不当干渉)を除く1号~4号の行為が課徴金の対象となる。
ただし、3号および4号に該当する行為の実体規定は、明確化をしたうえで2条9項5号ハに掲げられている。
② 4類型に係る課徴金賦課要件および額の算定(20条の2~20条の5)
(a)課徴金賦課要件(10年以内の繰返し等)
4類型は、10年以内に同種の行為を繰り返した場合に課徴金の対象となる。
不公正な取引方法は、その法益侵害の程度が「公正な競争を阻害するおそれ」であり、また、事業者の日常の取引活動と密接に関連する行為類型であることも踏まえ、事業者の正当な事業活動を過度に萎縮させることのないよう、繰返しがあったときのみ対象とする制度としている。
「繰返し」であるか否かは、調査開始日(立入検査日。これが行われない場合には課徴金納付命令の事前通知を受けた日)を起算日として、遡って10年以内に同一類型の違反行為について処分(排除措置命令または課徴金納付命令(確定しているものに限る))または違法宣言審決があったことで判断する。
(b)4類型に対する課徴金の算定方法および算定率
4類型に対する課徴金の算定においては、違反行為期間における違反対象商品等の売上額が算定の基礎となる。
また、算定率については、過去の事案における違反行為者の売上高営業利益率を踏まえ、抑止に必要な水準となるよう3%(製造業等を営む事業者の場合。小売業:2%、卸売業者:1%)とされ、中小企業等の事業者規模別算定率の適用はない。
③ 優越的地位の濫用に対する課徴金の算定方法および算定率(20条の6)
(a)課徴金賦課要件(継続性)
優越的地位の濫用は、2条9項5号に掲げる行為をしただけではなく、それを「継続してするものに限り」課徴金の対象となる。
「継続してする」の要件は、事案ごとに判断されるが、たとえば、一定期間従業員を派遣させる、定期的・継続的に不当に協賛金を収受する、恒常的に不当な返品を繰り返すなどがこれに該当する。
なお、上記4類型と異なり、10年以内の繰返しは要件とされていない。
(b)課徴金の算定方法および算定率
優越的地位の濫用に対する課徴金の基礎は、違反行為を開始した日からそれが終了した日までの期間(違反行為期間。上限は3年間)における、当該行為の相手方との間の取引額となる。
また、違反行為者は取引の相手方に対して商品等を供給する立場にある場合と需要する立場が考えられるところ、「取引額」は、違反事業者が前者である場合には相手方への「売上額」、後者である場合には相手方からの「購入額」となる。
また、算定率は、過去の違反行為における事案を参考に1%となる。
なお、中小企業等の事業者規模別の算定率、業種別算定率に係る規定はない。
2 課徴金制度に関する他の改正
(1)主導的役割を果たした事業者に対する課徴金算定率の割増し 共同行為であるカルテル、入札談合において、「幹事」など主導的な役割を果たす事業者は、その形成を容易にし、またそれを維持・継続することを可能ならしめているといえる。このような「主導的役割」を果たそうとする事業者の出現を抑止して、カルテル等の発生を防止し、またはその自壊を促すために、そのような事業者に対する課徴金を5割増すこととしている(7条の2第8項)。
この割増率は、不当な取引制限についてのみ適用され、他の行為類型には適用はない(同項柱書)。
関与の具体的形態は、7条の2第8項1号~3号に規定されている。
主導的地位にある事業者が繰返し加算(同条7項)の要件にも該当する場合には、算定率は20%(製造業等・大企業)となる(同条9項)。また、主導的事業者には、早期離脱による軽減率の適用はない(同条6項ただし書)。
(2)課徴金減免制度の改正
① 減免申請者数の拡大 旧法における課徴金減免制度では、減免申請が認められるのは最大3社までとされていたが、今回の改正により最大5社までとなった(7条の2第11項3号)。減免率は4、5番目ともに30%となる。
ただし、「最大5社」が認められるのは、調査開始日の前後により条件が異なる。
まず、調査開始前の減免申請については、最大5社まで認められる。なお、4、5番目の申請者が減免を受けるには、「公正取引委員会によって把握されていない事実に係る」情報を報告することが求められる(未知性の要件)。
次いで、調査開始後の申請については、調査前の申請者が5社未満である場合には、調査開始後の公正取引委員会規則で定める一定の期日までに、最大3社までの範囲で調査開始の前後を通して合計5社まで申請が可能となる(同条12項)。
調査開始後の申請に係る情報については、引き続き未知性の要件が求められる。
② グループ内企業による共同申請制度の導入 (a)概 要
旧法における課徴金減免制度での申請は、単独の事業者としてしか認められていなかった。しかしながら、近年、企業グループ全体での法令遵守の徹底が重要視されるようになってきており、一の企業グループ内で違法行為の有無に係る内部調査を行った結果、当該企業グループ内における複数の事業者が同一の違反行為に関与したとみられる事実が発見されることがある。
このような場合に、当該同一グループ企業における複数の事業者が同時に申請したときには、複数の「枠」が一挙に埋まってしまうこととなり、公正取引委員会が得ることとなる情報が限られることとなる。この結果、本来期待される事件の迅速処理が達成できなくなるおそれがある。
この問題を解消するため、同一企業グループ内における複数の事業者が、一定の要件を満たす場合には共同申請を認め、共同申請者に同一の順位を割り当てることとする(7条の2第13項)。
共同申請が認められるのは、(ⅰ)報告および資料提出をしたときに子会社等の関係にあることが必要である(同項1号)。また、(ⅱ)共同申請者が違反行為をしている全期間にわたり、子会社等の関係にあることが必要である(同項2号)。
これらの要件は、違反行為期間中またはその終了後、共同行為者の株式を取得して子会社等の関係を作り出すなど、共同申請を認める趣旨に反する申請を認めない趣旨である。
ただし、違反行為者が子会社等の関係にある者に、違反行為に係る事業を事業譲渡または会社分割により承継させ、承継の前後を通じて継続的に違反行為が行われていた場合には、被承継人と承継人は共同申請ができる(同項3号イ)。
また、共同行為をした事業者のうちの一部の者が他の事業者に譲渡または会社分割により承継させ、承継の前後を通じて継続的に違反行為が行われていた場合も、共同で申請できる(同項3号ロ)。
(b)共同申請の効果
上述の要件を満たす複数の事業者が共同申請を行った場合には、減免申請の順位、申請事業者数に関しては1つの事業者として数えられ、減免の効果を付与される。
したがって、調査開始前に子会社等の関係にある3社が3番目に共同申請した場合には、当該3社はいずれも調査開始前順位3番の効果を付与されることになり、また、その後2社(2グループ)まで申請が可能である(7条の2第13項柱書後段)。
一方、共同申請者のなかに1社でも、(ⅰ)虚偽報告、(ⅱ)要請された報告等の不提出または(ⅲ)他の事業者に対する違反行為の強要等の欠格事由がある場合には、共同申請者全部について、減免が認められなくなる(同条17項)。
Ⅲ.企業結合規制の見直し(表2参照)
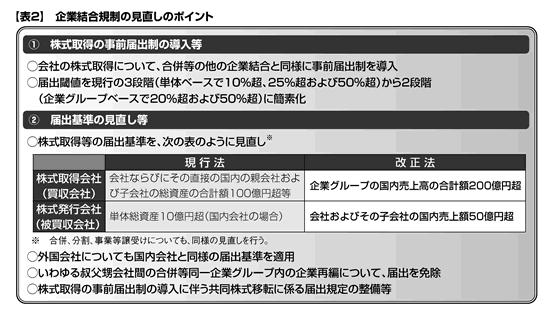
1 企業結合規制の見直しの背景等 従来の独占禁止法においては、株式取得については、海外の主要国と異なり事後報告制となっていたため、公正取引委員会への事前届出義務がなく、企業結合審査における海外競争当局との協力が行いにくい等の状況が生じていた。
また、わが国市場に与える影響の大きさからみて、本来であれば届出が行われるべきであるような企業結合が、従来の独占禁止法における届出基準では届出の対象となっていない状況もみられたことから、株式取得に係る事前届出制の導入や届出基準を見直すことなどを内容とした企業結合規制の見直しが行われることとなった。
2 企業結合規制の見直しの概要 今般の企業結合規制の見直しは、大きく(ⅰ)会社の株式取得についての事前届出制の導入、届出基準の見直し等、(ⅱ)合併、分割および事業等の譲受けについての届出基準の見直し、届出免除範囲の拡大、(ⅲ)共同株式移転についての規定の整備、(ⅳ)その他の4つに分けられる。
(1)会社の株式取得についての事前届出制の導入、届出基準の見直し等
① 事前届出制の導入、届出基準の見直し (a)事前届出制の導入(10条2項、8項等)
合併、分割等と同様の事前届出制を株式取得についても導入することとした。
届出受理の日から30日を経過するまでは、待機期間としてその届出に係る株式の取得は禁止されることになる。
(b)届出基準の変更(10条2項)
法改正後の事前届出制においては、株式取得会社の属する企業結合集団(株式取得会社の「最終親会社」(株式取得会社の親会社のうち他の親会社の子会社になっていない会社)とその子会社からなるグループのことをいう。子会社および親会社については、会社法等と同様に実質基準を用いる予定である)の国内売上高合計額(企業結合集団に属する会社等の国内売上高(国内で供給された商品および役務の価額の最終事業年度における合計額として公正取引委員会規則で定めるもの)を合計した額)が200億円超となるような株式取得会社が(なお、現行の株式取得会社の単体規模要件(総資産20億円超)は廃止された)、株式発行会社およびその子会社の国内売上高を合計した額が50億円超となるような株式発行会社の株式の取得をしようとする場合に届出義務が課せられる(具体的な金額は政令で定められる予定である)。
(c)届出閾値の簡素化(10条2項)
法改正後の事前届出制のもとでは、従来の3段階から届出閾値を簡素化し、株式取得会社の属する企業結合集団で株式発行会社の議決権を保有する割合が20%、50%を超える2段階に届出義務が課せられる(具体的な数値は政令で定められる予定である)。
(d)届出免除等(10条2項ただし書、10条3項・4項)
法改正後の事前届出制のもとでは、予め届出を行うことが困難である場合として公正取引委員会規則で定める場合について、届出免除とされる。
また、法改正後の事前届出制のもとでは、届出閾値の算定において、銀行や保険会社が株式を取得または所有する議決権(同業の会社の株式を取得または所有する場合を除く)等を除外し、他方、金銭または有価証券の信託に係る株式に係る議決権で、自らが委託者もしくは受益者としてその行使について受託者に指図を行うことができるもの等を含むものとしている。
なお、たとえば、株式発行会社が自己株式の取得をしたことにより株式取得会社の所有する議決権の割合が増加するケースは届出の対象外である。
(e)内外無差別の届出基準(10条2項)
従来の事後報告制のもとでは、株式発行会社が外国会社である場合には、その国内の営業所等の売上高が10億円を超えることを届出基準としていたが、法改正後の事前届出制のもとでは、外国会社であっても国内の会社と同様の届出基準を用いることとしている。
② 組合を通じた株式取得についてのみなし規定の整備(10条5項)
法改正後の事前届出制のもとでは、会社の子会社となっている法人格のない組合(任意組合、投資事業有限責任組合等)を通じて株式の取得をしようとする場合について、当該組合の直接の親会社が株式を取得しようとするものとみなし、その親会社が届出義務を負うことになる。
(2)合併、分割および事業等の譲受けについての届出基準の見直し、届出免除範囲の拡大
① 届出基準の見直し(15条2項、15条の2第2項・3項、16条2項)
合併および分割については、株式取得の届出基準と同様に、原則として、企業結合集団の国内売上高合計額が200億円を超える会社と企業結合集団の国内売上高合計額が50億円を超える会社が合併および分割をしようとする場合に届出義務が課せられることになる(具体的な金額は政令で定められる予定である)。
ただし、重要部分承継に係る分割については、承継の対象部分に係る国内売上高が100億円または30億円が届出基準となる(具体的な金額は政令で定められる予定である)。
また、事業等の譲受けについては、企業結合集団の国内売上高合計額が200億円を超える会社が、単体の国内売上高が30億円を超える会社の事業の全部を譲り受けようとする場合等に届出義務が課せられることになる(具体的な金額は政令で定められる予定である)。
② 届出免除範囲の拡大(15条2項ただし書、15条の2第2項ただし書・3項ただし書、16条2項ただし書)
法改正後は、合併、分割および事業等の譲受けをしようとするすべての当事会社が同一の企業結合集団に属する場合は届出を免除することとし、届出免除範囲を拡大することとした。
③ 内外無差別の届出基準(15条2項、15条の2第2項・3項、16条2項)
株式取得と同様、法改正後は、外国会社であっても国内の会社と同様の届出基準を用いることとしている。
(3)共同株式移転についての規定の整備
① 規定の趣旨 現行法では、共同株式移転(2以上の会社が持株会社を設立し、株式移転を行うことにより、当該持株会社の子会社となること)については10条に基づき規制が行われてきた。
法改正により、株式取得について事前届出制が導入されたが、仮に、企業結合審査の結果として公正取引委員会が競争上問題のあるような共同株式移転であると判断した場合であっても、持株会社はまだ設立されておらず、排除措置を命ぜられるべき会社が存在しないという事態が生じる。
また、株式取得に係る届出書の提出義務を負うべき持株会社が、届出の時点ではまだ設立されていないことから、事前届出が行われない状況になる。
このため、法改正によって、新たに共同株式移転について実体規定および届出規定等を整備することとしたものである。
② 規定の概要(15条の3)
合併等と同様の実体規定および届出規定を整備している。
届出については、共同株式移転をしようとする会社のうち、ある会社の属する企業結合集団の国内売上高合計額が200億円を超え、かつ、他のある会社の国内売上高合計額が50億円を超える場合に届出義務が生じることになる(具体的な金額は政令で定められる予定である)。
(4)その他 17条の2(排除措置)、18条(合併等の無効の訴え)、91条(株式保有、役員兼任等の制限禁止違反の罪)等について、株式取得に係る事前届出制の導入や共同株式移転に係る規定の整備等に伴い、所要の規定の整理を行っている。
(おまた・えいいちろう/まつかぜ・ひろゆき)
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -

Copyright (C) 2019
SHINNIPPON-HOKI PUBLISHING CO.,LTD.





















