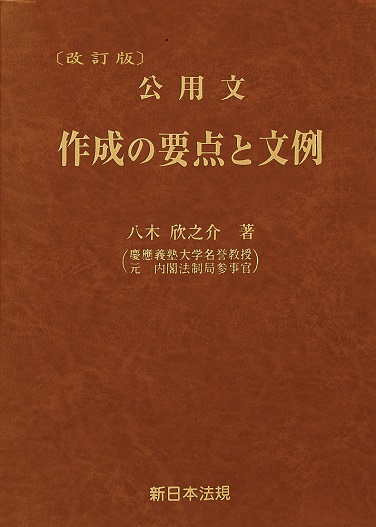解説記事2009年07月20日 【最新判決研究】 当初の遺産分割による申告に錯誤があったとする再遺産分割による更正の請求等の可否(2009年7月20日号・№315)
最新判決研究
当初の遺産分割による申告に錯誤があったとする再遺産分割による更正の請求等の可否
品川芳宣
早稲田大学大学院教授
東京地裁平成19年(行ウ)第322号
平成21年2月27日判決
一、事実
(1)本件は、平成14年8月26日に死亡した被相続人甲に係る相続(以下「本件相続」という。)に際し、相続人である妻X1及び子X2~X4の3名(以下これらの4名を「相続人ら」という。)並びに生命保険金等を取得した孫X5~X10の6名の計10名(原告、以下「X1ら」という。)がX1が取得する同族会社であるI会社の株式の価額につき、財産評価基本通達(以下「評価通達」という。)に定める配当還元方式による評価を前提として相続人らがした当初の遺産分割の合意(以下「第一次遺産分割」という。)に基づき、相続税の各申告をしたが、評価通達に従い同族会社の発行済株式数につき議決権のない株式数を除外して計算すると配当還元方式の適用を受けられず、類似業種比準方式による高額の評価を前提として課税されるという錯誤があったので、配当還元方式の適用を受けられるように各相続人が取得する株式数を調整した上でした新たな遺産分割の合意(以下「第二次遺産分割」という。)をし、それに基づき、法定申告期限から1年以内(更正の請求期間内)に更正の請求(以下「本件更正の請求」という。)をしたところ、Y(処分行政庁)から、上記株式の評価は第一次遺産分割の内容に従い類似業種比準方式によるべきであるとして、当初の各申告に係る各更正処分及び過少申告加算税の各賦課決定処分並びに更正すべき理由がない旨の処分(以下「本件各処分」という。)を受けたため、異議決定及び審査裁決により取り消された部分を除き、本件各処分の一部又は全部の取消しを国(被告)に対して求めている事案である。
なお、第一次遺産分割に基づく課税価格は、38億6,750万円余であり、第二次遺産分割に基づく課税価格は、20億0,351万円余であるが、その差額は、X1が取得する同族会社の株式の評価の差異から生じている。
(2)甲の相続財産には、I会社の株式155万4,024株が含まれており、本件相続の開始前、X1は、I会社の株式25万8,500株を有していた。本件相続の開始当時、I会社の従業員数は729人であり、評価通達178にいう大会社(従業員数が100人以上の会社)に該当する。I会社の株主のうち、E会社及びS会社(以下「関連2社」という。)については、I会社が関連2社の発行済株式の総数の4分の1を超える株式を保有していたため、当時の商法241条3項の規定によりI会社の株式につき議決権を有しないこととされる会社であった。
このため、評価通達188の適用上、I会社における各株主の持株割合の計算に当たっては、I会社の株式のうち、E会社の有する株式11万7,000株及びS会社の有する株式43万9,000株(合計55万6,000株)は、相互保有株式として発行済株式数から控除されるべきものであった。
(3)相続人らは、平成15年5月、T税理士の助言を受け遺産分割の協議を行い、甲の相続財産であるI会社の株式155万4,024株については、X1が71万8,300株、X2及びX3が各35万株、X4が13万5,724株を取得する旨を約し、同月17日、この約定を内容とする第一次遺産分割の合意をした。この株式の配分は、これにより各相続人とも配当還元方式の適用を受けられる旨のT税理士の助言に基づき、同方式の適用を受けられる配分の方法として相続人らの間で協議した結果、合意に至ったものであった。
この株式の配分により、I会社において、X1及び同族関係者のグループの持株割合は50%以上となったが、X1並びにX1の直系血族、兄弟姉妹及び一親等の姻族の有する株式数の合計数の持株割合は25%に満たなかったため、X1は、評価通達188の適用上、中心的な同族株主以外の同族株主に該当することとなった。
この株式の配分による場合、評価通達188等の適用上、I会社におけるX1の持株割合は、(a)I会社の発行済株式数から、関連2社の保有に係る株式数を控除して計算すると、5%以上(類似業種比準方式の適用対象)となるものの、(b)これを控除しないで計算すると、5%未満(配当還元方式の適用対象)となるところ、相続人らは、その控除を要することの認識を欠いたまま、第一次遺産分割の合意に至った。
(4)X1らは、第一次遺産分割の合意の成立後、上記(3)の株式の配分の内容を前提として、X1が取得する株式を配当還元方式により評価し、同年6月19日(法定申告期限は同年6月26日)、本件相続に係る相続税の各期限内申告をした。当該申告後、相続人らは、第一次遺産分割による株式の配分を前提とする評価としては、評価通達188等の適用上、I会社の発行済株式数から、関連2社の保有に係る株式数を相互保有株式として控除して計算すべきであり、これによるとX1の持株割合は5%以上となり、類似業種比準方式の適用による高額の評価を前提とした相続税の課税を受けるべきことを認識するに至った。
そこで、相続人らは、同年10月、改めて遺産分割の再協議を行い、X1の取得するI会社の株式数を15万4,024株減少させて56万4,276株とし、その減少分を2分して、X2及びX3が取得する株式を各7万7,012株ずつ増加させて各42万7,012株とする旨を約し、同月28日、I会社の株式の配分はこの約定を内容とし、それ以外は第一次遺産分割と同じ内容とする旨の第二次遺産分割の合意をした。この株式の配分は、関連2社の保有に係る株式数を控除して計算しても、X1の持株割合が5%未満となり、配当還元方式の適用が受けられるように、相続人らの間で合意に至ったものであった。
そして、X1らは、第二次遺産分割の分割内容を前提とした上で、X1が取得する株式を配当還元方式により評価し、同年11月6日付で、本件更正の請求等をした。
(5)Yは、I会社の株式の評価は第一次遺産分割の内容に従い類似業種比準方式によるべきであるとして、いずれも平成16年11月9日付で、本件各処分をした。また、Yは、第二次遺産分割は、遺産の分割ではなく、新たな取引行為であり、これによるX2及びX3の株式の取得はX1からの贈与であるとして、X2及びX3に対し、同年12月15日付で平成15年分の贈与税の決定処分及び無申告加算税の賦課決定処分をした。しかし、国税不服審判所の裁決において、第一次遺産分割は要素の錯誤により無効であり、第二次遺産分割におけるX1及びX2の株式の取得は贈与ではなく遺産の分割によるものであるとして、上記贈与税の決定及び無申告加算税の賦課決定はいずれも取り消された。
二、争点及び当事者の主張
1 争点
本件の争点は、当初の遺産分割に基づく株式の配分を前提とする相続税の申告がされ、法定申告期限後、課税価格の前提となる株式の評価方法の誤信を原因とする当該遺産分割の錯誤による無効を理由として、株式の配分を変更する新たな遺産分割がされた場合に、当該申告をした者は、課税庁に対し、更正の請求期間内に更正の請求をすることにより、当初の遺産分割の無効を主張して新たな遺産分割に基づく株式の配分を前提とする相続税の減額更正を求めることかできるか否かである。
2 X1らの主張
(1)更正の請求は、納税者が自らの申告により確定させた税額が過大であることを法定申告期限後に気付いた場合に、納税者の側からその変更・是正を求めることができるとする、納税者の権利を救済することを目的とする制度である。本件のように、錯誤による無効の場合はもちろん、仮に法定申告期限後の全員の合意による解除であるとしても、更正の請求がその期間内に行われており、所定の事由に該当する以上、Yは減額更正を認めるべき法的義務がある。
更正の請求においては、通常の錯誤と課税負担の錯誤を区別することなく、その無効を主張することができ、更正の請求期間内であるにもかかわらず、錯誤を主張することができないとは到底考えられない。特に、本件は、法定申告期限の5か月後、更正の請求期間内に自発的に誤りに気付いて更正の請求をしている事例である。
(2)処分行政庁から増額更正処分と更正の請求に対する更正すべき理由がない旨の通知処分がされた場合、税額等を争う納税者は、増額更正処分の取消訴訟を提起すれば足りる。増額更正処分の内容は、更正をすべき理由がない旨の通知処分の内容を包摂する関係にあり、更正処分と別個に通知処分を争う利益はない。増額更正処分に対する取消訴訟の中で、通知処分における減額更正をしない旨の判断に存する違法を主張して、申告税額等を下回る額にまで増額更正処分の取消しを求めることができ、更正の請求の理由の有無についても、更正処分の取消訴訟において実質的に審理すべきである。
3 国の主張
(1)租税法規は、経済活動ないし経済現象を課税の対象としており、それらは第一次的には私法によって規律されていることから、その私法上の法律関係が無効等であれば、その法律関係を前提に行われた申告は、原則として、「課税標準若しくは税額等の計算が国税に関する法律の規定に従っていなかつたこと」(通法23①一)に該当すると考えられる。したがって、遺産分割が一般の要素の錯誤により無効である場合には、そもそも遺産分割がされていない状態にあると解されるので、相続税法55条により法定相続分等に従って遺産を取得したものとして計算された相続税の税額よりも、「当該申告書の提出により納付すべき税額(中略)が過大であるとき」は、国税通則法23条1項1号による更正の請求が可能である。
(2)しかしながら、通常の錯誤と課税負担の錯誤は同列には論じられない。納税義務者は、納税義務の発生の原因となる私法上の法律行為を行った場合、当該法律行為の際に予定していなかった納税義務が生じたり、当該法律行為の際に予定していたものよりも重い納税義務が生じることが判明した結果、この課税負担の錯誤が当該法律行為の要素の錯誤に当たるとして、当該法律行為が無効であることを、法定申告期限を経過した時点で主張することは許されない。申告納税方式を採用し、申告義務の違反及び脱税に対しては加算税を課している結果、安易に納税義務の発生の原因となる法律行為の錯誤無効を認めて納税義務を免れさせたのでは、納税者間の公平を害し、租税法律関係を不安定なものとし、ひいては申告納税方式の破壊につながるからである。
また、課税庁は、納税者が、ある法律行為が有効であることを前提に申告をした場合、当該法律行為が有効であることを信頼することが合理的であり、法定申告期限後に、課税処分又は修正申告の勧奨を受けるや、にわかに課税庁に対し、納税義務の発生原因となる法律行為に課税負担の錯誤があったとして法律行為の無効を主張することは、課税庁の合理的な期待・信頼を裏切るものである上、租税法上の信義則ないし禁反言の法理に反し、許されないものというべきである。
(3)遺産分割が一般の要素の錯誤により無効であり、納税者がこれを主張し得る場合でも、その場合にはそもそも遺産分割が行われていない状態にあるものと解されるので、更正の請求をするには、まず、相続税法55条の規定による法定相続分等に従った計算に基づき、修正申告、更正又は決定を経ることが必要であり、その上で、新たな遺産分割が行われた場合には、相続税法32条1号による更正の請求又は同法31条1項による修正申告をすることになるが、相続税法55条の規定による法定相続分等に従った計算による修正申告、更正又は決定を経ていないときは、相続税法32条1号所定の同法「第55条の規定により民法(中略)の規定による相続分(中略)に従つて課税価格が計算されていた場合において、その後当該財産の分割が行われ」た場合に該当しないため、相続税法32条1号に基づく更正を請求することはできない。
(4)増額更正処分と更正の請求に対する更正すべき理由がない旨の通知処分がされた場合、増額更正処分の取消訴訟の中で、通知処分における減額更正をしない旨の判断の違法を主張して、申告税額等を下回る額にまで増額更正処分の取消しを求めることができることは、一般論としては異論はない。しかし、そのことは、更正の請求の理由の有無について、更正処分の取消訴訟において実質的に審理されることと同義ではなく、X1らは、申告税額等を下回る額にまで増額更正処分の取消しを求める方法として、端的に、本件各処分によって確定された税額が処分時に客観的に存在した税額を上回るか否かを問題とすべきである。
三、判決要旨
請求認容。
(1)本件においては、前提事実のほか、次の事実が認められる。
相続人らは、第一次遺産分割の協義に際し、相続税の負担等についてT税理士に相談しながら、配当還元方式の適用を受けられる方法でI会社の株式を配分する方法を協議し、事前に、T税理士から、当該株式の配分につき前提事実の配分方法によれば配当還元方式の適用を受けられるとの助言を受け、これに従い、当該株式の配分につき当該配分方法を採用した第一次遺産分割の合意に至った。
T税理士は、相続人らに上記助言をするに当たり、事前に、I会社の株式につき、配当還元方式の適用の可否についてM税務署の職員に相談し、一般的な回答として、同方式を適用して差し支えない旨の回答を受け、その旨を相続人らに伝えた。ところが、第一次遺産分割に基づく相続税の申告後、相続人らは、評価通達に基づく相互保有株式の控除の必要性を看過していたため前提事実の配分方法では配当還元方式の適用を受けられないことに気付いた。これは、Yの調査時の指摘、修正申告の勧奨、更正処分等を契機とするものではなく、税務調査の開始等の前に、相続人らが自ら気付いたものであった。そこで、相続人らは、評価通達に基づく相互保有株式の控除をしても配当還元方式の適用を受けられるようにして、第二次遺産分割の合意に至った。
(2)そこで、前提事実及び上記の認定事実を踏まえ、本件における課税負担の前提事項の錯誤が要素の錯誤に当たるか否か、その錯誤につき重大な過失があったか否かについて、以下検討する。
イ 第一次遺産分割の協議においては、I会社の株式の評価につき、配当還元方式によるか類似業種比準方式によるかで合計約19億円の相違が生ずることとなることから配当還元方式の適用を受けられる株式の配分方法を採ることを分割の方針として明示した上で、その方法についてT税理士に相談し、同税理士から所轄税務署との相談も踏まえた検討結果に基づく助言を受け、その助言に従い、配当還元方式の適用を受けられる株式の配分方法との誤信の下に、第一次遺産分割の合意に至っているものと認められることからすれば、X1が遺産分割により取得する株式について、配当還元方式による評価によることが、第一次遺産分割に当たっての重要な動機として明示的に表示され、第一次遺産分割の意思表示の内容となっていたものと認められ、かつ、その評価方法についての動機の錯誤がなかったならば相続人らはその意思表示をしなかったであろうと認められるから、第一次遺産分割のうち、株式の配分に係る部分には要素の錯誤があったと認めるのが相当である。
ロ 相続人らがI会社の株式の評価方法を誤信したのは、T税理士が評価通達上控除を要する関連会社の相互保有株式の存否の確認を怠って誤った助言をしたことに起因するものであり、事柄の内容も税務の専門家でない相続人らにとって同税理士の助言の誤りに直ちに気付くのが容易なものとはいえないと認められることからすれば、その誤信について、相続人らに過失があったことは否めないものの、過失の程度は通常要求される義務を著しく欠いているものとまでは認められず、相続人らに重大な過失があったということはできない。
ハ したがって、本件における遺産分割の私法上の効力については、第一次遺産分割のうち、I会社の株式の配分に係る部分は、要素の錯誤により無効であり、その余の部分は有効であって、当該株式の配分に係る部分は、第二次遺産分割により補充されており、これらの遺産分割の効力は相続開始時に遡及して生じている(民法909)というべきである。
(3)そこで、第一次遺産分割のうち、I会社の株式の配分に係る部分が課税負担の前提事項の錯誤により無効であることを前提として、第一次遺産分割に基づく相続税の申告をしたX1が、法定申告期限後、更正の請求期間内に、Yに対し、更正の請求において当該遺産分割の一部の無効を主張することの可否について検討する。
イ 我が国の租税法制は、相続税に関し、その課税標準等の決定については、最も相続関係の事情に通じている納税義務者自身の申告に基づくものとする観点から、相続税法において申告納税制度を採用するとともに、相続税額の減額更正については、租税法律関係の早期安定等の観点から、法定申告期限後は法律が特に認めた手続である更正の請求による場合に限るものとし、国税通則法及び相続税法において更正の請求の事由を限定列挙した上でその請求を所定の期間内に限定している。
したがって、納税義務の発生の原因となる遺産分割の効果を前提として相続税の申告がされた後、法定申告期限後に、当該遺産分割の要素の錯誤による無効を主張して相続税額の減額更正をするには、法定の更正の請求の事由のいずれかに該当することを要するところ、例えば、分割内容自体の錯誤が要素の錯誤に該当することにより当該遺産分割が無効とされる場合には、課税の根拠となる相続財産の取得を欠くことになるから、国税通則法23条1項1号にいう「当該申告書に記載した課税標準等若しくは税額等の計算が国税に関する法律の規定に従つていなかつたこと」との事由に該当することとなり、その結果、「当該申告書の提出により納付すべき税額(中略)が過大であるとき」に該当するときは、同号の規定による更正の請求をすることができるものと解される。
なお、遺産分割による財産の移転を課税の根拠とする場合において、国税通則法23条1項1号にいう「当該計算に誤りがあつたこと」とは、当該遺産分割の効果を前提とした数額の計算に誤りがあることをいうものであるので、遺産分割の錯誤無効の場合はこれには当たらないものと解され、また、国税通則法23条2項3号及び同法施行令6条1項2号の規定による更正の請求は、当該法律行為が有効に成立した後に後発的事由によってその効力の喪失その他の法律関係の変動が生じた場合に、課税の内容をその変動後の法律関係に適合させるための更正の手続であるところ、遺産分割の錯誤無効は、後発的事由ではなく、原始的事由であるから、国税通則法23条2項3号及び同法施行令6条1項2号に掲げる事由には当たらないものと解される。
ロ これに対し、分割内容自体の錯誤と異なり、課税負担の錯誤に関しては、それが要素の錯誤に該当する場合であっても、我が国の租税法制が、相続税に関し、申告納税制度を採用し、申告義務の懈怠等に対し加算税等の制裁を課していること、相続税の法定申告期限は相続の開始を知った日から原則として10月以内とされており、申告者は、その間に取得財産の価値の軽重と課税負担の軽重等を相応に検討し忖度した上で相続税の申告を行い得ること等にかんがみると、法定申告期限を経過した後も、更なる課税負担の軽減のみを目的とする課税負担の錯誤の主張を無制限に認め、当該遺産分割が無効であるとして納税義務を免れさせたのでは、租税法律関係が不安定となり、納税者間の公平を害し、申告納税制度の趣旨・構造に背馳することとなり、このことは、①申告者が、法定申告期限後の課税庁による申告内容の調査時の指摘、修正申告の勧奨、更正処分等を受けた後に自らの申告内容を翻し、更正の請求期間内に更正の請求の手続を執ることなく、更正処分等の取消訴訟において錯誤無効を主張する場合、②新たな遺産分割の合意による分割内容の変更をしていないため、当初の遺産分割の経済的成果が実質的に残存し得る場合、③法定申告期限後に更なる課税負担の軽減のみを目的とする錯誤無効の主張を安易に繰り返す場合等には、税法上の信義則の観点からも、看過し難い。したがって、上記の申告納税制度の趣旨・構造及び税法上の信義則に照らすと、申告者は、法定申告期限後は、課税庁に対し、原則として、課税負担又はその前提事項の錯誤を理由として当該遺産分割が無効であることを主張することはできず、例外的にその主張が許されるのは、分割内容自体の錯誤との権衡等にも照らし、①申告者が、更正の請求期間内に、かつ、課税庁の調査時の指摘、修正申告の勧奨、更正処分等を受ける前に、自ら誤信に気付いて、更正の請求をし、②更正の請求期間内に、新たな遺産分割の合意による分割内容の変更をして、当初の遺産分割の経済的成果を完全に消失させており、かつ、③その分割内容の変更がやむを得ない事情により誤信の内容を是正する一回的なものであると認められる場合のように、更正の請求期間内にされた更正の請求においてその主張を認めても上記の弊害が生ずるおそれがなく、申告納税制度の趣旨・構造及び租税法上の信義則に反するとはいえないと認めるべき特段の事情がある場合に限られるものと解するのが相当である(なお、国の指摘に係る最高裁平成18年10月6日第二小法廷決定・未公刊、同平成10年1月27日第三小法廷決定・税務訴訟資料230号152頁及び同平成13年4月13日第二小法廷決定・税務訴訟資料250号8882順号は、いずれも、申告者が、更正の請求期間内に更正の請求の手続を執ることなく、上記期間の経過後に課税庁の調査時の指摘、修正申告の勧奨、更正処分等を受けたことを契機として課税負担の誤信に気付き、更正処分等の取消訴訟において課税負担の錯誤による無効を主張した事案について、課税庁に対する当該主張は許されないとした原審の判断を当該事案の事実関係の下において是認したものであり、これらの事案とは異なり、上記の特段の事情がある場合に限りその例外を認めることは、これらの判例に抵触するものではないと解される。)。
なお、前記のとおり、租税法制上、法定申告期限後も、更正の請求期間内は、法定の更正の請求の手続による限り、課税の根拠となった遺産分割の要素の錯誤による無効を理由とする相続税額の減額更正が手続的に許容されていることにかんがみると、法定申告期限までに課税庁に生じた申告内容に対する信頼や租税法律関係の早期確定の要請等を勘案しても、なお、その無効の主張の制限について、更正の請求期間内にされた更正の請求における上記の限度での例外を許容し得ないとまでは解し難い。
(4)そこで、X1について、上記の特段の事情の有無を検討する。
イ まず、前提事実のとおり、①X1は、平成15年6月19日、第一次遺産分割に基づき、相続税の申告をし、その約5か月後の同年11月6日に、株式の分割の錯誤を理由として、更正の請求をしており、更正請求期間内に、第一次遺産分割のうちI会社の株式の配分に係る部分の錯誤による無効を理由として、国税通則法23条1項1号の規定による更正の請求をしたものと認められ、また、②X1は、課税庁の調査時の指摘、修正申告の勧奨、更正処分等を受ける前に、いまだ税務調査も始まっていない段階で、相続人らが自ら課税負担の前提事項の錯誤があることに気付いたため、上記更正の請求をしたのであり、更正処分がされたのも、更正の請求の日から約1年後の平成16年11月19日であったことが認められる。
ロ 次に、X1が第一次遺産分割により取得した経済的成果は、一定数のI会社の株式の帰属であるが、第一次遺産分割のうち本件会社の株式の配分に係る部分が無効であり、更正の請求期間内に、X1の取得するI会社の株式数を減ずる内容の第二次遺産分割がされたことにより(なお、同期間内に、これに基づく、I会社の株式名簿の名義書換えもされた。)、更正の請求の時点では、その減少分の株式はX2及びX3に確定的に帰属するに至っており、当該減少分の株式(15万4,024株)につき、第一次遺産分割によるX1の経済的成果は完全に消失しているものと認められる。
ハ さらに、前提事実及び上記の認定事実によれば、①I会社の株式の評価に係る配当還元方式の適用は、その適用の有無により評価額に合計約19億円の差異が生ずることから、遺産分割における重要な条件として当初から相続人らの間で明示的に協議されていた事項であり、相続人らが当該株式の評価方法を誤信して第一次遺産分割の合意に至ったのは、T税理士の誤った助言に起因するもので、事柄の内容も税務の専門家でない相続人らにとって同税理士の助言の誤りに直ちに気付くのが容易なものとはいえないものであったこと、②遺産分割の協議に際して、相続人らは、第1次遺産分割に基づく当初の申告を経て、自らその誤信に気付いた後、速やかに、配当還元方式の適用を受けられる内容に当該株式の配分方法を変更した第二次遺産分割の合意に至っていることが認められ、これらの経緯に照らすと、第一次遺産分割から第二次遺産分割への分割内容の変更は、やむを得ない事情により誤信の内容を是正する一回的なものであったと認められる。
ニ 以上によれば、本件は、更正の請求において課税負担の前提事項の錯誤を理由とする遺産分割の無効の主張を認めても上記の弊害が生ずるおそれがなく、申告納税制度の趣旨・構造及び租税法上の信義則に反するとはいえないと認めるべき特段の事情がある場合に該当するものというべきである。
(5)したがって、X1は、更正請求期間内にした更正の請求において、Yに対し、第一次遺産分割のうちI会社の株式の配分に係る部分の錯誤による無効を主張することができたものというべきであり、これにより当該株式の配分が無効とされる以上、課税の根拠となる相続財産である当該株式の取得を欠くことになるから、その錯誤による無効は、国税通則法23条1項1号にいう「当該申告書に記載した課税標準等若しくは税額等の計算が国税に関する法律の規定に従つていなかつたこと」との事由に該当するものと解される。
そして、前記のとおり、第一次遺産分割の一部が要素の錯誤により無効であり、その余の部分は有効であって、更正請求期間内に当該無効の部分が第二次遺産分割により補充され、これらの遺産分割の効力は相続開始時に遡及している(民法909)以上、申告書の記載に係る第一次遺産分割の配分内容に従った計算による税額が、第二次遺産分割の配分内容に従った計算による税額を上回るときは、国税通則法23条1項1号所定の「当該申告書の提出により納付すべき税額(中略)が過大であるとき」に該当するものとして、その差額の減額更正につき、同号の規定による更正の請求をすることができるものと解するのが相当である。
(6)他方で、遺産分割が要素の錯誤により無効であり、納税者がこれを主張し得る場合について、これをまだ遺産分割がされていない状態と同視し得るとすれば、更正の請求の手続として、まず、相続税法55条の規定による法定相続分等に従った計算に基づき、国税通則法23条1項1号による更正の請求又は修正申告等を経た上で、新たな遺産分割の配分内容に従った計算に基づき、改めて相続税法32条1号による更正の請求をするという手続も考えられ、上記の手続との関係について検討を要する。
そこで検討するに、相続税法32条各号は、国税通則法23条1項各号及び2項各号所定の一般的な更正の事由に該当しない場合であっても、相続、遺贈又は贈与により財産を取得した者の間の租税負担の公平を図るため、相続税に特有の更正の事由を定めるとともに、国税通則法23条1項及び2項所定の一般的な更正の請求期間とは別個に特有の更正の請求期間を定めており、このような相続税法32条各号の規定の趣旨・構造等に照らすと、同条各号は、国税通則法の通則規定に対する特則規定として、国税通則法の定める更正の請求事由に該当する場合のほか、同条各号所定の事由があれば同条所定の期間内に更正の請求ができるとしたものであって、国税通則法の定める更正の請求に該当する場合において、同条各号所定の更正の事由にも該当することがあるとしても、それによって、国税通則法の規定による更正の請求について更なる要件を加重してその請求を制限するものではなく、また、国税通則法の規定による更正の請求を排除するものでもないと解するのが相当である。そして、相続税法55条は、相続により取得した財産に係る相続税について申告書の提出又は更正若しくは決定をする場合において、当該相続により取得した財産の全部又は一部が共同相続人によってまだ分割されておらず、その後に当該財産の分割がされた場合についての二段階の処理方法を定める規定であり、まだ遺産分割がされていない場合を本来の適用対象とするものであって、既にされた遺産分割の全部又は一部が無効で新たな遺産分割がされている場合を同条の適用対象に含めるか否かは個別事案の評価の問題と解されるところ、本件においては、申告書の提出時を基準とすれば、第一次遺産分割の一部無効により相続財産の一部が未分割である状態と同視し得るものの、更正の請求期間内に既に第二次遺産分割がされているため、更正の請求に基づく更正時を基準とすれば、相続財産の全部が既に分割されている場合に当たる以上、このような場合の更正の請求において同条に基づく二段階の処理が必須の手続として義務付けられるものとは解されないので、いずれにしても、同条に基づく二段階の方法により相続税法32条1号の規定による更正の請求をすることができると解し得ることをもって、上記の直截的な方法により国税通則法23条1項1号の規定による更正の請求をすることが妨げられるものとは解されない。
(7)なお、更正をすべき理由がない旨の通知処分と同時にされた増額更正処分の内容に更正をすべき理由がないとする趣旨が含まれている場合には、通知処分の取消しを求める利益はなく、更正処分の取消しを求めれば足り、更正処分の取消訴訟において、更正の請求の事由の有無は、処分時における客観的な納付すべき税額の判断の前提となる減額更正の可否に係る手続要件として検討されることとなり、本件訴訟においても、これと同様の観点から検討の対象とされるものである。
四、解説
はじめに
本件では、取引相場のない株式を相続して相続税を申告するに当たって、当該株式の評価通達上の評価額が有利になる(配当還元方式の適用)ように相続人間で遺産分割(第一次遺産分割)して当初申告を済ませた後、第一次遺産分割の方法では評価通達上の配当還元方式の適用が受けられなくなることが発覚したので、法定申告期限から1年以内(更正の請求の期間内)に、当該株式の相続分を調整する新たな遺産分割の合意(第二次遺産分割)をして更正の請求(本件更正の請求)及び修正申告したことが適法であるか否かが問題となった。
本件のように、課税上の有利性を目的として私法上の契約等を締結し、それに基づいて納税申告を行った後、当該契約等では課税上の有利性が得られないことが発覚することはまま見受けられることであるが、その場合に、いつまでに当該契約等の解約等をすれば不利な課税を免れるかが問題となり、それをめぐって争訟事件となることも多い。
かくして、従来の学説、判例等では、当該解約等は、法定申告期限までに行えば課税関係が生じないとするのが通説的である(注1)。しかし、それとても、関係税法における明文規定に根拠があるわけではない。
ところが、本件においては、前述の第二次遺産分割に基づく更正の請求が法定申告期限から1年以内にされたこともあって容認されたものであるが、従前の裁判例と趣を異にしており、リーディング・ケースとして大いに注目される。そこで、このような問題に関し、関係条項と関係判例等に照らして、以下論述することとする。
1 国税通則法上の更正の請求
(1)納税申告書を提出した者は、①当該申告書に記載した課税標準等若しくは税額等の計算が国税に関する法律の規定に従っていなかったこと、又は②当該計算に誤りがあったことにより、納付すべき税額が過大であるとき、又は純損失の金額が過少であるか、記載がなかったときには、当該申告書に係る国税の法定申告期限から1年以内に限り、税務署長に対し、それらを更正すべき旨の請求をすることができる(通法23①)。これが、通常の場合の更正の請求制度である。
この場合、特に問題となるのが、「国税に関する法律の規定に従っていなかったこと」の解釈である。原則的には、納税申告書の提出段階で違法であったこと(例えば、相続等により取得した財産の時価が100万円であるにもかかわらず、150万円であるとして申告した場合)を意味するであろうが(注2)、後述する後発的事由に基づく更正の請求が法定申告期限から1年経過する日後に限って行うこととされている(通法23②かっこ書)ところ、当該経過する日前(法定申告期限から1年以内)に後発的事由が生じた場合に問題となる。
すなわち、このような場合に、国税通則法23条2項に基づく更正の請求ができないというのであれば、同条1項に基づく更正の請求を認めざるを得ないであろうが(同項の更正の請求も認められないとする考え方もあろうが)、そうすると、「国税に関する法律の規定に従っていなかったこと」を弾力的に解さざるを得なくなる。このことは、本件のように、法定申告期限から1年以内に遺産分割の変更を事由とする更正の請求が行われた場合にも問題となる。
(2)また、このような通常の場合の更正の請求のみでは納税者の権利保護が不十分であるということ(換言すると、結果的に国に不当利得が生じること)で、昭和45年の法律改正により、後発的事由に基づく更正の請求制度が設けられた。
すなわち、納税申告書を提出した者は、次に該当する場合には(通常の更正の請求ができる期間の満了する日後に到来する場合に限る。)、次に掲げる期間において、更正の請求をすることができる(通法23②)。
① その申告、更正又は決定に係る課税標準等又は税額等の計算の基礎となった事実に関する訴えについての判決(判決と同一の効力を有する和解その他の行為を含む。)により、その事実が当該計算の基礎としたところと異なることが確定したとき その確定した日の翌日から起算して2月以内② その申告・更正又は決定に係る課税標準等又は税額等の計算に当たってその申告をし、又は決定を受けたものに帰属するものとされていた所得その他課税物件が他の者に帰属するものとする当該他の者に係る国税の更正又は決定があったとき 当該更正又は決定があった日の翌日から起算して2月以内
③ その他当該国税の法定申告期限に生じた①及び②に類する政令で定めるやむを得ない理由があるとき 当該理由が生じた日の翌日から起算して2月以内
この本則規定に関しては、①の「……事実に関する訴えについての判決」の意義とその範囲をめぐって争われることが多い(注3)。
(3)次に、前記③の政令で定めるやむを得ない理由については、国税通則法施行令6条1項において、次のように定められている。
① その申告、更正又は決定に係る課税標準等の計算の基礎となった事実のうちに含まれていた行為の効力に係る官公署の許可その他の処分が取り消されたこと。
② その申告、更正又は決定に係る課税標準等又は税額等の計算の基礎となった事実に係る契約が、解除権の行使によって解除され、若しくは当該契約の成立後生じたやむを得ない事情によって解除され、又は取り消されたこと。
③ 帳簿書類の押収その他やむを得ない事情により、課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき帳簿書類その他の記録に基づいて国税の課税標準等又は税額等を計算することができなかった場合において、その後、当該事情が消滅したこと。
④ わが国が締結した所得に対する租税に関する二重課税の回避又は脱税の防止のための条約に規定する権限のある当局間の協議により、その申告、更正又は決定に係る課税標準等又は税額等に関し、その内容と異なる内容の合意が行われたこと。
⑤ その申告、更正又は決定に係る課税標準等又は税額等の計算の基礎となった事実に係る国税庁長官が発した通達に示されている法令の解釈その他の国税庁長官の法令の解釈が、更正又は決定に係る審査請求若しくは訴えについての裁決若しくは判決に伴って変更され、変更後の解釈が国税庁長官により公表されたことにより、当該課税標準等又は税額等が異なることとなる取扱いを受けることとなったことを知ったこと。
これらの事由のうち、本件においては、②の規定との関係が問題となる。すなわち、本件のような遺産分割も、「相対立する二つ以上の意思表示の合致(合意)によって成立する法律行為」(注4)であるから、②にいう「契約」に該当するものと解されるが、その契約解除が法定申告期限から1年以内に生じている。そのため、本件において、第一次遺産分割の解消がやむを得ない事情があったとしても、国税通則法23条2項に基づく更正の請求はできないことになる。この場合、同条1項に基づく通常の更正の請求を認めるべきであるとしても、文理上の問題を残す。
また、前記⑤については、本判決について国側は控訴を断念しているようであるが、国税庁が新たな取扱いを公表することによって本件と類似する更正の請求を惹起することになるのかが注目される。
2 相続税法上の更正の請求の特則
(1)後発的事由に基づく更正の請求については、前述の国税通則法上の規定のほか、各税目の特質に応じ、各税法にその特則が設けられている。
例えば、所得税法においては、同法63条(事業を廃止した場合の必要経費の特例)又は64条(資産の譲渡代金の回収不能の場合等の所得計算の特例)に規定する事実が生じたことその他その年分の各種所得の金額(事業所得の金額等を除く)の計算の基礎となったうちに含まれていた無効な行為又は取り消し得べき行為により生じた経済的成果がそれらの事由により失われた場合には、当該事実が生じた日の翌日から2月以内に限り、更正の請求をすることができる(所法152)。
また、法人税法については、後発的事由に基づく更正の請求は一層厳しく制限されており、修正申告書を提出し、又は更正若しくは決定を受けた法人は、それらに従いその修正申告等に係る事業年度後の事業年度の確定申告書に記載すべき法人税額等が過大となる場合には更正の請求ができる(法法82)が、国税通則法上認められている解除権の行使等による契約解除等があっても、それを事由に更正の請求は認められないものと解されている(注5)。
(2)他方、相続税法においては、相続税又は贈与税について申告書を提出した者又は決定を受けた者は、次に掲げるような事由により当該申告等に係る課税価格等が過大となったときは、当該事由が生じたことを知った日の翌日から4月以内に限り、更正の請求をすることができる。
① 分割されていない財産について民法の規定による相続分又は包括遺贈の割合に従って課税価格が計算されていた場合において、その後当該財産の分割が行われ、共同相続人又は包括受遺者が当該分割により取得した財産に係る課税価格が当該相続分又は包括遺贈の割合に従って計算された課税価格と異なることとなったこと。
② 民法の規定による認知、相続人の廃除又はその取消しに関する裁判の確定、相続の回復、相続の放棄の取消しその他の事由により相続人に異動を生じたこと。
③ 遺留分による減殺の請求に基づき返還すべき、又は弁償すべき額が確定したこと。
④ 遺贈に係る遺言書が発見され、又は遺贈の放棄があったこと。
⑤ 条件を付して物納の許可がされた場合において、当該条件に係る物納に充てた財産の性質その他の事情に関し政令で定めるものが生じたこと。
⑥ ①から⑤に規定する事由に準ずるものとして政令で定める事由が生じたこと。(以下略)
なお、⑥にいう政令で定める事由としては、相続若しくは遺贈又は贈与により取得した財産についての権利の帰属に関する訴えについての判決があったこと等が挙げられている(相令8②)。
以上のように、相続税法上の更正の請求の特則においても、未分割のまま相続税を申告した後に分割が行われた場合には、更正の請求は認められるが、分割のやり直しによる更正の請求は想定されていない。しかし、国は、本件においても、まずもってこの規定によるべきことを主張しているが、本判決は、その必要性を否定している。
3 契約の合意解除等と更正の請求
(1)本件のように、課税上の有利性が得られることを期待して私法上の契約等を行ったもののその期待に反して予期せぬ税負担が生じることはまま見受けられることである。これは、納税者にとって、租税法律主義の下で経済取引における税負担の予測可能性が保障されているところ、法令規定を合理的(合法的)に解して税負担を最小にしようと意図するところから必然的に生じてくることでもある。
かくして、納税者においては、当初の契約等に要素の錯誤等があったとして当該契約等が無効であると主張したり、当事者間でやむを得ない事情があったとして合意解除したり、更には、国税通則法23条2項1号にいう「判決」があったことに適合するように、当事者間で馴れ合い訴訟を提起して当該納税者にとって有利な判決を得ようとすることもある(注6)。
ところで、所得税の納税義務は、暦年の終了の時に成立する(通法15②一)から、その年中の資産譲渡等に係る契約をその年の12月31日までに合意解除すれば、そもそも納税義務が成立しないことは是認できる。しかしながら、相続税については、相続又は遺贈による財産の取得の時に納税義務が成立する(通法15①四)から、期間税である所得税のような考慮期間も存在しない。
もっとも、納税義務の成立後の合意解除が行われた場合には、法令上の明文規定の存在はともかくとして、それが法定申告期限以内の(相続税であれば、相続開始10月以内)であれば、当該合意解除等の法律効果を主張し得るものと解されている(注7)。
(2)ところが、法定申告期限後に予期せぬ租税負担が生じるということで合意解除した場合には、解釈は分かれていた。すなわち、法定申告期限から1年以内(通常の更正の請求の期限内)であれば更正の請求を認め得るとする見解(注8)と1年以内であっても「やむを得ぬ事情」がなければ認められないとする見解(注9)である。国側は、後説を採用して課税処分を行ってきたところであるが、多くの裁判例が当該課税処分を適法と認めてきた。
本判決が国の主張として引用している各最高裁判決(決定)においても、国側の主張が認められている。もっとも、これらの各最高裁判決(決定)は、本判決も指摘しているように、いずれも法定申告期限から1年経過したものではある。しかしながら、当該最高裁判決(決定)のうち、最高裁平成13年4月13日第二小法廷決定(上告不受理)の原審(大阪高裁平成12年11月2日判決・税資249号457頁)が引用している一審の大阪地裁平成12年2月23日判決(税資246号908頁)は、次のとおり判示している。
「我が国は、申告納税方式を採用し、申告義務の違反や脱税に対しては加算税等を課している結果、安易に納税義務の発生の原因となる法律行為の錯誤無効を認めて納税義務を免れさせたのでは、納税者間の公平を害し、租税法律関係が不安定となり、ひいては申告納税方式の破壊につながるのであるから、納税義務者は、納税義務の発生の原因となる私法上の法律行為を行った場合、右法律行為の際に予定していなかった納税義務が生じたり、右法律行為の際に予定していたものよりも重い納税義務が生じることが判明した結果、この課税負担の錯誤から当該法律行為の動機の錯誤であるとして、右法律行為が無効であることを法定申告期間を経過した時点で主張することはできないと解するのが相当である。」
また、同じく最高裁平成10年1月27日第三小法廷判決(注10)の原審である大阪高裁平成8年7月25日判決(訟務月報44巻12号2201頁)は、「右に定める解除権の行使でない合意解除は『当該契約成立後生じたやむを得ない事情』によるものであるときに限って更正請求の理由とすることができるとするものであり、右やむを得ない事情とは、法定の解除事由がある場合、事情の変更により契約内容に拘束力を認めるのが不当な場合、その他これに類する客観的な理由がある場合をいうものと解すべきである。」と判示している。
以上のような従前の裁判例では、当初の契約が課税上不利であるということで合意解除して更正の請求をすることについては、それが法定申告期限から1年以内に行われたものであっても厳しく制限する姿勢であったことが窺える。
4 本件更正の請求の適法性
(1)前述したように、本件においては、X1らが本件相続によって取得するI会社の株式を評価通達上の配当還元方式の適用が受けられるように各人の取得株式を調整・配分して第一次遺産分割をして相続税の申告を行い、その後、当該第一次遺産分割の方法ではX1が取得した株式について配当還元方式の適用が受けられないことを知ったので、当該株式の取得配分の再調整を行って第二次遺産分割を行い、それに基づいて平成15年11月6日付で更正の請求をしたというものである。そして、その更正の請求が当該相続税の法定申告期限(平成15年6月26日)から1年以内であったというものである。しかし、Yは、平成16年11月9日付で、第一次遺産分割に基づいて、X1が取得した株式について評価通達上の類似業種比準方式による評価を行って更正処分等の本件各処分を行ったものである。
かくして、X1らが行った更正の請求の適法性が争われたものであるが、国は、主として、前述の最高裁各判決の考え方に照らし、本件更正の請求は認められない旨主張した。
(2)これらの当事者の主張に対し、本判決は、まず、国が主張する従前の各最高裁判決との対比について、当該各事案では、国税通則法23条1項所定の更正の請求期間内に更正の請求の手続を執ることなく、当該期間経過後に課税庁の調査時の指摘等を受けたことを契機として当初契約についての錯誤による無効を主張したもので本件と事案を異にし、これらの事案とは異なり特段の事情がある場合に限りその例外を認めることは、上記各最高裁判決に抵触するものではない旨判示した。
次いで、本判決は、本件の事実関係の下では、「更正の請求において課税負担の前提事項の錯誤を理由とする遺産分割の無効の主張を認めても上記(2)の弊害が生ずるおそれがなく、申告納税制度の趣旨・構造及び租税法上の信義則に反するとはいえないと認めるべき特段の事情がある場合に該当するものというべきである。」と判示し、更に、本件においては、X1らが法定申告期限から1年以内に自主的に第一次遺産分割を是正した等の特段の事情が認められるので、第一次遺産分割のうちI会社の株式の配分に係る部分の錯誤による無効を主張できるとし、「その錯誤による無効は、国税通則法23条1項1号にいう『当該申告書に記載した課税標準等若しくは税額等の計算が国税に関する法律の規定に従っていなかったこと』の事由に該当するものと解される。」と判示した。
(3)このような本件判決の考え方は、本件事案において納税者の自主的な判断によって早期に当初契約が是正されて更正の請求が行われたという点で妥当なものと解されている(注11)。しかしながら、前記1で述べたように、国税通則法23条1項と2項の明文規定からは、仮に、本件において国税通則法施行令6条1項2号にいう「やむを得ない事情」を認め得るとしても、それだけでは1項の更正の請求は認められないことになる。
また、本判決は、国が主張する従前の各最高裁判決の事案では、いずれ法定申告期限から1年を経過した後の税務調査等において当初契約における錯誤が発覚して当該当初契約を変更したものであって、本件事案とは内容を異にすると指摘する。しかしながら、前掲の最高裁平成13年4月13日第二小法廷決定の原審が引用している大阪地裁平成12年2月23日判決は、「この課税負担の錯誤が当該法律行為の動機の錯誤であるとして、右法律行為が無効であることを法定申告期間を経過した時点で主張することはできないと解するのが相当である。」と判示しているのである。
また、前掲の最高裁平成10年1月27日第二小法廷判決の原審である大阪高裁平成8年7月25日判決は、国税通則法施行令6条1項2号にいう「やむを得ない事情」とは、法定の解除事由がある場合等、「これに類する客観的な理由がある場合をいうものと解すべきである。」と判示している。
このような従前の裁判例に照らした場合には、本件のように、節税方法の失敗を理由に法定申告期限から1年以内に第一次遺産分割を是正して更正の請求をしたとしても、当該更正の請求は、前掲各判決の考え方では適法なものとは認められないものと推測される。その点では、本判決が従前の各最高裁判決の事案と本件の事案とは異なるとすることには、疑義を残すことになる。
もっとも、前記1で述べたように、国税通則法23条1項と2項との間には、文理上理解し難い問題を残しているところ、本判決は、そのような立法上の問題を無視して個別妥当な判断をしたものとも評価しうる。しかし、このような問題については、やはり、立法上の解決が図られるべきである(注12)。
5 本判決の意義と問題点
以上のように、本件においては、課税上の有利性を目的として遺産分割を行って相続税の申告を済ませた後、当該有利性が得られないことが発覚して、当該遺産分割をやり直して更正の請求及び修正申告を行ったことの適法性が問題となったものである。このように、節税を目的とした当初契約が当該節税が得られないということで当初契約を解約(解消)することは、実務上まま生じることであり、当該解約が課税上認め得るか否かは争訟事件でも問題になってきた。そして、従前の争訟事件では、当該解約の課税上の有効性は否定されてきた。
しかしながら、本判決は、前述のように、本件においては、第一次遺産分割の是正が法定申告期限から1年以内にされ、かつ、税務調査前に更正の請求がされたこと等を重視して、従前の争訟事件とは事案を異にし、特段の事情が認め得るとして、当該更正の請求を適法なものと認めた。また、この判決は、国が控訴しなかったので、確定している。したがって、本判決は、節税の失敗が救済される場合の先例として、重視されるものである。
しかしながら、本判決は、前述のように、国税通則法23条1項と2項の規定上の不備を解決しているわけではなく、また、前掲各最高裁判決との整合性においても問題を残している。よって、これらの問題について、今後一層の検討が必要とされる。
なお、本訴において、国は、相続税法32条及び同法55条の規定を前提として、本件更正の請求の違法性を主張しているが、この点については、本判決の判示したところに委ねることとする。
(しながわ・よしのぶ)
(注1)金子宏『租税法 第14版』(弘文堂)109頁等参照。
(注2)志場喜徳郎ほか編『国税通則法精解 平成16年版』(大蔵財務協会)325頁参照。
(注3)最高裁昭和57年2月23日第三小法廷判決(民集36巻2号215頁)、最高裁昭和60年5月17日第二小法廷判決(税資145号463頁)、大阪地裁平成6年10月26日判決(同206号66頁)、横浜地裁平成9年11月19日判決(同229号663頁)、大阪高裁平成14年7月25日判決(同252号9167順号。同判決の評釈については、品川芳宣・TKC税研情報2003年2月号27頁等参照)等参照。
(注4)法令用語研究会編『法律用語辞典 第3版』(有斐閣)354頁参照。
(注5)法人税基本通達2-2-16、最高裁昭和62年7月10日第二小法廷判決(税資159号65頁)等参照。
(注6)このような判決が国税通則法23条2項1号にいう「判決」に該当しないことについては、横浜地裁平成9年11月19日判決(税資229号663頁)等参照。
(注7)前出(注1)109頁等参照。
(注8)武田昌輔監修『DHCコンメンタール国税通則法』(第一法規)1巻1429の2頁、谷口勢津夫「通常の更正の請求と特別の更正の請求との関係」シュトイエル328号1頁等参照。
(注9)今村隆「錯誤又は合意解除による無効主張」税理42巻6号196頁、一杉直「東京地裁昭和60年10月23日判決評釈」税経通信41巻14号216頁等参照。
(注10)同判決については、品川芳宣「現物出資に係る錯誤・合意解除による無効主張の可否」TKC税研情報1999年12月号20頁参照。
(注11)三木義一「遺産分割の錯誤無効と更正の請求―東京地裁平成21年2月27日判決を素材として―」税務事例2009年5月号1頁参照。
(注12)前出(注10)、同(注11)の各論文参照。
品川芳宣(しながわよしのぶ)
国税庁審理課課長補佐、東京地裁調査官、税務大学校教育二部長、国税庁資産評価企画官、同徴収課長、同管理課長、高松国税局長などを経て、平成7年筑波大学教授。平成17年早稲田大学大学院客員教授(専任)、筑波大学名誉教授、税務大学校客員教授。弁護士
【主要著書】
『課税所得と企業利益』(税務研究会)、『役員給与税務事例集』(商事法務研究会)、『役員報酬の法律と実務』(同)、『附帯税の事例研究』(財経詳報社)、『法人税の判例』(ぎょうせい)、『相続税財産評価の論点』(同)、『重要租税判決の実務研究・増補改訂版』(大蔵財務協会)、『役員報酬の税務事例研究』(財経詳報社)、『租税法律主義と税務通達』(ぎょうせい)、『徹底解明相続税財産評価の理論と実践』(同)他多数。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -

Copyright (C) 2019
SHINNIPPON-HOKI PUBLISHING CO.,LTD.