解説記事2009年07月27日 【制度解説】 「継続企業の前提に関する注記」に係る四半期連結財務諸表規則等の改正の要点(2009年7月27日号・№316)
解説
「継続企業の前提に関する注記」に係る四半期連結財務諸表規則等の改正の要点
金融庁総務企画局企業開示課主任会計専門官 平松 朗
前金融庁総務企画局企業開示課課長補佐 大橋英樹
Ⅰ.はじめに
今般、企業会計審議会から「中間監査基準及び四半期レビュー基準の改訂に関する意見書」(平成21年6月30日付)が公表され、継続企業
(ゴーイング・コンサーン)の前提に関する注記に係る中間監査基準および四半期レビュー基準の改訂が行われるとともに、7月8日付で「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」(平成21年内閣府令第41号)が公布され、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(以下「四半期財務諸表等規則」という)、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(以下「中間財務諸表等規則」という)、「企業内容等の開示に関する内閣府令」(以下「開示府令」という)など関係規定についても改正が行われた。
また、企業会計基準委員会(ASBJ)からは、6月26日付で改正企業会計基準第12号「四半期財務諸表に関する会計基準」(以下「四半期会計基準」という)が公表された(脚注1)。当該基準の改正は、継続企業の前提に関する注記に係る規定部分を内閣府令等に整合させるために行われたものと承知している。
企業会計審議会は、平成21年4月9日に開催された総会において「監査基準の改訂に関する意見書」(以下「改訂意見書」という)を確定した。また、4月20日付で「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」(平成21年内閣府令第27号)が公布され、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(以下「財務諸表等規則」という)、開示府令など関係規定が改正された。改正内容は継続企業の前提に関する注記に係るものであるが、経緯および詳細については別稿を参照されたい(脚注2)。
4月9日付の改訂意見書の前文においては、「中間監査基準及び四半期レビュー基準においても、継続企業の前提に関わる同様の基準が規定されていることから、今後、監査部会において同様の観点からの改訂を検討することが必要である」とされ、これに従って、5月14日に監査部会が開催され、さらに6月30日に開催された総会・監査部会合同会合において中間監査基準および四半期レビュー基準が確定された。今般の改正は、これに合わせる形で内閣府令等の改正が行われたものである。
改正内容は、年度決算に係る改正とほぼ同様であり、一定の事象や状況が存在する場合であって、経営者等の対応策等を勘案してもなお「継続企業の前提に関する重要な不確実性」がある場合に限って、継続企業の前提に関する注記を求めるよう改正されている。
また、半期報告書、四半期報告書におけるいわゆるリスク情報やMD&A情報についても有価証券報告書の開示内容に整合させるための改正が行われた。
これら一連の改正事項は、基本的に平成21年6月30日以後終了する中間会計期間および四半期会計期間から適用される(脚注3)。
以下では、改正の概要を解説することとするが、文中意見にわたる部分は私見であることをあらかじめ申し添える。
Ⅱ.四半期財務諸表等規則等の改正
1.財務諸表等規則等に係る4月改正の概要 「継続企業の前提に関する注記」に関する規定は、平成21年4月20日付の財務諸表等規則等の改正により大幅に修正された。
改正前までは、「継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況」があるか否かという、いわば形式的な基準によって、継続企業の前提に関する注記の要否が判断される実務が行われる傾向にあった。
たとえば、貸借対照表日において債務超過や重要な債務の不履行のみならず、継続的な営業損失の発生や重要な営業損失といった事象や状況が認められれば、ほぼ自動的に重要な疑義を抱かせる事象や状況が存在するものとして、注記が求められる実務が行われていた(脚注4)。
また、注記がされたうえで、監査報告書を作成する際に、監査人が経営者の対応や経営計画の合理性を検討し、最終的に監査人による意見が表明されるという仕組みになっていたが、改正後は、「継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況」が認められる場合は、まず、経営者がその事象や状況を解消し、または改善するための対応策を検討、評価することになる。そして、このような対応策を講じてもなお継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められるときに注記が必要となることに改められた。
条文(財務諸表等規則8条の27)に沿って説明すると、この改正により、まず、形式的な実務を招きやすい「債務超過等財務指標の悪化の傾向、重要な債務の不履行等財政破綻の可能性」という例示部分を削除した。
また、「……事象又は状況が存在する場合であつて、当該事象又は状況を解消し、又は改善するための対応をしてもなお継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められるときは……」という文言を挿入し、新しいプロセスの考え方を具体的に条文化している。
さらに、「ただし、貸借対照表日後において、当該重要な不確実性が認められなくなつた場合は、注記をすることを要しない。」というただし書を設けている。
これは、貸借対照表日後において重要な不確実性が認められなくなった場合には、むしろ注記をしない方が有用な情報になるという面があるという考え方に基づく。
2.四半期財務諸表等規則等に係る今般の改正の概要 以上のような財務諸表等規則および「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(以下「連結財務諸表規則」という)の改正内容を踏まえ、四半期財務諸表等規則、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(以下「四半期連結財務諸表規則」という)、中間財務諸表等規則の継続企業の前提に関する注記に係る各規定の改正が行われた(「中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」において継続企業の前提に関する注記について規定している17条の14は、準用・読替え方式であるため改正は行われなかったが、内容は改正後のものに変容している)。
改正内容は、年度決算に係る改正と同様であり、貸借対照表日は四半期貸借対照表日、中間貸借対照表日と置き換えられている。
また、四半期連結財務諸表規則27条は、準用・読替え方式に改められている。
3.四半期財規ガイドライン等に係る今般の改正の概要 ガイドラインに関しては、年度決算に準じた整備が行われるとともに、中間監査基準または四半期レビュー基準に関連した改正が行われた。
(1)財規ガイドラインの準用 まず、財規ガイドライン(「『財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則』の取扱いに関する留意事項について」。他のガイドラインについて同様に略す)8の27-3の改正に応じて、四半期財規ガイドライン、中間財規ガイドラインにおいても、「総合的かつ実質的に判断を行うものとし、……事象又は状況が存在するか否かといった画一的な判断を行うことのないよう留意する」旨を準用する改正が行われた(四半期財規ガイドライン21 2、中間財規ガイドライン5の18-2)。
(2)重要な不確実性の変化と対応策 次に、前会計期間の財務諸表において注記した継続企業の前提に関する重要な不確実性が四半期貸借対照表日において認められる場合には、重要な不確実性の変化も含めて記載する。変化が認められない場合は、前会計期間の注記を踏まえる必要があるとの留意規定が設けられている(四半期財規ガイドライン21 3、同旨:中間財規ガイドライン5の18-3)。
ここで「踏まえる」という用語には、前会計期間の注記に係る記載でそのまま使えるところは使うということが含意されている。
この点、日本公認会計士協会監査・保証実務委員会報告第83号「四半期レビューに関する実務指針」(以下「実務指針」という)においてもレビュー手続として「大きな変化がなかった場合には、前会計期間の開示を踏まえた同様の開示が行われているかどうかを検討しなければならない」とされており、両者は符合している。
また、「対応策」については、少なくとも翌四半期会計期間の末日まで(中間会計期間の場合は当該中間会計期間が属する事業年度の末日まで)を対象とした対応策を記載することが求められている(四半期財規ガイドライン21 4、中間財規ガイドライン5の18-4)。
「(……前会計期間の注記を踏まえる必要がある場合を除く。)」とは、重要な不確実性について変化が認められない場合には、前事業年度において立てられた対応策がそのまま生きているため「少なくとも翌四半期会計期間」というのは該当しないことを明らかにしている。
この点も、実務指針では、「……大きな変化がないときには、前事業年度において1年間の評価及び対応策が求められていることから、各四半期会計期間においてこれらを引き継ぎ、当四半期会計期間が属する事業年度の末日までの評価及び対応策を求めることになる」とされており、両者の内容は整合的である。
(3)重要な不確実性が認められる理由 前会計期間の決算日における継続企業の前提に関する重要な不確実性に大きな変化があった場合または当四半期会計期間に継続企業の前提に関する重要な不確実性が新たに認められた場合であって、当四半期会計期間の末日から1年にわたって継続企業の前提が成立するとの評価に基づいて四半期財務諸表を作成するときは、各規則が規定する「当該重要な不確実性が認められる理由」として、具体的な対応策が未定であること、対応策の対象期間を超えた期間についても継続企業の前提が成立すると評価した理由等を含めて記載することとされた(四半期財規ガイドライン21 5、同旨:中間財規ガイドライン5の18-5)。
経営者がそのように評価するについては何らかの対応があると考えられるからである。評価の根拠となった経営者の対応等を記載することにより、中間監査や四半期レビュー手続に資するという面もあろうかと思われる。
実務指針においては、「……経営者から具体的に対応策が提示されていない期間について、経営者はどのように対応する意向があるかについて質問等を行う」とされている。
(4)重要な後発事象に該当する場合 また、四半期(中間)貸借対照表日後に継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象または状況が発生した場合であって、当該事象または状況を解消し、または改善するための対応をしてもなお継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ、四半期会計期間が属する事業年度以降の財政状態、経営成績およびキャッシュ・フローの状況に重要な影響を及ぼすときは、当該重要な不確実性の存在は、重要な後発事象に該当する(四半期財規ガイドライン21 6、同旨:中間財規ガイドライン5の18-6)。
Ⅲ.開示府令等の改正
1.「事業等のリスク」等の開示 四半期財務諸表等規則等の改正と同時に「事業等のリスク」(リスク情報)および「財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析」(MD&A)に係る開示府令等の改正が行われた。
これらの改正は、四半期会計基準、四半期財務諸表等規則等の改正に伴い、継続企業の前提に関する注記の範囲が改正されたことに起因して行われたが、その趣旨については、中間監査基準の改訂に関する意見書および四半期レビュー基準の改訂に関する意見書のそれぞれの前文に言及がある。
たとえば、四半期レビュー基準の改訂に関する意見書においては「上場企業等において、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められず当該注記を行わないケースにおいても、四半期報告書の『事業等のリスク』等において、一定の事象や経営者の対応策等を開示し、利害関係者に情報提供が行われることが適切である」とされている。
そもそも「事業等のリスク」および「財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析」の開示は、平成15年3月31日公布、同年4月1日より施行された開示府令の改正に際して導入され、有価証券報告書については施行日以後開始する事業年度に係るものから適用されたもので、3月決算会社については平成16年3月期の有価証券報告書から適用された。
「事業等のリスク」については、「事業の内容」「経理の状況」等に関する事項のうち、投資判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事象などリスク情報の記載を求め、「財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析」として経営者による財政・経営成績等の分析についての記載を求める。
これらの情報は、有価証券報告書以外の開示書類では求められていなかったが、平成20年4月1日以後開始する事業年度から提出される四半期報告書においては、「財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析」の記載が求められていた。
2.開示府令に係る今般の改正の概要
(1)改正の全体像 今般の改正は、次のようなものとなっている。
① 四半期報告書では、「事業等のリスク」の欄が新設され、提出会社が将来にわたって事業活動を継続するとの前提に重要な疑義を生じさせるような事象または状況その他提出会社の経営に重要な影響を及ぼす事象(重要事象等)の記載等を求めるとともに、「財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析」において、新たに重要事項等についての分析・検討内容、対応策等の記載を求める。
② 半期報告書においては、「事業等のリスク」および「財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析」の欄を新設し、四半期報告書と同様の内容の記載を求める。
これらの改正は、重要事象等を開示する受け皿として設けられたというよりは、開示を求めることとしたことを契機に、「事業等のリスク」および「財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析」の開示を求めることにより、四半期報告書や半期報告書における情報開示の一層の充実を図ることとしたものである。
上述の欄の新設に伴い、第4号の3様式(内国会社の四半期報告書)の「記載上の注意」の(9-2)が新設された。
また、(11)が改正され、b項が追加・挿入された。
さらに、第5号様式(内国会社の半期報告書)では、記載上の注意(11-2)および(11-3)が新設された。
他に第9号の3様式(外国会社の四半期報告書)、第10号様式(外国会社の半期報告書)、第11号様式(内国会社の発行登録書)および第12号様式(内国会社の発行登録追補書類)についても同様の改正が行われている。
以下では、第4号の3様式を中心に解説を進める。
(2)改正の具体的内容 上述のように今回の改正では、第4号の3様式において「事業等のリスク」および記載上の注意(9-2)が新設された。より具体的には、まず、「事業等のリスク」の記載事項として、四半期報告書におけるリスク情報についての包括的な規定が置かれた。
すなわち、当四半期会計期間において、「財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況」の異常な変動等、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項が発生した場合、または前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」について重要な変更があった場合には、その旨および具体的な内容をわかりやすく、かつ、簡潔に記載することとされた((9-2)a項)。
さらに、包括的な規定の設置を踏まえ、継続企業の前提に「重要な疑義を生じさせるような事象又は状況その他提出会社の経営に重要な影響を及ぼす事象(重要事象等)が存在する場合」には、その旨、その内容を具体的に、かつ、投資者にわかりやすく記載することとする、四半期財務諸表等規則における継続企業の前提に関する注記に対応する規定が新設された((9-2)b項)。
また、「財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析」に係る記載上の注意として、リスク情報として重要事象等を記載した場合には、「当該重要事象等についての分析・検討内容及び当該重要事象等を解消し、又は改善するための対応策を具体的に」記載することを求める規定が新設された((11)b項)。
3.個別ガイドラインに係る今般の改正の概要 これらの改正に併せて、企業内容等開示ガイドラインの個別ガイドラインのⅠである「『事業等のリスク』に関する取扱いガイドライン」が第4号の3様式および第5号様式にも対応するよう改正されている。
実質的な変更を伴う内容の改正は行われておらず、重要事象等に関しては、その会社の経営への影響も含めて具体的な内容を記載することとされている。
このうち、継続企業の前提に「重要な疑義を生じさせるような事象又は状況」が生じた場合に、その内容が確実に記載されるよう、例示列挙された事象または状況(表参照)が単独で、または複合的に生ずることによってこれに該当しうる旨が示されている(同ガイドライン2)。
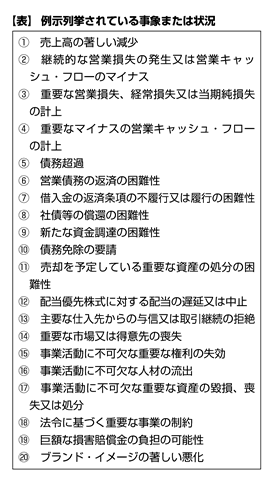 ただし、「事業等のリスク」の記載にあたっては、これらの例示にとらわれることなく、積極的に記載することが望まれるところである。
ただし、「事業等のリスク」の記載にあたっては、これらの例示にとらわれることなく、積極的に記載することが望まれるところである。
さらに、個別ガイドラインのⅡの「『財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析』に関する取扱いガイドライン」についても、第4号の3様式および第5号様式にも対応するよう改正された。
実質的な変更を伴う内容の改正は行われておらず、「当該重要事象等を解消し、又は改善するための対応策」については、提出会社の「財務の健全性に悪影響を及ぼしている、又は及ぼし得る要因に関して経営者が講じている、又は講じる予定の対応策の具体的な内容(実施時期、実現可能性の程度、金額等を含む。)」を記載することとされている。
また、対応策の例としては、(ⅰ)資産の処分に関する計画、(ⅱ)資金調達の計画、(ⅲ)債務免除の計画、(ⅳ)その他が挙げられている。
Ⅳ.中間監査基準および四半期レビュー基準の改訂
中間監査基準および四半期レビュー基準についても、企業会計審議会から平成21年6月30日付で公表された「中間監査基準及び四半期レビュー基準の改訂に関する意見書」により、既述の考え方に沿って継続企業の前提に関する部分の改訂が行われている。同意見書は「中間監査基準の改訂に関する意見書」(以下「改訂中間監査基準」という)、「四半期レビュー基準の改訂に関する意見書」(以下「改訂四半期レビュー基準」という)の2本建ての構成になっている。
改訂中間監査基準の前文では、「監査人は、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在すると判断した場合には、当該事象又は状況に関して合理的な期間について経営者が行った評価及び対応策について検討した上で、なお継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められるか否かを確かめなければならない」とされ、また、監査報告についても「継続企業の前提に関する重要な不確実性」が認められるときの中間財務諸表の記載に関して意見を表明することとされた。
また、改訂四半期レビュー基準の前文においても、「国際レビュー業務基準(ISRE)との整合性を踏まえつつ、継続企業の前提に関する四半期レビューについて、年度監査に準じて、改定監査基準の実施基準と同様の考え方を明確化することにした」とされている。
一連の改訂の意義・内容等の詳細は監査論の専門家による解説を待ちたいが、1点指摘するとすれば、改訂前と異なり、経営者の評価期間と対応策の対象期間が異なる場合もあることが想定されていることから、たとえば、四半期については、前文において「当該四半期会計期間末から1年間について経営者の行った評価及び少なくとも当該四半期会計期間の翌四半期会計期間の末日までの経営者の対応策について検討を行った上で、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められるか否か」について判断するものとされている。
この際、経営者の対応策については、たとえば、「1年間の経営計画のようなものが必ずしも存在していること」は求められておらず、また、「当該四半期会計期間の末日後1年間に返済期限が来る債務の返済に対する資金的な手当てが具体的に決定していること」も必ずしも求められていないということに今回の改訂の1つのポイントがある(中間期についても同様)。
また、監査基準同様、「合理性」という用語が、制定当初の一応の合理性という意味ではなく経済的な合理性というような想定外のリジッドな意味に受け取られる傾向が強かったので、改訂基準上、極力「合理性」という用語を使用しないこととされた。
たとえば、中間監査基準の実施基準9の「対応及び経営計画等の合理性を検討」するという部分を「対応策について検討」というように改訂されている。
中間監査基準の報告基準8においても、経営者が「合理的な経営計画等を提示しないときには」意見不表明を検討するという文言が「評価及び対応策を示さないときには、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められるか否かを確かめる十分かつ適切な監査証拠を入手できないことがあるため、」と改訂されており、経営者から合理的な経営計画が示されない場合に、直ちに意見不表明とするような実務については見直しを求めている。
以上の中間監査基準および四半期レビュー基準の改訂に従い、日本公認会計士協会の関係する実務指針も見直され、7月8日付で同月10日に公表されている(脚注5)。
Ⅴ.おわりに
以上に述べたような一連の改正により、半期報告書や四半期報告書における「事業等のリスク」および「財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析」と中間財務諸表や四半期財務諸表における継続企業の前提の注記とを一体として経営上のリスクを開示することになる。
また、継続企業の前提の注記については、改訂中間監査基準や改訂四半期レビュー基準による手続が行われることにより注記内容の確度が向上し、もって、一層の投資者保護が図られることになると思われる。
これらの改正は、中間財務諸表(半期報告書)に係るものは平成21年6月中間期から、四半期財務諸表(四半期報告書)に係るものは平成21年6月四半期から適用される。
関係者には、検討する時間は短期間であろうとは思うが、以上のような改正の趣旨を汲み取っていただき、積極的な取組みをお願いしたい。(ひらまつ・あきら/おおはし・ひでき)
脚注
1 丸山顕義「改正企業会計基準第12号『四半期財務諸表に関する会計基準』について」本誌315号20頁参照。
2 平松朗・山下祐士「『継続企業の前提に関する注記』に係る財務諸表等規則等の改正の要点」本誌304号19頁参照。
3 四半期財務諸表等規則、開示府令等の改正規定の適用は、次のとおりである。
(1)四半期財務諸表および四半期連結財務諸表:平成21年6月30日以後に終了する四半期会計期間および四半期累計期間等に係るものから適用。
(2)中間財務諸表:平成21年6月30日以後に終了する中間会計期間に係るものから適用。
(3)四半期報告書:平成21年6月30日に終了する四半期会計期間に係るものから適用。
(4)半期報告書:平成21年6月30日以後に終了する中間会計期間に係るものから適用。
4 「監査基準の改訂について」(平成21年4月9日・企業会計審議会)においては、「継続企業の前提に関する注記の開示を規定している財務諸表等規則等やその監査を規定する監査基準において、一定の事象や状況が存在すれば直ちに継続企業の前提に関する注記及び追記情報の記載を要するとの規定となっているとの理解がなされ、一定の事実の存在により画一的に当該注記を行う実務となっているとの指摘がある。また、それらの規定や実務は国際的な基準とも必ずしも整合的でないとも指摘されている。」との記述がある。
5 平成21年7月8日付で日本公認会計士協会から今回の一連の改正に関連し、次の実務指針が公表されている。
(監査・保証実務委員会報告関係)
(1)第83号「四半期レビューに関する実務指針」の改正について
(2)第75号「監査報告書作成に関する実務指針」の改正について
(3)第76号「後発事象に関する監査上の取扱い」の改正について
(監査基準委員会報告書関係)
(4)第17号「中間監査」の一部改正について
「継続企業の前提に関する注記」に係る四半期連結財務諸表規則等の改正の要点
金融庁総務企画局企業開示課主任会計専門官 平松 朗
前金融庁総務企画局企業開示課課長補佐 大橋英樹
Ⅰ.はじめに
今般、企業会計審議会から「中間監査基準及び四半期レビュー基準の改訂に関する意見書」(平成21年6月30日付)が公表され、継続企業
(ゴーイング・コンサーン)の前提に関する注記に係る中間監査基準および四半期レビュー基準の改訂が行われるとともに、7月8日付で「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」(平成21年内閣府令第41号)が公布され、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(以下「四半期財務諸表等規則」という)、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(以下「中間財務諸表等規則」という)、「企業内容等の開示に関する内閣府令」(以下「開示府令」という)など関係規定についても改正が行われた。
また、企業会計基準委員会(ASBJ)からは、6月26日付で改正企業会計基準第12号「四半期財務諸表に関する会計基準」(以下「四半期会計基準」という)が公表された(脚注1)。当該基準の改正は、継続企業の前提に関する注記に係る規定部分を内閣府令等に整合させるために行われたものと承知している。
企業会計審議会は、平成21年4月9日に開催された総会において「監査基準の改訂に関する意見書」(以下「改訂意見書」という)を確定した。また、4月20日付で「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」(平成21年内閣府令第27号)が公布され、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(以下「財務諸表等規則」という)、開示府令など関係規定が改正された。改正内容は継続企業の前提に関する注記に係るものであるが、経緯および詳細については別稿を参照されたい(脚注2)。
4月9日付の改訂意見書の前文においては、「中間監査基準及び四半期レビュー基準においても、継続企業の前提に関わる同様の基準が規定されていることから、今後、監査部会において同様の観点からの改訂を検討することが必要である」とされ、これに従って、5月14日に監査部会が開催され、さらに6月30日に開催された総会・監査部会合同会合において中間監査基準および四半期レビュー基準が確定された。今般の改正は、これに合わせる形で内閣府令等の改正が行われたものである。
改正内容は、年度決算に係る改正とほぼ同様であり、一定の事象や状況が存在する場合であって、経営者等の対応策等を勘案してもなお「継続企業の前提に関する重要な不確実性」がある場合に限って、継続企業の前提に関する注記を求めるよう改正されている。
また、半期報告書、四半期報告書におけるいわゆるリスク情報やMD&A情報についても有価証券報告書の開示内容に整合させるための改正が行われた。
これら一連の改正事項は、基本的に平成21年6月30日以後終了する中間会計期間および四半期会計期間から適用される(脚注3)。
以下では、改正の概要を解説することとするが、文中意見にわたる部分は私見であることをあらかじめ申し添える。
Ⅱ.四半期財務諸表等規則等の改正
1.財務諸表等規則等に係る4月改正の概要 「継続企業の前提に関する注記」に関する規定は、平成21年4月20日付の財務諸表等規則等の改正により大幅に修正された。
改正前までは、「継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況」があるか否かという、いわば形式的な基準によって、継続企業の前提に関する注記の要否が判断される実務が行われる傾向にあった。
たとえば、貸借対照表日において債務超過や重要な債務の不履行のみならず、継続的な営業損失の発生や重要な営業損失といった事象や状況が認められれば、ほぼ自動的に重要な疑義を抱かせる事象や状況が存在するものとして、注記が求められる実務が行われていた(脚注4)。
また、注記がされたうえで、監査報告書を作成する際に、監査人が経営者の対応や経営計画の合理性を検討し、最終的に監査人による意見が表明されるという仕組みになっていたが、改正後は、「継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況」が認められる場合は、まず、経営者がその事象や状況を解消し、または改善するための対応策を検討、評価することになる。そして、このような対応策を講じてもなお継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められるときに注記が必要となることに改められた。
条文(財務諸表等規則8条の27)に沿って説明すると、この改正により、まず、形式的な実務を招きやすい「債務超過等財務指標の悪化の傾向、重要な債務の不履行等財政破綻の可能性」という例示部分を削除した。
また、「……事象又は状況が存在する場合であつて、当該事象又は状況を解消し、又は改善するための対応をしてもなお継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められるときは……」という文言を挿入し、新しいプロセスの考え方を具体的に条文化している。
さらに、「ただし、貸借対照表日後において、当該重要な不確実性が認められなくなつた場合は、注記をすることを要しない。」というただし書を設けている。
これは、貸借対照表日後において重要な不確実性が認められなくなった場合には、むしろ注記をしない方が有用な情報になるという面があるという考え方に基づく。
2.四半期財務諸表等規則等に係る今般の改正の概要 以上のような財務諸表等規則および「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(以下「連結財務諸表規則」という)の改正内容を踏まえ、四半期財務諸表等規則、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(以下「四半期連結財務諸表規則」という)、中間財務諸表等規則の継続企業の前提に関する注記に係る各規定の改正が行われた(「中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」において継続企業の前提に関する注記について規定している17条の14は、準用・読替え方式であるため改正は行われなかったが、内容は改正後のものに変容している)。
改正内容は、年度決算に係る改正と同様であり、貸借対照表日は四半期貸借対照表日、中間貸借対照表日と置き換えられている。
また、四半期連結財務諸表規則27条は、準用・読替え方式に改められている。
3.四半期財規ガイドライン等に係る今般の改正の概要 ガイドラインに関しては、年度決算に準じた整備が行われるとともに、中間監査基準または四半期レビュー基準に関連した改正が行われた。
(1)財規ガイドラインの準用 まず、財規ガイドライン(「『財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則』の取扱いに関する留意事項について」。他のガイドラインについて同様に略す)8の27-3の改正に応じて、四半期財規ガイドライン、中間財規ガイドラインにおいても、「総合的かつ実質的に判断を行うものとし、……事象又は状況が存在するか否かといった画一的な判断を行うことのないよう留意する」旨を準用する改正が行われた(四半期財規ガイドライン21 2、中間財規ガイドライン5の18-2)。
(2)重要な不確実性の変化と対応策 次に、前会計期間の財務諸表において注記した継続企業の前提に関する重要な不確実性が四半期貸借対照表日において認められる場合には、重要な不確実性の変化も含めて記載する。変化が認められない場合は、前会計期間の注記を踏まえる必要があるとの留意規定が設けられている(四半期財規ガイドライン21 3、同旨:中間財規ガイドライン5の18-3)。
ここで「踏まえる」という用語には、前会計期間の注記に係る記載でそのまま使えるところは使うということが含意されている。
この点、日本公認会計士協会監査・保証実務委員会報告第83号「四半期レビューに関する実務指針」(以下「実務指針」という)においてもレビュー手続として「大きな変化がなかった場合には、前会計期間の開示を踏まえた同様の開示が行われているかどうかを検討しなければならない」とされており、両者は符合している。
また、「対応策」については、少なくとも翌四半期会計期間の末日まで(中間会計期間の場合は当該中間会計期間が属する事業年度の末日まで)を対象とした対応策を記載することが求められている(四半期財規ガイドライン21 4、中間財規ガイドライン5の18-4)。
「(……前会計期間の注記を踏まえる必要がある場合を除く。)」とは、重要な不確実性について変化が認められない場合には、前事業年度において立てられた対応策がそのまま生きているため「少なくとも翌四半期会計期間」というのは該当しないことを明らかにしている。
この点も、実務指針では、「……大きな変化がないときには、前事業年度において1年間の評価及び対応策が求められていることから、各四半期会計期間においてこれらを引き継ぎ、当四半期会計期間が属する事業年度の末日までの評価及び対応策を求めることになる」とされており、両者の内容は整合的である。
(3)重要な不確実性が認められる理由 前会計期間の決算日における継続企業の前提に関する重要な不確実性に大きな変化があった場合または当四半期会計期間に継続企業の前提に関する重要な不確実性が新たに認められた場合であって、当四半期会計期間の末日から1年にわたって継続企業の前提が成立するとの評価に基づいて四半期財務諸表を作成するときは、各規則が規定する「当該重要な不確実性が認められる理由」として、具体的な対応策が未定であること、対応策の対象期間を超えた期間についても継続企業の前提が成立すると評価した理由等を含めて記載することとされた(四半期財規ガイドライン21 5、同旨:中間財規ガイドライン5の18-5)。
経営者がそのように評価するについては何らかの対応があると考えられるからである。評価の根拠となった経営者の対応等を記載することにより、中間監査や四半期レビュー手続に資するという面もあろうかと思われる。
実務指針においては、「……経営者から具体的に対応策が提示されていない期間について、経営者はどのように対応する意向があるかについて質問等を行う」とされている。
(4)重要な後発事象に該当する場合 また、四半期(中間)貸借対照表日後に継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象または状況が発生した場合であって、当該事象または状況を解消し、または改善するための対応をしてもなお継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ、四半期会計期間が属する事業年度以降の財政状態、経営成績およびキャッシュ・フローの状況に重要な影響を及ぼすときは、当該重要な不確実性の存在は、重要な後発事象に該当する(四半期財規ガイドライン21 6、同旨:中間財規ガイドライン5の18-6)。
Ⅲ.開示府令等の改正
1.「事業等のリスク」等の開示 四半期財務諸表等規則等の改正と同時に「事業等のリスク」(リスク情報)および「財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析」(MD&A)に係る開示府令等の改正が行われた。
これらの改正は、四半期会計基準、四半期財務諸表等規則等の改正に伴い、継続企業の前提に関する注記の範囲が改正されたことに起因して行われたが、その趣旨については、中間監査基準の改訂に関する意見書および四半期レビュー基準の改訂に関する意見書のそれぞれの前文に言及がある。
たとえば、四半期レビュー基準の改訂に関する意見書においては「上場企業等において、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められず当該注記を行わないケースにおいても、四半期報告書の『事業等のリスク』等において、一定の事象や経営者の対応策等を開示し、利害関係者に情報提供が行われることが適切である」とされている。
そもそも「事業等のリスク」および「財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析」の開示は、平成15年3月31日公布、同年4月1日より施行された開示府令の改正に際して導入され、有価証券報告書については施行日以後開始する事業年度に係るものから適用されたもので、3月決算会社については平成16年3月期の有価証券報告書から適用された。
「事業等のリスク」については、「事業の内容」「経理の状況」等に関する事項のうち、投資判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事象などリスク情報の記載を求め、「財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析」として経営者による財政・経営成績等の分析についての記載を求める。
これらの情報は、有価証券報告書以外の開示書類では求められていなかったが、平成20年4月1日以後開始する事業年度から提出される四半期報告書においては、「財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析」の記載が求められていた。
2.開示府令に係る今般の改正の概要
(1)改正の全体像 今般の改正は、次のようなものとなっている。
① 四半期報告書では、「事業等のリスク」の欄が新設され、提出会社が将来にわたって事業活動を継続するとの前提に重要な疑義を生じさせるような事象または状況その他提出会社の経営に重要な影響を及ぼす事象(重要事象等)の記載等を求めるとともに、「財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析」において、新たに重要事項等についての分析・検討内容、対応策等の記載を求める。
② 半期報告書においては、「事業等のリスク」および「財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析」の欄を新設し、四半期報告書と同様の内容の記載を求める。
これらの改正は、重要事象等を開示する受け皿として設けられたというよりは、開示を求めることとしたことを契機に、「事業等のリスク」および「財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析」の開示を求めることにより、四半期報告書や半期報告書における情報開示の一層の充実を図ることとしたものである。
上述の欄の新設に伴い、第4号の3様式(内国会社の四半期報告書)の「記載上の注意」の(9-2)が新設された。
また、(11)が改正され、b項が追加・挿入された。
さらに、第5号様式(内国会社の半期報告書)では、記載上の注意(11-2)および(11-3)が新設された。
他に第9号の3様式(外国会社の四半期報告書)、第10号様式(外国会社の半期報告書)、第11号様式(内国会社の発行登録書)および第12号様式(内国会社の発行登録追補書類)についても同様の改正が行われている。
以下では、第4号の3様式を中心に解説を進める。
(2)改正の具体的内容 上述のように今回の改正では、第4号の3様式において「事業等のリスク」および記載上の注意(9-2)が新設された。より具体的には、まず、「事業等のリスク」の記載事項として、四半期報告書におけるリスク情報についての包括的な規定が置かれた。
すなわち、当四半期会計期間において、「財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況」の異常な変動等、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項が発生した場合、または前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」について重要な変更があった場合には、その旨および具体的な内容をわかりやすく、かつ、簡潔に記載することとされた((9-2)a項)。
さらに、包括的な規定の設置を踏まえ、継続企業の前提に「重要な疑義を生じさせるような事象又は状況その他提出会社の経営に重要な影響を及ぼす事象(重要事象等)が存在する場合」には、その旨、その内容を具体的に、かつ、投資者にわかりやすく記載することとする、四半期財務諸表等規則における継続企業の前提に関する注記に対応する規定が新設された((9-2)b項)。
また、「財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析」に係る記載上の注意として、リスク情報として重要事象等を記載した場合には、「当該重要事象等についての分析・検討内容及び当該重要事象等を解消し、又は改善するための対応策を具体的に」記載することを求める規定が新設された((11)b項)。
3.個別ガイドラインに係る今般の改正の概要 これらの改正に併せて、企業内容等開示ガイドラインの個別ガイドラインのⅠである「『事業等のリスク』に関する取扱いガイドライン」が第4号の3様式および第5号様式にも対応するよう改正されている。
実質的な変更を伴う内容の改正は行われておらず、重要事象等に関しては、その会社の経営への影響も含めて具体的な内容を記載することとされている。
このうち、継続企業の前提に「重要な疑義を生じさせるような事象又は状況」が生じた場合に、その内容が確実に記載されるよう、例示列挙された事象または状況(表参照)が単独で、または複合的に生ずることによってこれに該当しうる旨が示されている(同ガイドライン2)。
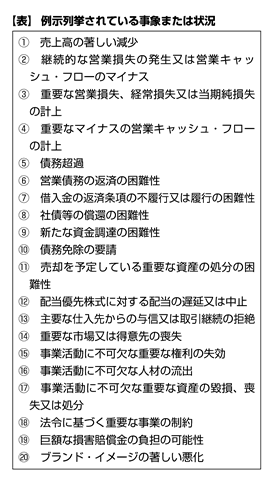 ただし、「事業等のリスク」の記載にあたっては、これらの例示にとらわれることなく、積極的に記載することが望まれるところである。
ただし、「事業等のリスク」の記載にあたっては、これらの例示にとらわれることなく、積極的に記載することが望まれるところである。さらに、個別ガイドラインのⅡの「『財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析』に関する取扱いガイドライン」についても、第4号の3様式および第5号様式にも対応するよう改正された。
実質的な変更を伴う内容の改正は行われておらず、「当該重要事象等を解消し、又は改善するための対応策」については、提出会社の「財務の健全性に悪影響を及ぼしている、又は及ぼし得る要因に関して経営者が講じている、又は講じる予定の対応策の具体的な内容(実施時期、実現可能性の程度、金額等を含む。)」を記載することとされている。
また、対応策の例としては、(ⅰ)資産の処分に関する計画、(ⅱ)資金調達の計画、(ⅲ)債務免除の計画、(ⅳ)その他が挙げられている。
Ⅳ.中間監査基準および四半期レビュー基準の改訂
中間監査基準および四半期レビュー基準についても、企業会計審議会から平成21年6月30日付で公表された「中間監査基準及び四半期レビュー基準の改訂に関する意見書」により、既述の考え方に沿って継続企業の前提に関する部分の改訂が行われている。同意見書は「中間監査基準の改訂に関する意見書」(以下「改訂中間監査基準」という)、「四半期レビュー基準の改訂に関する意見書」(以下「改訂四半期レビュー基準」という)の2本建ての構成になっている。
改訂中間監査基準の前文では、「監査人は、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在すると判断した場合には、当該事象又は状況に関して合理的な期間について経営者が行った評価及び対応策について検討した上で、なお継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められるか否かを確かめなければならない」とされ、また、監査報告についても「継続企業の前提に関する重要な不確実性」が認められるときの中間財務諸表の記載に関して意見を表明することとされた。
また、改訂四半期レビュー基準の前文においても、「国際レビュー業務基準(ISRE)との整合性を踏まえつつ、継続企業の前提に関する四半期レビューについて、年度監査に準じて、改定監査基準の実施基準と同様の考え方を明確化することにした」とされている。
一連の改訂の意義・内容等の詳細は監査論の専門家による解説を待ちたいが、1点指摘するとすれば、改訂前と異なり、経営者の評価期間と対応策の対象期間が異なる場合もあることが想定されていることから、たとえば、四半期については、前文において「当該四半期会計期間末から1年間について経営者の行った評価及び少なくとも当該四半期会計期間の翌四半期会計期間の末日までの経営者の対応策について検討を行った上で、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められるか否か」について判断するものとされている。
この際、経営者の対応策については、たとえば、「1年間の経営計画のようなものが必ずしも存在していること」は求められておらず、また、「当該四半期会計期間の末日後1年間に返済期限が来る債務の返済に対する資金的な手当てが具体的に決定していること」も必ずしも求められていないということに今回の改訂の1つのポイントがある(中間期についても同様)。
また、監査基準同様、「合理性」という用語が、制定当初の一応の合理性という意味ではなく経済的な合理性というような想定外のリジッドな意味に受け取られる傾向が強かったので、改訂基準上、極力「合理性」という用語を使用しないこととされた。
たとえば、中間監査基準の実施基準9の「対応及び経営計画等の合理性を検討」するという部分を「対応策について検討」というように改訂されている。
中間監査基準の報告基準8においても、経営者が「合理的な経営計画等を提示しないときには」意見不表明を検討するという文言が「評価及び対応策を示さないときには、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められるか否かを確かめる十分かつ適切な監査証拠を入手できないことがあるため、」と改訂されており、経営者から合理的な経営計画が示されない場合に、直ちに意見不表明とするような実務については見直しを求めている。
以上の中間監査基準および四半期レビュー基準の改訂に従い、日本公認会計士協会の関係する実務指針も見直され、7月8日付で同月10日に公表されている(脚注5)。
Ⅴ.おわりに
以上に述べたような一連の改正により、半期報告書や四半期報告書における「事業等のリスク」および「財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析」と中間財務諸表や四半期財務諸表における継続企業の前提の注記とを一体として経営上のリスクを開示することになる。
また、継続企業の前提の注記については、改訂中間監査基準や改訂四半期レビュー基準による手続が行われることにより注記内容の確度が向上し、もって、一層の投資者保護が図られることになると思われる。
これらの改正は、中間財務諸表(半期報告書)に係るものは平成21年6月中間期から、四半期財務諸表(四半期報告書)に係るものは平成21年6月四半期から適用される。
関係者には、検討する時間は短期間であろうとは思うが、以上のような改正の趣旨を汲み取っていただき、積極的な取組みをお願いしたい。(ひらまつ・あきら/おおはし・ひでき)
脚注
1 丸山顕義「改正企業会計基準第12号『四半期財務諸表に関する会計基準』について」本誌315号20頁参照。
2 平松朗・山下祐士「『継続企業の前提に関する注記』に係る財務諸表等規則等の改正の要点」本誌304号19頁参照。
3 四半期財務諸表等規則、開示府令等の改正規定の適用は、次のとおりである。
(1)四半期財務諸表および四半期連結財務諸表:平成21年6月30日以後に終了する四半期会計期間および四半期累計期間等に係るものから適用。
(2)中間財務諸表:平成21年6月30日以後に終了する中間会計期間に係るものから適用。
(3)四半期報告書:平成21年6月30日に終了する四半期会計期間に係るものから適用。
(4)半期報告書:平成21年6月30日以後に終了する中間会計期間に係るものから適用。
4 「監査基準の改訂について」(平成21年4月9日・企業会計審議会)においては、「継続企業の前提に関する注記の開示を規定している財務諸表等規則等やその監査を規定する監査基準において、一定の事象や状況が存在すれば直ちに継続企業の前提に関する注記及び追記情報の記載を要するとの規定となっているとの理解がなされ、一定の事実の存在により画一的に当該注記を行う実務となっているとの指摘がある。また、それらの規定や実務は国際的な基準とも必ずしも整合的でないとも指摘されている。」との記述がある。
5 平成21年7月8日付で日本公認会計士協会から今回の一連の改正に関連し、次の実務指針が公表されている。
(監査・保証実務委員会報告関係)
(1)第83号「四半期レビューに関する実務指針」の改正について
(2)第75号「監査報告書作成に関する実務指針」の改正について
(3)第76号「後発事象に関する監査上の取扱い」の改正について
(監査基準委員会報告書関係)
(4)第17号「中間監査」の一部改正について
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -

Copyright (C) 2019
SHINNIPPON-HOKI PUBLISHING CO.,LTD.




















