コラム2009年08月03日 【未公開 裁決事例紹介】 地目宅地の土地を私道と認定、類似不動産を変更(2009年8月3日号・№317)
未公開裁決事例紹介
地目宅地の土地を私道と認定、類似不動産を変更
審判所、登録免許税額の過誤納を認める
○固定資産課税台帳に登録された価格のない土地の所有権移転登記の際に納付した登録税額が過大であるとして行われた還付請求について、審判所が、過誤納の事実を認め、還付通知をすべき理由がない旨の通知処分の全部を取り消した事例(仙裁(諸)平20第11号)
基礎事実 請求人の夫であるXは、平成19年6月14日、▲▲に所在する宅地307.66㎡(以下「本件甲土地」という)および▲▲に所在する宅地178.01㎡(以下「本件乙土地」といい、本件甲土地と併せて「本件両土地」という)について、登記の目的を所有権移転、その原因を平成19年6月8日交換、権利者をX、義務者をY、課税価格を××、登録免許税の額を××と記載した登記申請書を原処分庁に提出して、その所有権移転の登記(以下、本件登記申請書による所有権移転の登記を「本件登記」という)を受ける際に、本件登記に係る登録免許税について納付した。本件両土地は、本件登記の申請日において、いずれも台帳価格のない土地である。
本件登記の際に原処分庁が算定した登録免許税の課税標準の額は、本件両土地に隣接する▲▲に所在する宅地688.72㎡(以下「本件A土地」という)の平成19年度の台帳価格の1㎡当たりの価格××に、本件甲土地の面積307.66㎡と本件乙土地の面積178.01㎡をそれぞれ乗じて計算した価額を合計した金額である。
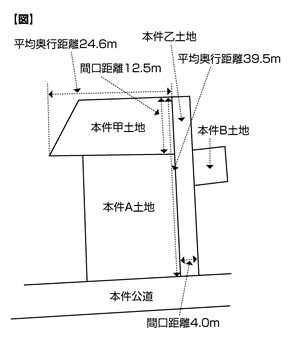
争点および主張 争点は、原処分庁が認定した本件両土地の価格は適正か否か。争点に係る請求人および原処分庁の主張は、次頁表のとおり。
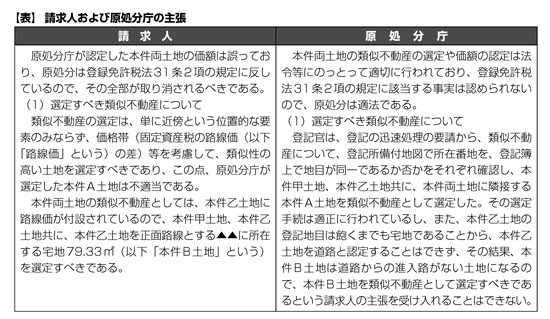
審判所の判断 本事案において、審判所は次の事実を認定している。①Xの死亡に伴う相続人間の遺産分割協議は平成20年4月1日に成立し、請求人は、この相続により本件登記の際に納付した登録免許税に係る還付請求の権利を取得した。②本件甲土地は、いわゆる袋地で、その東側に隣接する本件乙土地を通らないと本件甲土地へ出入りすることはできない。③本件乙土地は、南側で公道(以下「本件公道」という)に隣接しているが、その幅員や形状から建物を建築することは困難であり、近隣住民等の通行の用に供されていることを考慮すると、その実態は私道である。④平成18基準年度の○市固定資産税路線価等公開図によれば、平成17年1月1日を基準日とする路線価として、本件公道に××が、本件乙土地そのものに××が、それぞれ付設されており、本件公道は本件A土地の正面路線であり、本件乙土地は本件B土地の正面路線である。⑤本件両土地は同一の状況類似地域内にあり、その標準宅地も同じであるところ、平成19年度の時点修正率は「0.989」である。⑥「○市固定資産(土地)評価事務取扱要領」は、地方税法348条2項5号に規定する「公共の用に供する道路」に該当しない道路を「私道」と定義し、その台帳価格について、近傍路線価に補正率「0.15」を乗じて価額を求める旨定めている。
そして、上記の認定事実から審判所は、本件甲土地の類似不動産について、本件公道、本件乙土地には路線価がそれぞれ付設されているところ、本件甲土地は、本件公道に面していない袋地で、本件乙土地を通らないと出入りができないことから、本件甲土地の類似不動産は、本件乙土地を正面路線とする土地から選定すべきであるとした。
また、本件乙土地については、南側で本件公道に隣接しているものの、本件乙土地そのものに路線価が付設されていることを考慮すると、本件乙土地の価格水準を反映している路線は本件乙土地であると認められるので、その類似不動産も、本件乙土地を正面路線とする土地から選定すべきであるとした。そのうえで、本件両土地の類似不動産として本件乙土地を正面路線とする本件B土地が相当であると判断し、既に納付した登録免許税額と本件B土地を類似不動産として計算した同税額との差額は過誤納となるとした。
地目宅地の土地を私道と認定、類似不動産を変更
審判所、登録免許税額の過誤納を認める
○固定資産課税台帳に登録された価格のない土地の所有権移転登記の際に納付した登録税額が過大であるとして行われた還付請求について、審判所が、過誤納の事実を認め、還付通知をすべき理由がない旨の通知処分の全部を取り消した事例(仙裁(諸)平20第11号)
基礎事実 請求人の夫であるXは、平成19年6月14日、▲▲に所在する宅地307.66㎡(以下「本件甲土地」という)および▲▲に所在する宅地178.01㎡(以下「本件乙土地」といい、本件甲土地と併せて「本件両土地」という)について、登記の目的を所有権移転、その原因を平成19年6月8日交換、権利者をX、義務者をY、課税価格を××、登録免許税の額を××と記載した登記申請書を原処分庁に提出して、その所有権移転の登記(以下、本件登記申請書による所有権移転の登記を「本件登記」という)を受ける際に、本件登記に係る登録免許税について納付した。本件両土地は、本件登記の申請日において、いずれも台帳価格のない土地である。
本件登記の際に原処分庁が算定した登録免許税の課税標準の額は、本件両土地に隣接する▲▲に所在する宅地688.72㎡(以下「本件A土地」という)の平成19年度の台帳価格の1㎡当たりの価格××に、本件甲土地の面積307.66㎡と本件乙土地の面積178.01㎡をそれぞれ乗じて計算した価額を合計した金額である。
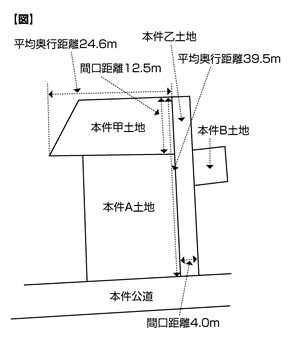
争点および主張 争点は、原処分庁が認定した本件両土地の価格は適正か否か。争点に係る請求人および原処分庁の主張は、次頁表のとおり。
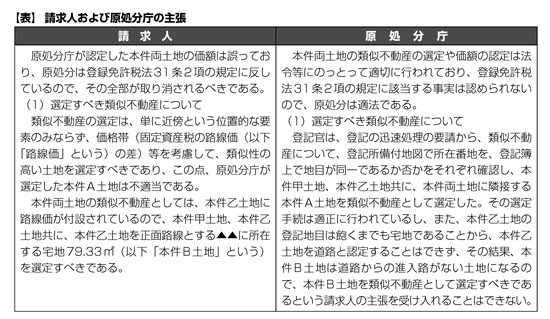
審判所の判断 本事案において、審判所は次の事実を認定している。①Xの死亡に伴う相続人間の遺産分割協議は平成20年4月1日に成立し、請求人は、この相続により本件登記の際に納付した登録免許税に係る還付請求の権利を取得した。②本件甲土地は、いわゆる袋地で、その東側に隣接する本件乙土地を通らないと本件甲土地へ出入りすることはできない。③本件乙土地は、南側で公道(以下「本件公道」という)に隣接しているが、その幅員や形状から建物を建築することは困難であり、近隣住民等の通行の用に供されていることを考慮すると、その実態は私道である。④平成18基準年度の○市固定資産税路線価等公開図によれば、平成17年1月1日を基準日とする路線価として、本件公道に××が、本件乙土地そのものに××が、それぞれ付設されており、本件公道は本件A土地の正面路線であり、本件乙土地は本件B土地の正面路線である。⑤本件両土地は同一の状況類似地域内にあり、その標準宅地も同じであるところ、平成19年度の時点修正率は「0.989」である。⑥「○市固定資産(土地)評価事務取扱要領」は、地方税法348条2項5号に規定する「公共の用に供する道路」に該当しない道路を「私道」と定義し、その台帳価格について、近傍路線価に補正率「0.15」を乗じて価額を求める旨定めている。
そして、上記の認定事実から審判所は、本件甲土地の類似不動産について、本件公道、本件乙土地には路線価がそれぞれ付設されているところ、本件甲土地は、本件公道に面していない袋地で、本件乙土地を通らないと出入りができないことから、本件甲土地の類似不動産は、本件乙土地を正面路線とする土地から選定すべきであるとした。
また、本件乙土地については、南側で本件公道に隣接しているものの、本件乙土地そのものに路線価が付設されていることを考慮すると、本件乙土地の価格水準を反映している路線は本件乙土地であると認められるので、その類似不動産も、本件乙土地を正面路線とする土地から選定すべきであるとした。そのうえで、本件両土地の類似不動産として本件乙土地を正面路線とする本件B土地が相当であると判断し、既に納付した登録免許税額と本件B土地を類似不動産として計算した同税額との差額は過誤納となるとした。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -























