解説記事2009年08月03日 【ニュース特集】 押さえておきたい「廃案」法案と今後の実現可能性(2009年8月3日号・№317)
確定拠出年金法改正、行政不服審査法改正、国による株式買取り……
押さえておきたい「廃案」法案と今後の実現可能性
7月21日の衆院解散に伴い、政府提出の17法案と与野党議員が提出した97法案の計114法案が成立しないまま廃案となった。
廃案となった法案のなかには、確定拠出年金法改正案や「行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案」など税制改正大綱にも改正の内容が明記されていたものや、国による株式買取りを実現するための法案など、当初は実現が見込まれていたものも含まれている。
そこで本特集では、本誌読者である実務家が押さえておくべき「廃案」となった法案と、それらの今後の実現可能性について整理してみた。
1 内閣提出法律案関係
確定拠出年金関連では、政令事項の拠出限度額引上げのみ実現 衆議院解散に伴い廃案となった政府提出の17法案と与野党議員が提出した97法案の計114法案のなかには、元々今国会での実現が難しいものも多く含まれる一方で、当然実現するものと思われていたものが少なからず含まれている。
その代表格が、確定拠出年金法改正案だ。平成21年度税制改正大綱には、確定拠出年金に関して、右頁図表1の改正項目が盛り込まれていた。
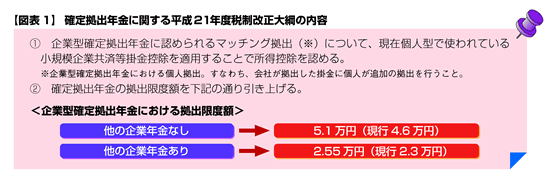
このうち①については、企業年金にマッチング拠出を認めることなどを盛り込んだ「企業年金等の整備を図るための確定拠出年金法等の一部を改正する法律案」(3月6日国会提出)の成立を前提として2010年1月1日から実施される予定だったが、今回、同法律案が廃案となったことで、税制改正大綱にその内容が明記されていたにもかかわらず改正が実現しないという異常事態となった(図表2参照。以下同様)。
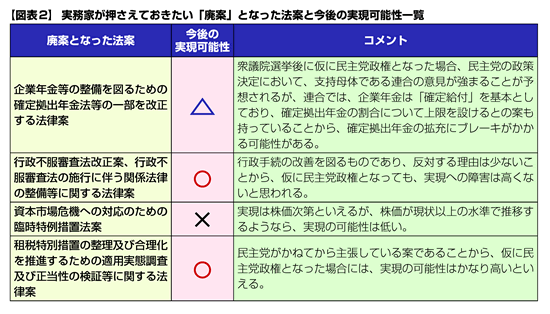
一方、確定拠出年金法の政令改正事項である②についても、確定拠出年金法の改正を待って実施される予定だったため実現が絶望視されていたが、手続上、法律改正と異なり国会を経る必要がないことから、政府は7月24日に閣議決定を行い、実現にこぎつけている(実施は2010年1月1日からとなる)。
行政不服審査法関係法律整備法の廃案で、国税通則法の改正も実現せず 確定拠出年金の改正同様、税制改正大綱(平成20年度税制改正)に盛り込まれていた国税に関する不服申立手続に関する国税通則法の改正も実現しないこととなった。
国税通則法の改正は、行政一般の不服申立手続を規定する行政不服審査法の全文改正とあわせ、「行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案」のなかで行われる予定だった。
具体的には、①現行の「異議申立て」に代わり「再調査の請求」を設ける、②行政不服審査法の審査請求期間が3か月に延長されることとあわせ、国税に関する処分についての不服申立期間についても、現行の2か月から3か月に延長したうえで、正当な理由がある場合の宥恕規定を設ける、③審査請求人または参加人は、審理手続が終結するまでの間に、担当審判官に対して、原処分庁が提出した処分の理由となる事実を証する書類その他の物件、または担当審判官が審理上必要とし、職権等で提出を求めた書類その他の物件の閲覧を求めることができるとし、この場合、担当審判官は、第三者の利益を害するおそれがあると認められることその他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができないことなどが規定される予定となっており、税理士等実務家の注目を集めていた。
しかし、行政不服審査法の改正案、行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案ともに廃案となってしまったため、これらの法案成立を前提としていた国税通則法の改正も実現しないこととなった。
2 衆議院議員提出法律案関係
国による株価買取りを実現する法案は、株価上昇も廃案の要因に 衆議院議員により提出された法案の多くが廃案となるなか成立にこぎつけたのが、景気対策関連の法案だ。
具体的には、日本政策投資銀行が企業の資金繰りを支援しやすくするため、同行の財務基盤を強化すべく、政府による同行への追加出資を平成24年3月末まで可能とすることなどを盛り込んだ「株式会社日本政策投資銀行法の一部を改正する法律案」、銀行の健全な運営を確保するため、銀行等保有株式取得機構による株式買取りを再開することなどを盛り込んだ「銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律の一部を改正する法律案」、中小企業への融資拡大に伴う商工中金の財務基盤悪化に歯止めをかけるため、政府による商工中金への追加出資を可能とする「中小企業者及び中堅事業者等に対する資金供給の円滑化を図るための株式会社商工組合中央金庫法等の一部を改正する法律案」が成立している。
上記の景気対策関連法案が成立する一方で、株価が大幅に下落した際に公的資金でETF(上場投資信託)等を買い取る「資本市場危機への対応のための臨時特例措置法案」は廃案となっている。
一時は究極の株価対策として注目を集めた同法案だが、日経平均が1万円前後で推移するなど、株価が最悪期を脱するなか、同法案を成立させるインセンティブが失われたことも、今回の廃案につながった一因ということができそうだ。
3 参議院議員提出法律案関係
“租税特別措置法透明化法案”、民主党政権誕生なら実現可能性も 成立した法案がわずか1つ(保健師助産師看護師及び看護師等の人材確保の促進に関する法律の一部を改正する法律案)となった参議院議員提出法律案のなかで押さえておきたいのが、民主党により提出された「租税特別措置の整理及び合理化を推進するための適用実態調査及び正当性の検証等に関する法律案」だ。
同法案は、租税特別措置の整理・合理化を推進するため、租税特別措置の適用数、その増減収額、適用実績に関する調査を行うことを国に義務付ける一方、納税者に対しても、適用実態調査等への協力を義務付けるもので、平成21年4月24日に参議院本会議で可決されたものの、衆議院で与党が過半数を占めるなか、廃案となっている。
ただ、同法案の内容は、以前から民主党が主張しているものであり、このほど民主党が明らかにしたマニフェストにも盛り込まれている。このため、今度の衆議院選挙後に民主党政権(あるいは民主党を中心とする政権)が誕生した場合には、実現の可能性が高い法案であるといえ、また、「租税特別措置に関する増減額明細書」の提出を求められる場合があるなど(下掲・同法案7条参照)、実務にも影響が及ぶ可能性が高いことから、実務家にあっては要チェックといえよう。
(適用実態調査の実施) 第七条 財務大臣は、租税特別措置ごとに、適用実態調査を行うものとする。
2 財務大臣は、国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第十六条第一項各号に掲げる方式による税額の確定の手続における申告、調査又は処分の機会を利用して租税特別措置の適用の実績に関する調査を行うことができる。この場合において、財務大臣は、納税申告書(同法第二条第六号に規定する納税申告書をいう。以下この項において同じ。)の提出を行う者に対して、納付すべき税額の算定において適用される租税特別措置に関する増減額明細書(当該適用される租税特別措置について、その内容及びその適用により増加する税額又は軽減若しくは免除される税額を一覧することができるように記載した書類をいう。第四項において同じ。)を作成し、これを納税申告書に添付するよう求めることができる。
押さえておきたい「廃案」法案と今後の実現可能性
7月21日の衆院解散に伴い、政府提出の17法案と与野党議員が提出した97法案の計114法案が成立しないまま廃案となった。
廃案となった法案のなかには、確定拠出年金法改正案や「行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案」など税制改正大綱にも改正の内容が明記されていたものや、国による株式買取りを実現するための法案など、当初は実現が見込まれていたものも含まれている。
そこで本特集では、本誌読者である実務家が押さえておくべき「廃案」となった法案と、それらの今後の実現可能性について整理してみた。
1 内閣提出法律案関係
確定拠出年金関連では、政令事項の拠出限度額引上げのみ実現 衆議院解散に伴い廃案となった政府提出の17法案と与野党議員が提出した97法案の計114法案のなかには、元々今国会での実現が難しいものも多く含まれる一方で、当然実現するものと思われていたものが少なからず含まれている。
その代表格が、確定拠出年金法改正案だ。平成21年度税制改正大綱には、確定拠出年金に関して、右頁図表1の改正項目が盛り込まれていた。
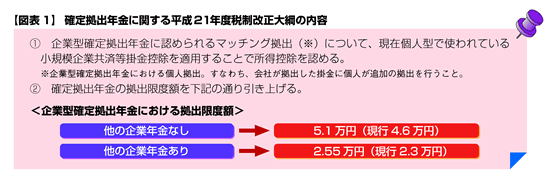
このうち①については、企業年金にマッチング拠出を認めることなどを盛り込んだ「企業年金等の整備を図るための確定拠出年金法等の一部を改正する法律案」(3月6日国会提出)の成立を前提として2010年1月1日から実施される予定だったが、今回、同法律案が廃案となったことで、税制改正大綱にその内容が明記されていたにもかかわらず改正が実現しないという異常事態となった(図表2参照。以下同様)。
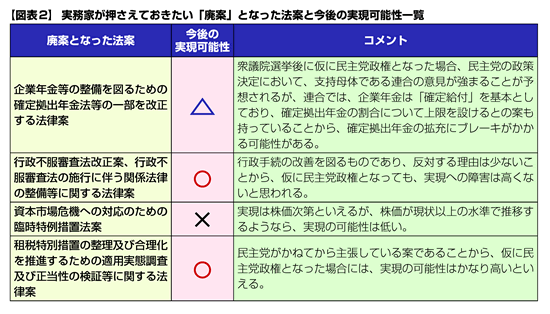
一方、確定拠出年金法の政令改正事項である②についても、確定拠出年金法の改正を待って実施される予定だったため実現が絶望視されていたが、手続上、法律改正と異なり国会を経る必要がないことから、政府は7月24日に閣議決定を行い、実現にこぎつけている(実施は2010年1月1日からとなる)。
行政不服審査法関係法律整備法の廃案で、国税通則法の改正も実現せず 確定拠出年金の改正同様、税制改正大綱(平成20年度税制改正)に盛り込まれていた国税に関する不服申立手続に関する国税通則法の改正も実現しないこととなった。
国税通則法の改正は、行政一般の不服申立手続を規定する行政不服審査法の全文改正とあわせ、「行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案」のなかで行われる予定だった。
具体的には、①現行の「異議申立て」に代わり「再調査の請求」を設ける、②行政不服審査法の審査請求期間が3か月に延長されることとあわせ、国税に関する処分についての不服申立期間についても、現行の2か月から3か月に延長したうえで、正当な理由がある場合の宥恕規定を設ける、③審査請求人または参加人は、審理手続が終結するまでの間に、担当審判官に対して、原処分庁が提出した処分の理由となる事実を証する書類その他の物件、または担当審判官が審理上必要とし、職権等で提出を求めた書類その他の物件の閲覧を求めることができるとし、この場合、担当審判官は、第三者の利益を害するおそれがあると認められることその他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができないことなどが規定される予定となっており、税理士等実務家の注目を集めていた。
しかし、行政不服審査法の改正案、行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案ともに廃案となってしまったため、これらの法案成立を前提としていた国税通則法の改正も実現しないこととなった。
2 衆議院議員提出法律案関係
国による株価買取りを実現する法案は、株価上昇も廃案の要因に 衆議院議員により提出された法案の多くが廃案となるなか成立にこぎつけたのが、景気対策関連の法案だ。
具体的には、日本政策投資銀行が企業の資金繰りを支援しやすくするため、同行の財務基盤を強化すべく、政府による同行への追加出資を平成24年3月末まで可能とすることなどを盛り込んだ「株式会社日本政策投資銀行法の一部を改正する法律案」、銀行の健全な運営を確保するため、銀行等保有株式取得機構による株式買取りを再開することなどを盛り込んだ「銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律の一部を改正する法律案」、中小企業への融資拡大に伴う商工中金の財務基盤悪化に歯止めをかけるため、政府による商工中金への追加出資を可能とする「中小企業者及び中堅事業者等に対する資金供給の円滑化を図るための株式会社商工組合中央金庫法等の一部を改正する法律案」が成立している。
上記の景気対策関連法案が成立する一方で、株価が大幅に下落した際に公的資金でETF(上場投資信託)等を買い取る「資本市場危機への対応のための臨時特例措置法案」は廃案となっている。
一時は究極の株価対策として注目を集めた同法案だが、日経平均が1万円前後で推移するなど、株価が最悪期を脱するなか、同法案を成立させるインセンティブが失われたことも、今回の廃案につながった一因ということができそうだ。
3 参議院議員提出法律案関係
“租税特別措置法透明化法案”、民主党政権誕生なら実現可能性も 成立した法案がわずか1つ(保健師助産師看護師及び看護師等の人材確保の促進に関する法律の一部を改正する法律案)となった参議院議員提出法律案のなかで押さえておきたいのが、民主党により提出された「租税特別措置の整理及び合理化を推進するための適用実態調査及び正当性の検証等に関する法律案」だ。
同法案は、租税特別措置の整理・合理化を推進するため、租税特別措置の適用数、その増減収額、適用実績に関する調査を行うことを国に義務付ける一方、納税者に対しても、適用実態調査等への協力を義務付けるもので、平成21年4月24日に参議院本会議で可決されたものの、衆議院で与党が過半数を占めるなか、廃案となっている。
ただ、同法案の内容は、以前から民主党が主張しているものであり、このほど民主党が明らかにしたマニフェストにも盛り込まれている。このため、今度の衆議院選挙後に民主党政権(あるいは民主党を中心とする政権)が誕生した場合には、実現の可能性が高い法案であるといえ、また、「租税特別措置に関する増減額明細書」の提出を求められる場合があるなど(下掲・同法案7条参照)、実務にも影響が及ぶ可能性が高いことから、実務家にあっては要チェックといえよう。
(適用実態調査の実施) 第七条 財務大臣は、租税特別措置ごとに、適用実態調査を行うものとする。
2 財務大臣は、国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第十六条第一項各号に掲げる方式による税額の確定の手続における申告、調査又は処分の機会を利用して租税特別措置の適用の実績に関する調査を行うことができる。この場合において、財務大臣は、納税申告書(同法第二条第六号に規定する納税申告書をいう。以下この項において同じ。)の提出を行う者に対して、納付すべき税額の算定において適用される租税特別措置に関する増減額明細書(当該適用される租税特別措置について、その内容及びその適用により増加する税額又は軽減若しくは免除される税額を一覧することができるように記載した書類をいう。第四項において同じ。)を作成し、これを納税申告書に添付するよう求めることができる。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -

Copyright (C) 2019
SHINNIPPON-HOKI PUBLISHING CO.,LTD.




















