資料2009年08月31日 【重要資料】 平成20年12月26日付課法2?14ほか1課共同「法人税基本通達等の一部改正について」(法令解釈通達)の趣旨説明(国税庁)(2009年8月31日号・№320)
重要資料
平成20年12月26日付課法2?14ほか1課共同「法人税基本通達等の一部改正について」(法令解釈通達)の趣旨説明(国税庁)
この趣旨説明は、平成20年12月26日現在の法令に基づいて作成している。
第一 法人税基本通達関係
1 外国法人の納税義務(課税標準)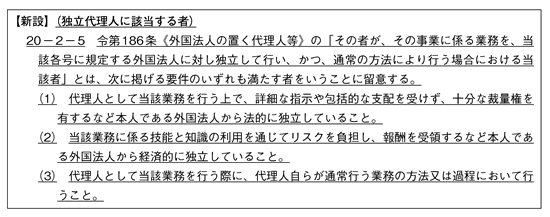
【解説】
1 国内で事業を行う外国法人については、その事業を行うために有する恒久的施設(PE)の態様に応じて法人税の課税範囲が定められており、国内に自己のために契約を締結する権限のある者等(以下「代理人等」という。)を置く外国法人は我が国に恒久的施設を有するものとされている(法141三)。
その一方で、我が国の締結している租税条約及び主として先進国間の二国間条約の基礎となるOECDモデル租税条約においては、上記のような権限を有する代理人であっても独立の地位を有する代理人(以下「独立代理人」という。)は恒久的施設とされる代理人の範囲から除かれていることを踏まえ、この取扱いと同様となるよう、平成20年度の税制改正により、租税条約上のいわゆる「独立代理人」に相当する規定を国内法に導入し、国内法に規定する代理人等の範囲から独立代理人を除外することとされた(法令186)。
2 租税条約上の独立代理人であるかの判断基準については、OECDモデル租税条約コメンタリーに考え方が示されている。同コメンタリーでは、独立代理人の要件として、代理人が本人(非居住者又は外国法人)の事業に係る業務を、本人に対して独立で行い、かつ、通常の方法により行っているというためには、代理人が、①法的にも経済的にも本人から独立していること(「法的独立性」及び「経済的独立性」)、かつ、②本人に代わって行動する際に、代理人の事業の通常の過程において行動する(「通常業務性」)必要があるとされている(OECDモデル租税条約第5条コメンタリー・パラ37)。
上記の改正の経緯等を踏まえれば、税務上の独立代理人とは、本人である外国法人のために、その外国法人の事業に係る業務を外国法人とは独立して行い、かつ、その業務を通常の方法により行う代理人をいい、その判断基準は、租税条約上の取扱いと同様のものとなろう。
このため、「独立して」行っているか否かについては、代理人が本人である外国法人の業務を行う際、本人からの詳細な指示や包括的な支配を受けず、十分な裁量権を有して自らの事業を行っているかどうか(法的独立性)、代理人が、当該業務に係る技能と知識の利用を通じてリスクを負担し、報酬を受領するなど企業家として行う事業活動に係るリスクを自ら負担しているかどうか(経済的独立性)、等の観点から判断されることになる。
また、「通常の方法」により行っているか否かについては、本人の事業に係る代理人の業務が、その代理人が通常行う業務の方法又は過程により行われているかどうか、その業務が、代理人が行う取引において慣習的に行われるかどうか(通常業務性)、等の観点から判断されることになる。
そこで、本通達では、税務上の独立代理人であるかどうかの判断基準として、上記の3つの要件を掲げ、これらの要件をいずれも満たす者がこれに該当することを留意的に明らかにしている。
第二 租税特別措置法関係通達(法人税編)関係
1 第42条の7《事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除》関係 平成20年度の税制改正により、中小企業者に該当する法人又は農業協同組合等で青色申告書を提出するものの平成20年4月1日から平成21年3月31日までの間に開始する各事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の事業年度を除く。)において、その事業年度の労務費の額のうちに教育訓練費の額(その教育訓練費に充てるため他の者から支払を受ける金額がある場合には、当該金額を控除した金額)の占める割合が0.15%以上である場合には、その教育訓練費の額に一定の税額控除割合を乗じて計算した金額を法人税額から控除することができる制度が本制度に追加された(措法42の7⑤)。
1 適用対象法人
本制度の適用対象法人は、中小企業者に該当する法人又は農業協同組合等で青色申告書を提出するものである。
(注) 中小企業者とは、資本金の額若しくは出資金の額が1億円以下の法人(その発行済株式又は出資の総数又は総額の2分の1以上を同一の大規模法人に所有されている法人及びその発行済株式又は出資の総数又は総額の3分の2以上を大規模法人に所有されている法人を除く。)又は資本若しくは出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人をいう(措法42の4⑫五、措令27の4⑩)。
2 適用対象となる教育訓練費の範囲
本制度の適用対象となる教育訓練費とは、法人がその使用人(その法人の役員と特殊の関係のある者及び使用人兼務役員を除く。)の職務に必要な技術又は知識を習得させ、又は向上させるために支出する費用で、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次のものをいう(措法42の7⑥一、措令27の7⑧~⑩、措規20の3⑥~⑨)。
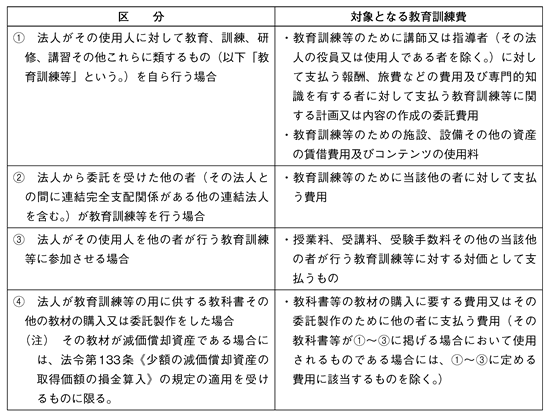
(注)その法人の役員と特殊の関係のある者とは、次に掲げる者をいう(措令27の7⑧)。
① 役員の親族
② 役員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
③ 上記①②に掲げる者以外の者で役員から生計の支援を受けているもの
④ 上記②③に掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族
3 税額控除限度額
税額控除限度額は、次の算式により計算した金額である。ただし、控除を受ける金額は適用年度の所得に対する法人税額の20%相当額を限度とする。
〔算式〕
教育訓練費割合が0.25%以上の場合
税額控除限度額 = 教育訓練費の額 × 12%
教育訓練費割合が0.15%以上0.25%未満の場合
税額控除限度額 = 教育訓練費の額 ×(8%+(教育訓練費割合(注1)-0.15%)×40)(注2)
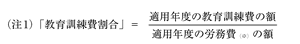
(注2) この割合に小数点以下3位未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
(※)「労務費」とは、所得税法第28条第1項に規定する給与等(使用人に対して支給するものに限る。)、法定福利費(法令の規定により事業主が負担することとされているものに限る。)及び教育訓練費の合計額をいう(措法42の7⑥二、措令27の7⑪、措規20の3⑩)。
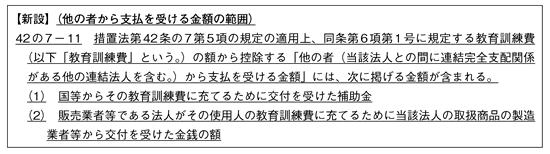
【解説】
1 本制度は、当該事業年度において教育訓練費の額がある場合に、その教育訓練費の額が当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される労務費の額に占める割合(「教育訓練費割合」という。)が0.15%以上であるときは、当該教育訓練費の額の総額に教育訓練費割合に応じた一定の割合を乗じて計算した金額を、それぞれ当該事業年度の法人税額(その20%が限度とされる。)から控除することができる制度である(措法42の7⑤)。
本制度の適用対象となる教育訓練費の額は、各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額に限られるのであるが、その教育訓練費に充てるため他の者から支払いを受ける金額がある場合には、当該金額を控除した金額とされている(措法42の7⑤)。
本通達においては、適用対象となる教育訓練費の額に含めないこととされる「他の者から支払を受ける金額」の範囲について、例示により明らかにしている。
すなわち、厚生労働省の「キャリア形成促進助成金」などで、教育訓練費に充てるために国等から交付を受けた補助金のほか、販売店がその使用人に対して販売促進等の目的で実施した教育訓練等に要した費用に充てるため、その取扱商品に係るメーカー等から交付を受けた金銭の額などがこれに含まれる。
2 ところで、関連会社等と共同で教育訓練等を実施した場合には、その教育訓練等に要した費用の総額を合理的な基準によって按分する方法で計算した自社負担分の金額だけが本制度の適用対象である教育訓練費の額となる(措通42の7-12の(注)参照)。
したがって、関連会社等と共同で教育訓練等を実施した場合において、その教育訓練等に要した費用の総額をいったん立替払いし、その費用の総額を合理的な基準によって按分する方法で計算した関連会社等の負担分の金額を受け取ったときは、この受け取った金額は立替金の清算金に過ぎず、自社の使用人の教育訓練費に充てるために支払を受けたものではないことから、「他の者から支払を受ける金額」には該当しない。
ただし、関連会社等と共同で教育訓練等を実施した場合において、合理的な基準によって按分する方法で計算した関連会社等の負担分の金額を超える金額の支払を受けたときは、その超える部分の金額は関連会社等から贈与されたものであり、「他の者から支払を受けた金額」に該当することになる。
3 連結納税制度に係る租税特別措置法第68条の12《事業基盤強化設備を取得した場合等の法人税額の特別控除》についても、同様の通達(連措通68の12-11)を定めている。
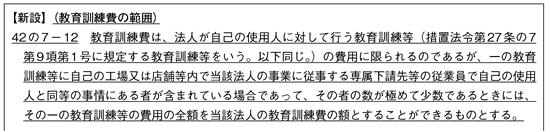
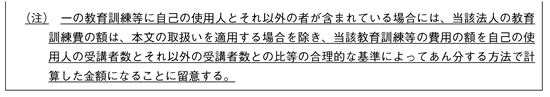 【解説】
【解説】
1 本制度の適用対象となる教育訓練費とは、法人がその使用人の職務に必要な技術又は知識を習得させ、又は向上させるために支出する費用とされており(措法42の7⑥一)、原則として、自社と雇用関係のある使用人(自社の役員と特殊の関係のある者及び自社の使用人としての職務を有する役員を除く。)に対して実施する教育訓練等に要した費用に限られる。
したがって、一の教育訓練等の対象者の中に自社の使用人以外の者が一人でも含まれている場合には、本制度の適用対象となる教育訓練費は、その教育訓練等に要した費用の総額ではなく、その総額のうち自社の使用人以外の者の部分を除いた金額を厳密に計算すべきという考え方もある。
2 この点、一の教育訓練等の対象者の中に自社の工場又は店舗等内で自社の事業に従事する専属下請先等の従業員が含まれる場合であっても、その者が自社の使用人と同等の事情にある者であるときは、その教育訓練等を実施した効果は自社の事業に対して反映されるため、教育訓練の奨励を目的とした本制度の趣旨に合致するものと考えられる。
そこで、一の教育訓練に法人の使用人以外の者が含まれている場合であっても、その者が当該法人の使用人と同等の事情にあり、かつ、その者の数が極めて少数であるときは、その者の部分を含めた教育訓練等に要した費用の全額を本制度の適用対象となる教育訓練費に含めることができるものとして取り扱うこととしたものである。このことを本通達の本文において明らかにしている。
なお、この「極めて少数」であるかどうかの判断については、教育訓練等の対象者全体に占める専属下請先等の従業員の割合によって判断するのではないかと考える向きもあろうが、その教育訓練等の規模にかかわらず一律に「受講者全体の何%以下」であれば「極めて少数」として取り扱うこととすると、その教育訓練等の規模が小さいことをもって、一人の対象者も含めることができないこととなり、適当ではないと考えられる。したがって、その教育訓練等の規模によっては、その専属下請先等の従業員が数名程度であっても「極めて少数」として取り扱って差し支えないものと考えられる。
3 また、本通達の(注)において、関連会社等と共同で教育訓練等を実施した場合のように、一の教育訓練等に自社の使用人とそれ以外の者が含まれている場合の原則的な取扱いを留意的に明らかにしている。
すなわち、上記2の取扱いを適用する場合を除き、当該法人の教育訓練費は、その教育訓練等に要した費用の総額を自社が負担すべき金額と関連会社等が負担すべき金額とに合理的な基準によってあん分する方法で計算した金額となる。この場合の「合理的な基準」とは、例えば、それぞれの受講者数の比や、これに間接経費等の額を勘案した比などが考えられる。
4 次に、自社の使用人に対して実施する教育訓練等に要した費用が本制度の対象となることは上記1のとおりであり、この場合の「使用人」とは、通常、正社員、契約社員、パート・アルバイト(以下「正社員等」という。)といった自己と雇用関係のある者をいうものと考えられる。
したがって、自己と雇用関係のない派遣社員や請負労働者については、一義的には派遣先や注文主の使用人に該当しないことになるのであるから、派遣社員や請負労働者のように雇用関係のない者については、すべからく本制度の適用対象となる「使用人」に当たらないものとして厳密に取り扱うべきという考えもある。
この点、これらの者のうち派遣社員(派遣労働者)の派遣先は、いわゆる労働者派遣法の適用を受け、労働者の危険・健康障害防止措置、労働時間の遵守等の責務を負い、派遣社員との間において指揮命令関係を有するものであることから、派遣社員は正社員等たる使用人と同等の立場にあるという側面も有している。さらに、個々の派遣社員の職務や教育訓練等の実態によっては、当該個々の派遣社員を本制度の適用における「使用人」に該当するものとして取り扱い得る場合も考えられる。
そこで、この派遣先の企業と指揮命令関係にある派遣社員が、①当該企業に使用される正社員等と同一の職務に従事しており、②当該同一の職務に係る一の教育訓練等(当該正社員等を主体としたものに限る。)に参加している場合には、本制度の適用上、その企業の職務に必要な技術又は知識を習得させ、又は向上させるための支出を増加させるという趣旨に鑑み、当該派遣社員に係る教育訓練費の額を派遣先の企業の教育訓練費の額に含めても差し支えないものと考える。
他方、請負労働者については、注文主との間で派遣社員のような指揮命令関係がないことから、上記のような取扱いはなく、本通達の本文の取扱いに従い、その者の数が極めて少数である場合に限り、本制度の適用対象となる。
5 連結納税制度に係る租税特別措置法第68条の12《事業基盤強化設備を取得した場合等の法人税額の特別控除》についても、同様の通達(連措通68の12-12)を定めている。
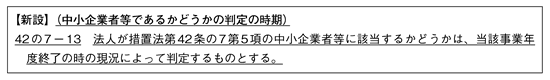
【解説】
1 中小企業者等の教育訓練費に係る税額控除制度(措法42の7⑤)は、資本金の額若しくは出資金の額が1億円以下の法人(大法人の子会社等を除く。)、資本若しくは出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人又は農業協同組合等(措法42の4⑫五、措令27の4⑩)について適用があるが、その適用対象法人に該当するかどうかをいつの時点で判定するかが問題となる。
この点、本制度は一事業年度を通じた教育訓練費の額を対象として特別税額控除を行うものであるから、事業年度の中途で適用対象法人に該当するかどうかを判定するという考え方にはなじまない。
そこで、本通達において、法人が本制度の適用対象法人に該当する法人であるかどうかは、各事業年度終了の時の現況によって判定するものとしている。
2 連結納税制度に係る租税特別措置法第68条の12《事業基盤強化設備を取得した場合等の法人税額の特別控除》についても、同様の通達(連措通68の12-13)を定めている。
2 第46条の3《支援事業所取引金額が増加した場合の3年以内取得資産の割増償却》関係 平成20年度の税制改正により、青色申告書を提出する法人が、平成20年4月1日から平成25年3月31日までの間に開始する各事業年度において、障害者就労支援事業所に対して、資産を譲り受け、又は役務の提供を受けた対価として支払った金額(以下「支援事業所取引金額」という。)がある場合において、その事業年度における支援事業所取引金額の合計額が前事業年度における支援事業所取引金額の合計額を超えるときは、その超える金額(支援事業所取引増加額)を限度として、その事業年度終了の日において有する減価償却資産で事業の用に供されているもののうちその事業年度又はその事業年度開始の日前2年以内に開始した各事業年度において取得等をしたものについて、普通償却限度額の30%相当額の割増償却を行うことができるという制度が創設された(措法46の3)。
(注)「障害者就労支援事業所」とは、障害者自立支援法第5条第14項に規定する就労移行支援を行う事業所、同条第15項に規定する就労継続支援を行う事業所その他次に掲げる事業所又は施設をいう(措法46の3①、措令29の2の2①)。
① 障害者自立支援法第5条第1項に規定する障害福祉サービス事業(同条第6項に規定する生活介護、同条第14項に規定する就労移行支援又は同条第15項に規定する就労継続支援を行う事業に限る。)を行う事業所
② 障害者自立支援法第5条第1項に規定する施設障害福祉サービスとして同条第6項に規定する生活介護又は同条第14項に規定する就労移行支援を行う障害者支援施設等
③ 障害者自立支援法第5条第21項に規定する地域活動支援センター
④ 障害者の雇用の促進等に関する法律第44条第1項の認定に係る同項に規定する子会社の事業所
⑤ 次に掲げる要件のすべてを満たす事業所
ⅰ その資産を譲り受け、又は役務の提供を受けた日を含む年の前年12月31日(以下「取引日の前年末」という。)におけるその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長(以下「公共職業安定所長」という。)の証明を受けた障害者数が5人以上であること
ⅱ 取引日の前年末における公共職業安定所長の証明を受けた障害者割合が100分の20以上であること
ⅲ 取引日の前年末における公共職業安定所長の証明を受けた重度障害者等割合が100分の30以上であること
平成20年4月1日から障害者自立支援法附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日の前日までの間においては、次の施設も障害者就労支援事業所となる(措令29の2の2②、措規20の18の2①)。
⑥ 障害者自立支援法附則第41条第1項、第48条又は第58条第1項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた同法附則第35条の規定による改正前の身体障害者福祉法第31条に規定する身体障害者授産施設
⑦ 障害者自立支援法附則第46条の規定による改正前の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第50条の2第3項に規定する精神障害者授産施設
⑧ 障害者自立支援法附則第46条の規定による改正前の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第50条の2第5項に規定する精神障害者福祉工場
⑨ 障害者自立支援法附則第52条の規定による改正前の知的障害者福祉法第21条の7に規定する知的障害者授産施設
⑩ 障害者自立支援法第5条第1項に規定する障害福祉サービスのうち障害者自立支援法施行規則附則第1条の2により読み替えて適用する同令第1条の2に規定する就労継続支援を行う障害者支援施設等
1 適用対象資産
本制度の適用対象資産は、当該事業年度終了の日においてその法人の有する減価償却資産で事業の用に供されているもののうち、当該事業年度又は当該事業年度開始の日前2年以内に開始した各事業年度において取得し、又は製作し、若しくは建設したもの(所有権移転外リース取引により取得したものを除く。以下「3年以内取得資産」という。)である。
2 償却限度額
〔算式〕
割増償却限度額 = 3年以内取得資産の普通償却限度額 × 30%
ただし、上記算式により計算した割増償却限度額の合計額が当該事業年度の支援事業所取引増加額(※)を超えるときは、その支援事業所取引増加額が限度となる(措法46の3①)。
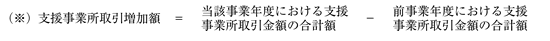
3 適用要件
本制度の適用を受けるためには、法人が資産を譲り受け、又は役務の提供を受けた対価として支払った金額につき支援事業所取引金額に該当するものとして障害者就労支援事務所から交付を受けた一定の書類を保存していることが必要とされている(措令29の2の2⑨、措規20の18の2⑧)。
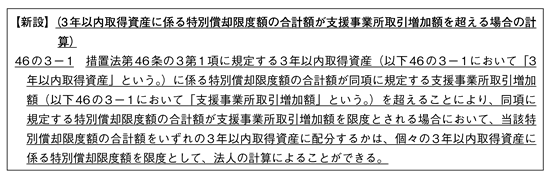 【解説】
【解説】
1 平成20年度の税制改正において、青色申告法人が、障害者自立支援法に規定する就労移行支援等を行う事業所に対して、資産を譲り受け、又は役務の提供を受けた対価として支払った金額(以下「支援事業所取引金額」という。)がある場合において、その事業年度における支援事業所取引金額の合計額が前事業年度における支援事業所取引金額の合計額を超えるときは、その事業年度終了の日において有する減価償却資産で事業の用に供されているもののうちその事業年度又はその事業年度開始の日前2年以内に開始した各事業年度において取得等したもの(以下「3年以内取得資産」という。)について、普通償却限度額の30%に相当する金額(以下「特別償却限度額」という。)の割増償却を行うことができる制度が創設された(措法46の3)。
2 この場合において、3年以内取得資産に係る特別償却限度額の合計額が支援事業所取引増加額(その事業年度における支援事業所取引金額の合計額が前事業年度における支援事業所取引金額の合計額を超える場合のその超える金額をいう。)を超えるときには、当該特別償却限度額の合計額は、支援事業所取引増加額を限度とされるのであるが、3年以内取得資産が複数ある場合に、特別償却限度額の合計額をいずれの3年以内取得資産に配分することとなるのか疑義が生じる。
この点、計算の簡便性の観点からは、特別償却限度額の合計額を3年以内取得資産の取得価額等に応じてプロラタ計算により配分する方法が、一般的な計算方法であるとも考えられる。
しかしながら、本制度の対象となる3年以内取得資産は、「その事業年度終了の日において有する減価償却資産で事業の用に供されているもののうちその事業年度又はその事業年度開始の日前2年以内に開始した各事業年度において取得等したもの」とされているのみで、資産の種類や構造・用途等について何ら限定されているものではない。また、本制度が、授産施設等の支援事業所に対する一般企業からの発注の増加促進を税制の側面からも支援しようという趣旨から創設されたものであることからすれば、支援事業所取引増加額を限度とされた特別償却限度額の合計額を、個々の3年以内取得資産に係る特別償却限度額の範囲内で法人の計算により任意に配分することを認めることが本制度の趣旨に即した取扱いになるものと考えられる。
そこで、3年以内取得資産に係る特別償却限度額の合計額が支援事業所取引増加額を限度とされる場合において、当該特別償却限度額の合計額をいずれの3年以内取得資産に配分するかは、個々の3年以内取得資産に係る特別償却限度額を限度として、法人の計算によることができる旨を本通達において明らかにしている。
3 連結納税制度に係る租税特別措置法第68条の32《支援事業所取引金額が増加した場合の3年以内取得資産の割増償却》についても、同様の通達(連措通68の32-1)を定めている。
3 第52条の3《準備金方式による特別償却》関係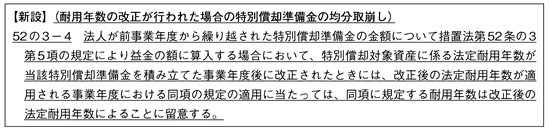 【解説】
【解説】
1 法人が積み立てた特別償却準備金の額は、特別償却対象資産ごとにその積立てをした事業年度の翌事業年度から、特別償却対象資産の法定耐用年数に応じて、法定耐用年数が10年以上のものは7年間、5年以上10年未満のものは5年間、それ以外のものは法定耐用年数に相当する期間に均分して益金の額に算入することとされている(措法52の3⑤)。
2 平成20年度の税制改正により、耐用年数省令が改正され、資産区分が多い機械及び装置を中心に、使用実態を踏まえた年数を基礎としつつ、資産区分が整理されるとともに、法定耐用年数の見直しが行われた。このように、特別償却準備金の積立てをした事業年度後において特別償却対象資産に係る法定耐用年数が改正された場合に、特別償却準備金の均分取崩しは、改正前後のいずれの法定耐用年数によるべきか疑義が生じる。
この点、特別償却準備金の取崩しは、特別償却の適用を受けた場合のその後の償却計算と均衡を図るものであるところ、法定耐用年数が短くなった場合には償却費を多く計上できることから、それに応じて特別償却準備金の取崩期間も短くするのが合理的であると考えられる。また、このことは法定耐用年数が長くなった場合も同様である。
本通達では、特別償却準備金の積立てをした事業年度後において特別償却対象資産に係る法定耐用年数が改正された場合には、改正後の法定耐用年数が適用される事業年度における特別償却準備金の均分取崩しの年数は、改正後の法定耐用年数により判断することを留意的に明らかにしている。
具体例で示せば、次のとおりである。
○ 特別償却対象資産の法定耐用年数が短くなった場合
特別償却限度額 700
法定耐用年数 12年から9年に改正(改正後の法定耐用年数はX+3期から適用)
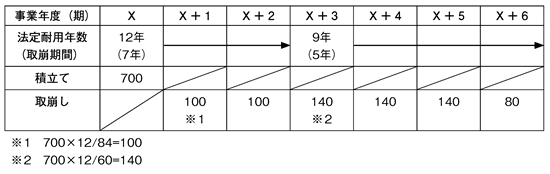
4 第67条の3《農業生産法人の肉用牛の売却に係る所得の課税の特例》関係 〔制度の概要〕
この制度は、農業生産法人が、昭和56年4月1日から平成24年3月31日までの期間内の日を含む各事業年度において、その飼育した肉用牛を家畜市場、中央卸売市場等において売却した場合等において、その売却した肉用牛のうちに免税対象飼育牛があるときは、その売却による利益の額(年2,000頭を超える場合には超える部分の利益の額を除く。)に相当する金額を、その売却した日を含む事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入することができるというものである(措法67の3)。
1 適用対象法人
本制度の適用対象法人は、農地法第2条第7項に規定する農業生産法人とされている(措法67の3①)。
2 適用対象となる免税対象飼育牛
本制度の適用対象となる免税対象飼育牛は、肉用牛(農業災害補償法第111条第1項に規定する肉用牛等及び乳牛の雌等(乳牛の雌のうち子牛の生産の用に供されたもの及び牛の胎児を除く。))のうち、家畜改良増殖法第32条の2第1項の規定による農林水産大臣の承認を受けた同項に規定する登録規程に基づく一定の登録がされているもの又はその売却価額が100万円未満(ホルスタイン種、ジャージー種又は乳用種である乳牛に該当する場合には、50万円未満)であるものとされている(措法67の3①②、措令39の26①④、措規22の16①)。
3 適用対象となる売却
(1)家畜取引法第2条第3項に規定する家畜市場、中央卸売市場又は家畜取引法第27条第1項の規定による届出に係る市場等において行う売却の方法により、農業生産法人が飼育した肉用牛を売却した場合。
(2)肉用子牛生産安定等特別措置法第6条第2項に規定する指定協会から同法第7条第2項に規定する生産者補給金交付業務に関する事務の委託を受けている農業協同組合又は農業協同組合連合会で農林水産大臣が指定したものに委託して行う売却の方法により、農業生産法人が飼育した生産後1年未満の肉用牛を売却した場合。
(措法67の3①、措令39の26②③)
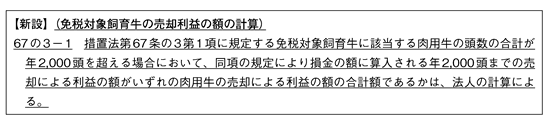
【解説】
1 本制度は、農業生産法人がその飼育した肉用牛を家畜市場、中央卸売市場等において売却した場合等において、その売却した肉用牛のうちに免税対象飼育牛があるときは、その売却による利益の額に相当する金額を、その売却をした日を含む事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入することができるというものである(措法67の3①)。
2 平成20年度の税制改正により、免税対象飼育牛の売却頭数の合計が年2,000頭を超える場合には、その超える部分の売却による利益の額については、免税対象から除外された。この改正により、免税対象飼育牛の売却頭数の合計が年2,000頭以内である場合には、その売却したすべての免税対象飼育牛の売却による利益の額について本制度を適用することができるが、年2,000頭を超える場合に損金の額に算入される年2,000頭までの売却による利益の額がいずれの免税対象飼育牛の売却によるものとすべきなのかといった疑問が生じる。
この点、法令上は何ら限定されておらず、また、本制度が年2,000頭までの肉用牛の売却による所得を全免するものであり、個々の売却による利益の大小に着目した制度でないことからすれば、免税対象飼育牛の売却頭数の合計が年2,000頭を超える場合には、損金の額に算入される年2,000頭までの売却による利益の額がいずれの免税対象飼育牛の売却によるものかは、法人の計算によることとして差し支えないものと考えられる。本通達ではこのことを明らかにしている。
3 なお、免税対象飼育牛の売却による利益の額は、一頭ごとに計算するのではなく、選択した2,000頭すべてに係る収益の額からその収益に係る原価の額とその売却に係る経費の額との合計額を控除した金額となる(措令39の26⑤)。したがって、2,000頭のうちに、一頭ごとに計算すると損失が生じる免税対象飼育牛があったとしても、これを除外して免税対象飼育牛の売却による利益の額を計算することはできない。また、本制度の適用を受けるためには、2,000頭すべてについての証明書類が確定申告書等に添付されている必要がある(措法67の3③)のであるから、その点、留意する必要がある。
4 連結納税制度に係る租税特別措置法第68条の101《農業生産法人の肉用牛の売却に係る連結所得の課税の特例》についても、同様の通達(連措通68の101-1)を新たに定めている。
平成20年12月26日付課法2?14ほか1課共同「法人税基本通達等の一部改正について」(法令解釈通達)の趣旨説明(国税庁)
この趣旨説明は、平成20年12月26日現在の法令に基づいて作成している。
第一 法人税基本通達関係
1 外国法人の納税義務(課税標準)
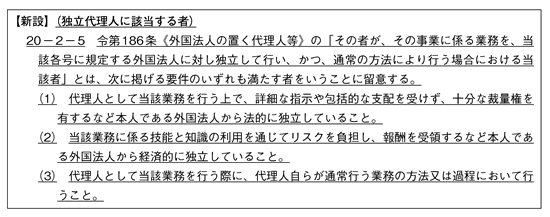
【解説】
1 国内で事業を行う外国法人については、その事業を行うために有する恒久的施設(PE)の態様に応じて法人税の課税範囲が定められており、国内に自己のために契約を締結する権限のある者等(以下「代理人等」という。)を置く外国法人は我が国に恒久的施設を有するものとされている(法141三)。
その一方で、我が国の締結している租税条約及び主として先進国間の二国間条約の基礎となるOECDモデル租税条約においては、上記のような権限を有する代理人であっても独立の地位を有する代理人(以下「独立代理人」という。)は恒久的施設とされる代理人の範囲から除かれていることを踏まえ、この取扱いと同様となるよう、平成20年度の税制改正により、租税条約上のいわゆる「独立代理人」に相当する規定を国内法に導入し、国内法に規定する代理人等の範囲から独立代理人を除外することとされた(法令186)。
2 租税条約上の独立代理人であるかの判断基準については、OECDモデル租税条約コメンタリーに考え方が示されている。同コメンタリーでは、独立代理人の要件として、代理人が本人(非居住者又は外国法人)の事業に係る業務を、本人に対して独立で行い、かつ、通常の方法により行っているというためには、代理人が、①法的にも経済的にも本人から独立していること(「法的独立性」及び「経済的独立性」)、かつ、②本人に代わって行動する際に、代理人の事業の通常の過程において行動する(「通常業務性」)必要があるとされている(OECDモデル租税条約第5条コメンタリー・パラ37)。
上記の改正の経緯等を踏まえれば、税務上の独立代理人とは、本人である外国法人のために、その外国法人の事業に係る業務を外国法人とは独立して行い、かつ、その業務を通常の方法により行う代理人をいい、その判断基準は、租税条約上の取扱いと同様のものとなろう。
このため、「独立して」行っているか否かについては、代理人が本人である外国法人の業務を行う際、本人からの詳細な指示や包括的な支配を受けず、十分な裁量権を有して自らの事業を行っているかどうか(法的独立性)、代理人が、当該業務に係る技能と知識の利用を通じてリスクを負担し、報酬を受領するなど企業家として行う事業活動に係るリスクを自ら負担しているかどうか(経済的独立性)、等の観点から判断されることになる。
また、「通常の方法」により行っているか否かについては、本人の事業に係る代理人の業務が、その代理人が通常行う業務の方法又は過程により行われているかどうか、その業務が、代理人が行う取引において慣習的に行われるかどうか(通常業務性)、等の観点から判断されることになる。
そこで、本通達では、税務上の独立代理人であるかどうかの判断基準として、上記の3つの要件を掲げ、これらの要件をいずれも満たす者がこれに該当することを留意的に明らかにしている。
第二 租税特別措置法関係通達(法人税編)関係
1 第42条の7《事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除》関係 平成20年度の税制改正により、中小企業者に該当する法人又は農業協同組合等で青色申告書を提出するものの平成20年4月1日から平成21年3月31日までの間に開始する各事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の事業年度を除く。)において、その事業年度の労務費の額のうちに教育訓練費の額(その教育訓練費に充てるため他の者から支払を受ける金額がある場合には、当該金額を控除した金額)の占める割合が0.15%以上である場合には、その教育訓練費の額に一定の税額控除割合を乗じて計算した金額を法人税額から控除することができる制度が本制度に追加された(措法42の7⑤)。
1 適用対象法人
本制度の適用対象法人は、中小企業者に該当する法人又は農業協同組合等で青色申告書を提出するものである。
(注) 中小企業者とは、資本金の額若しくは出資金の額が1億円以下の法人(その発行済株式又は出資の総数又は総額の2分の1以上を同一の大規模法人に所有されている法人及びその発行済株式又は出資の総数又は総額の3分の2以上を大規模法人に所有されている法人を除く。)又は資本若しくは出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人をいう(措法42の4⑫五、措令27の4⑩)。
2 適用対象となる教育訓練費の範囲
本制度の適用対象となる教育訓練費とは、法人がその使用人(その法人の役員と特殊の関係のある者及び使用人兼務役員を除く。)の職務に必要な技術又は知識を習得させ、又は向上させるために支出する費用で、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次のものをいう(措法42の7⑥一、措令27の7⑧~⑩、措規20の3⑥~⑨)。
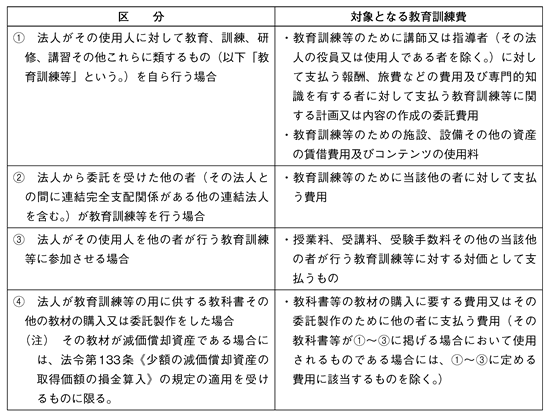
(注)その法人の役員と特殊の関係のある者とは、次に掲げる者をいう(措令27の7⑧)。
① 役員の親族
② 役員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
③ 上記①②に掲げる者以外の者で役員から生計の支援を受けているもの
④ 上記②③に掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族
3 税額控除限度額
税額控除限度額は、次の算式により計算した金額である。ただし、控除を受ける金額は適用年度の所得に対する法人税額の20%相当額を限度とする。
〔算式〕
教育訓練費割合が0.25%以上の場合
税額控除限度額 = 教育訓練費の額 × 12%
教育訓練費割合が0.15%以上0.25%未満の場合
税額控除限度額 = 教育訓練費の額 ×(8%+(教育訓練費割合(注1)-0.15%)×40)(注2)
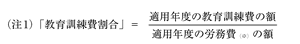
(注2) この割合に小数点以下3位未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
(※)「労務費」とは、所得税法第28条第1項に規定する給与等(使用人に対して支給するものに限る。)、法定福利費(法令の規定により事業主が負担することとされているものに限る。)及び教育訓練費の合計額をいう(措法42の7⑥二、措令27の7⑪、措規20の3⑩)。
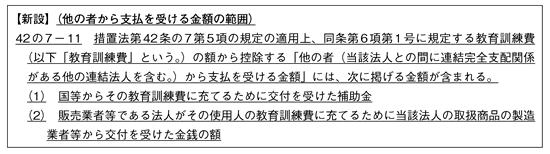
【解説】
1 本制度は、当該事業年度において教育訓練費の額がある場合に、その教育訓練費の額が当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される労務費の額に占める割合(「教育訓練費割合」という。)が0.15%以上であるときは、当該教育訓練費の額の総額に教育訓練費割合に応じた一定の割合を乗じて計算した金額を、それぞれ当該事業年度の法人税額(その20%が限度とされる。)から控除することができる制度である(措法42の7⑤)。
本制度の適用対象となる教育訓練費の額は、各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額に限られるのであるが、その教育訓練費に充てるため他の者から支払いを受ける金額がある場合には、当該金額を控除した金額とされている(措法42の7⑤)。
本通達においては、適用対象となる教育訓練費の額に含めないこととされる「他の者から支払を受ける金額」の範囲について、例示により明らかにしている。
すなわち、厚生労働省の「キャリア形成促進助成金」などで、教育訓練費に充てるために国等から交付を受けた補助金のほか、販売店がその使用人に対して販売促進等の目的で実施した教育訓練等に要した費用に充てるため、その取扱商品に係るメーカー等から交付を受けた金銭の額などがこれに含まれる。
2 ところで、関連会社等と共同で教育訓練等を実施した場合には、その教育訓練等に要した費用の総額を合理的な基準によって按分する方法で計算した自社負担分の金額だけが本制度の適用対象である教育訓練費の額となる(措通42の7-12の(注)参照)。
したがって、関連会社等と共同で教育訓練等を実施した場合において、その教育訓練等に要した費用の総額をいったん立替払いし、その費用の総額を合理的な基準によって按分する方法で計算した関連会社等の負担分の金額を受け取ったときは、この受け取った金額は立替金の清算金に過ぎず、自社の使用人の教育訓練費に充てるために支払を受けたものではないことから、「他の者から支払を受ける金額」には該当しない。
ただし、関連会社等と共同で教育訓練等を実施した場合において、合理的な基準によって按分する方法で計算した関連会社等の負担分の金額を超える金額の支払を受けたときは、その超える部分の金額は関連会社等から贈与されたものであり、「他の者から支払を受けた金額」に該当することになる。
3 連結納税制度に係る租税特別措置法第68条の12《事業基盤強化設備を取得した場合等の法人税額の特別控除》についても、同様の通達(連措通68の12-11)を定めている。
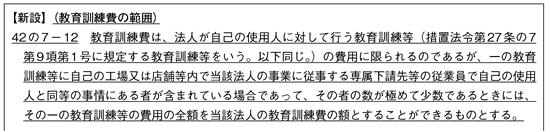
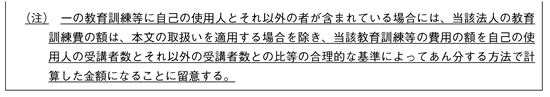 【解説】
【解説】1 本制度の適用対象となる教育訓練費とは、法人がその使用人の職務に必要な技術又は知識を習得させ、又は向上させるために支出する費用とされており(措法42の7⑥一)、原則として、自社と雇用関係のある使用人(自社の役員と特殊の関係のある者及び自社の使用人としての職務を有する役員を除く。)に対して実施する教育訓練等に要した費用に限られる。
したがって、一の教育訓練等の対象者の中に自社の使用人以外の者が一人でも含まれている場合には、本制度の適用対象となる教育訓練費は、その教育訓練等に要した費用の総額ではなく、その総額のうち自社の使用人以外の者の部分を除いた金額を厳密に計算すべきという考え方もある。
2 この点、一の教育訓練等の対象者の中に自社の工場又は店舗等内で自社の事業に従事する専属下請先等の従業員が含まれる場合であっても、その者が自社の使用人と同等の事情にある者であるときは、その教育訓練等を実施した効果は自社の事業に対して反映されるため、教育訓練の奨励を目的とした本制度の趣旨に合致するものと考えられる。
そこで、一の教育訓練に法人の使用人以外の者が含まれている場合であっても、その者が当該法人の使用人と同等の事情にあり、かつ、その者の数が極めて少数であるときは、その者の部分を含めた教育訓練等に要した費用の全額を本制度の適用対象となる教育訓練費に含めることができるものとして取り扱うこととしたものである。このことを本通達の本文において明らかにしている。
なお、この「極めて少数」であるかどうかの判断については、教育訓練等の対象者全体に占める専属下請先等の従業員の割合によって判断するのではないかと考える向きもあろうが、その教育訓練等の規模にかかわらず一律に「受講者全体の何%以下」であれば「極めて少数」として取り扱うこととすると、その教育訓練等の規模が小さいことをもって、一人の対象者も含めることができないこととなり、適当ではないと考えられる。したがって、その教育訓練等の規模によっては、その専属下請先等の従業員が数名程度であっても「極めて少数」として取り扱って差し支えないものと考えられる。
3 また、本通達の(注)において、関連会社等と共同で教育訓練等を実施した場合のように、一の教育訓練等に自社の使用人とそれ以外の者が含まれている場合の原則的な取扱いを留意的に明らかにしている。
すなわち、上記2の取扱いを適用する場合を除き、当該法人の教育訓練費は、その教育訓練等に要した費用の総額を自社が負担すべき金額と関連会社等が負担すべき金額とに合理的な基準によってあん分する方法で計算した金額となる。この場合の「合理的な基準」とは、例えば、それぞれの受講者数の比や、これに間接経費等の額を勘案した比などが考えられる。
4 次に、自社の使用人に対して実施する教育訓練等に要した費用が本制度の対象となることは上記1のとおりであり、この場合の「使用人」とは、通常、正社員、契約社員、パート・アルバイト(以下「正社員等」という。)といった自己と雇用関係のある者をいうものと考えられる。
したがって、自己と雇用関係のない派遣社員や請負労働者については、一義的には派遣先や注文主の使用人に該当しないことになるのであるから、派遣社員や請負労働者のように雇用関係のない者については、すべからく本制度の適用対象となる「使用人」に当たらないものとして厳密に取り扱うべきという考えもある。
この点、これらの者のうち派遣社員(派遣労働者)の派遣先は、いわゆる労働者派遣法の適用を受け、労働者の危険・健康障害防止措置、労働時間の遵守等の責務を負い、派遣社員との間において指揮命令関係を有するものであることから、派遣社員は正社員等たる使用人と同等の立場にあるという側面も有している。さらに、個々の派遣社員の職務や教育訓練等の実態によっては、当該個々の派遣社員を本制度の適用における「使用人」に該当するものとして取り扱い得る場合も考えられる。
そこで、この派遣先の企業と指揮命令関係にある派遣社員が、①当該企業に使用される正社員等と同一の職務に従事しており、②当該同一の職務に係る一の教育訓練等(当該正社員等を主体としたものに限る。)に参加している場合には、本制度の適用上、その企業の職務に必要な技術又は知識を習得させ、又は向上させるための支出を増加させるという趣旨に鑑み、当該派遣社員に係る教育訓練費の額を派遣先の企業の教育訓練費の額に含めても差し支えないものと考える。
他方、請負労働者については、注文主との間で派遣社員のような指揮命令関係がないことから、上記のような取扱いはなく、本通達の本文の取扱いに従い、その者の数が極めて少数である場合に限り、本制度の適用対象となる。
5 連結納税制度に係る租税特別措置法第68条の12《事業基盤強化設備を取得した場合等の法人税額の特別控除》についても、同様の通達(連措通68の12-12)を定めている。
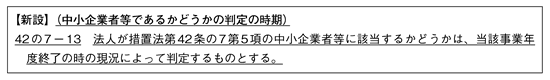
【解説】
1 中小企業者等の教育訓練費に係る税額控除制度(措法42の7⑤)は、資本金の額若しくは出資金の額が1億円以下の法人(大法人の子会社等を除く。)、資本若しくは出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人又は農業協同組合等(措法42の4⑫五、措令27の4⑩)について適用があるが、その適用対象法人に該当するかどうかをいつの時点で判定するかが問題となる。
この点、本制度は一事業年度を通じた教育訓練費の額を対象として特別税額控除を行うものであるから、事業年度の中途で適用対象法人に該当するかどうかを判定するという考え方にはなじまない。
そこで、本通達において、法人が本制度の適用対象法人に該当する法人であるかどうかは、各事業年度終了の時の現況によって判定するものとしている。
2 連結納税制度に係る租税特別措置法第68条の12《事業基盤強化設備を取得した場合等の法人税額の特別控除》についても、同様の通達(連措通68の12-13)を定めている。
2 第46条の3《支援事業所取引金額が増加した場合の3年以内取得資産の割増償却》関係 平成20年度の税制改正により、青色申告書を提出する法人が、平成20年4月1日から平成25年3月31日までの間に開始する各事業年度において、障害者就労支援事業所に対して、資産を譲り受け、又は役務の提供を受けた対価として支払った金額(以下「支援事業所取引金額」という。)がある場合において、その事業年度における支援事業所取引金額の合計額が前事業年度における支援事業所取引金額の合計額を超えるときは、その超える金額(支援事業所取引増加額)を限度として、その事業年度終了の日において有する減価償却資産で事業の用に供されているもののうちその事業年度又はその事業年度開始の日前2年以内に開始した各事業年度において取得等をしたものについて、普通償却限度額の30%相当額の割増償却を行うことができるという制度が創設された(措法46の3)。
(注)「障害者就労支援事業所」とは、障害者自立支援法第5条第14項に規定する就労移行支援を行う事業所、同条第15項に規定する就労継続支援を行う事業所その他次に掲げる事業所又は施設をいう(措法46の3①、措令29の2の2①)。
① 障害者自立支援法第5条第1項に規定する障害福祉サービス事業(同条第6項に規定する生活介護、同条第14項に規定する就労移行支援又は同条第15項に規定する就労継続支援を行う事業に限る。)を行う事業所
② 障害者自立支援法第5条第1項に規定する施設障害福祉サービスとして同条第6項に規定する生活介護又は同条第14項に規定する就労移行支援を行う障害者支援施設等
③ 障害者自立支援法第5条第21項に規定する地域活動支援センター
④ 障害者の雇用の促進等に関する法律第44条第1項の認定に係る同項に規定する子会社の事業所
⑤ 次に掲げる要件のすべてを満たす事業所
ⅰ その資産を譲り受け、又は役務の提供を受けた日を含む年の前年12月31日(以下「取引日の前年末」という。)におけるその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長(以下「公共職業安定所長」という。)の証明を受けた障害者数が5人以上であること
ⅱ 取引日の前年末における公共職業安定所長の証明を受けた障害者割合が100分の20以上であること
ⅲ 取引日の前年末における公共職業安定所長の証明を受けた重度障害者等割合が100分の30以上であること
平成20年4月1日から障害者自立支援法附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日の前日までの間においては、次の施設も障害者就労支援事業所となる(措令29の2の2②、措規20の18の2①)。
⑥ 障害者自立支援法附則第41条第1項、第48条又は第58条第1項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた同法附則第35条の規定による改正前の身体障害者福祉法第31条に規定する身体障害者授産施設
⑦ 障害者自立支援法附則第46条の規定による改正前の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第50条の2第3項に規定する精神障害者授産施設
⑧ 障害者自立支援法附則第46条の規定による改正前の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第50条の2第5項に規定する精神障害者福祉工場
⑨ 障害者自立支援法附則第52条の規定による改正前の知的障害者福祉法第21条の7に規定する知的障害者授産施設
⑩ 障害者自立支援法第5条第1項に規定する障害福祉サービスのうち障害者自立支援法施行規則附則第1条の2により読み替えて適用する同令第1条の2に規定する就労継続支援を行う障害者支援施設等
1 適用対象資産
本制度の適用対象資産は、当該事業年度終了の日においてその法人の有する減価償却資産で事業の用に供されているもののうち、当該事業年度又は当該事業年度開始の日前2年以内に開始した各事業年度において取得し、又は製作し、若しくは建設したもの(所有権移転外リース取引により取得したものを除く。以下「3年以内取得資産」という。)である。
2 償却限度額
〔算式〕
割増償却限度額 = 3年以内取得資産の普通償却限度額 × 30%
ただし、上記算式により計算した割増償却限度額の合計額が当該事業年度の支援事業所取引増加額(※)を超えるときは、その支援事業所取引増加額が限度となる(措法46の3①)。
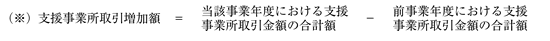
3 適用要件
本制度の適用を受けるためには、法人が資産を譲り受け、又は役務の提供を受けた対価として支払った金額につき支援事業所取引金額に該当するものとして障害者就労支援事務所から交付を受けた一定の書類を保存していることが必要とされている(措令29の2の2⑨、措規20の18の2⑧)。
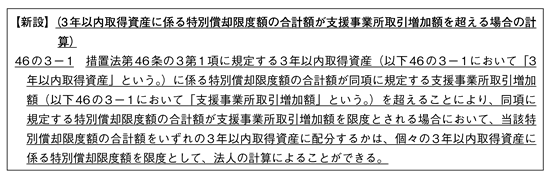 【解説】
【解説】1 平成20年度の税制改正において、青色申告法人が、障害者自立支援法に規定する就労移行支援等を行う事業所に対して、資産を譲り受け、又は役務の提供を受けた対価として支払った金額(以下「支援事業所取引金額」という。)がある場合において、その事業年度における支援事業所取引金額の合計額が前事業年度における支援事業所取引金額の合計額を超えるときは、その事業年度終了の日において有する減価償却資産で事業の用に供されているもののうちその事業年度又はその事業年度開始の日前2年以内に開始した各事業年度において取得等したもの(以下「3年以内取得資産」という。)について、普通償却限度額の30%に相当する金額(以下「特別償却限度額」という。)の割増償却を行うことができる制度が創設された(措法46の3)。
2 この場合において、3年以内取得資産に係る特別償却限度額の合計額が支援事業所取引増加額(その事業年度における支援事業所取引金額の合計額が前事業年度における支援事業所取引金額の合計額を超える場合のその超える金額をいう。)を超えるときには、当該特別償却限度額の合計額は、支援事業所取引増加額を限度とされるのであるが、3年以内取得資産が複数ある場合に、特別償却限度額の合計額をいずれの3年以内取得資産に配分することとなるのか疑義が生じる。
この点、計算の簡便性の観点からは、特別償却限度額の合計額を3年以内取得資産の取得価額等に応じてプロラタ計算により配分する方法が、一般的な計算方法であるとも考えられる。
しかしながら、本制度の対象となる3年以内取得資産は、「その事業年度終了の日において有する減価償却資産で事業の用に供されているもののうちその事業年度又はその事業年度開始の日前2年以内に開始した各事業年度において取得等したもの」とされているのみで、資産の種類や構造・用途等について何ら限定されているものではない。また、本制度が、授産施設等の支援事業所に対する一般企業からの発注の増加促進を税制の側面からも支援しようという趣旨から創設されたものであることからすれば、支援事業所取引増加額を限度とされた特別償却限度額の合計額を、個々の3年以内取得資産に係る特別償却限度額の範囲内で法人の計算により任意に配分することを認めることが本制度の趣旨に即した取扱いになるものと考えられる。
そこで、3年以内取得資産に係る特別償却限度額の合計額が支援事業所取引増加額を限度とされる場合において、当該特別償却限度額の合計額をいずれの3年以内取得資産に配分するかは、個々の3年以内取得資産に係る特別償却限度額を限度として、法人の計算によることができる旨を本通達において明らかにしている。
3 連結納税制度に係る租税特別措置法第68条の32《支援事業所取引金額が増加した場合の3年以内取得資産の割増償却》についても、同様の通達(連措通68の32-1)を定めている。
3 第52条の3《準備金方式による特別償却》関係
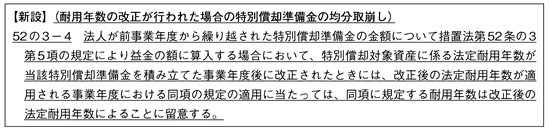 【解説】
【解説】1 法人が積み立てた特別償却準備金の額は、特別償却対象資産ごとにその積立てをした事業年度の翌事業年度から、特別償却対象資産の法定耐用年数に応じて、法定耐用年数が10年以上のものは7年間、5年以上10年未満のものは5年間、それ以外のものは法定耐用年数に相当する期間に均分して益金の額に算入することとされている(措法52の3⑤)。
2 平成20年度の税制改正により、耐用年数省令が改正され、資産区分が多い機械及び装置を中心に、使用実態を踏まえた年数を基礎としつつ、資産区分が整理されるとともに、法定耐用年数の見直しが行われた。このように、特別償却準備金の積立てをした事業年度後において特別償却対象資産に係る法定耐用年数が改正された場合に、特別償却準備金の均分取崩しは、改正前後のいずれの法定耐用年数によるべきか疑義が生じる。
この点、特別償却準備金の取崩しは、特別償却の適用を受けた場合のその後の償却計算と均衡を図るものであるところ、法定耐用年数が短くなった場合には償却費を多く計上できることから、それに応じて特別償却準備金の取崩期間も短くするのが合理的であると考えられる。また、このことは法定耐用年数が長くなった場合も同様である。
本通達では、特別償却準備金の積立てをした事業年度後において特別償却対象資産に係る法定耐用年数が改正された場合には、改正後の法定耐用年数が適用される事業年度における特別償却準備金の均分取崩しの年数は、改正後の法定耐用年数により判断することを留意的に明らかにしている。
具体例で示せば、次のとおりである。
○ 特別償却対象資産の法定耐用年数が短くなった場合
特別償却限度額 700
法定耐用年数 12年から9年に改正(改正後の法定耐用年数はX+3期から適用)
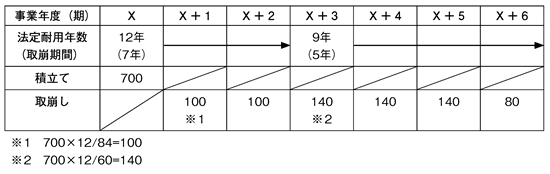
4 第67条の3《農業生産法人の肉用牛の売却に係る所得の課税の特例》関係 〔制度の概要〕
この制度は、農業生産法人が、昭和56年4月1日から平成24年3月31日までの期間内の日を含む各事業年度において、その飼育した肉用牛を家畜市場、中央卸売市場等において売却した場合等において、その売却した肉用牛のうちに免税対象飼育牛があるときは、その売却による利益の額(年2,000頭を超える場合には超える部分の利益の額を除く。)に相当する金額を、その売却した日を含む事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入することができるというものである(措法67の3)。
1 適用対象法人
本制度の適用対象法人は、農地法第2条第7項に規定する農業生産法人とされている(措法67の3①)。
2 適用対象となる免税対象飼育牛
本制度の適用対象となる免税対象飼育牛は、肉用牛(農業災害補償法第111条第1項に規定する肉用牛等及び乳牛の雌等(乳牛の雌のうち子牛の生産の用に供されたもの及び牛の胎児を除く。))のうち、家畜改良増殖法第32条の2第1項の規定による農林水産大臣の承認を受けた同項に規定する登録規程に基づく一定の登録がされているもの又はその売却価額が100万円未満(ホルスタイン種、ジャージー種又は乳用種である乳牛に該当する場合には、50万円未満)であるものとされている(措法67の3①②、措令39の26①④、措規22の16①)。
3 適用対象となる売却
(1)家畜取引法第2条第3項に規定する家畜市場、中央卸売市場又は家畜取引法第27条第1項の規定による届出に係る市場等において行う売却の方法により、農業生産法人が飼育した肉用牛を売却した場合。
(2)肉用子牛生産安定等特別措置法第6条第2項に規定する指定協会から同法第7条第2項に規定する生産者補給金交付業務に関する事務の委託を受けている農業協同組合又は農業協同組合連合会で農林水産大臣が指定したものに委託して行う売却の方法により、農業生産法人が飼育した生産後1年未満の肉用牛を売却した場合。
(措法67の3①、措令39の26②③)
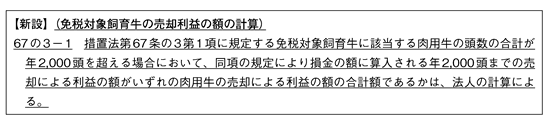
【解説】
1 本制度は、農業生産法人がその飼育した肉用牛を家畜市場、中央卸売市場等において売却した場合等において、その売却した肉用牛のうちに免税対象飼育牛があるときは、その売却による利益の額に相当する金額を、その売却をした日を含む事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入することができるというものである(措法67の3①)。
2 平成20年度の税制改正により、免税対象飼育牛の売却頭数の合計が年2,000頭を超える場合には、その超える部分の売却による利益の額については、免税対象から除外された。この改正により、免税対象飼育牛の売却頭数の合計が年2,000頭以内である場合には、その売却したすべての免税対象飼育牛の売却による利益の額について本制度を適用することができるが、年2,000頭を超える場合に損金の額に算入される年2,000頭までの売却による利益の額がいずれの免税対象飼育牛の売却によるものとすべきなのかといった疑問が生じる。
この点、法令上は何ら限定されておらず、また、本制度が年2,000頭までの肉用牛の売却による所得を全免するものであり、個々の売却による利益の大小に着目した制度でないことからすれば、免税対象飼育牛の売却頭数の合計が年2,000頭を超える場合には、損金の額に算入される年2,000頭までの売却による利益の額がいずれの免税対象飼育牛の売却によるものかは、法人の計算によることとして差し支えないものと考えられる。本通達ではこのことを明らかにしている。
3 なお、免税対象飼育牛の売却による利益の額は、一頭ごとに計算するのではなく、選択した2,000頭すべてに係る収益の額からその収益に係る原価の額とその売却に係る経費の額との合計額を控除した金額となる(措令39の26⑤)。したがって、2,000頭のうちに、一頭ごとに計算すると損失が生じる免税対象飼育牛があったとしても、これを除外して免税対象飼育牛の売却による利益の額を計算することはできない。また、本制度の適用を受けるためには、2,000頭すべてについての証明書類が確定申告書等に添付されている必要がある(措法67の3③)のであるから、その点、留意する必要がある。
4 連結納税制度に係る租税特別措置法第68条の101《農業生産法人の肉用牛の売却に係る連結所得の課税の特例》についても、同様の通達(連措通68の101-1)を新たに定めている。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -

Copyright (C) 2019
SHINNIPPON-HOKI PUBLISHING CO.,LTD.





















