解説記事2010年02月15日 【会社法関連解説】 日本経団連「会社法施行規則及び会社計算規則による株式会社の各種書類のひな型」改訂について(2010年2月15日号・№342)
実務解説
日本経団連「会社法施行規則及び会社計算規則による株式会社の各種書類のひな型」改訂について
日本経済団体連合会 経済基盤本部主幹 小畑良晴
日本経団連経済法規委員会企画部会(部会長:八丁地隆日立製作所副社長)は、昨年12月28日、「会社法施行規則及び会社計算規則による株式会社の各種書類のひな型」の改訂版(以下「ひな型」という。)を公表した。
平成21年3月27日に公布された会社法施行規則、会社計算規則の一部を改正する省令や、平成21年4月20日の財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令などを踏まえて、平成21年4月1日以後に事業年度の末日を迎える場合の事業年度に関する事業報告及びその附属明細書などを念頭に改訂したものである。平成19年2月に公表して以来、平成20年11月25日の改訂に続き2回目の改訂となる。
今回の改訂にあたっては、法務省民事局参事官室大野晃宏局付、黒田裕局付、髙木弘明局付のご協力を得て、澤口実先生・石井裕介先生はじめ森・濱田松本法律事務所の先生方、布施伸章先生・阿部光成先生はじめ有限責任監査法人トーマツの先生方のご助言・ご協力と、わが国を代表する企業実務の専門家である日本経団連経済法規委員会企画部会及び同委員会企業会計部会委員による検討結果を踏まえて作成したものである。
主な改正のポイントは以下の通りである(編注:原文は日本経済団体連合会のホームページ(http://www.keidanren.or.jp/japanese/policy/2009/118.pdf)からダウンロードすることができる。)。
Ⅰ.事業報告
今回の改訂は、前回の改訂以後の法務省令の改正を踏まえた修正にとどまらず、①各項目の冒頭に法務省令の対応条項を掲記するとともに、②平成18年5月の会社法施行以来の実務の定着状況を踏まえた修正を行い、さらに③昨年4月に当時の法務省担当官によって明らかにされた(脚注1)事業報告の開示事項の基準時点等に関する解釈を踏まえて基準時点等の明確化を図ったことから、前回よりも広範囲な見直しを行うこととなった。
1.開示項目の基準時点 各開示項目について事業報告の記載の対象となる期間が、必ずしも会社法施行規則上すべて明記されているわけではないことから、「第2 各記載事項の記載方法」として、その判断基準を概括的に説明を加えた。
事業報告とは、報告の対象となる事業年度における事業の経過及び成果を株主に対して報告するという性質のものであるため、原則として、対象となる事業年度の初日から末日までに発生ないし変動した事象を内容とすれば足りる。
事業年度末日後に生じた事象については、株主にとり重要な事項に限り「その他株式会社の現況に関する重要な事項」(会社法施行規則120条1項9号)や「会社役員に関する重要な事項」(会社法施行規則121条9号)、「当該株式会社の状況に関する重要な事項」(会社法施行規則118条1号)などとして事業報告の内容とすることが考えられる。
ただし、会社法施行規則上、明文によって記載の基準時が定められているものや、 記載事項の性質上、事業報告作成時点における内容を記載することが適切であると考えられるものも存在する。記載事項の性質上、事業報告作成時点における内容を記載することが適切であると考えられる事項としては、「当該株式会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者のあり方に関する基本方針」(会社法施行規則118条3号)、「各会社役員の報酬等の額又はその算定方法に係る決定に関する方針の概要」(会社法施行規則121条5号)、「会計監査人の解任又は不再任の決定の方針」(会社法施行規則126条4号)、「剰余金の配当等の方針」(会社法施行規則126条10号)といった株式会社の将来に向けた方針に関する事項や、当該事業年度の事業の経過及び成果を踏まえて現時点における対処すべき課題を報告する趣旨の「対処すべき課題」(会社法施行規則120条1項8号)が挙げられる。
2.上位10名の株主の状況 これまで、発行済株式総数の10分の1以上の数の株式を有する大株主が開示事項とされていたところ、平成21年3月27日に公布された会社法施行規則の改正により、発行済株式総数に対する割合において上位の者10名(株主名簿における保有株式数(種類株式も含む。)を基準として形式的に算出するものであり、かつ分子分母から自己株式は除かれる。)の株主の氏名等を開示することとなった(会社法施行規則122条1号)ことから、改正後の法務省令に対応した。
なお、この改訂に伴い、項目のタイトルを「発行済株式の10分の1以上を有する大株主の状況」から「上位10名の株主の状況」に改めた。これは、上位10名の株主が必ずしも「大株主」に該当するとは限らないことを踏まえたものである。
3.その他新株予約権等に関する重要な事項 具体的な記載事項は会社法施行規則では列挙されていないが、従来のひな型では、「有利な条件の内容」を掲記していた。これまでの開示事例ではそのような記載例はほとんどなく、また、「有利な条件の内容」は新株予約権の発行時には株主にとって重要な事項であるが、いったん発行されればもはや重要性は失われるとも考えられることから、記載例から削除することとした。
また、会社法施行規則123条1号において「会社役員」の範囲が「当該事業年度の末日において在任している者に限る。」と明確化される一方、同条2号の使用人等については、「会社役員」のような限定が付されていないことを踏まえ、記載上の注意として、「(3)「交付された者」とは、交付時に使用人等であった者を意味する。したがって、事業年度中に使用人等となった者や使用人等でなくなった者であっても、交付時に使用人等でありさえすれば記載の対象となる。」旨、追加した。
4.辞任した会社役員又は解任された会社役員に関する事項、辞任した又は解任された会計監査人に関する事項 会社役員及び会計監査人の解任及び辞任に関する事項について、開示すべき事項の範囲の合理化に係る改正が行われ、旧規定における「当該事業年度中に」との文言が削除され、「意見があった」との文言が「意見がある」に改められた(会社法施行規則121条6号、126条9号)。
この改正を踏まえ、記載方法の説明中に、本項目における会社役員及び会計監査人については、過去に辞任した又は解任された全ての者(株主総会又は種類株主総会の決議によって解任されたものを除く。)が対象となることを明記した。
したがって、事業報告の対象となる事業年度中に、①辞任又は解任という事象が生じた場合、②辞任又は解任について株主総会において述べられる予定の意見又は辞任した理由が判明した場合、③辞任又は解任についての意見又は辞任した理由が株主総会において述べられた場合又は④事業報告に記載された意見と株主総会で実際に述べられた意見が異なる場合などにおいて記載の要否を検討する必要がある。
例えば3月末決算の会社において、平成22年3月10日に会計監査人が辞任し、同年4月15日に、来る定時株主総会(同年6月)において当該会計監査人であった者が述べる予定の意見又は理由が判明した場合には、同年に作成する事業報告において、当該会計監査人であった者の氏名及び株主総会で述べる予定の意見又は理由を開示することとなる。また、実際に同年6月の定時株主総会で述べられた意見又は理由が、事業報告に記載された内容と同じであれば、「当該事業年度前の事業年度に係る事業報告の内容としたものを除く」(会社法施行規則121条6号、126条9号)とされていることから、翌年の事業報告では、実際に述べられた意見又は理由を記載する必要はないと考えられる。ただし、実際に述べられた意見又は理由が予定されていたものと異なっていた場合には、翌年の事業報告で記載する必要があると考えられる。
5.重要な兼職の状況 会社法施行規則の改正により、会社役員に関する事項中、「他の法人等の代表状況」と「重要な兼職の状況」とが、「重要な兼職の状況」に一本化されたことから(会社法施行規則121条7号)、会社役員が他の法人等の代表者であったとしても、当然には本項目の記載対象とはならず、当該兼任のうち「重要な兼職」に該当するもののみを記載すれば足りることとなった。
重要な兼職であるか否かは、もっぱら事業報告作成会社の視点から兼職先が取引上重要な存在であるか否か、当該取締役等が兼職先で重要な職務を担当するか否か等を総合的に考慮して判断するため、兼職先にとって事業報告作成会社が重要な取引先であったとしても、事業報告作成会社にとっては多くの取引先の一つにすぎない場合は「重要な兼職」には該当せず、また兼職先の代表者であったとしても「重要な兼職」に該当しない場合もありうる。
なお、事業年度の途中に兼職の状況に変動があった場合、その変動が重要である場合には、変動の内容を記載することが考えられる。
会社法施行規則の改正前には、社外役員が他の「会社」の業務執行取締役等又は他の「株式会社」の社外役員を兼職又は兼任していることに関する開示が求められていた。業務執行取締役等の兼職先は「会社」、社外役員の兼任先は「株式会社」と微妙に差があったが、昨年の改正により「法人等」に統一された。また、当該兼職又は兼任について、通常の会社役員における「重要な兼職」に該当する場合とする旨、規定が整理された。社外役員と社内役員とで「重要な兼職」について同一の規律になったことから、従来のひな型で、「当社の会社役員に関する事項」と「社外役員の重要な兼職状況等」の2つに分けていた一覧表を一本化することとした(記載例1参照)。なお、社外役員について「重要な兼職」に該当する場合に開示される「当該他の法人等との関係」については、明文上重要なものに限るという限定は特に付されていないが、社外役員としての職務執行に何ら影響を与えるおそれがない一般的な取引条件に基づく単なる取引関係等については、開示の対象とならないと解されている(脚注2)。
また、一本化した一覧表では「地位及び担当」を一括した項目を設けた。これは、監査役には「担当」という概念がないことから(脚注3)、「担当」欄が独立していると空白が生じることを避ける趣旨である。
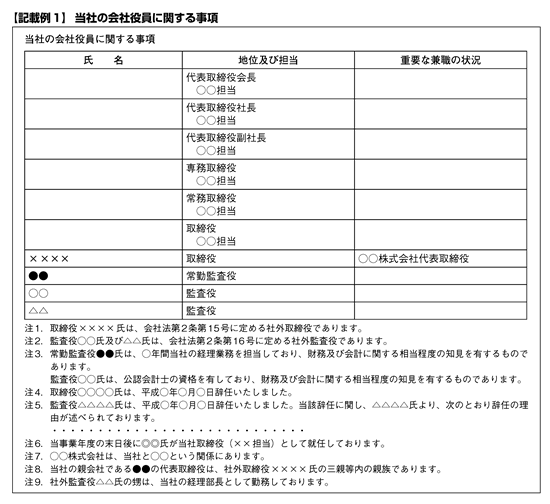 6.適用関係
本ひな型は、平成21年4月1日以後に事業年度の末日を迎える場合の事業年度に関する事業報告及びその附属明細書から適用する。
6.適用関係
本ひな型は、平成21年4月1日以後に事業年度の末日を迎える場合の事業年度に関する事業報告及びその附属明細書から適用する。
Ⅱ.株主総会参考書類
1.議案の提案の理由 株主総会参考書類については、会社法施行規則の改正により、取締役が提出するすべての議案について「提案の理由」を記載事項とすることとされたことから(会社法施行規則73条1項2号)、それぞれの項目について「提案の理由」を追加した。
実務上は、これまでも提案の理由・目的・趣旨等の記載が一般的になされており、これまでの実務を変えるものではない。例えば、取締役の選任議案の記載例では、「本総会終結の時をもって取締役○名が任期満了となりますので」の部分が「提案の理由」に該当する。
2.取締役・監査役の選任議案(重要な兼職の状況) 取締役の選任に関する議案及び監査役の選任に関する議案については、従来、他の法人等の代表状況の開示が求められていたが、会社法施行規則の改正により、事業報告に合わせて(Ⅰ.5参照)、「重要な兼職の状況」に概念統一された(会社法施行規則74条2項2号、76条2項2号)。
株主総会参考書類作成時における兼職のうち、重要なものを事業報告における「会社役員に関する事項」と同様に記載する。なお、作成時に兼職の事実が存在したとしても、就任時には兼職がなくなることが明らかである場合や将来予定される就任後間もなく当該「兼職」に該当する他の職から離れることが明らかな場合には、一般的には「重要」でないものとして開示する必要はないと考えられる(脚注4)。
3.社外取締役候補者又は社外監査役候補者に係る親族関係者 会社法施行規則の改正により、事業報告における同趣旨の開示(会社法施行規則124条3号)との整合性の観点から、社外取締役候補者又は社外監査役候補者に係る親族関係者の開示においても、「重要でないものを除く」との文言が追加されたことに注意が必要である。社外役員としての職務の遂行に影響を及ぼしうるかどうかに照らして判断を行う(脚注5)。
4.適用関係 本ひな型は、平成21年4月1日以後に事業年度の末日を迎える場合の事業年度に関する定時株主総会に係る株主総会参考書類から適用する。
Ⅲ.計算書類・連結計算書類
計算書類及び連結計算書類については、平成20年6月6日、同年8月7日、同年12月12日及び平成21年3月24日に公布された内閣府令による財務諸表等規則及び連結財務諸表規則の改正に対応するために行われた会社計算規則の改正及び平成21年4月20日の内閣府令による財務諸表等規則等の改正を踏まえたものである。
1.少数株主損益調整前当期純損益の表示 平成20年12月26日に公表された連結財務諸表に関する会計基準(企業会計基準第22号)及び平成21年3月3月24日に公布された平成21年内閣府令第5号による改正後の連結財務諸表規則65条2項において、連結損益計算書に少数株主損益調整前当期純損益の表示が義務付けられたことから、会社計算規則93条1項3号が追加された。
そこで、連結計算書類において、少数株主損益調整前当期純利益又は少数株主損益調整前当期純損失の記載例を追加した(記載例2参照)。ただし、この部分は、平成21年4月1日前に開始する事業年度に係る計算関係書類には適用されないが、施行日以後に作成されるものについては早期適用できることから設けたものである。
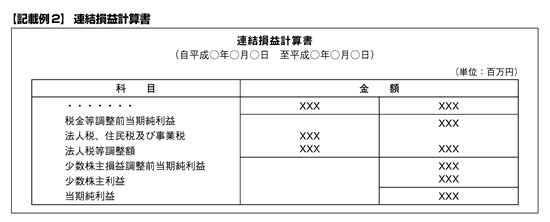 2.継続企業の前提に関する注記
注記表関係では、まず、継続企業の前提に関する注記について、平成21年4月20日の平成21年内閣府令第27号による改正後の財務諸表等規則等の改正を踏まえて修正した。
2.継続企業の前提に関する注記
注記表関係では、まず、継続企業の前提に関する注記について、平成21年4月20日の平成21年内閣府令第27号による改正後の財務諸表等規則等の改正を踏まえて修正した。
具体的には、「継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況」が認められる場合は、まず、経営者がその事象や状況を解消し、又は改善するための対応策を検討、評価し、こうした対策を講じてもなお継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められるとき(当該事業年度の末日後に当該重要な不確実性が認められなくなった場合を除く。)に注記が必要となる。なお、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められるか否かについては、総合的かつ実質的に判断を行う。
3.新たな注記事項の追加 会社計算規則の改正により、注記事項の追加が行われた(表参照)。具体的には、持分法損益等の注記(会社計算規則111条)、開示対象特別目的会社の概要等の注記(会社計算規則102条1項1号ホ)、金融商品に関する注記(会社計算規則109条)、賃貸等不動産に関する注記(会社計算規則110条)である。
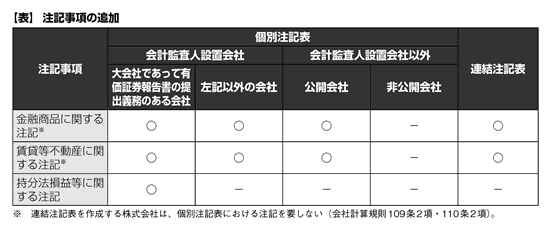 持分法損益等に関する注記は、連結計算書類の作成義務があるが、重要な子会社が存在しないために連結計算書類を作成しない株式会社について開示することに意味があることから、連結計算書類を作成する株式会社においては注記は不要であり(会社計算規則111条2項)、また、会計監査人設置以外の株式会社のみならず、会計監査人設置会社であっても大会社の有価証券報告書提出会社以外の株式会社は、その作成は不要である(会社計算規則98条2項3号)。
持分法損益等に関する注記は、連結計算書類の作成義務があるが、重要な子会社が存在しないために連結計算書類を作成しない株式会社について開示することに意味があることから、連結計算書類を作成する株式会社においては注記は不要であり(会社計算規則111条2項)、また、会計監査人設置以外の株式会社のみならず、会計監査人設置会社であっても大会社の有価証券報告書提出会社以外の株式会社は、その作成は不要である(会社計算規則98条2項3号)。
開示対象特別目的会社の概要等の注記は、連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記の一つであり、連結注記表のみであることは言うまでもない。
金融商品に関する注記及び賃貸等不動産に関する注記は、連結注記表を作成する場合には、個別注記表における注記は不要である(会社計算規則109条2項、110条2項)。これらの注記は、非公開会社の会計監査人設置会社以外の株式会社でない限り必要とされる。重要性の乏しいものを除き、それぞれ「状況に関する事項」と「時価等に関する事項」を記載する必要がある。もっとも、これらの注記は有価証券報告書を提出する会社のみを対象としているものではないことから、各社の実情に応じて、概括的に記載することで足りる(脚注6)。ひな型の記載例ではかなり詳細な記載を例示しているが、各社の実情に応じた記載が求められる。
次頁以降に掲げるのは、それぞれの事項の記載例である(記載例3~6参照)。
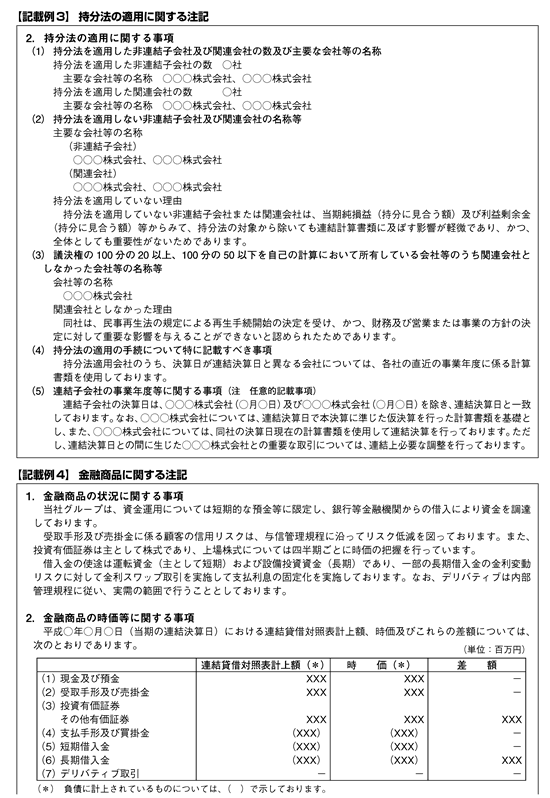
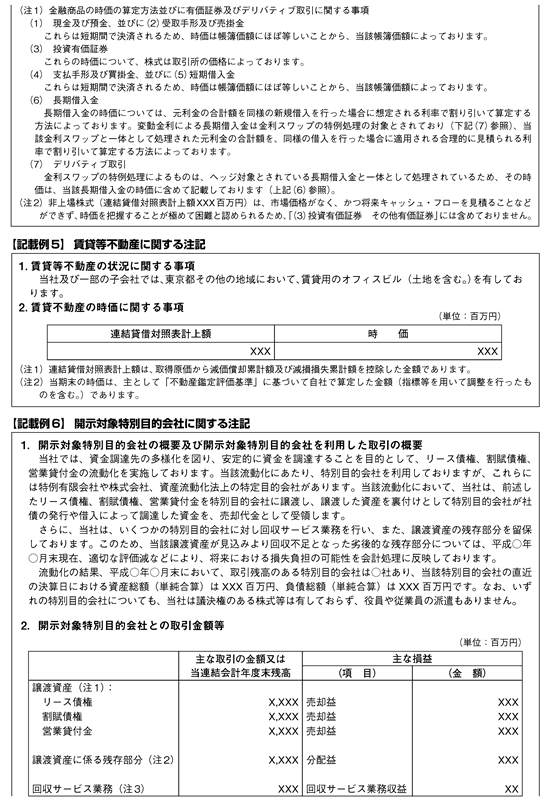
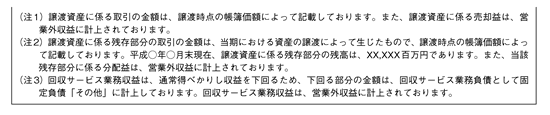 4.米国基準適用会社の注意点
これまで、連結財務諸表規則(旧連結財務諸表規則93条~96条)において米国基準によって連結財務諸表を作成することが許容されている株式会社について、会社法上の連結計算書類についても米国基準によって作成することが許容されていた(旧会社計算規則120条1項)。
4.米国基準適用会社の注意点
これまで、連結財務諸表規則(旧連結財務諸表規則93条~96条)において米国基準によって連結財務諸表を作成することが許容されている株式会社について、会社法上の連結計算書類についても米国基準によって作成することが許容されていた(旧会社計算規則120条1項)。
平成21年12月11日の平成21年内閣府令第73号による改正後の連結財務諸表規則において、平成22年3月期以降の連結財務諸表をIFRSによって作成することが許容されたことに伴い、連結財務諸表規則から米国基準適用会社に関する条項が削除され、現在、米国基準を適用している会社については、附則において、平成28年3月31日までに終了する連結会計年度に係るものまで引き続き米国基準の適用を認める経過措置が置かれた。
これを踏まえ、平成21年12月11日の平成21年法務省令第46号によって会社計算規則の一部が改正された。本省令附則3条において、連結計算書類についても、平成28年3月31日までに終了する連結会計年度に係るものまで引き続き米国基準の適用を認める経過措置が置かれた。
今般、注記事項に追加された賃貸等不動産に関する注記は、米国基準では記載が求められていなことから、米国基準適用会社においては、連結注記表に記載がなく、その結果として個別注記表における注記が求められる可能性がある(会社計算規則110条2項)。もっとも、平成21年12月に公表された連結財務諸表ガイドラインの附則において、米国式連結財務諸表を提出する場合、賃貸等不動産の総額に重要性があるときは注記する(「主要な相違点」として記載することができる。)こととされていることに留意する必要がある。
5.適用関係 計算書類に関するひな型については、書類や項目ごとに適用時期が異なることがあるため、注意が必要である。具体的には各項目における「記載上の注意」を参照されたい。
なお、「金融商品に関する注記」及び「賃貸等不動産に関する注記」は、原則として、2010(平成22)年3月31日前に終了する事業年度に係る計算関係書類については適用されないが、早期適用することは可能である点に特に注意されたい(会社法施行規則、会社計算規則等の一部を改正する省令(平成21年法務省令第7号)附則8条3項)。
脚注
1 小松岳志=澁谷亮「事業報告の内容に関する規律の全体像」商事法務1863号(2009)10頁以下。
2 前掲(注1)19頁。
3 前掲(注1)14頁。
4 大野晃宏=小松岳志=澁谷亮=黒田裕=和久友子「会社法施行規則、会社計算規則等の一部を改正する省令の解説―平成21年法務省令第7号―」商事法務1862号(2009)19頁。
5 前掲(注4)20頁。
6 前掲(注4)16頁。
日本経団連「会社法施行規則及び会社計算規則による株式会社の各種書類のひな型」改訂について
日本経済団体連合会 経済基盤本部主幹 小畑良晴
日本経団連経済法規委員会企画部会(部会長:八丁地隆日立製作所副社長)は、昨年12月28日、「会社法施行規則及び会社計算規則による株式会社の各種書類のひな型」の改訂版(以下「ひな型」という。)を公表した。
平成21年3月27日に公布された会社法施行規則、会社計算規則の一部を改正する省令や、平成21年4月20日の財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令などを踏まえて、平成21年4月1日以後に事業年度の末日を迎える場合の事業年度に関する事業報告及びその附属明細書などを念頭に改訂したものである。平成19年2月に公表して以来、平成20年11月25日の改訂に続き2回目の改訂となる。
今回の改訂にあたっては、法務省民事局参事官室大野晃宏局付、黒田裕局付、髙木弘明局付のご協力を得て、澤口実先生・石井裕介先生はじめ森・濱田松本法律事務所の先生方、布施伸章先生・阿部光成先生はじめ有限責任監査法人トーマツの先生方のご助言・ご協力と、わが国を代表する企業実務の専門家である日本経団連経済法規委員会企画部会及び同委員会企業会計部会委員による検討結果を踏まえて作成したものである。
主な改正のポイントは以下の通りである(編注:原文は日本経済団体連合会のホームページ(http://www.keidanren.or.jp/japanese/policy/2009/118.pdf)からダウンロードすることができる。)。
Ⅰ.事業報告
今回の改訂は、前回の改訂以後の法務省令の改正を踏まえた修正にとどまらず、①各項目の冒頭に法務省令の対応条項を掲記するとともに、②平成18年5月の会社法施行以来の実務の定着状況を踏まえた修正を行い、さらに③昨年4月に当時の法務省担当官によって明らかにされた(脚注1)事業報告の開示事項の基準時点等に関する解釈を踏まえて基準時点等の明確化を図ったことから、前回よりも広範囲な見直しを行うこととなった。
1.開示項目の基準時点 各開示項目について事業報告の記載の対象となる期間が、必ずしも会社法施行規則上すべて明記されているわけではないことから、「第2 各記載事項の記載方法」として、その判断基準を概括的に説明を加えた。
事業報告とは、報告の対象となる事業年度における事業の経過及び成果を株主に対して報告するという性質のものであるため、原則として、対象となる事業年度の初日から末日までに発生ないし変動した事象を内容とすれば足りる。
事業年度末日後に生じた事象については、株主にとり重要な事項に限り「その他株式会社の現況に関する重要な事項」(会社法施行規則120条1項9号)や「会社役員に関する重要な事項」(会社法施行規則121条9号)、「当該株式会社の状況に関する重要な事項」(会社法施行規則118条1号)などとして事業報告の内容とすることが考えられる。
ただし、会社法施行規則上、明文によって記載の基準時が定められているものや、 記載事項の性質上、事業報告作成時点における内容を記載することが適切であると考えられるものも存在する。記載事項の性質上、事業報告作成時点における内容を記載することが適切であると考えられる事項としては、「当該株式会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者のあり方に関する基本方針」(会社法施行規則118条3号)、「各会社役員の報酬等の額又はその算定方法に係る決定に関する方針の概要」(会社法施行規則121条5号)、「会計監査人の解任又は不再任の決定の方針」(会社法施行規則126条4号)、「剰余金の配当等の方針」(会社法施行規則126条10号)といった株式会社の将来に向けた方針に関する事項や、当該事業年度の事業の経過及び成果を踏まえて現時点における対処すべき課題を報告する趣旨の「対処すべき課題」(会社法施行規則120条1項8号)が挙げられる。
2.上位10名の株主の状況 これまで、発行済株式総数の10分の1以上の数の株式を有する大株主が開示事項とされていたところ、平成21年3月27日に公布された会社法施行規則の改正により、発行済株式総数に対する割合において上位の者10名(株主名簿における保有株式数(種類株式も含む。)を基準として形式的に算出するものであり、かつ分子分母から自己株式は除かれる。)の株主の氏名等を開示することとなった(会社法施行規則122条1号)ことから、改正後の法務省令に対応した。
なお、この改訂に伴い、項目のタイトルを「発行済株式の10分の1以上を有する大株主の状況」から「上位10名の株主の状況」に改めた。これは、上位10名の株主が必ずしも「大株主」に該当するとは限らないことを踏まえたものである。
3.その他新株予約権等に関する重要な事項 具体的な記載事項は会社法施行規則では列挙されていないが、従来のひな型では、「有利な条件の内容」を掲記していた。これまでの開示事例ではそのような記載例はほとんどなく、また、「有利な条件の内容」は新株予約権の発行時には株主にとって重要な事項であるが、いったん発行されればもはや重要性は失われるとも考えられることから、記載例から削除することとした。
また、会社法施行規則123条1号において「会社役員」の範囲が「当該事業年度の末日において在任している者に限る。」と明確化される一方、同条2号の使用人等については、「会社役員」のような限定が付されていないことを踏まえ、記載上の注意として、「(3)「交付された者」とは、交付時に使用人等であった者を意味する。したがって、事業年度中に使用人等となった者や使用人等でなくなった者であっても、交付時に使用人等でありさえすれば記載の対象となる。」旨、追加した。
4.辞任した会社役員又は解任された会社役員に関する事項、辞任した又は解任された会計監査人に関する事項 会社役員及び会計監査人の解任及び辞任に関する事項について、開示すべき事項の範囲の合理化に係る改正が行われ、旧規定における「当該事業年度中に」との文言が削除され、「意見があった」との文言が「意見がある」に改められた(会社法施行規則121条6号、126条9号)。
この改正を踏まえ、記載方法の説明中に、本項目における会社役員及び会計監査人については、過去に辞任した又は解任された全ての者(株主総会又は種類株主総会の決議によって解任されたものを除く。)が対象となることを明記した。
したがって、事業報告の対象となる事業年度中に、①辞任又は解任という事象が生じた場合、②辞任又は解任について株主総会において述べられる予定の意見又は辞任した理由が判明した場合、③辞任又は解任についての意見又は辞任した理由が株主総会において述べられた場合又は④事業報告に記載された意見と株主総会で実際に述べられた意見が異なる場合などにおいて記載の要否を検討する必要がある。
例えば3月末決算の会社において、平成22年3月10日に会計監査人が辞任し、同年4月15日に、来る定時株主総会(同年6月)において当該会計監査人であった者が述べる予定の意見又は理由が判明した場合には、同年に作成する事業報告において、当該会計監査人であった者の氏名及び株主総会で述べる予定の意見又は理由を開示することとなる。また、実際に同年6月の定時株主総会で述べられた意見又は理由が、事業報告に記載された内容と同じであれば、「当該事業年度前の事業年度に係る事業報告の内容としたものを除く」(会社法施行規則121条6号、126条9号)とされていることから、翌年の事業報告では、実際に述べられた意見又は理由を記載する必要はないと考えられる。ただし、実際に述べられた意見又は理由が予定されていたものと異なっていた場合には、翌年の事業報告で記載する必要があると考えられる。
5.重要な兼職の状況 会社法施行規則の改正により、会社役員に関する事項中、「他の法人等の代表状況」と「重要な兼職の状況」とが、「重要な兼職の状況」に一本化されたことから(会社法施行規則121条7号)、会社役員が他の法人等の代表者であったとしても、当然には本項目の記載対象とはならず、当該兼任のうち「重要な兼職」に該当するもののみを記載すれば足りることとなった。
重要な兼職であるか否かは、もっぱら事業報告作成会社の視点から兼職先が取引上重要な存在であるか否か、当該取締役等が兼職先で重要な職務を担当するか否か等を総合的に考慮して判断するため、兼職先にとって事業報告作成会社が重要な取引先であったとしても、事業報告作成会社にとっては多くの取引先の一つにすぎない場合は「重要な兼職」には該当せず、また兼職先の代表者であったとしても「重要な兼職」に該当しない場合もありうる。
なお、事業年度の途中に兼職の状況に変動があった場合、その変動が重要である場合には、変動の内容を記載することが考えられる。
会社法施行規則の改正前には、社外役員が他の「会社」の業務執行取締役等又は他の「株式会社」の社外役員を兼職又は兼任していることに関する開示が求められていた。業務執行取締役等の兼職先は「会社」、社外役員の兼任先は「株式会社」と微妙に差があったが、昨年の改正により「法人等」に統一された。また、当該兼職又は兼任について、通常の会社役員における「重要な兼職」に該当する場合とする旨、規定が整理された。社外役員と社内役員とで「重要な兼職」について同一の規律になったことから、従来のひな型で、「当社の会社役員に関する事項」と「社外役員の重要な兼職状況等」の2つに分けていた一覧表を一本化することとした(記載例1参照)。なお、社外役員について「重要な兼職」に該当する場合に開示される「当該他の法人等との関係」については、明文上重要なものに限るという限定は特に付されていないが、社外役員としての職務執行に何ら影響を与えるおそれがない一般的な取引条件に基づく単なる取引関係等については、開示の対象とならないと解されている(脚注2)。
また、一本化した一覧表では「地位及び担当」を一括した項目を設けた。これは、監査役には「担当」という概念がないことから(脚注3)、「担当」欄が独立していると空白が生じることを避ける趣旨である。
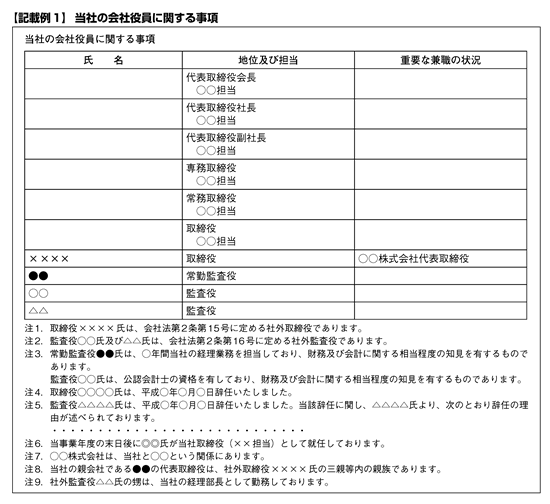 6.適用関係
本ひな型は、平成21年4月1日以後に事業年度の末日を迎える場合の事業年度に関する事業報告及びその附属明細書から適用する。
6.適用関係
本ひな型は、平成21年4月1日以後に事業年度の末日を迎える場合の事業年度に関する事業報告及びその附属明細書から適用する。 Ⅱ.株主総会参考書類
1.議案の提案の理由 株主総会参考書類については、会社法施行規則の改正により、取締役が提出するすべての議案について「提案の理由」を記載事項とすることとされたことから(会社法施行規則73条1項2号)、それぞれの項目について「提案の理由」を追加した。
実務上は、これまでも提案の理由・目的・趣旨等の記載が一般的になされており、これまでの実務を変えるものではない。例えば、取締役の選任議案の記載例では、「本総会終結の時をもって取締役○名が任期満了となりますので」の部分が「提案の理由」に該当する。
2.取締役・監査役の選任議案(重要な兼職の状況) 取締役の選任に関する議案及び監査役の選任に関する議案については、従来、他の法人等の代表状況の開示が求められていたが、会社法施行規則の改正により、事業報告に合わせて(Ⅰ.5参照)、「重要な兼職の状況」に概念統一された(会社法施行規則74条2項2号、76条2項2号)。
株主総会参考書類作成時における兼職のうち、重要なものを事業報告における「会社役員に関する事項」と同様に記載する。なお、作成時に兼職の事実が存在したとしても、就任時には兼職がなくなることが明らかである場合や将来予定される就任後間もなく当該「兼職」に該当する他の職から離れることが明らかな場合には、一般的には「重要」でないものとして開示する必要はないと考えられる(脚注4)。
3.社外取締役候補者又は社外監査役候補者に係る親族関係者 会社法施行規則の改正により、事業報告における同趣旨の開示(会社法施行規則124条3号)との整合性の観点から、社外取締役候補者又は社外監査役候補者に係る親族関係者の開示においても、「重要でないものを除く」との文言が追加されたことに注意が必要である。社外役員としての職務の遂行に影響を及ぼしうるかどうかに照らして判断を行う(脚注5)。
4.適用関係 本ひな型は、平成21年4月1日以後に事業年度の末日を迎える場合の事業年度に関する定時株主総会に係る株主総会参考書類から適用する。
Ⅲ.計算書類・連結計算書類
計算書類及び連結計算書類については、平成20年6月6日、同年8月7日、同年12月12日及び平成21年3月24日に公布された内閣府令による財務諸表等規則及び連結財務諸表規則の改正に対応するために行われた会社計算規則の改正及び平成21年4月20日の内閣府令による財務諸表等規則等の改正を踏まえたものである。
1.少数株主損益調整前当期純損益の表示 平成20年12月26日に公表された連結財務諸表に関する会計基準(企業会計基準第22号)及び平成21年3月3月24日に公布された平成21年内閣府令第5号による改正後の連結財務諸表規則65条2項において、連結損益計算書に少数株主損益調整前当期純損益の表示が義務付けられたことから、会社計算規則93条1項3号が追加された。
そこで、連結計算書類において、少数株主損益調整前当期純利益又は少数株主損益調整前当期純損失の記載例を追加した(記載例2参照)。ただし、この部分は、平成21年4月1日前に開始する事業年度に係る計算関係書類には適用されないが、施行日以後に作成されるものについては早期適用できることから設けたものである。
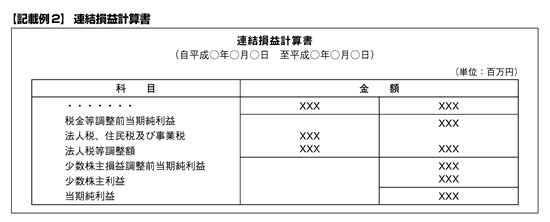 2.継続企業の前提に関する注記
注記表関係では、まず、継続企業の前提に関する注記について、平成21年4月20日の平成21年内閣府令第27号による改正後の財務諸表等規則等の改正を踏まえて修正した。
2.継続企業の前提に関する注記
注記表関係では、まず、継続企業の前提に関する注記について、平成21年4月20日の平成21年内閣府令第27号による改正後の財務諸表等規則等の改正を踏まえて修正した。具体的には、「継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況」が認められる場合は、まず、経営者がその事象や状況を解消し、又は改善するための対応策を検討、評価し、こうした対策を講じてもなお継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められるとき(当該事業年度の末日後に当該重要な不確実性が認められなくなった場合を除く。)に注記が必要となる。なお、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められるか否かについては、総合的かつ実質的に判断を行う。
3.新たな注記事項の追加 会社計算規則の改正により、注記事項の追加が行われた(表参照)。具体的には、持分法損益等の注記(会社計算規則111条)、開示対象特別目的会社の概要等の注記(会社計算規則102条1項1号ホ)、金融商品に関する注記(会社計算規則109条)、賃貸等不動産に関する注記(会社計算規則110条)である。
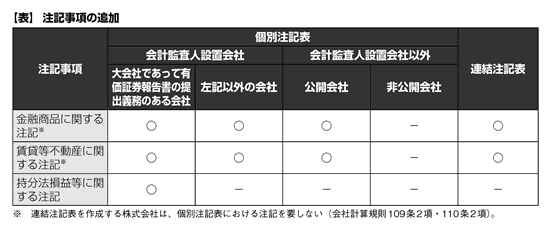 持分法損益等に関する注記は、連結計算書類の作成義務があるが、重要な子会社が存在しないために連結計算書類を作成しない株式会社について開示することに意味があることから、連結計算書類を作成する株式会社においては注記は不要であり(会社計算規則111条2項)、また、会計監査人設置以外の株式会社のみならず、会計監査人設置会社であっても大会社の有価証券報告書提出会社以外の株式会社は、その作成は不要である(会社計算規則98条2項3号)。
持分法損益等に関する注記は、連結計算書類の作成義務があるが、重要な子会社が存在しないために連結計算書類を作成しない株式会社について開示することに意味があることから、連結計算書類を作成する株式会社においては注記は不要であり(会社計算規則111条2項)、また、会計監査人設置以外の株式会社のみならず、会計監査人設置会社であっても大会社の有価証券報告書提出会社以外の株式会社は、その作成は不要である(会社計算規則98条2項3号)。開示対象特別目的会社の概要等の注記は、連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記の一つであり、連結注記表のみであることは言うまでもない。
金融商品に関する注記及び賃貸等不動産に関する注記は、連結注記表を作成する場合には、個別注記表における注記は不要である(会社計算規則109条2項、110条2項)。これらの注記は、非公開会社の会計監査人設置会社以外の株式会社でない限り必要とされる。重要性の乏しいものを除き、それぞれ「状況に関する事項」と「時価等に関する事項」を記載する必要がある。もっとも、これらの注記は有価証券報告書を提出する会社のみを対象としているものではないことから、各社の実情に応じて、概括的に記載することで足りる(脚注6)。ひな型の記載例ではかなり詳細な記載を例示しているが、各社の実情に応じた記載が求められる。
次頁以降に掲げるのは、それぞれの事項の記載例である(記載例3~6参照)。
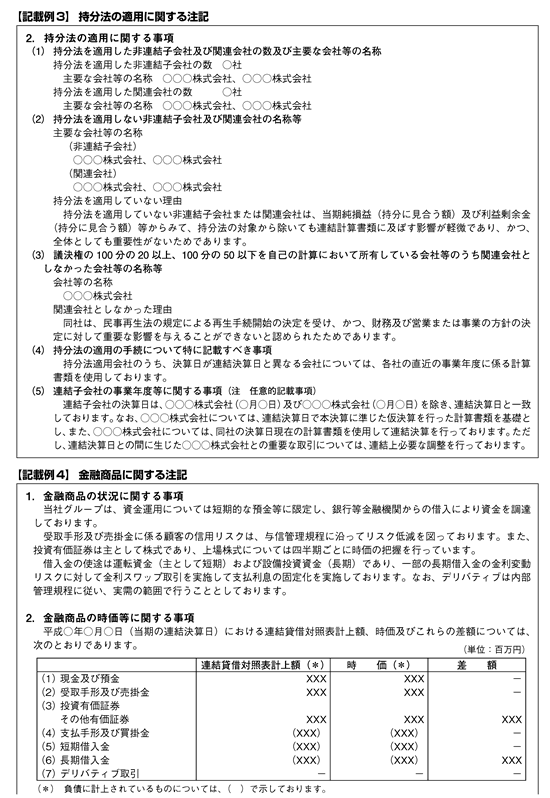
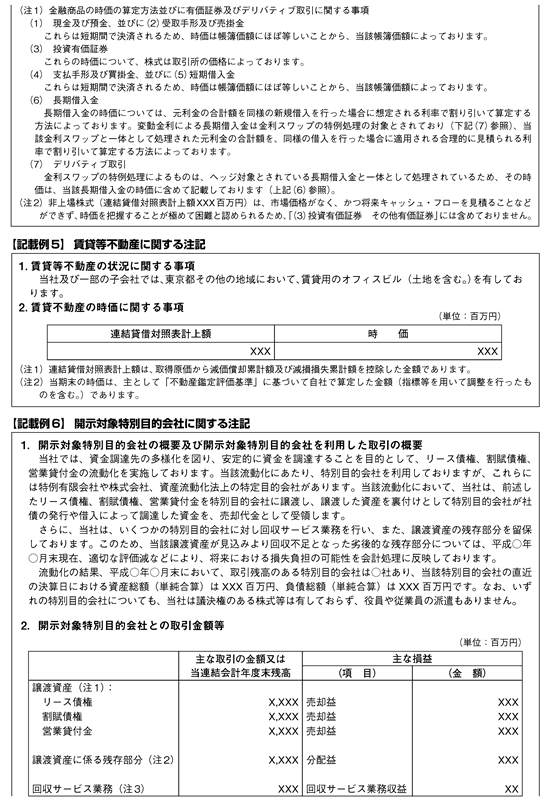
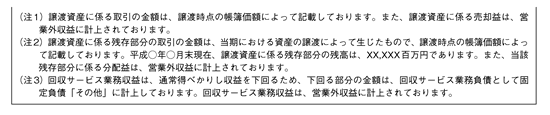 4.米国基準適用会社の注意点
これまで、連結財務諸表規則(旧連結財務諸表規則93条~96条)において米国基準によって連結財務諸表を作成することが許容されている株式会社について、会社法上の連結計算書類についても米国基準によって作成することが許容されていた(旧会社計算規則120条1項)。
4.米国基準適用会社の注意点
これまで、連結財務諸表規則(旧連結財務諸表規則93条~96条)において米国基準によって連結財務諸表を作成することが許容されている株式会社について、会社法上の連結計算書類についても米国基準によって作成することが許容されていた(旧会社計算規則120条1項)。平成21年12月11日の平成21年内閣府令第73号による改正後の連結財務諸表規則において、平成22年3月期以降の連結財務諸表をIFRSによって作成することが許容されたことに伴い、連結財務諸表規則から米国基準適用会社に関する条項が削除され、現在、米国基準を適用している会社については、附則において、平成28年3月31日までに終了する連結会計年度に係るものまで引き続き米国基準の適用を認める経過措置が置かれた。
これを踏まえ、平成21年12月11日の平成21年法務省令第46号によって会社計算規則の一部が改正された。本省令附則3条において、連結計算書類についても、平成28年3月31日までに終了する連結会計年度に係るものまで引き続き米国基準の適用を認める経過措置が置かれた。
今般、注記事項に追加された賃貸等不動産に関する注記は、米国基準では記載が求められていなことから、米国基準適用会社においては、連結注記表に記載がなく、その結果として個別注記表における注記が求められる可能性がある(会社計算規則110条2項)。もっとも、平成21年12月に公表された連結財務諸表ガイドラインの附則において、米国式連結財務諸表を提出する場合、賃貸等不動産の総額に重要性があるときは注記する(「主要な相違点」として記載することができる。)こととされていることに留意する必要がある。
5.適用関係 計算書類に関するひな型については、書類や項目ごとに適用時期が異なることがあるため、注意が必要である。具体的には各項目における「記載上の注意」を参照されたい。
なお、「金融商品に関する注記」及び「賃貸等不動産に関する注記」は、原則として、2010(平成22)年3月31日前に終了する事業年度に係る計算関係書類については適用されないが、早期適用することは可能である点に特に注意されたい(会社法施行規則、会社計算規則等の一部を改正する省令(平成21年法務省令第7号)附則8条3項)。
脚注
1 小松岳志=澁谷亮「事業報告の内容に関する規律の全体像」商事法務1863号(2009)10頁以下。
2 前掲(注1)19頁。
3 前掲(注1)14頁。
4 大野晃宏=小松岳志=澁谷亮=黒田裕=和久友子「会社法施行規則、会社計算規則等の一部を改正する省令の解説―平成21年法務省令第7号―」商事法務1862号(2009)19頁。
5 前掲(注4)20頁。
6 前掲(注4)16頁。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -

Copyright (C) 2019
SHINNIPPON-HOKI PUBLISHING CO.,LTD.





















