コラム2010年03月01日 【SCOPE】 DESを行う場合の税務上の時価評価の方法が明らかに(2010年3月1日号・№344)
合理的な見積り回収可能額に基づく評価が妥当
DESを行う場合の税務上の時価評価の方法が明らかに
デットエクイティスワップ(DES)の税務上の評価方法が明確化されたことで、今後は、DESの利用も増えることになりそうだ。国税庁が2月22日に、「企業再生税制適用場面においてDESが行われた場合の債権等の評価に係る税務上の取扱いについて」と題する経済産業省からの事前照会に対する文書回答を公表したからである。今回の事前照会は、もともと経済産業省の産業再生課長の私的研究会である「事業再生に係るDES研究会」が1月14日に公表した「事業再生に係るDES(Debt Equity Swap:債務の株式化)研究会報告書」をもとに行われたものである(本誌339号参照)。
報告書では、企業再生税制の適用場面におけるDESの対象となる債権の税務上の評価を行う場合について、①再生企業の合理的に見積もられた回収可能額の算定し、②それを基に留保される債権とDESの対象となる債権に分け、③DESの対象となる債権の時価を決めるとしている。また、債権者がDESにより取得する株式については、DESの対象となる債権の時価を用いて評価するとしており、国税庁の見解もこれを認めるものとなっている。
DESの対象となる債権の時価とは? DESに関しては、平成18年度および21年度の税制改正で措置が講じられている。しかし、経済産業省は、DESを行う場合税務上の時価評価の具体的な方法が不明確であるため、まだ、DESが利用しにくい環境にあると指摘している。
このため、同省では、「事業再生に係るDES研究会」を設置し、前述の報告書を取りまとめた。今回の事前照会は、この報告書を踏まえたものとなっている。
企業再生税制適用場面における債務者の取扱いをみると(参考参照)、企業再生を行う際には、一般に公表された債務処理を行うための手続についての準則に従い合理的な再建計画が策定されることとなり、その策定過程において資産評定基準に基づき資産および負債ごとに評価が行われ実態貸借対照表が作成されることになる。次に、実態貸借対照表の債務超過金額をベースに債権者調整が行われ、事業再生計画における損益見込み等を考慮し、債務者および債権者双方の合意のもとで回収可能額が算定されることになる。
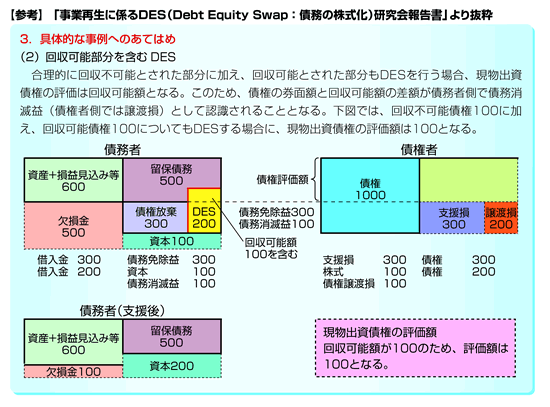 債務免除が行われる場合には、この合理的に見積もられた回収可能額に基づき債務免除額が決定されることとなる。つまり、合理的な再建計画においては、債権のうちこの回収可能額を超える部分(回収不能と見込まれる部分)の金額が債務免除額となる。この場合、債務者は、この債務免除額につき、債務免除益を計上することになる。
債務免除が行われる場合には、この合理的に見積もられた回収可能額に基づき債務免除額が決定されることとなる。つまり、合理的な再建計画においては、債権のうちこの回収可能額を超える部分(回収不能と見込まれる部分)の金額が債務免除額となる。この場合、債務者は、この債務免除額につき、債務免除益を計上することになる。
また、DESが行われた場合でも、債務免除が行われる場合と同様に実態貸借対照表の債務超過金額をベースに債権者調整が行われ、事業再生計画における損益見込み等を考慮し、債務者および債権者双方の合意のもとで回収可能額が算定されることになり、この合理的に見積もられた回収可能額に基づいて実質的な債務免除額が決定される。つまり、合理的な再建計画においては、債権のうちこの回収可能額を超える部分(回収不能と見込まれる部分)についてはDESの対価である株式の交付の対象とならず、回収可能額に相当する部分に限って、株式の交付の対象となる。このため、DESの対象となる債権の時価については、合理的に見積もられた回収可能額に基づいて評価することが妥当となる。
この場合、債務者は、債権金額(額面)と債権の時価との差額について、債務消滅益を計上することになる。
これらにより算定された現物出資債権の時価が、被現物出資法人が給付を受けた金銭以外の資産の価額(DESにより増加する資本金等の額)となる。
現物出資債権の時価は被現物出資債権の評価額と一致 一方、DESにより新たに株主となる債権者の場合(参考参照)については、債権者が保有する金銭以外の資産である債権を現物出資し、その対価として株式の交付を受けるものであるため、現物出資債権の時価(現物出資により給付をした金銭以外の資産の価額の合計額)が、交付を受ける株式の取得価額となる。この場合の現物出資債権の時価は、債務者および債権者の双方が合理的な再建計画に合意する立場にあるため、合意した回収可能額に基づき評価されることが合理的であり、かつ、債務者における処理とも整合的である。このため、前述の被現物出資債権の評価額と一致させることが合理的となる。
この結果、前述の債務者が給付を受けた金銭以外の資産の価額が、現物出資により給付をした金銭以外の資産の価額(DESにより交付を受ける株式の取得価額)となり、債権の帳簿価額からDESにより交付を受ける株式の取得価額(取得費用を含む)を控除した金額が債権者における債権の譲渡損の額となる。
DESを行う場合の税務上の時価評価の方法が明らかに
デットエクイティスワップ(DES)の税務上の評価方法が明確化されたことで、今後は、DESの利用も増えることになりそうだ。国税庁が2月22日に、「企業再生税制適用場面においてDESが行われた場合の債権等の評価に係る税務上の取扱いについて」と題する経済産業省からの事前照会に対する文書回答を公表したからである。今回の事前照会は、もともと経済産業省の産業再生課長の私的研究会である「事業再生に係るDES研究会」が1月14日に公表した「事業再生に係るDES(Debt Equity Swap:債務の株式化)研究会報告書」をもとに行われたものである(本誌339号参照)。
報告書では、企業再生税制の適用場面におけるDESの対象となる債権の税務上の評価を行う場合について、①再生企業の合理的に見積もられた回収可能額の算定し、②それを基に留保される債権とDESの対象となる債権に分け、③DESの対象となる債権の時価を決めるとしている。また、債権者がDESにより取得する株式については、DESの対象となる債権の時価を用いて評価するとしており、国税庁の見解もこれを認めるものとなっている。
DESの対象となる債権の時価とは? DESに関しては、平成18年度および21年度の税制改正で措置が講じられている。しかし、経済産業省は、DESを行う場合税務上の時価評価の具体的な方法が不明確であるため、まだ、DESが利用しにくい環境にあると指摘している。
このため、同省では、「事業再生に係るDES研究会」を設置し、前述の報告書を取りまとめた。今回の事前照会は、この報告書を踏まえたものとなっている。
企業再生税制適用場面における債務者の取扱いをみると(参考参照)、企業再生を行う際には、一般に公表された債務処理を行うための手続についての準則に従い合理的な再建計画が策定されることとなり、その策定過程において資産評定基準に基づき資産および負債ごとに評価が行われ実態貸借対照表が作成されることになる。次に、実態貸借対照表の債務超過金額をベースに債権者調整が行われ、事業再生計画における損益見込み等を考慮し、債務者および債権者双方の合意のもとで回収可能額が算定されることになる。
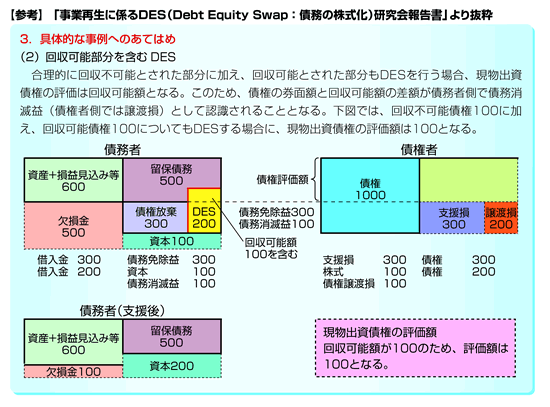 債務免除が行われる場合には、この合理的に見積もられた回収可能額に基づき債務免除額が決定されることとなる。つまり、合理的な再建計画においては、債権のうちこの回収可能額を超える部分(回収不能と見込まれる部分)の金額が債務免除額となる。この場合、債務者は、この債務免除額につき、債務免除益を計上することになる。
債務免除が行われる場合には、この合理的に見積もられた回収可能額に基づき債務免除額が決定されることとなる。つまり、合理的な再建計画においては、債権のうちこの回収可能額を超える部分(回収不能と見込まれる部分)の金額が債務免除額となる。この場合、債務者は、この債務免除額につき、債務免除益を計上することになる。また、DESが行われた場合でも、債務免除が行われる場合と同様に実態貸借対照表の債務超過金額をベースに債権者調整が行われ、事業再生計画における損益見込み等を考慮し、債務者および債権者双方の合意のもとで回収可能額が算定されることになり、この合理的に見積もられた回収可能額に基づいて実質的な債務免除額が決定される。つまり、合理的な再建計画においては、債権のうちこの回収可能額を超える部分(回収不能と見込まれる部分)についてはDESの対価である株式の交付の対象とならず、回収可能額に相当する部分に限って、株式の交付の対象となる。このため、DESの対象となる債権の時価については、合理的に見積もられた回収可能額に基づいて評価することが妥当となる。
この場合、債務者は、債権金額(額面)と債権の時価との差額について、債務消滅益を計上することになる。
これらにより算定された現物出資債権の時価が、被現物出資法人が給付を受けた金銭以外の資産の価額(DESにより増加する資本金等の額)となる。
現物出資債権の時価は被現物出資債権の評価額と一致 一方、DESにより新たに株主となる債権者の場合(参考参照)については、債権者が保有する金銭以外の資産である債権を現物出資し、その対価として株式の交付を受けるものであるため、現物出資債権の時価(現物出資により給付をした金銭以外の資産の価額の合計額)が、交付を受ける株式の取得価額となる。この場合の現物出資債権の時価は、債務者および債権者の双方が合理的な再建計画に合意する立場にあるため、合意した回収可能額に基づき評価されることが合理的であり、かつ、債務者における処理とも整合的である。このため、前述の被現物出資債権の評価額と一致させることが合理的となる。
この結果、前述の債務者が給付を受けた金銭以外の資産の価額が、現物出資により給付をした金銭以外の資産の価額(DESにより交付を受ける株式の取得価額)となり、債権の帳簿価額からDESにより交付を受ける株式の取得価額(取得費用を含む)を控除した金額が債権者における債権の譲渡損の額となる。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -

Copyright (C) 2019
SHINNIPPON-HOKI PUBLISHING CO.,LTD.





















