解説記事2010年03月15日 【制度解説】 事業再生に係るDESの税務上の評価方法(2010年3月15日号・№346)
実務解説
事業再生に係るDESの税務上の評価方法
経済産業省経済産業政策局産業再生課課長補佐 藤井敏央
Ⅰ.はじめに
近年、資源価格の高騰と、サブプライムローン問題を端緒とした金融危機から始まった世界同時不況の影響により、債務者企業を取り巻く環境は引き続き厳しい状況である。この厳しい環境の中、債務者企業は、景気の悪化と資金市場の切迫により、過剰債務となる状況は増え、その結果、デットエクイティスワップ(Debt Equity Swap.以下「DES」という)を利用するニーズも増加すると想定される。
DESは、平成18年度税制改正において、DESを実施した債務者に係る資本金等の額は債権を適格現物出資した場合を除き時価評価によることとされ、税務上の時価評価の問題が生じるようになった。
一方、DESに伴い生じた債務消滅益については、債務免除益と同様、期限切欠損金を青色欠損金に優先して相殺可能とする措置がなされた。また、平成21年度税制改正においては、企業再生税制の適用の条件の1つである「2以上の金融機関等の債務の免除」にDESを加えることで、DESを利用しやすい環境が整備されてきた。
しかし、このような制度改正は行われてきたものの、DESを行う場合の税務上の時価評価の具体的な方法が不明のままであったため、DESの活用に支障があるといわれていた。
これを受け、経済産業省において、平成21年8月5日及び12月3日に、経済産業政策局産業再生課長の私的研究会として「事業再生に係るDES研究会」を開催した。研究会では、DESの実態・実務に詳しい有識者、オブザーバーとして中小企業支援全国本部、事業再生実務家協会(事業再生ADRの認定事業者)、整理回収機構、全国銀行協会に参加いただき、DESの税務上の評価方法についてご議論いただいた。その結果、平成22年1月に「事業再生に係るDES研究会報告書」を公表した。
さらに、当該報告書の内容について国税庁に文書照会を行い、平成22年2月22日に「御照会に係る事実関係を前提とする限り、貴見のとおりで差し支えありません。」との回答を得たところである。
以下では、「事業再生に係るDES研究会報告書」の内容を中心に説明する。
Ⅱ.DESの概要と債権放棄に比した優位性
1.DESの定義 DESとは、債権者側からは、債権者が債務者に対して有する債権を債務者が発行する株式に振り替えること、債務者側からは、債権者に対する債務を資本金に振り替えることをいう。
2.DESの債権放棄に対する優位性 冒頭で述べたとおり、景気の悪化と資金市場の切迫により、倒産に至る過剰債務企業が増加している。この過剰債務に対する金融支援の方法として、債権放棄とDESが存在している。
DESを行うことは、議決権がある場合、債権放棄に比べて、再建を行う債務者企業及び債権者である金融機関等に次のようなメリットが存在しており、債権放棄に比して優位性がある。
まず、再建する債務者企業にとってDESは、単なる債権放棄と比べ、過去の債権者に株主として企業経営に参画してもらいつつ、取引関係の維持を図ることができるメリットがある。
一方、債権者にとっては、債権放棄と異なり、将来、債務者企業が実際に再生した場合、保有株式からキャピタルゲイン及びインカムゲインを得ることができるメリットがある。また、議決権がある場合は、経営に関与することも可能となり、モラルハザードを防ぐ効果がある。
しかし、このような優位性があるにもかかわらず、DESの税務上の評価方法が不明確である等の理由に加え、一時的な景気の回復も相俟って、DESの利用は減少していた。
Ⅲ.過去の企業再生税制改正の経緯
平成17年度企業再生税制の創設、その後のDESに関連した企業再生税制の改正の内容は、次のとおりである。
1.平成17年度企業再生税制の創設 迅速な企業再生を促進する観点から、民事再生法等の法的整理に加え、一定の要件を満たす私的整理において債務免除が行われた際、評価損の損金算入及び期限切れ欠損金の優先利用を認めることにより、債務免除益への課税回避を可能とした(図表1参照)。
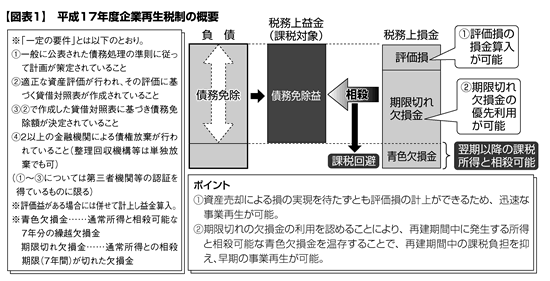
2.平成18年度企業再生税制の改正 DESにおいてその債務の消滅に係る利益が生じる場合、債権としての回収を放棄するという意味において実質的には債務免除と同質のものと考えられる。
このため、平成18年度税制改正において、①債務者側においてDESに係る債務消滅益を認識し、課税されることが一般的になった。
また同時に、②平成17年度に創設された再生税制の枠組みに、DESの債務消滅益も含まれることとなり、評価損(評価益を相殺後)や期限切れ欠損金により相殺が可能となった(法人税法59条2項1号)(図表2参照)。
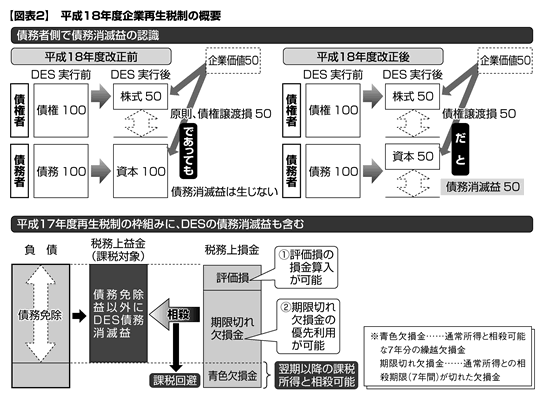 3.平成21年度企業再生税制の改正
企業再生税制の適用要件である「2以上の金融機関等による債権放棄」にDESを加え、「2以上の金融機関等による債権放棄・DES」に拡大した(図表3参照)。
3.平成21年度企業再生税制の改正
企業再生税制の適用要件である「2以上の金融機関等による債権放棄」にDESを加え、「2以上の金融機関等による債権放棄・DES」に拡大した(図表3参照)。
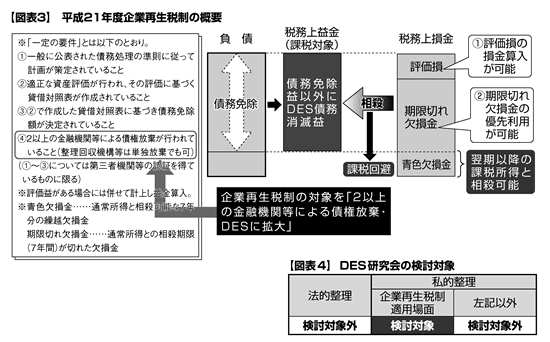 4.平成21年度改正後に残った問題点
平成21年度の改正後に残る問題点としては、DESを行う場合に現物出資される債権の時価評価の方法が明確でないこと等が挙げられている。
4.平成21年度改正後に残った問題点
平成21年度の改正後に残る問題点としては、DESを行う場合に現物出資される債権の時価評価の方法が明確でないこと等が挙げられている。
そこで、本研究会において、DESの実務に精通する実務家・専門家により、この点に関して検討していただくこととした。
Ⅳ.事業再生に係るDES研究会における検討範囲
DESは、再生局面以外で行われることも想定され、また再生局面においても、多様な再生手法が存在する。このため、本研究会において、これら全般におけるDESの対象債権の時価評価の方法を検討することも考えられる。
しかしながら、一般的にDESは再生局面で実施されることが実務上多く、また、再生局面の中でも企業再生税制の適用対象となる一定の私的整理(法人税法施行令24条の2第1項の要件を満たすもの)におけるDESは、合理的な再建計画に基づいて行われており、実務構築はこのような場面から検討していくことが望ましいと考えられる。
このため、本研究会では、企業再生税制の適用対象となる場面において、DESの対象となる債権の税務上の時価評価の方法を検討することとした。ここで一定の私的整理とは、民事再生法等の法的整理に準じた私的整理のことをいい、主要なものは次のとおりである。
●「私的整理に関するガイドライン及び同Q&Aに基づき策定された再建計画」
●「『中小企業再生支援協議会の支援による再生計画の策定手順(再生計画検討委員会が再生計画案の調査・報告を行う場合)』に従って策定された再生計画」
●「『RCC企業再生スキーム』に基づき策定された再生計画」
●「事業再生ADRの手続による再生計画」
●「企業再生支援機構の支援による再生計画」(同機構は平成21年10月設立)
本研究会の検討対象外とされている場面については、本研究会の検討結果を踏まえた企業再生税制の適用対象となる一定の私的整理の今後の実務の成熟度合いを踏まえ、必要に応じて検討することとした(以上について、図表4参照)。
Ⅴ.DESの税務上の評価方法
1.概 略 企業再生税制の適用場面におけるDESの対象となる債権の税務上の評価を行う場合、(1)再生企業の合理的に見積られた回収可能額を算定し、(2)これを基に留保される債権とDESの対象となる債権に分け、(3)DESの対象となる債権の時価を決めることになる。
なお、債権者がDESにより取得する株式は、DESの対象となる債権の時価を用いて評価することになる。
それぞれに関する本研究会の検討結果は、次のとおりである。
2.現物出資債権の評価方法の検討
(1)再生企業の合理的に見積られた回収可能額 企業再生税制が適用されるような再生の実務では、実務上、債権者会議の開催に先立ち、資産評定基準に基づき、各資産項目及び各負債項目ごとに評価を行い、実態貸借対照表が作成される。そして、この実態貸借対照表の債務超過金額をベースに債権者調整が行われ、事業再生計画における損益の見込み等を考慮して債務免除額が決定される。
このように、再生企業・債権者双方の合意のもと、再生企業の合理的に見積られた回収可能額に基づいて債務免除額が決定されることとなる。
なお、この実務を踏まえて、法人税法施行令24条の2第1項では、企業再生税制の適用場面における債務免除額の算定方法として、①資産評定基準に従って資産評定が行われ、その評定による価額を基礎とした再生企業の貸借対照表が作成されていること(同項第2号)、②前号の貸借対照表における資産及び負債の額、債務処理に関する計画における損益の見込み等に基づいて債務免除等をする金額が定められていること(同項第3号)が規定されている。
(2)DESの対象となる債権の時価 企業再生税制の適用される案件で、DESが行われる場合においても、再生企業からの回収可能額は、債務免除のみを行う場合と同様に算定される。
このことから、再生企業が受け入れたDESの対象となる債権の時価は、合理的に見積られた再生企業からの回収可能額に基づき評価することとなる(脚注1)。
このような場合において、再生企業からの回収可能額の算定は、前述(1)①に従い作成した実態貸借対照表の債務超過金額に(1)②の損益の見込み等を考慮して算定されることとなる。
(3)DESに伴い交付された株式の税務上の評価 金銭以外の資産の給付により取得した有価証券の取得価額は、法人税法施行令119条1項2号において、給付をした金銭以外の資産の価額の合計額とされている。
この点、DESは、債権者が保有する金銭以外の資産である債権を現物出資し、その対価として株式の交付を受けるものであるため、交付を受ける株式の取得価額は、現物出資をする債権の時価によることとなる。
この場合における現物出資債権の時価は、企業再生税制の適用場面においては、再生企業、債権者双方が合意をした回収可能額に基づき評価をすることが合理的であり、かつ、再生企業の処理とも整合的である(脚注2)。このため、DESに伴い交付された株式の税務上の評価額は、前述(2)により算定されるDESの対象となる債権の時価となる。
3.具体的な事例へのあてはめ
(1)回収不可能部分のDES 合理的に回収不可能とされた部分について、DESを行う場合、現物出資債権の評価はゼロとなり、債権の券面額を債務者側の債務消滅益(債権者側では譲渡損)として認識することとなる。
図表5では、回収不可能債権(=実質債務超過部分)が400存在し、うち、300について債権放棄し、100をDESする場合、現物出資債権の評価額はゼロとなる。
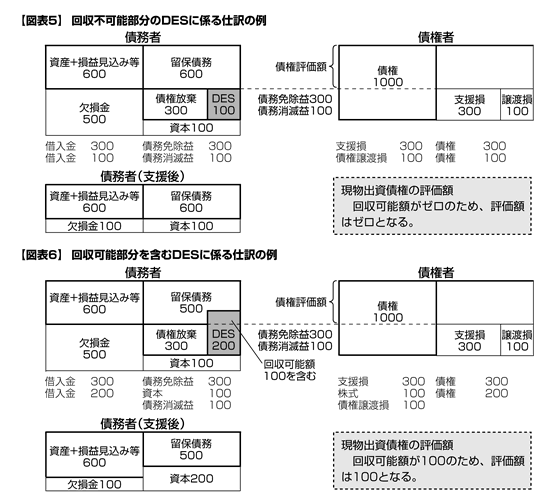 (2)回収可能部分を含むDES
合理的に回収不可能とされた部分に加え、回収可能とされた部分もDESを行う場合、現物出資債権の評価は回収可能額となる。このため、債権の券面額と回収可能額の差額が債務者側で債務消滅益(債権者側では譲渡損)として認識されることとなる。
(2)回収可能部分を含むDES
合理的に回収不可能とされた部分に加え、回収可能とされた部分もDESを行う場合、現物出資債権の評価は回収可能額となる。このため、債権の券面額と回収可能額の差額が債務者側で債務消滅益(債権者側では譲渡損)として認識されることとなる。
図表6では、回収不可能債権100に加え、回収可能債権100についてもDESする場合に、現物出資債権の評価額は100となる。
(3)種類株式の評価 DESの際には、一定期間内に一定金額での償還請求権を債権者に付すなど、種類株式が発行されることも想定される。この場合であっても、当該種類株式の評価額は、上記の方法に則って行う。
つまり、一定期間経過後に再生企業が債権者(=種類株式保有者)からの求めに応じて一定金額で株式の買取りを行う場合、種類株式の評価額は、償還条件の内容にかかわらず、前述2において合理的に算定された再生企業からの回収可能額を原資として償還できる金額とする。
図表7では、券面額200の債権を現物出資して、償還条件付きの種類株式の交付を受けた場合、当該償還条件の内容にかかわらず、交付を受けた種類株式の評価額は100となる。
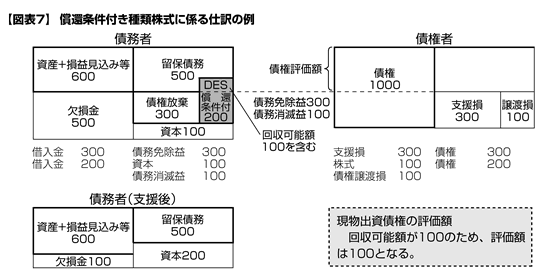 Ⅵ.おわりに
Ⅵ.おわりに
本研究会報告書は、再生局面の中でも企業再生税制の適用対象となる一定の私的整理(法人税法施行令24条の2第1項の要件を満たすもの)におけるDESについて、再生企業の合理的に見積られた回収可能額を基礎に、現物出資債権の評価とDESに伴い交付された株式の税務上の評価を検討したものである。
特に、償還条件付株式の評価についてあえて言及を行ったのは、再生実務の中で、多くの場合、DESにより種類株式を発行しているからである。また、ここで合理的な再建計画であったとしても、事業計画の上ブレ期待により回収する部分や、債務処理に関する計画における損益の見込み等の期間を超える期間で回収する部分は回収不能と判断される可能性があるため、注意が必要である。
また、当該報告書の内容に係る文書照会の結果は、Ⅰに述べたとおりである。
最後に、本研究会で検討したDESの税務上の評価方法が、企業再生実務に活用され、今後の企業再生が健全に発展することを期待したい。
脚注
1 DESの対象となる債権又は再生企業が交付する株式に取引価額がある場合
DESを再生企業側からみた場合には、債権者から現物出資により債権を取得し、その取得の対価として株式を交付する取引ということになる。
ここで、取得をする債権について、相対での取引価額がある場合には、その価額により評価するという考え方もある。しかし、企業再生税制の適用場面において行われるこのような取引は、少数の特定取引であることが多く、そこで付される価額は客観的、かつ合理的な価額とは限らない。
一方で、取得をする資産を評価するにあたっては、交付する資産の価額により評価するという考え方もある。この点、交付する資産が株式である場合には、一般的に株式の価値は、その発行に際して払い込まれる資産(DESの場合は債権)を含めた会社財産の実体価値であるため、上場企業における株式市場での株価や非上場会社での客観的な相対価格が存在する場合を除けば、その株式の価値をもって取得する資産を評価することは問題があると考える。
また、上場企業における株式市場での株価や非上場会社での客観的な相対価格が存在する場合においても、これらの価格には、債権の回収期間後の期待価値が含まれ、債権の評価と異なる価額となり、企業再生税制の適用場面における合理的な現物出資債権の評価として適切ではない。
さらに、再生企業の株価は、業績の回復の期待や倒産の噂等に左右されるほか、既存株主の責任としての減資や株式併合が適切に行われない場合、再生企業における株主持分を正確に表さない結果となることも考えられる。
以上のことから、企業再生税制の適用場面におけるDESの対象となる債権の評価は、上記の方法に比べて、再生企業の合理的に見積られた回収可能額に基づき評価することが合理的である。
2 DESにより現物出資をする債権又は再生企業から交付を受ける株式に取引価額がある場合についても、脚注1と同様のことがいえるため、企業再生税制の適用場面におけるDESの対象となる債権及び交付を受ける株式の評価は、再生企業の合理的に見積られた回収可能額に基づき評価することが適当である。
事業再生に係るDESの税務上の評価方法
経済産業省経済産業政策局産業再生課課長補佐 藤井敏央
Ⅰ.はじめに
近年、資源価格の高騰と、サブプライムローン問題を端緒とした金融危機から始まった世界同時不況の影響により、債務者企業を取り巻く環境は引き続き厳しい状況である。この厳しい環境の中、債務者企業は、景気の悪化と資金市場の切迫により、過剰債務となる状況は増え、その結果、デットエクイティスワップ(Debt Equity Swap.以下「DES」という)を利用するニーズも増加すると想定される。
DESは、平成18年度税制改正において、DESを実施した債務者に係る資本金等の額は債権を適格現物出資した場合を除き時価評価によることとされ、税務上の時価評価の問題が生じるようになった。
一方、DESに伴い生じた債務消滅益については、債務免除益と同様、期限切欠損金を青色欠損金に優先して相殺可能とする措置がなされた。また、平成21年度税制改正においては、企業再生税制の適用の条件の1つである「2以上の金融機関等の債務の免除」にDESを加えることで、DESを利用しやすい環境が整備されてきた。
しかし、このような制度改正は行われてきたものの、DESを行う場合の税務上の時価評価の具体的な方法が不明のままであったため、DESの活用に支障があるといわれていた。
これを受け、経済産業省において、平成21年8月5日及び12月3日に、経済産業政策局産業再生課長の私的研究会として「事業再生に係るDES研究会」を開催した。研究会では、DESの実態・実務に詳しい有識者、オブザーバーとして中小企業支援全国本部、事業再生実務家協会(事業再生ADRの認定事業者)、整理回収機構、全国銀行協会に参加いただき、DESの税務上の評価方法についてご議論いただいた。その結果、平成22年1月に「事業再生に係るDES研究会報告書」を公表した。
さらに、当該報告書の内容について国税庁に文書照会を行い、平成22年2月22日に「御照会に係る事実関係を前提とする限り、貴見のとおりで差し支えありません。」との回答を得たところである。
以下では、「事業再生に係るDES研究会報告書」の内容を中心に説明する。
Ⅱ.DESの概要と債権放棄に比した優位性
1.DESの定義 DESとは、債権者側からは、債権者が債務者に対して有する債権を債務者が発行する株式に振り替えること、債務者側からは、債権者に対する債務を資本金に振り替えることをいう。
2.DESの債権放棄に対する優位性 冒頭で述べたとおり、景気の悪化と資金市場の切迫により、倒産に至る過剰債務企業が増加している。この過剰債務に対する金融支援の方法として、債権放棄とDESが存在している。
DESを行うことは、議決権がある場合、債権放棄に比べて、再建を行う債務者企業及び債権者である金融機関等に次のようなメリットが存在しており、債権放棄に比して優位性がある。
まず、再建する債務者企業にとってDESは、単なる債権放棄と比べ、過去の債権者に株主として企業経営に参画してもらいつつ、取引関係の維持を図ることができるメリットがある。
一方、債権者にとっては、債権放棄と異なり、将来、債務者企業が実際に再生した場合、保有株式からキャピタルゲイン及びインカムゲインを得ることができるメリットがある。また、議決権がある場合は、経営に関与することも可能となり、モラルハザードを防ぐ効果がある。
しかし、このような優位性があるにもかかわらず、DESの税務上の評価方法が不明確である等の理由に加え、一時的な景気の回復も相俟って、DESの利用は減少していた。
Ⅲ.過去の企業再生税制改正の経緯
平成17年度企業再生税制の創設、その後のDESに関連した企業再生税制の改正の内容は、次のとおりである。
1.平成17年度企業再生税制の創設 迅速な企業再生を促進する観点から、民事再生法等の法的整理に加え、一定の要件を満たす私的整理において債務免除が行われた際、評価損の損金算入及び期限切れ欠損金の優先利用を認めることにより、債務免除益への課税回避を可能とした(図表1参照)。
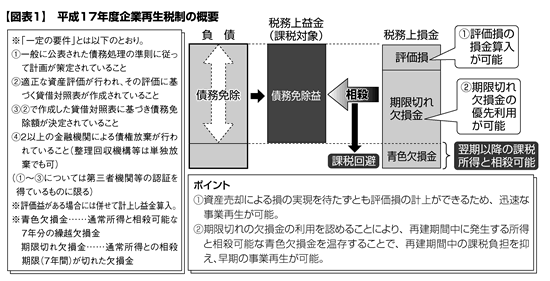
2.平成18年度企業再生税制の改正 DESにおいてその債務の消滅に係る利益が生じる場合、債権としての回収を放棄するという意味において実質的には債務免除と同質のものと考えられる。
このため、平成18年度税制改正において、①債務者側においてDESに係る債務消滅益を認識し、課税されることが一般的になった。
また同時に、②平成17年度に創設された再生税制の枠組みに、DESの債務消滅益も含まれることとなり、評価損(評価益を相殺後)や期限切れ欠損金により相殺が可能となった(法人税法59条2項1号)(図表2参照)。
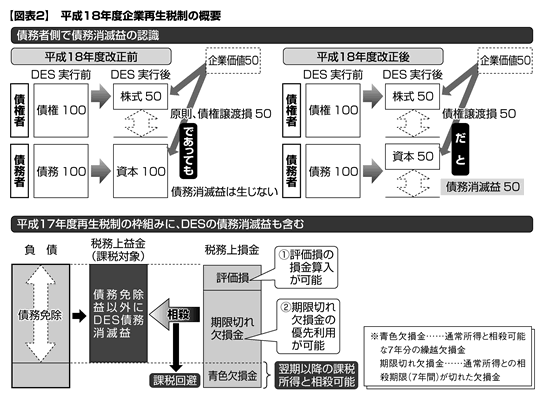 3.平成21年度企業再生税制の改正
企業再生税制の適用要件である「2以上の金融機関等による債権放棄」にDESを加え、「2以上の金融機関等による債権放棄・DES」に拡大した(図表3参照)。
3.平成21年度企業再生税制の改正
企業再生税制の適用要件である「2以上の金融機関等による債権放棄」にDESを加え、「2以上の金融機関等による債権放棄・DES」に拡大した(図表3参照)。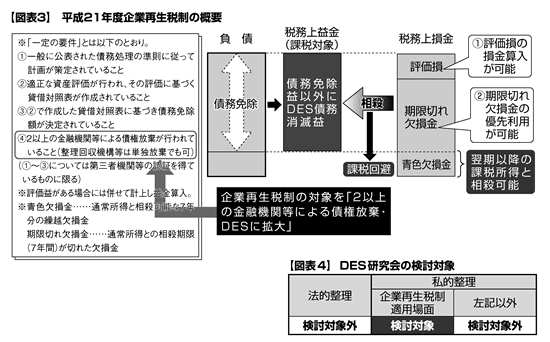 4.平成21年度改正後に残った問題点
平成21年度の改正後に残る問題点としては、DESを行う場合に現物出資される債権の時価評価の方法が明確でないこと等が挙げられている。
4.平成21年度改正後に残った問題点
平成21年度の改正後に残る問題点としては、DESを行う場合に現物出資される債権の時価評価の方法が明確でないこと等が挙げられている。そこで、本研究会において、DESの実務に精通する実務家・専門家により、この点に関して検討していただくこととした。
Ⅳ.事業再生に係るDES研究会における検討範囲
DESは、再生局面以外で行われることも想定され、また再生局面においても、多様な再生手法が存在する。このため、本研究会において、これら全般におけるDESの対象債権の時価評価の方法を検討することも考えられる。
しかしながら、一般的にDESは再生局面で実施されることが実務上多く、また、再生局面の中でも企業再生税制の適用対象となる一定の私的整理(法人税法施行令24条の2第1項の要件を満たすもの)におけるDESは、合理的な再建計画に基づいて行われており、実務構築はこのような場面から検討していくことが望ましいと考えられる。
このため、本研究会では、企業再生税制の適用対象となる場面において、DESの対象となる債権の税務上の時価評価の方法を検討することとした。ここで一定の私的整理とは、民事再生法等の法的整理に準じた私的整理のことをいい、主要なものは次のとおりである。
●「私的整理に関するガイドライン及び同Q&Aに基づき策定された再建計画」
●「『中小企業再生支援協議会の支援による再生計画の策定手順(再生計画検討委員会が再生計画案の調査・報告を行う場合)』に従って策定された再生計画」
●「『RCC企業再生スキーム』に基づき策定された再生計画」
●「事業再生ADRの手続による再生計画」
●「企業再生支援機構の支援による再生計画」(同機構は平成21年10月設立)
本研究会の検討対象外とされている場面については、本研究会の検討結果を踏まえた企業再生税制の適用対象となる一定の私的整理の今後の実務の成熟度合いを踏まえ、必要に応じて検討することとした(以上について、図表4参照)。
Ⅴ.DESの税務上の評価方法
1.概 略 企業再生税制の適用場面におけるDESの対象となる債権の税務上の評価を行う場合、(1)再生企業の合理的に見積られた回収可能額を算定し、(2)これを基に留保される債権とDESの対象となる債権に分け、(3)DESの対象となる債権の時価を決めることになる。
なお、債権者がDESにより取得する株式は、DESの対象となる債権の時価を用いて評価することになる。
それぞれに関する本研究会の検討結果は、次のとおりである。
2.現物出資債権の評価方法の検討
(1)再生企業の合理的に見積られた回収可能額 企業再生税制が適用されるような再生の実務では、実務上、債権者会議の開催に先立ち、資産評定基準に基づき、各資産項目及び各負債項目ごとに評価を行い、実態貸借対照表が作成される。そして、この実態貸借対照表の債務超過金額をベースに債権者調整が行われ、事業再生計画における損益の見込み等を考慮して債務免除額が決定される。
このように、再生企業・債権者双方の合意のもと、再生企業の合理的に見積られた回収可能額に基づいて債務免除額が決定されることとなる。
なお、この実務を踏まえて、法人税法施行令24条の2第1項では、企業再生税制の適用場面における債務免除額の算定方法として、①資産評定基準に従って資産評定が行われ、その評定による価額を基礎とした再生企業の貸借対照表が作成されていること(同項第2号)、②前号の貸借対照表における資産及び負債の額、債務処理に関する計画における損益の見込み等に基づいて債務免除等をする金額が定められていること(同項第3号)が規定されている。
(2)DESの対象となる債権の時価 企業再生税制の適用される案件で、DESが行われる場合においても、再生企業からの回収可能額は、債務免除のみを行う場合と同様に算定される。
このことから、再生企業が受け入れたDESの対象となる債権の時価は、合理的に見積られた再生企業からの回収可能額に基づき評価することとなる(脚注1)。
このような場合において、再生企業からの回収可能額の算定は、前述(1)①に従い作成した実態貸借対照表の債務超過金額に(1)②の損益の見込み等を考慮して算定されることとなる。
(3)DESに伴い交付された株式の税務上の評価 金銭以外の資産の給付により取得した有価証券の取得価額は、法人税法施行令119条1項2号において、給付をした金銭以外の資産の価額の合計額とされている。
この点、DESは、債権者が保有する金銭以外の資産である債権を現物出資し、その対価として株式の交付を受けるものであるため、交付を受ける株式の取得価額は、現物出資をする債権の時価によることとなる。
この場合における現物出資債権の時価は、企業再生税制の適用場面においては、再生企業、債権者双方が合意をした回収可能額に基づき評価をすることが合理的であり、かつ、再生企業の処理とも整合的である(脚注2)。このため、DESに伴い交付された株式の税務上の評価額は、前述(2)により算定されるDESの対象となる債権の時価となる。
3.具体的な事例へのあてはめ
(1)回収不可能部分のDES 合理的に回収不可能とされた部分について、DESを行う場合、現物出資債権の評価はゼロとなり、債権の券面額を債務者側の債務消滅益(債権者側では譲渡損)として認識することとなる。
図表5では、回収不可能債権(=実質債務超過部分)が400存在し、うち、300について債権放棄し、100をDESする場合、現物出資債権の評価額はゼロとなる。
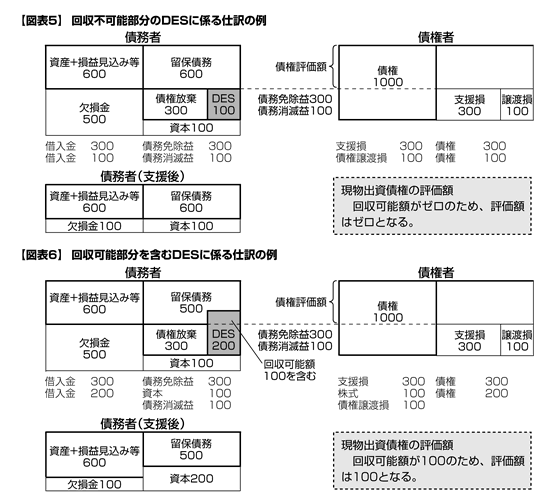 (2)回収可能部分を含むDES
合理的に回収不可能とされた部分に加え、回収可能とされた部分もDESを行う場合、現物出資債権の評価は回収可能額となる。このため、債権の券面額と回収可能額の差額が債務者側で債務消滅益(債権者側では譲渡損)として認識されることとなる。
(2)回収可能部分を含むDES
合理的に回収不可能とされた部分に加え、回収可能とされた部分もDESを行う場合、現物出資債権の評価は回収可能額となる。このため、債権の券面額と回収可能額の差額が債務者側で債務消滅益(債権者側では譲渡損)として認識されることとなる。図表6では、回収不可能債権100に加え、回収可能債権100についてもDESする場合に、現物出資債権の評価額は100となる。
(3)種類株式の評価 DESの際には、一定期間内に一定金額での償還請求権を債権者に付すなど、種類株式が発行されることも想定される。この場合であっても、当該種類株式の評価額は、上記の方法に則って行う。
つまり、一定期間経過後に再生企業が債権者(=種類株式保有者)からの求めに応じて一定金額で株式の買取りを行う場合、種類株式の評価額は、償還条件の内容にかかわらず、前述2において合理的に算定された再生企業からの回収可能額を原資として償還できる金額とする。
図表7では、券面額200の債権を現物出資して、償還条件付きの種類株式の交付を受けた場合、当該償還条件の内容にかかわらず、交付を受けた種類株式の評価額は100となる。
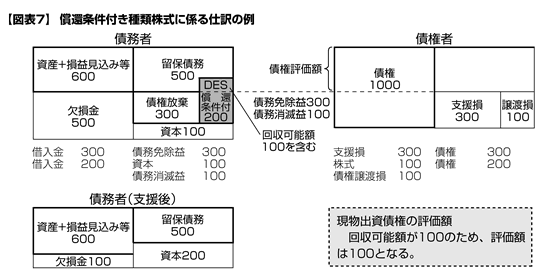 Ⅵ.おわりに
Ⅵ.おわりに
本研究会報告書は、再生局面の中でも企業再生税制の適用対象となる一定の私的整理(法人税法施行令24条の2第1項の要件を満たすもの)におけるDESについて、再生企業の合理的に見積られた回収可能額を基礎に、現物出資債権の評価とDESに伴い交付された株式の税務上の評価を検討したものである。
特に、償還条件付株式の評価についてあえて言及を行ったのは、再生実務の中で、多くの場合、DESにより種類株式を発行しているからである。また、ここで合理的な再建計画であったとしても、事業計画の上ブレ期待により回収する部分や、債務処理に関する計画における損益の見込み等の期間を超える期間で回収する部分は回収不能と判断される可能性があるため、注意が必要である。
また、当該報告書の内容に係る文書照会の結果は、Ⅰに述べたとおりである。
最後に、本研究会で検討したDESの税務上の評価方法が、企業再生実務に活用され、今後の企業再生が健全に発展することを期待したい。
脚注
1 DESの対象となる債権又は再生企業が交付する株式に取引価額がある場合
DESを再生企業側からみた場合には、債権者から現物出資により債権を取得し、その取得の対価として株式を交付する取引ということになる。
ここで、取得をする債権について、相対での取引価額がある場合には、その価額により評価するという考え方もある。しかし、企業再生税制の適用場面において行われるこのような取引は、少数の特定取引であることが多く、そこで付される価額は客観的、かつ合理的な価額とは限らない。
一方で、取得をする資産を評価するにあたっては、交付する資産の価額により評価するという考え方もある。この点、交付する資産が株式である場合には、一般的に株式の価値は、その発行に際して払い込まれる資産(DESの場合は債権)を含めた会社財産の実体価値であるため、上場企業における株式市場での株価や非上場会社での客観的な相対価格が存在する場合を除けば、その株式の価値をもって取得する資産を評価することは問題があると考える。
また、上場企業における株式市場での株価や非上場会社での客観的な相対価格が存在する場合においても、これらの価格には、債権の回収期間後の期待価値が含まれ、債権の評価と異なる価額となり、企業再生税制の適用場面における合理的な現物出資債権の評価として適切ではない。
さらに、再生企業の株価は、業績の回復の期待や倒産の噂等に左右されるほか、既存株主の責任としての減資や株式併合が適切に行われない場合、再生企業における株主持分を正確に表さない結果となることも考えられる。
以上のことから、企業再生税制の適用場面におけるDESの対象となる債権の評価は、上記の方法に比べて、再生企業の合理的に見積られた回収可能額に基づき評価することが合理的である。
2 DESにより現物出資をする債権又は再生企業から交付を受ける株式に取引価額がある場合についても、脚注1と同様のことがいえるため、企業再生税制の適用場面におけるDESの対象となる債権及び交付を受ける株式の評価は、再生企業の合理的に見積られた回収可能額に基づき評価することが適当である。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -

Copyright (C) 2019
SHINNIPPON-HOKI PUBLISHING CO.,LTD.





















