解説記事2010年03月15日 【実務解説】 新公益法人制度の税務上の論点(3・了)(2010年3月15日号・№346)
実務解説
新公益法人制度の税務上の論点(3・了)
公認会計士・税理士 長谷川敏也
Ⅴ.法人区分の移行に伴う課税問題
1.法人区分の移行に伴う累積所得金額の益金算入 公益法人等が普通法人(非営利型法人以外の法人)に移行する場合、課税所得の範囲に変更が生じ、収益事業課税から全所得課税となる。この場合には、原則として公益目的以外に特定の者に分配されないことを前提に非課税とされてきた所得の累積額について構成員に分配することも可能となる(脚注1)。
そこでこのような場合には、非課税とされていた前提が存在しなくなったことから、全所得課税が行われていたとしたならば課税されていたであろう部分についてこの時点で課税所得を構成するものとされた。
そのケースは表1の通りである。
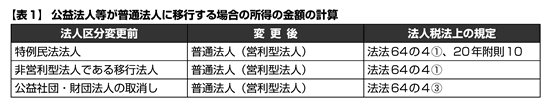 なお、表1の法人税法64条の4は、当面は、特例民法法人等が普通法人たる一般社団・財団法人へ移行する場合のことであるから、特例民法法人が非営利型法人へ移行する場合や、公益社団・財団法人へ移行する場合には課税範囲が変わらず、この累積所得金額についての課税問題は生じない。しかし、公益社団・財団法人の公益認定取消し(認定法29①②)や非営利型法人の否認によって営利型法人に移行する場合にも生じる課税リスクであるので、あらかじめ理解しておく必要がある。
なお、表1の法人税法64条の4は、当面は、特例民法法人等が普通法人たる一般社団・財団法人へ移行する場合のことであるから、特例民法法人が非営利型法人へ移行する場合や、公益社団・財団法人へ移行する場合には課税範囲が変わらず、この累積所得金額についての課税問題は生じない。しかし、公益社団・財団法人の公益認定取消し(認定法29①②)や非営利型法人の否認によって営利型法人に移行する場合にも生じる課税リスクであるので、あらかじめ理解しておく必要がある。
2.公益認定の取消しに伴う課税問題
(1)「公益目的取得財産残額」の贈与 公益法人は、公益認定基準に抵触した場合(認定法29②一)、公益法人が自ら一般社団・財団法人となるべく申請した場合(同条①四)や役員が認定法に規定されている罪で罰金刑に処せられた場合(同条①一)等に、公益認定の取消しがなされ、「公益目的取得財産残額」の贈与という事態が生じる。公益社団・財団法人に移行した後に公益認定が取り消され、公益目的取得財産の残額に相当する金額の贈与(認定法30)という事態を招いて、法人の財産を失ってしまう。
認定法上は、1ヶ月以内に公益目的取得財産残額を他の公益法人等に贈与すべきとし、取消しの日における金額の確定と報告の期限を3ヶ月以内としている(認定法規則50①)。なお、1ヶ月以内に贈与契約が成立していないときは国又は都道府県が公益目的取得財産残額に相当する額の金銭について認定取消法人から受贈されたとみなすことになっているので留意が必要である(認定法30①)。
(2)「公益目的取得財産残額」の範囲及び計算 したがって、「公益目的取得財産残額」の範囲及び計算については十分留意する必要がある。公益目的取得財産残額は、法人の意思と宣言によって確定するからである。
公益目的取得財産残額は、毎事業年度末における公益目的事業財産の未使用残高であり、公益目的保有財産と公益目的増減差額との合計額で、毎事業年度末、計算し行政庁に報告するものである(認定法30、認定法規則48)。
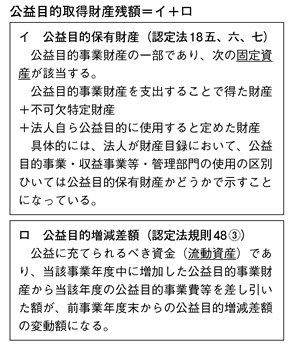 このイ及びロと、貸借対照表内訳表、並びに財産目録は密接な関係にあるが、正確には公益法人の事業報告書(定期提出書類)別表Hにて計算することになり、損益計算書(公益目的事業会計)から誘導的に算出されることとなる。
このイ及びロと、貸借対照表内訳表、並びに財産目録は密接な関係にあるが、正確には公益法人の事業報告書(定期提出書類)別表Hにて計算することになり、損益計算書(公益目的事業会計)から誘導的に算出されることとなる。
(3)公益法人が普通法人(営利型法人)に移行する場合の所得の金額の計算 公益社団・財団法人が行政庁から認定の取消しを受けたことにより非営利型法人以外の法人に該当することとなった場合には、当該取消しの日以降に公益目的のために支出されることが義務付けられている公益目的取得財産残額を累積所得金額から控除することとされている(法令131の5①一)。
もっとも、公益社団・財団法人に移行した後に公益認定が取り消された場合には、公益目的取得財産の残額の贈与(認定法30)が生じるので、控除するのは当然のことであり、公益三法上は債務であるので、法人税法上の簿価純資産額から単純に差し引く。なお、この贈与により生じた損失の額は損金に算入しない(法令131の5④)。寄附金損金不算入の特例(法法37⑦)の対象ともならない。
したがって、過去の収益事業以外の事業から生じた所得の累積額が大きい場合には、(1)の贈与に加えて、一時に多額の課税が生じることとなる(下記算式参照)。
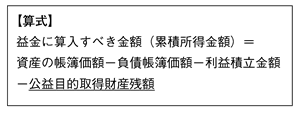
3.移行法人が営利型法人となる場合の取扱い(移行時点) 特例民法法人が普通法人に移行する場合及び、非営利型法人である移行法人(移行の認可を受けて移行の登記をした一般社団・財団法人のうち、公益目的支出計画の実施の完了の確認を受けていない法人)が営利型法人である移行法人(普通法人)となる場合の二つのケースでは、累積所得金額の計算に当たって、移行日における「修正公益目的財産残額」と「資産の帳簿価額から負債帳簿価額等を控除した金額」とのうちいずれか少ない金額(以下「当初調整公益目的財産残額」)を累積所得金額から控除し、累積所得金額から控除しきれないときは、その控除しきれない金額を累積欠損金額とみなすこととなる(法法64の4③、法令131の5①三・②)(表2参照)。
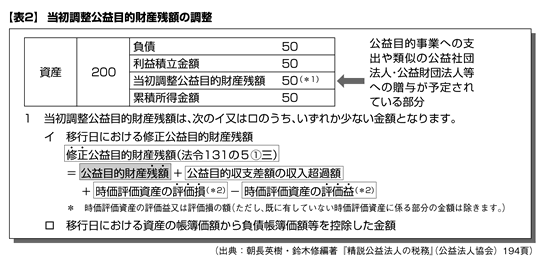
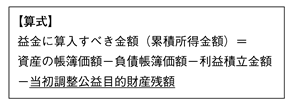 このうち「修正公益目的財産残額」は、整備法上の「公益目的財産残額」と公益目的収支差額の収入超過額の合計額に、時価評価資産の評価損の額を加算し、時価評価資産の評価益の額を控除した金額となる(法令131の5①三イ、法規27の16の4①)。
このうち「修正公益目的財産残額」は、整備法上の「公益目的財産残額」と公益目的収支差額の収入超過額の合計額に、時価評価資産の評価損の額を加算し、時価評価資産の評価益の額を控除した金額となる(法令131の5①三イ、法規27の16の4①)。
4.時価概念である公益目的財産額と当初調整公益目的財産残額 「公益目的財産額」とは、移行の登記をした日の前日(以下「算定日」)における貸借対照表の純資産の部に計上すべき額に、一定の調整(時価評価)をして得た額をいう(整備法施行規則14①)。
整備法上の「公益目的財産額」は時価概念であり、かつ純資産の部に保全が義務付けられている額、あるいは退職給付引当金の会計基準変更時差異も差し引く等の計算が認められている(脚注2)ので、法人税法上そのまま採用できる概念ではない。
法人税法上は法人税法上の簿価へ修正(元に戻す)して控除することとなるため「修正公益目的財産残額」という。したがって用語こそ類似しているが、公益社団・財団法人に移行した後に公益認定が取り消された場合の「公益目的取得財産残額」とは、計算の難易度も概念も異なる。
「当初調整公益目的財産残額」は、会計上認識される資産と負債の差額である整備法上の純資産を基礎として算出されるものの、課税対象となる「累積所得金額」は、税制上認識される資産と負債等の差額として算出されることから(法令131の4①)差異が生じる。このことは、法人区分の変更に際して十分留意する必要がある(下掲6・事例1参照)。
すなわち、公益法人会計基準では、たとえば賞与引当金、退職給付引当金、役員退職慰労引当金などは、通常の会計処理において負債として計上する(公益法人会計基準の運用指針12(1))が、法人税法上の負債には該当しない。このため、これら引当金は、「当初調整公益目的財産残額」の計算上は負債としてその減少項目となるが、累積所得金額の計算上は負債に該当せずその減少項目とはならないこととなる。
5.移行時点以降の各事業年度の課税 営利型法人である移行法人(普通法人)は全所得課税である。ところで3、4で述べた移行に伴う累積所得金額の課税を受けたので、移行後は普通法人と同じ課税方式で済むかというと、そうではない。
移行法人は、「公益目的財産額」がある場合には、公益目的財産額に相当する額を公益目的のために支出して零とするための「公益目的支出計画」を作成しなければならないこととされている(整備法119①)。
法人税法では、移行日の属する事業年度以後の各事業年度(公益目的支出計画の実施が完了したことの確認に係る事業年度後の事業年度を除く)の公益目的支出の額(実施事業に係る事業費の額、特定寄付の額及び実施事業に係る経常外費用の額の合計額)が実施事業収入の額(実施事業に係る収益の額と実施事業資産から生じた収益の額の合計額)を超えるときは、その超える部分の金額(「支出超過額」)を損金の額に算入しないこととされ(法令131の5⑤)、実施事業収入の額が公益目的支出を超えるときは、その超える部分の金額(「収入超過額」)を益金の額に算入しないこととされている(法令131の5⑥)(表3参照)。
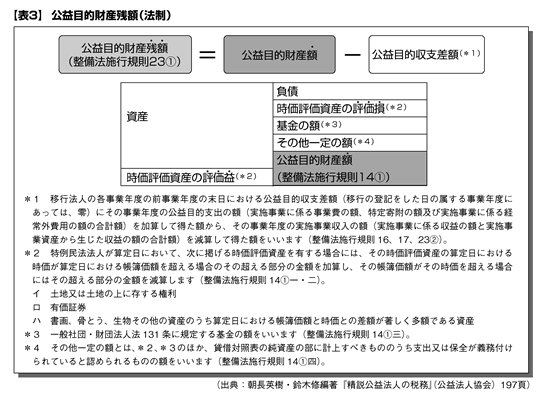 「調整公益目的財産残額」とは、3で計算した当初調整公益目的財産残額から、過年度の支出超過額の合計額を減算し、過年度の収入超過額の合計額を加算した金額(公益目的支出計画の実施が完了したことの確認に係る事業年度後の事業年度にあっては、ゼロ)とされている(法令131の5⑦)。
「調整公益目的財産残額」とは、3で計算した当初調整公益目的財産残額から、過年度の支出超過額の合計額を減算し、過年度の収入超過額の合計額を加算した金額(公益目的支出計画の実施が完了したことの確認に係る事業年度後の事業年度にあっては、ゼロ)とされている(法令131の5⑦)。
なぜ「支出超過額」を損金に算入できないのか。これは3、4で普通法人(全所得課税法人)に移行したときの累積所得金額の計算時に、「修正公益目的財産残額」を一括して控除(損金算入と同じ効果)しているためである。
「調整公益目的財産残額」がゼロになればその後の各事業年度においてこのような調整計算からは解放されるが、それまでの期間はこの法人税法上の「調整公益目的財産残額」を計算する必要があり、公益目的支出計画実施中の各事業年度では継続して申告書作成に留意が必要である。
6.事例 1 移行法人が普通法人に該当することとなった場合の累積所得金額の益金算入計算は、具体的には、別表十四(六)の「Ⅱ 移行法人が普通法人に該当することとなった場合等の累積所得金額又は累積欠損金額の益金又は損金算入等に関する明細書」にて当初調整公益目的財産残額の計算を行い、調整後の累積所得金額又は累積欠損金額の益金算入額又は損金算入額を記載することとなる。
簡単な計算を試みると次の通り(事例1参照)。
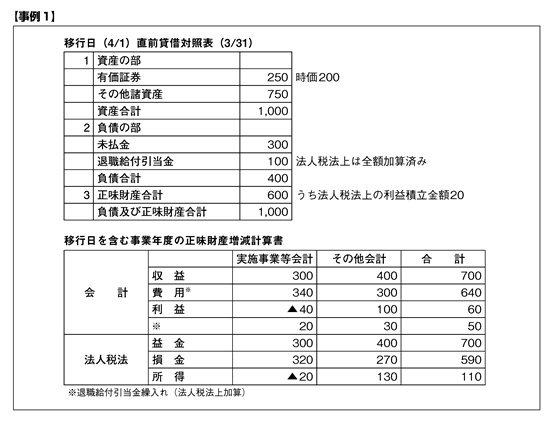 ① 公益目的財産残額(整備法上)
① 公益目的財産残額(整備法上)
資産1,000-会計上の負債400-含み損50=550
② 法人税法上の簿価純資産価額
資産1,000-(負債400-退職給付引当金100)-利益積立金額20=680
③ 修正公益目的財産残額(法人税法上)
公益目的財産残額(整備法上)550+含み損50=600
④ 累積所得金額
法人税法上の簿価純資産価額680-修正公益目的財産残額600=80
この金額80(結果的に退職給付引当金超過額-利益積立金額)が移行日の属する事業年度の益金に算入されることとなる。
⑤ 移行日を含む事業年度の損益
簡略化のため、その他会計(法人会計の費用配賦後)がすべて法人税法上の収益事業であるとすると、所得130に対して課税される。実施事業等会計の所得▲20については損金に算入されない(通算されない)。
法人税別表十四(六)の記載事例及び「記載の仕方」は31頁掲載の別表の通り。
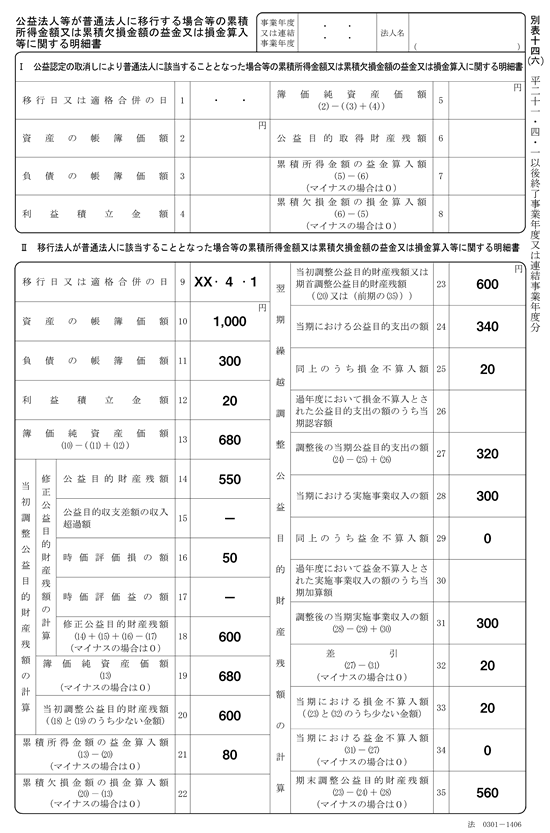 7.事例 2
公益目的財産残額には次の申告調整要因がある。
7.事例 2
公益目的財産残額には次の申告調整要因がある。
① 整備法上の「公益目的財産残額」は時価概念であり、法人税法上は法人税法上の簿価へ修正(元に戻す)して「修正公益目的財産残額」を算定していること
② しかし、その後は、法人税法上も整備法上の公益目的支出超過額を共通の減少額として期末調整公益目的財産残額を減少させていること
③ 整備法上の「公益目的支出計画の実施が完了したことの確認事業年度」を共通の指標とし、法人税法上の損金不算入規制を継続すること
以上から、含み損があれば法人税法上の調整公益目的財産残額が残り、含み益があれば公益目的支出計画完了前に調整公益目的財産残額がゼロになってしまう。
次の事例2(上記参照)は、含み損が大きいので、公益目的支出計画が1年目で完了する場合である。
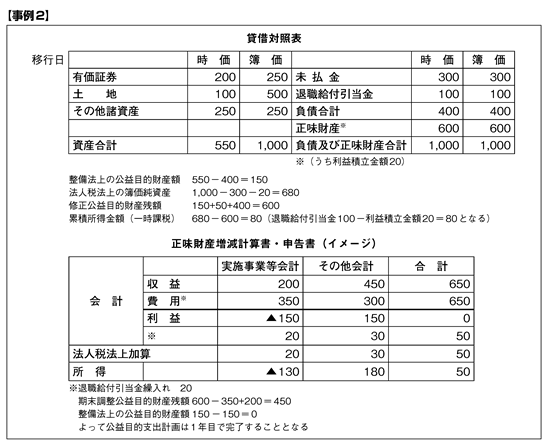 この場合の法人税別表十四(六)の記載事例及び「記載の仕方」は33、34頁掲載の別表の通り。
この場合の法人税別表十四(六)の記載事例及び「記載の仕方」は33、34頁掲載の別表の通り。
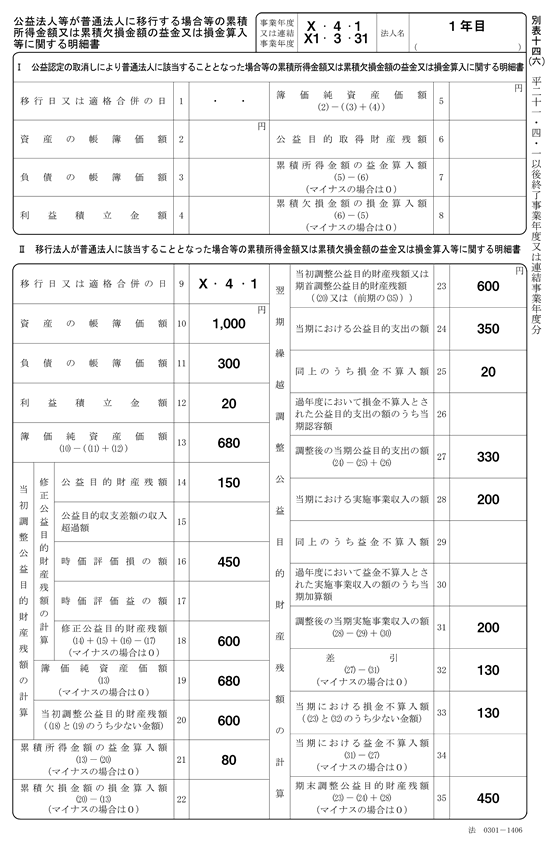
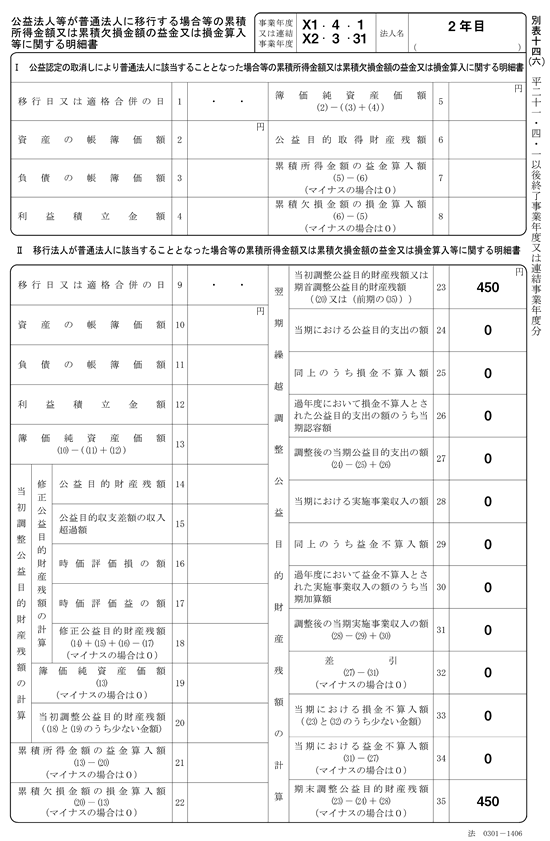 公益目的支出計画の実施期間(この事例では1年間)と法人税法上の調整公益目的財産残額がゼロになる期間(1年超)が異なる。スタートになる金額が相違することから、法人税法上の調整公益目的財産残額がゼロではないのに、公益目的支出計画の実施が完了してしまい、齟齬が生じている。
公益目的支出計画の実施期間(この事例では1年間)と法人税法上の調整公益目的財産残額がゼロになる期間(1年超)が異なる。スタートになる金額が相違することから、法人税法上の調整公益目的財産残額がゼロではないのに、公益目的支出計画の実施が完了してしまい、齟齬が生じている。
この場合、期末調整公益目的財産残額の記載(この事例では450)はいつまで、何のために続けるのだろうか。公益目的支出超過額(この事例では130)を損金の額に算入しない規制は、公益目的支出計画の実施が完了したことの確認事業年度以後は発生しない(法令131の5⑤)ので、2年目からは支出超過額は損金算入できる上に、確認後は行政庁の監督もなくなり、法人法に規定する一般社団・財団法人として存続するので、2年目以降の記載は不要と考える。
逆に含み益がある場合には、期末調整公益目的財産残額はゼロになっていたとしても、公益目的支出超過額を損金の額に算入しない規制(法令131の5⑤)は、公益目的支出計画の実施が完了したことの確認事業年度まで継続すると考えられる。
8.移行法人のみなし解散と清算 移行法人は、偽りその他不正の手段により移行認可を受けた場合には、その認可が取り消され、取消し処分の日が、移行期間満了日以後(特例民法法人の経過措置期間経過後)であると、みなし解散となる(整備法131④)。
みなし解散後清算法人となった場合には、公益目的財産残額があるときはその公益目的財産残額に相当する財産について認定法5条17号に規定するもの(他の公益法人等、国、地方公共団体等)に帰属させなければならない(整備法130)。
Ⅵ.公益目的支出計画と法人税課税
1.トレードオフ関係の危険性 一般社団・財団法人は、「公益目的財産額」がある場合には、公益目的財産額に相当する額を公益目的のために支出してゼロとするための「公益目的支出計画」を作成しなければならない(整備法119①)(図1参照)。整備法上公益目的支出計画を早期に完了させるために、移行法人は勢い実施事業等会計の赤字を拡大するために、法人会計に属する管理費をできるだけ実施事業等に配賦計算したり、金融資産運用益を法人会計に属させようとする。しかし、このことは結果として一時的に法人税課税を大きくする危険性がある。公益目的支出計画と法人税課税はトレードオフの関係となる場合があることに留意が必要である。
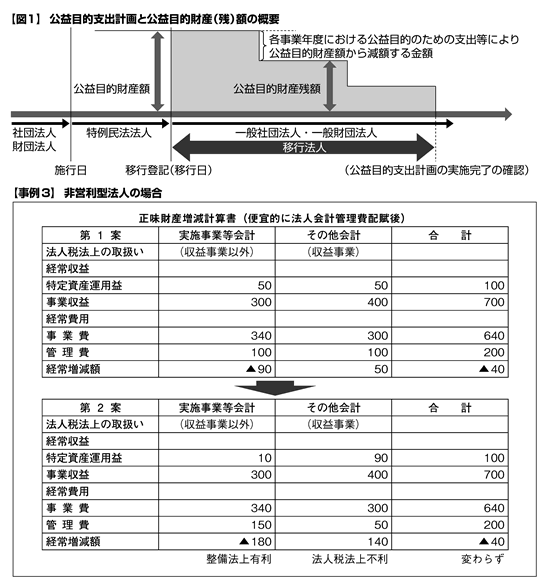
2.収益・費用の配分の留意点 非営利型の移行法人が、合理的な論理構成をして特定資産運用収益を実施事業等会計以外へ、管理費を実施事業等会計へ移したとすると次のように計算できる(事例3参照)。簡略化のために、その他会計を法人税法上、収益事業とすると、実施事業等会計の赤字が増えて公益目的支出計画の実施期間が短縮される(整備法上有利)が、法人税課税が増える(法人税法上不利)結果となる。もっとも法人税法上の収益事業か否かと、整備法上の実施事業会計、その他会計の区分は整合的である必要はないので、すべてトレードオフの関係となる訳ではない。
公益目的支出計画の実施期間に制限はないので、充分にシミュレーションをすべきである。
営利型法人の場合には全所得課税でありながら、実施事業等会計の公益目的支出計画支出超過額は損金不算入(法令131の5⑤)であるので、やはり一時的には法人税法上不利となる。
なお、有価証券等の運用益が法人税法上の収益事業等に含まれるかについて、収益事業以外の事業に属する資産として区分経理をしたときは、その区分経理に係る資産を運用する行為は、収益事業に付随して行われる行為に含めないことができる(脚注3)。
3.事業区分の留意点 公益目的支出計画の実施事業については、整備法の規定に反しない限り、法人が任意に選択できる。
営利型法人である移行法人の場合、前記Ⅴ5記載の通り、全部課税であるにもかかわらず、実施事業等の「支出超過額」を損金の額に算入できないために、赤字を大きくしても収益事業の所得の圧縮には直接はつながらない。
この場面においても、公益目的支出計画と法人税課税は一時的にはトレードオフの関係にあることに留意が必要である(事例4参照)。但し公益目的財産額が損金とならない総額であるので、長期的に見れば課税所得総額は第1案も第2案も同額である。
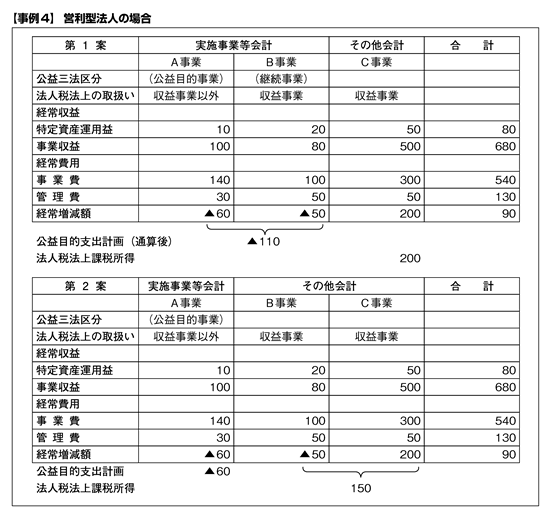 なお、非営利型法人の場合には、収益事業課税であるので、B事業とC事業(収益事業)課税なので第1案でも第2案でも同じ課税所得金額となる。
なお、非営利型法人の場合には、収益事業課税であるので、B事業とC事業(収益事業)課税なので第1案でも第2案でも同じ課税所得金額となる。
脚注
1 一般法人法等239条1項では「残余財産の帰属は、定款で定めるところによる。」、同条2項では「前項の規定により残余財産の帰属が定まらないときは、その帰属は、清算法人の社員総会又は評議員会の決議によって定める。」とある。
2 公益認定等ガイドラインⅡ―1(4)①公益目的財産額の算定について(引当金について)※退職給付会計の導入に伴う会計基準変更時差異の扱いについて
3 法人税基本通達(抜粋)
15-1-7 (収益事業の所得の運用)
公益法人等が、収益事業から生じた所得を預金、有価証券等に運用する場合においても、当該預金、有価証券等のうち当該収益事業の運営のために通常必要と認められる金額に見合うもの以外のものにつき収益事業以外の事業に属する資産として区分経理をしたときは、その区分経理に係る資産を運用する行為は、15-1-6にかかわらず、収益事業に付随して行われる行為に含めないことができる。
15-1-6 (付随行為)
収益事業の範囲に規定する「その性質上その事業に附随して行われる行為」とは、例えば次に掲げる行為のように、通常その収益事業に係る事業活動の一環として、又はこれに関連して行われる行為をいう。
(1)~(4)略
(5) 公益法人等が収益事業から生じた所得を預金、有価証券等に運用する行為
(6) 公益法人等が収益事業に属する固定資産等を処分する行為
新公益法人制度の税務上の論点(3・了)
公認会計士・税理士 長谷川敏也
Ⅴ.法人区分の移行に伴う課税問題
1.法人区分の移行に伴う累積所得金額の益金算入 公益法人等が普通法人(非営利型法人以外の法人)に移行する場合、課税所得の範囲に変更が生じ、収益事業課税から全所得課税となる。この場合には、原則として公益目的以外に特定の者に分配されないことを前提に非課税とされてきた所得の累積額について構成員に分配することも可能となる(脚注1)。
そこでこのような場合には、非課税とされていた前提が存在しなくなったことから、全所得課税が行われていたとしたならば課税されていたであろう部分についてこの時点で課税所得を構成するものとされた。
そのケースは表1の通りである。
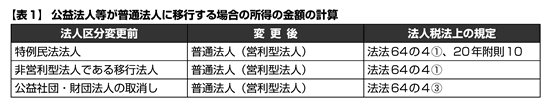 なお、表1の法人税法64条の4は、当面は、特例民法法人等が普通法人たる一般社団・財団法人へ移行する場合のことであるから、特例民法法人が非営利型法人へ移行する場合や、公益社団・財団法人へ移行する場合には課税範囲が変わらず、この累積所得金額についての課税問題は生じない。しかし、公益社団・財団法人の公益認定取消し(認定法29①②)や非営利型法人の否認によって営利型法人に移行する場合にも生じる課税リスクであるので、あらかじめ理解しておく必要がある。
なお、表1の法人税法64条の4は、当面は、特例民法法人等が普通法人たる一般社団・財団法人へ移行する場合のことであるから、特例民法法人が非営利型法人へ移行する場合や、公益社団・財団法人へ移行する場合には課税範囲が変わらず、この累積所得金額についての課税問題は生じない。しかし、公益社団・財団法人の公益認定取消し(認定法29①②)や非営利型法人の否認によって営利型法人に移行する場合にも生じる課税リスクであるので、あらかじめ理解しておく必要がある。2.公益認定の取消しに伴う課税問題
(1)「公益目的取得財産残額」の贈与 公益法人は、公益認定基準に抵触した場合(認定法29②一)、公益法人が自ら一般社団・財団法人となるべく申請した場合(同条①四)や役員が認定法に規定されている罪で罰金刑に処せられた場合(同条①一)等に、公益認定の取消しがなされ、「公益目的取得財産残額」の贈与という事態が生じる。公益社団・財団法人に移行した後に公益認定が取り消され、公益目的取得財産の残額に相当する金額の贈与(認定法30)という事態を招いて、法人の財産を失ってしまう。
認定法上は、1ヶ月以内に公益目的取得財産残額を他の公益法人等に贈与すべきとし、取消しの日における金額の確定と報告の期限を3ヶ月以内としている(認定法規則50①)。なお、1ヶ月以内に贈与契約が成立していないときは国又は都道府県が公益目的取得財産残額に相当する額の金銭について認定取消法人から受贈されたとみなすことになっているので留意が必要である(認定法30①)。
(2)「公益目的取得財産残額」の範囲及び計算 したがって、「公益目的取得財産残額」の範囲及び計算については十分留意する必要がある。公益目的取得財産残額は、法人の意思と宣言によって確定するからである。
公益目的取得財産残額は、毎事業年度末における公益目的事業財産の未使用残高であり、公益目的保有財産と公益目的増減差額との合計額で、毎事業年度末、計算し行政庁に報告するものである(認定法30、認定法規則48)。
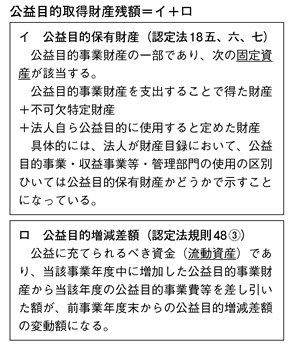 このイ及びロと、貸借対照表内訳表、並びに財産目録は密接な関係にあるが、正確には公益法人の事業報告書(定期提出書類)別表Hにて計算することになり、損益計算書(公益目的事業会計)から誘導的に算出されることとなる。
このイ及びロと、貸借対照表内訳表、並びに財産目録は密接な関係にあるが、正確には公益法人の事業報告書(定期提出書類)別表Hにて計算することになり、損益計算書(公益目的事業会計)から誘導的に算出されることとなる。(3)公益法人が普通法人(営利型法人)に移行する場合の所得の金額の計算 公益社団・財団法人が行政庁から認定の取消しを受けたことにより非営利型法人以外の法人に該当することとなった場合には、当該取消しの日以降に公益目的のために支出されることが義務付けられている公益目的取得財産残額を累積所得金額から控除することとされている(法令131の5①一)。
もっとも、公益社団・財団法人に移行した後に公益認定が取り消された場合には、公益目的取得財産の残額の贈与(認定法30)が生じるので、控除するのは当然のことであり、公益三法上は債務であるので、法人税法上の簿価純資産額から単純に差し引く。なお、この贈与により生じた損失の額は損金に算入しない(法令131の5④)。寄附金損金不算入の特例(法法37⑦)の対象ともならない。
したがって、過去の収益事業以外の事業から生じた所得の累積額が大きい場合には、(1)の贈与に加えて、一時に多額の課税が生じることとなる(下記算式参照)。
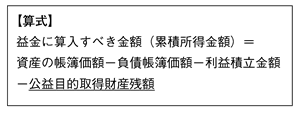
3.移行法人が営利型法人となる場合の取扱い(移行時点) 特例民法法人が普通法人に移行する場合及び、非営利型法人である移行法人(移行の認可を受けて移行の登記をした一般社団・財団法人のうち、公益目的支出計画の実施の完了の確認を受けていない法人)が営利型法人である移行法人(普通法人)となる場合の二つのケースでは、累積所得金額の計算に当たって、移行日における「修正公益目的財産残額」と「資産の帳簿価額から負債帳簿価額等を控除した金額」とのうちいずれか少ない金額(以下「当初調整公益目的財産残額」)を累積所得金額から控除し、累積所得金額から控除しきれないときは、その控除しきれない金額を累積欠損金額とみなすこととなる(法法64の4③、法令131の5①三・②)(表2参照)。
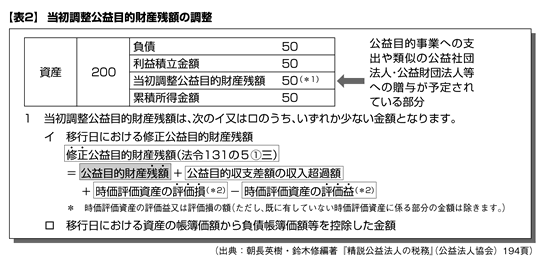
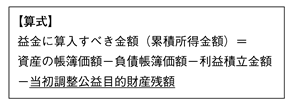 このうち「修正公益目的財産残額」は、整備法上の「公益目的財産残額」と公益目的収支差額の収入超過額の合計額に、時価評価資産の評価損の額を加算し、時価評価資産の評価益の額を控除した金額となる(法令131の5①三イ、法規27の16の4①)。
このうち「修正公益目的財産残額」は、整備法上の「公益目的財産残額」と公益目的収支差額の収入超過額の合計額に、時価評価資産の評価損の額を加算し、時価評価資産の評価益の額を控除した金額となる(法令131の5①三イ、法規27の16の4①)。4.時価概念である公益目的財産額と当初調整公益目的財産残額 「公益目的財産額」とは、移行の登記をした日の前日(以下「算定日」)における貸借対照表の純資産の部に計上すべき額に、一定の調整(時価評価)をして得た額をいう(整備法施行規則14①)。
整備法上の「公益目的財産額」は時価概念であり、かつ純資産の部に保全が義務付けられている額、あるいは退職給付引当金の会計基準変更時差異も差し引く等の計算が認められている(脚注2)ので、法人税法上そのまま採用できる概念ではない。
法人税法上は法人税法上の簿価へ修正(元に戻す)して控除することとなるため「修正公益目的財産残額」という。したがって用語こそ類似しているが、公益社団・財団法人に移行した後に公益認定が取り消された場合の「公益目的取得財産残額」とは、計算の難易度も概念も異なる。
「当初調整公益目的財産残額」は、会計上認識される資産と負債の差額である整備法上の純資産を基礎として算出されるものの、課税対象となる「累積所得金額」は、税制上認識される資産と負債等の差額として算出されることから(法令131の4①)差異が生じる。このことは、法人区分の変更に際して十分留意する必要がある(下掲6・事例1参照)。
すなわち、公益法人会計基準では、たとえば賞与引当金、退職給付引当金、役員退職慰労引当金などは、通常の会計処理において負債として計上する(公益法人会計基準の運用指針12(1))が、法人税法上の負債には該当しない。このため、これら引当金は、「当初調整公益目的財産残額」の計算上は負債としてその減少項目となるが、累積所得金額の計算上は負債に該当せずその減少項目とはならないこととなる。
5.移行時点以降の各事業年度の課税 営利型法人である移行法人(普通法人)は全所得課税である。ところで3、4で述べた移行に伴う累積所得金額の課税を受けたので、移行後は普通法人と同じ課税方式で済むかというと、そうではない。
移行法人は、「公益目的財産額」がある場合には、公益目的財産額に相当する額を公益目的のために支出して零とするための「公益目的支出計画」を作成しなければならないこととされている(整備法119①)。
法人税法では、移行日の属する事業年度以後の各事業年度(公益目的支出計画の実施が完了したことの確認に係る事業年度後の事業年度を除く)の公益目的支出の額(実施事業に係る事業費の額、特定寄付の額及び実施事業に係る経常外費用の額の合計額)が実施事業収入の額(実施事業に係る収益の額と実施事業資産から生じた収益の額の合計額)を超えるときは、その超える部分の金額(「支出超過額」)を損金の額に算入しないこととされ(法令131の5⑤)、実施事業収入の額が公益目的支出を超えるときは、その超える部分の金額(「収入超過額」)を益金の額に算入しないこととされている(法令131の5⑥)(表3参照)。
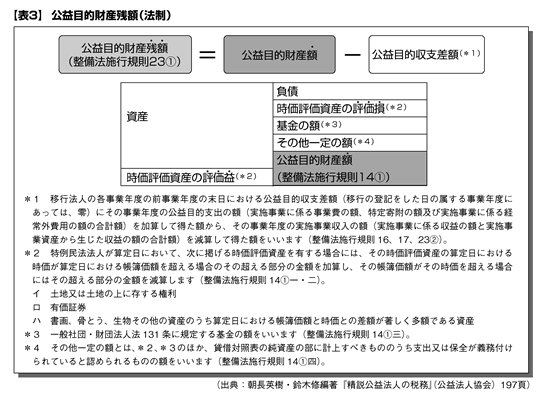 「調整公益目的財産残額」とは、3で計算した当初調整公益目的財産残額から、過年度の支出超過額の合計額を減算し、過年度の収入超過額の合計額を加算した金額(公益目的支出計画の実施が完了したことの確認に係る事業年度後の事業年度にあっては、ゼロ)とされている(法令131の5⑦)。
「調整公益目的財産残額」とは、3で計算した当初調整公益目的財産残額から、過年度の支出超過額の合計額を減算し、過年度の収入超過額の合計額を加算した金額(公益目的支出計画の実施が完了したことの確認に係る事業年度後の事業年度にあっては、ゼロ)とされている(法令131の5⑦)。なぜ「支出超過額」を損金に算入できないのか。これは3、4で普通法人(全所得課税法人)に移行したときの累積所得金額の計算時に、「修正公益目的財産残額」を一括して控除(損金算入と同じ効果)しているためである。
「調整公益目的財産残額」がゼロになればその後の各事業年度においてこのような調整計算からは解放されるが、それまでの期間はこの法人税法上の「調整公益目的財産残額」を計算する必要があり、公益目的支出計画実施中の各事業年度では継続して申告書作成に留意が必要である。
6.事例 1 移行法人が普通法人に該当することとなった場合の累積所得金額の益金算入計算は、具体的には、別表十四(六)の「Ⅱ 移行法人が普通法人に該当することとなった場合等の累積所得金額又は累積欠損金額の益金又は損金算入等に関する明細書」にて当初調整公益目的財産残額の計算を行い、調整後の累積所得金額又は累積欠損金額の益金算入額又は損金算入額を記載することとなる。
簡単な計算を試みると次の通り(事例1参照)。
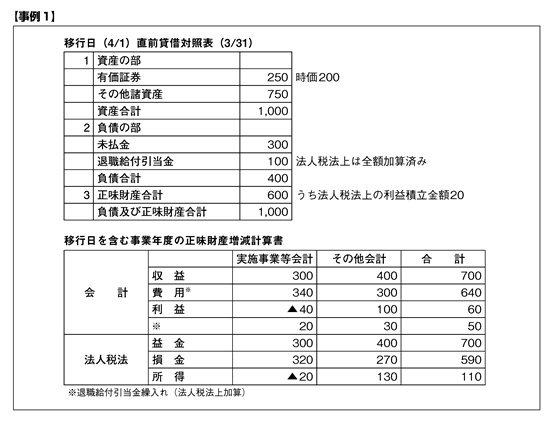 ① 公益目的財産残額(整備法上)
① 公益目的財産残額(整備法上)資産1,000-会計上の負債400-含み損50=550
② 法人税法上の簿価純資産価額
資産1,000-(負債400-退職給付引当金100)-利益積立金額20=680
③ 修正公益目的財産残額(法人税法上)
公益目的財産残額(整備法上)550+含み損50=600
④ 累積所得金額
法人税法上の簿価純資産価額680-修正公益目的財産残額600=80
この金額80(結果的に退職給付引当金超過額-利益積立金額)が移行日の属する事業年度の益金に算入されることとなる。
⑤ 移行日を含む事業年度の損益
簡略化のため、その他会計(法人会計の費用配賦後)がすべて法人税法上の収益事業であるとすると、所得130に対して課税される。実施事業等会計の所得▲20については損金に算入されない(通算されない)。
法人税別表十四(六)の記載事例及び「記載の仕方」は31頁掲載の別表の通り。
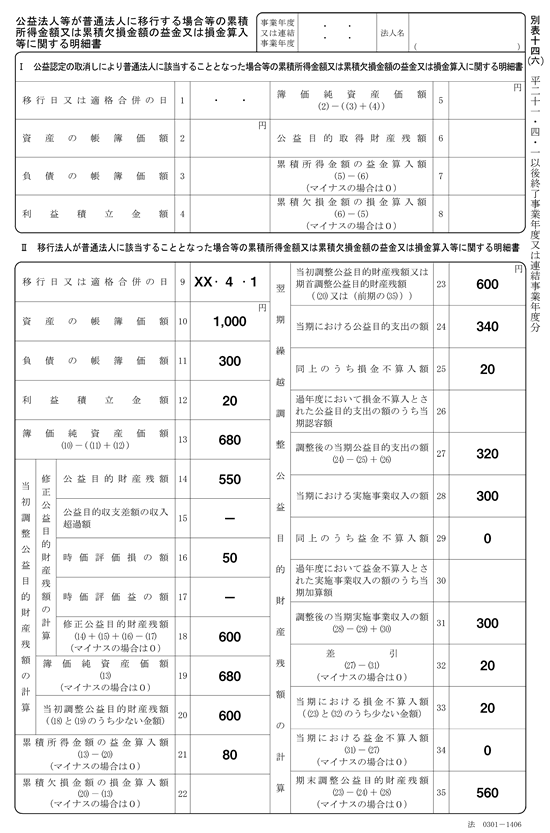 7.事例 2
公益目的財産残額には次の申告調整要因がある。
7.事例 2
公益目的財産残額には次の申告調整要因がある。① 整備法上の「公益目的財産残額」は時価概念であり、法人税法上は法人税法上の簿価へ修正(元に戻す)して「修正公益目的財産残額」を算定していること
② しかし、その後は、法人税法上も整備法上の公益目的支出超過額を共通の減少額として期末調整公益目的財産残額を減少させていること
③ 整備法上の「公益目的支出計画の実施が完了したことの確認事業年度」を共通の指標とし、法人税法上の損金不算入規制を継続すること
以上から、含み損があれば法人税法上の調整公益目的財産残額が残り、含み益があれば公益目的支出計画完了前に調整公益目的財産残額がゼロになってしまう。
次の事例2(上記参照)は、含み損が大きいので、公益目的支出計画が1年目で完了する場合である。
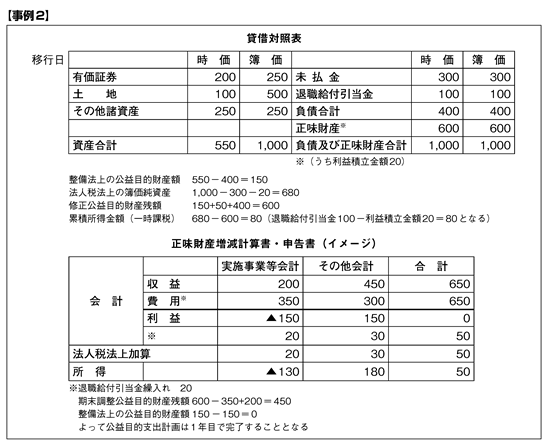 この場合の法人税別表十四(六)の記載事例及び「記載の仕方」は33、34頁掲載の別表の通り。
この場合の法人税別表十四(六)の記載事例及び「記載の仕方」は33、34頁掲載の別表の通り。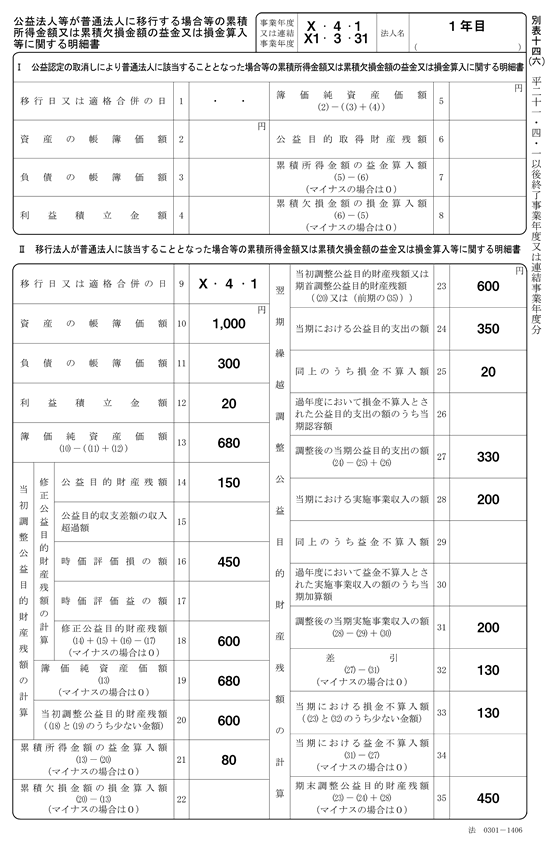
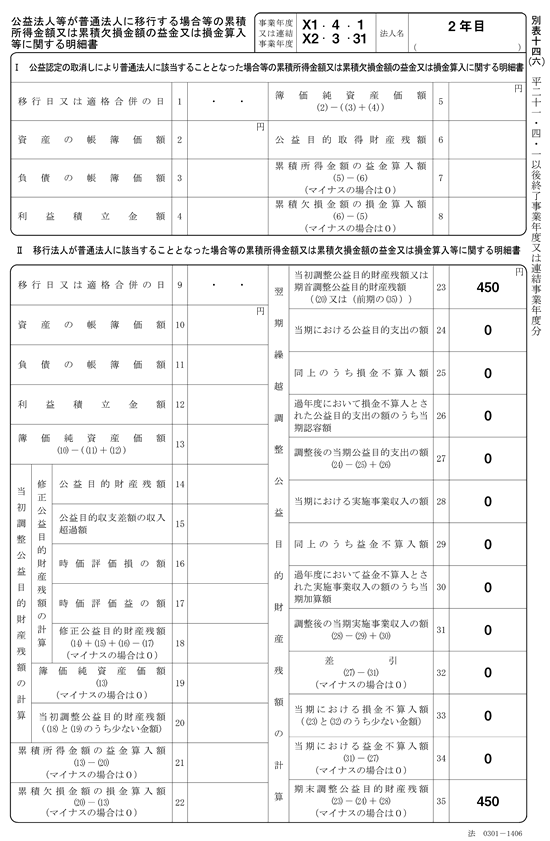 公益目的支出計画の実施期間(この事例では1年間)と法人税法上の調整公益目的財産残額がゼロになる期間(1年超)が異なる。スタートになる金額が相違することから、法人税法上の調整公益目的財産残額がゼロではないのに、公益目的支出計画の実施が完了してしまい、齟齬が生じている。
公益目的支出計画の実施期間(この事例では1年間)と法人税法上の調整公益目的財産残額がゼロになる期間(1年超)が異なる。スタートになる金額が相違することから、法人税法上の調整公益目的財産残額がゼロではないのに、公益目的支出計画の実施が完了してしまい、齟齬が生じている。この場合、期末調整公益目的財産残額の記載(この事例では450)はいつまで、何のために続けるのだろうか。公益目的支出超過額(この事例では130)を損金の額に算入しない規制は、公益目的支出計画の実施が完了したことの確認事業年度以後は発生しない(法令131の5⑤)ので、2年目からは支出超過額は損金算入できる上に、確認後は行政庁の監督もなくなり、法人法に規定する一般社団・財団法人として存続するので、2年目以降の記載は不要と考える。
逆に含み益がある場合には、期末調整公益目的財産残額はゼロになっていたとしても、公益目的支出超過額を損金の額に算入しない規制(法令131の5⑤)は、公益目的支出計画の実施が完了したことの確認事業年度まで継続すると考えられる。
8.移行法人のみなし解散と清算 移行法人は、偽りその他不正の手段により移行認可を受けた場合には、その認可が取り消され、取消し処分の日が、移行期間満了日以後(特例民法法人の経過措置期間経過後)であると、みなし解散となる(整備法131④)。
みなし解散後清算法人となった場合には、公益目的財産残額があるときはその公益目的財産残額に相当する財産について認定法5条17号に規定するもの(他の公益法人等、国、地方公共団体等)に帰属させなければならない(整備法130)。
Ⅵ.公益目的支出計画と法人税課税
1.トレードオフ関係の危険性 一般社団・財団法人は、「公益目的財産額」がある場合には、公益目的財産額に相当する額を公益目的のために支出してゼロとするための「公益目的支出計画」を作成しなければならない(整備法119①)(図1参照)。整備法上公益目的支出計画を早期に完了させるために、移行法人は勢い実施事業等会計の赤字を拡大するために、法人会計に属する管理費をできるだけ実施事業等に配賦計算したり、金融資産運用益を法人会計に属させようとする。しかし、このことは結果として一時的に法人税課税を大きくする危険性がある。公益目的支出計画と法人税課税はトレードオフの関係となる場合があることに留意が必要である。
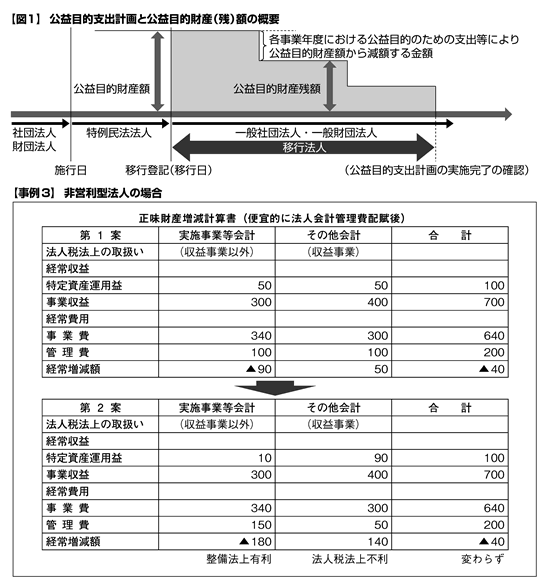
2.収益・費用の配分の留意点 非営利型の移行法人が、合理的な論理構成をして特定資産運用収益を実施事業等会計以外へ、管理費を実施事業等会計へ移したとすると次のように計算できる(事例3参照)。簡略化のために、その他会計を法人税法上、収益事業とすると、実施事業等会計の赤字が増えて公益目的支出計画の実施期間が短縮される(整備法上有利)が、法人税課税が増える(法人税法上不利)結果となる。もっとも法人税法上の収益事業か否かと、整備法上の実施事業会計、その他会計の区分は整合的である必要はないので、すべてトレードオフの関係となる訳ではない。
公益目的支出計画の実施期間に制限はないので、充分にシミュレーションをすべきである。
営利型法人の場合には全所得課税でありながら、実施事業等会計の公益目的支出計画支出超過額は損金不算入(法令131の5⑤)であるので、やはり一時的には法人税法上不利となる。
なお、有価証券等の運用益が法人税法上の収益事業等に含まれるかについて、収益事業以外の事業に属する資産として区分経理をしたときは、その区分経理に係る資産を運用する行為は、収益事業に付随して行われる行為に含めないことができる(脚注3)。
3.事業区分の留意点 公益目的支出計画の実施事業については、整備法の規定に反しない限り、法人が任意に選択できる。
営利型法人である移行法人の場合、前記Ⅴ5記載の通り、全部課税であるにもかかわらず、実施事業等の「支出超過額」を損金の額に算入できないために、赤字を大きくしても収益事業の所得の圧縮には直接はつながらない。
この場面においても、公益目的支出計画と法人税課税は一時的にはトレードオフの関係にあることに留意が必要である(事例4参照)。但し公益目的財産額が損金とならない総額であるので、長期的に見れば課税所得総額は第1案も第2案も同額である。
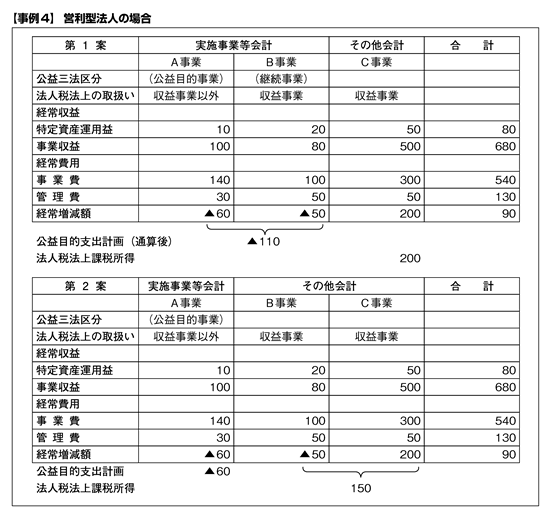 なお、非営利型法人の場合には、収益事業課税であるので、B事業とC事業(収益事業)課税なので第1案でも第2案でも同じ課税所得金額となる。
なお、非営利型法人の場合には、収益事業課税であるので、B事業とC事業(収益事業)課税なので第1案でも第2案でも同じ課税所得金額となる。脚注
1 一般法人法等239条1項では「残余財産の帰属は、定款で定めるところによる。」、同条2項では「前項の規定により残余財産の帰属が定まらないときは、その帰属は、清算法人の社員総会又は評議員会の決議によって定める。」とある。
2 公益認定等ガイドラインⅡ―1(4)①公益目的財産額の算定について(引当金について)※退職給付会計の導入に伴う会計基準変更時差異の扱いについて
3 法人税基本通達(抜粋)
15-1-7 (収益事業の所得の運用)
公益法人等が、収益事業から生じた所得を預金、有価証券等に運用する場合においても、当該預金、有価証券等のうち当該収益事業の運営のために通常必要と認められる金額に見合うもの以外のものにつき収益事業以外の事業に属する資産として区分経理をしたときは、その区分経理に係る資産を運用する行為は、15-1-6にかかわらず、収益事業に付随して行われる行為に含めないことができる。
15-1-6 (付随行為)
収益事業の範囲に規定する「その性質上その事業に附随して行われる行為」とは、例えば次に掲げる行為のように、通常その収益事業に係る事業活動の一環として、又はこれに関連して行われる行為をいう。
(1)~(4)略
(5) 公益法人等が収益事業から生じた所得を預金、有価証券等に運用する行為
(6) 公益法人等が収益事業に属する固定資産等を処分する行為
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
最近閲覧した記事
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -























