解説記事2010年03月22日 【最新判決研究】 交際費等の範囲─優待入場券の無償交付と業務委託料の差額─(2010年3月22日号・№347)
最新判決研究
交際費等の範囲─優待入場券の無償交付と業務委託料の差額─
品川芳宣
早稲田大学大学院教授
東京地裁平成19年(行ウ)第655号
平成21年7月31日判決
一、事実
(1)X会社(原告)は、遊園施設の運営等を業とする株式会社であるが、平成11年3月期ないし同17年3月期の各事業年度(以下「本件各係争年度」という。)分法人税について、①本社ビル等の清掃業務(以下「本件清掃業務」という。)につきN会社に対して支払った業務委託料(以下「本件委託料」という。)を損金の額に算入し、②事業関係者等に対して交付したX会社が運営する遊園施設への入場及びその施設の利用等を無償とする優待入場券(以下「本件優待入場券」という。)については何ら課税上の処理を行わなかった。
これに対し、Y税務署長(処分行政庁)は、本件委託料のうち、N会社等がC会社等に対して再委託し、当該再委託料(以下「本件再委託料」という。)との差額(以下「本件委託料差額」という。)及び本件優待入場券に係る費用相当額が租税特別措置法(以下「措置法」という。)61条の4にいう交際費等に当たるとして、当該各金員を損金不算入とする各更正処分(以下「本件各更正」という。)及び本件委託料差額に係る過少申告部分については重加算税の各賦課決定をし、本件優待入場券に係る過少申告部分については過少申告加算税の各賦課決定(以下各処分を一括して「本件各課税処分」という。)をした。
X会社は、本件各課税処分を不服とし、前審手続を経て、国(被告)に対して同処分の取消しを求めて本訴を提訴した。なお、消費税の課税処分関係については、省略する。
(2)本件各係争年度における本件委託料差額及び本件優待入場券の費用相当額は、次(編注:表1・2参照)のとおりである。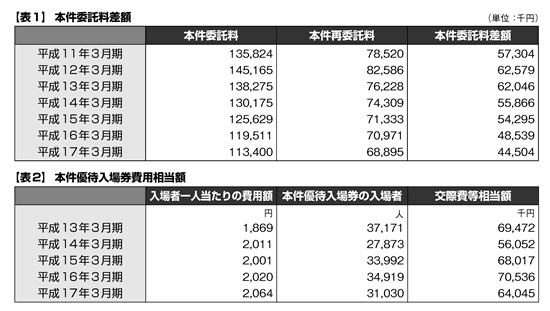
二、争点及び当事者の主張
1 争点
(1)本件委託料差額は交際費等に当たるか。
(2)本件優待入場券の使用に係る費用が交際費等に当たるか。また、その額は幾らか。
2 国の主張
(1)交際費等の支出の相手方の範囲は相当に広く、その支出の態様は直接的であると間接的であるとを問わないのであり、また、その支出内容は、事業に関係のある者等に対するものであれば、接待等の消費的性格を有する支出、贈与等の個人所得を形成する可能性のある支出及びこれらに類する支出のすべてに及ぶのである。
また、ある支出が交際費等に該当するか否かを判断するに当たっては、単にその支出の金額の多寡のみを問題とすべきではなく、支出の相手方及び目的並びに行為の形態等を考慮して決すべきである。
(2)X会社は、形式的にはN会社との間で本件清掃業務に係る契約を締結しているものの、その実態は、本件清掃業務についてはC会社に委託し、本件業務委託料差額については、N会社に支払うように装って、その実質的経営者である甲に支払っていた。そして、甲は、いわゆる総会屋や右翼団体の幹部とされている人物であり、X会社の地元対策等に多大な影響力を与えている者である。したがって、①本件委託料差額の支出の相手方は、X会社の事業に関係のある者といえる。
また、X会社は、N会社との間の本件清掃業務に係る契約については、総務部、開発部及び技術本部に担当させており、X会社において清掃業務を担当する本来の部署と異なること、本件清掃業務については、C会社において約8パーセントの利益率を確保した上で、N会社が約40パーセントもの利益率を得ていること、N会社とC会社との間に甲の関係会社を介していたことからすれば、本件清掃業務の業務委託料は極めて高額であり、本件清掃業務の対価として不自然不合理であるところ、前記のとおり、支出の相手方は、いわゆる総会屋や右翼団体の幹部とされている甲のいわゆるフロント企業であり、甲がX会社の地元対策等に多大な影響力を持っている者であることなどを考え併せれば、②本件委託料差額を支出した目的は、甲に対して利益を供与することによって、X会社の営業活動の円滑な進行や運営を図るなどのためであるといえる。
そして、前記のとおり、X会社は、総会屋等とされX会社の地元対策等に多大な影響力を持つ甲に対して、役務の提供と何ら関係することなく、清掃業務委託料の名目で本件委託料差額を支払ったものであり、また、本件委託料差額の趣旨は、今後とも地元対策その他種々の便宜を受けることができるようにするための謝礼、贈答等の行為として、上記のような立場にある甲に対する利益供与であるから、③本件委託料差額は、支出の原因となる行為の形態が接待等に当たる。したがって、本件委託料差額は、措置法61条の4第3項が規定する交際費等に当たる。
(3)本件優待入場券の使用に係る費用が交際費等に該当するか否かをみるに、X会社は、遊園施設への入場及びその利用を無償とする本件優待入場券を発行しているが、役員扱い入場券は、X会社の役員又は部長の判断で特に重要な得意先に交付していること、役員が私的に使用している事実も認められないこと、プレス関係入場券は、X会社が特に選定したマスコミ関係者に対して発送した招待状を持参した者及びその家族に対して交付していることから、①本件優待入場券の使用に係る費用の支出の相手方は、事業に関係のある者等といえる。
また、前記のとおり、X会社は、X会社の特定の事業関係者に対し、本件優待入場券を無償交付していること、特にマスコミ関係者に対しては、家族共々無償で招待するとともに食事券まで交付してX会社の遊園施設を利用させていることが認められるから、本件優待入場券の交付は、X会社の事業と特に関係の深い者に対する謝礼の意であり、②本件優待入場券の使用に係る費用の支出の目的は、これらの者との親睦の度を密にして取引関係の円滑な進行を図るためであるといえる。
そして、X会社は、X会社の事業関係者に対し、本来有償である入場券を上記の目的をもって無償交付したところ、その交付は、これを受けた特定の得意先又はマスコミ関係者の歓心を買うとともに、これらの者に対するその利用による慰安のために行った接待又は贈答であるから、③本件優待入場券の使用に係る費用は、その支出の原因となる行為の形態が接待等に当たる。したがって、本件優待入場券の使用に係る費用は、措置法61条の4第3項が規定する交際費等に当たる。
3 X会社の主張
(1)ある費用が交際費等に該当するか否かは、その金額が経済的にみて合理的かつ公正な価格であるか否かによって判断されるべきである。支出の相手方がどのような者であっても、支出の金額が経済的に合理的なものである限り、企業の適正な費用として経理処理され、損金算入されるのは当然である。支出の金額が経済的に合理的であるにもかかわらず、支出の相手方が右翼関係者等であることを理由に交際費等として課税することは、課税権の濫用である。
X会社からN会社に対して支払われた本件委託料は、その価格見積りに照らせば、本件清掃業務に対する対価として経済的に合理的な価格であることは明らかであるから、本件委託料差額は交際費等に該当しないというべきである。
(2)本件優待入場券による入場者数の割合は、総入場者の0.2パーセント程度にすぎず、1日当たりの平均値でみても100人程度で、最大入場者数をTディズニーランドで7万人、Tディズニーシーで5万人と想定するこれらの施設の1日当たりの平均入場者数の0.25パーセントから0.3パーセント程度であって、電鉄会社における優待乗車券と同様に、X会社が保有する遊園施設を余裕枠の範囲において有償入場券による入場者を排除することなく使用させるにすぎない。仮に、X会社が本件優待入場券の交付を廃止しても、X会社の人件費、営業資材費、エンターテイメント・ショー制作費、業務委託費、販促活動費、ロイヤルティー及びその他の費用の支出は、本件優待入場券の作成に直接要した費用、すなわち本件優待入場券の製作、印刷費用を除いては、全く不変である。本件優待入場券の製作、印刷費用を除く上記の費用は、本件優待入場券による入場者の存否にかかわらず、X会社が施設を運営するためには否応なしに支出しなければならない不可欠の費用であり、本件優待入場券による入場者の接待等のために支出した費用ではない。本件優待入場券の交付は、上記製作、印刷費用を除き、何らの金銭の出えんを伴わないのであるから、上記製作、印刷費用以外の費用は、そもそも交際費等に該当しない。また、企業の冗費を節約して資本蓄積の充実等により企業基盤の強化を図るという交際費課税の趣旨からすれば、ある費用が交際費等であると認定して損金不算入制度を適用するためには、大前提として、当該接待等が減少すればそのために要していた費用が不要となることが要件となるところ、そのような観点からも、上記製作、印刷費用以外の費用が交際費等に当たるとはいえない。
そして、上記製作、印刷費用の単価は、1枚当たり2.4円ないし5.8円程度であるところ、交際費等の損金不算入の制度趣旨が前記のとおりであることにかんがみれば、このようなわずかな支出が冗費、濫費となる余地はないのであるから、上記製作、印刷費用が交際費等に該当する余地はない。したがって、本件優待入場券に関しては、交際費等として課税をする余地がないのであり、国が主張する諸費用は、X会社が本件優待入場券による入場者に対する接待等の「ために支出する」費用に当たらないことは明白である。
三、判決要旨
請求棄却。
1 本件委託料差額の交際費等該当性
(1)措置法61条の4第1項は、交際費等の額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない旨を規定し、同条3項は、交際費等とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待等のために支出するものをいう旨を規定している。そして、租税特別措置法通達(以下「措置法通達」という。)61の4(1)-22は、措置法61条の4第3項に規定する「得意先、仕入先その他事業に関係のある者等」には、直接当該法人の営む事業に取引関係のある者だけでなく間接に当該法人の利害に関係ある者及び当該法人の役員、従業員、株主等も含むことに留意するものとしている。上記のような同条3項の文言に照らすと、特定の費用が同項の交際費等に当たるか否かを判断するに当たっては、個別の事案の事実関係に即し、その支出の相手方、支出の目的及び支出に係る法人の行為の形態を考慮することが必要とされるものと解される。
(2)前記前提となる事実については、各証拠及び弁論の全趣旨によれば、次の事実が認められる。
① N会社の株主は、甲の妻子や実兄などの甲の親族又は甲の関係者であり、その役員も、X会社との間で本件清掃業務に係る業務委託契約が締結された昭和59年9月1日当時の代表取締役を甲の実兄である乙が務めるなど、甲の親族がそのほとんどを占め、それぞれ報酬を受領し、甲及びその妻は、相談役又は顧問等として、平成10年8月から平成17年7月までの7年間だけでも、それぞれ3,990万円強及び2,050万円の報酬を受領していた。
② X会社と甲の間には、昭和48年に設立され甲が代表取締役になるなどしていたK会社について、昭和58年当時のX会社の代表取締役社長であったTが発起人や取締役となったり、X会社が昭和51年に出資したりしていたほか、昭和60年に設立され遅くとも平成7年には甲の娘婿である丙が代表取締役社長を務めるなどしていたS会社についても、Tが遅くとも上記のころまでに取締役となったり、X会社が平成8年に出資したりするなどのつながりがあった。
③ X会社は、昭和58年1月、X会社の株主の子会社であるD会社との間で、本件清掃業務を含むTディズニーランドのバックヤード施設清掃業務を委託する旨の契約を締結していたが、甲とTとが協議した結果、X会社は、同年8月31日付けで、上記契約のうち本件清掃業務に係る部分を終了させ、これに伴ってその後のD会社との間の契約における業務委託料を1か月当たり338万円余減ずるものとする一方で、甲の指示によって設立され甲が実質的に経営権を有していたM会社との間で、翌9月1日、業務委託料を1か月当たり381万円として本件清掃業務に係る業務委託契約を締結した。この際、X会社の当時の代表取締役であったTが、かねてC会社の役員と面識を有していたことから、本件清掃業務の実施についてはC会社に再委託されることになった。
しかし、約1年後には、甲の指示により本件清掃業務がM会社からN会社に移管されることとなったため、X会社は、契約の相手方をM会社からN会社に変更し、昭和59年9月1日、N会社との間で、業務委託料を1か月当たり487万円として本件清掃業務に係る業務委託契約を締結した。N会社は、昭和54年に設立された直後から事業を休止する状態が続いており、清掃業務の実施につき実績は全くなく、上記契約を締結するわずか4か月前に本店所在地を千葉県浦安市内に移転した上で上記契約を締結するに至ったものであり、以後約20年間にわたって上記契約は更新されたが、N会社の売上げは上記契約によるもの以外にはなかった。そして、上記契約締結の事実が公になったことを契機に、平成17年6月2日、上記契約は契約期間の満了前に解約された。
④ N会社は、実際に本件清掃業務を実施することはなかったにもかかわらず、N会社の収益に相当する本件委託料差額は、X会社がN会社に対して支払う金額のうちの約40パーセントに上り、一方、本件清掃業務の実施によるC会社の利益率は、約8パーセントであった。
(3)前記で認定判断した甲の社会的な立場、X会社とM会社又はN会社との間で本件清掃業務に係る業務委託契約が締結される前からX会社と甲又はその関係する法人との間の関係、甲が実質的な経営者であるM会社又はN会社との間で本件清掃業務に係る業務委託契約が締結された当時の事情及びその後の経緯等に照らすと、X会社がN会社との間で本件清掃業務に係る業務委託契約の更新を繰り返して金銭の支払を行ってきたことについては、形式的には、N会社との間の本件清掃業務に係る業務委託契約に基づくものではあるが、実質的には、上記のような甲の社会的な立場を前提に、その影響力をX会社の事業の遂行、管理等に利用すべく、N会社を介し甲に経済的利益を提供して甲との関係を良好に保つものとしてされたもので、本件清掃業務の内容に応じ業務委託料として相当とされる金額を超える金銭の支払については、甲に対する謝礼又は贈答の趣旨でされたと認めるのが相当である。そして、上記のような甲の立場に照らすと、甲が措置法61条の4第3項の「その他事業に関係のある者等」に当たることは明らかというべきである。
そうすると、本件委託料差額に相当する金銭については、上記のような支出の相手方、支出の目的及び支出に係る行為の形態に照らし、同項の交際費等に当たると認めるのが相当である。
2 本件優待入場券に係る費用相当額の交際費等該当性
(1)各証拠及び弁論の全趣旨によれば、X会社は、役員扱い入場券については、X会社の役員等において重要な取引先と判断した企業に対して交付し、プレス関係入場券については、全国紙の役員等のX会社が特に選定したいわゆるマスコミ関係者及びその家族に対して交付していたこと、これらを使用する者は、X会社が運営する遊園施設であるTディズニーランド又はTディズニーシーに無償で入場してその施設の利用等をすることができること、上記各遊園施設は、我が国屈指の人気を得ているものであり、その入場及び施設の利用等に係る有償入場券の売価は、5,000円前後であったことが認められる。
そして、X会社においては、1日当たりの最大入場可能数及び平均入場者数が、Tディズニーランドにあっては7万人及びおおむね4万人、Tディズニーシーにあっては5万人及びおおむね3万人であることを前提に、本件優待入場券を発行し、それを使用して入場等をする者に対して有償入場券により入場等をする者に対するのと同等の役務を提供することとして、施設の運営に当たっていたことが認められるところ、このような事実関係の下においては、本件優待入場券が現に使用されて遊園施設への入場等がされたときに、その者に対し、X会社の提供する役務に係る原価のうちその者に対応する分につき費用の支出があったものと認めるのが相当である。
そうすると、X会社が本件優待入場券を発行してこれを使用させていたことについては、遂行する事業に関係のある企業及びマスコミ関係者等の特定の者に対し、その歓心を買って関係を良好なものとしX会社の事業を円滑に遂行すべく、接待又は供応の趣旨でされたと認めるのが相当であり、これを使用して入場等をした者に対して役務を提供するに当たりX会社が支出した上記の費用については、上記のような支出の相手方、支出の目的及び支出に係る行為の形態に照らし、措置法61条の4第3項の交際費等に当たると認めるのが相当である。
(2)X会社は、本件優待入場券の発行等に伴って生ずる費用はその製作、印刷費用のみである等と主張し、これに沿う証拠を提出するが、既に述べた事実関係の下におけるように、例えば、1日といった単位となる期間においてその対象となる者が相当の多数にわたりあらかじめその数を確定することが困難であることを踏まえ、一定の見込みに立って、それらの者に対して包括して特定の役務を提供することを事業とする法人が、当該役務を現に提供し、かつ、当該役務の提供を無償で受ける者がこれを有償で受ける者と別異の取扱いをされていない場合、当該役務の提供に要した費用は、当該役務の提供を受けた者との関係においては、これを無償で受けた者を含め、対象となった者全員に対する当該役務の提供のために支出されたとみるのが相当である。このことを基礎に、当該役務の提供に要した費用のうちこれを無償で受けた者に対応する分につきその全部又は一部が交際費等に当たるか否かを論ずることは、法人のする特定の行為について一定の政策的見地から法人税の課税の基礎となる所得の金額の計算に当たりそのために支出した費用の額を損金の額に算入しないものとすることによって抑制しようとする措置法61条の4の規定の趣旨と矛盾するものではない。これとは異なる前提に立つX会社の主張等は、いずれも採用することができない。
(3)証拠及び弁論の全趣旨によれば、本件裁決において、国税不服審判所長は、X会社の平成13年3月期ないし平成17年3月期における費用として各損益計算書の「原価計上額」欄記載のとおり計上されたところのうち、X会社の運営する遊園施設に入場等をした者に対する役務の提供に要した費用に相当するものである入場券売上げに対応する原価に関し、これとは異なるものであるとして商品売上原価、飲食売上原価、施設更新関連費、租税公課及び減価償却費を除いた上で、①入場券売上げに個別に対応する費用の金額と、②入場券売上げを含む他の売上げと共通する費用のうち入場券売上げに対応する部分の金額とを求め、その合計額をもってその金額を算定する方法を採り、本件優待入場券に係る費用相当額を算出したものであって、本件訴訟における国の主張もこれを基礎とするものであることが認められる。
そして、「左のうち、入場券売上げに対応する原価」の各金額の算出に当たっては、本件裁決がされるまでの間にX会社の提出した資料その他調査により収集された資料に基づき、各費用科目の内訳等についての分類がされた上で、入場券売上げを含む他の売上げと共通する費用のうち入場券売上げに対応する部分の金額については、X会社がその運営する遊園施設に入場等をした者に対して役務を提供するに当たって要する費用の主体が人件費であることを踏まえ、各売上げに個別に対応するとみられる人件費の割合を基礎に按分計算がされたもので、このようにして算出された上記の各金額については、その合理性を首肯することができる。
(4)ところで、証拠によれば、X会社は、U・ディズニー社に対し、ロイヤルティーとして、有償入場券や年間パスポート等の売上額の10パーセント相当額を支払っていることが認められるところ、X会社は、無償で交付された本件優待入場券についてはロイヤルティーが発生しないから、これを本件優待入場券を使用して入場等をする者に対してX会社の提供する役務に係る原価に含めるべきではないと主張する。しかしながら、前記認定のとおり、本件優待入場券を使用して入場等をする者は、有償入場券により入場等をする者と別異の取扱いをされることなく、X会社の役務の提供を受けることができるところ、X会社は、U・ディズニー社に対して上記ロイヤルティーを支払うことによって初めてその遊園施設を運営することができるものと推認されることからすれば、ロイヤルティーの金額が有償入場券の売上げを基に計算されるとしても、それは、X会社の運営する遊園施設に入場等をした者全員に対する役務の提供につき必要となる費用であり、当該役務に係る原価を構成するものと評価し得る。そして、上記のロイヤルティーは、入場券売上げに対応する原価中の入場券売上げに個別に対応する費用に当たると認めるのが相当である。
(5)そうすると、平成13年3月期ないし平成17年3月期における入場券売上げに対応する原価の金額は、323億円余ないし516億円余となる。
その上で、証拠及び弁論の全趣旨によれば、平成13年3月期ないし平成17年3月期における年間の総入場者数は、1,730万余人ないし2,547万余人であり、そのうち本件優待入場券を使用して入場等をした者の推計数は、27,873人ないし37,171人であると認められる。
してみると、本件優待入場券を使用して入場等をした者に対してX会社の提供した役務に係る原価のうちその者に対応する分については、本件各係争年度において1,869円ないし2,064円となり、以上に述べたところを基礎として上記の各係争年度におけるこれらの者に対して支出された交際費等の額を算定すると、5,605万余円ないし7,053万余円となる。
四、解説
はじめに
本件は、我が国を代表する遊園施設を運営するX会社に対する交際費課税が問題となったものである。具体的には、①本社ビル等の清掃業務の委託に介在したN会社に支払った本件委託料差額及び②役員・部長やマスコミ関係者に提供した本件優待入場券に係る費用相当額が、措置法61条の4にいう「交際費等」に該当するか否かが争われたものである。
①については、N会社の代表者甲が、いわゆる総会屋や右翼団体の幹部とされる人物で、地元対策等に多大な影響力を与えていると目されているだけに、一種の地元対策費としても考えられ、②については、優待入場券の交付などは多くのサービス業において行われているものと考えられるが、広告宣伝費等との区分が問題となる。また、従来の交際費課税においては、これらに類似事案が法廷で争われることはなかった(そのような課税関係が明らかにされることもなかった。)。したがって、本件は、交際費課税における「交際費等」の範囲を検討する上において、意義のある事案であると言える。
なお、本件各課税処分においては、本件委託料差額に関しては、7年間遡及して本件各更正が行われ、かつ、重加算税の各賦課決定が行われている。このことは、本件委託料差額に係る過少申告部分について、「偽りその他不正の行為によりその全部若しくは一部の税額を免れ」(通法70⑤)た事実があり、「納税者がその国税の課税標準等又は一部を隠ぺいし、又は仮装し、その隠ぺいし、又は仮装したところに基づき納税申告書を提出していた」(通法68①)ことを意味している。しかし、本件の事実関係からみて、そのような課税要件を充足したものと認め得るか否か必ずしも明らかではないが、それらが本訴の争点にもなっていない。したがって、X会社は、不服申立ての段階からこのような争点を争わなかったものと推測できるが、それらは、本件各更正の効力(7年遡及課税の是非等)にも深く関わる問題であるので、X会社側の争訟上の戦略が疑問視されるところである。
1 交際費等の意義と範囲
(1)措置法61条の4第1項は、法人が支出する交際費等の額は、所得の金額の計算上、損金の額に算入しないこととし、ただし、資本金の額が1億円以下等の中小法人に対してのみ、年600万円の90%相当額の損金算入を認めることとしている(注1)。
そして、この場合の「交際費等」とは、「交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為(<略>)のために支出するもの(<略>)をいう。」(措法61の4③)と定義されている。ただし、次に掲げる費用のいずれかに該当するものは、「交際費等」に当たらないとされている(措法61の4③、措令37の5)。
① 専ら従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行等のために通常要する費用
② 飲食その他これに類する行為のために要する費用(専ら当該法人の役員若しくは従業員又はこれらの親族に対する接待等のために支出するものを除く。)であって、その費用が1人当たり5,000円以下の費用
③ カレンダー、手帳、扇子、うちわ、手ぬぐいその他これらに類する物品を贈与するために通常要する費用
④ 会議に関連して、茶葉、弁当その他これらに類する飲食物を供与するために通常要する費用
⑤ 新聞、雑誌等の出版物又は放送番組を編集するために行われる座談会その他記事の収集のために又は放送のための取材に通常要する費用
(2)以上のような措置法上の交際費等の定義に照らせば、ある目的のために支出された費用が交際費等に該当するためには、本判決も判示するように、①支出の相手方(得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対するものであること)、②支出の目的(交際費、接待費、機密費その他の費用であること)及び③法人の行為の形態(接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出されたもであること)の三要件を充足する必要があると解されている(注2)。そして、これらの三要件の充足の有無は、個別の事案の事実関係に即して判断されることになる。
他方、前述のように、ある費用が交際費等に該当するか否かの判断が三要件に照らして判断されるにしても、隣接費用との区分が極めて困難であるが故に、実務上は、国税庁の取扱い通達(措置法通達)に依拠して判断される場合が多い。また、国税庁の措置法通達に依拠する課税処分が法廷で争われる場合には、当該裁判において、当該事案に即して措置法通達の取扱いの是非も判断されることになる。
ところで、措置法通達61の4(1)-1は、交際費等に意義について、「「交際費等」とは、交際費、接待費、機密費、その他の費用でその得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、きょう応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出するものをいうのであるが、主として次に掲げるような性質を有するものは交際費等には含まれないものとする。」と定めている。そして、交際費等に含まれない費用として、①寄附金、②値引及び割戻し、③広告宣伝費、④福利厚生費及び⑤給与等を挙げている。
また、措置法通達は、交際費等とこれら隣接費用との具体的区分について、数多くの取扱いを定めているところである(措通61の4(1)-2~61の4(2)-7参照)。
2 本件委託料差額の交際費等該当性
(1)本件委託料差額は、N会社に対して本件清掃業務の委託料として支払った本件委託料とN会社から実際に清掃業務を実施するC会社に支払われた本件再委託料との差額である。この本件委託料差額は、本件委託料の約40%を占めるが、C会社の利益率は、約8%というものである。また、N会社の代表者である甲は、いわゆる総会屋や右翼団体の幹部として地元対策等に多大な影響力を有しており、X会社の元代表者とも知己の間柄であったというのである。
かくして、このような性質を有する本件委託料差額が、前述の交際費等となる三要件を充足するか否かが問題となる。特に、支出の相手方であるN会社が、「その他事業に関係のある者」に該当するか否か、本件委託料差額が、「……これらに類する行為のために支出されたもの」であるか否かが問題となる。
これらの点について、本件各課税処分の論拠となる措置法通達では、交際費等の支出の相手方の範囲について、「「得意先、仕入先その他事業に関係のある者等」には、直接当該法人の営む事業に取引関係のある者だけではなく間接に当該法人の利害に関係のある者及び当該法人の役員、従業員、株主等も含むことに留意する。」(同通達61の4(1)-22)と定めている。
また、同通達は、本件委託料差額に関連するものと思われるものとして「いわゆる総会対策等のために支出する費用で総会屋等に対して会費、賛助金、寄附金、広告料、購読料等の名目で支出する金品に係るもの」及び「建設業者等が高層ビル、マンション等の建設に当たり、周辺の住民の同意を得るために、当該住民又はその関係者を旅行、観劇等に招待し、又はこれらの者に酒食を提供した場合におけるこれらの行為のために要した費用」を交際費等に該当する費用として明示している(同通達61の4(1)-15(6)(7))。
(2)かくして、本判決は、本件の事実関係を認定した上で、N会社の代表者である甲が措置法61条の4第3項にいう「その他事業に関係のある者等」に当たることは明らかであるとした上で、本件清掃業務に係る業務委託契約が更新され本件委託料が支払われたことにつき、「形式的には、N会社との間の本件清掃業務に係る業務委託契約に基づくものではあるが、実質的には、上記のような甲の社会的な立場を前提に、その影響力をX会社の事業の遂行、管理等に利用すべく、N会社を介し甲に経済的利益を提供して甲との関係を良好に保つものとしてされたもので、本件清掃業務の内容に応じ業務委託料として相当とされる金額を超える金銭の支払いについては、甲に対する謝礼又は贈答の趣旨でされたと認めるのが相当である。」と判示し、本件委託料差額については、前記のような支出の相手方、支出の目的および支出に係る行為の形態に照らし、「交際費等」に当たると認めるのが相当であると判示している。
ところで、本件委託料が支払われた背景には、X会社の設立において、大型な遊園施設等を建設するに当たって地元住民対策のために甲の尽力に預ったことも推測され、その後の住民対策等のためにもその必要があったものと推測されるので、本件委託料差額には、それらの尽力(役務提供)の対価であるとも解される。しかしながら、このような役務提供の対価であっても、本件委託料のような不明瞭な形で支出せざるを得ないというのであれば、本件委託料差額は、本判決が判示するように、「接待、供応……その他これらに類する行為のために支出するもの」と判断せざるを得ないものと考えられる。
3 本件優待入場券に係る費用相当額の交際費等該当性
(1)本件優待入場券は、X会社の役員等において重要な取引先と判断した企業に対して交付される役員扱い入場券とX会社が特に選定したいわゆるマスコミ関係者及びその家族に対して交付するプレス関係入場券に区分されている。いずれも、これを使用する者は、X会社が運営する遊園施設であるTディズニーランド等に無償で入場してその施設の利用等をすることができる。これらの各遊園施設は、我が国屈指の人気を得ているものであり、その入場及び施設の利用等に係る有償入場券の売価は、5,000円前後であったというものである。そして、本件優待入場券の使用者は、年間3万人前後というものである(因みに、総入場者数は、年間2,000万人を超える状況にある。)。
このように、自社の少額なサービスや製品を事業関係者等に提供して、販売促進や広告宣伝を目的とすることは、一般に行われている。特に、映画館等への招待入場券などは、よく見かけるところである。このような場合に、当該入場券等を交付する法人にとっては、特段の費用を支出するわけではなく、むしろ、当該入場券の使用者が、当該施設に付設されている食堂等を利用すれば、売上増に結びつくことも期待される。したがって、本件優待入場券のような本業としている自社のサービスを無償で提供する無料入場券等については、広告宣伝費等との区分も困難であり、その費用の額を正確に算定することも困難である。
(2)そこで、措置法通達は、本件優待券入場券の交付と類似する行為に伴って支出する費用について、次のような取扱いを定めている。
① 物品の交付については、一般的に交際費等とされるが、物品を交付する場合であっても、その物品が得意先である事業者において棚卸資産若しくは固定資産として販売し若しくは使用することが明らかな物品(事業用資産)又はその購入単価が少額(概ね3,000円以下)である物品(少額物品)であり、かつ、その交付の基準が売上割戻し等の算定基準と同一であるときは、これらの物品を交付するために要する費用は、交際費等に該当しないものとする(措通61の4(1)-4)。
② 不特定多数の者に対する宣伝的効果を意図するものは広告宣伝費の性質を有するものとし、次のようなものは、交際費等に含まれないものとする(措通61の4(1)-9)。
・一般の工場見学者等に製品の試飲、試食をさせる費用(これらの者に対する通常の茶菓子等の接待に要する費用を含む。)
・得意先等に対する見本品、試用品の供与に通常要する費用
・製造業者又は卸売業者が、自己の製品又はその取扱商品に関し、これらの者の依頼に基づき、継続的に試用を行った一般消費者又は消費動向調査に協力した一般消費者に対しその謝礼として金品を交付するために通常要する費用
③ 法人が不特定又は多数の被災者を救援するために緊急に行う自社製品等の提供に要する費用は、交際費等に該当しないものとする(措通61の4(1)-10の4)。
なお、前述したように、カレンダー、手帳、扇子、うちわ、手ぬぐいその他これらに類する物品を贈与するために通常要する費用は、政令の定め(措令37の5)によって交際費等に当たらないとされているが、高額なカレンダー等の贈与に要する費用は、交際費等に当たると解されている(注3)。
以上の取扱い等に照らしても、①支出の相手方が「事業に関係のある者等」に該当するか、②支出の目的や形態が、接待、供応等に類するものであるか、等について必ずしも判然としないところがある。更に、本件優待入場券の交付が「交際費等」の支出に当たるとしても、その金額を算定することも困難である。
(3)かくして、本判決は、本件優待入場券の発行・交付・使用の事実関係を認定した上で、「X会社の遂行する事業に関係のある企業及びマスコミ関係者等の特定の者に対し、その歓心を買って関係を良好なものとしX会社の事業を円滑に遂行すべく、接待又は供応の趣旨でされたと認めるのが相当であり、これを使用して入場等をした者に対して役務を提供するに当たりX会社が支出した上記の費用については、上記のような支出の相手方、支出の目的及び支出に係る行為の形態に照らし、措置法61条の4第3項の交際費等に当たる」と判示した。
また、交際費等の額については、X会社が本件優待入場券の交付のために直接(特別に)要した印刷代等の金額は1枚当たり2~5円程度に過ぎない旨主張したことに対し、本判決は、「包括して特定の役務を提供することを事業とする法人が、当該役務を現に提供し、かつ、当該役務の提供を無償で受ける者がこれを有償で受ける者と別異の取扱いをされていない場合、当該役務の提供に要した費用は、当該役務の提供を受けた者との関係においては、これを無償で受けた者を含め、対象となった者全員に対する当該役務の提供のために支出されたとみるのが相当である。」と判示し、X会社の損益計算上の「原価計上額」を基礎として、全入場者1人当たりの費用額を本件各係争年度別に1,869円ないし2,064円と認定した。
(4)本判決は、要するに、①役員扱い入場者は、役員又は部長の判断で特に重要な得意先に交付し、プレス関係入場券は、X会社が特に選定したマスコミ関係者に交付しているから、本件優待入場券に係る費用の相手方は事業に関係のある者等に当たること、②本件優待入場券の使用に係る費用の支出の目的は、これらの者との親睦の度を密にして取引関係の円滑な進行を図るためであること、及び③本件優待入場券の使用に係る費用は、その支出の原因となる行為の形態が接待等に当たること、という交際費等該当性の三要件を充足する、というものである。
そうであれば、他の映画興業会社、鉄道会社等が、自社が営むサービス業について無料入場券を発行・交付した場合に、本件優待入場券のように、全て交際費課税が適用されるか否かが問題となる。いずれの無料入場券等の交付も、何らかの形で事業に関係する者に交付・使用されるものであろうし、それらの者に対して歓心を買いあるいは贈与する意図も否定し難い場合もあろうし、当該入場券等に要する費用の額についても、本件優待入場券に係る費用のように算定することも可能であろう。しかしながら、反面、一般的な無料入場券等は、広告宣伝的なもの、あるいはカレンダー、手ぬぐいなどに類する少額な物品程度のものであるとも解される。
してみると、本判決が本件優待入場券に係る費用相当額を交際費等に当たると認定したことは、他の一般的な無料入場券等に対する交際費課税の先例となるかについては疑問が残る。けだし、本件優待入場券は、我が国随一ともいえる遊園施設の利用券であって多くの人にとっても利用価値も高く、有料入場券の5,000円程度の価値を有するものであるから、それを交付することは、「接待、贈答」等の色彩が強いものといえる。他方、他の一般的な無料入場券等は、本件優待入場券のような利用価値の高いものは少なく、むしろ、広告宣伝的な色彩を有する場合が多いように考えられる。
したがって、本判決については、他の事案に影響を及ぼすにしても、本件優待入場券のような利用価値の高い無料入場券等に限定して、先例として考慮されるべきものと考えられる。
4 本判決の意義と問題点
(1)以上のように、本件は、①本社ビル等の清掃業務の委託に介在したN会社(代表者は、いわゆる総会屋等として、地元対策等に尽力があったものと推測される。)に支払った本件委託料と実際に清掃業務を実施する業者に対して支払った本件再委託料との差額(本件委託料差額)が交際費等に当たるか否か、及び②役員・部長又はマスコミ関係者を通じて交付した無料入場券(本件優待入場券)に係る費用相当額が交際費等に当たるか否かが争われたものである。
①については、N会社の代表である甲に対して便宜を図ったことの費用として「交際費等」に当たるか、②については、他のサービス提供会社における自社サービスへの無料入場券との異同や本件優待入場券に係る費用相当額の算定方法等が、それぞれ主として問題になったものである。
かくして、本判決は、前述のように、交際費等該当性の三要件に照らし、①及び②についても、交際費等に該当すると判示した。このような判決は、類似する費用の交際費等該当性が法廷で争われることがほとんど見られなかっただけに、一つの先例として参考になる。
(2)しかしながら、本件委託料差額については、それに係る過少申告において、「偽りその他不正の行為によりその全部若しくは一部の税額を免れ」たとして、更正の期間制限が7年に延長され、「隠ぺい又は仮装」したところにより納税申告書を提出したとして、重加算税の賦課決定が行われている。いずれも、国税通則法の関係条項の解釈上論点がありそうである。しかし、そのような争点は、本訴において何ら争われることはなかったが、X会社側の争訟戦略に疑問が残るところである。
また、本件優待入場券に関しては、他のサービス提供会社における無料入場券等への交際費課税の影響が懸念されることになる。しかし、本件優待入場券については、前述のような特殊性が認められるところであるので、他の無料入場券等への影響が一律に生じるものとも考えられない。もちろん、今後、課税庁がどのように対処するかについては注目する必要がある。
いずれにしても、本判決が控訴審でも争われるようであれば、その判決に注目する必要がある。
(注1)交際費課税の趣旨及び沿革については、武田昌輔『即答 交際費課税─理論と実務』(財経詳報社、平成16年)2頁以下等参照。
(注2)山本守之「事例研究 交際費」日本税務研究センター編『認定賞与・寄附金・交際費等の総合的検討』(財経詳報社、平成16年)所収233頁、大渕博義『法人税法解釈の検証と実践的展開』(税務経理協会、平成21年)529頁等参照。
(注3)前出(注1)109頁等参照。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -

Copyright (C) 2019
SHINNIPPON-HOKI PUBLISHING CO.,LTD.




















