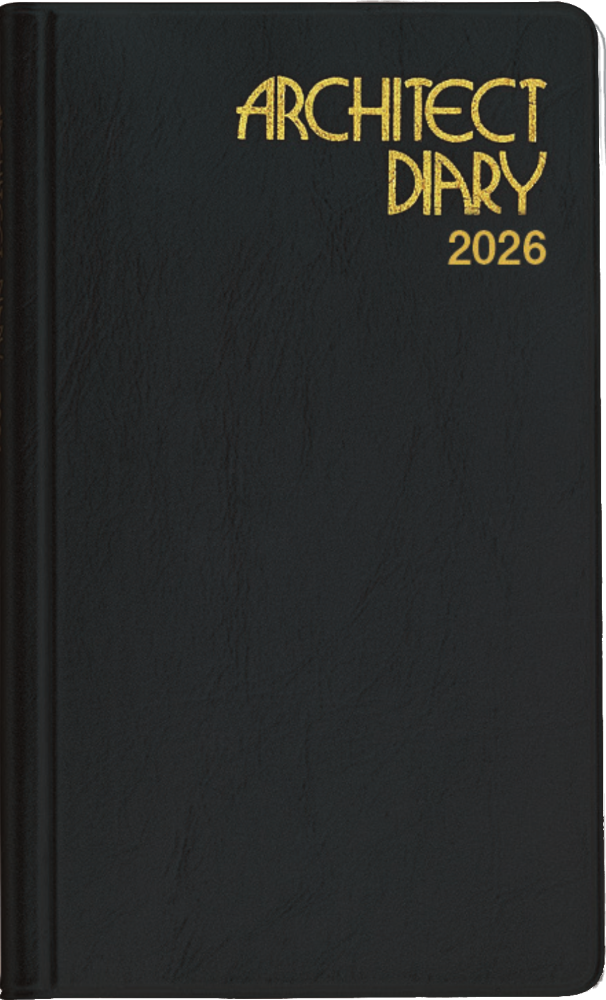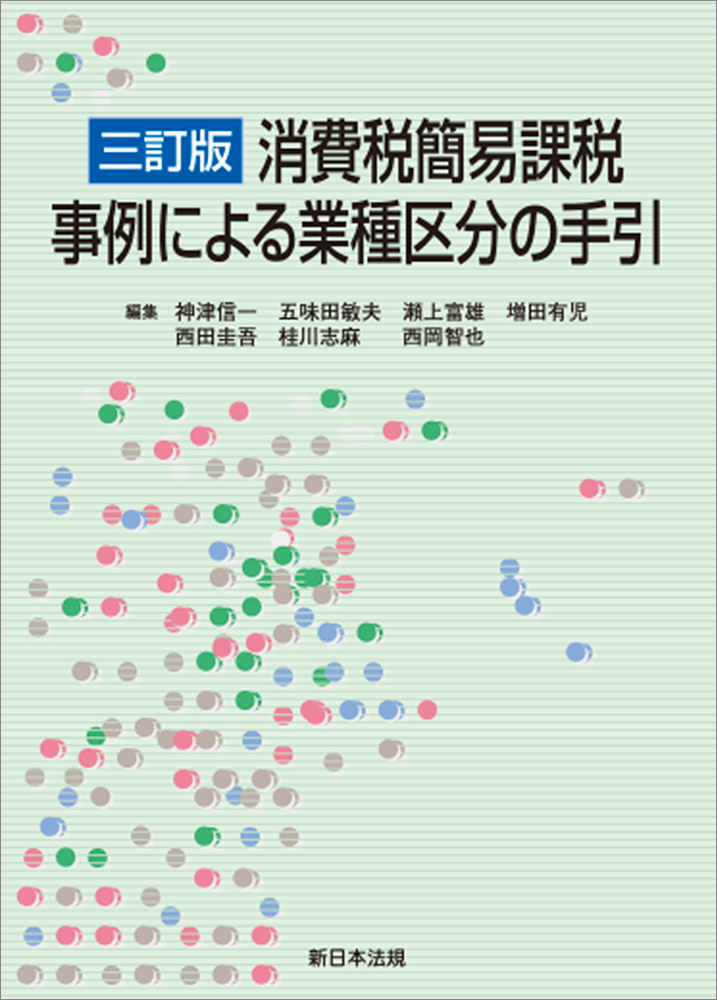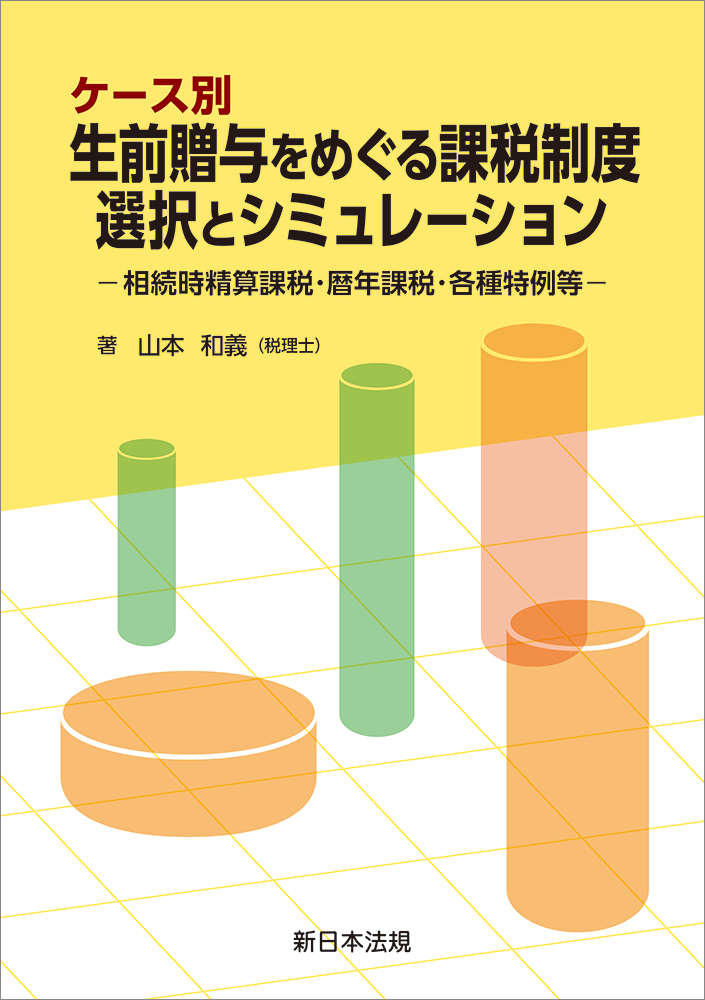解説記事2010年08月23日 【巻頭特集】 有価証券の売出しに係る新しい開示規制と実務への影響(2010年8月23日号・№367)
規制や適用場面に関する理解を深める!
有価証券の売出しに係る新しい開示規制と実務への影響
森・濱田松本法律事務所 弁護士 中村 聡
金融商品取引法の平成21年改正(平成21年6月24日法律第58号による)では、「有価証券の売出し」に関して定義が見直されるとともに「私売出し」「外国証券売出し」といった新たな概念・制度が設けられ、開示規制上、大幅な改正が施された。本改正は4月1日に施行されており、本稿では、改正後の実務において特に留意すべき点を、主に上場会社である発行会社関係者を対象にご紹介いただく。(編集部)
Ⅰ.はじめに
平成22年4月1日から施行された金融商品取引法の平成21年改正法により、有価証券の売出しに係る開示規制については、売出しの定義から従来の「均一の条件」という要件を削除し、募集の定義と類似の要件の構成とする、また外国証券売出しという類型を新たに設けて、緩和された情報提供の枠組みを設けるなど、大きな見直しが行われた。
有価証券の売出しに係る新しい開示規制の概要全般および改正の趣旨については、谷口義幸「『有価証券の売出し』に係る開示規制の見直しの要点」(本誌361号25頁参照。以下「谷口解説」という)において概説されているので、そちらを参照されたい。
本稿では、有価証券の売出しに係る新しい開示規制において、主として上場会社である発行会社およびその関係者を念頭に置き、規制の要点を整理するとともに、有価証券所有者の出口戦略その他の実務的観点から留意が必要ないくつかの事項について検討する(脚注1)。
Ⅱ.有価証券の売出しの定義
1.売出しの定義の再構成 有価証券の売出しは、既に発行された有価証券の売付けの申込みまたはその買付けの申込みの勧誘(定義府令9条で定める取得勧誘類似行為および定義府令13条の2で定めるもの(脚注2)を除く。以下「売付け勧誘等」という)のうち、施行令1条の7の3で定める有価証券の取引に係るものを除き、次のものをいうと定義される(法2条4項)。
既発行の第一項有価証券に係る勧誘が有価証券の売出しに該当するかの判断は、図表1記載のフローチャートのとおり、整理することができる。
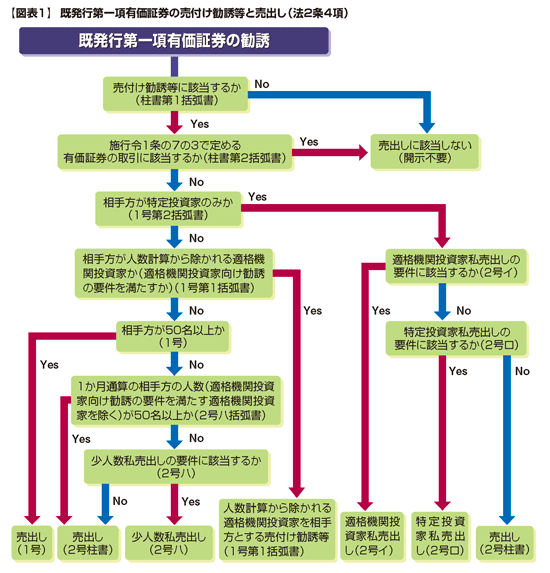
有価証券の売出しの定義の条文構造は、有価証券の募集(法2条3項)の定義と概ね同様となり、第一項有価証券の場合、原則として、50名以上の者を相手方として売付け勧誘等を行う場合(前掲①)が該当するほか、適格機関投資家私売出し、特定投資家私売出しおよび少人数私売出しのいずれの要件も満たさない場合(前掲②)が該当する。
そして、有価証券の私募と同様、私売出しの場合にも、上場会社の上場株券等は継続開示義務に服するため、私売出しの対象とすることはできず(施行令1条の7の4第1号イ、1条の8の2第1号イ、1条の8の3第3号イ参照)、誰が所有者であるかを問わず、また相手方の人数および属性を問わず、後述の適用除外取引に該当しない限り、必ず、売出しの定義に該当することには留意が必要である。
なお、優先株式の場合には、剰余金の配当または残余財産の分配が同一の内容である優先株式であって継続開示義務に服するものを既に発行していなければ、いずれかの私売出しの要件を満たすことが可能である。
2.適用除外取引 前述のとおり、売出しの定義が再構成され、売出しに該当する範囲が拡がったため、政令で売出しの定義から除外される有価証券の取引(法2条4項柱書第2括弧書、施行令1条の7の3)も大幅に拡大されている。
金融商品取引業者等ではない既発行有価証券の一般所有者にとって、利用可能な適用除外取引としては、主として、次のものがある(施行令1条の7の3)。
前述のとおり、上場株券等については、適用除外取引のいずれかに該当しない限り、売出しの定義に該当するため、上場株券等の一般所有者が売付け勧誘等(ひいては売買)を行う場合には、主にこれらの適用除外取引に該当するかの検討を行うことが必要である。
(1)取引所市場や業者を通じた売買 まず、取引所市場における売買(ToSTNeT取引を含む)は、売出規制に服せず、自由に行うことができる。PTSによる売買も同様である。所有者が特定投資家である場合には、金融商品取引業者等または他の特定投資家を相手方とするブロックトレードを行うことにより、売出規制に服することを回避できる。
(2)取引所市場外における売買 また、取引所市場外の売買であっても、上場株券等は譲渡制限のない有価証券であるため、「発行者関係者等」以外の所有者は、売出規制に服することなく、自由に売買することができる。
これに対して、「発行者関係者等」の取引所市場外の売買は、「発行者関係者等」間における売買(脚注7)は売出規制に服しないが、「発行者関係者等」以外の者に対して売却する場合には、他の適用除外取引に該当しない限り、売出規制に服することとなる。この場合には、情報の非対称性、販売圧力が存在すると考えられるからであると説明されている(脚注8)。
(3)主要株主などの上場株券等の譲渡 したがって、主要株主など発行者関係者等が上場株券等を売却する場合、取引所市場で行う場合は適用除外取引となるが、オークション市場では市場価格などに対するマーケットインパクトが大きいという問題があり、他方、取引所市場外で行う場合には、相手方が金融商品取引業者等など発行者関係者等でない限り、相手方が1名でも、また相手方が自らの関係会社であっても、原則として、売出しに該当することとなるため、所有株式の処分に係る出口戦略あるいはグループ再編戦略は大いに制約される。
そこで、主要株主など発行者関係者等の所有株式の処分については、いずれの適用除外取引として行うこととするかが実務上の重要な検討課題となる。
(4)発行者の買戻し 自己株式取得や社債の買入れなどの場合に、所有者が発行者に対して売り付けることや、発行者に売付けを行おうとする者(脚注9)に対して売付けをすることは、適用除外取引とされている。
3.売付け勧誘等の概念 適用除外取引に該当しない場合であっても、そもそも「売付け勧誘等」の定義(法2条4項柱書第1括弧書)に該当しない場合には、売出しに該当しないこととなる。
前述のとおり、取得勧誘類似行為に該当するもの(自己株式処分の場合など。法2条3項柱書、定義府令9条)および定義府令13条の2で定めるもの(認可金融商品取引業協会の協会員に対する有価証券に関する情報の提供など)が除かれる。
また、勧誘とは、一般的には、特定の有価証券についての投資者の関心を高め、その取得・買付けを促進することとなる行為と解されており(脚注10)、このような勧誘に該当しない場合は売付け勧誘等の定義に当たらないと考えられる。
(1)公開買付けへの応募等 発行会社以外の者による他社株公開買付けが行われる場合、取引所市場外における売買であるため、主要株主など発行者関係者等が公開買付けに応じて売り付けることが、適用除外取引に該当せず、売出しに該当しないかが問題となりうるが、公開買付けへの応募は勧誘行為ではないと考えられている(脚注11)。
しかし、公開買付けに先立って、主要株主など発行者関係者等が公開買付者と応募契約を締結する場合に、勧誘行為があったとみられるか否かは明らかではなく、具体的な状況次第とは思われるものの、売出しに該当すると取り扱われるおそれがある。
また、主要株主など発行者関係者等が所有株式の売却のため入札手続を経て、勝ち残った買主が公開買付けを行う場合には、公開買付けに先立つ入札過程において発行者関係者等による勧誘行為があったとみられるおそれがある。
(2)株主間のプットまたはコール 上場会社の場合、例は少ないが、株主間で締結された契約により、所有株式について一方が売付けの権利(プット)または買付けの権利(コール)を有することがある。この場合、大量保有報告規制の共同保有者とならないか、公開買付規制の特別関係者とならないかという問題とは別に、売出規制に服しないかも問題となると思われる。
まず、発行者関係者等以外の者が所有する上場株券が売買の対象となる場合には、前述の適用除外取引に該当する(施行令1条の7の3第7号)。
これに対して、発行者関係者等が所有する上場株券が売買の対象となる場合には、買付けを行う相手方が、発行者関係者等であるときは前述の別な適用除外取引に該当し(施行令1条の7の3第8号)、発行者関係者等でないときはいずれの適用除外取引にも該当しないことが多いと思われる。
ただし、この場合であっても、具体的な状況次第ではあるものの、買付けを行う者がコールを行使して売買が成立する場合には、そもそも売付け側の株主に勧誘行為がないとみる余地があるものと思われる。
Ⅲ.売出しと発行開示規制
1.届出その他の開示規制 有価証券の売出しの定義(法2条4項)に該当した場合は、届出免除事由のいずれかに該当しない限り、発行会社が届出をしているものでなければ行うことができない(法4条1項)。有価証券の売出しについての届出の要否は、届出免除事由(同項1号〜5号)に該当するかに従って、図表2(今号6頁参照)記載のフローチャートのとおり、整理することができる(脚注12)。
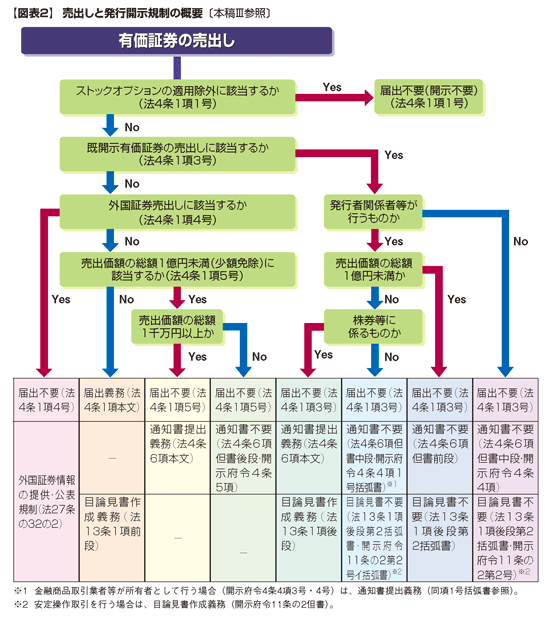
平成21年改正により、届出免除事由として追加された外国証券の売出し(法4条1項4号)については、届出のほか、目論見書の作成および有価証券通知書の提出も不要としつつ、簡易な情報提供として外国証券情報の提供・公表の規制が設けられている(法27条の32の2)。
また、平成21年改正により、法定の「開示が行われている場合」(法4条7項)の有価証券(以下「既開示有価証券」という)の売出しに係る目論見書の作成義務および有価証券通知書の提出義務の枠組みが変更されているが、これについては項を改める。
なお、有価証券の発行者は、売出し、すなわち勧誘が始められる前に届出を行うことが必要であり(法4条1項)、有価証券通知書の提出も、特定募集等である売出しが開始される日の前日までに行うことが必要である(同条6項)。目論見書については、発行者・売出人・引受人・金融商品取引業者などが、原則として、売付けに係る合意が成立する以前に交付しなければならない(法15条2項)。
2.既開示有価証券の売出し 上場有価証券など既開示有価証券の売出しについては、従来から、届出義務が免除されていたが(法4条1項3号)、目論見書に関しては、届出売出しの場合と並んで、売出価額の総額が1億円未満でない限り、作成義務が課されていた。また、売出価額の総額が1億円未満でない限り、有価証券通知書の提出義務が課されていた。
平成21年改正後は、既開示有価証券の売出しについての目論見書作成義務および有価証券通知書の提出義務が緩和され、発行者関係者等(脚注13)以外の者が行う場合には、安定操作取引を行うときを除き、目論見書の作成は不要であり(法13条1項後段第2括弧書、開示府令11条の2第2号、同条但書)、また有価証券通知書の提出も不要である(法4条6項但書中段、開示府令4条4項)。
これに対して、発行者関係者等が所有者である既開示有価証券の売出しを行う場合には、売出価額の総額が1億円以上であって、株券等(脚注14)に係る売出しであるときは、発行者において、目論見書の作成義務(法13条1項後段)および有価証券通知書の提出義務(法4条6項本文)が生じる。
売出価額の総額が1億円未満の場合は、目論見書の作成は不要であり(法13条1項後段第2括弧書)、有価証券通知書の提出も不要である(法4条6項但書前段)(脚注15)。
株券等以外の有価証券(社債券など)の売出しであるときは、安定操作取引を行うときを除き、目論見書の作成は不要であり(法13条1項後段第2括弧書、開示府令11条の2第2号イ括弧書、同条但書)、また有価証券通知書の提出も原則として不要であるが、金融商品取引業者等が所有者として行う場合にだけは提出義務がある(法4条6項但書中段、開示府令4条4項1号括弧書)。
このような既開示有価証券の売出しについての目論見書作成義務および有価証券通知書の提出義務は、図表2記載のフローチャートのとおり、整理することができる。
なお、目論見書の作成が不要である場合に、任意に目論見書相当の説明文書を作成することは可能であるが、その場合は、目論見書ではなく販売資料(法13条5項)に該当するものと考えられる(脚注16)。
脚注
1 本稿では、「金融商品取引法」を「法」、「金融商品取引法施行令」を「施行令」、「金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令」を「定義府令」、「企業内容等の開示に関する内閣府令」を「開示府令」と表記する。
2 認可金融商品取引業協会がその協会員に対して行う店頭売買、取扱有価証券の売買および上場株券等の取引所市場外での売買に関する事項の通知その他法令上の義務の履行として行う有価証券に関する情報の提供や、認可金融商品取引業協会などに対してその規則に基づき行われる有価証券に関する情報の提供が定められている。
3 本稿では、法2条4項2号イの要件を満たす場合を「適格機関投資家私売出し」、同号ロの要件を満たす場合を「特定投資家私売出し」、同号ハの要件を満たす場合を「少人数私売出し」といい、併せて「私売出し」と総称する。
4 ブロックトレード等が想定されている(平成21年金融商品取引法等の一部改正に係る政令案・内閣府令案等に関する平成21年12月22日付「コメントの概要及びコメントに対する金融庁の考え方」9頁21番、谷口解説28頁)。
5 本稿Ⅱでは、(イ)発行者、(ロ)発行者である法人の役員または発起人その他これに準ずる者、(ハ)主要株主(法163条1項の定義により、原則として、総株主等の議決権の10%以上の議決権を保有している株主をいう)または法人である主要株主の役員または発起人その他これに準ずる者、(ニ)発行者である法人の子会社その他これに準ずる法人またはこれらの役員もしくは発起人その他これに準ずる者、(ホ)金融商品取引業者等を意味して用いる(施行令1条の7の3第7号イ~ホ)。
6 金融商品取引業者等による積極的な勧誘がない場合であって、顧客からの注文に対し当該注文に応じるための取引についてのものであると説明されている(「企業内容等の開示に関する内閣府令(案)」等に関する平成22年3月31日付「コメントの概要及びコメントに対する金融庁の考え方」54頁180番)。
7 当事者の双方が金融商品取引業者等であるものが除外されているが、専門業者間取引として他の規定(基本的に、譲渡制限のない海外発行証券の売買に関する適用除外取引)が適用されると考えられるためと説明されている(前掲注4・「コメントの概要及びコメントに対する金融庁の考え方」15頁48番、谷口義幸「『有価証券の売出し』に係る開示規制の見直しの概要〔上〕」商事法務1902号40頁)。
8 前掲注7・谷口40頁。
9 この者が有価証券の売買を行うことを業とする場合には、業規制の問題があるため、基本的に、金融商品取引業者等が想定されていると思われる。
10 たとえば、神崎克郎=志谷匡史=川口恭弘『証券取引法』(青林書院、2006年)217頁。なお、勧誘概念に関する問題状況をまとめた近時の文献として、金融法委員会の平成22年6月1日付「金融商品取引法の開示規制上の『勧誘』の解釈を巡る現状と課題」がある。
11 平成21年金融商品取引法等の一部改正等に係る企業内容等の開示制度における内閣府令案等に関する平成21年12月28日付「コメントの概要及びコメントに対する金融庁の考え方」16頁62番。
12 説明の便宜上、特定組織再編成交付手続に係る場合を省略する。
13 本稿Ⅲでは、(1)発行者、(2)(イ)発行者の子会社または主要株主(法163条1項の定義により、原則として、総株主等の議決権の10%以上の議決権を保有している株主をいう)、(ロ)発行者の役員または発起人、(ハ)発行者の子会社の役員または発起人、(ニ)発行者が外国会社その他の会社以外の者の場合は(イ)~(ハ)に類するもの、(3)有価証券を他の者に取得させることを目的として(1)および(2)に掲げる者からその保有有価証券を取得した金融商品取引業者等、(4)有価証券の売出しに係る引受人(残額引受契約をした者に限る)に該当する金融商品取引業者等を意味して用いる(開示府令4条4項1号~4号、11条の2第2号イ~ニ)。
14 本稿Ⅲでは、株券、新株予約権証券、新株予約権が付されている有価証券もしくは株券に転換しうる有価証券または外国有価証券のうちこれらの有価証券の性質を有するものを意味して用いる(開示府令4条4項1号括弧書、11条の2第2号イ括弧書)。
15 既開示有価証券の売出しの場合の有価証券通知書提出義務の例外として、改正により追加された発行者関係者等以外の者が行うもの(法4条6項但書中段)のほか、従来からある売出価額の総額が1億円未満のもの(同前段)が利用可能かという解釈上の問題がありうる。改正前においては既開示有価証券の売出しの有価証券通知書提出義務の基準が売出価額の総額が1億円未満か否かとされていたこと、また、目論見書は有価証券通知書の添付書類として提出されるところ、目論見書の交付を必要とする場合については引き続き有価証券通知書の提出を求めることとされたと説明されていること(谷口義幸「『有価証券の売出し』に係る開示規制の見直しの概要〔下〕」商事法務1903号40頁)に照らし、発行者関係者等が行うものであっても、売出価額の総額が1億円未満である場合には、改正前と同様、有価証券通知書の提出は不要と考えるのが合理的と思われる。
16 前掲注6・「コメントの概要及びコメントに対する金融庁の考え方」54頁181番。
有価証券の売出しに係る新しい開示規制と実務への影響
森・濱田松本法律事務所 弁護士 中村 聡
金融商品取引法の平成21年改正(平成21年6月24日法律第58号による)では、「有価証券の売出し」に関して定義が見直されるとともに「私売出し」「外国証券売出し」といった新たな概念・制度が設けられ、開示規制上、大幅な改正が施された。本改正は4月1日に施行されており、本稿では、改正後の実務において特に留意すべき点を、主に上場会社である発行会社関係者を対象にご紹介いただく。(編集部)
Ⅰ.はじめに
平成22年4月1日から施行された金融商品取引法の平成21年改正法により、有価証券の売出しに係る開示規制については、売出しの定義から従来の「均一の条件」という要件を削除し、募集の定義と類似の要件の構成とする、また外国証券売出しという類型を新たに設けて、緩和された情報提供の枠組みを設けるなど、大きな見直しが行われた。
有価証券の売出しに係る新しい開示規制の概要全般および改正の趣旨については、谷口義幸「『有価証券の売出し』に係る開示規制の見直しの要点」(本誌361号25頁参照。以下「谷口解説」という)において概説されているので、そちらを参照されたい。
本稿では、有価証券の売出しに係る新しい開示規制において、主として上場会社である発行会社およびその関係者を念頭に置き、規制の要点を整理するとともに、有価証券所有者の出口戦略その他の実務的観点から留意が必要ないくつかの事項について検討する(脚注1)。
Ⅱ.有価証券の売出しの定義
1.売出しの定義の再構成 有価証券の売出しは、既に発行された有価証券の売付けの申込みまたはその買付けの申込みの勧誘(定義府令9条で定める取得勧誘類似行為および定義府令13条の2で定めるもの(脚注2)を除く。以下「売付け勧誘等」という)のうち、施行令1条の7の3で定める有価証券の取引に係るものを除き、次のものをいうと定義される(法2条4項)。
| (1)第一項有価証券に係るものである場合 ① 50名以上の者(適格機関投資家向け勧誘の要件を満たす場合(施行令1条の7の4)の適格機関投資家を除く)を相手方として行う場合(特定投資家のみを相手方とする場合を除く)(法2条4項1号、施行令1条の8) ② そのほか、次に掲げる場合のいずれにも該当しない場合(法2条4項2号柱書)(脚注3) イ 適格機関投資家私売出し ロ 特定投資家私売出し ハ 少人数私売出し (2) 第二項有価証券に係るものである場合 その売付け勧誘等に応じることにより500名以上の者が当該売付け勧誘等に係る有価証券を所有することとなる場合(法2条4項3号、施行令1条の8の5) |
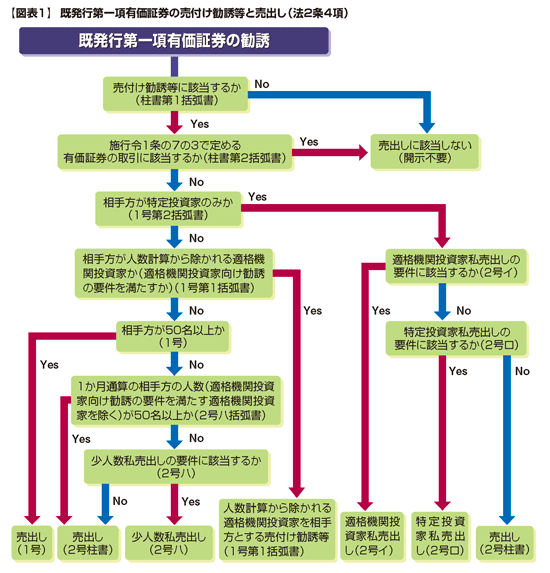
有価証券の売出しの定義の条文構造は、有価証券の募集(法2条3項)の定義と概ね同様となり、第一項有価証券の場合、原則として、50名以上の者を相手方として売付け勧誘等を行う場合(前掲①)が該当するほか、適格機関投資家私売出し、特定投資家私売出しおよび少人数私売出しのいずれの要件も満たさない場合(前掲②)が該当する。
そして、有価証券の私募と同様、私売出しの場合にも、上場会社の上場株券等は継続開示義務に服するため、私売出しの対象とすることはできず(施行令1条の7の4第1号イ、1条の8の2第1号イ、1条の8の3第3号イ参照)、誰が所有者であるかを問わず、また相手方の人数および属性を問わず、後述の適用除外取引に該当しない限り、必ず、売出しの定義に該当することには留意が必要である。
なお、優先株式の場合には、剰余金の配当または残余財産の分配が同一の内容である優先株式であって継続開示義務に服するものを既に発行していなければ、いずれかの私売出しの要件を満たすことが可能である。
2.適用除外取引 前述のとおり、売出しの定義が再構成され、売出しに該当する範囲が拡がったため、政令で売出しの定義から除外される有価証券の取引(法2条4項柱書第2括弧書、施行令1条の7の3)も大幅に拡大されている。
金融商品取引業者等ではない既発行有価証券の一般所有者にとって、利用可能な適用除外取引としては、主として、次のものがある(施行令1条の7の3)。
| ・取引所市場における売買(1号) ・私設取引システム(PTS)による有価証券の売買(3号) ・金融商品取引業者等または特定投資家が他の金融商品取引業者等または特定投資家と行う取引所市場外の売買のうち、公正な価格形成および流通の円滑を図るために行うものであって、取引所市場における売買価格を基礎として取引状況を勘案した適正な価格で行うもの(脚注4)(4号) ・私募または私売出しが行われていない有価証券(譲渡制限のない有価証券)であって、「発行者関係者等」(脚注5)以外の者が所有するものの売買(7号) ・譲渡制限のない有価証券の売買であって、その当事者の双方が発行者関係者等であるもの(双方が金融商品取引業者等であるものを除く)(8号) ・発行者または発行者に対する有価証券の売付けを行おうとする者(その者に対して売付けを行おうとする者を含む)に対する有価証券の売付け(10号) ・金融商品取引業者等が顧客のために取引所市場または外国市場における有価証券の売買の取次ぎを行うことに伴う有価証券の売買(脚注6)(11号) |
(1)取引所市場や業者を通じた売買 まず、取引所市場における売買(ToSTNeT取引を含む)は、売出規制に服せず、自由に行うことができる。PTSによる売買も同様である。所有者が特定投資家である場合には、金融商品取引業者等または他の特定投資家を相手方とするブロックトレードを行うことにより、売出規制に服することを回避できる。
(2)取引所市場外における売買 また、取引所市場外の売買であっても、上場株券等は譲渡制限のない有価証券であるため、「発行者関係者等」以外の所有者は、売出規制に服することなく、自由に売買することができる。
これに対して、「発行者関係者等」の取引所市場外の売買は、「発行者関係者等」間における売買(脚注7)は売出規制に服しないが、「発行者関係者等」以外の者に対して売却する場合には、他の適用除外取引に該当しない限り、売出規制に服することとなる。この場合には、情報の非対称性、販売圧力が存在すると考えられるからであると説明されている(脚注8)。
(3)主要株主などの上場株券等の譲渡 したがって、主要株主など発行者関係者等が上場株券等を売却する場合、取引所市場で行う場合は適用除外取引となるが、オークション市場では市場価格などに対するマーケットインパクトが大きいという問題があり、他方、取引所市場外で行う場合には、相手方が金融商品取引業者等など発行者関係者等でない限り、相手方が1名でも、また相手方が自らの関係会社であっても、原則として、売出しに該当することとなるため、所有株式の処分に係る出口戦略あるいはグループ再編戦略は大いに制約される。
そこで、主要株主など発行者関係者等の所有株式の処分については、いずれの適用除外取引として行うこととするかが実務上の重要な検討課題となる。
(4)発行者の買戻し 自己株式取得や社債の買入れなどの場合に、所有者が発行者に対して売り付けることや、発行者に売付けを行おうとする者(脚注9)に対して売付けをすることは、適用除外取引とされている。
3.売付け勧誘等の概念 適用除外取引に該当しない場合であっても、そもそも「売付け勧誘等」の定義(法2条4項柱書第1括弧書)に該当しない場合には、売出しに該当しないこととなる。
前述のとおり、取得勧誘類似行為に該当するもの(自己株式処分の場合など。法2条3項柱書、定義府令9条)および定義府令13条の2で定めるもの(認可金融商品取引業協会の協会員に対する有価証券に関する情報の提供など)が除かれる。
また、勧誘とは、一般的には、特定の有価証券についての投資者の関心を高め、その取得・買付けを促進することとなる行為と解されており(脚注10)、このような勧誘に該当しない場合は売付け勧誘等の定義に当たらないと考えられる。
(1)公開買付けへの応募等 発行会社以外の者による他社株公開買付けが行われる場合、取引所市場外における売買であるため、主要株主など発行者関係者等が公開買付けに応じて売り付けることが、適用除外取引に該当せず、売出しに該当しないかが問題となりうるが、公開買付けへの応募は勧誘行為ではないと考えられている(脚注11)。
しかし、公開買付けに先立って、主要株主など発行者関係者等が公開買付者と応募契約を締結する場合に、勧誘行為があったとみられるか否かは明らかではなく、具体的な状況次第とは思われるものの、売出しに該当すると取り扱われるおそれがある。
また、主要株主など発行者関係者等が所有株式の売却のため入札手続を経て、勝ち残った買主が公開買付けを行う場合には、公開買付けに先立つ入札過程において発行者関係者等による勧誘行為があったとみられるおそれがある。
(2)株主間のプットまたはコール 上場会社の場合、例は少ないが、株主間で締結された契約により、所有株式について一方が売付けの権利(プット)または買付けの権利(コール)を有することがある。この場合、大量保有報告規制の共同保有者とならないか、公開買付規制の特別関係者とならないかという問題とは別に、売出規制に服しないかも問題となると思われる。
まず、発行者関係者等以外の者が所有する上場株券が売買の対象となる場合には、前述の適用除外取引に該当する(施行令1条の7の3第7号)。
これに対して、発行者関係者等が所有する上場株券が売買の対象となる場合には、買付けを行う相手方が、発行者関係者等であるときは前述の別な適用除外取引に該当し(施行令1条の7の3第8号)、発行者関係者等でないときはいずれの適用除外取引にも該当しないことが多いと思われる。
ただし、この場合であっても、具体的な状況次第ではあるものの、買付けを行う者がコールを行使して売買が成立する場合には、そもそも売付け側の株主に勧誘行為がないとみる余地があるものと思われる。
Ⅲ.売出しと発行開示規制
1.届出その他の開示規制 有価証券の売出しの定義(法2条4項)に該当した場合は、届出免除事由のいずれかに該当しない限り、発行会社が届出をしているものでなければ行うことができない(法4条1項)。有価証券の売出しについての届出の要否は、届出免除事由(同項1号〜5号)に該当するかに従って、図表2(今号6頁参照)記載のフローチャートのとおり、整理することができる(脚注12)。
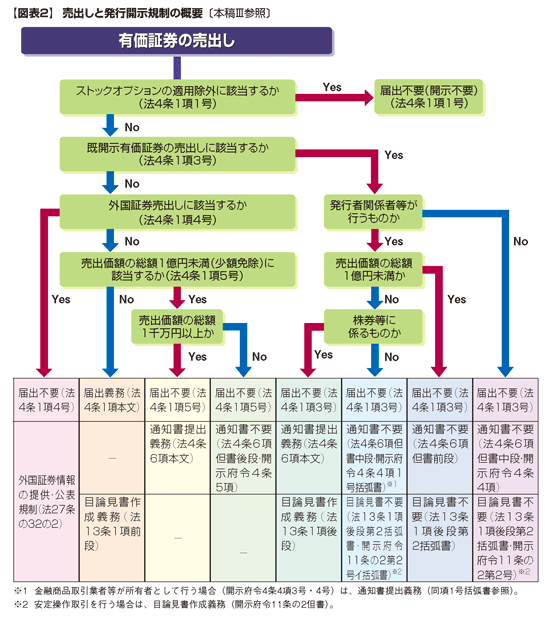
平成21年改正により、届出免除事由として追加された外国証券の売出し(法4条1項4号)については、届出のほか、目論見書の作成および有価証券通知書の提出も不要としつつ、簡易な情報提供として外国証券情報の提供・公表の規制が設けられている(法27条の32の2)。
また、平成21年改正により、法定の「開示が行われている場合」(法4条7項)の有価証券(以下「既開示有価証券」という)の売出しに係る目論見書の作成義務および有価証券通知書の提出義務の枠組みが変更されているが、これについては項を改める。
なお、有価証券の発行者は、売出し、すなわち勧誘が始められる前に届出を行うことが必要であり(法4条1項)、有価証券通知書の提出も、特定募集等である売出しが開始される日の前日までに行うことが必要である(同条6項)。目論見書については、発行者・売出人・引受人・金融商品取引業者などが、原則として、売付けに係る合意が成立する以前に交付しなければならない(法15条2項)。
2.既開示有価証券の売出し 上場有価証券など既開示有価証券の売出しについては、従来から、届出義務が免除されていたが(法4条1項3号)、目論見書に関しては、届出売出しの場合と並んで、売出価額の総額が1億円未満でない限り、作成義務が課されていた。また、売出価額の総額が1億円未満でない限り、有価証券通知書の提出義務が課されていた。
平成21年改正後は、既開示有価証券の売出しについての目論見書作成義務および有価証券通知書の提出義務が緩和され、発行者関係者等(脚注13)以外の者が行う場合には、安定操作取引を行うときを除き、目論見書の作成は不要であり(法13条1項後段第2括弧書、開示府令11条の2第2号、同条但書)、また有価証券通知書の提出も不要である(法4条6項但書中段、開示府令4条4項)。
これに対して、発行者関係者等が所有者である既開示有価証券の売出しを行う場合には、売出価額の総額が1億円以上であって、株券等(脚注14)に係る売出しであるときは、発行者において、目論見書の作成義務(法13条1項後段)および有価証券通知書の提出義務(法4条6項本文)が生じる。
売出価額の総額が1億円未満の場合は、目論見書の作成は不要であり(法13条1項後段第2括弧書)、有価証券通知書の提出も不要である(法4条6項但書前段)(脚注15)。
株券等以外の有価証券(社債券など)の売出しであるときは、安定操作取引を行うときを除き、目論見書の作成は不要であり(法13条1項後段第2括弧書、開示府令11条の2第2号イ括弧書、同条但書)、また有価証券通知書の提出も原則として不要であるが、金融商品取引業者等が所有者として行う場合にだけは提出義務がある(法4条6項但書中段、開示府令4条4項1号括弧書)。
このような既開示有価証券の売出しについての目論見書作成義務および有価証券通知書の提出義務は、図表2記載のフローチャートのとおり、整理することができる。
なお、目論見書の作成が不要である場合に、任意に目論見書相当の説明文書を作成することは可能であるが、その場合は、目論見書ではなく販売資料(法13条5項)に該当するものと考えられる(脚注16)。
脚注
1 本稿では、「金融商品取引法」を「法」、「金融商品取引法施行令」を「施行令」、「金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令」を「定義府令」、「企業内容等の開示に関する内閣府令」を「開示府令」と表記する。
2 認可金融商品取引業協会がその協会員に対して行う店頭売買、取扱有価証券の売買および上場株券等の取引所市場外での売買に関する事項の通知その他法令上の義務の履行として行う有価証券に関する情報の提供や、認可金融商品取引業協会などに対してその規則に基づき行われる有価証券に関する情報の提供が定められている。
3 本稿では、法2条4項2号イの要件を満たす場合を「適格機関投資家私売出し」、同号ロの要件を満たす場合を「特定投資家私売出し」、同号ハの要件を満たす場合を「少人数私売出し」といい、併せて「私売出し」と総称する。
4 ブロックトレード等が想定されている(平成21年金融商品取引法等の一部改正に係る政令案・内閣府令案等に関する平成21年12月22日付「コメントの概要及びコメントに対する金融庁の考え方」9頁21番、谷口解説28頁)。
5 本稿Ⅱでは、(イ)発行者、(ロ)発行者である法人の役員または発起人その他これに準ずる者、(ハ)主要株主(法163条1項の定義により、原則として、総株主等の議決権の10%以上の議決権を保有している株主をいう)または法人である主要株主の役員または発起人その他これに準ずる者、(ニ)発行者である法人の子会社その他これに準ずる法人またはこれらの役員もしくは発起人その他これに準ずる者、(ホ)金融商品取引業者等を意味して用いる(施行令1条の7の3第7号イ~ホ)。
6 金融商品取引業者等による積極的な勧誘がない場合であって、顧客からの注文に対し当該注文に応じるための取引についてのものであると説明されている(「企業内容等の開示に関する内閣府令(案)」等に関する平成22年3月31日付「コメントの概要及びコメントに対する金融庁の考え方」54頁180番)。
7 当事者の双方が金融商品取引業者等であるものが除外されているが、専門業者間取引として他の規定(基本的に、譲渡制限のない海外発行証券の売買に関する適用除外取引)が適用されると考えられるためと説明されている(前掲注4・「コメントの概要及びコメントに対する金融庁の考え方」15頁48番、谷口義幸「『有価証券の売出し』に係る開示規制の見直しの概要〔上〕」商事法務1902号40頁)。
8 前掲注7・谷口40頁。
9 この者が有価証券の売買を行うことを業とする場合には、業規制の問題があるため、基本的に、金融商品取引業者等が想定されていると思われる。
10 たとえば、神崎克郎=志谷匡史=川口恭弘『証券取引法』(青林書院、2006年)217頁。なお、勧誘概念に関する問題状況をまとめた近時の文献として、金融法委員会の平成22年6月1日付「金融商品取引法の開示規制上の『勧誘』の解釈を巡る現状と課題」がある。
11 平成21年金融商品取引法等の一部改正等に係る企業内容等の開示制度における内閣府令案等に関する平成21年12月28日付「コメントの概要及びコメントに対する金融庁の考え方」16頁62番。
12 説明の便宜上、特定組織再編成交付手続に係る場合を省略する。
13 本稿Ⅲでは、(1)発行者、(2)(イ)発行者の子会社または主要株主(法163条1項の定義により、原則として、総株主等の議決権の10%以上の議決権を保有している株主をいう)、(ロ)発行者の役員または発起人、(ハ)発行者の子会社の役員または発起人、(ニ)発行者が外国会社その他の会社以外の者の場合は(イ)~(ハ)に類するもの、(3)有価証券を他の者に取得させることを目的として(1)および(2)に掲げる者からその保有有価証券を取得した金融商品取引業者等、(4)有価証券の売出しに係る引受人(残額引受契約をした者に限る)に該当する金融商品取引業者等を意味して用いる(開示府令4条4項1号~4号、11条の2第2号イ~ニ)。
14 本稿Ⅲでは、株券、新株予約権証券、新株予約権が付されている有価証券もしくは株券に転換しうる有価証券または外国有価証券のうちこれらの有価証券の性質を有するものを意味して用いる(開示府令4条4項1号括弧書、11条の2第2号イ括弧書)。
15 既開示有価証券の売出しの場合の有価証券通知書提出義務の例外として、改正により追加された発行者関係者等以外の者が行うもの(法4条6項但書中段)のほか、従来からある売出価額の総額が1億円未満のもの(同前段)が利用可能かという解釈上の問題がありうる。改正前においては既開示有価証券の売出しの有価証券通知書提出義務の基準が売出価額の総額が1億円未満か否かとされていたこと、また、目論見書は有価証券通知書の添付書類として提出されるところ、目論見書の交付を必要とする場合については引き続き有価証券通知書の提出を求めることとされたと説明されていること(谷口義幸「『有価証券の売出し』に係る開示規制の見直しの概要〔下〕」商事法務1903号40頁)に照らし、発行者関係者等が行うものであっても、売出価額の総額が1億円未満である場合には、改正前と同様、有価証券通知書の提出は不要と考えるのが合理的と思われる。
16 前掲注6・「コメントの概要及びコメントに対する金融庁の考え方」54頁181番。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -