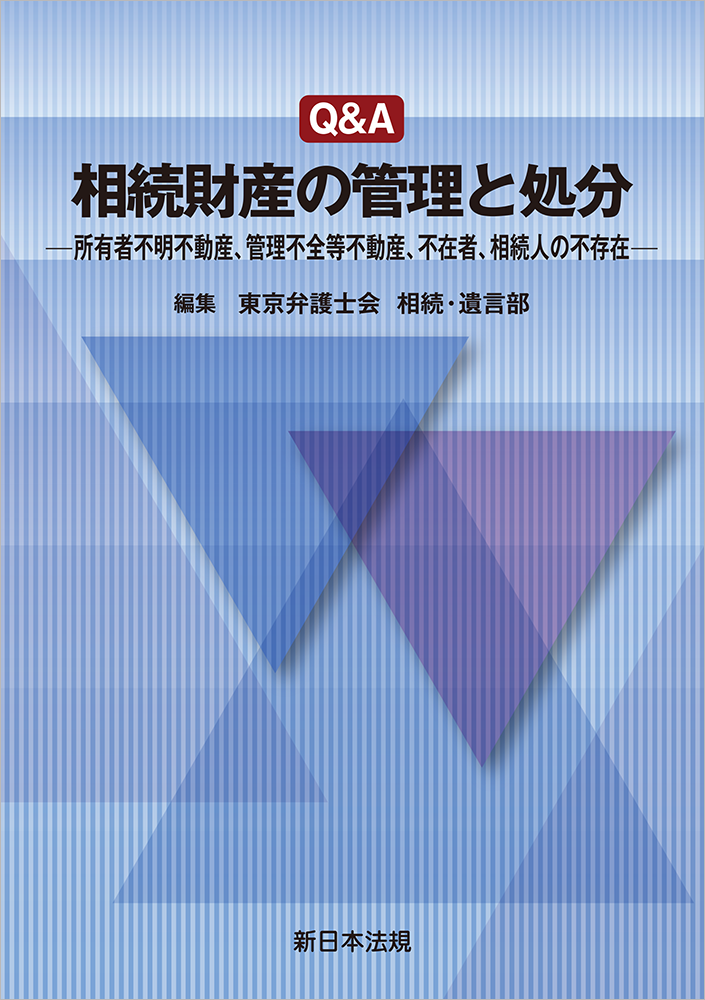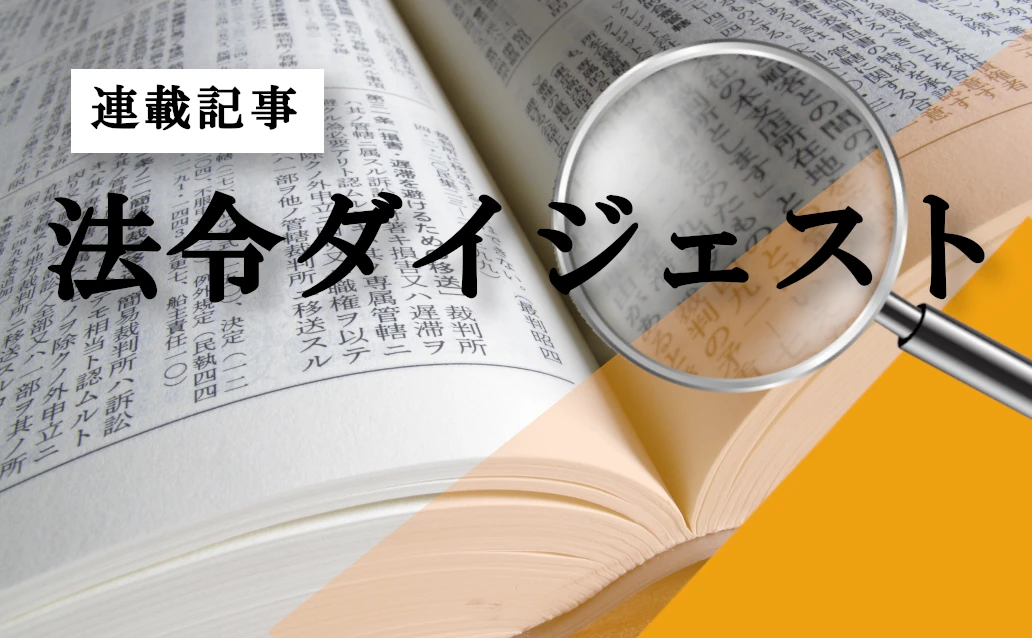解説記事2010年09月20日 【新会計基準解説】 改正企業会計基準第2号「1株当たり当期純利益に関する会計基準」等について(2010年9月20日号・№371)
新会計基準解説
改正企業会計基準第2号「1株当たり当期純利益に関する会計基準」等について
企業会計基準委員会 専門研究員 中條恵美
Ⅰ.はじめに
企業会計基準委員会(ASBJ)は、平成22年6月30日に次に掲げる会計基準等を公表した(脚注1)。
・ 改正企業会計基準第2号「1株当たり当期純利益に関する会計基準」(以下「本会計基準」という。)
・ 改正企業会計基準適用指針第4号「1株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」(以下「本適用指針」という。)
・ 改正実務対応報告第9号「1株当たり当期純利益に関する実務上の取扱い」(以下「本実務対応報告」という。)
本会計基準等は、本年4月2日に公開草案として公表されており、当該公開草案に寄せられたコメントを踏まえた修正を行った上で、公表に至っている。本稿では、これらの会計基準等の改正の概要について解説する。なお、文中、意見にわたる部分は、筆者の私見であることをあらかじめ申し添える。
Ⅱ. 改正の概要
本会計基準等は、平成21年12月に公表された企業会計基準第24号「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」(以下「企業会計基準第24号」という。)を受けての所要の改正のほか、国際的な会計基準とのコンバージェンスの観点から、国際会計基準審議会(IASB)における今後の検討でも影響を受けないと考えられる国際財務報告基準(IFRS)との既存の差異(脚注2)や我が国の市場関係者から実務上の対応要請がある点について短期的な対応を行うために、一部改正されている。
主な改正箇所及び概要の一覧は、表に記載のとおりである。
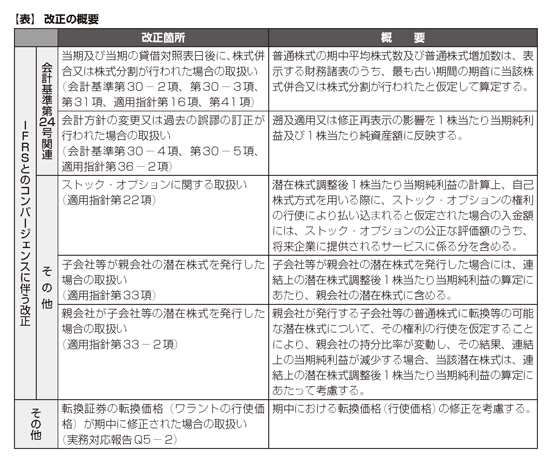
1.企業会計基準第24号関連の改正
(1)当期及び当期の貸借対照表日後に株式併合又は株式分割が行われた場合 我が国では、これまで過年度遡及修正の定めがなかったため、1株当たり情報についても、前期以前への遡及的な修正は行われてこなかった。ただし、当期及び当期の貸借対照表日後に株式併合や株式分割が行われ、発行済株式のみが変動する場合で、前期の財務情報を比較形式で開示しているときは、前期首に当該事象が行われたものと仮定した前期の1株当たり情報を注記として開示していた。
今般、平成21年12月に企業会計基準第24号が公表されたことを受けて、これまでの取扱いについて所要の改正が行われている。すなわち、当期及び当期の貸借対照表日後に株式併合又は株式分割が行われた場合には、普通株式の期中平均株式数及び普通株式増加数は、表示する財務諸表のうち、最も古い期間の期首に当該株式併合又は株式分割が行われたと仮定して、各表示期間の1株当たり情報を算定することとされた。
(2)会計方針の変更又は過去の誤謬の訂正が行われた場合 企業会計基準第24号では、会計方針の変更又は過去の誤謬の訂正が行われた場合に、表示期間における遡及適用後又は修正再表示後の1株当たり情報に対する影響額を開示することを求めており、また国際的な会計基準でも同様の取扱いが定められている。このため、本会計基準においても、遡及適用後又は修正再表示後の1株当たり情報の開示を求めることとされた。
なお、過去の期間の潜在株式数調整後1株当たり当期純利益の算定にあたり、潜在株式の行使に関して仮定した事項について、その後の期間の転換社債等の普通株式への転換や、普通株式の株価変動により当該仮定した事項が変化した場合であっても、過去の期間の潜在株式数調整後1株当たり当期純利益は遡及的に修正しないこととされている。
2.国際財務報告基準(IFRS)との既存の差異を解消するための改正
(1)ストック・オプション(脚注3)に関する取扱い 我が国では、潜在株式調整後1株当たり当期純利益の計算上、自己株式方式(脚注4)を用いる際に、ストック・オプションの権利の行使により払い込まれると仮定された場合の入金額には、行使時の払込金額のみを含めることとされていた。一方で、国際的な会計基準では、当該入金額には、ストック・オプションの公正な評価額のうち、将来企業に提供されるサービスに係る分を含める取扱いとされている。
潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定上、当該入金額にこのような未履行のサービスに係る分を含めることとすると、それに相応する部分だけ価値が多く計上されることから、現行よりも希薄化効果が少なく計上されることとなる。
本適用指針では、将来企業に提供されるサービスに係る分は、従業員が支払わなければならない対価と考えるべきであり、またこのような取扱いをすることは、国際的な会計基準の取扱いとも整合することから、当該分を行使による入金額に含めることとされている。なお、この場合、普通株式の期中平均株価が、将来企業に提供されるサービスに係る公正な評価単価を含めたストック・オプションの行使価格を上回るときに、希薄化効果を有することとなる。
(2)子会社等が親会社の潜在株式を発行した場合及び親会社が子会社等の潜在株式を発行した場合 我が国では、これまでこうした商品を発行した場合の潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定方法について、基準上明記はされていなかった。しかしながら、制度上こうした商品の発行が可能であることや、国際的な会計基準とのコンバージェンスの観点を踏まえ、本会計基準では、次のような取扱いをすることとされている。
・ 子会社等が、親会社の普通株式に転換等可能な潜在株式を発行し、その権利の行使を仮定することにより希薄化する場合には、連結上の潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定にあたり、親会社の潜在株式に含める。
・ 親会社が発行する子会社等の普通株式に転換等の可能な潜在株式について、その権利の行使を仮定することにより、親会社の持分比率が変動し、その結果、連結上の当期純利益が減少する場合、当該潜在株式は、連結上の潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定にあたって考慮する。
3.我が国の市場関係者から実務上の対応要請がある点に関する改正
(1)転換証券の転換価格が期中に修正された場合 これまでは、転換証券の転換価格が期中に修正された場合であったとしても、実務対応報告第9号Q5「(2)当初転換価格が将来の株価に基づいて決定されるため、当期末までには決まっていないケース」の取扱いの中で、転換請求可能期間が未到来の場合の考え方と同様に、転換仮定方式における転換の時点と転換価格の算定時点の整合性を重視して、「当期中に転換価格が修正されても、潜在株式調整後1株当たり当期純利益算定上の転換価格として、当期首における転換価格を利用することが適当と考えられる。」とされていた。
これに対し、財務諸表利用者からは、期中に転換価格が修正されたにもかかわらず、修正前の転換価格を用いて潜在株式調整後1株当たり当期純利益を算定し、開示することは適当ではないのではないかという意見もあった。
このため、期中の転換価格の修正を潜在株式調整後1株当たり当期純利益に反映する方式として、以下の2つが考えられた。
(1案)転換価格として、当期末における転換価格を利用する。
(2案)転換価格として、転換価格の修正日前は修正前の転換価格を利用し、転換価格の修正日後については、修正後の転換価格を利用する(転換価格の修正日において、転換社債を発行し直した場合と同様の取扱いとなる。)。
審議の過程では、(1案)は、期末における最新の転換価格による希薄化の効果を反映するため、1株当たり当期純利益に対する将来の潜在的な変動性を示すことができるとして、これを支持する意見もあった。
しかしながら、本会計基準等において、潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定目的は、1株当たり当期純利益に対する将来の潜在的な変動性を示す警告指標とすることではなく、1株当たり当期純利益と同様に、普通株主に関する一会計期間における企業の成果を示すことであり、これにより時系列比較等を通じ将来の普通株式の価値の算定に役立つものであるとされている(会計基準第37項、第38項)。このため、当該目的を変更せずに、期中における転換価格の変更という事象を反映することが可能であるという点が重視され、(2案)の転換価格の修正日前については、修正前の転換価格を用い、転換価格の修正後については、修正後の転換価格を用いて潜在株式調整後1株当たり当期純利益を算定するという方式が採用されている。
(2)ワラントの行使価格が期中に修正された場合 なお、当該取扱いは、ワラントの行使価格が、行使請求可能期間中に株価の変動によって修正された場合も同様である。
4.その他(四半期財務諸表における取扱い) 企業会計基準第12号「四半期財務諸表に関する会計基準」では、1株当たり四半期純利益、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益及び四半期の1株当たり純資産額の開示を求めているが、四半期財務諸表における算定方法が明記されていなかったため、本会計基準等では、中間会計期間の算定と同様に取り扱うことを確認的に記載している(適用指針第37項-2)。
Ⅲ.適用時期
上記Ⅱの改正について、本会計基準等では、平成23年4月1日以後開始する事業年度から適用することとし、早期適用は認めていない。これは、財務諸表の企業間比較及び時系列比較を確保する観点から、企業会計基準第24号と併せて適用することが適当と考えられたためであるとされている。
脚注
1 詳細については、ASBJのホームページ(https://www.asb.or.jp/asb/asb_j/documents/docs/touki/)を参照いただきたい。
2 IASBは、2008年8月に公開草案「1株当たり当期利益の簡素化」(IAS第33号改訂)を公表しているが、その後プロジェクトを一時中断しており、2010年度中はプロジェクトを再開しないこととされている。
3 ストック・オプションは、通常、付与後における一定期間の勤務の他、一定の利益水準や株価水準の達成などの特定の条件を満たした場合に、その権利が確定する。前者のように、一定期間の勤務後に権利が確定する場合には、行使期間が開始していなくとも、普通株式増加数の算定上、付与された時点から既に行使期間が開始したものとして取り扱うこととなる。これに対して、後者のように、単に時間の経過ではなく、特定の利益水準や株価水準の達成などの条件が付されている場合には、条件付発行可能潜在株式として取り扱うこととなる。ここで対象とされているのは、前者の場合である(適用指針第53項、第53-2項)。
4 期中平均株価が行使価格を上回る場合、ワラントが行使されたと仮定し、また、行使による入金額は、自己株式の買受に用いたと仮定する(会計基準第56項(2))。
改正企業会計基準第2号「1株当たり当期純利益に関する会計基準」等について
企業会計基準委員会 専門研究員 中條恵美
Ⅰ.はじめに
企業会計基準委員会(ASBJ)は、平成22年6月30日に次に掲げる会計基準等を公表した(脚注1)。
・ 改正企業会計基準第2号「1株当たり当期純利益に関する会計基準」(以下「本会計基準」という。)
・ 改正企業会計基準適用指針第4号「1株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」(以下「本適用指針」という。)
・ 改正実務対応報告第9号「1株当たり当期純利益に関する実務上の取扱い」(以下「本実務対応報告」という。)
本会計基準等は、本年4月2日に公開草案として公表されており、当該公開草案に寄せられたコメントを踏まえた修正を行った上で、公表に至っている。本稿では、これらの会計基準等の改正の概要について解説する。なお、文中、意見にわたる部分は、筆者の私見であることをあらかじめ申し添える。
Ⅱ. 改正の概要
本会計基準等は、平成21年12月に公表された企業会計基準第24号「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」(以下「企業会計基準第24号」という。)を受けての所要の改正のほか、国際的な会計基準とのコンバージェンスの観点から、国際会計基準審議会(IASB)における今後の検討でも影響を受けないと考えられる国際財務報告基準(IFRS)との既存の差異(脚注2)や我が国の市場関係者から実務上の対応要請がある点について短期的な対応を行うために、一部改正されている。
主な改正箇所及び概要の一覧は、表に記載のとおりである。
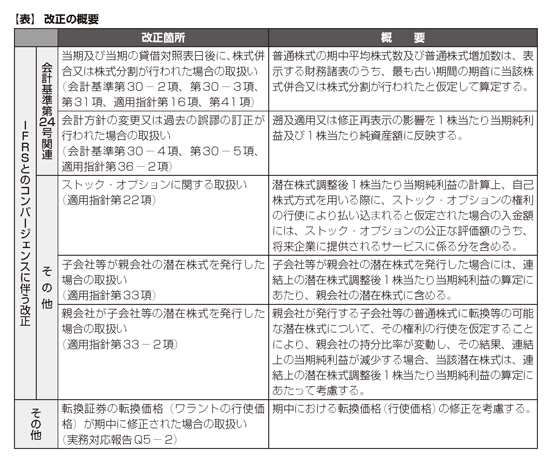
1.企業会計基準第24号関連の改正
(1)当期及び当期の貸借対照表日後に株式併合又は株式分割が行われた場合 我が国では、これまで過年度遡及修正の定めがなかったため、1株当たり情報についても、前期以前への遡及的な修正は行われてこなかった。ただし、当期及び当期の貸借対照表日後に株式併合や株式分割が行われ、発行済株式のみが変動する場合で、前期の財務情報を比較形式で開示しているときは、前期首に当該事象が行われたものと仮定した前期の1株当たり情報を注記として開示していた。
今般、平成21年12月に企業会計基準第24号が公表されたことを受けて、これまでの取扱いについて所要の改正が行われている。すなわち、当期及び当期の貸借対照表日後に株式併合又は株式分割が行われた場合には、普通株式の期中平均株式数及び普通株式増加数は、表示する財務諸表のうち、最も古い期間の期首に当該株式併合又は株式分割が行われたと仮定して、各表示期間の1株当たり情報を算定することとされた。
(2)会計方針の変更又は過去の誤謬の訂正が行われた場合 企業会計基準第24号では、会計方針の変更又は過去の誤謬の訂正が行われた場合に、表示期間における遡及適用後又は修正再表示後の1株当たり情報に対する影響額を開示することを求めており、また国際的な会計基準でも同様の取扱いが定められている。このため、本会計基準においても、遡及適用後又は修正再表示後の1株当たり情報の開示を求めることとされた。
なお、過去の期間の潜在株式数調整後1株当たり当期純利益の算定にあたり、潜在株式の行使に関して仮定した事項について、その後の期間の転換社債等の普通株式への転換や、普通株式の株価変動により当該仮定した事項が変化した場合であっても、過去の期間の潜在株式数調整後1株当たり当期純利益は遡及的に修正しないこととされている。
2.国際財務報告基準(IFRS)との既存の差異を解消するための改正
(1)ストック・オプション(脚注3)に関する取扱い 我が国では、潜在株式調整後1株当たり当期純利益の計算上、自己株式方式(脚注4)を用いる際に、ストック・オプションの権利の行使により払い込まれると仮定された場合の入金額には、行使時の払込金額のみを含めることとされていた。一方で、国際的な会計基準では、当該入金額には、ストック・オプションの公正な評価額のうち、将来企業に提供されるサービスに係る分を含める取扱いとされている。
潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定上、当該入金額にこのような未履行のサービスに係る分を含めることとすると、それに相応する部分だけ価値が多く計上されることから、現行よりも希薄化効果が少なく計上されることとなる。
本適用指針では、将来企業に提供されるサービスに係る分は、従業員が支払わなければならない対価と考えるべきであり、またこのような取扱いをすることは、国際的な会計基準の取扱いとも整合することから、当該分を行使による入金額に含めることとされている。なお、この場合、普通株式の期中平均株価が、将来企業に提供されるサービスに係る公正な評価単価を含めたストック・オプションの行使価格を上回るときに、希薄化効果を有することとなる。
(2)子会社等が親会社の潜在株式を発行した場合及び親会社が子会社等の潜在株式を発行した場合 我が国では、これまでこうした商品を発行した場合の潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定方法について、基準上明記はされていなかった。しかしながら、制度上こうした商品の発行が可能であることや、国際的な会計基準とのコンバージェンスの観点を踏まえ、本会計基準では、次のような取扱いをすることとされている。
・ 子会社等が、親会社の普通株式に転換等可能な潜在株式を発行し、その権利の行使を仮定することにより希薄化する場合には、連結上の潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定にあたり、親会社の潜在株式に含める。
・ 親会社が発行する子会社等の普通株式に転換等の可能な潜在株式について、その権利の行使を仮定することにより、親会社の持分比率が変動し、その結果、連結上の当期純利益が減少する場合、当該潜在株式は、連結上の潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定にあたって考慮する。
3.我が国の市場関係者から実務上の対応要請がある点に関する改正
(1)転換証券の転換価格が期中に修正された場合 これまでは、転換証券の転換価格が期中に修正された場合であったとしても、実務対応報告第9号Q5「(2)当初転換価格が将来の株価に基づいて決定されるため、当期末までには決まっていないケース」の取扱いの中で、転換請求可能期間が未到来の場合の考え方と同様に、転換仮定方式における転換の時点と転換価格の算定時点の整合性を重視して、「当期中に転換価格が修正されても、潜在株式調整後1株当たり当期純利益算定上の転換価格として、当期首における転換価格を利用することが適当と考えられる。」とされていた。
これに対し、財務諸表利用者からは、期中に転換価格が修正されたにもかかわらず、修正前の転換価格を用いて潜在株式調整後1株当たり当期純利益を算定し、開示することは適当ではないのではないかという意見もあった。
このため、期中の転換価格の修正を潜在株式調整後1株当たり当期純利益に反映する方式として、以下の2つが考えられた。
(1案)転換価格として、当期末における転換価格を利用する。
(2案)転換価格として、転換価格の修正日前は修正前の転換価格を利用し、転換価格の修正日後については、修正後の転換価格を利用する(転換価格の修正日において、転換社債を発行し直した場合と同様の取扱いとなる。)。
審議の過程では、(1案)は、期末における最新の転換価格による希薄化の効果を反映するため、1株当たり当期純利益に対する将来の潜在的な変動性を示すことができるとして、これを支持する意見もあった。
しかしながら、本会計基準等において、潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定目的は、1株当たり当期純利益に対する将来の潜在的な変動性を示す警告指標とすることではなく、1株当たり当期純利益と同様に、普通株主に関する一会計期間における企業の成果を示すことであり、これにより時系列比較等を通じ将来の普通株式の価値の算定に役立つものであるとされている(会計基準第37項、第38項)。このため、当該目的を変更せずに、期中における転換価格の変更という事象を反映することが可能であるという点が重視され、(2案)の転換価格の修正日前については、修正前の転換価格を用い、転換価格の修正後については、修正後の転換価格を用いて潜在株式調整後1株当たり当期純利益を算定するという方式が採用されている。
(2)ワラントの行使価格が期中に修正された場合 なお、当該取扱いは、ワラントの行使価格が、行使請求可能期間中に株価の変動によって修正された場合も同様である。
4.その他(四半期財務諸表における取扱い) 企業会計基準第12号「四半期財務諸表に関する会計基準」では、1株当たり四半期純利益、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益及び四半期の1株当たり純資産額の開示を求めているが、四半期財務諸表における算定方法が明記されていなかったため、本会計基準等では、中間会計期間の算定と同様に取り扱うことを確認的に記載している(適用指針第37項-2)。
Ⅲ.適用時期
上記Ⅱの改正について、本会計基準等では、平成23年4月1日以後開始する事業年度から適用することとし、早期適用は認めていない。これは、財務諸表の企業間比較及び時系列比較を確保する観点から、企業会計基準第24号と併せて適用することが適当と考えられたためであるとされている。
脚注
1 詳細については、ASBJのホームページ(https://www.asb.or.jp/asb/asb_j/documents/docs/touki/)を参照いただきたい。
2 IASBは、2008年8月に公開草案「1株当たり当期利益の簡素化」(IAS第33号改訂)を公表しているが、その後プロジェクトを一時中断しており、2010年度中はプロジェクトを再開しないこととされている。
3 ストック・オプションは、通常、付与後における一定期間の勤務の他、一定の利益水準や株価水準の達成などの特定の条件を満たした場合に、その権利が確定する。前者のように、一定期間の勤務後に権利が確定する場合には、行使期間が開始していなくとも、普通株式増加数の算定上、付与された時点から既に行使期間が開始したものとして取り扱うこととなる。これに対して、後者のように、単に時間の経過ではなく、特定の利益水準や株価水準の達成などの条件が付されている場合には、条件付発行可能潜在株式として取り扱うこととなる。ここで対象とされているのは、前者の場合である(適用指針第53項、第53-2項)。
4 期中平均株価が行使価格を上回る場合、ワラントが行使されたと仮定し、また、行使による入金額は、自己株式の買受に用いたと仮定する(会計基準第56項(2))。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -

Copyright (C) 2019
SHINNIPPON-HOKI PUBLISHING CO.,LTD.