解説記事2010年10月25日 【税制改正解説】 “源流”から辿るグループ税制 第3回 平成13年度改正(2)(2010年10月25日号・№375)
企業再編税制、連結納税……
~ルーツを知らずして真の理解なし~
“源流”から辿るグループ税制
第3回 平成13年度改正(2)
taxMLグループ
平成13年度改正の第2回目となります。前回(本誌371号18頁参照)は、平成13年度改正で創設された組織再編税制についてご解説いただきました。今回は、自己株式の取得等に係る商法・税法改正を中心にグループ税制との関係を明らかにしていただきます。 (編集部)
商法の改正
税理士 白井一馬
1.金庫株の解禁 平成13年10月施行の商法改正により、自己株式の取得・保有が原則自由化された。いわゆる金庫株解禁だ。自己株式の取得の範囲は、それ以前にも商法改正により、株式の消却やストックオプション、譲渡制限会社における相続人からの買取りなど、徐々に拡大されてきたという経緯はあったが、あくまで取得目的と保有期間を限定して認められていた。
戦後の日本企業は、外資による敵対的買収からの防衛のため、株式の持合いを行っていたが、景気の減速による株価低迷によって、持合い株の解消売りが始まった。特に株式を大量に保有していた銀行では、時価主義会計の導入により実現した含み損により、このままではBIS規制による8%の自己資本比率が維持できないおそれがあったことから、保有株式を売却せざるを得なくなっていた。
こうした株価低迷の悪循環への対策として、持合い株解消の受け皿として導入されたのが自己株式の取得・保有の自由化だった。自己株式は、定時株主総会の決議により、数量・保有期間に制限なく取得でき、任意に消却・譲渡することができるようになった。
2.資本政策への利用 自己株式は、登記手続を要することなく譲渡できるため、登録免許税の負担なしに多額の増資が可能となったほか、合併や株式交換などの企業買収において新株を発行する代わりに自己株式を対価として割り当てる手法が利用された。また、ストックオプション制度は、それまで取締役や従業員のみが付与対象者だったが、平成13年に新株予約権として整理され、誰にでも割当可能となった。新株予約権が行使された際に新株を発行せず、自己株式を交付するなど、自己株式は、いわば”予備株券”として多様な用途に活用されることとなった。
3.中小企業への影響 中小企業では、組織再編や相続人からの取得などで、やむを得ず自己株式を取得した場合に、その処分に苦慮していた。改正で保有期間や数量に制限がなくなったことで、長期保有ができるようになったため、早期処分の問題が解消しただけでなく、外部株主の整理や相続税などの資産税対策、経営権の確保のために利用されるなど、中小企業にとっても、便利な制度となった。
法人税法の改正
税理士 国田修平
1.自己株式取得に係る法人税法の改正 平成13年税制改正前は、法人税法においては、自己株式は単なる有価証券の取得・譲渡として取り扱われていた。
商法改正後は、自己株式の取得・保有が自由化されたことで、仮に、有価証券の売買とする従来の取扱いのままであれば、株主は、配当を受けることに代えて、少しずつ株式を発行法人に譲渡して対価を受け取ることで、配当への所得税課税を免れるという脱法が可能となってしまう。あるいは、自己株式を取得し、長期間保有した後に、利益剰余金で消却すれば、もはや旧株主にみなし配当課税を行うことはできない。
そこで、株式の発行法人への譲渡に対しては、その譲渡があった時にみなし配当として取り扱うという改正が必要となった。
2.みなし配当の計算方法 商法が自己株式の取得を資本の控除項目としたのを受け、法人税法においては、自己株式の取得を、資本の払戻しと課税済利益の配当を組み合わせた資本等取引として整理した。平成13年10月以降、株主が受け取る自己株式の譲渡の対価について、発行法人の資本等の金額(現行は資本金等の額)を超える部分が、みなし配当とされた。そして、発行法人においては、みなし配当に相当する金額を利益積立金額から減算することとされた。
自己株式に対応する資本等の金額は、発行済み株式に占める譲渡株式数の割合、いわゆる株数プロラタにより計算することとされた。
例外として、市場取引などの場合は、株主が譲渡の相手方が発行法人であるかどうかを認識できないことから、みなし配当課税を行わないこととされた。合併や営業譲渡により移転した自己株式についても租税回避のおそれがないことから、みなし配当課税は行われないこととされた。
3.減資や残余財産の分配時にもみなし配当課税が必要に 自己株式の取得を資本の払戻しと位置付けたことで、有償減資もこれに合わせ抜本的に改正された。
たとえば、自己株式を取得し、消却後に無償減資をするのと、株式消却を伴う有償減資は、実質的に同じ取引であるため、課税関係が異ならないように平仄を合わせる必要があったためだ。
改正前の有償減資では、減額した資本金を超える部分の払戻しについて、資本積立金額と利益積立金額のどちらを充てるかは、会社が決定できた。今回の改正で会社の裁量は排除され、減少させる資本等の金額は、会社の経理処理にかかわらず、法人税法の規定に基づき、計算することとされた。
商法の取扱いに係わらず、法人税法独自で資本積立金額と利益積立金額を計算するという規定は、平成13年税制改正の基本思想の表れといえた。
商法における「株式消却を伴う減資」と「株式消却を伴わない減資」について、法人税法では、次のようにみなし配当の計算を行うこととされた。
(1)株式消却を伴う減資 株式消却を伴う減資は、株主が対価の交付を受けた場合には、株数プロラタによって、対応する資本等の金額を計算し、これを超える金額がみなし配当となる。そして、対価からみなし配当を除いた金額が、株式の譲渡対価とされた。
無償の場合は、交付される対価がないことから、みなし配当は計算されず、消却される株式の帳簿価額がそのまま譲渡損失となった。
(2)株式消却を伴わない減資 株式消却を伴わない減資の場合には、(1)のように株数プロラタによる計算ができないため、純資産プロラタによって、対応する資本等の金額を計算することとされた。
無償の場合は、交付される対価がないことから、みなし配当は計算されず、譲渡損失とすべき株式の帳簿価額も計算上ゼロとなるため、株主においては何も処理しないこととなった。
さらに、残余財産の分配も、一種の減資払戻しであるため、みなし配当課税が行われることとなった。これで、自己株式の取得、減資、残余財産の分配の課税関係は整合されたわけだ。
4.その他資本剰余金の処分による配当の取扱い 商法改正により法定準備金の限度額が、資本準備金と利益準備金の合計額が資本金の4分の1に達するまでとされ、これを超える準備金の取崩しが認められた。資本準備金を取り崩した場合、その他資本剰余金となり、これを原資として配当することも認められた。これについて、法人税法上は、全額が利益の配当があったものとみなして配当課税されたが、平成18年税制改正で、純資産プロラタによって、対応する資本金等の額を計算し、それを超える部分が、みなし配当とされた。
5.自己株式の譲渡 商法改正により、会社が取得した自己株式は、取締役会の決議で譲渡が可能になった。自己株式の譲渡は、新株発行の手続きを経て行われるため、譲渡制限会社では、株主総会の特別決議が必要だ。この場合の帳簿価額と譲渡対価の差額は、法人税法上は、資本積立金の増減とする改正が平成14年に行われ、増資と同様の資本等取引として扱われることとなった。
自己株式取得に係る税法の取扱いの変遷
税理士 江崎一恵
1.自己株式の4つの歴史 税法における自己株式の取扱いは、次頁図のように区分できる。それは商法・会社法に追従し、かつ、税法理論の整合を図るための歴史だった。
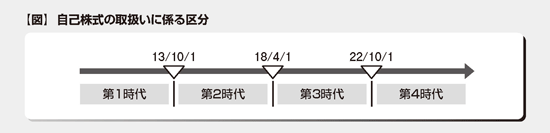
会社にとっては有価証券という単なる資産の取得に過ぎず、株主にとっては譲渡所得として取り扱われたのが、平成13年までの第1時代とすると、その後は以下のような変遷を辿った。
2.平成13年商法改正による金庫株解禁後の「第2時代」 平成13年10月の法人税法の改正後は、会社にとっては有価証券という資産であり、株式を発行法人に譲渡した株主には、配当所得課税が行われる時代となった。
金庫株解禁により、実務家を悩ませたのが、自己株式の適正時価の問題だ。時価の算定には、法人税法と所得税法の基本通達によって、財産評価基本通達を使用することが認められたが、株主が個人の場合には、通達をそのまま適用すると、株主から見た時価と発行法人から見た時価が異なるという問題が生じた。同族株主か否かの判定が、譲渡側で判定するか、譲受側で判定するかで結果が異なるためだ。
そして、個人株主と法人株主とで課税関係がまったく異なることになったのが第2時代だ。株式を発行法人に譲渡すると、仮に、簿価(取得価額)相当額で譲渡した場合であっても、受取配当と株式譲渡損が両建てになることがある。この場合でも、法人が売主の場合なら譲渡損を計上することができる。しかし、個人は、株式譲渡損を他の所得と損益通算することができない。
3.会社法改正後の「第3時代」 平成18年税制改正後は、会社にとっては資本の払戻しであり、株式を発行法人に譲渡した株主には、配当所得課税が行われる時代となった。
この改正によって、自己株式の取得が、資本等取引となったため、改正を境に、会社から見た自己株式の時価は幾らかという哲学論議から解放されたわけだ。株主から見た売り主としての判定で自己株式の適正時価が算定できることになった。
また、自己株式取得が資本等取引となったことで、低額譲受けについて受贈益課税がなくなるのではないかという見解もあった。しかし、低額譲受けの場合に、受贈益課税が行われてきた過去の取扱いとの整合が図れない。租税回避の意図がある場合には、受贈益課税が行われると考えるのが妥当だったと思う。
4.平成22年度税制改正後の「第4時代」 上述のとおり、株式を発行法人へ譲渡した場合、受取配当金と株式譲渡損が両建て計上される場合がある。法人株主の場合、受取配当金は益金不算入となるため、譲渡損を作出する節税手法として自己株式が利用された。具体的事例として日本IBMが、この手法を使い、連結所得をゼロにしたという事案が報道された。
平成22年度税制改正で、100%グループ内の自己株式取引に限っては、譲渡損相当額を資本金等の額と相殺する改正が行われ、このようなスキームは実行できなくなった。同時に、100%グループ内の自己株式の取引は、株主にとっても完全に資本等取引となったことで、結果として、適正時価が問題とならなくなったことを意味した。
~ルーツを知らずして真の理解なし~
“源流”から辿るグループ税制
第3回 平成13年度改正(2)
taxMLグループ
平成13年度改正の第2回目となります。前回(本誌371号18頁参照)は、平成13年度改正で創設された組織再編税制についてご解説いただきました。今回は、自己株式の取得等に係る商法・税法改正を中心にグループ税制との関係を明らかにしていただきます。 (編集部)
商法の改正
税理士 白井一馬
1.金庫株の解禁 平成13年10月施行の商法改正により、自己株式の取得・保有が原則自由化された。いわゆる金庫株解禁だ。自己株式の取得の範囲は、それ以前にも商法改正により、株式の消却やストックオプション、譲渡制限会社における相続人からの買取りなど、徐々に拡大されてきたという経緯はあったが、あくまで取得目的と保有期間を限定して認められていた。
戦後の日本企業は、外資による敵対的買収からの防衛のため、株式の持合いを行っていたが、景気の減速による株価低迷によって、持合い株の解消売りが始まった。特に株式を大量に保有していた銀行では、時価主義会計の導入により実現した含み損により、このままではBIS規制による8%の自己資本比率が維持できないおそれがあったことから、保有株式を売却せざるを得なくなっていた。
こうした株価低迷の悪循環への対策として、持合い株解消の受け皿として導入されたのが自己株式の取得・保有の自由化だった。自己株式は、定時株主総会の決議により、数量・保有期間に制限なく取得でき、任意に消却・譲渡することができるようになった。
2.資本政策への利用 自己株式は、登記手続を要することなく譲渡できるため、登録免許税の負担なしに多額の増資が可能となったほか、合併や株式交換などの企業買収において新株を発行する代わりに自己株式を対価として割り当てる手法が利用された。また、ストックオプション制度は、それまで取締役や従業員のみが付与対象者だったが、平成13年に新株予約権として整理され、誰にでも割当可能となった。新株予約権が行使された際に新株を発行せず、自己株式を交付するなど、自己株式は、いわば”予備株券”として多様な用途に活用されることとなった。
3.中小企業への影響 中小企業では、組織再編や相続人からの取得などで、やむを得ず自己株式を取得した場合に、その処分に苦慮していた。改正で保有期間や数量に制限がなくなったことで、長期保有ができるようになったため、早期処分の問題が解消しただけでなく、外部株主の整理や相続税などの資産税対策、経営権の確保のために利用されるなど、中小企業にとっても、便利な制度となった。
法人税法の改正
税理士 国田修平
1.自己株式取得に係る法人税法の改正 平成13年税制改正前は、法人税法においては、自己株式は単なる有価証券の取得・譲渡として取り扱われていた。
商法改正後は、自己株式の取得・保有が自由化されたことで、仮に、有価証券の売買とする従来の取扱いのままであれば、株主は、配当を受けることに代えて、少しずつ株式を発行法人に譲渡して対価を受け取ることで、配当への所得税課税を免れるという脱法が可能となってしまう。あるいは、自己株式を取得し、長期間保有した後に、利益剰余金で消却すれば、もはや旧株主にみなし配当課税を行うことはできない。
そこで、株式の発行法人への譲渡に対しては、その譲渡があった時にみなし配当として取り扱うという改正が必要となった。
2.みなし配当の計算方法 商法が自己株式の取得を資本の控除項目としたのを受け、法人税法においては、自己株式の取得を、資本の払戻しと課税済利益の配当を組み合わせた資本等取引として整理した。平成13年10月以降、株主が受け取る自己株式の譲渡の対価について、発行法人の資本等の金額(現行は資本金等の額)を超える部分が、みなし配当とされた。そして、発行法人においては、みなし配当に相当する金額を利益積立金額から減算することとされた。
自己株式に対応する資本等の金額は、発行済み株式に占める譲渡株式数の割合、いわゆる株数プロラタにより計算することとされた。
例外として、市場取引などの場合は、株主が譲渡の相手方が発行法人であるかどうかを認識できないことから、みなし配当課税を行わないこととされた。合併や営業譲渡により移転した自己株式についても租税回避のおそれがないことから、みなし配当課税は行われないこととされた。
3.減資や残余財産の分配時にもみなし配当課税が必要に 自己株式の取得を資本の払戻しと位置付けたことで、有償減資もこれに合わせ抜本的に改正された。
たとえば、自己株式を取得し、消却後に無償減資をするのと、株式消却を伴う有償減資は、実質的に同じ取引であるため、課税関係が異ならないように平仄を合わせる必要があったためだ。
改正前の有償減資では、減額した資本金を超える部分の払戻しについて、資本積立金額と利益積立金額のどちらを充てるかは、会社が決定できた。今回の改正で会社の裁量は排除され、減少させる資本等の金額は、会社の経理処理にかかわらず、法人税法の規定に基づき、計算することとされた。
商法の取扱いに係わらず、法人税法独自で資本積立金額と利益積立金額を計算するという規定は、平成13年税制改正の基本思想の表れといえた。
商法における「株式消却を伴う減資」と「株式消却を伴わない減資」について、法人税法では、次のようにみなし配当の計算を行うこととされた。
(1)株式消却を伴う減資 株式消却を伴う減資は、株主が対価の交付を受けた場合には、株数プロラタによって、対応する資本等の金額を計算し、これを超える金額がみなし配当となる。そして、対価からみなし配当を除いた金額が、株式の譲渡対価とされた。
無償の場合は、交付される対価がないことから、みなし配当は計算されず、消却される株式の帳簿価額がそのまま譲渡損失となった。
(2)株式消却を伴わない減資 株式消却を伴わない減資の場合には、(1)のように株数プロラタによる計算ができないため、純資産プロラタによって、対応する資本等の金額を計算することとされた。
無償の場合は、交付される対価がないことから、みなし配当は計算されず、譲渡損失とすべき株式の帳簿価額も計算上ゼロとなるため、株主においては何も処理しないこととなった。
さらに、残余財産の分配も、一種の減資払戻しであるため、みなし配当課税が行われることとなった。これで、自己株式の取得、減資、残余財産の分配の課税関係は整合されたわけだ。
4.その他資本剰余金の処分による配当の取扱い 商法改正により法定準備金の限度額が、資本準備金と利益準備金の合計額が資本金の4分の1に達するまでとされ、これを超える準備金の取崩しが認められた。資本準備金を取り崩した場合、その他資本剰余金となり、これを原資として配当することも認められた。これについて、法人税法上は、全額が利益の配当があったものとみなして配当課税されたが、平成18年税制改正で、純資産プロラタによって、対応する資本金等の額を計算し、それを超える部分が、みなし配当とされた。
5.自己株式の譲渡 商法改正により、会社が取得した自己株式は、取締役会の決議で譲渡が可能になった。自己株式の譲渡は、新株発行の手続きを経て行われるため、譲渡制限会社では、株主総会の特別決議が必要だ。この場合の帳簿価額と譲渡対価の差額は、法人税法上は、資本積立金の増減とする改正が平成14年に行われ、増資と同様の資本等取引として扱われることとなった。
自己株式取得に係る税法の取扱いの変遷
税理士 江崎一恵
1.自己株式の4つの歴史 税法における自己株式の取扱いは、次頁図のように区分できる。それは商法・会社法に追従し、かつ、税法理論の整合を図るための歴史だった。
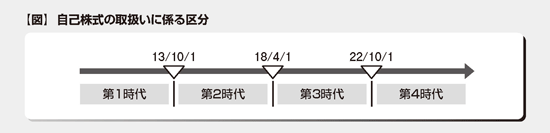
会社にとっては有価証券という単なる資産の取得に過ぎず、株主にとっては譲渡所得として取り扱われたのが、平成13年までの第1時代とすると、その後は以下のような変遷を辿った。
2.平成13年商法改正による金庫株解禁後の「第2時代」 平成13年10月の法人税法の改正後は、会社にとっては有価証券という資産であり、株式を発行法人に譲渡した株主には、配当所得課税が行われる時代となった。
金庫株解禁により、実務家を悩ませたのが、自己株式の適正時価の問題だ。時価の算定には、法人税法と所得税法の基本通達によって、財産評価基本通達を使用することが認められたが、株主が個人の場合には、通達をそのまま適用すると、株主から見た時価と発行法人から見た時価が異なるという問題が生じた。同族株主か否かの判定が、譲渡側で判定するか、譲受側で判定するかで結果が異なるためだ。
そして、個人株主と法人株主とで課税関係がまったく異なることになったのが第2時代だ。株式を発行法人に譲渡すると、仮に、簿価(取得価額)相当額で譲渡した場合であっても、受取配当と株式譲渡損が両建てになることがある。この場合でも、法人が売主の場合なら譲渡損を計上することができる。しかし、個人は、株式譲渡損を他の所得と損益通算することができない。
3.会社法改正後の「第3時代」 平成18年税制改正後は、会社にとっては資本の払戻しであり、株式を発行法人に譲渡した株主には、配当所得課税が行われる時代となった。
この改正によって、自己株式の取得が、資本等取引となったため、改正を境に、会社から見た自己株式の時価は幾らかという哲学論議から解放されたわけだ。株主から見た売り主としての判定で自己株式の適正時価が算定できることになった。
また、自己株式取得が資本等取引となったことで、低額譲受けについて受贈益課税がなくなるのではないかという見解もあった。しかし、低額譲受けの場合に、受贈益課税が行われてきた過去の取扱いとの整合が図れない。租税回避の意図がある場合には、受贈益課税が行われると考えるのが妥当だったと思う。
4.平成22年度税制改正後の「第4時代」 上述のとおり、株式を発行法人へ譲渡した場合、受取配当金と株式譲渡損が両建て計上される場合がある。法人株主の場合、受取配当金は益金不算入となるため、譲渡損を作出する節税手法として自己株式が利用された。具体的事例として日本IBMが、この手法を使い、連結所得をゼロにしたという事案が報道された。
平成22年度税制改正で、100%グループ内の自己株式取引に限っては、譲渡損相当額を資本金等の額と相殺する改正が行われ、このようなスキームは実行できなくなった。同時に、100%グループ内の自己株式の取引は、株主にとっても完全に資本等取引となったことで、結果として、適正時価が問題とならなくなったことを意味した。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -

Copyright (C) 2019
SHINNIPPON-HOKI PUBLISHING CO.,LTD.




















