解説記事2010年12月06日 【税務マエストロ】 国際税務における租税条約の役割(2010年12月6日号・№381)
税務マエストロ
税務における第一人者“税務マエストロ”による税実務講座
今週のマエストロ&テーマ
国際税務における租税条約の役割
#05 品川克己
日本公認会計士協会租税調査会専門委員(国際租税専門部会)税理士法人プライスウォーターハウスクーパース(マネージング・ディレクター)
略歴 89年より大蔵省主税局に勤務。90年7月より同国際租税課にて国際課税関係の政策立案・立法及び租税条約交渉等に従事。96年ハーバード・ロースクールにて客員研究員として日米租税条約について研究。97年より00年までOECD租税委員会に主任行政官として出向(在フランス)し、「OECD移転価格ガイドライン」及び「OECDモデル条約」の改定、及び関連会議の運営に従事。01年9月財務省を辞職し現職(平成22年10月現在)。
次回のテーマ
#06 経営戦略に応える企業再編成税制 税理士法人アクト22代表社員 朝長英樹
経営戦略の1つとして組織再編成税制を活用できる方法を、同税制等の創設に携わった著者が事例形式で解説する。
※取り上げて欲しいテーマを編集部にお寄せください。
e-mail:ta@lotus21.co.jp
1 進出先における源泉徴収 日本企業の海外進出は、別の視点でとらえれば、「海外への投資」と考えることができるが、この海外への投資にはいろいろなパターンが考えられる。それは、外国の企業との物品の売買のみならず、外国の株式・債券の保有・売買、外国での子会社の設立、関係会社へのローン、特許権など無体財産の使用許諾、従業員の海外出向、受入れ、海外の企業買収など、いろいろな形態の投資が考えられ、そこでは必ず相手国の税務問題が発生することとなる。そして、この相手国での税務問題で、もっとも頻繁に、かつ、最初に起こりうるものが源泉税(源泉徴収)の問題である。
具体的には、たとえば、日本企業が海外に子会社を設立(出資)して事業を始める場合、事業資金として出資(資本金)を利用することもあれば、別途親会社(日本企業)からローンという形で資金供与することも考えられる。出資つまり資本を持つということは、それに対するリターンとして配当が支払われることとなる。また、ローンという投資に対するリターンは利息ということとなる。こうした、配当や利息(利子)は、一般に「投資所得」とよばれ、その支払地国で源泉徴収により課税されることとなる(脚注1)。同様に、海外の企業に、その所有する特許などの使用許諾をする場合も、これも一種の海外投資であり、そのリターンとして使用料(ロイヤルティ)が支払われるが、この使用料(ロイヤルティ)も、通常は源泉徴収されることとなる。こうした利子、配当、使用料(ロイヤルティ)に対する源泉徴収の問題は、国際税務の最初の課題であり、そこに租税条約は大きく関係している。
2 租税条約の役割 租税条約は、2国間での課税関係についての取り決めである。一般に、相手国の個人や企業に対する自国での課税関係を明確にし、その効果として、2国間の投資を促進する効果を生み出している。
(1)源泉税の減免 租税条約上の措置としては、いくつかのものがあるが、もっとも重要なものは投資収益に対する課税の調整である。投資に対する収益としては、配当や利子がその典型例であるが、こうした配当や利子に対する源泉地(支払地)での課税、つまり源泉税は、投資収益の効率性の観点からはマイナスの要素とならざるを得ない(マイナス要因が少ないほうが投資しやすい)。したがって、これらに対する課税が過剰なものとならないように2国間で調整し、投資効率に対するマイナス要素を排除・軽減することが、まさに租税条約の重要な役割となっているのである。
具体的には、租税条約の相手国に利子や配当を支払う場合、国内法に定める原則的な源泉徴収税率に替えて軽減税率が適用され、結果的に源泉税の軽減(ゼロ税率、つまり免税となることもある)が図られることとなる。たとえば図表1のように、ある日本企業がアメリカ企業へ30%の出資を行う。この出資に対応する配当は、アメリカでは原則30%の源泉徴収の対象となるが、日米租税条約により5%での源泉徴収となるのである。
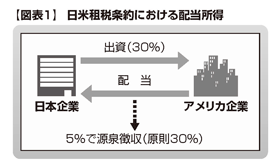
また、たとえば日本企業がアメリカ企業の所有する特許を日本国内で利用する場合、通常、この日本企業はアメリカ企業に対し、この特許の利用対価としてロイヤルティを支払うこととなろう。そしてこのロイヤルティは日本からの支払時に原則20%での源泉徴収が必要となるが、日米租税条約により免税となるのである(図表2参照)。
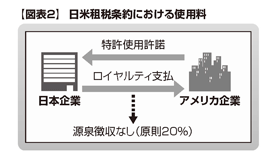
このように、投資先での源泉税が減免されることにより、当然のことながら投資が行いやすくなると期待される。これが、租税条約による最大の恩典の一つといえる。
(2)二重課税の排除効果 利子、配当等の投資所得に対する源泉税率が軽減されることは、結果的に二重課税の排除という効果をもたらす。利子や配当といった投資収益であっても、それを生み出すためのコストが必要であり、こうしたコストを勘案して収益をネットでとらえた場合、通常、支払額(グロス)に対する源泉税は過大な課税となってしまうケースが多いと考えられる。したがって、外国税額控除により二重課税を調整する際に、控除限度額を超過し、結果的に二重課税が排除されないことも起こりうるのである。源泉税率を軽減することは、外国税額控除における控除限度額を超過しないようにする方向に働き、結果的に二重課税の排除に資することとなる(脚注2)。
また、源泉税を課すのは、その国が、所得の源泉地であることを主張するからに他ならない。一つの所得に対して、二つの国が源泉地を主張すれば、源泉地課税の競合・重複が生じる(二重課税)ことは明白である。また、所得の源泉地を主張するということは、その国では国内所得としてとらえられることとなる。つまり国外所得としての認識ができないことであり、結果的に外国税額控除ができない可能性も高くなろう。
租税条約は、こうした源泉地の競合に対して所得源泉ルールを設け、所得の源泉地を振り分けることにより課税権を調整するとともに、結果として二重課税の排除を促す役割も果たしている。
3 租税条約ネットワーク 現在(平成22年10月現在)のところ、日本は48の租税条約を締結し、59カ国との間で適用がある。さらに、未発効の条約もあり、また現状、アラブ首長国連邦との交渉も進められているようである。
これら租税条約の締結相手国を見てみると、アフリカ諸国及び中南米を除き、日本と経済的な関係がある国は概ねカバーされつつある。当然のことながら、租税条約の対象は「租税」であり、その発生原因となる経済活動、経済交流がなければ、租税条約の存在そのものも必要ないところである。ある程度の経済的関係がある国々との間で租税条約が締結されている現在、日本の租税条約ネットワークは、数量の面からは概ね完成していると見ることもできる。
これら日本が締結した租税条約は、基本的には、グローバルスタンダードともいえる「OECDモデル条約」に準拠しつつ、条約締結当事国の諸事情を反映させたものとなっている。その内容からは、これまでの日本の租税条約ポリシーが読み取れるところであるが、また、それぞれ締結された時期の経済関係、経済情勢や世界的な国際課税についての考え方を反映させたものとなっている。たとえば、それまで使用料に対する源泉税率を10%とするのが日本のポリシーであったが(OECDモデル条約ではゼロ)、日米租税条約において、初めて使用料を免税としたことや、同じく日米租税条約において包括的な特典制限条項を導入したことは、こうした時代の要請を反映させたものである。
このように、租税条約は、締結された後も、経済情勢等に即して見直し、改正される必要がある。
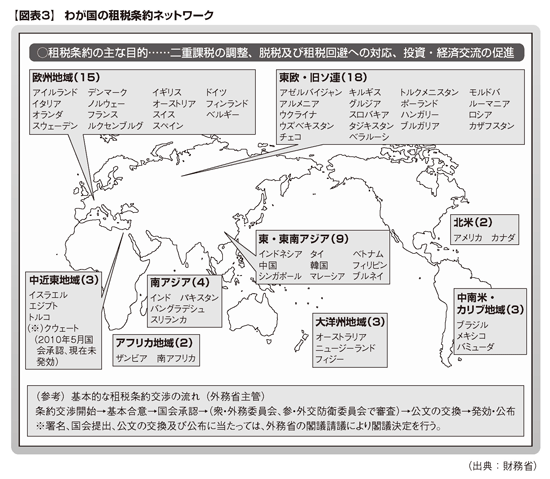
脚注
1 この源泉徴収の税率は、国によってまちまちである。日本の場合、15%(利子)または20%(配当、使用料など)であり、米国では原則30%とされている。
2 こうした観点から、日米租税条約においては金融機関等の受け取る利子が源泉税免除とされている。
この記事に関連するお問い合わせ先 この記事に関するお問い合わせは週刊「T&Amaster」編集部にお寄せください。執筆者に質問内容をお伝えいたします。
TEL:03-5281-0020 FAX:03-5281-0030 e-mail:ta@lotus21.co.jp
※なお、内容によっては回答いたしかねる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
今週のマエストロ&テーマ
国際税務における租税条約の役割
#05 品川克己
日本公認会計士協会租税調査会専門委員(国際租税専門部会)税理士法人プライスウォーターハウスクーパース(マネージング・ディレクター)
略歴 89年より大蔵省主税局に勤務。90年7月より同国際租税課にて国際課税関係の政策立案・立法及び租税条約交渉等に従事。96年ハーバード・ロースクールにて客員研究員として日米租税条約について研究。97年より00年までOECD租税委員会に主任行政官として出向(在フランス)し、「OECD移転価格ガイドライン」及び「OECDモデル条約」の改定、及び関連会議の運営に従事。01年9月財務省を辞職し現職(平成22年10月現在)。
次回のテーマ
#06 経営戦略に応える企業再編成税制 税理士法人アクト22代表社員 朝長英樹
経営戦略の1つとして組織再編成税制を活用できる方法を、同税制等の創設に携わった著者が事例形式で解説する。
※取り上げて欲しいテーマを編集部にお寄せください。
e-mail:ta@lotus21.co.jp
1 進出先における源泉徴収 日本企業の海外進出は、別の視点でとらえれば、「海外への投資」と考えることができるが、この海外への投資にはいろいろなパターンが考えられる。それは、外国の企業との物品の売買のみならず、外国の株式・債券の保有・売買、外国での子会社の設立、関係会社へのローン、特許権など無体財産の使用許諾、従業員の海外出向、受入れ、海外の企業買収など、いろいろな形態の投資が考えられ、そこでは必ず相手国の税務問題が発生することとなる。そして、この相手国での税務問題で、もっとも頻繁に、かつ、最初に起こりうるものが源泉税(源泉徴収)の問題である。
具体的には、たとえば、日本企業が海外に子会社を設立(出資)して事業を始める場合、事業資金として出資(資本金)を利用することもあれば、別途親会社(日本企業)からローンという形で資金供与することも考えられる。出資つまり資本を持つということは、それに対するリターンとして配当が支払われることとなる。また、ローンという投資に対するリターンは利息ということとなる。こうした、配当や利息(利子)は、一般に「投資所得」とよばれ、その支払地国で源泉徴収により課税されることとなる(脚注1)。同様に、海外の企業に、その所有する特許などの使用許諾をする場合も、これも一種の海外投資であり、そのリターンとして使用料(ロイヤルティ)が支払われるが、この使用料(ロイヤルティ)も、通常は源泉徴収されることとなる。こうした利子、配当、使用料(ロイヤルティ)に対する源泉徴収の問題は、国際税務の最初の課題であり、そこに租税条約は大きく関係している。
2 租税条約の役割 租税条約は、2国間での課税関係についての取り決めである。一般に、相手国の個人や企業に対する自国での課税関係を明確にし、その効果として、2国間の投資を促進する効果を生み出している。
(1)源泉税の減免 租税条約上の措置としては、いくつかのものがあるが、もっとも重要なものは投資収益に対する課税の調整である。投資に対する収益としては、配当や利子がその典型例であるが、こうした配当や利子に対する源泉地(支払地)での課税、つまり源泉税は、投資収益の効率性の観点からはマイナスの要素とならざるを得ない(マイナス要因が少ないほうが投資しやすい)。したがって、これらに対する課税が過剰なものとならないように2国間で調整し、投資効率に対するマイナス要素を排除・軽減することが、まさに租税条約の重要な役割となっているのである。
具体的には、租税条約の相手国に利子や配当を支払う場合、国内法に定める原則的な源泉徴収税率に替えて軽減税率が適用され、結果的に源泉税の軽減(ゼロ税率、つまり免税となることもある)が図られることとなる。たとえば図表1のように、ある日本企業がアメリカ企業へ30%の出資を行う。この出資に対応する配当は、アメリカでは原則30%の源泉徴収の対象となるが、日米租税条約により5%での源泉徴収となるのである。
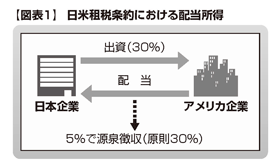
また、たとえば日本企業がアメリカ企業の所有する特許を日本国内で利用する場合、通常、この日本企業はアメリカ企業に対し、この特許の利用対価としてロイヤルティを支払うこととなろう。そしてこのロイヤルティは日本からの支払時に原則20%での源泉徴収が必要となるが、日米租税条約により免税となるのである(図表2参照)。
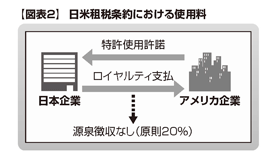
このように、投資先での源泉税が減免されることにより、当然のことながら投資が行いやすくなると期待される。これが、租税条約による最大の恩典の一つといえる。
(2)二重課税の排除効果 利子、配当等の投資所得に対する源泉税率が軽減されることは、結果的に二重課税の排除という効果をもたらす。利子や配当といった投資収益であっても、それを生み出すためのコストが必要であり、こうしたコストを勘案して収益をネットでとらえた場合、通常、支払額(グロス)に対する源泉税は過大な課税となってしまうケースが多いと考えられる。したがって、外国税額控除により二重課税を調整する際に、控除限度額を超過し、結果的に二重課税が排除されないことも起こりうるのである。源泉税率を軽減することは、外国税額控除における控除限度額を超過しないようにする方向に働き、結果的に二重課税の排除に資することとなる(脚注2)。
また、源泉税を課すのは、その国が、所得の源泉地であることを主張するからに他ならない。一つの所得に対して、二つの国が源泉地を主張すれば、源泉地課税の競合・重複が生じる(二重課税)ことは明白である。また、所得の源泉地を主張するということは、その国では国内所得としてとらえられることとなる。つまり国外所得としての認識ができないことであり、結果的に外国税額控除ができない可能性も高くなろう。
租税条約は、こうした源泉地の競合に対して所得源泉ルールを設け、所得の源泉地を振り分けることにより課税権を調整するとともに、結果として二重課税の排除を促す役割も果たしている。
3 租税条約ネットワーク 現在(平成22年10月現在)のところ、日本は48の租税条約を締結し、59カ国との間で適用がある。さらに、未発効の条約もあり、また現状、アラブ首長国連邦との交渉も進められているようである。
これら租税条約の締結相手国を見てみると、アフリカ諸国及び中南米を除き、日本と経済的な関係がある国は概ねカバーされつつある。当然のことながら、租税条約の対象は「租税」であり、その発生原因となる経済活動、経済交流がなければ、租税条約の存在そのものも必要ないところである。ある程度の経済的関係がある国々との間で租税条約が締結されている現在、日本の租税条約ネットワークは、数量の面からは概ね完成していると見ることもできる。
これら日本が締結した租税条約は、基本的には、グローバルスタンダードともいえる「OECDモデル条約」に準拠しつつ、条約締結当事国の諸事情を反映させたものとなっている。その内容からは、これまでの日本の租税条約ポリシーが読み取れるところであるが、また、それぞれ締結された時期の経済関係、経済情勢や世界的な国際課税についての考え方を反映させたものとなっている。たとえば、それまで使用料に対する源泉税率を10%とするのが日本のポリシーであったが(OECDモデル条約ではゼロ)、日米租税条約において、初めて使用料を免税としたことや、同じく日米租税条約において包括的な特典制限条項を導入したことは、こうした時代の要請を反映させたものである。
このように、租税条約は、締結された後も、経済情勢等に即して見直し、改正される必要がある。
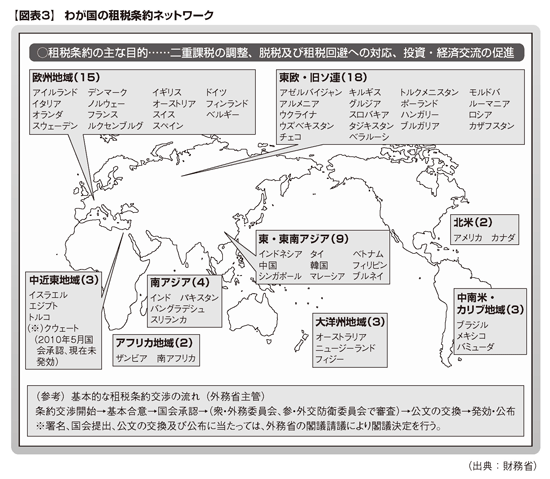
脚注
1 この源泉徴収の税率は、国によってまちまちである。日本の場合、15%(利子)または20%(配当、使用料など)であり、米国では原則30%とされている。
2 こうした観点から、日米租税条約においては金融機関等の受け取る利子が源泉税免除とされている。
この記事に関連するお問い合わせ先 この記事に関するお問い合わせは週刊「T&Amaster」編集部にお寄せください。執筆者に質問内容をお伝えいたします。
TEL:03-5281-0020 FAX:03-5281-0030 e-mail:ta@lotus21.co.jp
※なお、内容によっては回答いたしかねる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -

Copyright (C) 2019
SHINNIPPON-HOKI PUBLISHING CO.,LTD.





















