解説記事2011年01月10日 【新会計基準解説】 IASBのリース会計基準の公開草案について~日本基準との違い(2011年1月10日号・№385)
新会計基準解説
IASBのリース会計基準の公開草案について~日本基準との違い
さくら綜合事務所 公認会計士・税理士 中村里佳
Ⅰ はじめに
これまでのリース会計を抜本から変更する内容の公開草案が平成22年8月に国際会計基準審議会(IASB)から公表された(以下「新リース会計基準案」という)。新リース会計基準案は、これまでのオペレーティング・リースとファイナンス・リースのリース会計上の区別をなくし、借手と貸手に単一の新しい会計モデルを導入している。それは、すべてのリース契約に基づいて発生する権利と義務を財務諸表に資産と負債として認識することが要求されている。
これまでオペレーティング・リースは原則として「使用する権利」や「履行義務」を貸借対照表上に計上することはなかったが、新リース会計基準案では一部を除き、見積もりによる使用する権利や履行義務の計上を余儀なくされることになる(図表1参照)。これまでオペレーティング・リースにより資産計上せずに使用を続けていた資産を貸借対照表上に計上しなければならないだけではなく、減損会計の適用により、今まで計上されなかったリース資産の減損損失についても計上しなければならない可能性がでてきた。しかも計上する期間は契約期間だけではなく、50%超借りる(貸す)可能性のある最大期間となっているため、例えばオフィスや営業所の賃貸についてはたとえ2年更新の契約になっていたとしても長期間が対象となってくる可能性がある。
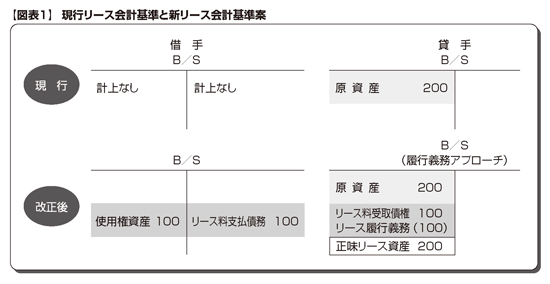
Ⅱ 誰が影響を受けるのか
日本では「リース契約」というと一部ファイナンス的な要素を含む賃貸取引という認識があるであろう。つまり、「レンタル」と「リース」は明確ではないにしろ、両者は異なるものとして言葉の定義がなされていることが多い。しかしながら新リース会計基準案の対象となる「リース」とは「特定資産を使用する権利を、一定期間にわたり、対価と交換に移転する契約」と定義されており、日本語で「レンタル」と表現されるような取引も含まれることになる。
これまでのリース会計の論点は主にファイナンス・リース取引に着目し、賃貸なのか売買なのかを問題としていた。したがってリース会計といえばリース契約の中のごく一部のファイナンス・リース取引に関連する企業のみが関連する会計基準であった。しかしながら今回の新リース会計基準案はオペレーティング・リースを含む全てのリース取引の会計基準を改訂するものであるため、ほとんどの企業が直面する会計基準の改訂となるであろう。飛行機やコンピュータシステム、機械リースだけではなく、例えばオフィスや営業所、店舗、倉庫等不動産の賃貸とか、OA機器のリースとか、ほとんどの会社がこのリース会計基準の適用の影響を受ける可能性があるのである。
特に賃貸不動産である「投資不動産」についてこの新リース会計基準案が適用されるとなると、賃貸不動産を保有する会社だけではなく、不動産を借りている企業にも影響を与えるものとなっている。現段階で国際会計基準は、IAS第40号「投資不動産」において、公正価値で測定されている投資不動産についてはリース会計基準の適用範囲から除くことを合意しているが、日本の投資不動産の会計基準はそもそも取得原価測定しか認められていないため、投資不動産の会計基準が改訂されない限り我が国においては全ての投資不動産について新リース会計基準案の適用を受けることになる。
Ⅲ 改正経緯
日本のリース会計取引に関する会計基準は平成5年に企業会計審議会第一部会から「リース取引に係る会計基準」が初めて公表され、平成19年に企業会計基準委員会から「リース取引に関する会計基準」として改正され現在適用の基準となっている。
平成5年の会計基準においてはリース会計をオペレーティング・リースとファイナンス・リースとに分類し、原則としてファイナンス・リースについては通常の売買に係る方法に準じて会計処理を行うこととしながらも、所有権移転外ファイナンス・リースについては、一定の注記を要件として通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を認めてきていた。しかしながら平成19年の改正により、この例外措置を廃止した。この改正により、国際会計基準や米国会計基準のリース会計と平仄を合わせたことになった。
一方、国際会計基準と米国会計基準は新リース会計基準開発の共同プロジェクトとして平成18年から検討を開始し、平成21年3月に借手の会計処理に関する提案を中心としたディスカッションペーパー「リース:予備的見解」を公表した。
そして今回平成22年8月に貸手の会計処理も含めた公開草案「リース」を共同で公表している。これを受けて企業会計基準委員会も「リース会計に関する論点整理」について、平成22年12月27日に公表している。
Ⅳ 新リース会計基準案の内容
1 適用範囲 新リース会計基準では(a)契約の履行が、特定の資産等の提供に依存していること、(b)契約が合意された期間にわたって特定の資産の使用を支配する権利を移転していることを満たすものをリースと定義し、以下の資産を除くすべてのリースが適用対象となる(ED5項~9項)。
・無形資産
・原資産の売買に相当する取引
・一定の不動産のリース(公正価値評価しているもの)
・契約にリース要素とサービス要素が含まれている場合のサービス要素
また、国際会計基準では、例えば委託契約など法律上はリース契約ではないものについても、特定の資産の使用権を移転する契約の中にリース契約として取り扱うものについても判断基準を有している(IFRIC第4号)。
2 借手の会計処理(ED10項~27項)~「使用権アプローチ(right-of-use approach)」による会計モデル~ 借手はリース契約開始時点(リース契約締結日とリースを約した日のいずれか早い日)で「資産使用権(リース資産を使用する権利)」を資産計上し、「リース料支払い義務」を負債として計上する。これまでオペレーティング・リースの場合、借手は支払う費用を損益計算書に計上するのみであり、「前払費用」「未払費用」の計上以外に貸借対照表に計上する会計基準はなかった。新リース会計基準案では借りる合理的な期間のリース料全額の現在価値等を資産及び負債に計上するわけで、全く新しい会計基準の導入となる。具体的な仕訳例等は以下の4「具体的な計算事例(現行案との比較)」を参考とされたい。
3 貸手の会計処理(ED28項~63項)~「履行義務アプローチ(performance obligation approach」と「認識中止アプローチ(derecognition approach)」の二つの会計モデルの提案~ 貸手は原資産に関する重要なリスク、または便益を留保しているかを判断し、「履行義務アプローチ」(図表2参照)を適用するか「認識中止アプローチ」(図表3参照)を適用するか決定する(図表4参照)。
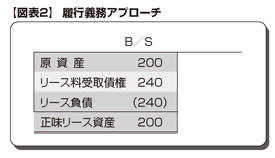
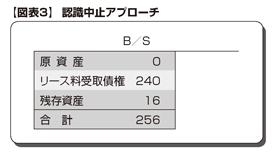

(1)履行義務アプローチ リース取引における貸手は、契約におけるリース料受取債権とリース負債(履行義務)を認識し会計処理を行う。つまり、原資産を計上したままリース債権債務を貸借対照表に計上することになる。
(2)認識中止アプローチ
履行義務アプローチによる契約におけるリース料債権とリース履行義務を貸借対照表に計上し会計処理を行うほか、貸手がリース物件に伴う重要なリスクまたは便益を留保していない場合には、貸手はそのリースに認識中止アプローチを適用し原資産の認識の中止(計上をとりやめ)をしなければならない。したがってこの場合には原資産とリース料債権が二重に計上されることはなくなる。しかし支配の移転と同様のリスク移転した場合に限られ、原資産の売却となるファイナンス・リースのこれまでの基準と近似する判断と想定されている。
4 具体的な計算事例(現行案との比較) 次に具体的な計算事例をみてみることにする。
この場合、借手の会計処理は以下のとおりとなる。

① リース料総額の現在価値をリース料支払債務として計上し、使用権資産として初期費用を加えて(例題では0)、使用権資産を計上する。
② 償却原価で測定し、実効金利法に従って利息費用を認識する。
③ リース期間または耐用年数のいずれか短い期間で規則的な方法により資産を償却する(240÷5年=48)。
※ 現行では毎年均等にリース料60百万円を費用計上していたが、新リース会計基準においてはリース期間の前の期間の方が後の期間よりも利息は多くなるため、これまでのオペレーティング・リースの費用処理よりも前倒しの費用化となる。
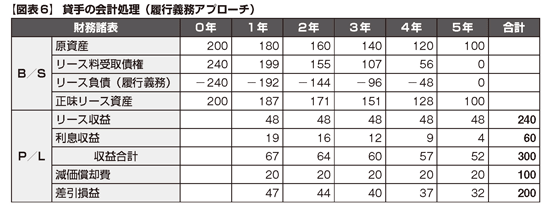
① 現行と同様。
② 現行と同様。
③ 貸手の利子率を使用した予想リース料総額の現在価値をリース負債として計上し、初期コスト(例題では0)を加えてリース料受取債権を計上する。
④ リース料受取債権を実効金利法に従って受取利息を計上していく。
⑤ リース負債(履行義務)をリース期間にわたり、履行義務を充足するに従い収益認識する。一般的には定額で収益認識する(費消パターンによる)。
※ 現行では毎年均等にリース料60百万円を売上計上していたが、新リース会計基準案においてはリース期間の前の期間の方が後の期間よりも利息は多くなるため、これまでのオペレーティング・リースの費用処理よりも前倒しの収益化となる。
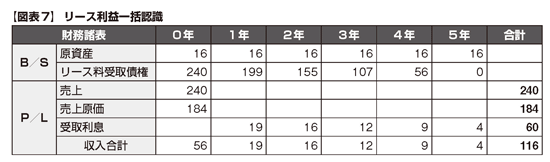
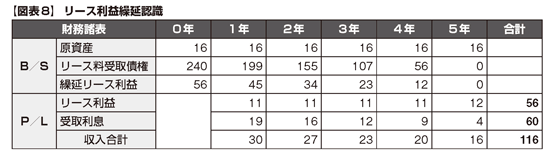
① 現行と同様。
②③ リース料受取債権を貸手の利子率で割引かれたリース料の現在価値+初期コストを売上計上し、原資産の帳簿価額にリース料の現在価値を原資産の公正価値で除した比率を乗じて売上原価を計上する。
④ リース利益を繰り延べる場合(図表8は利益を一括認識する方法)。
⑤ 同上。
⑥ リース料受取債権を実効金利法に従って受取利息を計上していく。
貸手は履行義務アプローチか、認識中止アプローチかにより、リース期間の合計する利益が異なることも想定されている。これは、認識中止アプローチにおいてはファイナンス・リースの譲渡処理と同様、売却する部分の原価と残存する原価の配分が行われるためであり、減価償却を原価とする履行義務アプローチとは対応する原価が異なるためである。
Ⅴ その他の論点
1 セール・アンド・リースバック 譲渡人からの移転がリース資産(原資産)の売却に関する条件を満たす場合にのみ、取引を売却とリースバック取引として会計処理する。
その譲渡が売却としての条件を満たさない場合には、譲渡人は金融取引として認識する。受け取った金額はすべて金融負債として認識する。
セール・アンド・リースバックの時には、通常の売却に関する判断基準(リース期間の終了時に所有権移転、割安購入権付与等)以外に以下のような条件を有している場合には売却とはならないとされている(ED・B31項)。
・公正価値ではない金額で買い戻す義務、オプション、買い戻しを強制可能な場合。
・売手が投資に係るリターンを保証している。
・売手が残価保証を提供している。
・売手がノンリコースローンの融資を提供している。
・売手が当該資産に係る既存の負債を返済する義務を留保している。
・売手が買手のために担保提供をしているか、債務の保証をしている。
・売手の支払賃料が、買手の将来の営業活動に関する何らかの事前に決定されたか、決定可能な水準に左右される。
・買手が資産の価値の増加相当分を売手と分け合う義務を有している。
2 サブリース サブリース契約においては、中間の貸手は貸手でもあり、借手にもなる。サブリース会社は使用権資産と転リースによるリース料受取債権およびリース負債を計上することになり、原リースによるリース料支払債務を転リースから生じる他の資産および負債と区別して表示することになる(ED43項)。特に相殺表示等の規定はされていない。
3 投資不動産 投資不動産についても新リース会計基準は今のところ除外されていない。しかしながら公開草案においては、IAS第40号において投資不動産の公正価値モデルが用いられている場合には新リース会計基準の適用はしないことが提案されている。現行の米国基準および日本基準においては、投資不動産について公正価値測定を認めてはいないため、投資不動産は全て新リース会計の範囲に含まれることになる。
しかしながら米国基準は現在投資不動産に公正価値測定を認める方向で検討されている(ED・BC57項)。
IASBのリース会計基準の公開草案について~日本基準との違い
さくら綜合事務所 公認会計士・税理士 中村里佳
Ⅰ はじめに
これまでのリース会計を抜本から変更する内容の公開草案が平成22年8月に国際会計基準審議会(IASB)から公表された(以下「新リース会計基準案」という)。新リース会計基準案は、これまでのオペレーティング・リースとファイナンス・リースのリース会計上の区別をなくし、借手と貸手に単一の新しい会計モデルを導入している。それは、すべてのリース契約に基づいて発生する権利と義務を財務諸表に資産と負債として認識することが要求されている。
これまでオペレーティング・リースは原則として「使用する権利」や「履行義務」を貸借対照表上に計上することはなかったが、新リース会計基準案では一部を除き、見積もりによる使用する権利や履行義務の計上を余儀なくされることになる(図表1参照)。これまでオペレーティング・リースにより資産計上せずに使用を続けていた資産を貸借対照表上に計上しなければならないだけではなく、減損会計の適用により、今まで計上されなかったリース資産の減損損失についても計上しなければならない可能性がでてきた。しかも計上する期間は契約期間だけではなく、50%超借りる(貸す)可能性のある最大期間となっているため、例えばオフィスや営業所の賃貸についてはたとえ2年更新の契約になっていたとしても長期間が対象となってくる可能性がある。
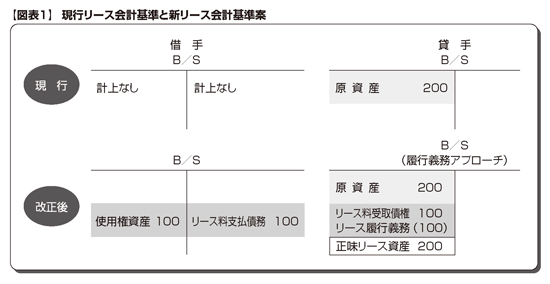
Ⅱ 誰が影響を受けるのか
日本では「リース契約」というと一部ファイナンス的な要素を含む賃貸取引という認識があるであろう。つまり、「レンタル」と「リース」は明確ではないにしろ、両者は異なるものとして言葉の定義がなされていることが多い。しかしながら新リース会計基準案の対象となる「リース」とは「特定資産を使用する権利を、一定期間にわたり、対価と交換に移転する契約」と定義されており、日本語で「レンタル」と表現されるような取引も含まれることになる。
これまでのリース会計の論点は主にファイナンス・リース取引に着目し、賃貸なのか売買なのかを問題としていた。したがってリース会計といえばリース契約の中のごく一部のファイナンス・リース取引に関連する企業のみが関連する会計基準であった。しかしながら今回の新リース会計基準案はオペレーティング・リースを含む全てのリース取引の会計基準を改訂するものであるため、ほとんどの企業が直面する会計基準の改訂となるであろう。飛行機やコンピュータシステム、機械リースだけではなく、例えばオフィスや営業所、店舗、倉庫等不動産の賃貸とか、OA機器のリースとか、ほとんどの会社がこのリース会計基準の適用の影響を受ける可能性があるのである。
特に賃貸不動産である「投資不動産」についてこの新リース会計基準案が適用されるとなると、賃貸不動産を保有する会社だけではなく、不動産を借りている企業にも影響を与えるものとなっている。現段階で国際会計基準は、IAS第40号「投資不動産」において、公正価値で測定されている投資不動産についてはリース会計基準の適用範囲から除くことを合意しているが、日本の投資不動産の会計基準はそもそも取得原価測定しか認められていないため、投資不動産の会計基準が改訂されない限り我が国においては全ての投資不動産について新リース会計基準案の適用を受けることになる。
Ⅲ 改正経緯
日本のリース会計取引に関する会計基準は平成5年に企業会計審議会第一部会から「リース取引に係る会計基準」が初めて公表され、平成19年に企業会計基準委員会から「リース取引に関する会計基準」として改正され現在適用の基準となっている。
平成5年の会計基準においてはリース会計をオペレーティング・リースとファイナンス・リースとに分類し、原則としてファイナンス・リースについては通常の売買に係る方法に準じて会計処理を行うこととしながらも、所有権移転外ファイナンス・リースについては、一定の注記を要件として通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を認めてきていた。しかしながら平成19年の改正により、この例外措置を廃止した。この改正により、国際会計基準や米国会計基準のリース会計と平仄を合わせたことになった。
一方、国際会計基準と米国会計基準は新リース会計基準開発の共同プロジェクトとして平成18年から検討を開始し、平成21年3月に借手の会計処理に関する提案を中心としたディスカッションペーパー「リース:予備的見解」を公表した。
そして今回平成22年8月に貸手の会計処理も含めた公開草案「リース」を共同で公表している。これを受けて企業会計基準委員会も「リース会計に関する論点整理」について、平成22年12月27日に公表している。
Ⅳ 新リース会計基準案の内容
1 適用範囲 新リース会計基準では(a)契約の履行が、特定の資産等の提供に依存していること、(b)契約が合意された期間にわたって特定の資産の使用を支配する権利を移転していることを満たすものをリースと定義し、以下の資産を除くすべてのリースが適用対象となる(ED5項~9項)。
・無形資産
・原資産の売買に相当する取引
・一定の不動産のリース(公正価値評価しているもの)
・契約にリース要素とサービス要素が含まれている場合のサービス要素
また、国際会計基準では、例えば委託契約など法律上はリース契約ではないものについても、特定の資産の使用権を移転する契約の中にリース契約として取り扱うものについても判断基準を有している(IFRIC第4号)。
2 借手の会計処理(ED10項~27項)~「使用権アプローチ(right-of-use approach)」による会計モデル~ 借手はリース契約開始時点(リース契約締結日とリースを約した日のいずれか早い日)で「資産使用権(リース資産を使用する権利)」を資産計上し、「リース料支払い義務」を負債として計上する。これまでオペレーティング・リースの場合、借手は支払う費用を損益計算書に計上するのみであり、「前払費用」「未払費用」の計上以外に貸借対照表に計上する会計基準はなかった。新リース会計基準案では借りる合理的な期間のリース料全額の現在価値等を資産及び負債に計上するわけで、全く新しい会計基準の導入となる。具体的な仕訳例等は以下の4「具体的な計算事例(現行案との比較)」を参考とされたい。
| (当初認識) 使用権資産:リース料支払債務+初期直接費用 リース料支払債務:借手の追加利子等により割引かれたリース期間における支払リース料の現在価値(貸手の利子率が容易に判明する場合にはその利子率を使用) (事後測定と再評価) 使用権資産の償却:リース期間または耐用年数のいずれか短い期間で規則的な方法により資産を償却する。また、IAS第36号に従って「資産の減損」の検討対象となる。有形固定資産の再評価モデルを採用することもできる。 リース料支払債務:償却原価で測定し、実効金利法に従って利息費用を認識する。 (リース期間) リース料支払債務はリース期間における支払リース料をもとに計算されるが、ここでいう「リース期間」は契約上の最低限の期間ではなく、発生する確率が発生しない確率よりも高いと考えられる最長の起こりうる期間と定義されており、契約上の要因のほか、契約外の様々な企業が置かれている要因も考慮しなければならない。 例えば10年の解約不能のリースに10年終了時に5年の更新オプション、更に5年後更新オプションを有し、企業は以下の発生可能性を判断している場合 ・10年の確率が40% ・15年の確率が30% ・20年の確率が30% このケースでは、解約は10年では発生しない確率が高く、15年では発生する確率が発生しない確率を上回るのでこのリースは15年をリース期間として計算することになる。 |
3 貸手の会計処理(ED28項~63項)~「履行義務アプローチ(performance obligation approach」と「認識中止アプローチ(derecognition approach)」の二つの会計モデルの提案~ 貸手は原資産に関する重要なリスク、または便益を留保しているかを判断し、「履行義務アプローチ」(図表2参照)を適用するか「認識中止アプローチ」(図表3参照)を適用するか決定する(図表4参照)。
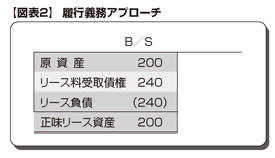
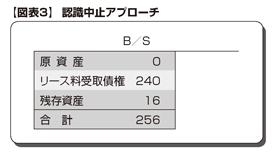

(1)履行義務アプローチ リース取引における貸手は、契約におけるリース料受取債権とリース負債(履行義務)を認識し会計処理を行う。つまり、原資産を計上したままリース債権債務を貸借対照表に計上することになる。
| (当初認識) リース資産(資産):認識の中止をしない。 リース債権(資産):貸手の利子率で割引かれたリース料の現在価値+初期コスト リース履行義務(負債):貸手の利子率を使用した予想リース料の現在価値 (事後測定) リース資産(資産)の償却:IAS第16号有形固定資産に従って償却 リース債権(資産):実効金利法に従って受取利息を計上していく。但し金融商品の減損を確認する。 リース履行義務(負債):リース期間にわたり、履行義務を充足するに従い収益認識する。一般的には定額で収益認識する(費消パターンによる)。 |
| (当初測定) リース資産(資産):リース期間の原資産を使用する借手の権利部分について認識の中止をする。
リース債権(資産):貸手の利子率で割引かれたリース料の現在価値+初期コスト (事後測定) リース資産(資産):残存する資産について必要に応じて再評価および減損損失の認識を行う場合を除き、再測定してはならない。 リース債権(資産):実効金利法に従って受取利息を計上していく。但し金融商品の減損を確認する。 |
4 具体的な計算事例(現行案との比較) 次に具体的な計算事例をみてみることにする。
| 例題 リース資産(原資産):200百万円 リース期間:5年 リース料:年60百万円 耐用年数:10年(年減価償却費20百万円) 割引率:8% リース料の総額の現在価値:240百万円 リース終了時の見積もり残存価値:21百万円 リース開始時の公正価値:261百万円 (残存価値案分簿価 16百万円 リース期間簿価 184百万円) |
この場合、借手の会計処理は以下のとおりとなる。
| (借手の会計処理) 現行の会計処理(毎期一律)
新リース会計基準案の会計処理(図表5参照)
|

① リース料総額の現在価値をリース料支払債務として計上し、使用権資産として初期費用を加えて(例題では0)、使用権資産を計上する。
② 償却原価で測定し、実効金利法に従って利息費用を認識する。
③ リース期間または耐用年数のいずれか短い期間で規則的な方法により資産を償却する(240÷5年=48)。
※ 現行では毎年均等にリース料60百万円を費用計上していたが、新リース会計基準においてはリース期間の前の期間の方が後の期間よりも利息は多くなるため、これまでのオペレーティング・リースの費用処理よりも前倒しの費用化となる。
| (貸手の会計処理) 現行の会計処理
新リース会計基準案の会計処理 A 履行義務アプローチ(図表6参照)
|
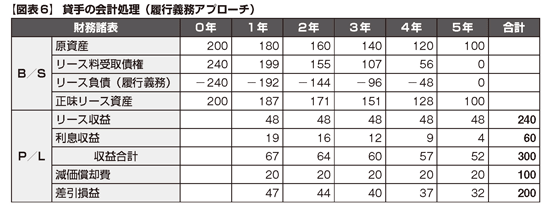
① 現行と同様。
② 現行と同様。
③ 貸手の利子率を使用した予想リース料総額の現在価値をリース負債として計上し、初期コスト(例題では0)を加えてリース料受取債権を計上する。
④ リース料受取債権を実効金利法に従って受取利息を計上していく。
⑤ リース負債(履行義務)をリース期間にわたり、履行義務を充足するに従い収益認識する。一般的には定額で収益認識する(費消パターンによる)。
※ 現行では毎年均等にリース料60百万円を売上計上していたが、新リース会計基準案においてはリース期間の前の期間の方が後の期間よりも利息は多くなるため、これまでのオペレーティング・リースの費用処理よりも前倒しの収益化となる。
B認識中止アプローチ(利息相当額を利息法で会計処理する方法)(図表7・8参照)
|
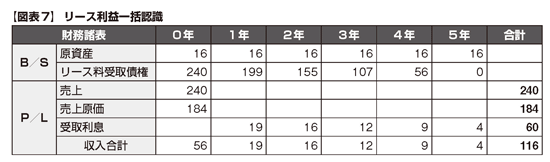
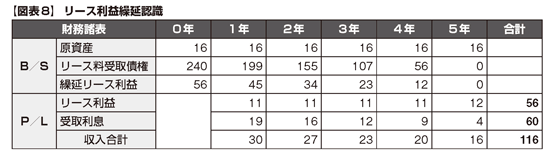
① 現行と同様。
②③ リース料受取債権を貸手の利子率で割引かれたリース料の現在価値+初期コストを売上計上し、原資産の帳簿価額にリース料の現在価値を原資産の公正価値で除した比率を乗じて売上原価を計上する。
④ リース利益を繰り延べる場合(図表8は利益を一括認識する方法)。
⑤ 同上。
⑥ リース料受取債権を実効金利法に従って受取利息を計上していく。
貸手は履行義務アプローチか、認識中止アプローチかにより、リース期間の合計する利益が異なることも想定されている。これは、認識中止アプローチにおいてはファイナンス・リースの譲渡処理と同様、売却する部分の原価と残存する原価の配分が行われるためであり、減価償却を原価とする履行義務アプローチとは対応する原価が異なるためである。
Ⅴ その他の論点
1 セール・アンド・リースバック 譲渡人からの移転がリース資産(原資産)の売却に関する条件を満たす場合にのみ、取引を売却とリースバック取引として会計処理する。
その譲渡が売却としての条件を満たさない場合には、譲渡人は金融取引として認識する。受け取った金額はすべて金融負債として認識する。
セール・アンド・リースバックの時には、通常の売却に関する判断基準(リース期間の終了時に所有権移転、割安購入権付与等)以外に以下のような条件を有している場合には売却とはならないとされている(ED・B31項)。
・公正価値ではない金額で買い戻す義務、オプション、買い戻しを強制可能な場合。
・売手が投資に係るリターンを保証している。
・売手が残価保証を提供している。
・売手がノンリコースローンの融資を提供している。
・売手が当該資産に係る既存の負債を返済する義務を留保している。
・売手が買手のために担保提供をしているか、債務の保証をしている。
・売手の支払賃料が、買手の将来の営業活動に関する何らかの事前に決定されたか、決定可能な水準に左右される。
・買手が資産の価値の増加相当分を売手と分け合う義務を有している。
2 サブリース サブリース契約においては、中間の貸手は貸手でもあり、借手にもなる。サブリース会社は使用権資産と転リースによるリース料受取債権およびリース負債を計上することになり、原リースによるリース料支払債務を転リースから生じる他の資産および負債と区別して表示することになる(ED43項)。特に相殺表示等の規定はされていない。
3 投資不動産 投資不動産についても新リース会計基準は今のところ除外されていない。しかしながら公開草案においては、IAS第40号において投資不動産の公正価値モデルが用いられている場合には新リース会計基準の適用はしないことが提案されている。現行の米国基準および日本基準においては、投資不動産について公正価値測定を認めてはいないため、投資不動産は全て新リース会計の範囲に含まれることになる。
しかしながら米国基準は現在投資不動産に公正価値測定を認める方向で検討されている(ED・BC57項)。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -

Copyright (C) 2019
SHINNIPPON-HOKI PUBLISHING CO.,LTD.




















