解説記事2011年05月23日 【税務マエストロ】 分割に際して未経過固定資産税相当額の金銭が交付される場合の取扱い(上)(2011年5月23日号・№403)
税務マエストロ
税務における第一人者“税務マエストロ”による税実務講座
今週のマエストロ&テーマ
分割に際して未経過固定資産税相当額の金銭が交付される場合の取扱い(上)
#16 朝長英樹(税理士)
略歴 財務省主税局において、金融取引に係る法人税改正(平成12年)・組織再編成税制の創設(平成13年)・連結納税制度の創設(平成14年)などを主導。
税務大学校研究部において、事業体税制等を研究。平成18年7月に税務大学校教授を最後に退官。日本税制研究所 代表理事(平成19年3月~)、参議院客員調査員(平成19年9月~20年2月)、税理士法人アクト22代表社員(平成20年4月~23年4月)、登録政治資金監査人(平成20年9月~)、朝長英樹税理士事務所 所長(平成23年4月~)
次回のテーマ
#17 見落としがちな国際課税のリスク
税理士法人プライスウォーターハウスクーパース 品川克己 税制改正や、中国進出企業の増加に伴い、国際課税上のリスクは高まっている。国際課税の第一人者がそのリスクを検証する。
※取り上げて欲しいテーマを編集部にお寄せください。
e-mail:ta@lotus21.co.jp
今回のテーマ 当社は、来年の4月1日に分割により固定資産を分割承継法人(当社と資本関係のない法人)に移転する予定となっていますが、来年の1月1日にはまだこの固定資産を持っていますので、来年も、この固定資産に課される固定資産税を支払わなければなりません。
しかし、この固定資産に関しては、来年の4月1日に分割によって分割承継法人に移転することになるため、この固定資産税の12分の9(来年の4月から12月までの9月分)を固定資産税の負担金として分割承継法人から現金で支払ってもらい、その支払ってもらった現金と当社の負担分である12分の3(来年の1月から3月までの3月分)の現金とを合わせて納税したいと考えています。
この場合、分割の税制上の取扱いは、どのようになるのでしょうか。
マエストロの解説
固定資産の取引においては、1月から12月まで(地域によっては、4月から翌年の3月まで)の1年間について固定資産税を負担するべき期間と考えて、その取引後の期間に対応する固定資産税に相当する金額(以下、「未経過固定資産税相当額」という。)を受け払いする実務が存在している。固定資産の移転を受けた者においては、その固定資産の代価に加えて、この未経過固定資産税相当額をその固定資産を移転した者に支払うわけである。
このように、分割において、固定資産が移転することに伴い、未経過固定資産税相当額の金銭の受払いが行われるということになると、分割が適格分割となるのか否か、また、未経過固定資産税相当額の金銭の受払いがある場合の取扱いがどのようなものとなるのかという問題が生ずることとなる。
以下、本号と407号においてこの問題に関する解説を行うこととするが、解説を行う項目は、下記の目次のとおりである。
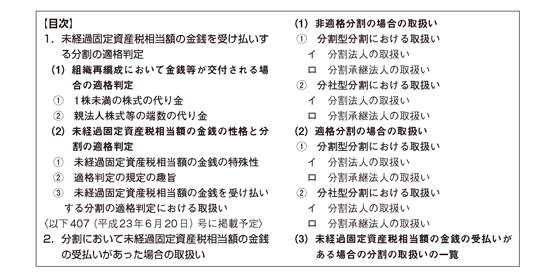
1 未経過固定資産税相当額の金銭を受け払いする分割の適格判定
(1)組織再編成において金銭等が交付される場合の適格判定 組織再編成に関する適格判定は、資産等の移転の対価として金銭等が交付される場合には非適格とするという点で共通となっている。
しかし、法令や通達において、1株未満の株式の代り金、親法人株式等の端数の代り金、剰余金の配当等として交付される金銭等、反対株主の買取請求に基づいて交付される金銭等が交付されても、それをもって組織再編成を非適格とはしないこととされている。
これらのうちの1株未満の株式の代り金と親法人株式等の端数の代り金に関しては、法人税法における適格判定の規定の解釈として、株式以外の資産に含めずに適格判定を行う、とされている。適格判定においても、画一的に対応するのではなく、特別なものに関しては、別途、適切な対応をとることとされているわけである。
剰余金の配当等として交付される金銭等と反対株主の買取請求に基づいて交付される金銭等に関しては、適格合併の場合には、法人税法2条(定義)の12号の8の規定において、「いずれか一方の株式又は出資以外の資産」から「当該株主等に対する剰余金の配当等(省略)として交付される金銭その他の資産及び合併に反対する当該株主等に対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産」を除いて適格判定を行う、と定められている。
<参考> 剰余金の配当等として交付される金銭等について考えてみると、いわゆる「配当落ち」の例からも分かるとおり、剰余金の配当等があれば株式の譲渡対価の額がその剰余金の配当等の額に相当する金額だけ減少するという関係にあるため、組織再編成に際して剰余金の配当等として交付される金銭等に関しては、これを「いずれか一方の株式又は出資以外の資産」から除かずに適格判定を行う仕組みとするという選択肢も立法論としては有り得る、ということになる。
また、組織再編成に際して反対株主の買取請求に基づいて交付される金銭等に関しても、組織再編成を全体として見れば、移転資産等の「対価」と捉えることが可能であり、これを「いずれか一方の株式又は出資以外の資産」から除かずに適格判定を行う仕組みとするという選択肢も有り得る。現に、アメリカの組織再編成に関する税制においては、反対株主等に交付される金銭等を含めて、我が国の適格判定に対応する判定を行うこととされている。
以下、①と②において、このような点を踏まえつつ、1株未満の株式の代り金と親法人株式等の端数の代り金に関して、もう少し詳しく内容を検討しておくこととするが、その検討等の便宜を考慮して、ここで関係法令等の確認を行っておくこととする(図表1参照)。
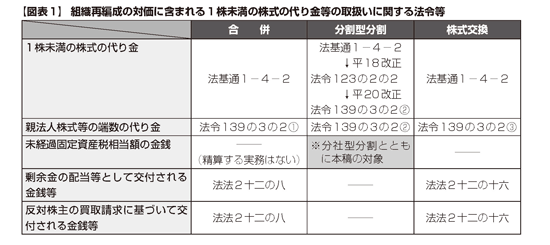
① 1株未満の株式の代り金 法人税基本通達1-4-2(合併等に際し1株未満の株式の譲渡代金を被合併法人等の株主等に交付した場合の適格合併等の判定)においては、次のように述べられている。
このように、合併等に際して交付される1株未満の株式の代り金に関しては、その経済的実質が1株未満の株式を交付することに代えてその時価に相当する金銭等の交付を行うものであるということを理由として、法人税基本通達により、交付される金銭等を株式と見て適格判定の規定を解釈するとしているわけである。
これは、金銭等が交付される場合であっても、適格判定の規定については、解釈によって適格と判定することがあり得る、ということを示すものとなっている。
ところで、この1株未満の株式の代り金に関しては、その発生の基因となる1株未満の株式と重複して交付されることはなく、移転する資産等の対価の額はこの1株未満の株式の代り金とそれ以外の株式等の時価との合計額となっている、という点にも留意する必要がある。
このように、1株未満の株式の代り金は移転する資産等の対価の一部であるため、組織再編成が非適格となってその移転する資産等の譲渡損益を計算するということになった場合には、当然のことながら、その移転する資産等の譲渡損益の計算上の譲渡収入の一部とされることになる。
「適格分割」に関して見てみると、法人税法2条12号の11にその定義が置かれているが、そこでは、「分割対価資産として分割承継法人の株式又は分割承継親法人株式(省略)のいずれか一方の株式以外の資産が交付されないもの(省略)」とされており、この「分割対価資産」とは、法人税法2条12号の9イ括弧書きにおいて「分割により分割法人が交付を受ける分割承継法人の株式(省略)その他の資産をいう」とされている。このため、その文言を字句どおりに解すれば、分割に際して交付される1株未満の株式の代り金はこの「分割対価資産」に含まれることとなる。
しかし、法人税法2条12号の11の規定の上記の部分に関しては、その文言を常に字句どおり形式的に解するのではなく、「分割対価資産」の内容を分析して、1株未満の株式の代り金が含まれている場合には、それを除いた上で同号の規定を適用するべきものと解されている。
<参考> 平成18年度改正による旧法人税法施行令123条の2の2(分割法人の株主等に交付されるべき分割承継法人の株式の端数の取扱い)の創設を受けて行われた改正前の法人税基本通達1-4-2においては、合併に関して現行の記述と同様の記述があり、その記述を受けて、「法人が行った分割が法第2条12号の11《適格分割》に規定する適格分割に該当するかどうかを判定する場合も、同様とする。」との文言が存在していた。
旧法人税法施行令123条の2の2は、その後、平成20年度改正において、法人税法施行令139条の3の2(合併等により交付する株式に一に満たない端数がある場合の所得計算)の2項として、一部、修正を加えた上で、承継されているが、これらの規定は、いずれも所得の金額の計算に関する定めであって、適格判定の定めではない。
ただし、法人税基本通達1-4-2から上記の文言が削除されたのは、政令により所得の金額の計算においてその取扱いが定められたため、適格判定における取扱いにおいても疑義がなくなった、という理解によるものと考えられる。
既に述べたとおり、分割に際して資産等の移転を受ける分割承継法人が交付するものは、分割を全体として見れば、その全てが「対価」となるはずであるが、適格判定の場面においては、その「対価」の内容がどのようなものとなっているのかを分析し、そこに1株未満の株式の代り金が含まれているということであれば、その1株未満の株式の代り金については、適格判定の規定である法人税法2条12号の11の「いずれか一方の株式以外の資産」には該当しない、とすることになるわけである。
② 親法人株式等の端数の代り金 「親法人株式等」とは、法人税法2条12号の8括弧書きにおいて「合併法人との間に当該合併法人の発行済株式等の全部を保有する関係として政令で定める関係がある法人の株式又は出資をいう」とされており、平成19年度改正において三角合併に適格要件を拡大するに当たって新たにその定義が設けられたわけであるが、その後、平成20年度改正で新たに設けられた親法人株式等の端数の代り金の取扱い(法令139の3の2①~③)は、組織再編成税制の適格判定における「対価」に関する考え方を確認する上で参考となるものとなっている。
三角合併に際し、合併法人は、合併親法人から取得して資産として保有している親法人株式等を対価として交付することとなるが、この際には、合併交付金として金銭等を交付する場合と同様に、その有する資産を減少させる処理を行うこととなり、合併法人株式を交付する場合のように資本金等の額を増加させる処理を行うわけではない。このような点からすると、親法人株式等の端数の代り金の交付は、上記(1)で述べた合併法人株式の1株未満の株式の代り金の交付よりも、なお一層、合併交付金の交付に近い、と考えることができる。
この親法人株式等の端数の代り金に関しては、平成20年度改正において、これを親法人株式等と同様に取り扱うこととし(法令139の3の2①)、分割型分割と株式交換においても同様とされているわけであるが(同②・③)、この改正に関しては、次のように説明されている。
この平成20年度改正で新たに設けられた法人税法施行令139条の3の2第1項から3項までの規定は、法人の各事業年度の所得の金額の計算に関する定めとなっており、適格判定の規定に関して定めるものではないが、上記のとおり、『平成20年度 税制改正の解説』によれば、適格要件においても、親法人株式等の端数の代り金に関しては、これを親法人株式等として判定をするべきであり、それが平成20年度のこれらの規定の改正によって明確化された、と認識されている(注)。そして、このような取扱いとするべき理由に関しては、「やむを得ず交付されたものであるため」とされている。
(注)法人税法施行令139条の3の2第1項から3項までの規定は、適格判定の規定ではないため、平成20年度改正においては、適格判定に関しては、法人税法の規定の解釈により、親法人株式等の端数の代り金を親法人株式等として判定をするべきであると考えられていた、ということになる。
ところで、この親法人株式等の端数の代り金を親法人株式等として適格判定を行うこととしたとしても、上記①の1株未満の株式の代り金の場合と同様に、他の適格要件に抵触し、合併が非適格となることも有り得る。この場合に、どのような取扱いとなるのかということを考えてみると、親法人株式等の端数の代り金は、1株未満の株式の代り金と同じように、合併によって移転する資産等の対価を構成するものであるため、被合併法人において、移転する資産等の譲渡損益の計算上の譲渡収入の一部とされることとなる。
このことは、合併によって移転する資産等の譲渡損益を計算する場合に親法人株式等の端数の代り金が被合併法人において譲渡収入とされるということが、その組織再編成が適格であるのか否かということを判定する場合に親法人株式等の端数の代り金が被合併法人において交付を受ける金銭等とされるということを意味するわけではない、ということを示している。
組織再編成が適格であるのか否かということを判定する場面と、その組織再編成によって移転する資産等の譲渡損益を計算する場面は、相互に連動する部分を有しつつも、異なる場面となっていることは、改めて言うまでもない。
(2)未経過固定資産税相当額の金銭の性格と分割の適格判定
① 未経過固定資産税相当額の金銭の特殊性 分割承継法人から分割法人に交付される未経過固定資産税相当額の金銭も、分割を全体として見れば分割によって移転する資産等の対価の一部と見るべきものであって、分割に際して交付される金銭であることに変わりはない。これは、未経過固定資産税相当額の金銭の受払いが固定資産の移転と離れて別の取引として存在し得ないことからしても、明らかである。組織再編成の全体を俯瞰して、上記(1)において述べた1株未満の株式の代り金、親法人株式等の端数の代り金、剰余金の配当等として交付される金銭等、反対株主の買取請求に基づいて交付される金銭等の4つの位置関係(図表2参照)を確認してみると、前の2つが合併や分割の中の取引とされており、後の2つが合併や分割の外の取引とされているわけであるが、未経過固定資産税相当額の金銭は、前の2つと同様に、組織再編成の中の取引となっているわけである。
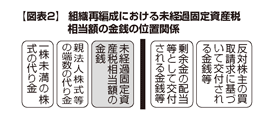
しかし、この未経過固定資産税相当額の金銭は、移転する固定資産の対価そのものである1株未満の株式の代り金や親法人株式等の端数の代り金とも異なり、分割によって移転する固定資産に課される固定資産税のその移転後の期間に対応するものとなっていることがその算出方法から明らかである。分割を含む組織再編成においては、移転する資産の公正価値をその資産から得られる将来のキャッシュフローによって算出する方法によって求めることが多くなっているが、分割によって移転する固定資産のこの方法によって求めた公正価値は、この未経過固定資産税相当額の金銭の有無や多寡によって変わることはない。
要するに、未経過固定資産税相当額の金銭の受払いは、固定資産を移転する取引の一部となっているものであり、固定資産を移転する取引と別の取引ということではないが、固定資産そのものの移転と未経過固定資産税相当額の金銭の受払いとをまったく同一と見ることはできず、両者には相違がある、ということである(図表3参照)。
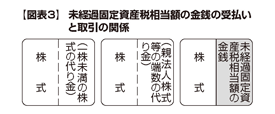
また、固定資産の譲渡取引においては、固定資産税を保有期間に応じて負担するのが合理的であるという認識が広く存在し、そのために、固定資産を移転する取引を行う場合には、未経過固定資産税相当額の金銭を受け払いするという実務が慣行的に広く行われてきたことにも留意する必要がある。固定資産を移転する取引において未経過固定資産税相当額の金銭の受払いが行われるケースがどの程度の割合となっているのかということは明らかではないが、その慣行があるところでのみ行われる借地権取引などとは異なり、相当額の固定資産税の課税が行われる固定資産を移転する取引においては、かなり高い割合で未経過固定資産税相当額の金銭の受払いが行われている可能性がある(注)。
(注)分割においても、固定資産を移転することとなるため、未経過固定資産税相当額の受払いをするべきであるが、法人税の取扱いが不明確で税に関して大きなリスクがあるために行い得ない、との指摘がなされてきた。
特に、税制改正の直後の時期などにおいては、税制上の取扱いが明確でないために、取引を行うことが難しいという例や取引の内容が変わってしまうという例が生ずることがあるが、本件に関しても、組織再編成において未経過固定資産税相当額の金銭の受払いをした場合の税制上の取扱いが不明確であるということが実務に大きな影響を与えているという現実を踏まえた上で、検討を行う必要がある。
未経過固定資産税相当額の金銭には、このような特殊性があるわけであるが、その取扱いは、当然、このような特殊性を考慮したものとなっていなければならない。
② 適格判定の規定の趣旨 法人税法2条12号の11の適格分割の定義は、他の適格組織再編成の定義と同様に、移転資産に対する支配が継続していると考えられるものについて移転資産の譲渡損益の計上を繰り延べるという趣旨によって設けられたものである(注)。
(注)「 このように、形式上は資産を他の法人に移転したが、実質上はまだその資産を保有していると言うことができる状態を、「移転資産に対する支配が継続」している状態と呼び、移転資産の譲渡損益の計上を繰り延べる課税特例の対象とすることとされたわけです。」(朝長英樹『企業組織再編成に係る税制についての講演録集』(日本租税研究協会、平成13年)25頁)
そして、移転する資産の対価として金銭等を交付する場合には非適格とすることとされているが、これは、次の引用からも分かるとおり、そのような組織再編成については、その経済実態が通常の売買取引と異ならない、と考えられるためである。
ただし、この適格判定に関しては、移転する資産の対価として交付する金銭等の多寡にかかわらず、1円でも交付する場合には、非適格とする、という割切りがなされている。
③ 未経過固定資産税相当額の金銭を受け払いする分割の適格判定における取扱い 上記①で述べたとおり、分割によって移転する固定資産の未経過固定資産税相当額の金銭の受払いに関しては、分割を全体として見た場合には対価の受払いとなるものではあるが、その固定資産そのものの対価の受払いとは言い難いこと、そして、未経過固定資産税相当額の金銭の受払いを行う実務が慣行的に行われてきたということ、この2つをその特殊性として挙げることができる。
また、上記②で述べたとおり、移転資産の対価として金銭等を交付する組織再編成を非適格とした趣旨は、そのような組織再編成はその経済実態が通常の売買取引と異ならないと考えられるということである。
このような点からすると、上記①で述べた特殊性のある未経過固定資産税相当額の金銭の受け払いをする分割が上記②で引用した「会社分割・合併等の企業組織再編成に係る税制の基本的考え方」で述べられている「通常の売買取引」と異ならないということになるのか否かということが問題となるわけであるが、これに関しては、固定資産そのものの対価として金銭等が交付されるのか否かによって「通常の売買取引」と異なるのか否かを判定するのが適切である、ということとなるものと考えられる。例えば、分割において移転する固定資産の未経過固定資産税相当額の金銭のみが交付されてその固定資産そのものの対価として交付される金銭がまったくないという場合には、その分割を「通常の売買取引」と異ならないと見ることはできない、と言わざるを得ない。このような点からすると、分割において、移転する固定資産の未経過固定資産税相当額の金銭のみが交付されてその固定資産そのものの対価として交付する分割承継法人の株式以外の資産がまったくないという場合には、その分割を非適格とするのは妥当でない、ということになろう。
仮に、移転する固定資産の未経過固定資産税相当額の金銭の交付があることをもって分割を非適格とするということになれば、移転する固定資産そのものの対価として交付する分割承継法人の株式以外の資産があるのか否かにかかわらず、慣行に従うのか否かによって適格か否かを決めるということになってしまうが、そのような取扱いは、個々の組織再編成ごとにその経済実態に即して適格判定を行おうとする法人税法2条12号の11の規定の趣旨に合わないものである。
記事に関連するお問い合わせ先 記事に関するお問い合わせは週刊「T&Amaster」編集部にお寄せください。執筆者に質問内容をお伝えいたします。
TEL:03-5281-0020 FAX:03-5281-0030 e-mail:ta@lotus21.co.jp
※なお、内容によっては回答いたしかねる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
今週のマエストロ&テーマ
分割に際して未経過固定資産税相当額の金銭が交付される場合の取扱い(上)
#16 朝長英樹(税理士)
略歴 財務省主税局において、金融取引に係る法人税改正(平成12年)・組織再編成税制の創設(平成13年)・連結納税制度の創設(平成14年)などを主導。
税務大学校研究部において、事業体税制等を研究。平成18年7月に税務大学校教授を最後に退官。日本税制研究所 代表理事(平成19年3月~)、参議院客員調査員(平成19年9月~20年2月)、税理士法人アクト22代表社員(平成20年4月~23年4月)、登録政治資金監査人(平成20年9月~)、朝長英樹税理士事務所 所長(平成23年4月~)
次回のテーマ
#17 見落としがちな国際課税のリスク
税理士法人プライスウォーターハウスクーパース 品川克己 税制改正や、中国進出企業の増加に伴い、国際課税上のリスクは高まっている。国際課税の第一人者がそのリスクを検証する。
※取り上げて欲しいテーマを編集部にお寄せください。
e-mail:ta@lotus21.co.jp
今回のテーマ 当社は、来年の4月1日に分割により固定資産を分割承継法人(当社と資本関係のない法人)に移転する予定となっていますが、来年の1月1日にはまだこの固定資産を持っていますので、来年も、この固定資産に課される固定資産税を支払わなければなりません。
しかし、この固定資産に関しては、来年の4月1日に分割によって分割承継法人に移転することになるため、この固定資産税の12分の9(来年の4月から12月までの9月分)を固定資産税の負担金として分割承継法人から現金で支払ってもらい、その支払ってもらった現金と当社の負担分である12分の3(来年の1月から3月までの3月分)の現金とを合わせて納税したいと考えています。
この場合、分割の税制上の取扱いは、どのようになるのでしょうか。
マエストロの解説
固定資産の取引においては、1月から12月まで(地域によっては、4月から翌年の3月まで)の1年間について固定資産税を負担するべき期間と考えて、その取引後の期間に対応する固定資産税に相当する金額(以下、「未経過固定資産税相当額」という。)を受け払いする実務が存在している。固定資産の移転を受けた者においては、その固定資産の代価に加えて、この未経過固定資産税相当額をその固定資産を移転した者に支払うわけである。
このように、分割において、固定資産が移転することに伴い、未経過固定資産税相当額の金銭の受払いが行われるということになると、分割が適格分割となるのか否か、また、未経過固定資産税相当額の金銭の受払いがある場合の取扱いがどのようなものとなるのかという問題が生ずることとなる。
以下、本号と407号においてこの問題に関する解説を行うこととするが、解説を行う項目は、下記の目次のとおりである。
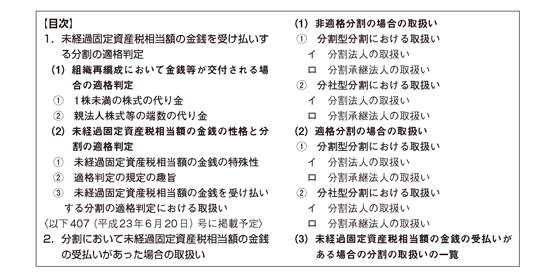
1 未経過固定資産税相当額の金銭を受け払いする分割の適格判定
(1)組織再編成において金銭等が交付される場合の適格判定 組織再編成に関する適格判定は、資産等の移転の対価として金銭等が交付される場合には非適格とするという点で共通となっている。
しかし、法令や通達において、1株未満の株式の代り金、親法人株式等の端数の代り金、剰余金の配当等として交付される金銭等、反対株主の買取請求に基づいて交付される金銭等が交付されても、それをもって組織再編成を非適格とはしないこととされている。
これらのうちの1株未満の株式の代り金と親法人株式等の端数の代り金に関しては、法人税法における適格判定の規定の解釈として、株式以外の資産に含めずに適格判定を行う、とされている。適格判定においても、画一的に対応するのではなく、特別なものに関しては、別途、適切な対応をとることとされているわけである。
剰余金の配当等として交付される金銭等と反対株主の買取請求に基づいて交付される金銭等に関しては、適格合併の場合には、法人税法2条(定義)の12号の8の規定において、「いずれか一方の株式又は出資以外の資産」から「当該株主等に対する剰余金の配当等(省略)として交付される金銭その他の資産及び合併に反対する当該株主等に対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産」を除いて適格判定を行う、と定められている。
<参考> 剰余金の配当等として交付される金銭等について考えてみると、いわゆる「配当落ち」の例からも分かるとおり、剰余金の配当等があれば株式の譲渡対価の額がその剰余金の配当等の額に相当する金額だけ減少するという関係にあるため、組織再編成に際して剰余金の配当等として交付される金銭等に関しては、これを「いずれか一方の株式又は出資以外の資産」から除かずに適格判定を行う仕組みとするという選択肢も立法論としては有り得る、ということになる。
また、組織再編成に際して反対株主の買取請求に基づいて交付される金銭等に関しても、組織再編成を全体として見れば、移転資産等の「対価」と捉えることが可能であり、これを「いずれか一方の株式又は出資以外の資産」から除かずに適格判定を行う仕組みとするという選択肢も有り得る。現に、アメリカの組織再編成に関する税制においては、反対株主等に交付される金銭等を含めて、我が国の適格判定に対応する判定を行うこととされている。
以下、①と②において、このような点を踏まえつつ、1株未満の株式の代り金と親法人株式等の端数の代り金に関して、もう少し詳しく内容を検討しておくこととするが、その検討等の便宜を考慮して、ここで関係法令等の確認を行っておくこととする(図表1参照)。
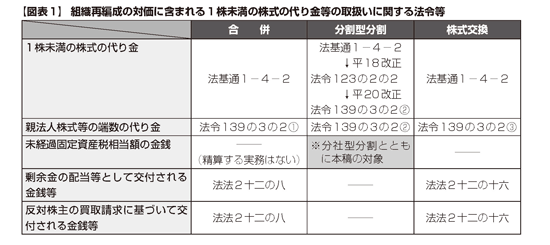
① 1株未満の株式の代り金 法人税基本通達1-4-2(合併等に際し1株未満の株式の譲渡代金を被合併法人等の株主等に交付した場合の適格合併等の判定)においては、次のように述べられている。
| 「 法人が行った合併が法第2条第12号の8《適格合併》に規定する適格合併に該当するかどうかを判定する場合において、被合併法人の株主等に交付された金銭が、その合併に際して交付すべき合併法人の株式(出資を含む。以下1-4-2において同じ。)に1株未満の端数が生じたためにその1株未満の株式の合計数に相当する数の株式を他に譲渡し、又は買い取った代金として交付されたものであるときは、当該株主等に対してその1株未満の株式に相当する株式を交付したこととなることに留意する。ただし、その交付された金銭が、その交付の状況その他の事由を総合的に勘案して実質的に当該株主等に対して支払う合併の対価であると認められるときは、当該合併の対価として金銭が交付されたものとして取り扱う。 法人が行った株式交換又は株式移転が法第2条第12号の16《適格株式交換》又は第12号の17《適格株式移転》に規定する適格株式交換又は適格株式移転に該当するかどうかを判定する場合についても、同様とする。 (注)(省略)」 |
これは、金銭等が交付される場合であっても、適格判定の規定については、解釈によって適格と判定することがあり得る、ということを示すものとなっている。
ところで、この1株未満の株式の代り金に関しては、その発生の基因となる1株未満の株式と重複して交付されることはなく、移転する資産等の対価の額はこの1株未満の株式の代り金とそれ以外の株式等の時価との合計額となっている、という点にも留意する必要がある。
このように、1株未満の株式の代り金は移転する資産等の対価の一部であるため、組織再編成が非適格となってその移転する資産等の譲渡損益を計算するということになった場合には、当然のことながら、その移転する資産等の譲渡損益の計算上の譲渡収入の一部とされることになる。
「適格分割」に関して見てみると、法人税法2条12号の11にその定義が置かれているが、そこでは、「分割対価資産として分割承継法人の株式又は分割承継親法人株式(省略)のいずれか一方の株式以外の資産が交付されないもの(省略)」とされており、この「分割対価資産」とは、法人税法2条12号の9イ括弧書きにおいて「分割により分割法人が交付を受ける分割承継法人の株式(省略)その他の資産をいう」とされている。このため、その文言を字句どおりに解すれば、分割に際して交付される1株未満の株式の代り金はこの「分割対価資産」に含まれることとなる。
しかし、法人税法2条12号の11の規定の上記の部分に関しては、その文言を常に字句どおり形式的に解するのではなく、「分割対価資産」の内容を分析して、1株未満の株式の代り金が含まれている場合には、それを除いた上で同号の規定を適用するべきものと解されている。
<参考> 平成18年度改正による旧法人税法施行令123条の2の2(分割法人の株主等に交付されるべき分割承継法人の株式の端数の取扱い)の創設を受けて行われた改正前の法人税基本通達1-4-2においては、合併に関して現行の記述と同様の記述があり、その記述を受けて、「法人が行った分割が法第2条12号の11《適格分割》に規定する適格分割に該当するかどうかを判定する場合も、同様とする。」との文言が存在していた。
旧法人税法施行令123条の2の2は、その後、平成20年度改正において、法人税法施行令139条の3の2(合併等により交付する株式に一に満たない端数がある場合の所得計算)の2項として、一部、修正を加えた上で、承継されているが、これらの規定は、いずれも所得の金額の計算に関する定めであって、適格判定の定めではない。
ただし、法人税基本通達1-4-2から上記の文言が削除されたのは、政令により所得の金額の計算においてその取扱いが定められたため、適格判定における取扱いにおいても疑義がなくなった、という理解によるものと考えられる。
既に述べたとおり、分割に際して資産等の移転を受ける分割承継法人が交付するものは、分割を全体として見れば、その全てが「対価」となるはずであるが、適格判定の場面においては、その「対価」の内容がどのようなものとなっているのかを分析し、そこに1株未満の株式の代り金が含まれているということであれば、その1株未満の株式の代り金については、適格判定の規定である法人税法2条12号の11の「いずれか一方の株式以外の資産」には該当しない、とすることになるわけである。
② 親法人株式等の端数の代り金 「親法人株式等」とは、法人税法2条12号の8括弧書きにおいて「合併法人との間に当該合併法人の発行済株式等の全部を保有する関係として政令で定める関係がある法人の株式又は出資をいう」とされており、平成19年度改正において三角合併に適格要件を拡大するに当たって新たにその定義が設けられたわけであるが、その後、平成20年度改正で新たに設けられた親法人株式等の端数の代り金の取扱い(法令139の3の2①~③)は、組織再編成税制の適格判定における「対価」に関する考え方を確認する上で参考となるものとなっている。
三角合併に際し、合併法人は、合併親法人から取得して資産として保有している親法人株式等を対価として交付することとなるが、この際には、合併交付金として金銭等を交付する場合と同様に、その有する資産を減少させる処理を行うこととなり、合併法人株式を交付する場合のように資本金等の額を増加させる処理を行うわけではない。このような点からすると、親法人株式等の端数の代り金の交付は、上記(1)で述べた合併法人株式の1株未満の株式の代り金の交付よりも、なお一層、合併交付金の交付に近い、と考えることができる。
この親法人株式等の端数の代り金に関しては、平成20年度改正において、これを親法人株式等と同様に取り扱うこととし(法令139の3の2①)、分割型分割と株式交換においても同様とされているわけであるが(同②・③)、この改正に関しては、次のように説明されている。
| 「 法人が自己を合併法人とする合併により合併対価として親法人株式等を交付する場合において、被合併法人の株主が交付を受けることとなる親法人株式等に1に満たない端数が生ずることとなり、その端数に代えて金銭が交付されたときに、「親法人株式等以外の資産が交付されないこと」(法法2十二の八、法法61の2②)という要件に該当しているといえるのか、不明確であるとの指摘もあったところです。 この対価要件の判定に当たって、親法人株式等の端数相当金額が交付された場合には、それは端株制度がないことにより端株に代えてやむを得ず交付されたものであるため、合併法人株式が交付される場合と同様に、一旦親法人株式等が交付されたものとして取り扱うべきと考えられます。(省略)これにより、合併対価として親法人株式等を交付する合併において、親法人株式等の1に満たない端数に代えて金銭が交付された場合には、その金銭を親法人株式等としてその合併が適格合併の要件及び被合併法人の株主の旧株の譲渡損益の計上を繰り延べる合併の要件のうち対価要件に該当するか否かを判定することが明確化されたものといえます。」(『平成20年度 税制改正の解説』(財務省)335頁) |
(注)法人税法施行令139条の3の2第1項から3項までの規定は、適格判定の規定ではないため、平成20年度改正においては、適格判定に関しては、法人税法の規定の解釈により、親法人株式等の端数の代り金を親法人株式等として判定をするべきであると考えられていた、ということになる。
ところで、この親法人株式等の端数の代り金を親法人株式等として適格判定を行うこととしたとしても、上記①の1株未満の株式の代り金の場合と同様に、他の適格要件に抵触し、合併が非適格となることも有り得る。この場合に、どのような取扱いとなるのかということを考えてみると、親法人株式等の端数の代り金は、1株未満の株式の代り金と同じように、合併によって移転する資産等の対価を構成するものであるため、被合併法人において、移転する資産等の譲渡損益の計算上の譲渡収入の一部とされることとなる。
このことは、合併によって移転する資産等の譲渡損益を計算する場合に親法人株式等の端数の代り金が被合併法人において譲渡収入とされるということが、その組織再編成が適格であるのか否かということを判定する場合に親法人株式等の端数の代り金が被合併法人において交付を受ける金銭等とされるということを意味するわけではない、ということを示している。
組織再編成が適格であるのか否かということを判定する場面と、その組織再編成によって移転する資産等の譲渡損益を計算する場面は、相互に連動する部分を有しつつも、異なる場面となっていることは、改めて言うまでもない。
(2)未経過固定資産税相当額の金銭の性格と分割の適格判定
① 未経過固定資産税相当額の金銭の特殊性 分割承継法人から分割法人に交付される未経過固定資産税相当額の金銭も、分割を全体として見れば分割によって移転する資産等の対価の一部と見るべきものであって、分割に際して交付される金銭であることに変わりはない。これは、未経過固定資産税相当額の金銭の受払いが固定資産の移転と離れて別の取引として存在し得ないことからしても、明らかである。組織再編成の全体を俯瞰して、上記(1)において述べた1株未満の株式の代り金、親法人株式等の端数の代り金、剰余金の配当等として交付される金銭等、反対株主の買取請求に基づいて交付される金銭等の4つの位置関係(図表2参照)を確認してみると、前の2つが合併や分割の中の取引とされており、後の2つが合併や分割の外の取引とされているわけであるが、未経過固定資産税相当額の金銭は、前の2つと同様に、組織再編成の中の取引となっているわけである。
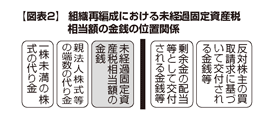
しかし、この未経過固定資産税相当額の金銭は、移転する固定資産の対価そのものである1株未満の株式の代り金や親法人株式等の端数の代り金とも異なり、分割によって移転する固定資産に課される固定資産税のその移転後の期間に対応するものとなっていることがその算出方法から明らかである。分割を含む組織再編成においては、移転する資産の公正価値をその資産から得られる将来のキャッシュフローによって算出する方法によって求めることが多くなっているが、分割によって移転する固定資産のこの方法によって求めた公正価値は、この未経過固定資産税相当額の金銭の有無や多寡によって変わることはない。
要するに、未経過固定資産税相当額の金銭の受払いは、固定資産を移転する取引の一部となっているものであり、固定資産を移転する取引と別の取引ということではないが、固定資産そのものの移転と未経過固定資産税相当額の金銭の受払いとをまったく同一と見ることはできず、両者には相違がある、ということである(図表3参照)。
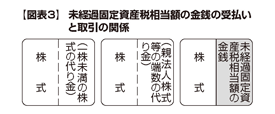
また、固定資産の譲渡取引においては、固定資産税を保有期間に応じて負担するのが合理的であるという認識が広く存在し、そのために、固定資産を移転する取引を行う場合には、未経過固定資産税相当額の金銭を受け払いするという実務が慣行的に広く行われてきたことにも留意する必要がある。固定資産を移転する取引において未経過固定資産税相当額の金銭の受払いが行われるケースがどの程度の割合となっているのかということは明らかではないが、その慣行があるところでのみ行われる借地権取引などとは異なり、相当額の固定資産税の課税が行われる固定資産を移転する取引においては、かなり高い割合で未経過固定資産税相当額の金銭の受払いが行われている可能性がある(注)。
(注)分割においても、固定資産を移転することとなるため、未経過固定資産税相当額の受払いをするべきであるが、法人税の取扱いが不明確で税に関して大きなリスクがあるために行い得ない、との指摘がなされてきた。
特に、税制改正の直後の時期などにおいては、税制上の取扱いが明確でないために、取引を行うことが難しいという例や取引の内容が変わってしまうという例が生ずることがあるが、本件に関しても、組織再編成において未経過固定資産税相当額の金銭の受払いをした場合の税制上の取扱いが不明確であるということが実務に大きな影響を与えているという現実を踏まえた上で、検討を行う必要がある。
未経過固定資産税相当額の金銭には、このような特殊性があるわけであるが、その取扱いは、当然、このような特殊性を考慮したものとなっていなければならない。
② 適格判定の規定の趣旨 法人税法2条12号の11の適格分割の定義は、他の適格組織再編成の定義と同様に、移転資産に対する支配が継続していると考えられるものについて移転資産の譲渡損益の計上を繰り延べるという趣旨によって設けられたものである(注)。
(注)「 このように、形式上は資産を他の法人に移転したが、実質上はまだその資産を保有していると言うことができる状態を、「移転資産に対する支配が継続」している状態と呼び、移転資産の譲渡損益の計上を繰り延べる課税特例の対象とすることとされたわけです。」(朝長英樹『企業組織再編成に係る税制についての講演録集』(日本租税研究協会、平成13年)25頁)
そして、移転する資産の対価として金銭等を交付する場合には非適格とすることとされているが、これは、次の引用からも分かるとおり、そのような組織再編成については、その経済実態が通常の売買取引と異ならない、と考えられるためである。
| 「 いずれの場合にも、移転資産の対価として金銭等の株式以外の資産が交付される場合には、その経済実態は通常の売買取引と異なるところがなく、移転資産の譲渡損益の計上を繰り延べることは適当でないと考えられる。」(「会社分割・合併等の企業組織再編成に係る税制の基本的考え方」第二、一(税制調査会 平成12年10月3日)) |
③ 未経過固定資産税相当額の金銭を受け払いする分割の適格判定における取扱い 上記①で述べたとおり、分割によって移転する固定資産の未経過固定資産税相当額の金銭の受払いに関しては、分割を全体として見た場合には対価の受払いとなるものではあるが、その固定資産そのものの対価の受払いとは言い難いこと、そして、未経過固定資産税相当額の金銭の受払いを行う実務が慣行的に行われてきたということ、この2つをその特殊性として挙げることができる。
また、上記②で述べたとおり、移転資産の対価として金銭等を交付する組織再編成を非適格とした趣旨は、そのような組織再編成はその経済実態が通常の売買取引と異ならないと考えられるということである。
このような点からすると、上記①で述べた特殊性のある未経過固定資産税相当額の金銭の受け払いをする分割が上記②で引用した「会社分割・合併等の企業組織再編成に係る税制の基本的考え方」で述べられている「通常の売買取引」と異ならないということになるのか否かということが問題となるわけであるが、これに関しては、固定資産そのものの対価として金銭等が交付されるのか否かによって「通常の売買取引」と異なるのか否かを判定するのが適切である、ということとなるものと考えられる。例えば、分割において移転する固定資産の未経過固定資産税相当額の金銭のみが交付されてその固定資産そのものの対価として交付される金銭がまったくないという場合には、その分割を「通常の売買取引」と異ならないと見ることはできない、と言わざるを得ない。このような点からすると、分割において、移転する固定資産の未経過固定資産税相当額の金銭のみが交付されてその固定資産そのものの対価として交付する分割承継法人の株式以外の資産がまったくないという場合には、その分割を非適格とするのは妥当でない、ということになろう。
仮に、移転する固定資産の未経過固定資産税相当額の金銭の交付があることをもって分割を非適格とするということになれば、移転する固定資産そのものの対価として交付する分割承継法人の株式以外の資産があるのか否かにかかわらず、慣行に従うのか否かによって適格か否かを決めるということになってしまうが、そのような取扱いは、個々の組織再編成ごとにその経済実態に即して適格判定を行おうとする法人税法2条12号の11の規定の趣旨に合わないものである。
記事に関連するお問い合わせ先 記事に関するお問い合わせは週刊「T&Amaster」編集部にお寄せください。執筆者に質問内容をお伝えいたします。
TEL:03-5281-0020 FAX:03-5281-0030 e-mail:ta@lotus21.co.jp
※なお、内容によっては回答いたしかねる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -

Copyright (C) 2019
SHINNIPPON-HOKI PUBLISHING CO.,LTD.





















