解説記事2011年06月20日 【法令解説】 資本市場および金融業の基盤強化のための金融商品取引法等の改正の要点(2011年6月20日号・№407)
法令解説
資本市場および金融業の基盤強化のための金融商品取引法等の改正の要点
金融庁総務企画局企画課調査室 課長補佐 澤飯 敦
金融庁総務企画局企画課金融トラブル解決制度推進室 課長補佐 出原正弘
Ⅰ.はじめに
わが国においては、少子高齢化が進展し、経済の低成長が続くなか、家計部門に適切な投資機会を提供し、企業等に多様な資金調達手段を確保することを通じて、金融がこれまで以上に実体経済をしっかりと支えることが求められている。
また、わが国は、1,400兆円を超える家計部門の金融資産、高度な人材・技術等を有し、成長著しいアジア経済圏に隣接しており、こうした好条件を活かし、わが国の金融業が成長産業として発展し、付加価値を高めることが求められている。
このような状況を踏まえ、資本市場および金融業の基盤強化を図るため、①多様で円滑な資金供給の実現、②国民資産を有効活用できる資産運用機会の提供、③市場の信頼性の確保に係る施策を盛り込んだ「資本市場及び金融業の基盤強化のための金融商品取引法等の一部を改正する法律案」が、平成23年3月11日に閣議決定され、4月1日に第177回国会(常会)に提出された。その後、国会における審議を経て、5月17日に成立、5月25日に公布された。
本稿においては、今般の改正の背景・経緯、改正の概要および施行に向けた今後のスケジュールについて解説を行うこととしたい。なお、文中意見にわたる部分については筆者の個人的見解であることを申し添える。
Ⅱ.改正の背景・経緯
平成22年6月18日に閣議決定された「新成長戦略~『元気な日本』復活のシナリオ~」においては、「金融戦略」を7つの戦略分野の1つとして位置付け、①金融が実体経済、企業のバックアップ役としてそのサポートを行うとともに、②金融自身が成長産業として経済をリードするため、様々な施策をできるだけ早期に実施していくこととされた。具体的には、「成長戦略実行計画(工程表)」において、外国企業等による英文開示の範囲拡大等について、23年度以降速やかに制度整備の実施を行うこととされた。
また、「成長戦略実行計画(工程表)」においては、22年度に実施すべき事項として、「金融資本市場及び金融産業の活性化等のためのアクションプラン(以下「アクションプラン」という)の策定」が掲げられ、12月24日、①企業等の規模・成長段階に応じた適切な資金供給、②アジアと日本をつなぐ金融、③国民が資産を安心して有効に活用できる環境整備の3つの柱からなるアクションプラン(最終版)を公表した。
アクションプラン(工程表)においては、「成長戦略実行計画(工程表)」に盛り込まれた施策に加え、開示制度・運用の見直し(発行登録における追補目論見書交付義務の免除)、ライツ・オファリングが円滑に行われるための開示制度等の整備等について、関連法案の早急な国会提出を図ることとされた。
このような取組み等を踏まえつつ、わが国資本市場および金融業の基盤強化を図るために必要な制度整備を包括的に盛り込んだ「資本市場及び金融業の基盤強化のための金融商品取引法等の一部を改正する法律案」が23年3月11日に閣議決定され、4月1日に第177回国会(常会)に提出された。
同法律案は、公認会計士試験の待機合格者問題等への対応についてはさらに検討すべきであるとの観点から、原案から公認会計士制度の見直しに関する規定をすべて削除する修正が行われ、5月17日に成立、5月25日に公布された(平成23年法律第49号。以下「改正法」という)。
なお、公認会計士制度の見直しについては、参議院財政金融委員会および衆議院財務金融委員会において、「公認会計士監査制度及び会計の専門家の活用に関しては、会計をめぐる国際的な動向や、公認会計士試験合格者数の適正な規模についての議論などを踏まえ、その在り方を引き続き検討すること。また、公認会計士による監査を充実・強化していくため、専門職業家団体による自主規律の重要性に配意して、その自主規制を活用した有効かつ効率的な監督を行うこと。」との附帯決議が全会一致で付された。
Ⅲ.改正の概要
1.改正の全体像 改正法は、金融が実体経済を支えるとともに、金融自身が成長産業として経済をリードする必要があるとの観点から、わが国資本市場および金融業の基盤強化を図るために不可欠な次の措置を講じるものである(図表1参照)。
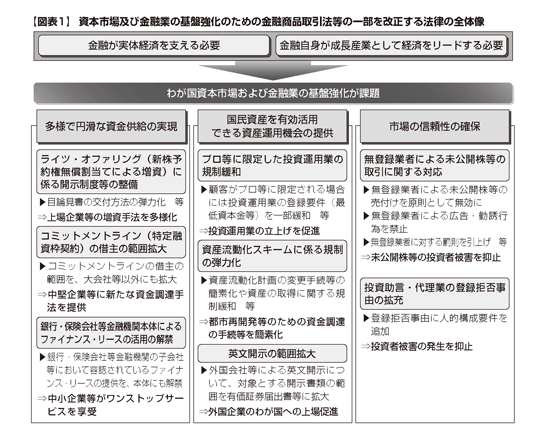
(1)多様で円滑な資金供給の実現 多様で円滑な資金供給の実現を図るため、①ライツ・オファリング(新株予約権無償割当てによる増資)に係る開示制度等の整備、②コミットメントライン(特定融資枠契約)の借主の範囲拡大、③銀行・保険会社等金融機関本体によるファイナンス・リースの活用の解禁などの措置を講じる。
(2)国民資産を有効活用できる資産運用機会の提供 国民資産を有効活用できる資産運用機会の提供を図るため、①プロ等に限定した投資運用業の規制緩和、②資産流動化スキームに係る規制の弾力化、③英文開示の範囲拡大の措置を講じる。
(3)市場の信頼性の確保 市場の信頼性の確保を図るため、①無登録業者による未公開株等の取引に関する対応、②投資助言・代理業の登録拒否事由の拡充などの措置を講じる。
2.多様で円滑な資金供給の実現
(1)ライツ・オファリング(新株予約権無償割当てによる増資)に係る開示制度等の整備 ライツ・オファリングは、欧州では大規模な増資を中心に一般的に利用されているが、公募増資や第三者割当増資と異なり、株式を取得する権利が既存株主にその持分割合に応じて与えられるため、既存株主の公平な取扱いに配慮した増資手法であるとの指摘がある。
また、既存株主の大幅な持分比率の低下を伴う第三者割当増資が、投資者保護の観点から問題となっているなか、投資者等からもライツ・オファリングの積極的活用を求める声がある。
このような背景を踏まえ、改正法では、①目論見書の交付方法の弾力化、②「有価証券の引受け」の範囲の見直し等を図ることとしている(図表2参照)。
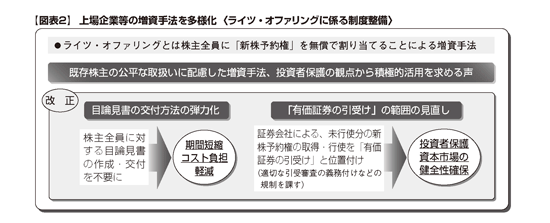
① 目論見書の交付方法の弾力化 現行法上、ライツ・オファリングを行う場合、形式的には有価証券の募集に該当するため、既存株主に新株予約権を割り当てることに伴い、株主全員に目論見書を交付することが義務付けられることとなる。このため、特に株主数が多い企業においては、ライツ・オファリングを行うことは事実上困難との指摘があったところである。
このような背景を踏まえ、投資者保護を図りつつも、ライツ・オファリングが企業の資金調達の現実的な選択肢となるよう、改正法では、①割り当てられる新株予約権が金融商品取引所に上場されている、または上場が予定されている場合であって、②当該新株予約権に係る有価証券届出書等の提出がなされた旨などが、その提出後遅滞なく日刊新聞紙に掲載される場合には、目論見書の作成・交付を不要とすることとしている(改正後の金融商品取引法(以下「法」という)13条1項、15条2項)。
② 「有価証券の引受け」の範囲の見直し ライツ・オファリングでは、①株主等が権利行使しなかった新株予約権を、発行者が取得したうえで証券会社に売却し、②当該証券会社が権利行使を行い、株式を取得するというコミットメント型のスキームの採用が想定される。
このコミットメント型ライツ・オファリングにおける証券会社の行為は、投資者が行使しない新株予約権について、その取得・行使を予め約束するものであり、行為態様やリスク負担の点で現行の「有価証券の引受け」と類似性があると考えられる。
このため、改正法では、証券会社に対し適切な引受審査の義務付けなどの規制を課し、投資者保護および資本市場の健全性確保が図られるよう、「引受人」等の定義に、有価証券の募集等に際し新株予約権の未行使分を取得して自己または第三者が当該新株予約権を行使することを内容とする契約をする者を追加することとしている(法2条6項、21条4項、28条7項)。
(2)コミットメントライン(特定融資枠契約)の借主の範囲拡大 コミットメントラインについては、平成11年の制度創設以来、契約額・利用額ともに拡大し、一定の定着がみられるとともに、リーマンショック後の社債・CP市場の低迷のなかで、改めて企業の資金調達手段としての有効性が確認されたところである。
このような背景を踏まえ、改正法では、借主保護に配慮しつつ、コミットメントラインを利用するニーズがあり、かつ、金融機関と十分な交渉力を有すると考えられる企業を借主に追加することとしている(図表3参照)。
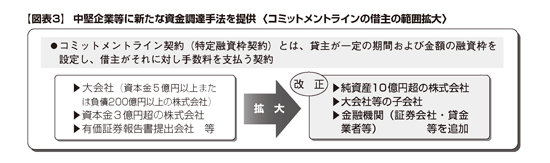
具体的には、①純資産の額が10億円を超える株式会社、②大会社等の子会社、③純資産の額が10億円を超える者等に相当する外国会社、④金融機関(証券会社、貸金業者等)、⑤資産流動化のための合同会社を追加することとしている(改正後の特定融資枠契約に関する法律2条)。
(3)銀行・保険会社等金融機関本体によるファイナンス・リースの活用の解禁 現在、ファイナンス・リース取引については、銀行・保険会社等の金融機関の子会社において行うことは認められているが、これらの金融機関本体が行うことは、他業禁止に該当するとの整理で認められていなかった。
しかしながら、ファイナンス・リース取引については、経済的な実質は設備投資資金の貸付けであると考えられることや、近年、銀行・保険会社等金融機関の取り巻く環境等において、これらが行う他の業務とのリスクの同質性が認められるようになってきている。
このような背景を踏まえ、改正法では、ファイナンス・リース取引および同取引の代理・媒介業務を銀行・保険会社等の金融機関本体の付随業務に追加することとしている(改正後の銀行法10条2項、保険業法98条1項等)。
3.国民資産を有効活用できる資産運用機会の提供
(1)プロ等に限定した投資運用業の規制緩和 現在、投資運用業を行う場合には、金融商品取引業の登録を受けなければならないが、その際、一般投資家を保護する観点から、取締役会の設置や最低資本金の額の充足等の厳格な登録拒否要件が課されている。また、投資信託の受益証券等のいわゆる第一項有価証券の募集または私募の取扱いを行う場合には、第一種金融商品取引業の登録が必要とされている。
これらの業規制が、たとえば、一定の投資判断能力を有するプロに顧客を限定して小規模なファンドの運用を行う場合の制約となっているとの指摘がある。
このような背景を踏まえ、改正法では、国民の様々な資産運用ニーズに応える投資運用ファンドの立上げを促進するため、①顧客がプロ等(適格投資家)に限定され、運用財産の総額が一定規模以下のファンドに係る投資運用業(適格投資家向け投資運用業)について、投資運用業の登録拒否要件を一部緩和する(株式会社要件を緩和し、監査役設置会社でも足りることとする)とともに、②有価証券の取得勧誘に係る業規制の緩和を行う(適格投資家を相手方として行う、自己が運用する投資信託の受益証券等の私募の取扱いを、第二種金融商品取引業とみなす)こととしている(法29条の5)。
(2)資産流動化スキームに係る規制の弾力化 現在、金融危機以降の不動産投資市場の低迷等を踏まえ、証券化の手法を活用して不動産開発の促進を図ることが求められているが、資産の流動化に関する法律(以下「資産流動化法」という)で定める資産流動化スキームについて、利用にあたっての手続が煩雑であるといった指摘がある。
このような背景を踏まえ、改正法では、資産流動化法を改正し、①資産流動化計画の変更届出義務の緩和(資産流動化計画の軽微な変更について、内閣総理大臣への届出義務を免除)、②資産の取得に係る規制の見直し(従たる特定資産の信託設定義務等の免除等)、③資産流動化の応用スキームの促進(特定目的信託における社債的受益権(予め定められた金額の分配を受ける種類の受益権)を発行する場合における、他の種類の受益権も併せて発行することの義務付けの撤廃)等を行うこととしている(改正後の資産流動化法9条1項、4条3項、230条1項等。図表4参照)。
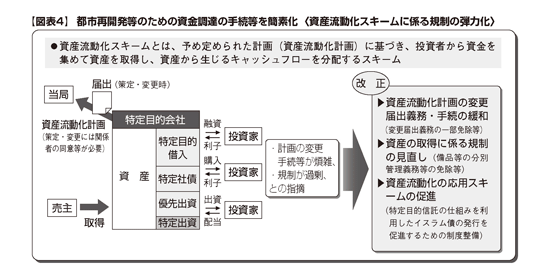
(3)英文開示の範囲拡大 現在、英文開示の対象範囲は、有価証券報告書等の継続開示書類に限られており、わが国において資金調達等を行う外国会社等は、有価証券の募集または売出しを行うために日本語による有価証券届出書を作成しなければならない。このため、日本語による有価証券届出書を提出した外国会社等は、この日本語による有価証券届出書をベースとすることにより、大きなコストを掛けることなく日本語による有価証券報告書等の作成が可能となり、あえて英文開示を行う必要性は低いことから、英文開示はほとんど利用されてないとの指摘がある。
このような背景を踏まえ、改正法では、英文開示の対象範囲を有価証券届出書等の発行開示書類および臨時報告書に拡大することとしている(図表5参照)。
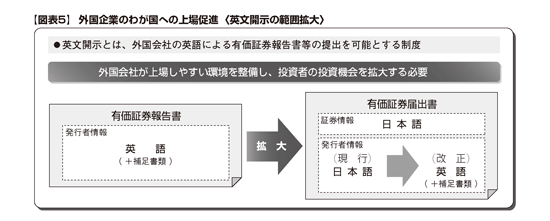
具体的には、有価証券届出書を提出しなければならない外国会社等は、当該外国会社等に関する情報が外国において適正に開示されている場合など、公益または投資者保護に欠けることがないと認められる場合には、日本語による有価証券届出書に代えて、①有価証券届出書に記載すべき証券情報(日本語)、②外国において開示が行われている有価証券報告書・有価証券届出書等に類する書類であって英語で記載されているもの、③補足書類(日本語による要約等)を提出することができることとしている(法5条6項~9項等)。
また、臨時報告書を提出しなければならない外国会社等は、当該臨時報告書の提出理由が日本語で記載されている場合など、公益または投資者保護に欠けることがないと認められる場合には、日本語による臨時報告書に代えて、臨時報告書に記載すべき内容が英語で記載されたものの提出が認められる(法24条の5)。
4.市場の信頼性の確保
(1)無登録業者による未公開株等の取引に関する対応 株式等を業として販売するためには、金融商品取引法(以下「金商法」という)による登録を受ける必要があり、これに違反する場合には罰則の適用などの措置は設けられているものの、金商法上、特段の民事ルールは規定されていなかった。
こうしたなか、近年、金商法上の登録を受けていない業者(以下「無登録業者」という)が、電話等により、未公開株等を「上場間近で必ず儲かる」などといった虚偽の勧誘を行うことによって、高齢者等に対し高額な価額で販売するといった被害が多発している状況にある。
金融庁においては、これまで未公開株等の問題に対する対応として、リーフレット等を通じた注意喚起や無登録業者に対する警告書の発出・公表等の取組みを実施してきたところである。
また、平成22年4月には、消費者委員会から、未公開株等の問題に関し、被害救済を迅速に進めるための民事ルールの整備および違法行為に対する抑止効果のある制裁措置の検討・導入について提言がなされた。
このような背景を踏まえ、改正法では、①取引の無効ルールの創設(無登録業者が非上場の株券等の売付け等を行った場合には、その売買契約を原則として無効とする。ただし、無登録業者側が、(i)契約の締結にあたって、顧客の知識、経験、財産の状況等に照らして投資者の保護に欠けるものではないこと、または(ⅱ)当該売付け等が不当な利得行為でないことを立証した場合に限り、契約が無効とならないこととする)、②無登録業者による広告・勧誘行為の禁止(無登録業者が、(i)金融商品取引業を行う旨の表示をすること、(ⅱ)金融商品取引業を行うことを目的として契約締結の勧誘を行うことを禁止)、③無登録業者に対する罰則の引上げ(罰則を5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金またはこれらの併科(法人重課5億円以下の罰金)に引上げ)を図ることとしている(法171条の2、31条の3の2、197条の2・207条。図表6参照)。
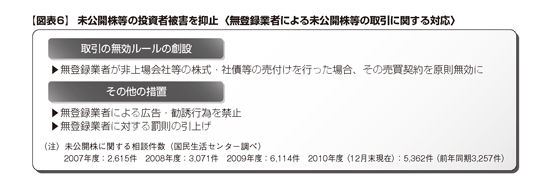
(2)投資助言・代理業の登録拒否事由の拡充 従来、投資助言・代理業者については、法令違反が認められた場合には行政処分を行うことによって、法令遵守態勢の是正を求め、さらに悪質な場合には登録取消しを行うこととしてきた。
しかしながら、近年、投資助言・代理業に関連する業務経験も保有資格もなく、法令遵守意識が著しく欠如しているなどの著しく不適切な者による参入が増加しており、こうした投資助言・代理業者によって投資者の利害が侵害される事例が増加している。また、政府全体の取組みとして許認可の付与にあたり、業の主体から暴力団等を排除する対策の充実が求められているところである。
このような背景を踏まえ、改正法では、投資助言・代理業の登録拒否事由に金融商品取引業を適確に遂行するに足りる人的構成を有しない者を追加することとしている(法29条の4第1項)。
Ⅳ.施行に向けたスケジュール
改正法の施行日については、関係者の準備期間等を踏まえ、原則、公布後1年以内の政令で定める日から施行することとしている。ただし、次の事項については、それぞれ記載する時期に施行することとしている(改正法附則1条)。
1.公布後20日施行 無登録業者による未公開株等の取引に関する対応のうち、無登録業者に対する罰則の引上げについては、投資者保護を図る観点から、すみやかに施行する必要がある一方で、一定の周知期間を設ける必要があることから、公布後20日(平成23年6月14日)から施行することとした。
2.公布後6月以内施行 無登録業者による未公開株等の取引に関する対応のうち、取引の無効ルールの創設および無登録業者による広告・勧誘行為の禁止ならびに資産流動化スキームに係る規制の弾力化については、早期に施行することが望まれるものの、関係政令・内閣府令の策定作業に要する期間等を踏まえ、公布後6月以内の政令で定める日から施行することとしている。
資本市場および金融業の基盤強化のための金融商品取引法等の改正の要点
金融庁総務企画局企画課調査室 課長補佐 澤飯 敦
金融庁総務企画局企画課金融トラブル解決制度推進室 課長補佐 出原正弘
Ⅰ.はじめに
わが国においては、少子高齢化が進展し、経済の低成長が続くなか、家計部門に適切な投資機会を提供し、企業等に多様な資金調達手段を確保することを通じて、金融がこれまで以上に実体経済をしっかりと支えることが求められている。
また、わが国は、1,400兆円を超える家計部門の金融資産、高度な人材・技術等を有し、成長著しいアジア経済圏に隣接しており、こうした好条件を活かし、わが国の金融業が成長産業として発展し、付加価値を高めることが求められている。
このような状況を踏まえ、資本市場および金融業の基盤強化を図るため、①多様で円滑な資金供給の実現、②国民資産を有効活用できる資産運用機会の提供、③市場の信頼性の確保に係る施策を盛り込んだ「資本市場及び金融業の基盤強化のための金融商品取引法等の一部を改正する法律案」が、平成23年3月11日に閣議決定され、4月1日に第177回国会(常会)に提出された。その後、国会における審議を経て、5月17日に成立、5月25日に公布された。
本稿においては、今般の改正の背景・経緯、改正の概要および施行に向けた今後のスケジュールについて解説を行うこととしたい。なお、文中意見にわたる部分については筆者の個人的見解であることを申し添える。
Ⅱ.改正の背景・経緯
平成22年6月18日に閣議決定された「新成長戦略~『元気な日本』復活のシナリオ~」においては、「金融戦略」を7つの戦略分野の1つとして位置付け、①金融が実体経済、企業のバックアップ役としてそのサポートを行うとともに、②金融自身が成長産業として経済をリードするため、様々な施策をできるだけ早期に実施していくこととされた。具体的には、「成長戦略実行計画(工程表)」において、外国企業等による英文開示の範囲拡大等について、23年度以降速やかに制度整備の実施を行うこととされた。
また、「成長戦略実行計画(工程表)」においては、22年度に実施すべき事項として、「金融資本市場及び金融産業の活性化等のためのアクションプラン(以下「アクションプラン」という)の策定」が掲げられ、12月24日、①企業等の規模・成長段階に応じた適切な資金供給、②アジアと日本をつなぐ金融、③国民が資産を安心して有効に活用できる環境整備の3つの柱からなるアクションプラン(最終版)を公表した。
アクションプラン(工程表)においては、「成長戦略実行計画(工程表)」に盛り込まれた施策に加え、開示制度・運用の見直し(発行登録における追補目論見書交付義務の免除)、ライツ・オファリングが円滑に行われるための開示制度等の整備等について、関連法案の早急な国会提出を図ることとされた。
このような取組み等を踏まえつつ、わが国資本市場および金融業の基盤強化を図るために必要な制度整備を包括的に盛り込んだ「資本市場及び金融業の基盤強化のための金融商品取引法等の一部を改正する法律案」が23年3月11日に閣議決定され、4月1日に第177回国会(常会)に提出された。
同法律案は、公認会計士試験の待機合格者問題等への対応についてはさらに検討すべきであるとの観点から、原案から公認会計士制度の見直しに関する規定をすべて削除する修正が行われ、5月17日に成立、5月25日に公布された(平成23年法律第49号。以下「改正法」という)。
なお、公認会計士制度の見直しについては、参議院財政金融委員会および衆議院財務金融委員会において、「公認会計士監査制度及び会計の専門家の活用に関しては、会計をめぐる国際的な動向や、公認会計士試験合格者数の適正な規模についての議論などを踏まえ、その在り方を引き続き検討すること。また、公認会計士による監査を充実・強化していくため、専門職業家団体による自主規律の重要性に配意して、その自主規制を活用した有効かつ効率的な監督を行うこと。」との附帯決議が全会一致で付された。
Ⅲ.改正の概要
1.改正の全体像 改正法は、金融が実体経済を支えるとともに、金融自身が成長産業として経済をリードする必要があるとの観点から、わが国資本市場および金融業の基盤強化を図るために不可欠な次の措置を講じるものである(図表1参照)。
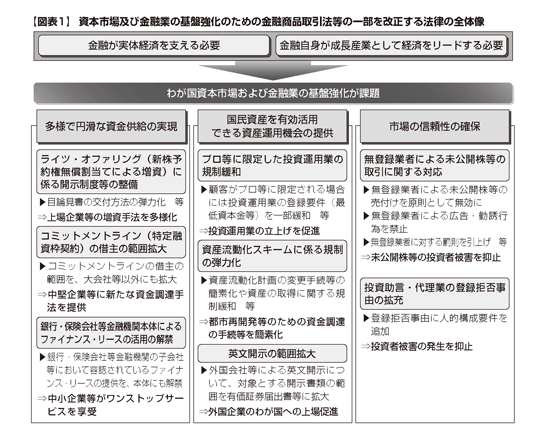
(1)多様で円滑な資金供給の実現 多様で円滑な資金供給の実現を図るため、①ライツ・オファリング(新株予約権無償割当てによる増資)に係る開示制度等の整備、②コミットメントライン(特定融資枠契約)の借主の範囲拡大、③銀行・保険会社等金融機関本体によるファイナンス・リースの活用の解禁などの措置を講じる。
(2)国民資産を有効活用できる資産運用機会の提供 国民資産を有効活用できる資産運用機会の提供を図るため、①プロ等に限定した投資運用業の規制緩和、②資産流動化スキームに係る規制の弾力化、③英文開示の範囲拡大の措置を講じる。
(3)市場の信頼性の確保 市場の信頼性の確保を図るため、①無登録業者による未公開株等の取引に関する対応、②投資助言・代理業の登録拒否事由の拡充などの措置を講じる。
2.多様で円滑な資金供給の実現
(1)ライツ・オファリング(新株予約権無償割当てによる増資)に係る開示制度等の整備 ライツ・オファリングは、欧州では大規模な増資を中心に一般的に利用されているが、公募増資や第三者割当増資と異なり、株式を取得する権利が既存株主にその持分割合に応じて与えられるため、既存株主の公平な取扱いに配慮した増資手法であるとの指摘がある。
また、既存株主の大幅な持分比率の低下を伴う第三者割当増資が、投資者保護の観点から問題となっているなか、投資者等からもライツ・オファリングの積極的活用を求める声がある。
このような背景を踏まえ、改正法では、①目論見書の交付方法の弾力化、②「有価証券の引受け」の範囲の見直し等を図ることとしている(図表2参照)。
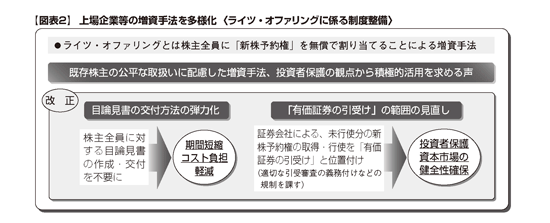
① 目論見書の交付方法の弾力化 現行法上、ライツ・オファリングを行う場合、形式的には有価証券の募集に該当するため、既存株主に新株予約権を割り当てることに伴い、株主全員に目論見書を交付することが義務付けられることとなる。このため、特に株主数が多い企業においては、ライツ・オファリングを行うことは事実上困難との指摘があったところである。
このような背景を踏まえ、投資者保護を図りつつも、ライツ・オファリングが企業の資金調達の現実的な選択肢となるよう、改正法では、①割り当てられる新株予約権が金融商品取引所に上場されている、または上場が予定されている場合であって、②当該新株予約権に係る有価証券届出書等の提出がなされた旨などが、その提出後遅滞なく日刊新聞紙に掲載される場合には、目論見書の作成・交付を不要とすることとしている(改正後の金融商品取引法(以下「法」という)13条1項、15条2項)。
② 「有価証券の引受け」の範囲の見直し ライツ・オファリングでは、①株主等が権利行使しなかった新株予約権を、発行者が取得したうえで証券会社に売却し、②当該証券会社が権利行使を行い、株式を取得するというコミットメント型のスキームの採用が想定される。
このコミットメント型ライツ・オファリングにおける証券会社の行為は、投資者が行使しない新株予約権について、その取得・行使を予め約束するものであり、行為態様やリスク負担の点で現行の「有価証券の引受け」と類似性があると考えられる。
このため、改正法では、証券会社に対し適切な引受審査の義務付けなどの規制を課し、投資者保護および資本市場の健全性確保が図られるよう、「引受人」等の定義に、有価証券の募集等に際し新株予約権の未行使分を取得して自己または第三者が当該新株予約権を行使することを内容とする契約をする者を追加することとしている(法2条6項、21条4項、28条7項)。
(2)コミットメントライン(特定融資枠契約)の借主の範囲拡大 コミットメントラインについては、平成11年の制度創設以来、契約額・利用額ともに拡大し、一定の定着がみられるとともに、リーマンショック後の社債・CP市場の低迷のなかで、改めて企業の資金調達手段としての有効性が確認されたところである。
このような背景を踏まえ、改正法では、借主保護に配慮しつつ、コミットメントラインを利用するニーズがあり、かつ、金融機関と十分な交渉力を有すると考えられる企業を借主に追加することとしている(図表3参照)。
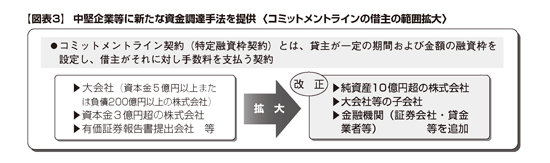
具体的には、①純資産の額が10億円を超える株式会社、②大会社等の子会社、③純資産の額が10億円を超える者等に相当する外国会社、④金融機関(証券会社、貸金業者等)、⑤資産流動化のための合同会社を追加することとしている(改正後の特定融資枠契約に関する法律2条)。
(3)銀行・保険会社等金融機関本体によるファイナンス・リースの活用の解禁 現在、ファイナンス・リース取引については、銀行・保険会社等の金融機関の子会社において行うことは認められているが、これらの金融機関本体が行うことは、他業禁止に該当するとの整理で認められていなかった。
しかしながら、ファイナンス・リース取引については、経済的な実質は設備投資資金の貸付けであると考えられることや、近年、銀行・保険会社等金融機関の取り巻く環境等において、これらが行う他の業務とのリスクの同質性が認められるようになってきている。
このような背景を踏まえ、改正法では、ファイナンス・リース取引および同取引の代理・媒介業務を銀行・保険会社等の金融機関本体の付随業務に追加することとしている(改正後の銀行法10条2項、保険業法98条1項等)。
3.国民資産を有効活用できる資産運用機会の提供
(1)プロ等に限定した投資運用業の規制緩和 現在、投資運用業を行う場合には、金融商品取引業の登録を受けなければならないが、その際、一般投資家を保護する観点から、取締役会の設置や最低資本金の額の充足等の厳格な登録拒否要件が課されている。また、投資信託の受益証券等のいわゆる第一項有価証券の募集または私募の取扱いを行う場合には、第一種金融商品取引業の登録が必要とされている。
これらの業規制が、たとえば、一定の投資判断能力を有するプロに顧客を限定して小規模なファンドの運用を行う場合の制約となっているとの指摘がある。
このような背景を踏まえ、改正法では、国民の様々な資産運用ニーズに応える投資運用ファンドの立上げを促進するため、①顧客がプロ等(適格投資家)に限定され、運用財産の総額が一定規模以下のファンドに係る投資運用業(適格投資家向け投資運用業)について、投資運用業の登録拒否要件を一部緩和する(株式会社要件を緩和し、監査役設置会社でも足りることとする)とともに、②有価証券の取得勧誘に係る業規制の緩和を行う(適格投資家を相手方として行う、自己が運用する投資信託の受益証券等の私募の取扱いを、第二種金融商品取引業とみなす)こととしている(法29条の5)。
(2)資産流動化スキームに係る規制の弾力化 現在、金融危機以降の不動産投資市場の低迷等を踏まえ、証券化の手法を活用して不動産開発の促進を図ることが求められているが、資産の流動化に関する法律(以下「資産流動化法」という)で定める資産流動化スキームについて、利用にあたっての手続が煩雑であるといった指摘がある。
このような背景を踏まえ、改正法では、資産流動化法を改正し、①資産流動化計画の変更届出義務の緩和(資産流動化計画の軽微な変更について、内閣総理大臣への届出義務を免除)、②資産の取得に係る規制の見直し(従たる特定資産の信託設定義務等の免除等)、③資産流動化の応用スキームの促進(特定目的信託における社債的受益権(予め定められた金額の分配を受ける種類の受益権)を発行する場合における、他の種類の受益権も併せて発行することの義務付けの撤廃)等を行うこととしている(改正後の資産流動化法9条1項、4条3項、230条1項等。図表4参照)。
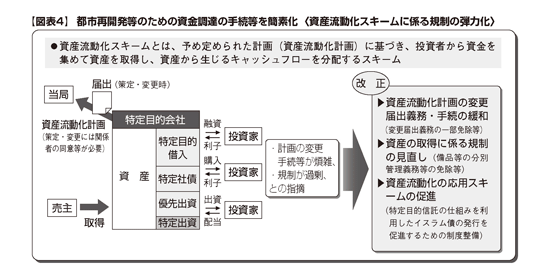
(3)英文開示の範囲拡大 現在、英文開示の対象範囲は、有価証券報告書等の継続開示書類に限られており、わが国において資金調達等を行う外国会社等は、有価証券の募集または売出しを行うために日本語による有価証券届出書を作成しなければならない。このため、日本語による有価証券届出書を提出した外国会社等は、この日本語による有価証券届出書をベースとすることにより、大きなコストを掛けることなく日本語による有価証券報告書等の作成が可能となり、あえて英文開示を行う必要性は低いことから、英文開示はほとんど利用されてないとの指摘がある。
このような背景を踏まえ、改正法では、英文開示の対象範囲を有価証券届出書等の発行開示書類および臨時報告書に拡大することとしている(図表5参照)。
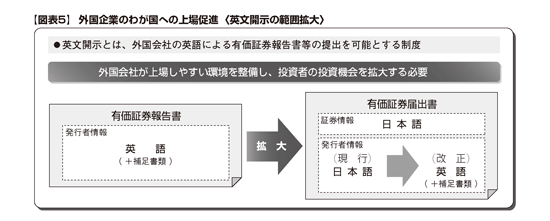
具体的には、有価証券届出書を提出しなければならない外国会社等は、当該外国会社等に関する情報が外国において適正に開示されている場合など、公益または投資者保護に欠けることがないと認められる場合には、日本語による有価証券届出書に代えて、①有価証券届出書に記載すべき証券情報(日本語)、②外国において開示が行われている有価証券報告書・有価証券届出書等に類する書類であって英語で記載されているもの、③補足書類(日本語による要約等)を提出することができることとしている(法5条6項~9項等)。
また、臨時報告書を提出しなければならない外国会社等は、当該臨時報告書の提出理由が日本語で記載されている場合など、公益または投資者保護に欠けることがないと認められる場合には、日本語による臨時報告書に代えて、臨時報告書に記載すべき内容が英語で記載されたものの提出が認められる(法24条の5)。
4.市場の信頼性の確保
(1)無登録業者による未公開株等の取引に関する対応 株式等を業として販売するためには、金融商品取引法(以下「金商法」という)による登録を受ける必要があり、これに違反する場合には罰則の適用などの措置は設けられているものの、金商法上、特段の民事ルールは規定されていなかった。
こうしたなか、近年、金商法上の登録を受けていない業者(以下「無登録業者」という)が、電話等により、未公開株等を「上場間近で必ず儲かる」などといった虚偽の勧誘を行うことによって、高齢者等に対し高額な価額で販売するといった被害が多発している状況にある。
金融庁においては、これまで未公開株等の問題に対する対応として、リーフレット等を通じた注意喚起や無登録業者に対する警告書の発出・公表等の取組みを実施してきたところである。
また、平成22年4月には、消費者委員会から、未公開株等の問題に関し、被害救済を迅速に進めるための民事ルールの整備および違法行為に対する抑止効果のある制裁措置の検討・導入について提言がなされた。
このような背景を踏まえ、改正法では、①取引の無効ルールの創設(無登録業者が非上場の株券等の売付け等を行った場合には、その売買契約を原則として無効とする。ただし、無登録業者側が、(i)契約の締結にあたって、顧客の知識、経験、財産の状況等に照らして投資者の保護に欠けるものではないこと、または(ⅱ)当該売付け等が不当な利得行為でないことを立証した場合に限り、契約が無効とならないこととする)、②無登録業者による広告・勧誘行為の禁止(無登録業者が、(i)金融商品取引業を行う旨の表示をすること、(ⅱ)金融商品取引業を行うことを目的として契約締結の勧誘を行うことを禁止)、③無登録業者に対する罰則の引上げ(罰則を5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金またはこれらの併科(法人重課5億円以下の罰金)に引上げ)を図ることとしている(法171条の2、31条の3の2、197条の2・207条。図表6参照)。
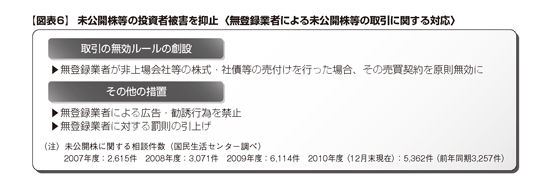
(2)投資助言・代理業の登録拒否事由の拡充 従来、投資助言・代理業者については、法令違反が認められた場合には行政処分を行うことによって、法令遵守態勢の是正を求め、さらに悪質な場合には登録取消しを行うこととしてきた。
しかしながら、近年、投資助言・代理業に関連する業務経験も保有資格もなく、法令遵守意識が著しく欠如しているなどの著しく不適切な者による参入が増加しており、こうした投資助言・代理業者によって投資者の利害が侵害される事例が増加している。また、政府全体の取組みとして許認可の付与にあたり、業の主体から暴力団等を排除する対策の充実が求められているところである。
このような背景を踏まえ、改正法では、投資助言・代理業の登録拒否事由に金融商品取引業を適確に遂行するに足りる人的構成を有しない者を追加することとしている(法29条の4第1項)。
Ⅳ.施行に向けたスケジュール
改正法の施行日については、関係者の準備期間等を踏まえ、原則、公布後1年以内の政令で定める日から施行することとしている。ただし、次の事項については、それぞれ記載する時期に施行することとしている(改正法附則1条)。
1.公布後20日施行 無登録業者による未公開株等の取引に関する対応のうち、無登録業者に対する罰則の引上げについては、投資者保護を図る観点から、すみやかに施行する必要がある一方で、一定の周知期間を設ける必要があることから、公布後20日(平成23年6月14日)から施行することとした。
2.公布後6月以内施行 無登録業者による未公開株等の取引に関する対応のうち、取引の無効ルールの創設および無登録業者による広告・勧誘行為の禁止ならびに資産流動化スキームに係る規制の弾力化については、早期に施行することが望まれるものの、関係政令・内閣府令の策定作業に要する期間等を踏まえ、公布後6月以内の政令で定める日から施行することとしている。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -























