解説記事2011年08月01日 【法令解説】 産活法の平成23年改正に係る要点(2011年8月1日号・№413)
法令解説
産活法の平成23年改正に係る要点
経済産業省経済産業政策局産業再生課 増田 悟
経済産業省経済産業政策局産業組織課 持田恵梨
経済産業省経済産業政策局競争環境整備室 石橋弘嗣
前経済産業省経済産業政策局産業資金課 森本 要
経済産業省中小企業庁事業環境部企画課 佐藤亮洋
はじめに
1.改正に至る経緯 バブル崩壊後、わが国経済は約20年間にわたり低迷を続けており、グローバル化の急速な進展や新興国市場の急速な台頭のなかで、世界における日本経済の地位が急速に転落するなど、日本経済および経済を支える産業の行き詰まりは深刻である。
このような状況を踏まえ、平成22年2月から、経済産業省では産業構造審議会産業競争力部会を開催し、日本経済・産業が直面する構造的な問題を克服するための戦略について検討を重ね、平成22年6月に「産業構造ビジョン2010」を策定した。
「産業構造ビジョン2010」で提言した施策は、政府全体の「新成長戦略」にも掲げ、法律、予算などさまざまな形で実現してきている。このたびの法改正も、産業構造ビジョンや新成長戦略で示された政策課題の一部を具現化していくためのものである。
2.改正法の制定・公布 「産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法(以下「産活法」という)の一部を改正する法律」は、産業構造ビジョンと新成長戦略の提言を踏まえ、わが国経済が最近の国際経済の構造的変化に対応できるよう、国際競争力の強化を目指した事業者の迅速かつ機動的な組織再編を促し、併せて、ベンチャー等の成長企業による新事業の展開等への支援、地域中小企業の体質改善・強化等への支援を実施することを趣旨としたものである(図表1参照)。
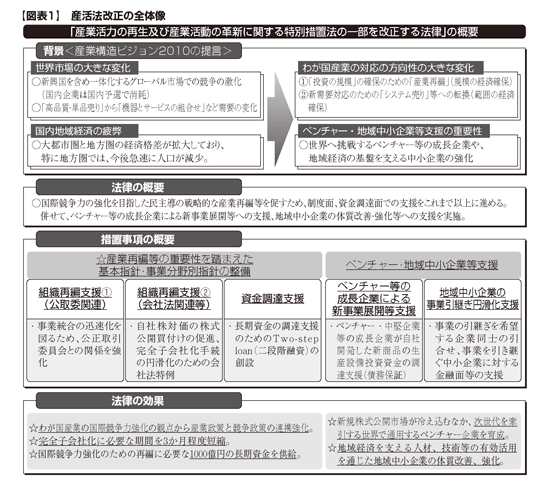
本法律は、衆議院・参議院における審議を経て、平成23年5月18日に参議院本会議で可決・成立し、5月25日に公布された(平成23年法律第48号)。
改正産活法に盛り込んだ産業再編に係る支援措置と中小企業の事業引継支援に関する措置を早期に施行することがきわめて重要であることから、公布後、施行の準備を早急に進め、法律は7月1日に施行された。
本稿では、改正法の趣旨および概要を説明したうえで、産活法に基づく認定計画の利用手続を解説する。
Ⅰ.公正取引委員会との協議制度の創設
1.措置の背景と制度の骨格 熾烈な国際競争のなかで、わが国産業が勝ち残るためには、投資の規模を確保することがカギとなる。わが国企業が世界の企業に遅れを取らないよう、組織再編を迅速かつ確実に実行していくことがきわめて重要である。
また、実際に、産業界において再編の機運が高まっている。このような状況のなか、政府としても、わが国企業の積極的な組織再編を促進するために、産活法の迅速な運用や事業者への強力なバックアップ体制を整備していくことが不可欠である。
旧法においては、主務大臣は事業者が申請を行う事業再構築等の計画を認定しようとする場合において、必要があると認められるときは、公正取引委員会に対し、競争に及ぼす影響に関する事項等について意見を述べることとし、当該意見に対し、公正取引委員会も、必要があると認められるときは、主務大臣に対し意見を述べることとされていた。
しかし、旧法の制度においては、これら意見の陳述を行うかどうかの判断については、主務大臣および公正取引委員会の裁量の余地が広く、事業者にとっては、どのような場合に意見の陳述がなされるのかが不透明であったこと、主務大臣と公正取引委員会の意見が異なる場合に、政府見解の統一に向けたプロセスとして不十分であったことといった問題点があった。
このような問題点を解消するために、改正法では、主務大臣に対し、事業再構築計画等の認定にあたり、適正な競争が確保されないおそれがある場合(脚注1)には、協議を義務付けることとした(産活法13条)。
また、協議の過程においては、公正取引委員会からの求めに応じ、所管業界の事情に知見のある主務大臣から、海外事業者の投資動向、異業種からの参入状況や可能性などに関する情報を積極的に提供することを想定している。
2.協議制度のメリット 大規模な再編であればあるほど、公正取引委員会が公正かつ自由な市場競争を確保するために行う企業結合審査の内容が高度になり、審査期間も長期化する可能性がある。再編の実行までの期間が長期化すれば、日々変化する世界経済の流れに乗り遅れることになりかねない。
この点、今回の協議制度の導入により、主務大臣と公正取引委員会との連携が強化され、わが国産業の国際競争力強化のための再編の迅速化、円滑化に資することとなる。
なお、産活法の改正と同時にして、公正取引委員会は企業結合規制の見直しを行っており、平成23年6月14日に成案を公表している。
同見直しは、今回の産活法の改正と同様、「新成長戦略」に基づき行われたもので、事前相談制度の廃止等の審査手続の改善や、国境を越えた市場画定の明確化等の審査基準の改善等を通じて、企業結合審査の迅速性および透明性を高めるとともに、国際整合性を一層強化することにより、グローバル市場にも配慮した審査を可能とするものとなっている(詳細については、公正取引委員会のウェブサイト等を参照されたい)。
Ⅱ.組織再編手続の簡素化・多様化(会社法特例)
1.自社株対価TOBの利用促進 近年、大型の買収に対するニーズが高まっており、多額の現金を用いずに買収が可能な自社株式を対価とする公開買付け(以下「自社株対価TOB」という)は、事業再構築等を進めていくうえで有効なツールとなり得る。
しかし、現行制度において、自社株対価TOBは、対象会社株式を現物出資財産として、買付会社株式を発行するという整理となることから、①プレミアムを付した自社株対価TOBを行う場合、買付会社において有利発行の株主総会決議が必要となる可能性があり、また、②検査役の調査が原則必要となる。
さらに、③株式発行時の対象会社株式の価額が、募集事項に定めた価額を著しく下回ることとなった場合には、応募株主および買付会社の取締役が填補責任を負う。このような懸念があることから、自社株対価TOBは、ほとんど利用されていないのが実情である。
そこで、買付会社株式の払込金額および対象会社株式の価額の代わりに、買付会社株式と対象会社株式の交換比率を募集事項とすることを認める特例措置を設け(産活法21条の2)、これにより、上記の①有利発行規制、②検査役調査、③価額不足填補責任の規定を適用しないこととした(図表2-1参照)。
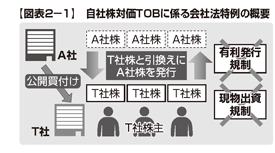
なお、買付会社の既存株主保護の観点から、株式買取請求権を付与する、原則として株主総会の特別決議を要する(ただし、発行する買付会社株式数に買付会社の1株当たり純資産額を乗じて得た額が、買付会社の純資産額の5分の1以下の場合は不要)等の株主保護手続を設けている。
2.完全子会社化手続の簡素化 事業再構築等を進めていくうえで、経営の機動性やグループ内資金の流動性を増大させ、効率的なグループ経営を可能とする完全子会社化が重要な選択肢である。
現在、キャッシュアウトによる完全子会社化は、公開買付けの後、対象会社において全部取得条項付種類株式を利用した手続を経る方法が一般的だが、この方法では、公開買付け終了後、株主総会の開催や端数の売却に係る裁判所の許可手続に約4~6か月の期間を要する。
しかし、公開買付けにより、買付会社が対象会社の大多数の株式を取得した場合、完全子会社化に関する株主総会の特別決議は可決されることが明らかであり、また、端数の売却に係る裁判所の許可手続も、特段の事情がない限り、公開買付価格を尊重する運用がなされている。
そこで、認定事業者が対象会社の完全子会社化を目的として公開買付けを行い、対象会社の10分の9以上の割合の議決権を取得した場合、法令または定款違反がないこと、公開買付価格に相当する対価が対象会社の株主に割り当てられること等を要件とする本特例利用の認定を受けることにより、全部取得条項付種類株式を利用した手続において、株主総会の特別決議による承認および端数の売却に係る裁判所の許可手続を省略できることとした(産活法21条の3。図表2-2参照)。
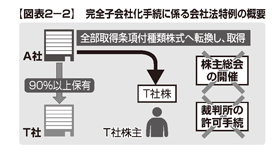
3.会社法特例のメリット これらの会社法特例を設けたことによるメリットとしては、次の点が挙げられる。
① 自社株対価TOBの特例により、有利発行規制、検査役調査および価額不足填補責任の規定の適用がなくなり、自社株対価TOBを利用した組織再編を実施しやすくなる。
② 完全子会社化手続の特例により、完全子会社化手続に要する期間を3か月ほど短縮できる。
Ⅲ.二段階融資制度の創設
1.措置の背景と制度の骨格 国際競争力の強化を念頭に置いた事業再編においては、研究開発・設備投資の資金、合併・買収に係る資金、設備を廃棄する場合の整地費用等の償還期間の長い資金が必要となることが多い。
また、このような再編後は、技術の擦り合わせや生産工程・物流および人員の最適配置の実現など、その効果が発揮されるまでに期間を要し、資金の回収が長期化することが想定されるが、民間金融機関による融資は5年未満等比較的短期のものが多く、十分な資金供給がされていない状況にある。
このため、民間金融を補完する支援措置として、株式会社日本政策金融公庫が、国際競争力の強化を念頭に置いた複数事業者が行う産業再編の取組みについて融資を行う指定金融機関に対し、財政投融資資金を原資とする長期・低利の貸付を行う二段階融資制度を創設した(産活法24条の3等)。
2.二段階融資制度のメリット この制度の創設により、事業者が、民間金融機関では供給されにくい5年以上の長期資金を、財政投融資資金を原資として借り入れられるだけでなく、呼び水効果的に、民間金融機関からの融資資金が入りやすくなる。
これにより、組織再編を円滑に進められることとなる。
Ⅳ.ベンチャー等の成長企業に対する資金調達支援
1.措置の背景と制度の骨格 近年、クリーンテックやライフサイエンス分野等におけるベンチャー等の成長企業は、急速に立ち上がるグローバル市場に対応し、自社の研究開発成果を利用した新商品を大規模に生産し、成長を図っていくことが必要になっている。
このような動きは、わが国経済の持続的な成長にきわめて重要であるが、新商品の量産化に際しては、大規模な設備投資と、それに伴い多額の設備投資資金を必要とする。また、これらの成長企業は、新規株式公開までの期間の長期化・困難化により、必要な資金が得られず、加えて、安定した売上実績がないこと等の理由により、民間金融機関からの資金調達も困難な状況にある。
このような状況を打開し、成長企業の大規模な新事業展開を促進するため、成長企業に民間金融機関が行う融資に対し、独立行政法人中小企業基盤整備機構が債務保証を実施する制度を創設した(産活法24条)。
2.中小機構による債務保証制度のメリット 制度創設により、資金調達難にあるベンチャー等の成長企業への民間金融機関の融資に対して債務保証を措置することにより、民間金融機関から、成長企業に対する資金供給が円滑化することとなる(図表3参照)。
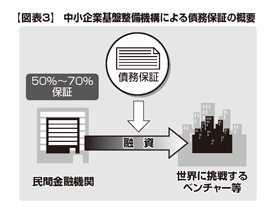
Ⅴ.地域中小企業の事業引継ぎ円滑化支援
1.措置の背景と制度の骨格 多くの地域中小企業の経営が既存の体制のままでは立ち行かなくなってきている。廃業・倒産が拡大し、雇用や技術など地域の財産を喪失しかねない。他方、事業の新たな展開を指向する中小企業もあるが、ヒト・モノ・カネ・技術が十分でないことから、単独での対応は容易ではない。
このような場合、他の事業者の経営資源を譲り受けることで迅速な事業の展開を行うことは有効な方策であるが、事業の引継ぎを希望する企業の仲介を支援する仕組みができていないことから、売手と買手のマッチングが困難である。
このため、産活法の規定に基づき、47都道府県に設置されている認定支援機関の業務に事業引継ぎ支援業務を追加し(産活法41条)、事業引継ぎに関する相談窓口を設けることにした。また、準備の整った認定支援機関から順次、事業引継ぎ支援センターを設置し、守秘義務を課した事業の譲渡、譲受けに関する専門家(経験のある税理士、公認会計士等)を配置し、事業引継ぎを希望する企業間の仲介および事業引継ぎ契約の成立に向けた支援を行う。
さらに、事業引継ぎの支援措置として、事業を譲り受ける側に対し、信用保険の別枠化、中小企業投資育成株式会社法の特例等の金融支援の措置を設けた(産活法25条)。また、事業引継ぎに伴う許認可承継の円滑化を図るための措置も設けることとした(同法32条の2)。
2.地域中小企業の事業引継ぎ支援措置のメリット 事業引継ぎを支援する公的支援機関を設け、かつ、専門家を配置することで、事業引継ぎの相談を安心して行えるとともに、低コストで専門家の支援を受けられるようになり、もって地域中小企業の経営基盤が強化され、事業の生産性の向上や新規分野の開拓に寄与すると考えている。
また、東日本大震災により直接・間接に大きな影響を受け、やむを得ず廃業を選択する中小企業が増えかねないことから、本措置の活用により、地域における雇用や技術を守るため、法律を早期に施行できるよう準備を進めてきた。
Ⅵ.その他の改正事項
1.事業再構築の定義の変更(産活法2条)
(1)事業構造の変更の要件の削除・追加 旧法において「資本の相当程度の増加」を事業再構築計画の対象としている。これは、わが国企業の自己資本の充実を図るため、財務体質強化の取組みを後押しするように措置したものである。しかし、わが国企業の自己資本比率は、平成11年度の産活法制定以降、順調に増加しており、おおむね当初の目的は達成された。
このため、今般の改正法においては、合併や分割等、企業の組織再編を伴う計画に支援対象を限定し、「資本の相当程度の増加」を事業構造の変更の要件から削除した。しかし、合併や分割等の組織再編を伴う「資本の相当程度の増加」は引き続き支援対象となる。
また、近年、事業再編の形態として、有限責任事業組合(以下「LLP」という)の利用が増えている。LLPは有限責任制、内部自治の原則、構成員課税等の組織運営上のメリットを持っている。
たとえば、大規模な生産設備を有する石油精製や化学などの製造事業者では、LLPを活用し複数事業者の設備間の生産効率等考慮したうえで生産最適化を図ることで、適切な設備稼働率を維持することが可能となるなど、当該事業者の中核的事業の強化を目指すことが有効であると考えられている。
したがって、LLPを活用した事業再編を一層促進するため、産活法の事業再構築計画に「LLPに対する出資」を規定し、それを活用した事業者の取組みを支援することとする。
(2)事業革新の要件の追加 改正法では、事業革新の対象として、「商品及び役務を一体的に組み合わせて行う」を規定として追加した。
これは、世界市場では、「高品質・単品モノ売り」から「機器とサービスの組合せ」への需要の変化など、大きな変化が生じており、このような変化に対応した取組みを後押しするために行ったものである。
具体的には、インフラ分野等の新たな需要に対応した「システム売り」への転換、たとえば、プラント製造事業者が、顧客の需要に応じて、プラントの販売のみならず、その後のメンテナンスサービス等を一体的に組み合わせて提供することなどを想定している。
2.事業分野別指針の追加 わが国産業の国際競争力強化のため、①投資の規模等の確保を意図した再編と、②新たな需要に対応したシステム売りを支援することがきわめて重要である。
このため、既存の過剰供給構造にある事業分野および生産性の向上が特に必要である事業分野に加え、新たに「事業分野別指針」として、
・わが国事業者が行う事業の規模が国際的な水準に比較して著しく小さい事業分野
・商品やサービスを一体的に組み合わせて行う販売等により、新たな需要を開拓することが特に必要な事業分野
について、それぞれ指針を定めることができることとしており、今後、これらに該当する事業分野について指針の策定が検討されることになる。
Ⅶ.認定計画の利用手続
1.申請のスケジュール 実際に申請を検討される場合は、まずは経済産業省産業再生課(電話:03-3501-1560)までご連絡をいただきたい。
申請スケジュールは、事前相談の開始から認定まで2か月ほどが見込まれる(図表4参照)。正式申請前の事前相談の段階では、おおまかな概要が分かる資料を基に、産活法の目的や要件に合致しているかを検討し、その後、正式な申請書の作成や数値要件の根拠等を精査することになる。
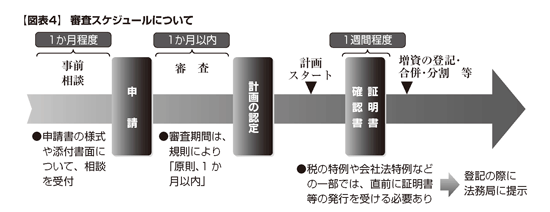
また、出資の円滑化措置、中小機構の債務保証を含む計画、二段階融資については、金融機関との事前相談が必要となっている。
2.申請窓口 各事業を所管する省庁にて申請を受け付けている(脚注2)。複数の官庁にまたがった事業を行っている場合は、まずは計画している主な事業を所管している官庁にご相談いただきたい。複数省庁による共同認定となるケースもある。経済産業省では、企業規模に応じて全国9か所の各地方経済産業局でも手続が可能である。
また、中小企業者の有する経営資源を承継して再生を図る「中小企業承継事業再生計画」の認定については、すべて各地方経済産業局での受付となっており、最寄りの地方経済産業局または中小企業再生支援協議会までご相談いただきたい。
おわりに
現在、新興国市場の急速な拡大により、市場競争の舞台は先進国から新興国を含めた世界市場に移行している。これに伴い、競争条件や需要構造が世界的に変化し、企業が様々な形での事業の統合、選択と集中、連携、事業転換を模索し、これに対応しようとしている。
しかし、このような激動な世界経済を勝ち抜くには、個別企業だけでは対応仕切れない部分も多く存在する。
今回の産活法改正は、国際競争力の強化を念頭に置いた産業再編の推進、システム売りへの転換、地域・ベンチャー企業の基盤強化が柱となっている。その支援策として、制度の創設や支援体制の整備を行った。また、厳しい国家財政のなか、限られた財源を最大限に有効活用した資金面の支援策も盛り込んでいる。
今後は、法律を適切に運用し、事業者の積極的な取組みを後押しし、わが国経済・産業の持続的な発展に寄与できるよう尽力していきたい。
脚注
1 「適正な競争が確保されないおそれ」は、政令において、①独占禁止法上の株式取得や合併等の届出を要する場合、あるいは②共同して措置を行う事業者のうち、一の事業者の国内売上高合計額が200億円超かつ他の一の事業者の国内売上高合計額が50億円超の場合としている。
2 申請資料の様式や記載例(テンプレート)については、次のウェブサイトを参照されたい。http://www.meti.go.jp/sankatsuhou/
産活法の平成23年改正に係る要点
経済産業省経済産業政策局産業再生課 増田 悟
経済産業省経済産業政策局産業組織課 持田恵梨
経済産業省経済産業政策局競争環境整備室 石橋弘嗣
前経済産業省経済産業政策局産業資金課 森本 要
経済産業省中小企業庁事業環境部企画課 佐藤亮洋
はじめに
1.改正に至る経緯 バブル崩壊後、わが国経済は約20年間にわたり低迷を続けており、グローバル化の急速な進展や新興国市場の急速な台頭のなかで、世界における日本経済の地位が急速に転落するなど、日本経済および経済を支える産業の行き詰まりは深刻である。
このような状況を踏まえ、平成22年2月から、経済産業省では産業構造審議会産業競争力部会を開催し、日本経済・産業が直面する構造的な問題を克服するための戦略について検討を重ね、平成22年6月に「産業構造ビジョン2010」を策定した。
「産業構造ビジョン2010」で提言した施策は、政府全体の「新成長戦略」にも掲げ、法律、予算などさまざまな形で実現してきている。このたびの法改正も、産業構造ビジョンや新成長戦略で示された政策課題の一部を具現化していくためのものである。
2.改正法の制定・公布 「産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法(以下「産活法」という)の一部を改正する法律」は、産業構造ビジョンと新成長戦略の提言を踏まえ、わが国経済が最近の国際経済の構造的変化に対応できるよう、国際競争力の強化を目指した事業者の迅速かつ機動的な組織再編を促し、併せて、ベンチャー等の成長企業による新事業の展開等への支援、地域中小企業の体質改善・強化等への支援を実施することを趣旨としたものである(図表1参照)。
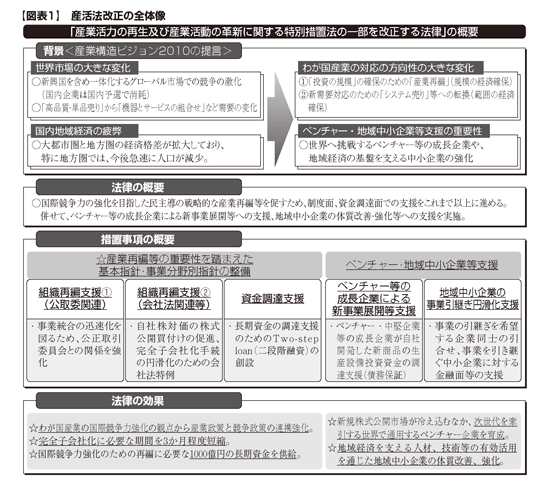
本法律は、衆議院・参議院における審議を経て、平成23年5月18日に参議院本会議で可決・成立し、5月25日に公布された(平成23年法律第48号)。
改正産活法に盛り込んだ産業再編に係る支援措置と中小企業の事業引継支援に関する措置を早期に施行することがきわめて重要であることから、公布後、施行の準備を早急に進め、法律は7月1日に施行された。
本稿では、改正法の趣旨および概要を説明したうえで、産活法に基づく認定計画の利用手続を解説する。
Ⅰ.公正取引委員会との協議制度の創設
1.措置の背景と制度の骨格 熾烈な国際競争のなかで、わが国産業が勝ち残るためには、投資の規模を確保することがカギとなる。わが国企業が世界の企業に遅れを取らないよう、組織再編を迅速かつ確実に実行していくことがきわめて重要である。
また、実際に、産業界において再編の機運が高まっている。このような状況のなか、政府としても、わが国企業の積極的な組織再編を促進するために、産活法の迅速な運用や事業者への強力なバックアップ体制を整備していくことが不可欠である。
旧法においては、主務大臣は事業者が申請を行う事業再構築等の計画を認定しようとする場合において、必要があると認められるときは、公正取引委員会に対し、競争に及ぼす影響に関する事項等について意見を述べることとし、当該意見に対し、公正取引委員会も、必要があると認められるときは、主務大臣に対し意見を述べることとされていた。
しかし、旧法の制度においては、これら意見の陳述を行うかどうかの判断については、主務大臣および公正取引委員会の裁量の余地が広く、事業者にとっては、どのような場合に意見の陳述がなされるのかが不透明であったこと、主務大臣と公正取引委員会の意見が異なる場合に、政府見解の統一に向けたプロセスとして不十分であったことといった問題点があった。
このような問題点を解消するために、改正法では、主務大臣に対し、事業再構築計画等の認定にあたり、適正な競争が確保されないおそれがある場合(脚注1)には、協議を義務付けることとした(産活法13条)。
また、協議の過程においては、公正取引委員会からの求めに応じ、所管業界の事情に知見のある主務大臣から、海外事業者の投資動向、異業種からの参入状況や可能性などに関する情報を積極的に提供することを想定している。
2.協議制度のメリット 大規模な再編であればあるほど、公正取引委員会が公正かつ自由な市場競争を確保するために行う企業結合審査の内容が高度になり、審査期間も長期化する可能性がある。再編の実行までの期間が長期化すれば、日々変化する世界経済の流れに乗り遅れることになりかねない。
この点、今回の協議制度の導入により、主務大臣と公正取引委員会との連携が強化され、わが国産業の国際競争力強化のための再編の迅速化、円滑化に資することとなる。
なお、産活法の改正と同時にして、公正取引委員会は企業結合規制の見直しを行っており、平成23年6月14日に成案を公表している。
同見直しは、今回の産活法の改正と同様、「新成長戦略」に基づき行われたもので、事前相談制度の廃止等の審査手続の改善や、国境を越えた市場画定の明確化等の審査基準の改善等を通じて、企業結合審査の迅速性および透明性を高めるとともに、国際整合性を一層強化することにより、グローバル市場にも配慮した審査を可能とするものとなっている(詳細については、公正取引委員会のウェブサイト等を参照されたい)。
Ⅱ.組織再編手続の簡素化・多様化(会社法特例)
1.自社株対価TOBの利用促進 近年、大型の買収に対するニーズが高まっており、多額の現金を用いずに買収が可能な自社株式を対価とする公開買付け(以下「自社株対価TOB」という)は、事業再構築等を進めていくうえで有効なツールとなり得る。
しかし、現行制度において、自社株対価TOBは、対象会社株式を現物出資財産として、買付会社株式を発行するという整理となることから、①プレミアムを付した自社株対価TOBを行う場合、買付会社において有利発行の株主総会決議が必要となる可能性があり、また、②検査役の調査が原則必要となる。
さらに、③株式発行時の対象会社株式の価額が、募集事項に定めた価額を著しく下回ることとなった場合には、応募株主および買付会社の取締役が填補責任を負う。このような懸念があることから、自社株対価TOBは、ほとんど利用されていないのが実情である。
そこで、買付会社株式の払込金額および対象会社株式の価額の代わりに、買付会社株式と対象会社株式の交換比率を募集事項とすることを認める特例措置を設け(産活法21条の2)、これにより、上記の①有利発行規制、②検査役調査、③価額不足填補責任の規定を適用しないこととした(図表2-1参照)。
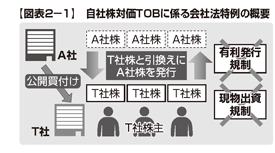
なお、買付会社の既存株主保護の観点から、株式買取請求権を付与する、原則として株主総会の特別決議を要する(ただし、発行する買付会社株式数に買付会社の1株当たり純資産額を乗じて得た額が、買付会社の純資産額の5分の1以下の場合は不要)等の株主保護手続を設けている。
2.完全子会社化手続の簡素化 事業再構築等を進めていくうえで、経営の機動性やグループ内資金の流動性を増大させ、効率的なグループ経営を可能とする完全子会社化が重要な選択肢である。
現在、キャッシュアウトによる完全子会社化は、公開買付けの後、対象会社において全部取得条項付種類株式を利用した手続を経る方法が一般的だが、この方法では、公開買付け終了後、株主総会の開催や端数の売却に係る裁判所の許可手続に約4~6か月の期間を要する。
しかし、公開買付けにより、買付会社が対象会社の大多数の株式を取得した場合、完全子会社化に関する株主総会の特別決議は可決されることが明らかであり、また、端数の売却に係る裁判所の許可手続も、特段の事情がない限り、公開買付価格を尊重する運用がなされている。
そこで、認定事業者が対象会社の完全子会社化を目的として公開買付けを行い、対象会社の10分の9以上の割合の議決権を取得した場合、法令または定款違反がないこと、公開買付価格に相当する対価が対象会社の株主に割り当てられること等を要件とする本特例利用の認定を受けることにより、全部取得条項付種類株式を利用した手続において、株主総会の特別決議による承認および端数の売却に係る裁判所の許可手続を省略できることとした(産活法21条の3。図表2-2参照)。
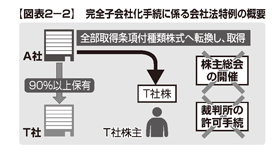
3.会社法特例のメリット これらの会社法特例を設けたことによるメリットとしては、次の点が挙げられる。
① 自社株対価TOBの特例により、有利発行規制、検査役調査および価額不足填補責任の規定の適用がなくなり、自社株対価TOBを利用した組織再編を実施しやすくなる。
② 完全子会社化手続の特例により、完全子会社化手続に要する期間を3か月ほど短縮できる。
Ⅲ.二段階融資制度の創設
1.措置の背景と制度の骨格 国際競争力の強化を念頭に置いた事業再編においては、研究開発・設備投資の資金、合併・買収に係る資金、設備を廃棄する場合の整地費用等の償還期間の長い資金が必要となることが多い。
また、このような再編後は、技術の擦り合わせや生産工程・物流および人員の最適配置の実現など、その効果が発揮されるまでに期間を要し、資金の回収が長期化することが想定されるが、民間金融機関による融資は5年未満等比較的短期のものが多く、十分な資金供給がされていない状況にある。
このため、民間金融を補完する支援措置として、株式会社日本政策金融公庫が、国際競争力の強化を念頭に置いた複数事業者が行う産業再編の取組みについて融資を行う指定金融機関に対し、財政投融資資金を原資とする長期・低利の貸付を行う二段階融資制度を創設した(産活法24条の3等)。
2.二段階融資制度のメリット この制度の創設により、事業者が、民間金融機関では供給されにくい5年以上の長期資金を、財政投融資資金を原資として借り入れられるだけでなく、呼び水効果的に、民間金融機関からの融資資金が入りやすくなる。
これにより、組織再編を円滑に進められることとなる。
Ⅳ.ベンチャー等の成長企業に対する資金調達支援
1.措置の背景と制度の骨格 近年、クリーンテックやライフサイエンス分野等におけるベンチャー等の成長企業は、急速に立ち上がるグローバル市場に対応し、自社の研究開発成果を利用した新商品を大規模に生産し、成長を図っていくことが必要になっている。
このような動きは、わが国経済の持続的な成長にきわめて重要であるが、新商品の量産化に際しては、大規模な設備投資と、それに伴い多額の設備投資資金を必要とする。また、これらの成長企業は、新規株式公開までの期間の長期化・困難化により、必要な資金が得られず、加えて、安定した売上実績がないこと等の理由により、民間金融機関からの資金調達も困難な状況にある。
このような状況を打開し、成長企業の大規模な新事業展開を促進するため、成長企業に民間金融機関が行う融資に対し、独立行政法人中小企業基盤整備機構が債務保証を実施する制度を創設した(産活法24条)。
2.中小機構による債務保証制度のメリット 制度創設により、資金調達難にあるベンチャー等の成長企業への民間金融機関の融資に対して債務保証を措置することにより、民間金融機関から、成長企業に対する資金供給が円滑化することとなる(図表3参照)。
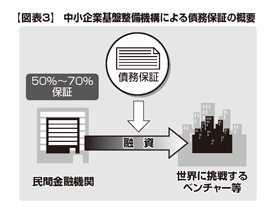
Ⅴ.地域中小企業の事業引継ぎ円滑化支援
1.措置の背景と制度の骨格 多くの地域中小企業の経営が既存の体制のままでは立ち行かなくなってきている。廃業・倒産が拡大し、雇用や技術など地域の財産を喪失しかねない。他方、事業の新たな展開を指向する中小企業もあるが、ヒト・モノ・カネ・技術が十分でないことから、単独での対応は容易ではない。
このような場合、他の事業者の経営資源を譲り受けることで迅速な事業の展開を行うことは有効な方策であるが、事業の引継ぎを希望する企業の仲介を支援する仕組みができていないことから、売手と買手のマッチングが困難である。
このため、産活法の規定に基づき、47都道府県に設置されている認定支援機関の業務に事業引継ぎ支援業務を追加し(産活法41条)、事業引継ぎに関する相談窓口を設けることにした。また、準備の整った認定支援機関から順次、事業引継ぎ支援センターを設置し、守秘義務を課した事業の譲渡、譲受けに関する専門家(経験のある税理士、公認会計士等)を配置し、事業引継ぎを希望する企業間の仲介および事業引継ぎ契約の成立に向けた支援を行う。
さらに、事業引継ぎの支援措置として、事業を譲り受ける側に対し、信用保険の別枠化、中小企業投資育成株式会社法の特例等の金融支援の措置を設けた(産活法25条)。また、事業引継ぎに伴う許認可承継の円滑化を図るための措置も設けることとした(同法32条の2)。
2.地域中小企業の事業引継ぎ支援措置のメリット 事業引継ぎを支援する公的支援機関を設け、かつ、専門家を配置することで、事業引継ぎの相談を安心して行えるとともに、低コストで専門家の支援を受けられるようになり、もって地域中小企業の経営基盤が強化され、事業の生産性の向上や新規分野の開拓に寄与すると考えている。
また、東日本大震災により直接・間接に大きな影響を受け、やむを得ず廃業を選択する中小企業が増えかねないことから、本措置の活用により、地域における雇用や技術を守るため、法律を早期に施行できるよう準備を進めてきた。
Ⅵ.その他の改正事項
1.事業再構築の定義の変更(産活法2条)
(1)事業構造の変更の要件の削除・追加 旧法において「資本の相当程度の増加」を事業再構築計画の対象としている。これは、わが国企業の自己資本の充実を図るため、財務体質強化の取組みを後押しするように措置したものである。しかし、わが国企業の自己資本比率は、平成11年度の産活法制定以降、順調に増加しており、おおむね当初の目的は達成された。
このため、今般の改正法においては、合併や分割等、企業の組織再編を伴う計画に支援対象を限定し、「資本の相当程度の増加」を事業構造の変更の要件から削除した。しかし、合併や分割等の組織再編を伴う「資本の相当程度の増加」は引き続き支援対象となる。
また、近年、事業再編の形態として、有限責任事業組合(以下「LLP」という)の利用が増えている。LLPは有限責任制、内部自治の原則、構成員課税等の組織運営上のメリットを持っている。
たとえば、大規模な生産設備を有する石油精製や化学などの製造事業者では、LLPを活用し複数事業者の設備間の生産効率等考慮したうえで生産最適化を図ることで、適切な設備稼働率を維持することが可能となるなど、当該事業者の中核的事業の強化を目指すことが有効であると考えられている。
したがって、LLPを活用した事業再編を一層促進するため、産活法の事業再構築計画に「LLPに対する出資」を規定し、それを活用した事業者の取組みを支援することとする。
(2)事業革新の要件の追加 改正法では、事業革新の対象として、「商品及び役務を一体的に組み合わせて行う」を規定として追加した。
これは、世界市場では、「高品質・単品モノ売り」から「機器とサービスの組合せ」への需要の変化など、大きな変化が生じており、このような変化に対応した取組みを後押しするために行ったものである。
具体的には、インフラ分野等の新たな需要に対応した「システム売り」への転換、たとえば、プラント製造事業者が、顧客の需要に応じて、プラントの販売のみならず、その後のメンテナンスサービス等を一体的に組み合わせて提供することなどを想定している。
2.事業分野別指針の追加 わが国産業の国際競争力強化のため、①投資の規模等の確保を意図した再編と、②新たな需要に対応したシステム売りを支援することがきわめて重要である。
このため、既存の過剰供給構造にある事業分野および生産性の向上が特に必要である事業分野に加え、新たに「事業分野別指針」として、
・わが国事業者が行う事業の規模が国際的な水準に比較して著しく小さい事業分野
・商品やサービスを一体的に組み合わせて行う販売等により、新たな需要を開拓することが特に必要な事業分野
について、それぞれ指針を定めることができることとしており、今後、これらに該当する事業分野について指針の策定が検討されることになる。
Ⅶ.認定計画の利用手続
1.申請のスケジュール 実際に申請を検討される場合は、まずは経済産業省産業再生課(電話:03-3501-1560)までご連絡をいただきたい。
申請スケジュールは、事前相談の開始から認定まで2か月ほどが見込まれる(図表4参照)。正式申請前の事前相談の段階では、おおまかな概要が分かる資料を基に、産活法の目的や要件に合致しているかを検討し、その後、正式な申請書の作成や数値要件の根拠等を精査することになる。
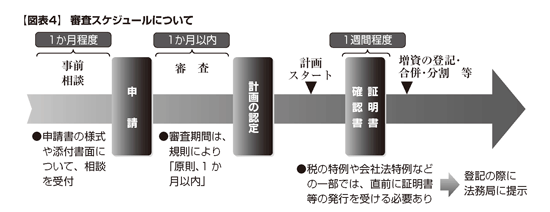
また、出資の円滑化措置、中小機構の債務保証を含む計画、二段階融資については、金融機関との事前相談が必要となっている。
2.申請窓口 各事業を所管する省庁にて申請を受け付けている(脚注2)。複数の官庁にまたがった事業を行っている場合は、まずは計画している主な事業を所管している官庁にご相談いただきたい。複数省庁による共同認定となるケースもある。経済産業省では、企業規模に応じて全国9か所の各地方経済産業局でも手続が可能である。
また、中小企業者の有する経営資源を承継して再生を図る「中小企業承継事業再生計画」の認定については、すべて各地方経済産業局での受付となっており、最寄りの地方経済産業局または中小企業再生支援協議会までご相談いただきたい。
おわりに
現在、新興国市場の急速な拡大により、市場競争の舞台は先進国から新興国を含めた世界市場に移行している。これに伴い、競争条件や需要構造が世界的に変化し、企業が様々な形での事業の統合、選択と集中、連携、事業転換を模索し、これに対応しようとしている。
しかし、このような激動な世界経済を勝ち抜くには、個別企業だけでは対応仕切れない部分も多く存在する。
今回の産活法改正は、国際競争力の強化を念頭に置いた産業再編の推進、システム売りへの転換、地域・ベンチャー企業の基盤強化が柱となっている。その支援策として、制度の創設や支援体制の整備を行った。また、厳しい国家財政のなか、限られた財源を最大限に有効活用した資金面の支援策も盛り込んでいる。
今後は、法律を適切に運用し、事業者の積極的な取組みを後押しし、わが国経済・産業の持続的な発展に寄与できるよう尽力していきたい。
脚注
1 「適正な競争が確保されないおそれ」は、政令において、①独占禁止法上の株式取得や合併等の届出を要する場合、あるいは②共同して措置を行う事業者のうち、一の事業者の国内売上高合計額が200億円超かつ他の一の事業者の国内売上高合計額が50億円超の場合としている。
2 申請資料の様式や記載例(テンプレート)については、次のウェブサイトを参照されたい。http://www.meti.go.jp/sankatsuhou/
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -























