解説記事2011年08月22日 【ニュース特集】 法律案からは読み取れない外国税額控除制度の改正項目(2011年8月22日号・№415)
法律案には未記載の政令改正項目も大綱には明記
法律案からは読み取れない外国税額控除制度の改正項目
外国税額控除制度については、1月に国会に提出された「所得税法等の一部を改正する法律案」により、表1に掲げた項目の改正が予定されていた。
しかし、同法案が「現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律」(平成23年6月30日に公布・施行)と「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律案」(現在国会で継続審議中)とに分離されたことから(本誌412号4頁等参照)、外国税額控除制度の改正項目についても、税制改正が実現された項目と未実現の項目が混在する結果となっている。
外国税額控除制度の改正は、本法だけではなく、政令の改正と併せて実現する項目も存在するため、法律案等からだけでは直接に読み取れない部分も少なからず存在する。
そこで本特集では、昨年12月17日に閣議決定された「平成23年度税制改正大綱」(以下「大綱」という)に明記された外国税額控除制度の改正項目の実現状況を、大綱に沿って確認していく。
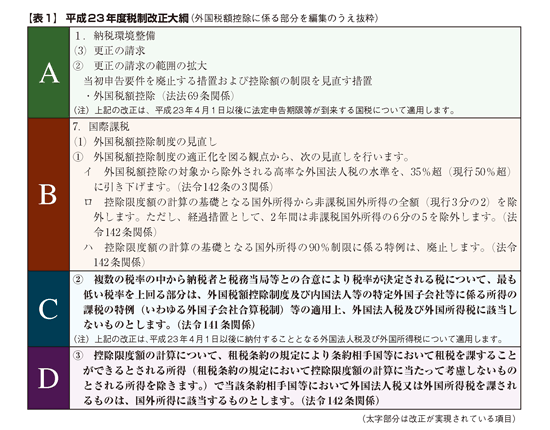
未改正
当初申告要件の廃止および控除額の制限の見直し(表1A)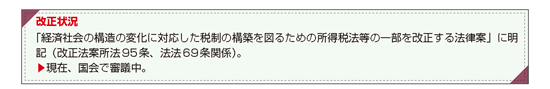
改正案では更正の請求や修正申告でも適用可 大綱では、納税環境の整備を図る観点から外国税額控除制度を含め、当初申告要件を見直すことが明記されている。
現行法上、外国税額控除の適用を受けるためには、確定申告書に控除を受けるべき金額を記載したうえ、所定の書類を添付する必要がある。加えて、控除金額の限度額は当初の確定申告書に記載した金額とされている。
したがって、確定申告書に金額の記載がない場合や所定の書類の添付がない場合は、後日、更正の請求や修正申告書を提出した場合であっても、外国税額控除の適用は原則として認められていない(法法69⑩)。
現在国会において審議中の法律案では、当初提出した確定申告書に控除を受けるべき金額の記載がない場合等であっても、後日、修正申告書または更正請求書に適用金額を記載した書類の添付等がある場合には、当該書類に記載された金額を限度とし、外国税額控除の適用を受けることができるとする改正が予定されている(改正法案法法69⑩)。しかし、現時点では未改正の項目であるため、外国税額控除の適用を受けるためには、確定申告書を提出する際に、控除対象外国法人税額等の記載漏れがないよう注意する必要がある。
未改正
外国税額控除制度の適正化を図る観点からの見直し(表1B)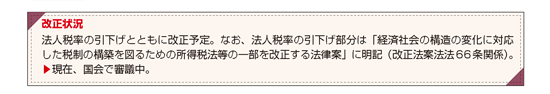
法人税率引下げとともに改正されるが…… 外国税額控除制度については、以前より「彼此流用の問題」が指摘されていた(図1参照)。具体的には、軽課税国へ進出している企業が、わが国で外国税額控除ができるという理由で高税率国への投資を行うことにより、本来であれば二重課税となっていない部分についても、外国税額控除が利用できるという問題が生じていた。そこで大綱では、法人税率の引下げを契機として、外国税額控除の対象から除かれる高率部分の水準を50%超から35%超に引き下げるなどの改正が明記されていた。これにより、二重課税となっていない外国税額についても、控除ができるという彼此流用の問題が解決される予定であった。
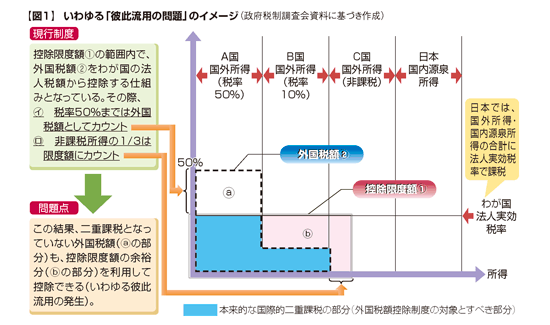
外国税額控除の適正化に係る改正項目は、政令による改正項目であることから、国会で審議中の法律案や6月30日に施行された税制改正法には改正内容が明記されていない。しかし、外国税額控除の適正化に係る改正項目は、法人税率の引下げによる減収分を課税ベースの拡大で補う措置の一環として行われるものであることから、国会で審議中の法律案において明記されている法人税率の引下げ(改正法案法法66条関係)が実現した場合、外国税額控除の適正化に係る政令改正も実現されることとなる。
改正済
外国法人税の範囲の見直し(表1C)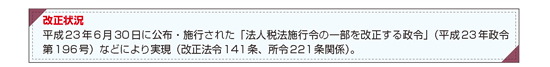
最高裁判決を踏まえた改正 国際的二重課税を調整する外国税額控除制度では、「外国法人税」の定義が法令(法法69①、法令141条)において定められており、納付後、任意に納税者が還付請求できるような税など、外国法人税として捉えるのが不適当なものは法令で除外されている。
しかし、「税率が納税者と税務当局との合意により決定される税」を外国法人税から除外する規定がないところ、最高裁判所第一小法廷平成21年12月3日判決(いわゆるガーンジー島事件。事件の概要はコラム参照)は、明文の規定がない以上、こうした税が外国法人税に該当しないとはいえないと判示。この判決を受けて、「税率が納税者と税務当局との合意により決定される」ような外国法人税として捉えることが不適当な部分は外国法人税に含まれない旨が明確化されることとなった。
6月30日以後納付分から対象に 大綱では、平成23年4月1日以後に納付することとなる外国法人税等について適用されることとされていた。しかし、「現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律」が6月30日に公布・施行されたことに伴い、法人税法施行令の一部を改正する政令が同日、公布・施行されたことを受け、平成23年6月30日以後に納付することとなる外国法人税等について適用されることとなった。
改正法案の成立を待たずに改正が実現 外国税額控除の適正化に係る改正項目(表1B参照)については、法人税率の引下げによる減収分を補う措置とされている。しかし、外国法人税の範囲の見直しは、法人税率の引下げ議論と直接関係なく、前述の最高裁判決を受けて改正されるものであることから、法人税率の引下げが明記されている審議中の法律案の成立を待たずに、改正が実現されている。
改正済
控除限度額の計算に係る国外所得の範囲の見直し(表1D)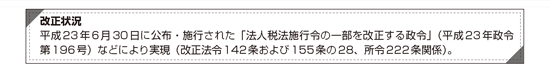
国外所得に該当と明記し二重課税を排除 大綱では、租税条約相手国で外国税等が課されるものは、国外所得に該当するとする改正が明記されていた。たとえば、韓国法人の役員である日本の居住者が、日本で役員としての役務提供を行い、韓国法人から役員報酬を受領した場合、日本および韓国で課税されることとなる。この場合、役員報酬が国外所得に該当すれば外国税額控除が適用できるところ、国外所得に該当しないことから、韓国で課税された税額が日本の外国税額控除の対象とならず、二重課税が排除されないという問題が発生していた(図2参照)。そこで、外国税額控除における控除限度額の計算上、条約相手国に条約上課税権を認めた所得は「国外所得」に該当するとの措置を講ずることにより、居住者について生じた二重課税の問題が解消されることとなった。
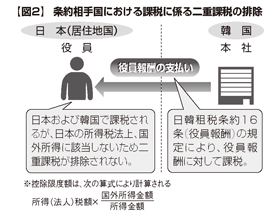
改正法案の成立を待たずに改正が実現 国外所得の範囲の見直しは、法人税率の引下げ議論と直接関係なく、二重課税の解消を目的とした改正であることから、審議中の法律案の成立を待たずに、改正が実現されている。
Column
「外国法人税」の範囲を改正するきっかけとなったガーンジー島事件とは? 納税者と税務当局との合意により「0%超30%以下」の範囲で税率が決定されるガーンジー島の租税が、わが国の法人税法上「外国法人税」に該当するかどうかが争われた事件(平成20年(行ヒ)43号)。最高裁は、ガーンジー島の租税について、租税法律主義の観点から、外国法人税に含まれないとされる法人税法施行令141条3項1号・2号に規定するこれらに類する税にも当たらず、法人税に相当する税ではないということも困難であることから、外国法人税に該当することを否定できないと判断。納税者勝訴となる逆転判決を言い渡している(本誌334号11頁参照)。
法律案からは読み取れない外国税額控除制度の改正項目
外国税額控除制度については、1月に国会に提出された「所得税法等の一部を改正する法律案」により、表1に掲げた項目の改正が予定されていた。
しかし、同法案が「現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律」(平成23年6月30日に公布・施行)と「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律案」(現在国会で継続審議中)とに分離されたことから(本誌412号4頁等参照)、外国税額控除制度の改正項目についても、税制改正が実現された項目と未実現の項目が混在する結果となっている。
外国税額控除制度の改正は、本法だけではなく、政令の改正と併せて実現する項目も存在するため、法律案等からだけでは直接に読み取れない部分も少なからず存在する。
そこで本特集では、昨年12月17日に閣議決定された「平成23年度税制改正大綱」(以下「大綱」という)に明記された外国税額控除制度の改正項目の実現状況を、大綱に沿って確認していく。
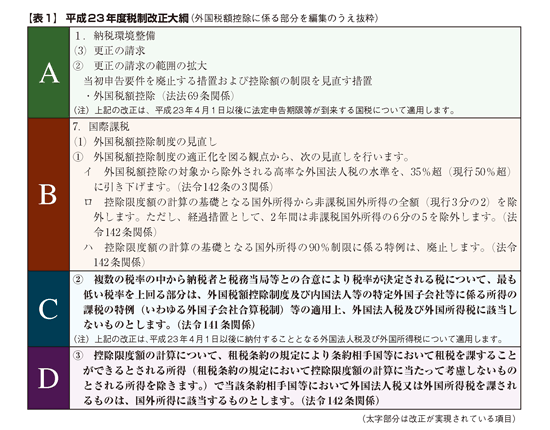
未改正
当初申告要件の廃止および控除額の制限の見直し(表1A)
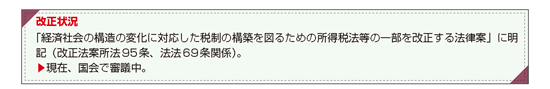
改正案では更正の請求や修正申告でも適用可 大綱では、納税環境の整備を図る観点から外国税額控除制度を含め、当初申告要件を見直すことが明記されている。
現行法上、外国税額控除の適用を受けるためには、確定申告書に控除を受けるべき金額を記載したうえ、所定の書類を添付する必要がある。加えて、控除金額の限度額は当初の確定申告書に記載した金額とされている。
したがって、確定申告書に金額の記載がない場合や所定の書類の添付がない場合は、後日、更正の請求や修正申告書を提出した場合であっても、外国税額控除の適用は原則として認められていない(法法69⑩)。
現在国会において審議中の法律案では、当初提出した確定申告書に控除を受けるべき金額の記載がない場合等であっても、後日、修正申告書または更正請求書に適用金額を記載した書類の添付等がある場合には、当該書類に記載された金額を限度とし、外国税額控除の適用を受けることができるとする改正が予定されている(改正法案法法69⑩)。しかし、現時点では未改正の項目であるため、外国税額控除の適用を受けるためには、確定申告書を提出する際に、控除対象外国法人税額等の記載漏れがないよう注意する必要がある。
未改正
外国税額控除制度の適正化を図る観点からの見直し(表1B)
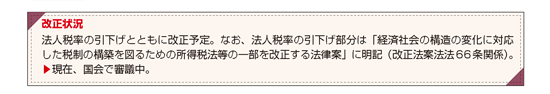
法人税率引下げとともに改正されるが…… 外国税額控除制度については、以前より「彼此流用の問題」が指摘されていた(図1参照)。具体的には、軽課税国へ進出している企業が、わが国で外国税額控除ができるという理由で高税率国への投資を行うことにより、本来であれば二重課税となっていない部分についても、外国税額控除が利用できるという問題が生じていた。そこで大綱では、法人税率の引下げを契機として、外国税額控除の対象から除かれる高率部分の水準を50%超から35%超に引き下げるなどの改正が明記されていた。これにより、二重課税となっていない外国税額についても、控除ができるという彼此流用の問題が解決される予定であった。
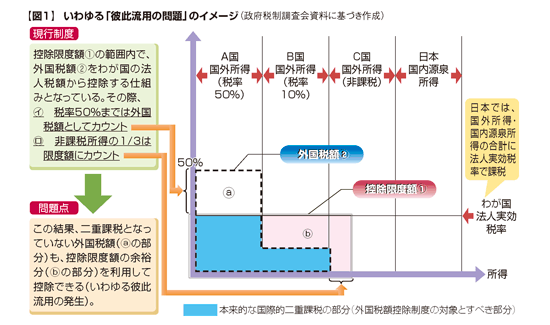
外国税額控除の適正化に係る改正項目は、政令による改正項目であることから、国会で審議中の法律案や6月30日に施行された税制改正法には改正内容が明記されていない。しかし、外国税額控除の適正化に係る改正項目は、法人税率の引下げによる減収分を課税ベースの拡大で補う措置の一環として行われるものであることから、国会で審議中の法律案において明記されている法人税率の引下げ(改正法案法法66条関係)が実現した場合、外国税額控除の適正化に係る政令改正も実現されることとなる。
改正済
外国法人税の範囲の見直し(表1C)
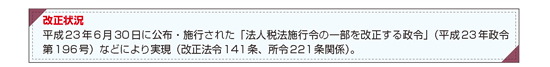
最高裁判決を踏まえた改正 国際的二重課税を調整する外国税額控除制度では、「外国法人税」の定義が法令(法法69①、法令141条)において定められており、納付後、任意に納税者が還付請求できるような税など、外国法人税として捉えるのが不適当なものは法令で除外されている。
しかし、「税率が納税者と税務当局との合意により決定される税」を外国法人税から除外する規定がないところ、最高裁判所第一小法廷平成21年12月3日判決(いわゆるガーンジー島事件。事件の概要はコラム参照)は、明文の規定がない以上、こうした税が外国法人税に該当しないとはいえないと判示。この判決を受けて、「税率が納税者と税務当局との合意により決定される」ような外国法人税として捉えることが不適当な部分は外国法人税に含まれない旨が明確化されることとなった。
6月30日以後納付分から対象に 大綱では、平成23年4月1日以後に納付することとなる外国法人税等について適用されることとされていた。しかし、「現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律」が6月30日に公布・施行されたことに伴い、法人税法施行令の一部を改正する政令が同日、公布・施行されたことを受け、平成23年6月30日以後に納付することとなる外国法人税等について適用されることとなった。
改正法案の成立を待たずに改正が実現 外国税額控除の適正化に係る改正項目(表1B参照)については、法人税率の引下げによる減収分を補う措置とされている。しかし、外国法人税の範囲の見直しは、法人税率の引下げ議論と直接関係なく、前述の最高裁判決を受けて改正されるものであることから、法人税率の引下げが明記されている審議中の法律案の成立を待たずに、改正が実現されている。
改正済
控除限度額の計算に係る国外所得の範囲の見直し(表1D)
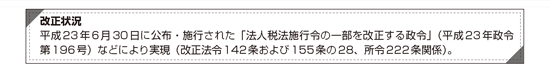
国外所得に該当と明記し二重課税を排除 大綱では、租税条約相手国で外国税等が課されるものは、国外所得に該当するとする改正が明記されていた。たとえば、韓国法人の役員である日本の居住者が、日本で役員としての役務提供を行い、韓国法人から役員報酬を受領した場合、日本および韓国で課税されることとなる。この場合、役員報酬が国外所得に該当すれば外国税額控除が適用できるところ、国外所得に該当しないことから、韓国で課税された税額が日本の外国税額控除の対象とならず、二重課税が排除されないという問題が発生していた(図2参照)。そこで、外国税額控除における控除限度額の計算上、条約相手国に条約上課税権を認めた所得は「国外所得」に該当するとの措置を講ずることにより、居住者について生じた二重課税の問題が解消されることとなった。
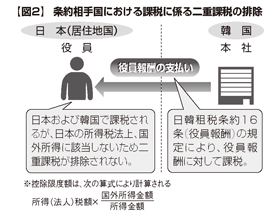
改正法案の成立を待たずに改正が実現 国外所得の範囲の見直しは、法人税率の引下げ議論と直接関係なく、二重課税の解消を目的とした改正であることから、審議中の法律案の成立を待たずに、改正が実現されている。
Column
「外国法人税」の範囲を改正するきっかけとなったガーンジー島事件とは? 納税者と税務当局との合意により「0%超30%以下」の範囲で税率が決定されるガーンジー島の租税が、わが国の法人税法上「外国法人税」に該当するかどうかが争われた事件(平成20年(行ヒ)43号)。最高裁は、ガーンジー島の租税について、租税法律主義の観点から、外国法人税に含まれないとされる法人税法施行令141条3項1号・2号に規定するこれらに類する税にも当たらず、法人税に相当する税ではないということも困難であることから、外国法人税に該当することを否定できないと判断。納税者勝訴となる逆転判決を言い渡している(本誌334号11頁参照)。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -

Copyright (C) 2019
SHINNIPPON-HOKI PUBLISHING CO.,LTD.





















