解説記事2011年11月28日 【ニュース特集】 検証・所有権移転外ファイナンス・リース取引の相続税評価(2011年11月28日号・№428)
法人税法改正で、“ゼロ評価”見直しも
検証・所有権移転外ファイナンス・リース取引の相続税評価
会計上、かつては賃貸借処理とされていた所有権移転外ファイナンス・リース取引だが、平成20年4月1日以後開始事業年度より原則として「売買処理」とされた。これを受け、平成19年度税制改正により、法人税法上も「平成20年4月1日以後に締結するリース契約」から売買処理とされたところだ。
この法人税法の改正が、相続税の純資産価額方式による株価の計算にどのような影響を与えるのか注目が集まっている。賃貸借処理を前提とすると、純資産価額方式による株価算定上、リース資産、リース債務とも“ゼロ評価”となるが、リース取引を「売買取引」ととらえた場合には、これまでとは異なる評価が成立することも考えられる。
ただ、現行の財産評価基本通達では所有権移転外ファイナンス・リースに対する明確な評価方法が定まっているわけではなく、課税当局としても、個別事案ごとに評価を検討することとしているようだ。
そこで本特集では、具体的にどのような評価が考えられるのか、本誌独自取材を踏まえ検証したい。
課税当局は、「個別事案ごとに評価」する姿勢 かつての日本の会計基準では、ファイナンス・リースのうちリース物件の所有権が借手に移転しないもの(所有権移転外ファイナンス・リース。コラム1参照)については、賃貸借取引と同様の会計処理が認められていた。しかし、国際会計基準では、このようなリースであっても、その実質に鑑み「売買取引」と取り扱っていることから、日本の会計基準においても、平成20年4月1日以後開始事業年度より原則として売買処理とされた。
会計基準の見直しを受け、平成19年度税制改正で法人税法が改正され、平成20年4月1日以後に締結するリース契約から、たとえ契約上は賃貸借取引であっても「売買があったものとみなす」旨の改正が行われたところだ(法法64条の2①)。法人税法改正前後の税務上の処理(借手側)は図表1のとおりとなる。

会計基準の改正に即座に法人税法が追随した形だが、これらの改正が影響をおよぼしかねないのが、相続税法上の純資産価額方式による株式の評価額だ。
従来の純資産価額方式による株価算定上は、「所有権移転外ファイナンス・リース=賃貸借取引」であることを前提として、リース資産、リース債務ともに“ゼロ評価”とされてきた。しかし、会計や法人税法同様に、所有権移転外ファイナンス・リースを「売買取引」ととらえた場合には、これまでとは異なる評価となることも考えられるところだ。
この点、現時点では明確な評価方法が定まっているわけではなく、課税当局としても、画一的な取扱いはせず、個別事案ごとに評価を判断していくとの姿勢のようだ。
では、具体的にどのような評価が考えられるのか、リース資産、リース債務に分けて整理してみよう。
リース資産の評価
「使用権」を評価対象とする考え方も 所有権移転外ファイナンス・リースが法人税法上(たとえ契約上は賃貸借取引であっても)「売買取引」とみなされることを踏まえ、相続税法上もリース資産の所有権は借手(評価会社)にあるとみなすこともあり得よう。そしてこの場合、所有権がある以上は、リース資産を時価評価するべきとの考え方が出てくる。
ただ、法人税法上は「売買取引」とみなされたとしても、私法上、所有権移転外ファイナンス・リース取引におけるリース資産の所有権はあくまで貸手(リース会社)にある。この点に着目すれば、純資産価額方式による株価もこれまでどおり「資産性なし=ゼロ評価」とされる可能性もある(コラム2参照)。
また、たとえ私法上は所有権がなくても、借手がリース資産の使用により収益を得ていることに着目すれば、「使用権」的なものを評価すべきとの考え方もある。実際、IFRSでは、借手に対し、リース物件の使用権に係る支払義務である「リース債務」とともに、リース期間中にリース物件を使用する権利である「使用権資産」の計上を求めることも検討されている(コラム3参照)。
リース債務の評価
「確実な債務か否か」は見方次第 リース債務については、それが「確実な債務」といえるかどうかにより、評価が変わってくることになる。
純資産価額方式においては、評価会社が課税時期において保有する各資産の相続税評価額から、各負債の金額の合計額(および評価差額に対する法人税額等に相当する金額)を控除することになるが(評基通185)、控除が認められる「各負債」は、相続税法14条1項の解釈を準用し、「課税時期現在における評価会社の負債で“確実”と認められるもの」に限定されている。
リース債務は、リース期間にわたり、いずれはその全額を支払うことが予定されているものであるうえ、一般的なリース契約では、中途解約が行われた場合、借手はリース会社に対し、リース債務残高相当額の違約金という“確定的な債務”の支払いを求められることになる。これらの点を踏まえれば、リース債務を「確実な債務」ととらえて、リース債務を簿価で評価するべきという考え方もあり得る。
その一方で、中途解約が行われた場合に違約金の支払いを求められるということは、逆にいえば、「中途解約をしない限り違約金の支払義務は発生しない」ということでもあり、この点からすると、中途解約をしない限り違約金の支払義務が発生しないリース債務は「確実な債務」とはいえないとの見方もでき、この場合、リース債務は従来どおり評価対象にはならない(ゼロ評価)とも考えられる。
リース契約の内容次第で評価が変わることも 今般、所有権移転外ファイナンス・リースの評価が問題となっている原因は、まぎれもなく会計基準の変更にある。
会計基準の変更によって相続税評価額が変わるということには違和感を唱える向きもあるだろう。ただ、会計基準や法人税法の改正は、所有権移転外ファイナス・リース取引のとらえ方を根本的に変えるものであるだけに、相続税評価がその影響を受けないとはいい切れないだろう。このように、会計基準の変更が相続税評価に影響を与えることは今後も起こり得るので、税理士等にあっては会計基準の変更にも気を配っておく必要がある(コラム3参照)。
もっとも、会計基準と相続税評価の関係は会計基準と法人税より希薄といえる。そのため、これまで述べてきたように所有権移転外ファイナス・リース取引に係るリース資産、リース債務の相続税評価には複数の選択肢が浮上しているのであり、課税当局としても、個別事案ごとの判断とならざるを得ないのが現状だろう。
さらに、一口にリース資産といっても、低額なものから高額なものまで様々なものが存在することや、リース契約の内容によって、実質的には売買取引に近いものや、あるいは賃貸借取引に近いものがあり、これらが画一的な評価を一層難しくしている。
とはいえ、納税者側の予測可能性の確保という観点からも、いずれは評価方法の明確化が求められることになりそうだ。
検証・所有権移転外ファイナンス・リース取引の相続税評価
会計上、かつては賃貸借処理とされていた所有権移転外ファイナンス・リース取引だが、平成20年4月1日以後開始事業年度より原則として「売買処理」とされた。これを受け、平成19年度税制改正により、法人税法上も「平成20年4月1日以後に締結するリース契約」から売買処理とされたところだ。
この法人税法の改正が、相続税の純資産価額方式による株価の計算にどのような影響を与えるのか注目が集まっている。賃貸借処理を前提とすると、純資産価額方式による株価算定上、リース資産、リース債務とも“ゼロ評価”となるが、リース取引を「売買取引」ととらえた場合には、これまでとは異なる評価が成立することも考えられる。
ただ、現行の財産評価基本通達では所有権移転外ファイナンス・リースに対する明確な評価方法が定まっているわけではなく、課税当局としても、個別事案ごとに評価を検討することとしているようだ。
そこで本特集では、具体的にどのような評価が考えられるのか、本誌独自取材を踏まえ検証したい。
課税当局は、「個別事案ごとに評価」する姿勢 かつての日本の会計基準では、ファイナンス・リースのうちリース物件の所有権が借手に移転しないもの(所有権移転外ファイナンス・リース。コラム1参照)については、賃貸借取引と同様の会計処理が認められていた。しかし、国際会計基準では、このようなリースであっても、その実質に鑑み「売買取引」と取り扱っていることから、日本の会計基準においても、平成20年4月1日以後開始事業年度より原則として売買処理とされた。
会計基準の見直しを受け、平成19年度税制改正で法人税法が改正され、平成20年4月1日以後に締結するリース契約から、たとえ契約上は賃貸借取引であっても「売買があったものとみなす」旨の改正が行われたところだ(法法64条の2①)。法人税法改正前後の税務上の処理(借手側)は図表1のとおりとなる。

会計基準の改正に即座に法人税法が追随した形だが、これらの改正が影響をおよぼしかねないのが、相続税法上の純資産価額方式による株式の評価額だ。
従来の純資産価額方式による株価算定上は、「所有権移転外ファイナンス・リース=賃貸借取引」であることを前提として、リース資産、リース債務ともに“ゼロ評価”とされてきた。しかし、会計や法人税法同様に、所有権移転外ファイナンス・リースを「売買取引」ととらえた場合には、これまでとは異なる評価となることも考えられるところだ。
この点、現時点では明確な評価方法が定まっているわけではなく、課税当局としても、画一的な取扱いはせず、個別事案ごとに評価を判断していくとの姿勢のようだ。
では、具体的にどのような評価が考えられるのか、リース資産、リース債務に分けて整理してみよう。
| コラム1 | 1分でわかる「所有権移転外ファイナンス・リース」 |
リース取引には大きく分けて「オペレーティング・リース」と「ファイナンス・リース」がある。そして、ファイナンス・リースはさらに「所有権移転ファイナンス・リース」と「所有権移転外ファイナンス・リース」に分かれる。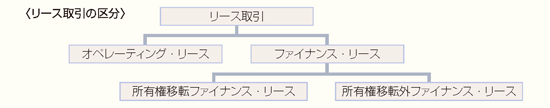 簡単にいうと、「物を貸して賃貸料をもらう」という元来のリースがオペレーティング・リースであるのに対し、「リース期間の満期まで解約が不能」かつ「フル・ペイアウト」を特徴とし、実質的には借手に資産を売却し、代金を割賦でもらうに等しいのが「ファイナンス・リース」だ。「フル・ペイアウト」とは、ユーザーが支払うリース料の合計額に、リース物件の取得価額および諸費用のほぼ全額が含まれていることを意味している。 そして、ファイナンス・リースのうち、リース物件の所有権が借手に移転するものが「所有権移転ファイナンス・リース」、移転しないものが「所有権移転外ファイナンス・リース」ということになる。 | |
リース資産の評価
「使用権」を評価対象とする考え方も 所有権移転外ファイナンス・リースが法人税法上(たとえ契約上は賃貸借取引であっても)「売買取引」とみなされることを踏まえ、相続税法上もリース資産の所有権は借手(評価会社)にあるとみなすこともあり得よう。そしてこの場合、所有権がある以上は、リース資産を時価評価するべきとの考え方が出てくる。
ただ、法人税法上は「売買取引」とみなされたとしても、私法上、所有権移転外ファイナンス・リース取引におけるリース資産の所有権はあくまで貸手(リース会社)にある。この点に着目すれば、純資産価額方式による株価もこれまでどおり「資産性なし=ゼロ評価」とされる可能性もある(コラム2参照)。
また、たとえ私法上は所有権がなくても、借手がリース資産の使用により収益を得ていることに着目すれば、「使用権」的なものを評価すべきとの考え方もある。実際、IFRSでは、借手に対し、リース物件の使用権に係る支払義務である「リース債務」とともに、リース期間中にリース物件を使用する権利である「使用権資産」の計上を求めることも検討されている(コラム3参照)。
| コラム2 | 償却資産税の申告と所有権 |
| 地方税法343条では、「償却資産」に対して固定資産税(償却資産税)を課しているが、リース資産もこの償却資産税の課税対象となる。といっても、所有権移転外ファイナス・リースのようにリース資産の所有権をリース会社(貸手)が持っている場合、償却資産税の申告を行うのはリース会社となる。 所有権移転外ファイナンス・リースの相続税評価では、リース資産の所有権がリース会社・借手のどちらにあるのかということが問題となるが、固定資産税においては、私法上の所有権者に課税を行っているわけだ。国税と地方税という違いはあるものの、相続税も固定資産税も同じ資産税であり、同様の考え方が採られても不思議ではない。 | |
| コラム3 | オペレーティング・リースも資産計上? |
| 会計上、使用権移転外ファイナンス・リースについて売買処理、すなわち資産計上が求められることになったのと同様、オペレーティング・リースについても同様に資産計上が求められることになる可能性がある。 国際会計基準審議会(IASB)と米国財務会計基準審議会(FASB)は2009年8月17日、リース取引に関する共同公開草案を公表、リースの借手は、リース期間中にリース物件を使用する権利である「使用権資産」、リース物件の使用権に係る支払義務である「リース債務」の計上を求めるとともに、ファイナンス・リースとオペレーティング・リースの区分を廃止、全てのリースを資産計上する方向を打ち出した。 仮にこれが実現した場合、所有権移転外ファイナンス・リースについて日本の会計基準が2008年(平成20年)4月1日以後開始する連結会計年度および事業年度より「売買処理」との立場を採ったことに連動し、税務上も資産計上が求められることになったのと同様、オペレーティング・リースについても同様に資産計上が求められる可能性は否定できない。 ただ、同案は欧米や日本でも批判が強く、IFRSと米国会計基準のコンバージェンスも当初予定の2011年6月から延期されている。 また、日本の会計基準が「オペレーティング・リースも資産計上」というIFRSを全面的に受け入れたとしても、いわゆるダイナミック・アプローチ(連結先行)により、資産計上が求められるのは連結財務諸表に限られる可能性が高く、個別財務諸表においては現行の費用処理が維持され、個別財務諸表をベースとする税務には影響が及ばないことも考えられる。 | |
リース債務の評価
「確実な債務か否か」は見方次第 リース債務については、それが「確実な債務」といえるかどうかにより、評価が変わってくることになる。
純資産価額方式においては、評価会社が課税時期において保有する各資産の相続税評価額から、各負債の金額の合計額(および評価差額に対する法人税額等に相当する金額)を控除することになるが(評基通185)、控除が認められる「各負債」は、相続税法14条1項の解釈を準用し、「課税時期現在における評価会社の負債で“確実”と認められるもの」に限定されている。
リース債務は、リース期間にわたり、いずれはその全額を支払うことが予定されているものであるうえ、一般的なリース契約では、中途解約が行われた場合、借手はリース会社に対し、リース債務残高相当額の違約金という“確定的な債務”の支払いを求められることになる。これらの点を踏まえれば、リース債務を「確実な債務」ととらえて、リース債務を簿価で評価するべきという考え方もあり得る。
その一方で、中途解約が行われた場合に違約金の支払いを求められるということは、逆にいえば、「中途解約をしない限り違約金の支払義務は発生しない」ということでもあり、この点からすると、中途解約をしない限り違約金の支払義務が発生しないリース債務は「確実な債務」とはいえないとの見方もでき、この場合、リース債務は従来どおり評価対象にはならない(ゼロ評価)とも考えられる。
リース契約の内容次第で評価が変わることも 今般、所有権移転外ファイナンス・リースの評価が問題となっている原因は、まぎれもなく会計基準の変更にある。
会計基準の変更によって相続税評価額が変わるということには違和感を唱える向きもあるだろう。ただ、会計基準や法人税法の改正は、所有権移転外ファイナス・リース取引のとらえ方を根本的に変えるものであるだけに、相続税評価がその影響を受けないとはいい切れないだろう。このように、会計基準の変更が相続税評価に影響を与えることは今後も起こり得るので、税理士等にあっては会計基準の変更にも気を配っておく必要がある(コラム3参照)。
もっとも、会計基準と相続税評価の関係は会計基準と法人税より希薄といえる。そのため、これまで述べてきたように所有権移転外ファイナス・リース取引に係るリース資産、リース債務の相続税評価には複数の選択肢が浮上しているのであり、課税当局としても、個別事案ごとの判断とならざるを得ないのが現状だろう。
さらに、一口にリース資産といっても、低額なものから高額なものまで様々なものが存在することや、リース契約の内容によって、実質的には売買取引に近いものや、あるいは賃貸借取引に近いものがあり、これらが画一的な評価を一層難しくしている。
とはいえ、納税者側の予測可能性の確保という観点からも、いずれは評価方法の明確化が求められることになりそうだ。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -

Copyright (C) 2019
SHINNIPPON-HOKI PUBLISHING CO.,LTD.




















