解説記事2011年12月26日 【第2特集】 企業組織再編でインサイダー取引規制が変わる!(2011年12月26日号・№432)
税理士・会計士も知らないでは済まされない
企業組織再編でインサイダー取引規制が変わる!
企業組織再編を行ううえで重要なのは何も税務上の「適格」「非適格」の判断や財産評価などだけではない。税理士や公認会計士が企業組織再編成に何らかの形で加わっている以上、インサイダー取引規制も是非とも覚えておきたいポイントの1つとなる。
金融審議会「インサイダー取引規制に関するワーキング・グループ」(座長:神田秀樹東京大学大学院法学政治学研究科教授)は12月15日、「企業グループ化に対応したインサイダー取引規制の見直しについて」と題する報告書を公表した(今号22頁参照)。報告書では、合併、会社分割、株式交換、事業譲渡を行う際に、その対価として行う自己株式の取得については新株発行と同様、インサイダー取引規制を適用しないなどとしている。今回の見直しは、企業が選択する組織再編の手段によってインサイダー取引規制の適用が異なるといった問題点などを調整するものであり、今後、インサイダー取引規制を考慮せず、組織再編が行いやすくなる。
なお、金融庁は来年の通常国会で金融商品取引法の一部改正案を提出する方針としている(本誌430号14頁参照)。
合併や会社分割の場合もインサイダー取引規制の対象に 金融審議会は今年3月の諮問を受けて「インサイダー取引規制に関するワーキング・グループ」を設置。企業組織再編など、グループ経営が一般化するなか、インサイダー取引規制が十分に対応していないなどの指摘を受け、7月8日から検討を行ってきたものだ。
今回公表された報告書でのポイントの1つは、企業の組織再編におけるインサイダー取引規制の適用関係を整理することにある。
企業が組織再編を行う際には、事業譲渡や合併、会社分割、株式交換等が主要な手段となる。現行のインサイダー取引規制は、上場株券等に係る売買等(金商法166条1項)を規制対象としているため、たとえば、事業譲渡は、個々の権利義務を承継させる行為(特定承継)であることから、金商法上の「売買等」に当たり、インサイダー取引規制の対象となる。
一方、合併や会社分割は権利義務を一括して承継させる行為(包括承継)であるため、「売買等」に当たらず、インサイダー取引規制の対象外となっている。
現状では、このように会社が選択する組織再編の手段によってインサイダー取引規制の適用関係が異なるという状況となっている。
上場株券20%未満等の3つのケースは除外 このため、報告書では、まず合併や会社分割により上場株券等を承継する場合についても、事業譲渡と同様に、インサイダー取引規制の対象とすることが適当としている(図表1参照)。そのうえで、インサイダー取引に利用される危険性が低いものと見込まれる3つのケースについては、適用除外とすることが適当とした。
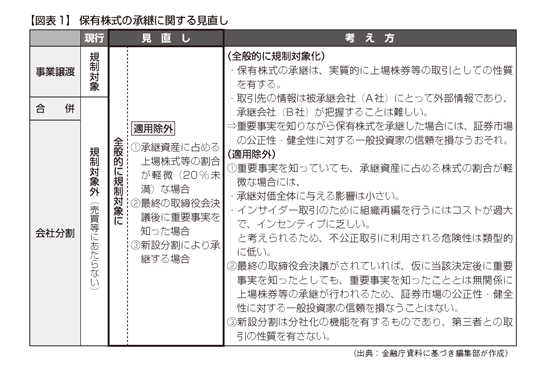
具体的には、①承継資産に占める上場株券等の割合が20%未満の場合、②最終の取締役会決議後に重要事実を知った場合、③新設分割による承継の場合については、インサイダー取引規制の対象外としている。
合併・会社分割等に伴う自己株取得は対象外に また、組織再編の対価として上場株券等を割り当てる場合の整理も行われる。現行、対価として新株発行を行う場合には、所有権の移転ではないため、「売買等」に当たらず、インサイダー取引規制の対象とならないが、自己株式の交付による場合には、すでに発行されている上場株券等を移転させるものであるため、「売買等」に当たり、インサイダー取引規制の対象となっている。
このため、報告書では、組織再編は原則として株主によるチェックを経て実施されることなどを踏まえ、合併、会社分割、株式交換、事業譲渡を行う際に、その対価として行う自己株式の交付および交付された自己株式の取得については、新株発行を行う場合と同じく、インサイダー取引規制を適用しないこととしている(図表2参照)。
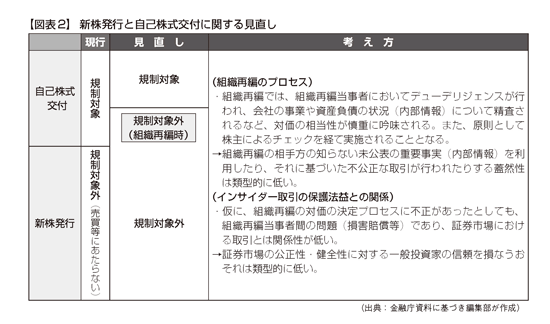
他社株TOB、TDnetによる開示で対象外に 他社株TOB(発行者以外の者による株券等の公開買付け)については、実務上、上場会社は取引所の適時開示ルールに基づき、TOB開始(公開買付届出書提出)前にTDnet(適時開示情報伝達システム)により、その決定事実または賛同表明を公表することが一般的とされている。
しかし、他社株TOBの場合、TDnetにより決定事実を公表しても、現行規定では、インサイダー取引規制上の公開買付け等事実の公表措置には該当しないため、当該公表後であってもアナリスト等へ説明ができない。
上場会社以外は上場会社との連名でOK このため、報告書では、公開買付者が上場会社である場合には、TDnetにより取引所への公開買付け等事実を通知することを公表措置として認めることとしている(図表3参照)。
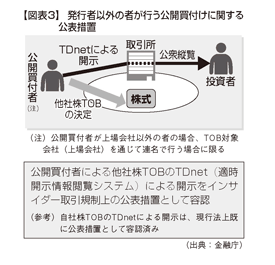
また、上場会社以外による他社株TOBについては、上場会社を通じた取引所への連名の通知・公衆縦覧がなされる場合には、当該措置を公表措置として認めることとしている。
なお、この点については、政令による改正が予定されている(本誌430号14頁参照)。
純粋持株会社の軽微基準は連結ベースで判断 そのほか、純粋持株会社の軽微基準も見直される。現行、純粋持株会社に係る合併等の軽微基準は売上高の10%未満などとされているが、純粋持株会社単体での売上等はグループ会社からの配当など、規模的には小さいものとなっている。
このため、グループ全体から見ると小規模なM&A等であっても重要事実に該当する場合があり、企業側から連結ベースで判断すべきとの要望が出ていたものである。
グループ会社からの収益が「80%以上」 報告書では、純粋持株会社の軽微基準については、連結ベースの計数を用いることとしている。
連結ベースの計数を用いる会社の範囲については、上場会社等の単体の売上高のうち、グループ会社からの収益(主として配当や経営指導料等)の占める割合が一定基準を上回る上場会社等を対象とすることし、その基準については、「80%以上」とすることが適当としている(図表4参照)。
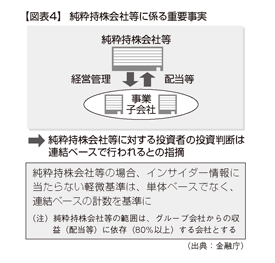
なお、この点については、内閣府令による改正が予定されている(本誌430号14頁参照)。
役員・社員だけでなく税理士・会計士なども対象に インサイダー取引規制では、①会社関係者(元会社関係者を含む)の関係者が、②上場会社等の業務等に関する重要事実を、③その者の職務等に関し知りながら、④当該重要事実が公表される前に、⑤当該上場会社等の株券等の売買等を行うこと(会社関係者から重要事実の伝達を受けた者が当該重要事実の公表前に売買等を行う場合を含む)を禁止している(金商法166条、公開買付者等関係者に関しては金商法167条)。
会社関係者とは、上場会社等の役員、社員、契約社員、派遣社員、アルバイト、パートタイマー等だけでなく、会計監査を行う公認会計士、増資の際の元引受証券会社、顧問弁護士、顧問税理士、コンサルティング会社など、幅広く対象となる。
たとえば、公開買付けでみれば、その関係者は、役員や社員だけでなく、公開買付けのFA(フィナンシャル・アドバイザー)となる証券会社、取引先、証券印刷会社、大株主(総株主の議決権または発行済株式数の3%以上を保有する株主等)なども対象となる(図表5参照)。
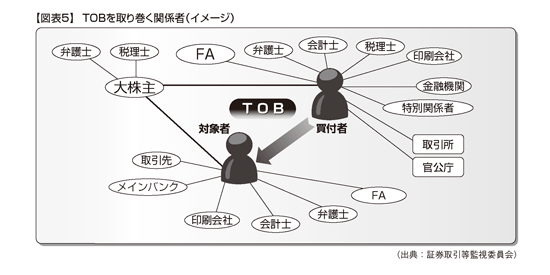
過去には税理士・会計士も課徴金対象に
また、インサイダー取引規制に違反した場合には、刑事罰(5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金またはこれらの併科など)または行政上の処分である課徴金の対象となる。
過去に税理士や公認会計士も課徴金による行政処分の対象となっている。税理士については、知人から公開買付けを行うという内部情報をもとに株式の売買を行ったものについて82万円の課徴金が課されている。また、公認会計士については、過去に2件課徴金の対象事案があり、いずれも監査上知りえた情報によるインサイダー取引である。課徴金による処分に加えて、2件とも金融庁から1年以上の業務停止処分を受けた。
税理士や公認会計士等は、会社の内部情報を知りうる立場にある者。税務や監査などだけでなく、インサイダー取引規制の対象となるかどうかなど、慎重な対応が求められることになる。
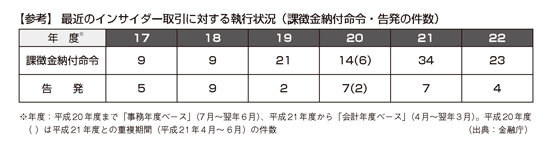
企業組織再編でインサイダー取引規制が変わる!
企業組織再編を行ううえで重要なのは何も税務上の「適格」「非適格」の判断や財産評価などだけではない。税理士や公認会計士が企業組織再編成に何らかの形で加わっている以上、インサイダー取引規制も是非とも覚えておきたいポイントの1つとなる。
金融審議会「インサイダー取引規制に関するワーキング・グループ」(座長:神田秀樹東京大学大学院法学政治学研究科教授)は12月15日、「企業グループ化に対応したインサイダー取引規制の見直しについて」と題する報告書を公表した(今号22頁参照)。報告書では、合併、会社分割、株式交換、事業譲渡を行う際に、その対価として行う自己株式の取得については新株発行と同様、インサイダー取引規制を適用しないなどとしている。今回の見直しは、企業が選択する組織再編の手段によってインサイダー取引規制の適用が異なるといった問題点などを調整するものであり、今後、インサイダー取引規制を考慮せず、組織再編が行いやすくなる。
なお、金融庁は来年の通常国会で金融商品取引法の一部改正案を提出する方針としている(本誌430号14頁参照)。
合併や会社分割の場合もインサイダー取引規制の対象に 金融審議会は今年3月の諮問を受けて「インサイダー取引規制に関するワーキング・グループ」を設置。企業組織再編など、グループ経営が一般化するなか、インサイダー取引規制が十分に対応していないなどの指摘を受け、7月8日から検討を行ってきたものだ。
今回公表された報告書でのポイントの1つは、企業の組織再編におけるインサイダー取引規制の適用関係を整理することにある。
企業が組織再編を行う際には、事業譲渡や合併、会社分割、株式交換等が主要な手段となる。現行のインサイダー取引規制は、上場株券等に係る売買等(金商法166条1項)を規制対象としているため、たとえば、事業譲渡は、個々の権利義務を承継させる行為(特定承継)であることから、金商法上の「売買等」に当たり、インサイダー取引規制の対象となる。
一方、合併や会社分割は権利義務を一括して承継させる行為(包括承継)であるため、「売買等」に当たらず、インサイダー取引規制の対象外となっている。
現状では、このように会社が選択する組織再編の手段によってインサイダー取引規制の適用関係が異なるという状況となっている。
上場株券20%未満等の3つのケースは除外 このため、報告書では、まず合併や会社分割により上場株券等を承継する場合についても、事業譲渡と同様に、インサイダー取引規制の対象とすることが適当としている(図表1参照)。そのうえで、インサイダー取引に利用される危険性が低いものと見込まれる3つのケースについては、適用除外とすることが適当とした。
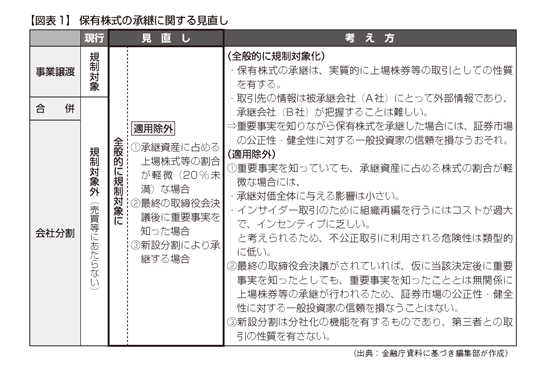
具体的には、①承継資産に占める上場株券等の割合が20%未満の場合、②最終の取締役会決議後に重要事実を知った場合、③新設分割による承継の場合については、インサイダー取引規制の対象外としている。
合併・会社分割等に伴う自己株取得は対象外に また、組織再編の対価として上場株券等を割り当てる場合の整理も行われる。現行、対価として新株発行を行う場合には、所有権の移転ではないため、「売買等」に当たらず、インサイダー取引規制の対象とならないが、自己株式の交付による場合には、すでに発行されている上場株券等を移転させるものであるため、「売買等」に当たり、インサイダー取引規制の対象となっている。
このため、報告書では、組織再編は原則として株主によるチェックを経て実施されることなどを踏まえ、合併、会社分割、株式交換、事業譲渡を行う際に、その対価として行う自己株式の交付および交付された自己株式の取得については、新株発行を行う場合と同じく、インサイダー取引規制を適用しないこととしている(図表2参照)。
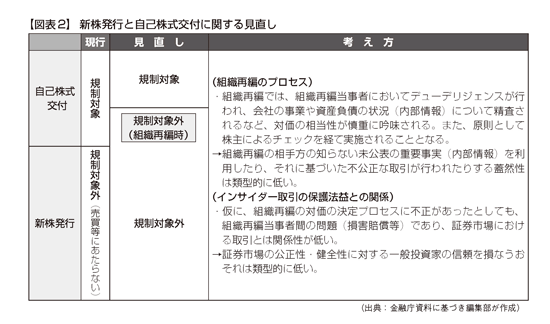
他社株TOB、TDnetによる開示で対象外に 他社株TOB(発行者以外の者による株券等の公開買付け)については、実務上、上場会社は取引所の適時開示ルールに基づき、TOB開始(公開買付届出書提出)前にTDnet(適時開示情報伝達システム)により、その決定事実または賛同表明を公表することが一般的とされている。
しかし、他社株TOBの場合、TDnetにより決定事実を公表しても、現行規定では、インサイダー取引規制上の公開買付け等事実の公表措置には該当しないため、当該公表後であってもアナリスト等へ説明ができない。
上場会社以外は上場会社との連名でOK このため、報告書では、公開買付者が上場会社である場合には、TDnetにより取引所への公開買付け等事実を通知することを公表措置として認めることとしている(図表3参照)。
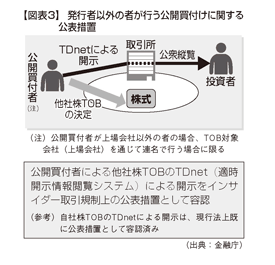
また、上場会社以外による他社株TOBについては、上場会社を通じた取引所への連名の通知・公衆縦覧がなされる場合には、当該措置を公表措置として認めることとしている。
なお、この点については、政令による改正が予定されている(本誌430号14頁参照)。
純粋持株会社の軽微基準は連結ベースで判断 そのほか、純粋持株会社の軽微基準も見直される。現行、純粋持株会社に係る合併等の軽微基準は売上高の10%未満などとされているが、純粋持株会社単体での売上等はグループ会社からの配当など、規模的には小さいものとなっている。
このため、グループ全体から見ると小規模なM&A等であっても重要事実に該当する場合があり、企業側から連結ベースで判断すべきとの要望が出ていたものである。
グループ会社からの収益が「80%以上」 報告書では、純粋持株会社の軽微基準については、連結ベースの計数を用いることとしている。
連結ベースの計数を用いる会社の範囲については、上場会社等の単体の売上高のうち、グループ会社からの収益(主として配当や経営指導料等)の占める割合が一定基準を上回る上場会社等を対象とすることし、その基準については、「80%以上」とすることが適当としている(図表4参照)。
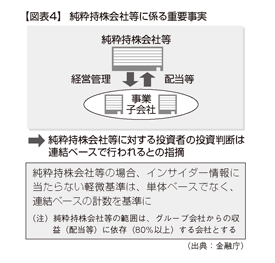
なお、この点については、内閣府令による改正が予定されている(本誌430号14頁参照)。
役員・社員だけでなく税理士・会計士なども対象に インサイダー取引規制では、①会社関係者(元会社関係者を含む)の関係者が、②上場会社等の業務等に関する重要事実を、③その者の職務等に関し知りながら、④当該重要事実が公表される前に、⑤当該上場会社等の株券等の売買等を行うこと(会社関係者から重要事実の伝達を受けた者が当該重要事実の公表前に売買等を行う場合を含む)を禁止している(金商法166条、公開買付者等関係者に関しては金商法167条)。
会社関係者とは、上場会社等の役員、社員、契約社員、派遣社員、アルバイト、パートタイマー等だけでなく、会計監査を行う公認会計士、増資の際の元引受証券会社、顧問弁護士、顧問税理士、コンサルティング会社など、幅広く対象となる。
たとえば、公開買付けでみれば、その関係者は、役員や社員だけでなく、公開買付けのFA(フィナンシャル・アドバイザー)となる証券会社、取引先、証券印刷会社、大株主(総株主の議決権または発行済株式数の3%以上を保有する株主等)なども対象となる(図表5参照)。
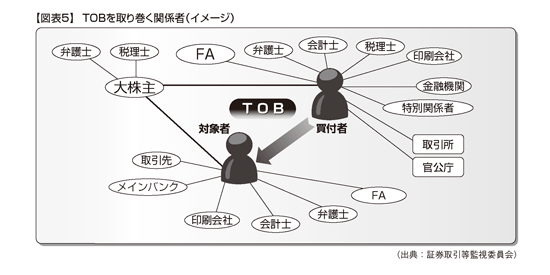
| >インサイダー取引規制の対象となる重要事実とは? |
| インサイダー取引規制の対象となる重要事実には、①増減資、株式分割、合併、事業提携、新製品企業化等の決定事実、②災害による損害、主要株主異動等の発生事実、③売上高、経常利益、純利益の予想値修正等の決算情報、④その他投資者の投資判断に著しい影響を与える事実(バスケット条項)がある(金商法166条2項)。 また、公開買付け等事実とは、公開買付けの実施、中止が該当する(金商法167条3項)。 |
過去に税理士や公認会計士も課徴金による行政処分の対象となっている。税理士については、知人から公開買付けを行うという内部情報をもとに株式の売買を行ったものについて82万円の課徴金が課されている。また、公認会計士については、過去に2件課徴金の対象事案があり、いずれも監査上知りえた情報によるインサイダー取引である。課徴金による処分に加えて、2件とも金融庁から1年以上の業務停止処分を受けた。
税理士や公認会計士等は、会社の内部情報を知りうる立場にある者。税務や監査などだけでなく、インサイダー取引規制の対象となるかどうかなど、慎重な対応が求められることになる。
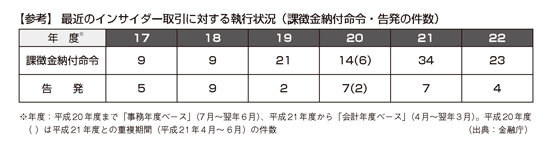
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
最近閲覧した記事
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -























