コラム2012年01月30日 【SCOPE】 グループ法人税制に伴う非上場株式の相続税評価(2012年1月30日号・№436)
国税庁、通達改正は行わず質疑応答事例で対応
グループ法人税制に伴う非上場株式の相続税評価
国税庁は、グループ法人税制に伴う取引相場のない株式の相続税評価に関する質疑応答事例を公表した。内容は、譲渡損益調整資産の譲渡益の繰延べ、現物分配などの取扱いについて。いずれも、法人税法の税務処理どおりの取扱いとなっている。なお、一部の実務家から、グループ法人税制に伴い、財産評価基本通達が改正されるのではないかとの声があがっていたが、国税庁は、財産評価基本通達の改正予定はないと回答している。
譲渡損益調整勘定の戻入益、「1株当たりの利益金額」から控除可
100%グループ法人間の譲渡損益は繰延べ 国税庁が公表した質疑応答事例は、類似業種比準方式の計算に関するものが中心となっている。取引相場のない株式の相続税評価の1つである類似業種比準方式は、評価会社と事業内容が類似する複数の上場会社の「1株当たりの利益金額」「1株当たりの配当金額」「1株当たりの純資産価額」の3つの要素を比準させて株価を求めるもの。
なお、株価の計算にあたり、財産評価基本通達では、利益計算の恣意性を排除することなどを理由に「1株当たりの利益金額」には、法人税法の課税所得金額が用いられる。また、評価会社の経常的収益力を株価に反映させるため、固定資産売却益等の非経常的な利益は、「1株当たりの利益金額」から控除することとされている。
ここで問題となっていたのは、グループ法人税制の導入で創設された譲渡損益調整資産(簿価1,000万円以上の固定資産、土地、有価証券等)の譲渡にともなう譲渡損益調整勘定の「戻入益」が、非経常的な利益として、「1株当たりの利益金額」から控除できるかどうかであった。
戻入益は非経常的な利益に該当 グループ法人税制の導入により、完全支配関係がある内国法人間において、譲渡損益調整資産の譲渡取引を行った場合、発生した譲渡益は繰り延べられることとなる。その後、完全支配関係がある法人(譲受法人)において、その譲渡損益調整資産を他に再譲渡した場合や減価償却した場合には、繰り延べられていた譲渡益の全部または一部が譲渡損益調整勘定の戻入益として、法人税の課税所得金額に計上される(図参照)。
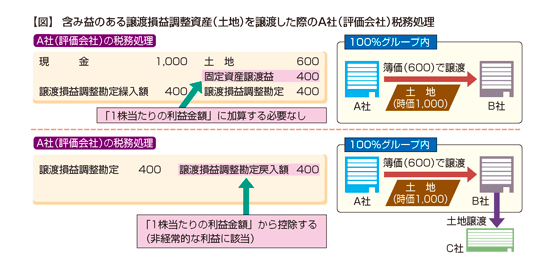
この譲渡益の戻入益の取扱いについて、国税庁は、質疑応答事例において、「1株当たりの利益金額」の計算上、非経常的な利益として控除できることを明確化している。戻入益は、財産評価基本通達183(2)が規定する非経常的な利益の金額に該当するとの見解だ。
なお、通常、固定資産譲渡益は、非経常的な利益として「1株当たりの利益金額」から控除される。しかし、グループ法人税制の適用を受ける場合、固定資産譲渡益は、譲渡損益調整勘定繰入額(損金)と相殺されるため、益金のマイナス要因として既に法人税の課税所得金額に織れ込まれていることに留意が必要だ。
譲渡損のケースで株価に相違が 含み損のある固定資産を譲渡した場合、グループ法人税制の適用を受けない評価会社は、固定資産譲渡損の損金算入により「1株当たりの利益金額」は低くなる。一方、グループ法人税制の適用を受ける評価会社は、譲渡損がなかったものとされるため、固定資産譲渡損と譲渡損益調整勘定繰入額(益金)が相殺されることとなる。つまりは、譲渡を行った事業年度でみると、グループ法人税制の適用を受ける評価会社は、適用を受けない評価会社に比べて株価が高く評価されることとなる。法人を利用した資産税のタックスプランニングを策定する際は、グループ法人税制の税務処理を常に考慮する必要がありそうだ。
現物分配、適格現物分配、寄附修正についても質疑応答事例を公表
法人税法の税務処理どおりの取扱い また、国税庁は、グループ法人税制で導入された「現物分配」「適格現物分配」「寄附修正事由が生じる場合の利益積立金の加減算」に関する質疑応答事例も公表している。具体的には、現物分配により評価会社に移転した資産の価額が「1株当たりの配当金額」に含まれるか否かは、その配当が将来毎期継続することが予想できるか否かにより判断することが明らかにされている。また、適格現物分配では、資産移転により受けた収益の額(法法62条の5④により益金不算入)は、「1株当たりに利益金額」の計算上、原則として「益金に算入されなかった剰余金の配当等」の金額に加算する必要はないとしている。さらに、寄附修正事由が生じるケースでは、完全支配関係にある法人間の寄附に伴う税務調整により、評価会社である親法人の利益積立金額が増減する場合でも、株式評価上、その利益積立金額の増減についての調整は必要はないとしている。いずれも、法人税法上の税務処理どおりの取扱いとなっている。
グループ法人税制に伴う非上場株式の相続税評価
国税庁は、グループ法人税制に伴う取引相場のない株式の相続税評価に関する質疑応答事例を公表した。内容は、譲渡損益調整資産の譲渡益の繰延べ、現物分配などの取扱いについて。いずれも、法人税法の税務処理どおりの取扱いとなっている。なお、一部の実務家から、グループ法人税制に伴い、財産評価基本通達が改正されるのではないかとの声があがっていたが、国税庁は、財産評価基本通達の改正予定はないと回答している。
譲渡損益調整勘定の戻入益、「1株当たりの利益金額」から控除可
100%グループ法人間の譲渡損益は繰延べ 国税庁が公表した質疑応答事例は、類似業種比準方式の計算に関するものが中心となっている。取引相場のない株式の相続税評価の1つである類似業種比準方式は、評価会社と事業内容が類似する複数の上場会社の「1株当たりの利益金額」「1株当たりの配当金額」「1株当たりの純資産価額」の3つの要素を比準させて株価を求めるもの。
なお、株価の計算にあたり、財産評価基本通達では、利益計算の恣意性を排除することなどを理由に「1株当たりの利益金額」には、法人税法の課税所得金額が用いられる。また、評価会社の経常的収益力を株価に反映させるため、固定資産売却益等の非経常的な利益は、「1株当たりの利益金額」から控除することとされている。
ここで問題となっていたのは、グループ法人税制の導入で創設された譲渡損益調整資産(簿価1,000万円以上の固定資産、土地、有価証券等)の譲渡にともなう譲渡損益調整勘定の「戻入益」が、非経常的な利益として、「1株当たりの利益金額」から控除できるかどうかであった。
戻入益は非経常的な利益に該当 グループ法人税制の導入により、完全支配関係がある内国法人間において、譲渡損益調整資産の譲渡取引を行った場合、発生した譲渡益は繰り延べられることとなる。その後、完全支配関係がある法人(譲受法人)において、その譲渡損益調整資産を他に再譲渡した場合や減価償却した場合には、繰り延べられていた譲渡益の全部または一部が譲渡損益調整勘定の戻入益として、法人税の課税所得金額に計上される(図参照)。
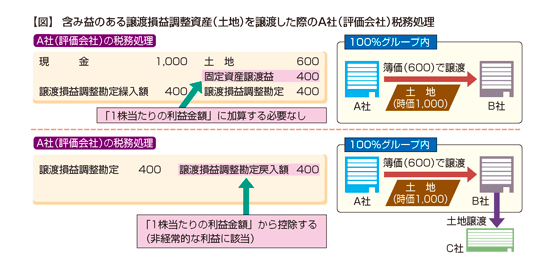
この譲渡益の戻入益の取扱いについて、国税庁は、質疑応答事例において、「1株当たりの利益金額」の計算上、非経常的な利益として控除できることを明確化している。戻入益は、財産評価基本通達183(2)が規定する非経常的な利益の金額に該当するとの見解だ。
なお、通常、固定資産譲渡益は、非経常的な利益として「1株当たりの利益金額」から控除される。しかし、グループ法人税制の適用を受ける場合、固定資産譲渡益は、譲渡損益調整勘定繰入額(損金)と相殺されるため、益金のマイナス要因として既に法人税の課税所得金額に織れ込まれていることに留意が必要だ。
譲渡損のケースで株価に相違が 含み損のある固定資産を譲渡した場合、グループ法人税制の適用を受けない評価会社は、固定資産譲渡損の損金算入により「1株当たりの利益金額」は低くなる。一方、グループ法人税制の適用を受ける評価会社は、譲渡損がなかったものとされるため、固定資産譲渡損と譲渡損益調整勘定繰入額(益金)が相殺されることとなる。つまりは、譲渡を行った事業年度でみると、グループ法人税制の適用を受ける評価会社は、適用を受けない評価会社に比べて株価が高く評価されることとなる。法人を利用した資産税のタックスプランニングを策定する際は、グループ法人税制の税務処理を常に考慮する必要がありそうだ。
現物分配、適格現物分配、寄附修正についても質疑応答事例を公表
法人税法の税務処理どおりの取扱い また、国税庁は、グループ法人税制で導入された「現物分配」「適格現物分配」「寄附修正事由が生じる場合の利益積立金の加減算」に関する質疑応答事例も公表している。具体的には、現物分配により評価会社に移転した資産の価額が「1株当たりの配当金額」に含まれるか否かは、その配当が将来毎期継続することが予想できるか否かにより判断することが明らかにされている。また、適格現物分配では、資産移転により受けた収益の額(法法62条の5④により益金不算入)は、「1株当たりに利益金額」の計算上、原則として「益金に算入されなかった剰余金の配当等」の金額に加算する必要はないとしている。さらに、寄附修正事由が生じるケースでは、完全支配関係にある法人間の寄附に伴う税務調整により、評価会社である親法人の利益積立金額が増減する場合でも、株式評価上、その利益積立金額の増減についての調整は必要はないとしている。いずれも、法人税法上の税務処理どおりの取扱いとなっている。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -

Copyright (C) 2019
SHINNIPPON-HOKI PUBLISHING CO.,LTD.




















