解説記事2012年04月02日 【実務解説】 過年度遡及会計基準適用後の連結財務諸表・財務諸表の作成にあたっての留意事項(下)(2012年4月2日号・№445)
過年度遡及会計基準適用後の連結財務諸表・財務諸表の作成にあたっての留意事項(下)
金融庁総務企画局企業開示課課長補佐 徳重昌宏
金融庁総務企画局企業開示課専門官 中村慎二
Ⅰ はじめに
「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」(平成21年12月4日公表。以下「過年度遡及会計基準」という)の公表を踏まえ、平成22年9月30日に「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」(平成22年内閣府令第45号)が公布され、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「財務諸表等規則」という)等に遡及適用(新たな会計方針を前事業年度以前の財務諸表に遡って適用としたと仮定して会計処理を行うこと。財務諸表等規則8条51項)および財務諸表の組替え(新たな表示方法を前事業年度以前の財務諸表に遡って適用したと仮定して表示を変更すること。財務諸表等規則8条52項)等が規定された。
併せて「企業内容等の開示に関する留意事項について」(以下「企業内容等開示ガイドライン」という)に5-12-2の規定が新設され、財務諸表に係る遡及適用等と【主要な経営指標等の推移】に記載される主要な経営指標等との関係が規定された。
本稿は、有価証券報告書作成にあたって求められる取扱いについて、財務諸表に記載される数値と主要な経営指標等の推移に記載される数値に関する留意事項を中心に解説するものであるが、文中意見にわたる部分については筆者らの個人的な見解であることをあらかじめお断りしておく(比較情報(注記関連)の作成にあたっては、本稿(上)本誌444号22頁を参照されたい)。
Ⅱ 主要な経営指標等の記載にあたっての留意事項
今般の改正により、企業内容等開示ガイドライン5-12-2において「遡及適用等は最近連結会計年度の直前連結会計年度及び最近事業年度の直前事業年度に係る主要な経営指標等について行わなければならないことに留意する」旨を規定し、遡及適用等と主要な経営指標等との関係が整理された(表1参照)。
ただし、前事業年度に係る主要な経営指標等には、売上高、経常利益金額、当期純利益金額等、会計方針の変更等が行われた場合に遡及適用等が求められる場合が考えられる数値と資本金等、遡及適用等の影響を受けないと考えられる数値が混在していることから、前事業年度に係る主要な経営指標等のすべてについて遡及適用等の後の数値を記載することが求められるのか、一部、遡及適用等を考慮しない数値を記載することが求められるのかが明確ではないとの指摘があった。
これを踏まえ、本稿では、前事業年度に係る主要な経営指標等の数値の記載にあたっての考え方を示し、遡及適用等が求められない数値があることを個々の経営指標ごとに解説することとする(後述1および2を踏まえた前事業年度の主要な経営指標等の記載については表2参照)。
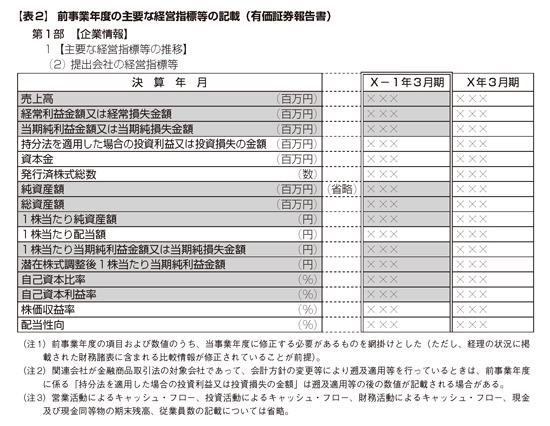
なお、以下では提出会社における主要な経営指標等を引用することとするが、連結会計年度に係る主要な経営指標等についても考え方は同様である。また、有価証券報告書に記載される【主要な経営指標等の推移】の記載については、開示府令第三号様式記載上の注意(5)において、同令第二号様式記載上の注意(25)に準じて記載することとされていることから、第二号様式記載上の注意(25)の規定を直接引用することとする。
1 遡及適用等の影響を受ける前事業年度の主要な経営指標等について 主要な経営指標等の数値の多くは、財務諸表(注記を含む。以下同じ)に記載された数値から転記されるものであることから、財務諸表に含まれる比較情報について遡及適用等の後の数値が記載されている場合には、当該数値がそのまま前事業年度の主要な経営指標等に記載されるものと考えられる。
したがって、主要な経営指標等のうち、(財務諸表の比較情報について遡及適用等が行われたことを前提に)遡及適用等の後の数値が記載されるのは売上高、経常利益金額、当期純利益金額、純資産額、総資産額、1株当たり純資産額、1株当たり当期純利益金額、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額、自己資本比率、自己資本利益率、営業活動によるキャッシュ・フロー、投資活動によるキャッシュ・フロー、財務活動によるキャッシュ・フロー、現金及び現金同等物の期末残高となる(開示府令第二号様式記載上の注意(25)b(提出会社の最近5事業年度に係る主要な経営指標等)(a)~(c)、(g)~(i)、(k)~(n)、(q)~(t))。
上記のように主要な経営指標等に記載された数値と財務諸表に記載された数値が一致していることが原則であることを踏まえると、企業内容等開示ガイドライン5-12-2において、直前事業年度に係る主要な経営指標等について遡及適用等が求められるのは、財務諸表において遡及適用等が行われた数値であると解することが適当であり、財務諸表で遡及適用等が行われていない数値および財務諸表に記載されていない数値については別途検討されるべきものと考えられる。
なお、企業内容等開示ガイドライン5-12-2では、財務諸表等規則8条51項等(連結財務諸表規則2条34号)の規定による遡及適用等、すなわち会計方針の変更に係る遡及適用等に限定しており、1株当たり当期純利益金額に係る前事業年度数値の修正、すなわち当事業年度または貸借対照表日後に株式分割または株式併合(以下「株式分割等」という)が行われた場合に前事業年度の期首に株式分割等が行われたと仮定して前事業年度の1株当たり当期純利益金額を比較情報として財務諸表に注記を求める規定(財務諸表等規則95条の5の2、連結財務諸表規則65条の2)については言及されていない。
しかしながら、当該規定の根拠となる「1株当たり当期純利益に関する会計基準」(企業会計基準委員会)の規定が過年度遡及会計基準の導入に伴って改正されたものであること、前事業年度の数値を遡及して修正する処理は、財務諸表等規則8条51項の遡及適用等と変わるものではなく、また、財務諸表に注記された数値はそのまま主要な経営指標等に転記することが通常であることから、主要な経営指標等に記載される1株当たり当期純利益金額の前事業年度の数値についても、比較情報が遡及して修正されている場合には遡及修正後の数値が当期の財務諸表から当然に転記されるものと考えられる。なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額や1株当たり当期純資産額の注記についても同様である(財務諸表等規則95条の5の3、68条の4、連結財務諸表規則65条の3、44条の2)。
2 遡及適用等の影響を受けない前事業年度の主要な経営指標等について 次に、企業内容等開示ガイドライン5-12-2における遡及適用等の対象とはならないと考えられる経営指標等について検討を行う。
資本金、発行済株式総数、1株当たり配当額、株価収益率、配当性向(開示府令第二号様式記載上の注意(25)b(e)(f)(j)(o)(p))については、遡及適用等とは関係なく前年に提出済みの有価証券報告書に記載された数値をそのまま記載することが適当であると考えられる。
なお、前事業年度の持分法を適用した場合の投資利益の金額(同記載上の注意(25)b(d))については、持分法適用の範囲の変更が会計方針の変更には該当せず、持分法適用の範囲の変更があった場合でも比較情報の数値を変更することにはならないため、基本的には資本金等と同様、前事業年度の数値を記載することが適当であると考えられる。
ただし、関連会社が金融商品取引法に基づく開示を行っている場合、すなわち過年度遡及会計基準の適用による前事業年度の数値に対する遡及適用等が義務付けられる場合であって、当該関連会社が会計方針の変更等により当期純利益に影響を及ぼすような遡及適用等を行っているときは、有価証券報告書提出会社は、当事業年度の財務諸表に含まれる比較情報の記載において前事業年度の持分法を適用した場合の投資利益の金額を遡及適用後の数値で記載することが考えられる。
この場合には、主要な経営指標等の前事業年度の持分法を適用した場合の投資利益の金額についても遡及適用等の後の金額が記載されるものと考えられる。なお、関連会社の遡及適用等に係る会計処理を有価証券報告書提出会社の財務諸表に反映するかどうかについては、有価証券報告書提出会社にとっての当該会計処理の重要性も勘案されるものと考えられる。
(1)資本金および発行済株式総数 前事業年度の資本金および発行済株式総数については、遡及適用等の考え方がなじまないこと、【発行済株式】【発行済株式総数、資本金等の推移】の項に記載された数値と異なる数値が記載されると財務諸表利用者の誤解を招くおそれもあることから、前事業年度の数値をそのまま記載することが適当であると考えられる。
(2)1株当たり配当額、株価収益率および配当性向 前事業年度の1株当たり配当額、株価収益率および配当性向に関して、まず、前事業年度の1株当たり配当額については、株式分割等が行われた場合に、1株当たり当期純利益金額の算定にあたり前事業年度の期首に株式分割等が行われたと仮定して計算することと同様の方法により算定することが考えられる。
しかしながら、配当に関する注記(財務諸表等規則109条)において1株当たり配当額については遡及修正が求められていないこと、当該注記や【配当政策】の項に記載された数値と異なる数値が記載されると財務諸表利用者の誤解を招くおそれもあることから、前事業年度の数値をそのまま記載することが適当であると考えられる。
前事業年度の株価収益率(貸借対照表日における株価を1株当たり当期純利益金額で除した割合)については、株式分割等が前事業年度の期首に行われたと仮定した場合の株価を算定することは困難であると考えられることから、分母の数値(1株当たり当期純利益金額)についても遡及修正とは関係のない前事業年度の数値を使用することが適当であると考えられる。
また、前事業年度の配当性向(1株当たり配当額を1株当たり当期純利益金額で除した割合)については、財務諸表注記において1株当たり当期純利益金額は遡及修正後の数値で記載されることを踏まえると、配当性向の算定に使用する1株当たり当期純利益金額についても遡及修正後の数値を使用することが考えられる。
しかしながら、1株当たり配当額は遡及修正とは関係のない前事業年度の数値で財務諸表に注記されていることを踏まえると、遡及修正前の数値(1株当たり配当額)を遡及修正後の数値(1株当たり当期純利益金額)で除した値に意味はないことから、配当性向の算定にあたって使用する1株当たり当期純利益金額は遡及修正前の前事業年度の数値と考えることが適当である。
仮に当事業年度の財務諸表に含まれる比較情報について当期純利益金額が遡及修正後の数値となっている場合においても、株価収益率や配当性向を算定する際に使用する1株当たり当期純利益金額については、遡及修正前の数値を使用することが適当であると考えられる。すなわち、1株当たり当期純利益金額自体の数値は遡及修正の対象となるが、当該数値を使用して別の指標(株価収益率や配当性向)を算定する際には、当該別の指標を算定する際に使用する他の数値(株価や1株当たり配当額)が遡及修正されているのかいないかを考慮し、(遡及修正の有無に関して)同じ性質の数値を使用する必要があると考えられる。
その結果、開示府令第二号様式記載上の注意(25)b(k)における1株当たり当期純利益金額と同(o)の株価収益率や同(p)の配当性向の算定にあたって使用される1株当たり当期純利益金額は異なる数値となることがあり得る。
なお、遡及修正後の数値の記載が求められない指標のうち、遡及修正が可能なものについては、遡及修正を行った旨を記載し、遡及修正後の数値を欄外に記載することを妨げるものではないと考えられる。
Ⅲ そ の 他
過年度遡及会計基準の公表を踏まえ、財務諸表等規則等において、会計上の見積りの変更に関する注記(財務諸表等規則8条の3の5、連結財務諸表規則14条の6)、会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区別することが困難な場合の注記(財務諸表等規則8条の3の6、連結財務諸表規則14条の7)の規定が新設された。これらの規定に関し、平成23年3月31日に公表された「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」(平成23年内閣府令第10号)と併せて改正財務諸表等規則ガイドライン(8の3の5-3)および改正連結財務諸表規則ガイドライン(14-6)が規定された。なお、連結財務諸表規則および同ガイドラインの規定は財務諸表等規則および同ガイドラインの準用規定であることから、財務諸表等規則および同ガイドラインの規定を引用することとする。
連結財務諸表規則14条の6において準用する財務諸表等規則8条の3の5は、会計上の見積りの変更を行った場合に、当該変更が(当事業年度の)財務諸表に与えている影響額(同条2号)および翌事業年度以降の財務諸表に与えている影響額(同条3号イ。合理的に見積ることができる場合に限る)の注記を求めている。すなわち、会計上の見積りの変更が当事業年度および翌事業年度以降の財務諸表に影響を与えている場合には、当事業年度の財務諸表に与える影響額だけでなく、翌事業年度以降の財務諸表に与える影響額の注記が必要となる。
他方、過年度遡及会計基準18項(2)は、会計上の見積りの変更が当事業年度に影響を及ぼす場合は当事業年度への影響額、当事業年度への影響がない場合でも将来の期間に影響を及ぼす場合には当該影響額(合理的に見積ることができる場合に限る)の注記を求めている(表3参照)が、会計上の見積りの変更が当事業年度および翌事業年度以降に影響を及ぼす場合における翌事業年度以降の影響額の記載の有無が明らかではない。
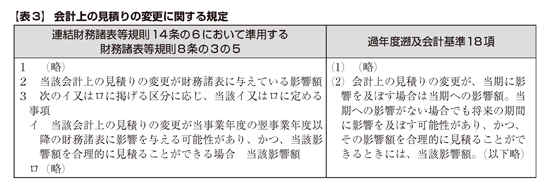 したがって、財務諸表等規則8条の3の5の規定と過年度遡及会計基準18項(2)の規定との間に齟齬が生じている可能性があった。そのため、前記のとおり、平成23年3月31日付で財務諸表等規則ガイドライン8の3の5-3および連結財務諸表規則ガイドライン14-6が新設され、財務諸表等規則8条の3の5(3号イ)および連結財務諸表規則14条の6、財務諸表等規則8条の3の6(4号イ)および連結財務諸表規則14条の7の規定が明確化されたことにより、これらの規定と過年度遡及会計基準18項(2)の規定は実質的には異ならないことが明確にされた。
したがって、財務諸表等規則8条の3の5の規定と過年度遡及会計基準18項(2)の規定との間に齟齬が生じている可能性があった。そのため、前記のとおり、平成23年3月31日付で財務諸表等規則ガイドライン8の3の5-3および連結財務諸表規則ガイドライン14-6が新設され、財務諸表等規則8条の3の5(3号イ)および連結財務諸表規則14条の6、財務諸表等規則8条の3の6(4号イ)および連結財務諸表規則14条の7の規定が明確化されたことにより、これらの規定と過年度遡及会計基準18項(2)の規定は実質的には異ならないことが明確にされた。
会計上の見積りの変更が当事業年度および翌事業年度以降の財務諸表に影響を及ぼす場合(重要性が乏しい場合を除く)に、無条件に翌事業年度以降の連結財務諸表に与える影響額の記載を要しないとすることは財務諸表利用者の保護の観点から困難である。
しかしながら、当事業年度の財務諸表に与えている影響額に基づき、翌事業年度以降の財務諸表に与える影響の概要を財務諸表利用者が把握できる場合には、利用者の保護上問題がないと考えられる。そこで、利用者が翌事業年度以降の財務諸表に与える影響額の概要を把握できる場合を重要性が乏しい場合に該当するものとして、翌事業年度以降の財務諸表に与える影響額の注記を省略できることがガイドライン上明確にされた。
過年度遡及会計基準40項において、会計上の見積りの変更の事例として、有形固定資産の耐用年数の変更が挙げられている。耐用年数の変更は、通常、当事業年度だけでなく翌事業年度以降の財務諸表に影響を及ぼすと考えられるが、当事業年度の財務諸表に与えている影響額の注記により、翌事業年度以降の財務諸表に与える影響の概要を把握できるケースに該当する場合が考えられ、その場合には翌事業年度以降の財務諸表に与える影響額の注記の省略が認められるものと考えられる。
なお、前記のとおり、連結財務諸表規則14条の7において準用する財務諸表等規則8条の3の6(会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区別することが困難な場合の注記。減価償却方法の変更の場合等が考えられる)4号イも同様と考えられる。
金融庁総務企画局企業開示課課長補佐 徳重昌宏
金融庁総務企画局企業開示課専門官 中村慎二
Ⅰ はじめに
「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」(平成21年12月4日公表。以下「過年度遡及会計基準」という)の公表を踏まえ、平成22年9月30日に「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」(平成22年内閣府令第45号)が公布され、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「財務諸表等規則」という)等に遡及適用(新たな会計方針を前事業年度以前の財務諸表に遡って適用としたと仮定して会計処理を行うこと。財務諸表等規則8条51項)および財務諸表の組替え(新たな表示方法を前事業年度以前の財務諸表に遡って適用したと仮定して表示を変更すること。財務諸表等規則8条52項)等が規定された。
併せて「企業内容等の開示に関する留意事項について」(以下「企業内容等開示ガイドライン」という)に5-12-2の規定が新設され、財務諸表に係る遡及適用等と【主要な経営指標等の推移】に記載される主要な経営指標等との関係が規定された。
本稿は、有価証券報告書作成にあたって求められる取扱いについて、財務諸表に記載される数値と主要な経営指標等の推移に記載される数値に関する留意事項を中心に解説するものであるが、文中意見にわたる部分については筆者らの個人的な見解であることをあらかじめお断りしておく(比較情報(注記関連)の作成にあたっては、本稿(上)本誌444号22頁を参照されたい)。
Ⅱ 主要な経営指標等の記載にあたっての留意事項
今般の改正により、企業内容等開示ガイドライン5-12-2において「遡及適用等は最近連結会計年度の直前連結会計年度及び最近事業年度の直前事業年度に係る主要な経営指標等について行わなければならないことに留意する」旨を規定し、遡及適用等と主要な経営指標等との関係が整理された(表1参照)。
| 【表1】企業内容等開示ガイドライン5-12-2 |
|
ただし、前事業年度に係る主要な経営指標等には、売上高、経常利益金額、当期純利益金額等、会計方針の変更等が行われた場合に遡及適用等が求められる場合が考えられる数値と資本金等、遡及適用等の影響を受けないと考えられる数値が混在していることから、前事業年度に係る主要な経営指標等のすべてについて遡及適用等の後の数値を記載することが求められるのか、一部、遡及適用等を考慮しない数値を記載することが求められるのかが明確ではないとの指摘があった。
これを踏まえ、本稿では、前事業年度に係る主要な経営指標等の数値の記載にあたっての考え方を示し、遡及適用等が求められない数値があることを個々の経営指標ごとに解説することとする(後述1および2を踏まえた前事業年度の主要な経営指標等の記載については表2参照)。
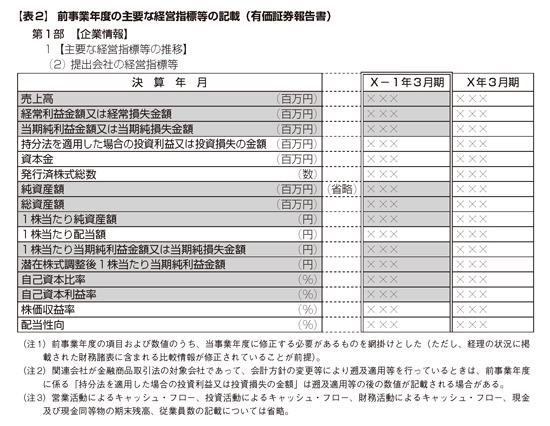
なお、以下では提出会社における主要な経営指標等を引用することとするが、連結会計年度に係る主要な経営指標等についても考え方は同様である。また、有価証券報告書に記載される【主要な経営指標等の推移】の記載については、開示府令第三号様式記載上の注意(5)において、同令第二号様式記載上の注意(25)に準じて記載することとされていることから、第二号様式記載上の注意(25)の規定を直接引用することとする。
1 遡及適用等の影響を受ける前事業年度の主要な経営指標等について 主要な経営指標等の数値の多くは、財務諸表(注記を含む。以下同じ)に記載された数値から転記されるものであることから、財務諸表に含まれる比較情報について遡及適用等の後の数値が記載されている場合には、当該数値がそのまま前事業年度の主要な経営指標等に記載されるものと考えられる。
したがって、主要な経営指標等のうち、(財務諸表の比較情報について遡及適用等が行われたことを前提に)遡及適用等の後の数値が記載されるのは売上高、経常利益金額、当期純利益金額、純資産額、総資産額、1株当たり純資産額、1株当たり当期純利益金額、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額、自己資本比率、自己資本利益率、営業活動によるキャッシュ・フロー、投資活動によるキャッシュ・フロー、財務活動によるキャッシュ・フロー、現金及び現金同等物の期末残高となる(開示府令第二号様式記載上の注意(25)b(提出会社の最近5事業年度に係る主要な経営指標等)(a)~(c)、(g)~(i)、(k)~(n)、(q)~(t))。
上記のように主要な経営指標等に記載された数値と財務諸表に記載された数値が一致していることが原則であることを踏まえると、企業内容等開示ガイドライン5-12-2において、直前事業年度に係る主要な経営指標等について遡及適用等が求められるのは、財務諸表において遡及適用等が行われた数値であると解することが適当であり、財務諸表で遡及適用等が行われていない数値および財務諸表に記載されていない数値については別途検討されるべきものと考えられる。
なお、企業内容等開示ガイドライン5-12-2では、財務諸表等規則8条51項等(連結財務諸表規則2条34号)の規定による遡及適用等、すなわち会計方針の変更に係る遡及適用等に限定しており、1株当たり当期純利益金額に係る前事業年度数値の修正、すなわち当事業年度または貸借対照表日後に株式分割または株式併合(以下「株式分割等」という)が行われた場合に前事業年度の期首に株式分割等が行われたと仮定して前事業年度の1株当たり当期純利益金額を比較情報として財務諸表に注記を求める規定(財務諸表等規則95条の5の2、連結財務諸表規則65条の2)については言及されていない。
しかしながら、当該規定の根拠となる「1株当たり当期純利益に関する会計基準」(企業会計基準委員会)の規定が過年度遡及会計基準の導入に伴って改正されたものであること、前事業年度の数値を遡及して修正する処理は、財務諸表等規則8条51項の遡及適用等と変わるものではなく、また、財務諸表に注記された数値はそのまま主要な経営指標等に転記することが通常であることから、主要な経営指標等に記載される1株当たり当期純利益金額の前事業年度の数値についても、比較情報が遡及して修正されている場合には遡及修正後の数値が当期の財務諸表から当然に転記されるものと考えられる。なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額や1株当たり当期純資産額の注記についても同様である(財務諸表等規則95条の5の3、68条の4、連結財務諸表規則65条の3、44条の2)。
2 遡及適用等の影響を受けない前事業年度の主要な経営指標等について 次に、企業内容等開示ガイドライン5-12-2における遡及適用等の対象とはならないと考えられる経営指標等について検討を行う。
資本金、発行済株式総数、1株当たり配当額、株価収益率、配当性向(開示府令第二号様式記載上の注意(25)b(e)(f)(j)(o)(p))については、遡及適用等とは関係なく前年に提出済みの有価証券報告書に記載された数値をそのまま記載することが適当であると考えられる。
なお、前事業年度の持分法を適用した場合の投資利益の金額(同記載上の注意(25)b(d))については、持分法適用の範囲の変更が会計方針の変更には該当せず、持分法適用の範囲の変更があった場合でも比較情報の数値を変更することにはならないため、基本的には資本金等と同様、前事業年度の数値を記載することが適当であると考えられる。
ただし、関連会社が金融商品取引法に基づく開示を行っている場合、すなわち過年度遡及会計基準の適用による前事業年度の数値に対する遡及適用等が義務付けられる場合であって、当該関連会社が会計方針の変更等により当期純利益に影響を及ぼすような遡及適用等を行っているときは、有価証券報告書提出会社は、当事業年度の財務諸表に含まれる比較情報の記載において前事業年度の持分法を適用した場合の投資利益の金額を遡及適用後の数値で記載することが考えられる。
この場合には、主要な経営指標等の前事業年度の持分法を適用した場合の投資利益の金額についても遡及適用等の後の金額が記載されるものと考えられる。なお、関連会社の遡及適用等に係る会計処理を有価証券報告書提出会社の財務諸表に反映するかどうかについては、有価証券報告書提出会社にとっての当該会計処理の重要性も勘案されるものと考えられる。
(1)資本金および発行済株式総数 前事業年度の資本金および発行済株式総数については、遡及適用等の考え方がなじまないこと、【発行済株式】【発行済株式総数、資本金等の推移】の項に記載された数値と異なる数値が記載されると財務諸表利用者の誤解を招くおそれもあることから、前事業年度の数値をそのまま記載することが適当であると考えられる。
(2)1株当たり配当額、株価収益率および配当性向 前事業年度の1株当たり配当額、株価収益率および配当性向に関して、まず、前事業年度の1株当たり配当額については、株式分割等が行われた場合に、1株当たり当期純利益金額の算定にあたり前事業年度の期首に株式分割等が行われたと仮定して計算することと同様の方法により算定することが考えられる。
しかしながら、配当に関する注記(財務諸表等規則109条)において1株当たり配当額については遡及修正が求められていないこと、当該注記や【配当政策】の項に記載された数値と異なる数値が記載されると財務諸表利用者の誤解を招くおそれもあることから、前事業年度の数値をそのまま記載することが適当であると考えられる。
前事業年度の株価収益率(貸借対照表日における株価を1株当たり当期純利益金額で除した割合)については、株式分割等が前事業年度の期首に行われたと仮定した場合の株価を算定することは困難であると考えられることから、分母の数値(1株当たり当期純利益金額)についても遡及修正とは関係のない前事業年度の数値を使用することが適当であると考えられる。
また、前事業年度の配当性向(1株当たり配当額を1株当たり当期純利益金額で除した割合)については、財務諸表注記において1株当たり当期純利益金額は遡及修正後の数値で記載されることを踏まえると、配当性向の算定に使用する1株当たり当期純利益金額についても遡及修正後の数値を使用することが考えられる。
しかしながら、1株当たり配当額は遡及修正とは関係のない前事業年度の数値で財務諸表に注記されていることを踏まえると、遡及修正前の数値(1株当たり配当額)を遡及修正後の数値(1株当たり当期純利益金額)で除した値に意味はないことから、配当性向の算定にあたって使用する1株当たり当期純利益金額は遡及修正前の前事業年度の数値と考えることが適当である。
仮に当事業年度の財務諸表に含まれる比較情報について当期純利益金額が遡及修正後の数値となっている場合においても、株価収益率や配当性向を算定する際に使用する1株当たり当期純利益金額については、遡及修正前の数値を使用することが適当であると考えられる。すなわち、1株当たり当期純利益金額自体の数値は遡及修正の対象となるが、当該数値を使用して別の指標(株価収益率や配当性向)を算定する際には、当該別の指標を算定する際に使用する他の数値(株価や1株当たり配当額)が遡及修正されているのかいないかを考慮し、(遡及修正の有無に関して)同じ性質の数値を使用する必要があると考えられる。
その結果、開示府令第二号様式記載上の注意(25)b(k)における1株当たり当期純利益金額と同(o)の株価収益率や同(p)の配当性向の算定にあたって使用される1株当たり当期純利益金額は異なる数値となることがあり得る。
なお、遡及修正後の数値の記載が求められない指標のうち、遡及修正が可能なものについては、遡及修正を行った旨を記載し、遡及修正後の数値を欄外に記載することを妨げるものではないと考えられる。
Ⅲ そ の 他
過年度遡及会計基準の公表を踏まえ、財務諸表等規則等において、会計上の見積りの変更に関する注記(財務諸表等規則8条の3の5、連結財務諸表規則14条の6)、会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区別することが困難な場合の注記(財務諸表等規則8条の3の6、連結財務諸表規則14条の7)の規定が新設された。これらの規定に関し、平成23年3月31日に公表された「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」(平成23年内閣府令第10号)と併せて改正財務諸表等規則ガイドライン(8の3の5-3)および改正連結財務諸表規則ガイドライン(14-6)が規定された。なお、連結財務諸表規則および同ガイドラインの規定は財務諸表等規則および同ガイドラインの準用規定であることから、財務諸表等規則および同ガイドラインの規定を引用することとする。
連結財務諸表規則14条の6において準用する財務諸表等規則8条の3の5は、会計上の見積りの変更を行った場合に、当該変更が(当事業年度の)財務諸表に与えている影響額(同条2号)および翌事業年度以降の財務諸表に与えている影響額(同条3号イ。合理的に見積ることができる場合に限る)の注記を求めている。すなわち、会計上の見積りの変更が当事業年度および翌事業年度以降の財務諸表に影響を与えている場合には、当事業年度の財務諸表に与える影響額だけでなく、翌事業年度以降の財務諸表に与える影響額の注記が必要となる。
他方、過年度遡及会計基準18項(2)は、会計上の見積りの変更が当事業年度に影響を及ぼす場合は当事業年度への影響額、当事業年度への影響がない場合でも将来の期間に影響を及ぼす場合には当該影響額(合理的に見積ることができる場合に限る)の注記を求めている(表3参照)が、会計上の見積りの変更が当事業年度および翌事業年度以降に影響を及ぼす場合における翌事業年度以降の影響額の記載の有無が明らかではない。
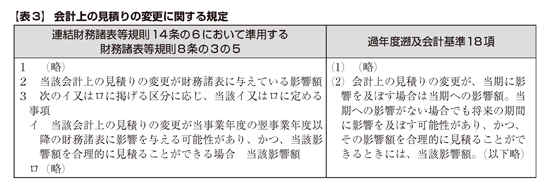 したがって、財務諸表等規則8条の3の5の規定と過年度遡及会計基準18項(2)の規定との間に齟齬が生じている可能性があった。そのため、前記のとおり、平成23年3月31日付で財務諸表等規則ガイドライン8の3の5-3および連結財務諸表規則ガイドライン14-6が新設され、財務諸表等規則8条の3の5(3号イ)および連結財務諸表規則14条の6、財務諸表等規則8条の3の6(4号イ)および連結財務諸表規則14条の7の規定が明確化されたことにより、これらの規定と過年度遡及会計基準18項(2)の規定は実質的には異ならないことが明確にされた。
したがって、財務諸表等規則8条の3の5の規定と過年度遡及会計基準18項(2)の規定との間に齟齬が生じている可能性があった。そのため、前記のとおり、平成23年3月31日付で財務諸表等規則ガイドライン8の3の5-3および連結財務諸表規則ガイドライン14-6が新設され、財務諸表等規則8条の3の5(3号イ)および連結財務諸表規則14条の6、財務諸表等規則8条の3の6(4号イ)および連結財務諸表規則14条の7の規定が明確化されたことにより、これらの規定と過年度遡及会計基準18項(2)の規定は実質的には異ならないことが明確にされた。会計上の見積りの変更が当事業年度および翌事業年度以降の財務諸表に影響を及ぼす場合(重要性が乏しい場合を除く)に、無条件に翌事業年度以降の連結財務諸表に与える影響額の記載を要しないとすることは財務諸表利用者の保護の観点から困難である。
しかしながら、当事業年度の財務諸表に与えている影響額に基づき、翌事業年度以降の財務諸表に与える影響の概要を財務諸表利用者が把握できる場合には、利用者の保護上問題がないと考えられる。そこで、利用者が翌事業年度以降の財務諸表に与える影響額の概要を把握できる場合を重要性が乏しい場合に該当するものとして、翌事業年度以降の財務諸表に与える影響額の注記を省略できることがガイドライン上明確にされた。
過年度遡及会計基準40項において、会計上の見積りの変更の事例として、有形固定資産の耐用年数の変更が挙げられている。耐用年数の変更は、通常、当事業年度だけでなく翌事業年度以降の財務諸表に影響を及ぼすと考えられるが、当事業年度の財務諸表に与えている影響額の注記により、翌事業年度以降の財務諸表に与える影響の概要を把握できるケースに該当する場合が考えられ、その場合には翌事業年度以降の財務諸表に与える影響額の注記の省略が認められるものと考えられる。
なお、前記のとおり、連結財務諸表規則14条の7において準用する財務諸表等規則8条の3の6(会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区別することが困難な場合の注記。減価償却方法の変更の場合等が考えられる)4号イも同様と考えられる。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -

Copyright (C) 2019
SHINNIPPON-HOKI PUBLISHING CO.,LTD.




















