解説記事2012年06月04日 【ニュース特集】 消費税の事業者免税点制度、新設法人3期目に潜む税賠リスク(2012年6月4日号・№453)
期末在庫の税額調整を巡る事案で税理士勝訴
消費税の事業者免税点制度、新設法人3期目に潜む税賠リスク
消費税の事業者免税点制度を巡り、税理士が設立2期の末日までに課税事業者選択届出書の提出に関する指導を怠ったとして、納税者が税理士を訴えていた税賠訴訟で3月30日、東京地裁は税理士勝訴の判決を言い渡した。裁判所は、納税者が設立2期末までに在庫がわかる資料等を税理士へ送付しなかったことなどを指摘し、税理士が設立3期に課税事業者となった方が課税上有利になることを容易に認識し得たとはいえないと判断した。消費税の税賠訴訟については、将来消費税率が上昇するに連れて税賠に直面する金額も大きくなるだけに、税理士勝訴の本判決は押さえておきたいものといえる。
設立2期に課税仕入れ、在庫となった商品の仕入税額控除が不可 消費税の事業者免税点制度については、資本金1,000万円以上の新設法人は設立1期と設立2期の事業年度の消費税の納税義務が免除されない(消法12条の2)が、設立1期の課税売上高が1,000万円以下であれば設立3期は免税事業者となる(消法9条①)。
しかし、設立2期に課税事業者であった事業者が翌課税期間である設立3期に免税事業者となるケースにおいて、設立2期目に課税仕入れをし、その課税仕入れが在庫として期末棚卸資産に含まれていれば、その期末棚卸資産に係る仕入税額はその設立2期目において仕入税額控除の適用対象外とされる(消法36条⑤)。いわゆる期末棚卸資産の税額調整が発生するケースだ。
したがって、この期末棚卸資産の税額調整を回避するためには、設立2期の末日までに「課税事業者選択届出書」を提出し、設立3期(および設立4期)において課税事業者を選択する必要がある。
納税者、届出書の助言義務等を怠ったと主張 今回紹介する事案は、まさにこの「課税事業者選択届出書」の提出を巡り、設立3期に免税事業者となった納税者が、税理士法人である被告との間で結んだ税務等に関する顧問契約に関連し、税理士が課税事業者選択届出書の提出に関する指導、助言等の義務を怠ったことから、納税者は設立2期の消費税について仕入税額控除を受けられなかったと主張し、税理士に対して、債務不履行に基づき仕入税額控除を受けられていた場合に還付を受けることができた約1,600万円の損害賠償を求めていたものだ(図参照)。
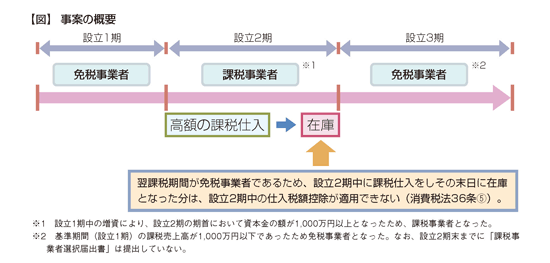
納税者である原告は、①税理士は設立2期末までに課税事業者となるかまたは免税事業者となるかを選択できる課税事業者選択届出制度の存在をあらかじめ助言する義務があったこと、また、②第2期末において在庫商品が生じることが見込まれるときは同届出書を提出する必要があるからあらかじめ納税者に連絡をするように注意喚起し、助言・指導をする義務があったと主張していた。
裁判所、税理士は課税上有利なことを容易に認識できなかったと指摘 原告である納税者の税賠請求に対して裁判所は、まず納税者と税理士の間で締結された顧問契約(次頁表参照)について、①税務に関する経営コンサルタント業務まで含むとは定められていないこと、②税理士による納税者への定期訪問が予定されていないこと、③納税者は税理士に対して委任業務の遂行に必要な資料等を提供する責任を負うものと定めていること、④顧問報酬は月額2万円と比較的低廉であることを認定。これらの事情からすれば、納税者から事前に税務相談に関する問い合わせがない限り、税理士は、納税者の業務内容を積極的に調査・予見し、納税者への税務に関する助言、指導を行う義務は原則としてないものと解すべきであるとした。
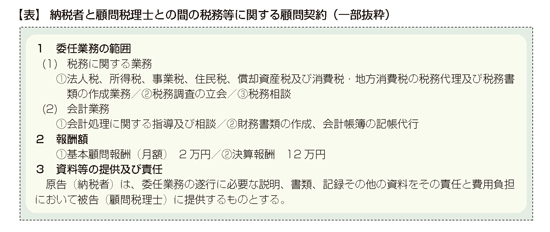
一方で裁判所は、納税者から事前に税務相談に関する問合せがなくても、納税者から適切に情報提供がされるなどして、納税者に課税上重大な利害得失があり得ることを具体的に認識しまたは容易に認識し得るような事情がある場合には、納税者に対し、その旨の助言、指導等をすべき付随的な義務が生じる場合もあるというべきであるとしている。
3期以降も課税事業者の方が有利と指摘も そのうえで、設立2期において課税事業者である納税者が、本来であれば設立3期に免税事業者となるところ、「課税事業者選択届出書」を設立2期末までに提出することにより、消費税法上有利であるといえるケースは、設立2期末の時点で仕入額が高額となる大量の在庫を抱え、かつそれを翌期以降(設立3期および設立4期)の事業年度にも販売することが見込めないような特段の事情がある場合に限られるとの枠組みを示している。今回紹介した事案については、納税者が設立3期以降も課税事業者を選択した方が消費税法上有利といえる特段の事情があったことを認定。しかしその一方で、納税者は税理士に対して、設立2期末までに設立2期末の在庫がわかる資料等を送付していなかったことなどから、税理士が「課税事業者選択届出書」を第2期末までに提出することにより、第3期において課税事業者となった方が課税上有利になることを具体的に認識または容易に認識し得たとはいえないと判断。納税者の税賠請求を棄却する判決を言い渡している。
23年度改正で上半期1,000万円超の課税売上で翌期から課税事業者
3月決算法人、平成24年4月から判定開始 なお今回紹介した事案は、設立3期目の納税義務の判定にあたり、基準期間である前々事業年度(設立1期)の課税売上高をもとに納税義務の有無が判定されたもの。
事業者免税点制度については、平成23年6月施行の税制改正により、基準期間である前々事業年度の判定に加え、前事業年度の上半期の課税売上高が1,000万円超である場合にも、翌事業年度から課税事業者に該当することとされている。そして、この1,000万円超の判定は、個人事業者は平成24年1月1日から、3月決算法人は平成24年4月1日から既に始まっている。
ここで注意が必要なのは、前事業年度の上半期の課税売上高が1,000万円超であっても、その上半期に支払った給与等の額が1,000万円以下である場合は、事業者免税点制度の適用を受けることができることだ。この給与等の額は、新設された消費税法基本通達1-5-23において、給与や賞与等が該当する一方、所得税法上非課税とされる通勤手当や旅費等は該当しないこと、また未払給与の額は含まれないことが規定されている。
事業者免税点制度が適用されるか否かは、事業者の納税額に大きな影響を及ぼすこととなる。将来、消費税率が8%、10%に上がれば、その分納税額も増え税賠に直面する金額も大きくなる。それだけに、クライアントが事業者免税点制度の適用を受けることができるか否かの判定は、税理士にとって細心の注意を払う必要があるといえる。
消費税の事業者免税点制度、新設法人3期目に潜む税賠リスク
消費税の事業者免税点制度を巡り、税理士が設立2期の末日までに課税事業者選択届出書の提出に関する指導を怠ったとして、納税者が税理士を訴えていた税賠訴訟で3月30日、東京地裁は税理士勝訴の判決を言い渡した。裁判所は、納税者が設立2期末までに在庫がわかる資料等を税理士へ送付しなかったことなどを指摘し、税理士が設立3期に課税事業者となった方が課税上有利になることを容易に認識し得たとはいえないと判断した。消費税の税賠訴訟については、将来消費税率が上昇するに連れて税賠に直面する金額も大きくなるだけに、税理士勝訴の本判決は押さえておきたいものといえる。
設立2期に課税仕入れ、在庫となった商品の仕入税額控除が不可 消費税の事業者免税点制度については、資本金1,000万円以上の新設法人は設立1期と設立2期の事業年度の消費税の納税義務が免除されない(消法12条の2)が、設立1期の課税売上高が1,000万円以下であれば設立3期は免税事業者となる(消法9条①)。
しかし、設立2期に課税事業者であった事業者が翌課税期間である設立3期に免税事業者となるケースにおいて、設立2期目に課税仕入れをし、その課税仕入れが在庫として期末棚卸資産に含まれていれば、その期末棚卸資産に係る仕入税額はその設立2期目において仕入税額控除の適用対象外とされる(消法36条⑤)。いわゆる期末棚卸資産の税額調整が発生するケースだ。
したがって、この期末棚卸資産の税額調整を回避するためには、設立2期の末日までに「課税事業者選択届出書」を提出し、設立3期(および設立4期)において課税事業者を選択する必要がある。
納税者、届出書の助言義務等を怠ったと主張 今回紹介する事案は、まさにこの「課税事業者選択届出書」の提出を巡り、設立3期に免税事業者となった納税者が、税理士法人である被告との間で結んだ税務等に関する顧問契約に関連し、税理士が課税事業者選択届出書の提出に関する指導、助言等の義務を怠ったことから、納税者は設立2期の消費税について仕入税額控除を受けられなかったと主張し、税理士に対して、債務不履行に基づき仕入税額控除を受けられていた場合に還付を受けることができた約1,600万円の損害賠償を求めていたものだ(図参照)。
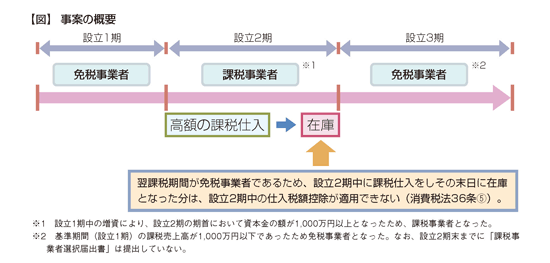
納税者である原告は、①税理士は設立2期末までに課税事業者となるかまたは免税事業者となるかを選択できる課税事業者選択届出制度の存在をあらかじめ助言する義務があったこと、また、②第2期末において在庫商品が生じることが見込まれるときは同届出書を提出する必要があるからあらかじめ納税者に連絡をするように注意喚起し、助言・指導をする義務があったと主張していた。
裁判所、税理士は課税上有利なことを容易に認識できなかったと指摘 原告である納税者の税賠請求に対して裁判所は、まず納税者と税理士の間で締結された顧問契約(次頁表参照)について、①税務に関する経営コンサルタント業務まで含むとは定められていないこと、②税理士による納税者への定期訪問が予定されていないこと、③納税者は税理士に対して委任業務の遂行に必要な資料等を提供する責任を負うものと定めていること、④顧問報酬は月額2万円と比較的低廉であることを認定。これらの事情からすれば、納税者から事前に税務相談に関する問い合わせがない限り、税理士は、納税者の業務内容を積極的に調査・予見し、納税者への税務に関する助言、指導を行う義務は原則としてないものと解すべきであるとした。
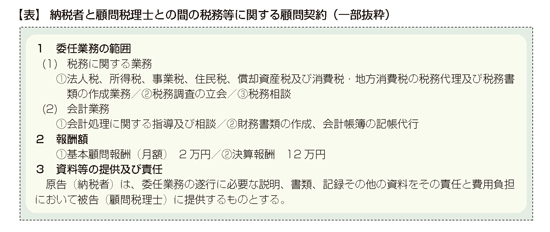
一方で裁判所は、納税者から事前に税務相談に関する問合せがなくても、納税者から適切に情報提供がされるなどして、納税者に課税上重大な利害得失があり得ることを具体的に認識しまたは容易に認識し得るような事情がある場合には、納税者に対し、その旨の助言、指導等をすべき付随的な義務が生じる場合もあるというべきであるとしている。
3期以降も課税事業者の方が有利と指摘も そのうえで、設立2期において課税事業者である納税者が、本来であれば設立3期に免税事業者となるところ、「課税事業者選択届出書」を設立2期末までに提出することにより、消費税法上有利であるといえるケースは、設立2期末の時点で仕入額が高額となる大量の在庫を抱え、かつそれを翌期以降(設立3期および設立4期)の事業年度にも販売することが見込めないような特段の事情がある場合に限られるとの枠組みを示している。今回紹介した事案については、納税者が設立3期以降も課税事業者を選択した方が消費税法上有利といえる特段の事情があったことを認定。しかしその一方で、納税者は税理士に対して、設立2期末までに設立2期末の在庫がわかる資料等を送付していなかったことなどから、税理士が「課税事業者選択届出書」を第2期末までに提出することにより、第3期において課税事業者となった方が課税上有利になることを具体的に認識または容易に認識し得たとはいえないと判断。納税者の税賠請求を棄却する判決を言い渡している。
23年度改正で上半期1,000万円超の課税売上で翌期から課税事業者
3月決算法人、平成24年4月から判定開始 なお今回紹介した事案は、設立3期目の納税義務の判定にあたり、基準期間である前々事業年度(設立1期)の課税売上高をもとに納税義務の有無が判定されたもの。
事業者免税点制度については、平成23年6月施行の税制改正により、基準期間である前々事業年度の判定に加え、前事業年度の上半期の課税売上高が1,000万円超である場合にも、翌事業年度から課税事業者に該当することとされている。そして、この1,000万円超の判定は、個人事業者は平成24年1月1日から、3月決算法人は平成24年4月1日から既に始まっている。
ここで注意が必要なのは、前事業年度の上半期の課税売上高が1,000万円超であっても、その上半期に支払った給与等の額が1,000万円以下である場合は、事業者免税点制度の適用を受けることができることだ。この給与等の額は、新設された消費税法基本通達1-5-23において、給与や賞与等が該当する一方、所得税法上非課税とされる通勤手当や旅費等は該当しないこと、また未払給与の額は含まれないことが規定されている。
事業者免税点制度が適用されるか否かは、事業者の納税額に大きな影響を及ぼすこととなる。将来、消費税率が8%、10%に上がれば、その分納税額も増え税賠に直面する金額も大きくなる。それだけに、クライアントが事業者免税点制度の適用を受けることができるか否かの判定は、税理士にとって細心の注意を払う必要があるといえる。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -

Copyright (C) 2019
SHINNIPPON-HOKI PUBLISHING CO.,LTD.




















