解説記事2012年12月03日 【ニュース特集】 麻酔医師の所得区分、裁判所の着眼点は?(2012年12月3日号・№477)
給与所得であれば病院側に源泉義務が発生
麻酔医師の所得区分、裁判所の着眼点は?
麻酔医師が、非常勤医師として派遣された病院から受け取る報酬の所得区分について、疑義が生じることは少なくない。給与所得に該当すれば支払者である病院側には源泉義務が発生するため、所得区分の問題は、支払いを受ける医師だけでなく、病院側にとっても重要な事柄といえるだろう。この麻酔医師の所得区分をめぐり、東京地裁(定塚誠裁判長)は9月21日、事業所得と主張する納税者の主張を棄却するなかで、所得区分についての判断の枠組みを示している。本判決は、既に確定済みであるだけに、麻酔医師を巡る所得区分の判断材料として参考にすることができるだろう。特集では、定塚裁判長の判断の枠組みと、今回紹介する事案への具体的な当てはめなどをお伝えする。
麻酔業務に伴い医療法人から得た報酬の所得区分、給与か事業か
納税者側は事業所得、国側は給与所得と主張 今回の事案は、麻酔科医師である納税者(原告)が、自身が麻酔手術等を施行した各医療法人から得た報酬が事業所得と給与所得のいずれかに該当するかが争われていたもの。
納税者は、医療法人Aを始めとする複数の医療法人・国立病院において、非常勤医師として麻酔業務を行っており、医療法人Aでは、報酬や費用について、表1のような条件のもとで麻酔業務を行っていた。なお、納税者は、医療法人A以外の病院においても、ほぼ同様の条件で麻酔業務を行っている。
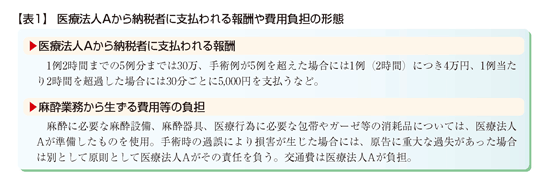
各医療法人から得た収入について、納税者が事業所得に該当するとして確定申告をしたことに対し、税務署側は、給与所得に当たるとして更正処分等を行っていた。納税者は更正処分等の取り消しを求めて訴訟を提起していた(当事者の主張は表2参照)。
裁判所、麻酔業務が赤字にならない点などを指摘し事業所得と認めず 東京地裁民事第38部の定塚誠裁判長は、事業所得と給与所得の区別の基準について、最高裁昭和56年4月24日判決を踏まえ、事業所得の本質は、自己の計算と危険において独立して反復継続して営まれる業務から生ずる所得である点にあり、給与所得の本質は、自己の計算と危険によらず、非独立的労務、すなわち使用者の指揮命令ないし空間的、時間的な拘束に服して提供した労務事態の対価として使用者から受ける給付である点にあると指摘。
そのうえで定塚裁判長は、①自己の計算と危険によってその経済的活動が行われているかどうか、すなわち経済的活動の内容やその成果等によって変動し得る収益や費用が誰に帰属するか、あるいは費用が収益を上回る場合などのリスクを誰が負担するのかという点、②遂行する経済的活動が他者の指揮命令を受けて行うものであるか否かという点、③経済的活動が何らかの空間的、時間的拘束を受けて行われるものであるか否かという点などを総合的に考慮して、個別具体的に判断すべきであるとの判断の枠組みを示している。
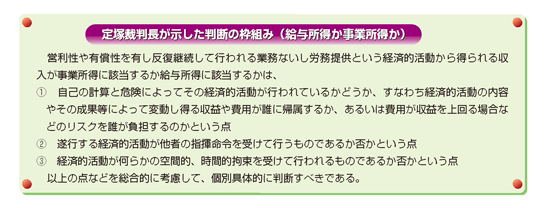
難易度等で変動する報酬体系ではない 定塚裁判長は、今回の事案について、判断の枠組みで示した「①自己の計算と危険によってその経済的活動が行われているかどうか」を次のように判断している。
まず、医療法人Aから納税者に支払われる報酬については、術例数が1例であっても2例であっても定額の報酬が支払われており、手術や麻酔施術の難易度や用いる薬剤等の価格などに応じて変動する仕組みにはなっておらず、医療行為等に対する対価として患者や公的医療保険から医療法人Aに支払われる診療報酬の金額の多寡に応じて納税者に対する報酬が変動する報酬体系にはなっていない点を指摘している。
また、麻酔業務から生ずる費用等の帰属については、麻酔に必要な麻酔設備等、包帯等の消耗品は医療法人Aが準備したものが使用され、麻酔薬剤は、使用した薬剤代金を医療法人Aが公的医療機関等から受領することとされていること、手術時の過誤で損害が生じた場合には、原則として医療法人Aがその責任を負うこと、交通費は、医療法人Aが負担していることを指摘。
そのうえで定塚裁判長は、麻酔業務から生ずる費用は、基本的に医療法人Aが負担しており、納税者は、たとえば高額の麻酔機器を購入することによって生じる費用(減価償却費)が麻酔業務から生じる収益を上回るなどして麻酔業務による損益計算が赤字になるというような事業の収支から一般的に生じ得る危険を負担することはないと認定している。
勤務時間や手術場所等は医療法人が決定 定塚裁判長は、「②納税者が業務遂行において医療法人Aの指揮命令に服していたか否か」については、納税者が麻酔を担当する患者数、各手術の内容や要する時間、手術や麻酔の施行場所や患者の入退室予定時間等が医療法人Aによって他律的に決定されていたことを踏まえれば、麻酔業務を行う対象、場所、時間など業務の一般的な態様は、医療法人Aの指揮命令に服していたと認定。
また、「③納税者が医療法人Aから空間的、時間的拘束を受けていたといえるか否か」については、勤務時間が毎週木・金曜日の手術開始時から終了時までと定められていたこと、業務が医療法人Aが経営する病院内で術中麻酔管理等を行うことであったこと、出勤・退勤時刻が派遣医出勤簿に記録され、医療法人Aにおいて他の非常勤職員と同様に勤務時間が管理されていたことを踏まえれば、納税者は医療法人Aの空間的、時間的拘束に服していたと認定している。
そのうえで定塚裁判長は、納税者が医療法人Aから支払を受けた報酬は、自己の計算と危険において独立して営まれる業務から生ずる所得であるということはできないと指摘。納税者は、医療法人Aの指揮命令に基づき、医療法人Aによる空間的、時間的拘束を受けて行った業務ないし労務提供の対価として報酬を受けたものであるから、所得税法28条1項に規定する給与所得に当たると認めるのが相当であると結論付けている。
麻酔医療の高度専門性を主張も裁判所は一蹴 なお、訴訟において納税者は、麻酔医療について高度の専門性を有し、手術の指揮監督者として独立して業務を行い、病院から指揮命令監督を受ける立場にないから、各医療法人から得た収入は、事業所得に該当する旨主張していた。
この点について定塚裁判長は、使用者の指揮命令に服して労務を提供するものであるか否かは、業務を行う対象、場所、時間などを他者が決定し、それに従って労務や役務の提供が行われているか否かという問題であり、業務遂行に必要な様々な判断が自分自身でできるからといって、他者の指揮命令に服していないということにはならないと指摘。
このことは、たとえば国会議員でいえば、出席すべき委員会やそこでの議事の対象、委員会や本会議が行われる日時や場所など、裁判官でいえば勤務すべき裁判所や法定の場所、扱うべき事件や開廷できる時間などについて、他者に規律されて職務を遂行し、その業務の内容や成果等に応じて変動する収益を得たり費用負担をしたりする報酬体系になっていない者については、その報酬は給与所得とされていることからも明らかであるとして、納税者の主張を斥けている。
麻酔医師の所得区分、裁判所の着眼点は?
麻酔医師が、非常勤医師として派遣された病院から受け取る報酬の所得区分について、疑義が生じることは少なくない。給与所得に該当すれば支払者である病院側には源泉義務が発生するため、所得区分の問題は、支払いを受ける医師だけでなく、病院側にとっても重要な事柄といえるだろう。この麻酔医師の所得区分をめぐり、東京地裁(定塚誠裁判長)は9月21日、事業所得と主張する納税者の主張を棄却するなかで、所得区分についての判断の枠組みを示している。本判決は、既に確定済みであるだけに、麻酔医師を巡る所得区分の判断材料として参考にすることができるだろう。特集では、定塚裁判長の判断の枠組みと、今回紹介する事案への具体的な当てはめなどをお伝えする。
麻酔業務に伴い医療法人から得た報酬の所得区分、給与か事業か
納税者側は事業所得、国側は給与所得と主張 今回の事案は、麻酔科医師である納税者(原告)が、自身が麻酔手術等を施行した各医療法人から得た報酬が事業所得と給与所得のいずれかに該当するかが争われていたもの。
納税者は、医療法人Aを始めとする複数の医療法人・国立病院において、非常勤医師として麻酔業務を行っており、医療法人Aでは、報酬や費用について、表1のような条件のもとで麻酔業務を行っていた。なお、納税者は、医療法人A以外の病院においても、ほぼ同様の条件で麻酔業務を行っている。
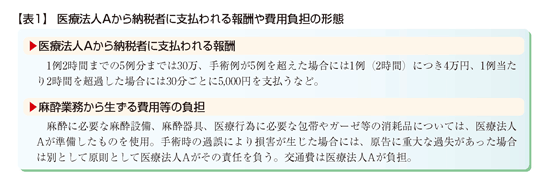
各医療法人から得た収入について、納税者が事業所得に該当するとして確定申告をしたことに対し、税務署側は、給与所得に当たるとして更正処分等を行っていた。納税者は更正処分等の取り消しを求めて訴訟を提起していた(当事者の主張は表2参照)。
| 【表2】所得区分を巡る原告側(納税者)と被告側(国側)の主張 |
| 原告側(納税者側) | 被告側(国側) |
| 原告は、麻酔治療について、医療法人Aから指揮命令を受ける立場になく、また、医療法人Aとの間の業務委託契約において、場所的、時間的に拘束する旨の定めはない。業務委託契約書では、麻酔業務日に原告に代わる代理麻酔医を派遣することで麻酔業務の責任を果たすことができる契約をしており、また、原告と医療法人Aの双方には、1週間前までに麻酔の委託または受託をキャンセルできる旨のキャンセル権が担保されており、現に双方がキャンセル権を行使したことがあった。報酬額については、1例分で6万円を受領しなければ原告の業務が成立しないと考えて基本料金および超過報酬を定め、交通費として実費相当額の受領を申し出たものである。1例分の単価に基づいて症例数に応じて出来高を定める報酬の定め方は、請負ないし業務委託契約の労働対価の定め方そのものであり、収入は、一定しておらず極めて不安定である。原告は、麻酔器具等の設備の使用料や消耗品代をディスカウントしたうえで、医療法人Aとの間の報酬を決めており、麻酔に必要な設備の使用料や消耗品代を実質的に負担している。 したがって、医療法人Aから支給された報酬は、事業所得に該当する。 | 原告は、所定の勤務日(毎週木、金曜日)に当日実施される手術の開始予定時間までに出勤しなければならず、手術が終了するまでは勤務を離れることはできない。勤務時間は、「派遣医出勤簿」への記録等によって管理されており、勤務地は、医療法人Aの手術室と定められている。また、手術に携わる症例の件数は、病院によって指定されており、原告が提供する労務または労務提供の内容は、他律的に決定されている。 そして、報酬額の定め方は、1か月当たり基本給として定額(約30万円)を支払うが、手術例が5例を超えた場合には、1例(2時間)につき4万円、1例当たり2時間を超過した場合には30分ごとに5,000円を支払うこととされており、報酬額は、一定程度あらかじめ定められている。さらに、麻酔手術に必要な器具、薬剤、術衣等は、医療法人Aが費用負担しており、交通費も医療法人Aが支給している。 したがって、原告の労務提供の態様は、医療法人Aから時間的、空間的な拘束を受け、その指揮監督に服するもので、報酬受給の態様は、自己の危険と計算によって行うものとはいえないのであって、原告が医療法人Aから支給された報酬は、給与所得に該当する。 |
裁判所、麻酔業務が赤字にならない点などを指摘し事業所得と認めず 東京地裁民事第38部の定塚誠裁判長は、事業所得と給与所得の区別の基準について、最高裁昭和56年4月24日判決を踏まえ、事業所得の本質は、自己の計算と危険において独立して反復継続して営まれる業務から生ずる所得である点にあり、給与所得の本質は、自己の計算と危険によらず、非独立的労務、すなわち使用者の指揮命令ないし空間的、時間的な拘束に服して提供した労務事態の対価として使用者から受ける給付である点にあると指摘。
そのうえで定塚裁判長は、①自己の計算と危険によってその経済的活動が行われているかどうか、すなわち経済的活動の内容やその成果等によって変動し得る収益や費用が誰に帰属するか、あるいは費用が収益を上回る場合などのリスクを誰が負担するのかという点、②遂行する経済的活動が他者の指揮命令を受けて行うものであるか否かという点、③経済的活動が何らかの空間的、時間的拘束を受けて行われるものであるか否かという点などを総合的に考慮して、個別具体的に判断すべきであるとの判断の枠組みを示している。
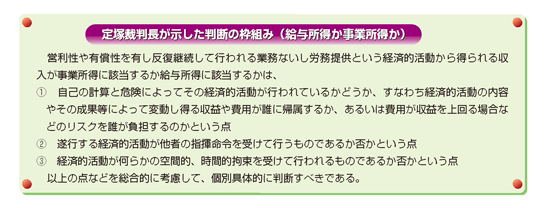
難易度等で変動する報酬体系ではない 定塚裁判長は、今回の事案について、判断の枠組みで示した「①自己の計算と危険によってその経済的活動が行われているかどうか」を次のように判断している。
まず、医療法人Aから納税者に支払われる報酬については、術例数が1例であっても2例であっても定額の報酬が支払われており、手術や麻酔施術の難易度や用いる薬剤等の価格などに応じて変動する仕組みにはなっておらず、医療行為等に対する対価として患者や公的医療保険から医療法人Aに支払われる診療報酬の金額の多寡に応じて納税者に対する報酬が変動する報酬体系にはなっていない点を指摘している。
また、麻酔業務から生ずる費用等の帰属については、麻酔に必要な麻酔設備等、包帯等の消耗品は医療法人Aが準備したものが使用され、麻酔薬剤は、使用した薬剤代金を医療法人Aが公的医療機関等から受領することとされていること、手術時の過誤で損害が生じた場合には、原則として医療法人Aがその責任を負うこと、交通費は、医療法人Aが負担していることを指摘。
そのうえで定塚裁判長は、麻酔業務から生ずる費用は、基本的に医療法人Aが負担しており、納税者は、たとえば高額の麻酔機器を購入することによって生じる費用(減価償却費)が麻酔業務から生じる収益を上回るなどして麻酔業務による損益計算が赤字になるというような事業の収支から一般的に生じ得る危険を負担することはないと認定している。
| Column | 麻酔器具等の使用料・消耗品代を実質負担していても事業所得に該当せず |
| 納税者は、麻酔業務に係る費用を巡り、麻酔器具等の設備の使用料や消耗品代を差し引いたうえで各病院との間の報酬を決めているから、実質的にこれらの経費は納税者が負担している旨を主張していた。この点について定塚裁判長は、仮に、費用の一部を負担する趣旨で相当額を減額して報酬を決めたという事情があったとしても、そのことから「原告が自己の計算と危険において独立して」業務を営んでいることにはならないことは明らかであると指摘している。 | |
勤務時間や手術場所等は医療法人が決定 定塚裁判長は、「②納税者が業務遂行において医療法人Aの指揮命令に服していたか否か」については、納税者が麻酔を担当する患者数、各手術の内容や要する時間、手術や麻酔の施行場所や患者の入退室予定時間等が医療法人Aによって他律的に決定されていたことを踏まえれば、麻酔業務を行う対象、場所、時間など業務の一般的な態様は、医療法人Aの指揮命令に服していたと認定。
また、「③納税者が医療法人Aから空間的、時間的拘束を受けていたといえるか否か」については、勤務時間が毎週木・金曜日の手術開始時から終了時までと定められていたこと、業務が医療法人Aが経営する病院内で術中麻酔管理等を行うことであったこと、出勤・退勤時刻が派遣医出勤簿に記録され、医療法人Aにおいて他の非常勤職員と同様に勤務時間が管理されていたことを踏まえれば、納税者は医療法人Aの空間的、時間的拘束に服していたと認定している。
そのうえで定塚裁判長は、納税者が医療法人Aから支払を受けた報酬は、自己の計算と危険において独立して営まれる業務から生ずる所得であるということはできないと指摘。納税者は、医療法人Aの指揮命令に基づき、医療法人Aによる空間的、時間的拘束を受けて行った業務ないし労務提供の対価として報酬を受けたものであるから、所得税法28条1項に規定する給与所得に当たると認めるのが相当であると結論付けている。
麻酔医療の高度専門性を主張も裁判所は一蹴 なお、訴訟において納税者は、麻酔医療について高度の専門性を有し、手術の指揮監督者として独立して業務を行い、病院から指揮命令監督を受ける立場にないから、各医療法人から得た収入は、事業所得に該当する旨主張していた。
この点について定塚裁判長は、使用者の指揮命令に服して労務を提供するものであるか否かは、業務を行う対象、場所、時間などを他者が決定し、それに従って労務や役務の提供が行われているか否かという問題であり、業務遂行に必要な様々な判断が自分自身でできるからといって、他者の指揮命令に服していないということにはならないと指摘。
このことは、たとえば国会議員でいえば、出席すべき委員会やそこでの議事の対象、委員会や本会議が行われる日時や場所など、裁判官でいえば勤務すべき裁判所や法定の場所、扱うべき事件や開廷できる時間などについて、他者に規律されて職務を遂行し、その業務の内容や成果等に応じて変動する収益を得たり費用負担をしたりする報酬体系になっていない者については、その報酬は給与所得とされていることからも明らかであるとして、納税者の主張を斥けている。
| Column | 最高裁、事業所得と給与所得の判断基準を明らかに |
| 最高裁昭和56年4月24日判決は、事業所得とは、自己の計算と危険において独立して営まれ、営利性、有償性を有し、かつ反復継続して遂行する意思と社会的地位とが客観的に認められる業務から生ずる所得をいうと解するのが相当であり、給与所得とは、雇用契約またはこれに類する原因に基づき使用者の指揮命令に服して提供した党務の対価として使用者から受ける給付をいうと解するのが相当であるとの判断基準を示した。また、給与所得該当性の判断に当たっては、給与支給者との関係において何らかの空間的、時間的な拘束を受け、継続的ないし断続的に労務または役務の提供があり、その対価として支給されるものであるかどうかを重視するのが相当であるとした。 | |
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -

Copyright (C) 2019
SHINNIPPON-HOKI PUBLISHING CO.,LTD.




















