解説記事2012年12月03日 【実務解説】 事業再生実務の税務・会計-第2会社方式による事業再生事例の研究等-(2012年12月3日号・№477)
実務解説
事業再生実務の税務・会計
-第2会社方式による事業再生事例の研究等-
公認会計士・税理士 棟田裕幸
Ⅰ 序 論
中小企業に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律(以下「中小企業金融円滑化法」という。)は、平成25年3月31日をもって終了する。その後は、多くの中小企業が金融機関に対して条件変更を申し入れた場合に、法律の後ろ盾がなくなることから、従来のように応じてもらえなくなることが予想され、多くの中小企業が相当に厳しい立場に追い込まれることが予想される。かような事態に遭遇した中小企業は、今後どうすればよいのか、今回は、事業再生実務の事例研究として、中小企業において従来から多くの事例がある第2会社方式による事業再生実務を例にとり、具体的数値例をもって流れを追うとともに、その税務処理、会計処理についても言及することとしたい。
Ⅱ 事例編・事業再生実務の研究
事業再生の手続は、前回(本誌476号26頁参照)「実務解説 事業再生実務の法務」(以下「法務編」という。)のとおり、大きく分けて法的整理と私的整理があり、法的整理とは裁判所が関与する再建手続、私的整理とは裁判所が関与しない再建手続をいう。
実務において私的整理は、再建手続に入ったことが公表されないため、「倒産」のレッテルが貼られることを回避できる、取引業者に対する債務を債務整理の対象としないことから取引業者との関係を円滑に保つことができる、というようなメリットがあることから、実務では使われることが多い。私的整理には、前回「法務編」のとおり、様々な手法が存在するが、中小企業においては、第三者が介入する私的整理手法としての「中小企業再生支援協議会(以下「協議会」という。)」の支援による再生が行われることが多い。
表1の「協議会」金融支援の活動状況のとおり、①金融機関による条件変更(リスケジュール)が70.0%、②事業譲渡・会社分割による第2会社方式が10.6%、③デット・デット・スワップ(以下「DDS」という。)(DDS1及びDDS2合わせて)が7.4%、という順で適用されている。
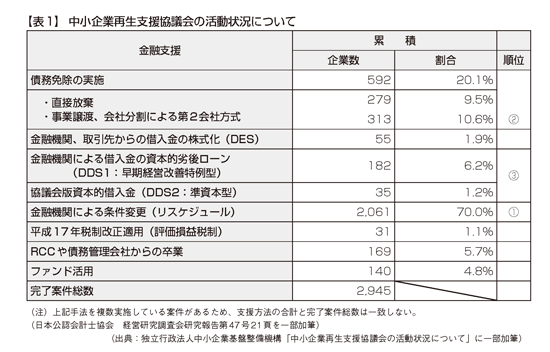
今回は、①リスケジュールで金融機関への支援要請を検討したが、会社の置かれた厳しい実情を鑑みた結果として、抜本的事業再生策として有効な手法としての、②第2会社方式による事業再生策を実施した事例を紹介する。
Ⅲ 私的整理における第2会社方式について
「中小企業再生支援協議会スキーム」の金融支援の方法として、第2会社方式が存在する。その全体的な概要は図1のとおり。事業部門を優良部門と不採算部門とに分け、優良部門を第2会社に移転し、過剰な金融債務等を旧会社に残し、身軽になったところで、新会社により新たな事業存続を図るものである。残った旧会社はその後特別清算等により清算する。
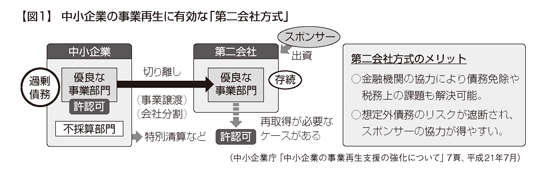
第2会社方式には大きく分けて、事業譲渡型と会社分割型とがある。各々の受け皿会社が、既存会社か新設会社かによって、図2のようなパターンが考えられる。今回紹介した事例は、図2の「(3)新設分割型」である。
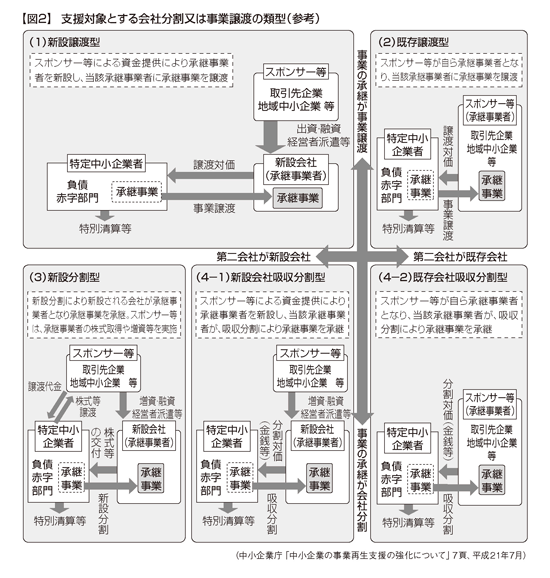
【事例研究】第2会社方式(会社分割)による事業再生の事例
1 会社の概要 (業種)
コンテンツ及びソフトウェアの制作・開発
(主要製品)
ゲームソフト等のコンテンツ制作、ソフトウェア製品の開発、その他
(相談時の直近の業績)
平成23年3月期 売上高 463百万円(経常利益 △127百万円)
平成24年3月期 売上高 367百万円(経常利益 △124百万円)
(業歴)30年
(従業員数)40人
2 会社の状況説明 (相談時の状況及び相談内容(平成23年4月))
今後の売上の見込みはあるが、運転資金、夏季賞与支払い等の資金繰りが厳しい状況のため、1億円程度の資金調達の支援を希望。
・相談時の銀行借入金残高
約530百万円(月額返済額約12百万円)
・相談時の月次決算状況
年々売上は減少、損失体質が定着化。
・相談時のキャッシュフロー状況
資金繰り状況はますます悪化。
(1)決算状況の推移 ※ 前頁表2・3を参照
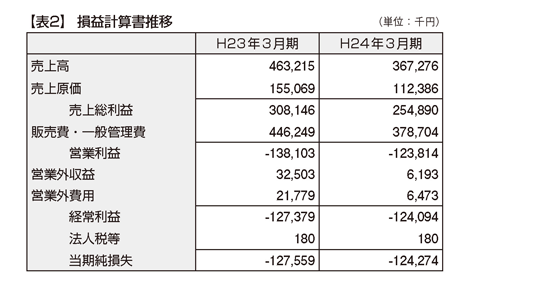
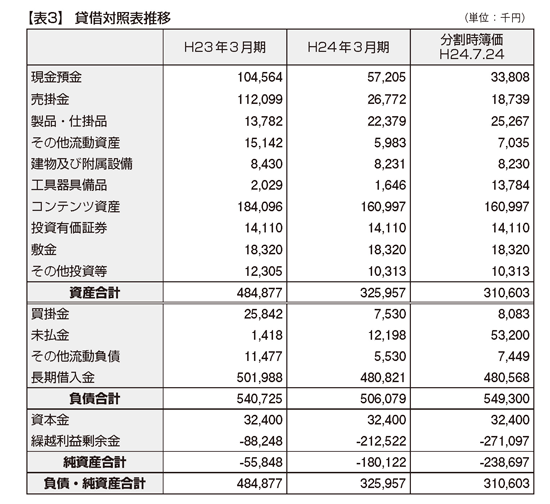
(2)第2会社方式法適用までの経緯
① 財務リストラ策の検討(リスケから第2会社方式へ) 甲社は、現状の厳しい資金繰り状況への対応として、銀行へのリスケジュールを検討していた。しかし、今後の現況を冷静に判断するに、このままの状況が継続するならば近いうちの資金繰り破綻は免れえず会社破綻に至ることは必至の状況と判断された。リスケジュールはあくまでも会社延命策に過ぎず、抜本的な方策ではないと考えられたため、抜本的会社再生策として検討したのが、第2会社方式である。
② 事業リストラ策 事業再生への事業リストラ策として、次の具体的施策を実行することを決定した。事業の選択と集中、原価率改善、成果報酬型給与制度の導入、役員報酬及び給与の大幅減額、販売管理費の大幅節減等。そして更に、毎月1回の定期経営会議の実施、徹底した計数管理を実行することとした。
③ 事業リストラ計画(事業再生計画)の提示 上記②の事業リストラ策を基に「事業再生計画」を取りまとめ、債権者である金融機関に提示し了解を得ることとした。
3 第2会社の設立
(1)会社分割のスキーム概要 当社は中小企業であることから、法的整理の場合には民事再生法の適用が考えられる。しかし、民事再生法の場合、再建計画に入ったことについて公表されることから「倒産」のレッテルが貼られ、得意先及び取引先との円滑な関係に支障が生ずることが多分に懸念されるところである。そのため、私的整理を選択することとし、様々な手法を比較衡量した結果、前述の「協議会」における、第2会社方式による事業再生策を選択することとした。それは、「協議会」という第三者による公平中立な立場により債権者等利害関係人の調整を図ってもらうことができ、債権者からの同意が得られやすいという点で意味が大きかった。
そこで、中小企業承継事業再生計画を作成し、図3の認定要件を満たしていることを確認したうえで、国による計画の認定を受けることとした。
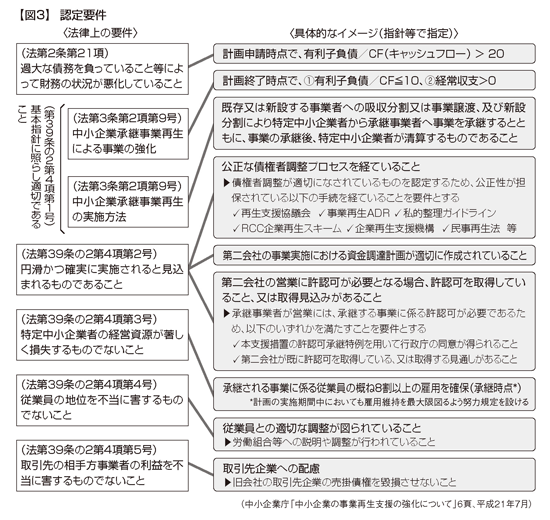
なお、第2会社方式には、事業譲渡による方法と会社分割による方法があるが、甲社は様々な契約関係が多岐にわたっており、これらすべてについて個別に相手方の同意を得ることは、事務手続きが煩雑かつ時間が膨大にかかることから、包括承継である会社分割の方法を選択することとした。
新設分割の手続及び債権者である金融機関(銀行等)への説明と了解のうえ、会社分割は平成24年7月24日に実行するに至った。
会社分割による甲社の第2会社方式のスキーム概要は次頁の図4のとおり。
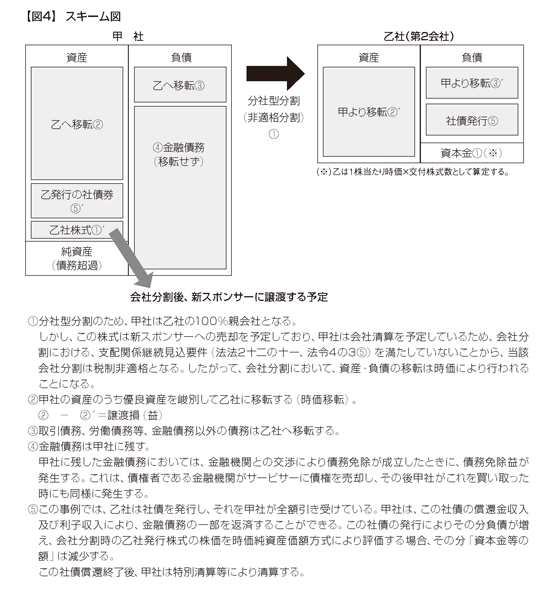
(2)第2会社設立までの数値の流れ 上記のスキームを、甲社の会社分割日現在の貸借対照表に基づき、第2会社設立までの流れを数値例をもって表4・5(29・30頁参照)により示すこととする。
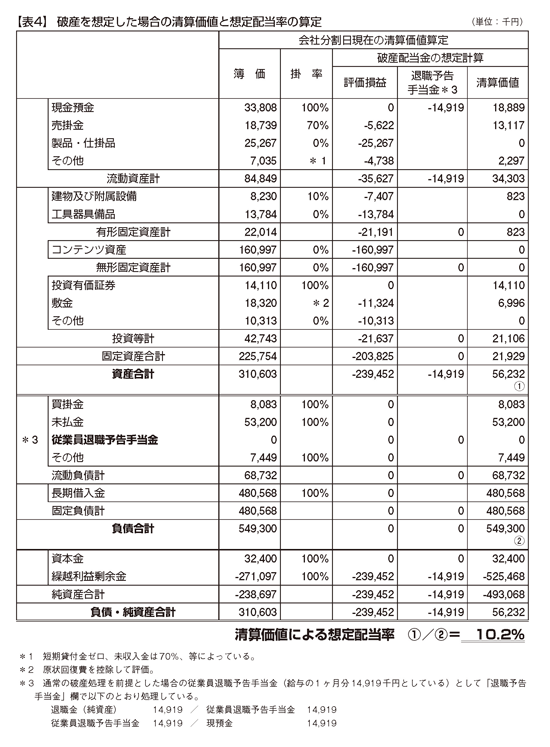
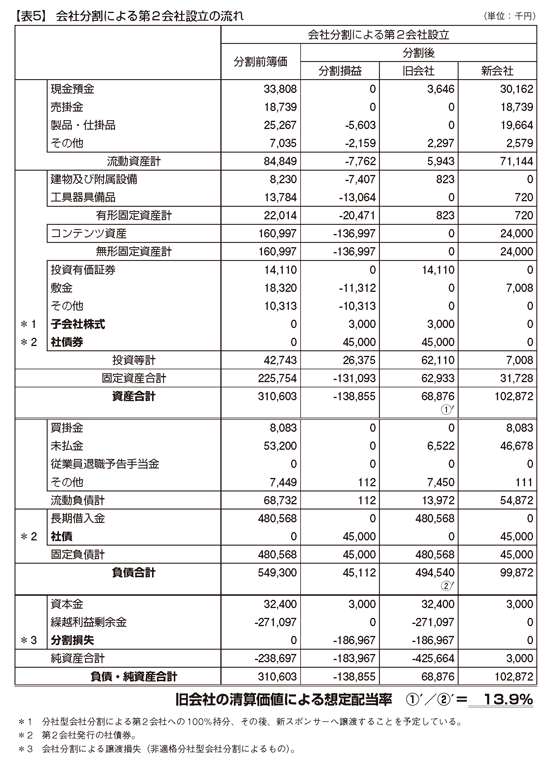
第2会社方式においても、債権者である金融機関への説明上、破産をしたと想定したときの清算価値に基づく配当率を算定し、これよりも第2会社方式による旧会社の配当率の方が上回っていることが要求される。
以下に、「表4 破産を想定した場合の清算価値と想定配当率」(29頁)そして「表5 会社分割による第2会社方式の流れ」(30頁)を会社分割日現在の貸借対照表を基に展開する。
表4、5のとおり、清算した場合の配当率10.2%に対して、会社分割による第2会社方式の場合の甲社(旧会社)の配当率は13.9%であり、この方が大きく、債権者である金融機関としての重要な判断材料になりうるものと考えられる。
(3)新設会社による社債の発行について 甲社は会社分割に際して、事前に債権者である金融機関に説明を行った。金融機関としては、再生計画を簡単に了承できるものではなく、実際には交渉を行う必要がある。そのなかでひとつの有効策として考えられる方法が、事例にある第2会社による「社債」の発行である。
この事例では、会社分割による移転した資産・負債の差額部分(貸方差額)に近い金額で発行しており、その分乙社の負債金額が増額し、資本金等の額を時価純資産価額方式により算定する場合、その分資本金等の額は減額される。本例では、発行条件を次のように想定している。
・発行総額 45,000千円
・引受け者は、全額甲社である。
・1口50万円
・2年据置き、据置後分割償還する。据置き期間中は金利支払いのみ実施。
・金利2%から始め、償還期間の経過につれて2.6%まで徐々に逓増する。
(4)甲社のその後 甲社は、社債を全額引き受けており、その金利収入及び償還金収入を期待でき、それをもって金融機関への借入金返済に充てる予定。
この社債の償還が全額完了した後、甲社は金融機関の了解のもと清算する。清算による税務処理は下記のとおり。
(5)(税務処理):【表5】旧会社の清算価値の数値例を「会社更生」「民事再生」「一定の私的整理」に置き換えた場合の税務処理 表5の旧会社を清算する場合の税務処理は、解散・清算の処理となる。「表5の清算価値」は譲渡損失により生じたものだが、この清算価値の数値例を、「会社更生」「民事再生」「一定の私的再生」という事業再生により生じた評価損によるものに置き換えた場合の税務処理については後述する。
(以上、資料協力 株式会社事業パートナー)
解 説 編
事業再生の税務・会計については、日本公認会計士協会、経営研究調査会研究報告47号「事業再生実務と公認会計士の役割」平成24年3月1日(以下「研究報告47号」という。)が詳しい。以下、「研究報告47号」を参考にして解説する。
Ⅳ 解説編・事業再生の税務・会計
事業再生における税務の最大の論点は、債務免除益に課税を受けることなく事業再生が可能に遂行できるかどうかにある。事業再生税制では、青色繰越欠損金の控除のほか、これに対応して主に資産の評価損益や期限切れ欠損金の控除の特例を設けている。
1 資産の評価損益 各種事業再生手続の過程で債務処理計画等が承認され、債権放棄が確定すると債務免除益が計上される。これに対応して、法人税法上は再生企業に対しての例外規定として、資産の評価益(及び評価益)の計上を認めている。債務処理計画等において、この特例と欠損金の特例を組み合わせ、債務免除益課税を軽減することが可能となる。法人税法上のこの例外規定は、会社更生法の場合、民事再生法及び一定の私的整理の場合、各々について下記のとおり取扱いが異なっている。
(1)会社更生法の場合 会社更生法第232条第2項により、更生手続開始の決定があったときは、更生会社の事業年度は、その開始の時に終了し、これに続く事業年度は、更生計画認可の時に終了する。会社更生法の適用を受けた場合、管財人は、更生手続開始後遅滞なく、更生手続開始時点における更生会社のすべての財産につき、時価を基準とする財産評定を行う必要がある(更生法83)。この財産評定額は、更生会社の認可決定時貸借対照表及び財産目録における取得価額とみなされ会計帳簿の基礎となる(更生則1②、会社計算規則5①・②)。
会社更生法の規定による更生計画認可の決定があった場合、財産評定手続による評定が行われ、会計帳簿に反映した資産の評価益の益金算入及び資産の評価損の損金算入が行われる(法法25②、同33③)、評価換えによって減額又は増額された金額が更生計画の認可日を期末とする事業年度の評価損益となる。
(2)民事再生法の場合 民事再生法の規定による民事再生手続開始の決定があった場合、会社更生法の取扱いと異なり、事業年度の特例が定められておらず、通常どおりの事業年度で決算を行い、法人税等の確定申告を行うことになる。
『民事再生においても財産評定手続が設けられている(民再法124)が、その目的は会社更生の財産評定の結果が更生会社の会計帳簿の基礎となるのに対して、民事再生では、債権者が再生計画の適否を破産した場合の配当率と比較して判断するための資料とすることを目的としているため、原則として財産を処分するものとして行う(民事再生規則56①)こととされている。このため、民事再生の財産評定の結果がそのまま会計帳簿に反映するものではなく、民事再生会社が資産評定を行う場合には財産評定とは別に事業の継続を前提とした価額(法人税法上は法人税法上の時価(法基通4-1-3、同9-1-3等))を算定して進めることが必要となる。』(「経営研究調査会研究報告第47号」37頁、日本公認会計士協会)。
民事再生の場合、資産の評価損益を計上する方法として、「損金経理により資産の評価損を計上する方法(法法33②、法令68条)」と、「別表添付により資産の評価損益を計上する方法(法法25③及び33④)」が認められている。この両方式は、重複適用は認められず、いずれかを選択することとなる(法令68②)、損金経理方式は評価損のみだが別表添付方式は評価損の他に評価益の計上も要求されている等、その要件の違いに留意して検討する必要がある。
① 損金経理方式(法法33②) 法的整理の事実(会社更生の規定による更生手続における評定が行われることに準ずる特別の事実をいう)が生じた場合には、損金経理を行うことにより、事業年度末の時価まで評価損を計上できることとされ(法令68①)、民事再生法による再生手続開始の決定があった場合が、この「準ずる特別の事実」に該当すると考えられる(法基通9-1-3の3)。
したがって、民事再生法の再生手続開始の決定があった日の属する事業年度において損金経理を行う場合には、損金経理を行った部分の金額のうち、その評価替えの直前の当該資産の帳簿価額とその評価替えをした日の属する事業年度終了の時における当該資産の価額との差額に達するまでの金額について、法人税法上の評価損の計上が認められる(法法33②)。
なお、これは税務上、損金経理を要件としているので、一般に公正妥当と認められる会計処理の基準(以下「公正処理基準」という。)の適用により、評価損が計上できない場合には、要件を満たせないことが考えられる。
② 別表添付方式(法法25③、同33④) 民事再生法の規定による再生計画認可の決定があった場合、確定申告書に必要な別表を添付することにより資産の評価損の損金算入が認められるが、この場合資産には評価益の益金算入も行わなければならない(「別表添付方式」、法法25③、同33④)。
ア.資産の評価損益計上対象外の資産 次のものは資産の評価損益対象資産から外されている(法令24の2④)。
ⅰ 圧縮記帳の適用を受けた資産のうち、一定のもの
ⅱ 短期売買商品
ⅲ 売買目的有価証券
ⅳ 償還有価証券
ⅴ その資産の価額とその帳簿価額との差額が当該法人の認可決定時(法基通4-1-9)の資本金等の額の2分の1に相当する金額と1,000万円(中小規模再生(有利子負債の額が10億円未満である企業再生)の場合には100万円)とのいずれか少ない金額に満たない場合の、その資産
ここで、注意しなければならないのは、ⅴの規定であり、評価損益の金額が少額なものについては、評価損益の計上の対象とはならない点である(損金経理方式にはこのような金額制限自体がない。)。
イ.会計基準を尊重する 民事再生会社は会社更生と異なり、再生手続の開始決定をもって資産の評価換えを行うべき事象には該当しないため、資産の評価替えを行うには減損会計等の会計基準を援用することが必要とされる。別表添付方式の適用を受けるには、会計基準により損益計算書に計上される評価損の対象とならない場合、原則としては資産の評価替えを行うことはできないが、損金経理は要件とされていない。したがって、損金経理を行わなかった場合には、申告調整により減算調整をすることとなる(減算調整が原則とはなっているが、損金経理処理も認められる。)。この適用を受ける場合には、確定申告書に「評価損明細」及び「評価益明細」を添付することが要件とされている。
以上のように、①、②両方式においては、資産の評価損益の計上時点が異なっていることに留意が必要である。すわなち、損金経理方式の場合は、民事再生法による場合その再生手続開始の決定の日、別表添付方式の場合は、同法による再生計画認可の決定の日である。
(3)一定の私的整理の場合 一定の私的整理の場合においても、資産の価額につき一定の評定を行っているときは、民事再生法の別表添付方式の場合と同様、評価損益の計上を行うことができる(法法25③及び同33④)。ただし、一定の要件を満たす「債務処理計画」に基づくものであることが必要である。
私的整理の場合も民事再生の場合と同様、会計基準を尊重し、減損会計等の企業会計の基準に基づく評価損に限られることになるので、会計上は評価替えができない資産が生じ得るため、別表添付方式により評価損を計上(法法33④)する場合、損金経理は要件ではないが、そのときには申告書の減額調整は必要となる。
この要件を満たしたものについては、評価損益の計上ができ、期限切れ欠損金を青色欠損金に優先して使用することができる(法法59②三)。ここに、一定の要件を満たす「債務処理計画」とは、次のものをいう。
一定の私的整理の要件 ① 一般に公表された債務処理を行うための手続についての準則に従って策定されていること(法令24の2①一)。
② 債務者の有する資産及び負債につき①に従って資産評定が行われ、当該資産評定による価額を基礎とした当該債務者の貸借対照表が作成されていること(法令24の2①二)
③ ②の貸借対照表における資産及び負債の価額、当該計画における損益の見込み等に基づいて債務者に対して債務の免除をする金額が定められていること(法令24の2①三)
④ 2以上の金融機関等が債務免除等(※)をすることが定められていること(法令24の2①四)。
⑤ 一定の政府関係金融機関又は協定銀行(RCC)が有する債権その他財務省令で定める債権につき債務免除等(※)をすることが定められていること(法令24の2①五)。なお、政府関係金融機関とは株式会社日本政策金融公庫及び沖縄振興開発金融公庫をいう(法令24の2②一)。
※ 債務免除等とは債務の免除又は債権のその債務者に対する現物出資による移転(いわゆるDESにより見込まれる債務消滅益が生じる場合)をいう(法令24の2②三)。
2 欠損金
(1)概要 法人税法においては、資産の評価損の損金算入規定とともに、債務免除益課税を軽減するために一定の欠損金の損金算入を認める特例規定が設けられている。
この特例規定で問題となる点は下記のとおりである。
① 損金の額に算入する欠損金の範囲 元々、法人税法では青色欠損金の損金算入規定が設けられているが、その青色欠損金の繰越期間を超過した期限切れ欠損金を使用することができるかどうかが問題となる。
② 青色欠損金と期限切れ欠損金の使用順序 上記①で述べた期限切れ欠損金を使用できる場合において、青色欠損金と期限切れ欠損金のどちらを先に使用できるのかが問題となる。もちろん期限切れ欠損金を先に使用したほうが有利である。
③ 資産の評価損と期限切れ欠損金の使用順序 資産の評価損と期限切れ欠損金の両方を使用できる場合において、どちらを優先的に使用できるかが問題となる。一定の場合には資産の評価損の金額は青色欠損金として引き継ぐことができるので、期限切れ欠損金を先に使用したほうが有利となる。
上記の関係については、後述「資産の評価損・期限切れ欠損金・青色欠損金等の関係」に示すとおりであるが、ここでも法律等による各手続き制度自体の厳格性・保守性を考慮して各手続間で差異が設けられている。
法人税法で規定する各手続の欠損金の特例規定は下記のとおりである。
(2)会社更生等により債務免除等があった場合の欠損金の取扱い
① 会社更生等の場合の欠損金の損金算入額(法法59①) 以下のいずれか少ない金額
i.(a)
ii.債務免除益等 + 私財提供益等 +(評価益-評価損)(マイナスの場合は、ゼロ)
② 民事再生等又は一定の私的整理の場合で一定の評価損益の計上があるときの欠損金の損金算入額(法法59②) i.(a)
ii.債務免除益等 + 私財提供益等 +(評価益-評価損)(マイナスの場合は、マイナス)
iii.所得金額(欠損金等の控除前)(「別表四の総額差引計」)
③ 民事再生等又は一定の私的整理の場合で一定の評価損益の計上がないときの欠損金の損金算入額(法法59②) i.(a)-(b)
ii.債務免除益等+私財提供益等
iii.所得金額(青色欠損金等の損金算入額の控除後)(「別表四の総額差引計-(b)」)
なお、上記(a)について、法人税法施行令第116条の3又は第117条の2第一号においては「前事業年度以前の事業年度より繰り越された欠損金額の合計額」と規定しており、法人税基本通達12-3-2で「利益積立金額のマイナスの金額」とされているが、筆者の意見として「前事業年度以前の事業年度より繰り越された欠損金額の合計額=利益積立金額のマイナスの金額」とすることについて疑問を呈するところである。詳細については省略させていただくが、本来欠損金と利益積立金は全く異なるものである。したがって、法人税法施行令第116条の3又は第117条の2第一号の「前事業年度以前の事業年度より繰り越された欠損金額の合計額」に関しては、過去の欠損金額の合計額と解するべきではないだろうか。
(朝長英樹『期限切れ欠損金の額』、本誌471号24頁参照)
(3)青色欠損金の繰越金額 平成23年12月改正の「青色欠損金の損金算入の80%制限」に伴い、法人税法第59条(会社更生等があった場合の欠損金の損金算入)に関して、下記の制度が追加された。
下記により青色欠損金の繰越金額が定められている。
① 会社更生法等の場合の青色欠損金の繰越金額(法法57⑤、法令112⑨) 上記(2)①の適用を受ける場合には、その適用事業年度以後の事業年度の所得の計算上、青色欠損金額のうち上記(2)①で損金の額に算入される金額として次の算式により計算した金額はないものとされる。
(算式)
ⅰ-ⅱの金額(マイナスの場合は、ゼロ)
② 民事再生等又は一定の私的整理の場合で一定の評価損益の計上があるときの欠損金の損金算入額(法法57⑤、法令112⑨)
上記(2)②の適用を受ける場合には、その適用事業年度以後の各事業年度の所得の計算上、青色欠損金額のうち上記(2)②で損金の額に算入される金額として次の算式により計算した金額はないものとされる。
(算式)
ⅰ-ⅱの金額(マイナスの場合は、ゼロ)
③ 民事再生等又は一定の私的整理の場合で一定の評価損益の計上がないときの欠損金の損金算入額(法法57⑤、法令112⑨)
上記(2)③の適用を受ける場合には、当該適用年度以後の各事業年度の所得の金額の計算上、青色欠損金額のうち上記(2)③で損金の額に算入される金額として次に掲げる金額はないものとする。
上記(2)③により適用年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額
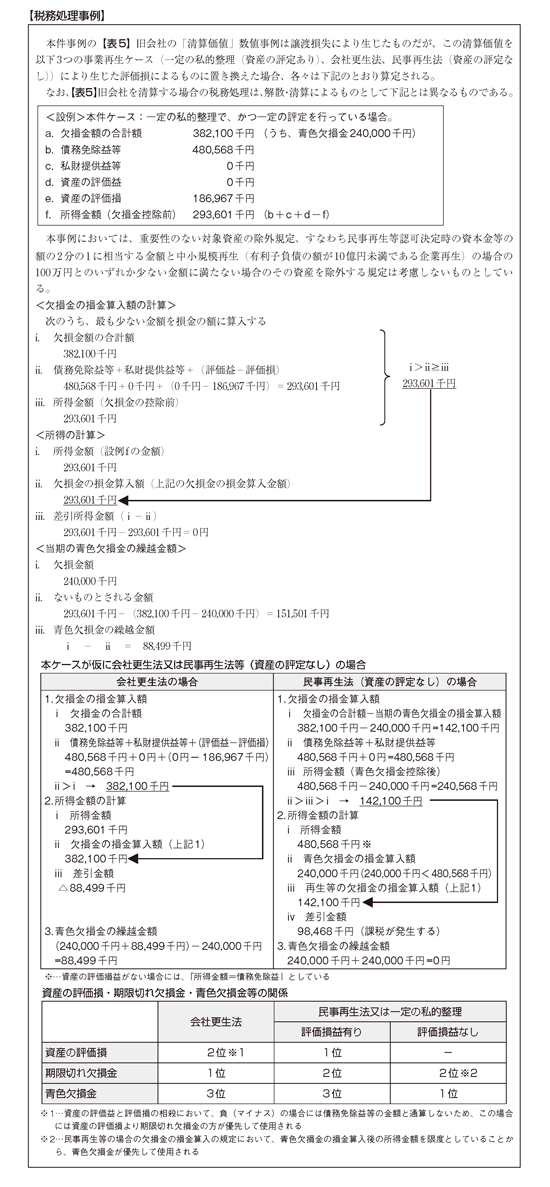
3 第2会社方式と税制 前述のように、第2会社方式による事業再生においては、事業譲渡型と会社分割型とがある。これらの税制上の課題は、下記のとおりである。
① 分社型会社分割の組織再編税制における適格・非適格判定 事例において既述したように、会社分割型は分社型会社分割によることとなり、これは組織再編税制においては税制非適格となる。なぜなら、分割法人(旧会社)が所有する分割承継法人(移転先法人)の株式は、新スポンサーへの売却を予定しており、旧会社は清算を予定していることから、支配関係継続見込要件(法法2十二の十一、法令4の3⑤)を満たしていないためである。したがって、資産・負債の移転は時価によることとなる。
② 資産・負債の譲渡価額の妥当性 事業譲渡においては、資産・負債の移転は時価により行われる。会社分割においても、上記①のとおり時価によることとなる。いずれにおいても、譲渡金額の妥当性の問題が主ずる。
③ のれんの償却 資産・負債の譲渡は時価により行われることから、会計上の「のれん」または「負ののれん」が生ずることがある。これらは、法人税法上は「資産調整勘定(法法62の8①)」または「負債調整勘定(法法62の8③)」となる。これらの償却については、60ケ月による均等償却を行うことになる(資産調整勘定償却は法法62の8④、負債調整勘定償却は法法62の8⑦)。
④ 移転にかかる諸税金 ⅰ.不動産取得税
会社分割により不動産を取得した場合、下記のすべての要件を満たした場合に限り、不動産取得税は課されない(地方税法73の7二、地方税法施行令37の14)。
・会社分割に伴って金銭等の交付がないこと
・分割事業に係る主要な資産及び負債が分割承継法人に移転していること
・分割事業が分割承継法人において引き続き営まれることが見込まれていること
・分割直前の分割事業に係る従業者のうち、その総数の概ね80%以上に相当する数の者が分割後に分割承継法人の業務に従事することが見込まれていること
このように、法人税法上の税制非適格ではあっても、不動産取得税では要件を満たせば非課税とすることが可能となる。
ⅱ.登録免許税
土地及び建物の登録免許税は、「事業譲渡」の場合、固定資産税評価額に対して1,000分の20。会社分割では、下記のとおり軽減されている。
平成24年4月1日から平成26年3月31日まで、 1,000分の15
平成26年4月1日から平成27年3月31日まで、 1,000分の18
ⅲ.消費税
会社分割型は課税対象外に該当、事業譲渡型は課税に該当する。
ただし、会社分割型の場合でも、分割型分割を行った後に分割承継法人の株式を新スポンサーに譲渡する場合には、当該株式の譲渡は非課税取引に該当するため、債務者企業の課税売上取引の計算上、株式の譲渡価額の5%について非課税取引として考慮することから(消法6①、消令48⑤)、債務者企業の仕入税額控除の計算に影響を与えることになる。
参考文献
・日本公認会計士協会 経営研究調査会研究報告第47号「事業再生実務と公認会計士の役割」平成24年3月1日
・事例の資料協力:株式会社事業パートナー
・「ケース別にわかる企業再生の税務 第2版」中央経済社、稲見誠一、佐藤信祐著
棟田裕幸 むねた ひろゆき
公認会計士・税理士。大手監査法人等を経て、1995年棟田公認会計士・税理士事務所開設(現在に至る)、1999年株式会社BSM設立(現在に至る)。公認会計士試験・修了考査(経営科目元出題委員)、日本公認会計士協会東京実務補習所運営委員会(元委員長)、日本公認会計士協会東京会調査研究部税務委員会(元副委員長)等を歴任。著作として、『組織再編の手法と会計・税務Q&A』(編者、中央経済社)、『会社合併実務必携』(共著、法令出版)、『Q&A 株主資本の実務』(共著、新日本法規出版)など。
事業再生実務の税務・会計
-第2会社方式による事業再生事例の研究等-
公認会計士・税理士 棟田裕幸
Ⅰ 序 論
中小企業に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律(以下「中小企業金融円滑化法」という。)は、平成25年3月31日をもって終了する。その後は、多くの中小企業が金融機関に対して条件変更を申し入れた場合に、法律の後ろ盾がなくなることから、従来のように応じてもらえなくなることが予想され、多くの中小企業が相当に厳しい立場に追い込まれることが予想される。かような事態に遭遇した中小企業は、今後どうすればよいのか、今回は、事業再生実務の事例研究として、中小企業において従来から多くの事例がある第2会社方式による事業再生実務を例にとり、具体的数値例をもって流れを追うとともに、その税務処理、会計処理についても言及することとしたい。
Ⅱ 事例編・事業再生実務の研究
事業再生の手続は、前回(本誌476号26頁参照)「実務解説 事業再生実務の法務」(以下「法務編」という。)のとおり、大きく分けて法的整理と私的整理があり、法的整理とは裁判所が関与する再建手続、私的整理とは裁判所が関与しない再建手続をいう。
実務において私的整理は、再建手続に入ったことが公表されないため、「倒産」のレッテルが貼られることを回避できる、取引業者に対する債務を債務整理の対象としないことから取引業者との関係を円滑に保つことができる、というようなメリットがあることから、実務では使われることが多い。私的整理には、前回「法務編」のとおり、様々な手法が存在するが、中小企業においては、第三者が介入する私的整理手法としての「中小企業再生支援協議会(以下「協議会」という。)」の支援による再生が行われることが多い。
表1の「協議会」金融支援の活動状況のとおり、①金融機関による条件変更(リスケジュール)が70.0%、②事業譲渡・会社分割による第2会社方式が10.6%、③デット・デット・スワップ(以下「DDS」という。)(DDS1及びDDS2合わせて)が7.4%、という順で適用されている。
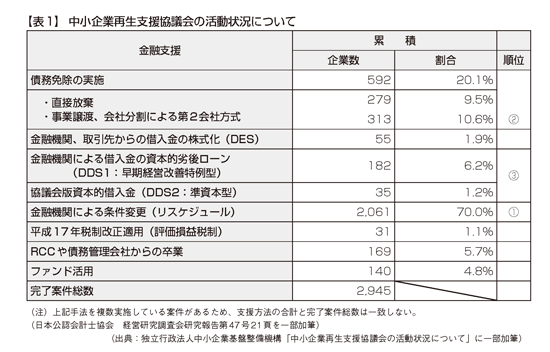
今回は、①リスケジュールで金融機関への支援要請を検討したが、会社の置かれた厳しい実情を鑑みた結果として、抜本的事業再生策として有効な手法としての、②第2会社方式による事業再生策を実施した事例を紹介する。
Ⅲ 私的整理における第2会社方式について
「中小企業再生支援協議会スキーム」の金融支援の方法として、第2会社方式が存在する。その全体的な概要は図1のとおり。事業部門を優良部門と不採算部門とに分け、優良部門を第2会社に移転し、過剰な金融債務等を旧会社に残し、身軽になったところで、新会社により新たな事業存続を図るものである。残った旧会社はその後特別清算等により清算する。
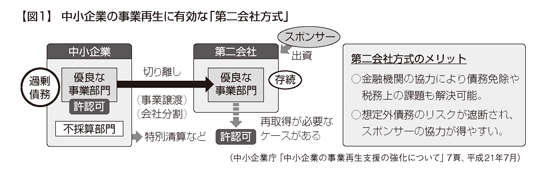
第2会社方式には大きく分けて、事業譲渡型と会社分割型とがある。各々の受け皿会社が、既存会社か新設会社かによって、図2のようなパターンが考えられる。今回紹介した事例は、図2の「(3)新設分割型」である。
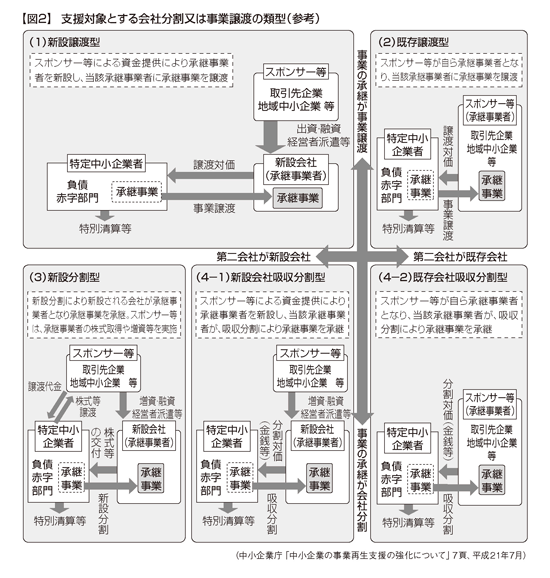
【事例研究】第2会社方式(会社分割)による事業再生の事例
1 会社の概要 (業種)
コンテンツ及びソフトウェアの制作・開発
(主要製品)
ゲームソフト等のコンテンツ制作、ソフトウェア製品の開発、その他
(相談時の直近の業績)
平成23年3月期 売上高 463百万円(経常利益 △127百万円)
平成24年3月期 売上高 367百万円(経常利益 △124百万円)
(業歴)30年
(従業員数)40人
2 会社の状況説明 (相談時の状況及び相談内容(平成23年4月))
今後の売上の見込みはあるが、運転資金、夏季賞与支払い等の資金繰りが厳しい状況のため、1億円程度の資金調達の支援を希望。
・相談時の銀行借入金残高
約530百万円(月額返済額約12百万円)
・相談時の月次決算状況
年々売上は減少、損失体質が定着化。
・相談時のキャッシュフロー状況
資金繰り状況はますます悪化。
(1)決算状況の推移 ※ 前頁表2・3を参照
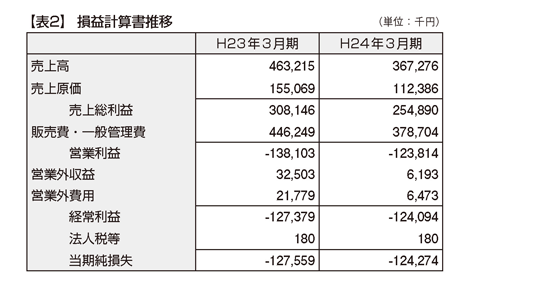
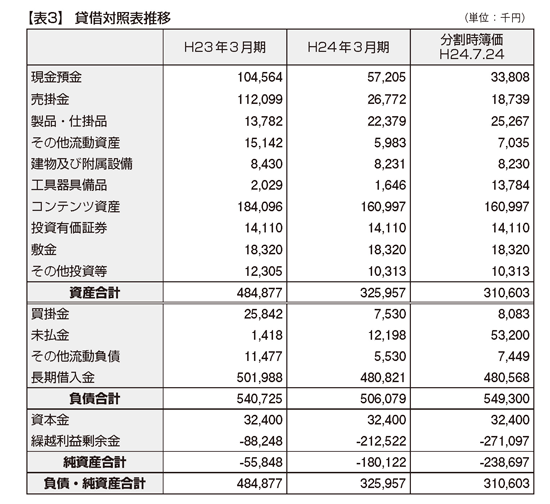
(2)第2会社方式法適用までの経緯
① 財務リストラ策の検討(リスケから第2会社方式へ) 甲社は、現状の厳しい資金繰り状況への対応として、銀行へのリスケジュールを検討していた。しかし、今後の現況を冷静に判断するに、このままの状況が継続するならば近いうちの資金繰り破綻は免れえず会社破綻に至ることは必至の状況と判断された。リスケジュールはあくまでも会社延命策に過ぎず、抜本的な方策ではないと考えられたため、抜本的会社再生策として検討したのが、第2会社方式である。
② 事業リストラ策 事業再生への事業リストラ策として、次の具体的施策を実行することを決定した。事業の選択と集中、原価率改善、成果報酬型給与制度の導入、役員報酬及び給与の大幅減額、販売管理費の大幅節減等。そして更に、毎月1回の定期経営会議の実施、徹底した計数管理を実行することとした。
③ 事業リストラ計画(事業再生計画)の提示 上記②の事業リストラ策を基に「事業再生計画」を取りまとめ、債権者である金融機関に提示し了解を得ることとした。
3 第2会社の設立
(1)会社分割のスキーム概要 当社は中小企業であることから、法的整理の場合には民事再生法の適用が考えられる。しかし、民事再生法の場合、再建計画に入ったことについて公表されることから「倒産」のレッテルが貼られ、得意先及び取引先との円滑な関係に支障が生ずることが多分に懸念されるところである。そのため、私的整理を選択することとし、様々な手法を比較衡量した結果、前述の「協議会」における、第2会社方式による事業再生策を選択することとした。それは、「協議会」という第三者による公平中立な立場により債権者等利害関係人の調整を図ってもらうことができ、債権者からの同意が得られやすいという点で意味が大きかった。
そこで、中小企業承継事業再生計画を作成し、図3の認定要件を満たしていることを確認したうえで、国による計画の認定を受けることとした。
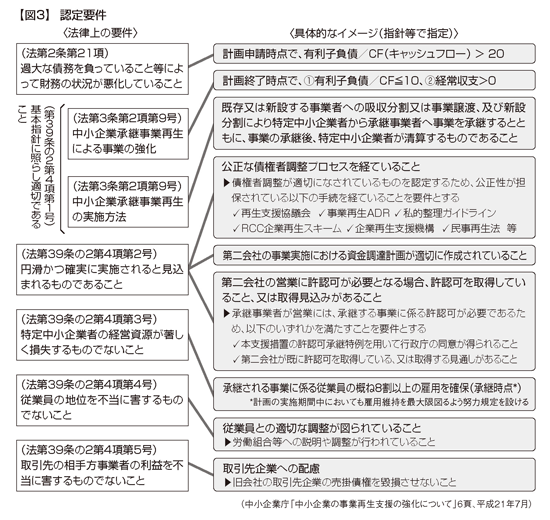
なお、第2会社方式には、事業譲渡による方法と会社分割による方法があるが、甲社は様々な契約関係が多岐にわたっており、これらすべてについて個別に相手方の同意を得ることは、事務手続きが煩雑かつ時間が膨大にかかることから、包括承継である会社分割の方法を選択することとした。
新設分割の手続及び債権者である金融機関(銀行等)への説明と了解のうえ、会社分割は平成24年7月24日に実行するに至った。
会社分割による甲社の第2会社方式のスキーム概要は次頁の図4のとおり。
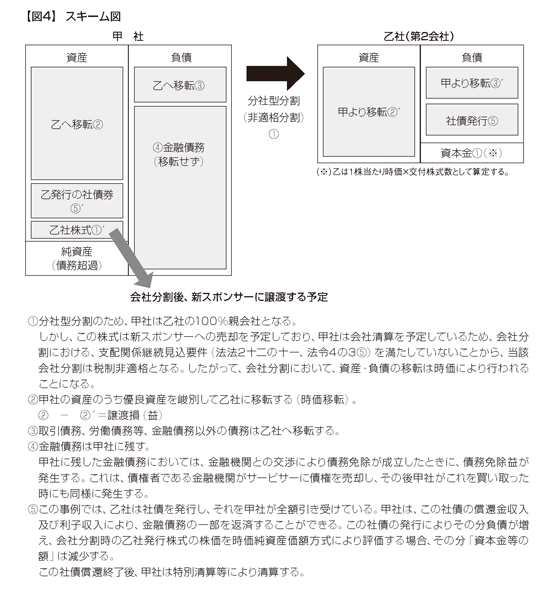
(2)第2会社設立までの数値の流れ 上記のスキームを、甲社の会社分割日現在の貸借対照表に基づき、第2会社設立までの流れを数値例をもって表4・5(29・30頁参照)により示すこととする。
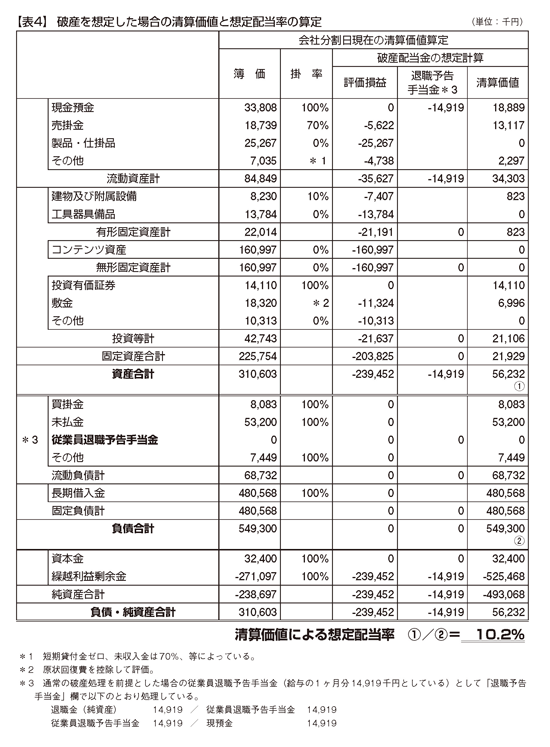
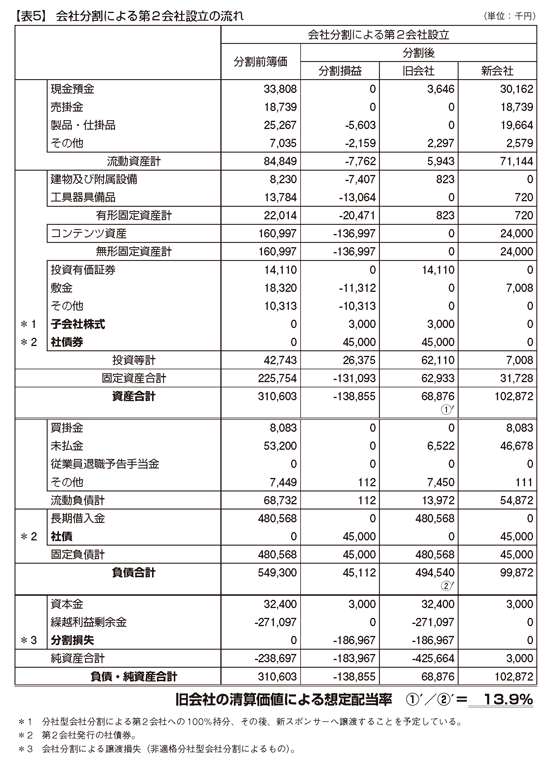
第2会社方式においても、債権者である金融機関への説明上、破産をしたと想定したときの清算価値に基づく配当率を算定し、これよりも第2会社方式による旧会社の配当率の方が上回っていることが要求される。
以下に、「表4 破産を想定した場合の清算価値と想定配当率」(29頁)そして「表5 会社分割による第2会社方式の流れ」(30頁)を会社分割日現在の貸借対照表を基に展開する。
表4、5のとおり、清算した場合の配当率10.2%に対して、会社分割による第2会社方式の場合の甲社(旧会社)の配当率は13.9%であり、この方が大きく、債権者である金融機関としての重要な判断材料になりうるものと考えられる。
(3)新設会社による社債の発行について 甲社は会社分割に際して、事前に債権者である金融機関に説明を行った。金融機関としては、再生計画を簡単に了承できるものではなく、実際には交渉を行う必要がある。そのなかでひとつの有効策として考えられる方法が、事例にある第2会社による「社債」の発行である。
この事例では、会社分割による移転した資産・負債の差額部分(貸方差額)に近い金額で発行しており、その分乙社の負債金額が増額し、資本金等の額を時価純資産価額方式により算定する場合、その分資本金等の額は減額される。本例では、発行条件を次のように想定している。
・発行総額 45,000千円
・引受け者は、全額甲社である。
・1口50万円
・2年据置き、据置後分割償還する。据置き期間中は金利支払いのみ実施。
・金利2%から始め、償還期間の経過につれて2.6%まで徐々に逓増する。
(4)甲社のその後 甲社は、社債を全額引き受けており、その金利収入及び償還金収入を期待でき、それをもって金融機関への借入金返済に充てる予定。
この社債の償還が全額完了した後、甲社は金融機関の了解のもと清算する。清算による税務処理は下記のとおり。
(5)(税務処理):【表5】旧会社の清算価値の数値例を「会社更生」「民事再生」「一定の私的整理」に置き換えた場合の税務処理 表5の旧会社を清算する場合の税務処理は、解散・清算の処理となる。「表5の清算価値」は譲渡損失により生じたものだが、この清算価値の数値例を、「会社更生」「民事再生」「一定の私的再生」という事業再生により生じた評価損によるものに置き換えた場合の税務処理については後述する。
(以上、資料協力 株式会社事業パートナー)
解 説 編
事業再生の税務・会計については、日本公認会計士協会、経営研究調査会研究報告47号「事業再生実務と公認会計士の役割」平成24年3月1日(以下「研究報告47号」という。)が詳しい。以下、「研究報告47号」を参考にして解説する。
Ⅳ 解説編・事業再生の税務・会計
事業再生における税務の最大の論点は、債務免除益に課税を受けることなく事業再生が可能に遂行できるかどうかにある。事業再生税制では、青色繰越欠損金の控除のほか、これに対応して主に資産の評価損益や期限切れ欠損金の控除の特例を設けている。
1 資産の評価損益 各種事業再生手続の過程で債務処理計画等が承認され、債権放棄が確定すると債務免除益が計上される。これに対応して、法人税法上は再生企業に対しての例外規定として、資産の評価益(及び評価益)の計上を認めている。債務処理計画等において、この特例と欠損金の特例を組み合わせ、債務免除益課税を軽減することが可能となる。法人税法上のこの例外規定は、会社更生法の場合、民事再生法及び一定の私的整理の場合、各々について下記のとおり取扱いが異なっている。
(1)会社更生法の場合 会社更生法第232条第2項により、更生手続開始の決定があったときは、更生会社の事業年度は、その開始の時に終了し、これに続く事業年度は、更生計画認可の時に終了する。会社更生法の適用を受けた場合、管財人は、更生手続開始後遅滞なく、更生手続開始時点における更生会社のすべての財産につき、時価を基準とする財産評定を行う必要がある(更生法83)。この財産評定額は、更生会社の認可決定時貸借対照表及び財産目録における取得価額とみなされ会計帳簿の基礎となる(更生則1②、会社計算規則5①・②)。
会社更生法の規定による更生計画認可の決定があった場合、財産評定手続による評定が行われ、会計帳簿に反映した資産の評価益の益金算入及び資産の評価損の損金算入が行われる(法法25②、同33③)、評価換えによって減額又は増額された金額が更生計画の認可日を期末とする事業年度の評価損益となる。
(2)民事再生法の場合 民事再生法の規定による民事再生手続開始の決定があった場合、会社更生法の取扱いと異なり、事業年度の特例が定められておらず、通常どおりの事業年度で決算を行い、法人税等の確定申告を行うことになる。
『民事再生においても財産評定手続が設けられている(民再法124)が、その目的は会社更生の財産評定の結果が更生会社の会計帳簿の基礎となるのに対して、民事再生では、債権者が再生計画の適否を破産した場合の配当率と比較して判断するための資料とすることを目的としているため、原則として財産を処分するものとして行う(民事再生規則56①)こととされている。このため、民事再生の財産評定の結果がそのまま会計帳簿に反映するものではなく、民事再生会社が資産評定を行う場合には財産評定とは別に事業の継続を前提とした価額(法人税法上は法人税法上の時価(法基通4-1-3、同9-1-3等))を算定して進めることが必要となる。』(「経営研究調査会研究報告第47号」37頁、日本公認会計士協会)。
民事再生の場合、資産の評価損益を計上する方法として、「損金経理により資産の評価損を計上する方法(法法33②、法令68条)」と、「別表添付により資産の評価損益を計上する方法(法法25③及び33④)」が認められている。この両方式は、重複適用は認められず、いずれかを選択することとなる(法令68②)、損金経理方式は評価損のみだが別表添付方式は評価損の他に評価益の計上も要求されている等、その要件の違いに留意して検討する必要がある。
① 損金経理方式(法法33②) 法的整理の事実(会社更生の規定による更生手続における評定が行われることに準ずる特別の事実をいう)が生じた場合には、損金経理を行うことにより、事業年度末の時価まで評価損を計上できることとされ(法令68①)、民事再生法による再生手続開始の決定があった場合が、この「準ずる特別の事実」に該当すると考えられる(法基通9-1-3の3)。
したがって、民事再生法の再生手続開始の決定があった日の属する事業年度において損金経理を行う場合には、損金経理を行った部分の金額のうち、その評価替えの直前の当該資産の帳簿価額とその評価替えをした日の属する事業年度終了の時における当該資産の価額との差額に達するまでの金額について、法人税法上の評価損の計上が認められる(法法33②)。
なお、これは税務上、損金経理を要件としているので、一般に公正妥当と認められる会計処理の基準(以下「公正処理基準」という。)の適用により、評価損が計上できない場合には、要件を満たせないことが考えられる。
② 別表添付方式(法法25③、同33④) 民事再生法の規定による再生計画認可の決定があった場合、確定申告書に必要な別表を添付することにより資産の評価損の損金算入が認められるが、この場合資産には評価益の益金算入も行わなければならない(「別表添付方式」、法法25③、同33④)。
ア.資産の評価損益計上対象外の資産 次のものは資産の評価損益対象資産から外されている(法令24の2④)。
ⅰ 圧縮記帳の適用を受けた資産のうち、一定のもの
ⅱ 短期売買商品
ⅲ 売買目的有価証券
ⅳ 償還有価証券
ⅴ その資産の価額とその帳簿価額との差額が当該法人の認可決定時(法基通4-1-9)の資本金等の額の2分の1に相当する金額と1,000万円(中小規模再生(有利子負債の額が10億円未満である企業再生)の場合には100万円)とのいずれか少ない金額に満たない場合の、その資産
ここで、注意しなければならないのは、ⅴの規定であり、評価損益の金額が少額なものについては、評価損益の計上の対象とはならない点である(損金経理方式にはこのような金額制限自体がない。)。
イ.会計基準を尊重する 民事再生会社は会社更生と異なり、再生手続の開始決定をもって資産の評価換えを行うべき事象には該当しないため、資産の評価替えを行うには減損会計等の会計基準を援用することが必要とされる。別表添付方式の適用を受けるには、会計基準により損益計算書に計上される評価損の対象とならない場合、原則としては資産の評価替えを行うことはできないが、損金経理は要件とされていない。したがって、損金経理を行わなかった場合には、申告調整により減算調整をすることとなる(減算調整が原則とはなっているが、損金経理処理も認められる。)。この適用を受ける場合には、確定申告書に「評価損明細」及び「評価益明細」を添付することが要件とされている。
以上のように、①、②両方式においては、資産の評価損益の計上時点が異なっていることに留意が必要である。すわなち、損金経理方式の場合は、民事再生法による場合その再生手続開始の決定の日、別表添付方式の場合は、同法による再生計画認可の決定の日である。
(3)一定の私的整理の場合 一定の私的整理の場合においても、資産の価額につき一定の評定を行っているときは、民事再生法の別表添付方式の場合と同様、評価損益の計上を行うことができる(法法25③及び同33④)。ただし、一定の要件を満たす「債務処理計画」に基づくものであることが必要である。
私的整理の場合も民事再生の場合と同様、会計基準を尊重し、減損会計等の企業会計の基準に基づく評価損に限られることになるので、会計上は評価替えができない資産が生じ得るため、別表添付方式により評価損を計上(法法33④)する場合、損金経理は要件ではないが、そのときには申告書の減額調整は必要となる。
この要件を満たしたものについては、評価損益の計上ができ、期限切れ欠損金を青色欠損金に優先して使用することができる(法法59②三)。ここに、一定の要件を満たす「債務処理計画」とは、次のものをいう。
一定の私的整理の要件 ① 一般に公表された債務処理を行うための手続についての準則に従って策定されていること(法令24の2①一)。
② 債務者の有する資産及び負債につき①に従って資産評定が行われ、当該資産評定による価額を基礎とした当該債務者の貸借対照表が作成されていること(法令24の2①二)
③ ②の貸借対照表における資産及び負債の価額、当該計画における損益の見込み等に基づいて債務者に対して債務の免除をする金額が定められていること(法令24の2①三)
④ 2以上の金融機関等が債務免除等(※)をすることが定められていること(法令24の2①四)。
⑤ 一定の政府関係金融機関又は協定銀行(RCC)が有する債権その他財務省令で定める債権につき債務免除等(※)をすることが定められていること(法令24の2①五)。なお、政府関係金融機関とは株式会社日本政策金融公庫及び沖縄振興開発金融公庫をいう(法令24の2②一)。
※ 債務免除等とは債務の免除又は債権のその債務者に対する現物出資による移転(いわゆるDESにより見込まれる債務消滅益が生じる場合)をいう(法令24の2②三)。
2 欠損金
(1)概要 法人税法においては、資産の評価損の損金算入規定とともに、債務免除益課税を軽減するために一定の欠損金の損金算入を認める特例規定が設けられている。
この特例規定で問題となる点は下記のとおりである。
① 損金の額に算入する欠損金の範囲 元々、法人税法では青色欠損金の損金算入規定が設けられているが、その青色欠損金の繰越期間を超過した期限切れ欠損金を使用することができるかどうかが問題となる。
② 青色欠損金と期限切れ欠損金の使用順序 上記①で述べた期限切れ欠損金を使用できる場合において、青色欠損金と期限切れ欠損金のどちらを先に使用できるのかが問題となる。もちろん期限切れ欠損金を先に使用したほうが有利である。
③ 資産の評価損と期限切れ欠損金の使用順序 資産の評価損と期限切れ欠損金の両方を使用できる場合において、どちらを優先的に使用できるかが問題となる。一定の場合には資産の評価損の金額は青色欠損金として引き継ぐことができるので、期限切れ欠損金を先に使用したほうが有利となる。
上記の関係については、後述「資産の評価損・期限切れ欠損金・青色欠損金等の関係」に示すとおりであるが、ここでも法律等による各手続き制度自体の厳格性・保守性を考慮して各手続間で差異が設けられている。
法人税法で規定する各手続の欠損金の特例規定は下記のとおりである。
(2)会社更生等により債務免除等があった場合の欠損金の取扱い
① 会社更生等の場合の欠損金の損金算入額(法法59①) 以下のいずれか少ない金額
i.(a)
ii.債務免除益等 + 私財提供益等 +(評価益-評価損)(マイナスの場合は、ゼロ)
② 民事再生等又は一定の私的整理の場合で一定の評価損益の計上があるときの欠損金の損金算入額(法法59②) i.(a)
ii.債務免除益等 + 私財提供益等 +(評価益-評価損)(マイナスの場合は、マイナス)
iii.所得金額(欠損金等の控除前)(「別表四の総額差引計」)
③ 民事再生等又は一定の私的整理の場合で一定の評価損益の計上がないときの欠損金の損金算入額(法法59②) i.(a)-(b)
ii.債務免除益等+私財提供益等
iii.所得金額(青色欠損金等の損金算入額の控除後)(「別表四の総額差引計-(b)」)
| 上記算式の(a)及び(b)の意味は下記のとおりである。 (a)…適用年度終了の時における前事業年度以前の事業年度から繰り越された欠損金額の合計額(=「別表五(一)の期首現在利益積立金額の合計額が負(マイナス)である場合の当該金額」)(法令116の3、117の2一、法基通12-3-2) (b)…法人税法第57条第1項(青色欠損金)又は第58条1項(災害欠損金)の規定により適用年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される欠損金額(=「青色欠損金又は災害欠損金の当期の損金算入金額」)(法令117の2ニ) |
(朝長英樹『期限切れ欠損金の額』、本誌471号24頁参照)
(3)青色欠損金の繰越金額 平成23年12月改正の「青色欠損金の損金算入の80%制限」に伴い、法人税法第59条(会社更生等があった場合の欠損金の損金算入)に関して、下記の制度が追加された。
下記により青色欠損金の繰越金額が定められている。
① 会社更生法等の場合の青色欠損金の繰越金額(法法57⑤、法令112⑨) 上記(2)①の適用を受ける場合には、その適用事業年度以後の事業年度の所得の計算上、青色欠損金額のうち上記(2)①で損金の額に算入される金額として次の算式により計算した金額はないものとされる。
(算式)
ⅰ-ⅱの金額(マイナスの場合は、ゼロ)
| 上記算式のi及びiiの意味は下記のとおりである。 i.法人税法第59条1項の規定により損金の額に算入される欠損金額 ii.① - ② ① 法人税法施行令第116条の3に規定する欠損金の合計額 ② 法人税法第57条1項のただし書を適用しない場合に適用年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される欠損金額 |
(算式)
ⅰ-ⅱの金額(マイナスの場合は、ゼロ)
| 上記算式のi及びiiの意味は下記のとおりである。 i.法人税法第59条第2項の規定により損金の額に算入される欠損金額 ii.① - ② ① 法人税法施行令第117条の2第一号に規定する欠損金の合計額 ② 法人税法第57条第1項のただし書を適用しない場合に適用年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される欠損金額 |
上記(2)③により適用年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額
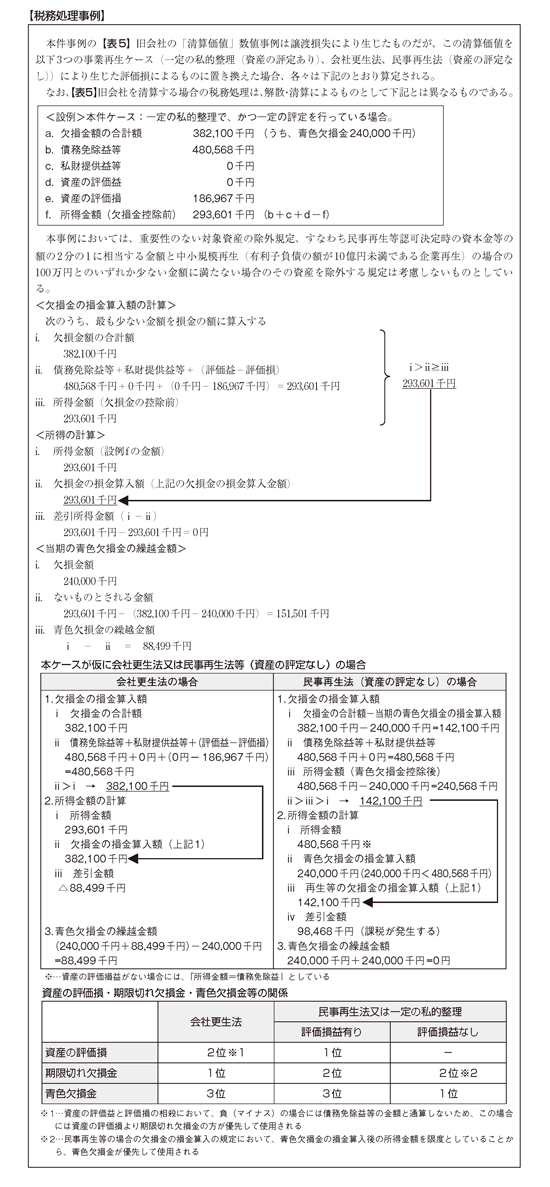
3 第2会社方式と税制 前述のように、第2会社方式による事業再生においては、事業譲渡型と会社分割型とがある。これらの税制上の課題は、下記のとおりである。
① 分社型会社分割の組織再編税制における適格・非適格判定 事例において既述したように、会社分割型は分社型会社分割によることとなり、これは組織再編税制においては税制非適格となる。なぜなら、分割法人(旧会社)が所有する分割承継法人(移転先法人)の株式は、新スポンサーへの売却を予定しており、旧会社は清算を予定していることから、支配関係継続見込要件(法法2十二の十一、法令4の3⑤)を満たしていないためである。したがって、資産・負債の移転は時価によることとなる。
② 資産・負債の譲渡価額の妥当性 事業譲渡においては、資産・負債の移転は時価により行われる。会社分割においても、上記①のとおり時価によることとなる。いずれにおいても、譲渡金額の妥当性の問題が主ずる。
③ のれんの償却 資産・負債の譲渡は時価により行われることから、会計上の「のれん」または「負ののれん」が生ずることがある。これらは、法人税法上は「資産調整勘定(法法62の8①)」または「負債調整勘定(法法62の8③)」となる。これらの償却については、60ケ月による均等償却を行うことになる(資産調整勘定償却は法法62の8④、負債調整勘定償却は法法62の8⑦)。
④ 移転にかかる諸税金 ⅰ.不動産取得税
会社分割により不動産を取得した場合、下記のすべての要件を満たした場合に限り、不動産取得税は課されない(地方税法73の7二、地方税法施行令37の14)。
・会社分割に伴って金銭等の交付がないこと
・分割事業に係る主要な資産及び負債が分割承継法人に移転していること
・分割事業が分割承継法人において引き続き営まれることが見込まれていること
・分割直前の分割事業に係る従業者のうち、その総数の概ね80%以上に相当する数の者が分割後に分割承継法人の業務に従事することが見込まれていること
このように、法人税法上の税制非適格ではあっても、不動産取得税では要件を満たせば非課税とすることが可能となる。
ⅱ.登録免許税
土地及び建物の登録免許税は、「事業譲渡」の場合、固定資産税評価額に対して1,000分の20。会社分割では、下記のとおり軽減されている。
平成24年4月1日から平成26年3月31日まで、 1,000分の15
平成26年4月1日から平成27年3月31日まで、 1,000分の18
ⅲ.消費税
会社分割型は課税対象外に該当、事業譲渡型は課税に該当する。
ただし、会社分割型の場合でも、分割型分割を行った後に分割承継法人の株式を新スポンサーに譲渡する場合には、当該株式の譲渡は非課税取引に該当するため、債務者企業の課税売上取引の計算上、株式の譲渡価額の5%について非課税取引として考慮することから(消法6①、消令48⑤)、債務者企業の仕入税額控除の計算に影響を与えることになる。
参考文献
・日本公認会計士協会 経営研究調査会研究報告第47号「事業再生実務と公認会計士の役割」平成24年3月1日
・事例の資料協力:株式会社事業パートナー
・「ケース別にわかる企業再生の税務 第2版」中央経済社、稲見誠一、佐藤信祐著
棟田裕幸 むねた ひろゆき
公認会計士・税理士。大手監査法人等を経て、1995年棟田公認会計士・税理士事務所開設(現在に至る)、1999年株式会社BSM設立(現在に至る)。公認会計士試験・修了考査(経営科目元出題委員)、日本公認会計士協会東京実務補習所運営委員会(元委員長)、日本公認会計士協会東京会調査研究部税務委員会(元副委員長)等を歴任。著作として、『組織再編の手法と会計・税務Q&A』(編者、中央経済社)、『会社合併実務必携』(共著、法令出版)、『Q&A 株主資本の実務』(共著、新日本法規出版)など。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -

Copyright (C) 2019
SHINNIPPON-HOKI PUBLISHING CO.,LTD.





















