解説記事2012年12月17日 【ニュース特集】 詳報・払戻限度額超過額の寄附金該当性を巡る裁判(2012年12月17日号・№479)
一連の事業再編スキームから詳しく!
詳報・払戻限度額超過額の寄附金該当性を巡る裁判
実務家の間でも注目を集めていた旧商法の払戻限度額を超過する違法収益の寄附金該当性を巡る裁判は国側勝訴という結果となったが(478号8ページ参照)、一部の実務家の間では「組織再編関係の事案」といった誤解もあるなど、その全容を知る者は意外と少ないようだ。
本特集では、一連の事業再編スキームのどの部分が問題となったのかや、寄附金該当性を巡る原告・被告の主張などを詳報する(平成24年11月28日判決、平成22年(行ウ)第314号)。
事業再編スキームの全容
本件は、原告が産業活力再生法の事業再構築計画(下記コラム参照)として平成18年に認定を受けた一連の事業再編のうちの一部の課税関係が問題となったものだ。
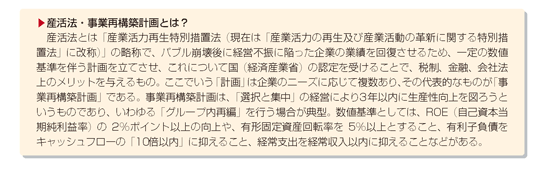
本件の最大の争点は後述するように寄附金課税にあるが、本件が一部の実務家に「組織再編」関係の事案と誤解されていた背景には、この一連の事業再編の存在がある。
一連の事業再編とは、原告の連結販売会社52社を分社型分割により「資産管理会社」と「販売事業会社」に分割し、このうち資産管理会社を、原告が金融機関から買収し100%子会社としていた不動産会社と合併させるというもの(図1参照)。
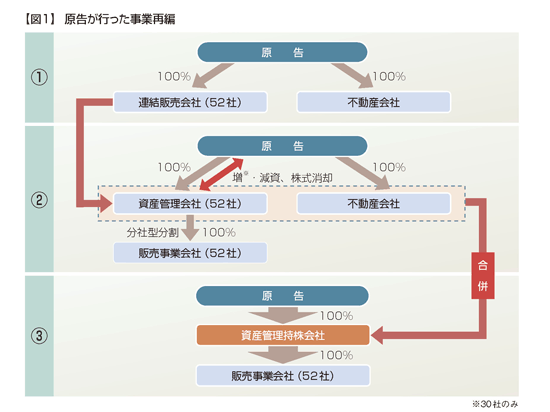
そして、分社型分割と合併の合間には、原告と資産管理会社の間で増・減資および株式消却が行われている(図2参照)。
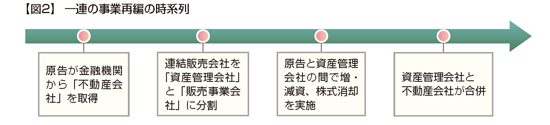
図1②③の通り、合併によって消滅する予定となっていた資産管理会社に対して増資が行われたのは、資産管理会社52社のうち30社が債務超過状態にあったため。旧商法では、債務超過会社を吸収合併することはできないとされていたため、これを解消する必要があったというわけだ。
このように原告は資産管理会社のうち30社に対して増資を行ったのだが、その後、資産管理会社52社は一転して「減資」を行っている。この点、産活法の事業再構築計画には「合併に先立って適正な規模の資本金額とする観点から」との説明がなされているほか、事業税の外形標準課税の適用を回避する目的もあった模様。
そして、当該減資に伴い、資産管理会社52社は、旧商法の規定により減資に対応する株式の消却を行った。また、資産管理会社52社のうち「原告から増資を受けなかった者」については、減資の額および減準備金の額の合計額を原告に対して払い戻した(なお、旧商法で「有償減資」とされていた株主への出資払戻しは、会社法上は①資本金の剰余金への振替え、②剰余金の配当の2つに分解され、株主への払戻しは「剰余金の配当」によるしかなくなった。すなわち、会社法上は資本金の減少額を株主に直接払い戻すことはできない)。一方、原告から増資を受けた者は、払戻しにより再び債務超過になる恐れがあったことから、払戻しは行わなかった。
課税上問題となったのは、「原告から増資を受けなかった者」が原告に行った払戻しの額の適正性だ。
株式の消却は「みなし配当」とされる金額を除き、発行会社への株式の譲渡とされることになる。原告は、払戻し金額を「譲渡対価」として譲渡所得を計算し、1,390億円余りを譲渡損失として計上した。これに対し税務当局は、「当該払戻し額は、当該株式の適正な譲渡対価(各社の時価純資産価額のうち株式消却に係る部分)の額より低い」として、628億円余りを寄附金と認定して課税処分を行った(なお、債務超過のため原告から増資を受けた30社に係る株式消却について、原告はすべて譲渡対価を「0」と計上していたが、税務当局はこれらについても適正譲渡対価を認定し、寄附金課税を行っている。
課税関係を生じさせない「他の選択肢」とは?
本件の最大の争点は、減資払戻し額と税務当局が主張する株式の適正な譲渡対価の差額の「寄附金該当性」にある。
この点について原告は、税務当局のいう譲渡対価の額715億円余りのうち「405億円余りは、旧商法における資本金及び準備金の減少に伴う払戻しにおける払戻し限度額(下記コラム参照)を超えている」と主張し、仮に税務当局が適正とする価額で現実に払戻しが行われ、現実に受領していた場合、払戻限度額超過額(405億円余り)の部分は、違法・無効な収益であると主張した。
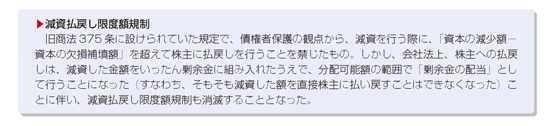
寄附金該当性については、対価性要件(経済的利益を対価なく他に移転していること)と、合理性要件(通常の経済取引として是認できる合理的な理由が存在しないこと)の二つの判断基準があるが(名古屋高裁金沢支部平成14.5.15判決)、原告と被告の主張の対立が際立ったのが、対価要件に対する考え方である。
両者の主張を整理すれば、表のとおりとなる。
結局、東京地裁は国側の主張を全面的に支持する判決を下したわけだが、「払戻限度額を超える額は、対価を収受する私法上の権利がない」ことを前面に押し出した原告の主張が採用されなかった要因の一つと考えられるのが、裁判所が指摘する「原告は、旧商法の払戻限度額の規制を遵守しつつ対価なく経済的利益を移転させない取引方法があるにもかかわらず、あえて適正な価額による払戻額が払戻限度額を下回ることとなる内容で本件株式消却を伴う減資を行うことを選択し、払戻限度超過額に係る経済的利益を移転させた」点であろう。具体的には、消却株式の株式数を増減させることによって、旧商法の払戻限度額を遵守しながら消却株式の経済的価値に見合う払い戻しを受けられるよう調整したり、株式消却を行わずに株式併合を行うことも可能であったと考えられる。
他に課税関係を生じさせない選択肢があったにもかかわらず、その方法を選ばずに課税関係が発生したという点では、株式移転に伴って子会社の自己株式に割り当てられた親会社(持株会社)株式の譲渡原価を「ゼロ」とし、譲渡対価のほぼ全額に対し譲渡益課税を行った課税処分の是非を巡り現在最高裁で係争中の事案を彷彿させる(426号12ページ、457号8ページ)。本件は、自己株式を予め消却しておくことにより、譲渡益の発生を回避できた事案であり、本誌では4年以上前にこの点を報じていたところだ(なお、国側の証拠資料として本誌記事が提出されている。262号 8ページ参照)。
両者は該当条文も論点も全く異なる事案ではあるが、両者に登場する「他に選択肢があったかどうか」という視点が、今回の判決における寄附金該当性の「合理性要件」の判断に影響していると言えそうだ。
本件課税処分は、100%グループ内における株式譲渡所得を繰延べることとなるグループ法人税制が施行された平成22年10月1日以後は起こり得ないことになる。ただし、その前に行われた100%グループ内取引で、まだ税務上の除斥期間内にあるものが存在する可能性もあるだけに、税務調査での思わぬ指摘に備え、いま一度過去の取引について税務上の問題を検証しておくのも有益だろう。
このほか本件では、原告が採用した時価純資産法(法人税基本通達4-1-6)に基づく評価額と、税務当局が採用したDBJ(政策投資銀行)評価額(法人税基本通達4-1-5(4)に基づく評価額)のどちらを採用すべきかという点が争点となっていたが、この点についても裁判所は、法人税基本通達4-1-6が「課税上弊害がない限り」という条件を明示していることから「原告が自らに有利な評価方法として恣意的に採用した時価純資産法は認められない」とした国側の主張を支持している。
詳報・払戻限度額超過額の寄附金該当性を巡る裁判
実務家の間でも注目を集めていた旧商法の払戻限度額を超過する違法収益の寄附金該当性を巡る裁判は国側勝訴という結果となったが(478号8ページ参照)、一部の実務家の間では「組織再編関係の事案」といった誤解もあるなど、その全容を知る者は意外と少ないようだ。
本特集では、一連の事業再編スキームのどの部分が問題となったのかや、寄附金該当性を巡る原告・被告の主張などを詳報する(平成24年11月28日判決、平成22年(行ウ)第314号)。
事業再編スキームの全容
本件は、原告が産業活力再生法の事業再構築計画(下記コラム参照)として平成18年に認定を受けた一連の事業再編のうちの一部の課税関係が問題となったものだ。
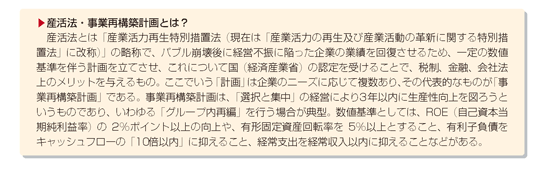
本件の最大の争点は後述するように寄附金課税にあるが、本件が一部の実務家に「組織再編」関係の事案と誤解されていた背景には、この一連の事業再編の存在がある。
一連の事業再編とは、原告の連結販売会社52社を分社型分割により「資産管理会社」と「販売事業会社」に分割し、このうち資産管理会社を、原告が金融機関から買収し100%子会社としていた不動産会社と合併させるというもの(図1参照)。
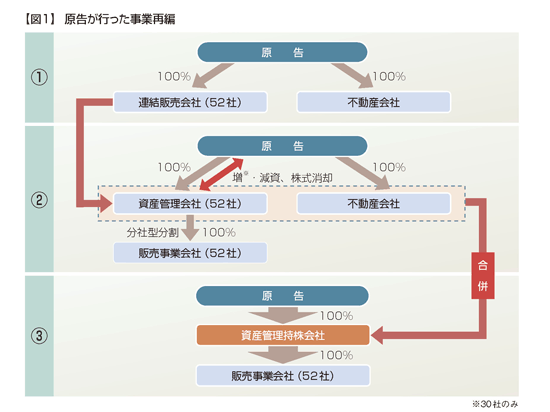
そして、分社型分割と合併の合間には、原告と資産管理会社の間で増・減資および株式消却が行われている(図2参照)。
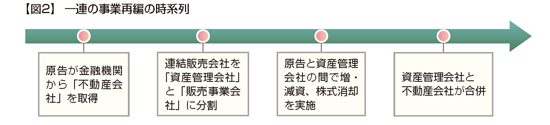
図1②③の通り、合併によって消滅する予定となっていた資産管理会社に対して増資が行われたのは、資産管理会社52社のうち30社が債務超過状態にあったため。旧商法では、債務超過会社を吸収合併することはできないとされていたため、これを解消する必要があったというわけだ。
このように原告は資産管理会社のうち30社に対して増資を行ったのだが、その後、資産管理会社52社は一転して「減資」を行っている。この点、産活法の事業再構築計画には「合併に先立って適正な規模の資本金額とする観点から」との説明がなされているほか、事業税の外形標準課税の適用を回避する目的もあった模様。
そして、当該減資に伴い、資産管理会社52社は、旧商法の規定により減資に対応する株式の消却を行った。また、資産管理会社52社のうち「原告から増資を受けなかった者」については、減資の額および減準備金の額の合計額を原告に対して払い戻した(なお、旧商法で「有償減資」とされていた株主への出資払戻しは、会社法上は①資本金の剰余金への振替え、②剰余金の配当の2つに分解され、株主への払戻しは「剰余金の配当」によるしかなくなった。すなわち、会社法上は資本金の減少額を株主に直接払い戻すことはできない)。一方、原告から増資を受けた者は、払戻しにより再び債務超過になる恐れがあったことから、払戻しは行わなかった。
課税上問題となったのは、「原告から増資を受けなかった者」が原告に行った払戻しの額の適正性だ。
株式の消却は「みなし配当」とされる金額を除き、発行会社への株式の譲渡とされることになる。原告は、払戻し金額を「譲渡対価」として譲渡所得を計算し、1,390億円余りを譲渡損失として計上した。これに対し税務当局は、「当該払戻し額は、当該株式の適正な譲渡対価(各社の時価純資産価額のうち株式消却に係る部分)の額より低い」として、628億円余りを寄附金と認定して課税処分を行った(なお、債務超過のため原告から増資を受けた30社に係る株式消却について、原告はすべて譲渡対価を「0」と計上していたが、税務当局はこれらについても適正譲渡対価を認定し、寄附金課税を行っている。
課税関係を生じさせない「他の選択肢」とは?
本件の最大の争点は、減資払戻し額と税務当局が主張する株式の適正な譲渡対価の差額の「寄附金該当性」にある。
この点について原告は、税務当局のいう譲渡対価の額715億円余りのうち「405億円余りは、旧商法における資本金及び準備金の減少に伴う払戻しにおける払戻し限度額(下記コラム参照)を超えている」と主張し、仮に税務当局が適正とする価額で現実に払戻しが行われ、現実に受領していた場合、払戻限度額超過額(405億円余り)の部分は、違法・無効な収益であると主張した。
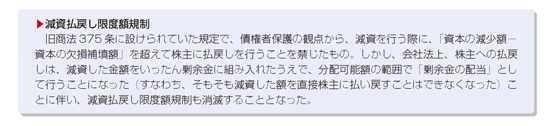
寄附金該当性については、対価性要件(経済的利益を対価なく他に移転していること)と、合理性要件(通常の経済取引として是認できる合理的な理由が存在しないこと)の二つの判断基準があるが(名古屋高裁金沢支部平成14.5.15判決)、原告と被告の主張の対立が際立ったのが、対価要件に対する考え方である。
両者の主張を整理すれば、表のとおりとなる。
| 【表】 |
| 納税者(原告)の主な主張 | 国(被告)の主な主張 |
| ・払戻限度額を超える部分については「払戻しを受ける法的地位」にないため、対価要件を充足しない。 ・払戻限度額を超える額は、対価を収受する私法上の権利がないものであり、対価を収受すると同時に不可避的にその返還義務が発生する法律関係にあるため、当該対価を収受しなかったとしても、対価要件を充足することはない。 ・私法上の法律関係の引き直しが可能になるのは、法人税法132条1項(同族会社等の行為・計算の否認)の要件を満たす場合に限られる。 | ・対価要件とは、私法上対価を受領できるか否かが問題となる要件ではない。 ・仮に、旧商法の払戻限度額規制により原告が払戻限度超過額の対価を受け取る法的地位にない点が問題となるとしても、それは、払戻限度超過額に係る経済的利益の移転が、通常の経済取引として是認できる合理的な理由によるかどうかという「合理性要件」において検討されるべき要素である。 ・旧商法による払戻限度額の超過が、株主自らの意思で決定した行為により発生したものであると認定できる場合には、いったん払戻限度額を超えて払戻しを受けた株主が、払戻限度額を超える部分を返還したという事実があったとしても、法人税法37条の適用上、株主による贈与があったものと同視でき、寄付金の額が認定される。 |
結局、東京地裁は国側の主張を全面的に支持する判決を下したわけだが、「払戻限度額を超える額は、対価を収受する私法上の権利がない」ことを前面に押し出した原告の主張が採用されなかった要因の一つと考えられるのが、裁判所が指摘する「原告は、旧商法の払戻限度額の規制を遵守しつつ対価なく経済的利益を移転させない取引方法があるにもかかわらず、あえて適正な価額による払戻額が払戻限度額を下回ることとなる内容で本件株式消却を伴う減資を行うことを選択し、払戻限度超過額に係る経済的利益を移転させた」点であろう。具体的には、消却株式の株式数を増減させることによって、旧商法の払戻限度額を遵守しながら消却株式の経済的価値に見合う払い戻しを受けられるよう調整したり、株式消却を行わずに株式併合を行うことも可能であったと考えられる。
他に課税関係を生じさせない選択肢があったにもかかわらず、その方法を選ばずに課税関係が発生したという点では、株式移転に伴って子会社の自己株式に割り当てられた親会社(持株会社)株式の譲渡原価を「ゼロ」とし、譲渡対価のほぼ全額に対し譲渡益課税を行った課税処分の是非を巡り現在最高裁で係争中の事案を彷彿させる(426号12ページ、457号8ページ)。本件は、自己株式を予め消却しておくことにより、譲渡益の発生を回避できた事案であり、本誌では4年以上前にこの点を報じていたところだ(なお、国側の証拠資料として本誌記事が提出されている。262号 8ページ参照)。
両者は該当条文も論点も全く異なる事案ではあるが、両者に登場する「他に選択肢があったかどうか」という視点が、今回の判決における寄附金該当性の「合理性要件」の判断に影響していると言えそうだ。
本件課税処分は、100%グループ内における株式譲渡所得を繰延べることとなるグループ法人税制が施行された平成22年10月1日以後は起こり得ないことになる。ただし、その前に行われた100%グループ内取引で、まだ税務上の除斥期間内にあるものが存在する可能性もあるだけに、税務調査での思わぬ指摘に備え、いま一度過去の取引について税務上の問題を検証しておくのも有益だろう。
このほか本件では、原告が採用した時価純資産法(法人税基本通達4-1-6)に基づく評価額と、税務当局が採用したDBJ(政策投資銀行)評価額(法人税基本通達4-1-5(4)に基づく評価額)のどちらを採用すべきかという点が争点となっていたが、この点についても裁判所は、法人税基本通達4-1-6が「課税上弊害がない限り」という条件を明示していることから「原告が自らに有利な評価方法として恣意的に採用した時価純資産法は認められない」とした国側の主張を支持している。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -

Copyright (C) 2019
SHINNIPPON-HOKI PUBLISHING CO.,LTD.





















