解説記事2013年01月21日 【対談】 平成18年度改正で生じた配当還元方式の問題点(2013年1月21日号・№483)
対 談
「資本金等の額」への変更により配当還元価額が急騰
平成18年度改正で生じた配当還元方式の問題点
品川芳宣(筑波大学名誉教授/弁護士)
緑川正博(公認会計士/税理士)
平成18年度税制改正により、法人税法は、資本金と資本積立金を一本化し、資本金等の額に変更した。これを受けて財産評価基本通達は、配当還元方式の計算式について、「資本金の額」から「資本金等の額」に改正した。その結果、少数株主の評価額である配当還元価額が、改正前の取扱いに比べてかなり上昇することになるという問題が生じている。対談では、国税庁在職中には財産評価基本通達の策定に携われた品川芳宣先生をお招きし、緑川正博先生とともに財産評価基本通達における配当還元方式の改正の変遷(32頁の表参照)を辿りながら、その問題点について論じていただいた。
配当還元方式が導入された経緯とは?~昭和39年改正
緑川正博氏(以下、敬称等は省略)
本日は品川芳宣先生をお招きして、財産評価基本通達における配当還元方式の問題点について議論していきたいと思います。配当還元価額は、所得税および法人税の通達にそのまま準用されています。また、平成18年の評価通達の改正でこの評価方法の計算が「資本金の額」から「資本金等の額」に見直されたことにより、配当還元価額がかなり上昇するという問題が生じています。特に、組織再編成を行う場合には、顕著に影響が生じています。そもそも配当還元価額とはどのようなものであるのかという点について、ご意見をお伺いしながら、最後に平成18年改正の資本金等の額についての議論をしていただければと思っています。
まず、昭和39年に配当還元方式が導入された経緯というのはどうだったのでしょうか。
品川芳宣氏(以下、敬称等は省略)
もともと取引相場のない株式の評価方法というのは、基本的には3つあります。純資産価額方式、比準方式、収益方式です。このうち、収益方式に関しては、本来、配当を基準にするやり方とその会社の収益力を反映して評価する方法の2つに分けて考えることができますが、実際の収益力を反映した評価方式というのは、将来の収益力の見込みや還元率をどうするかなど、非常に難しいものです。むしろこれは企業会計などで対応されています。
税法は、その収益方式の中の最も簡便な配当還元方式を伝統的に採用しているわけです。収益方式は本来、少数株主だけではなくて、原則的評価方式の1つとして考えられるのですが、通達は、配当に限って少数株主への配慮として配当還元方式を採用しているわけです。この場合、少数株主においては、株式を所有していることについて、配当しか期待できないという経済的価値を10%という還元率で現在価値として置き換えるのが基本的な考え方です。また、もう1つ言えば少数株主というのは、会社の決算書の中身がわかりませんので、評価の簡便方法として寄与してきたと言えます。
そういう意味で、昭和39年に導入された配当還元方式は、収益方式のワンオブゼム(one of them)の1つであり、少数株主に対する経済的価値の測定と簡便的な評価方式であるという2つの要素を兼ねているということだと思います。
緑川:昭和39年当時というのは、中小会社のほとんどが株主総会を開催していないのが現状だったと思います。このような状況で、配当だけを還元するというのは非常に理解できます。現在は、中小会社でも招集通知を出さないような会社はなくなってきていると思いますが、類似業種あるいは純資産にしても申告書を見ないとわかりません。申告書を見られない少数株主がどうやって配当還元価額を計算できるのでしょうか。
品川:実際の配当を基準に通達の定める方程式に当てはめ、10%還元することで実務は回っています。10%の率の是非はともかくとして、配当をもらうだけの少数株主にとっては簡単に評価できて申告にも支障がありません。また、従業員持株会のように、かつては額面価額で買い取るという売買が行われているという慣行もあるわけですので、株式を保有していればいずれは額面で買い取ってもらえるという意味で額面を基準とした配当還元方式というのは、それなりに説得力があったのではないかと思います。
緑川:1つの評価方式としてわかりやすかったと思います。
法人税法を準用する理由は?
緑川:もう1つ疑問なのは、財産評価基本通達が法人税法を準用したりしなかったりする点です。たとえば、法人税法施行令4条の「同族関係者」を株式の評価の中に持ってきて同族判定にそのまま使ったりしています。基本的に同族関係者の判定ということについて、法人税では留保金課税という年度・年度の判定だと思うのですが、相続税・贈与税というのは、個人のことでいつどうなるかわからないし、かといって個人のことは会社が知る由もありません。なぜ、法人税法の規定をそのまま持ってきているのですか。
品川:評価通達は、基本的に相続税や贈与税という特定の税目を対象に出来上がっています。通達自体は、相続税法の解釈として国税庁が発遣しているので、本来、法人税法とは独立した概念です。ただ、通達上用語の定義をするに当たっては、関連する会社法なり法人税法の規定を参酌し、取引相場のない株式の評価に有効な定義として借りてくるということはよくあることです。
法人税法施行令が定めている同族関係者の範囲なるものは、所得税法でも採用されておりますし、評価通達でも参考にしています。いわば同族関係者とは何かというようなことを議論する場合に、この概念を持ってくるのが最も無難といいますか、最も広く支持されているという意味で評価通達上もその範囲で同族判定をしようということにしているわけです。ただ、個々の結果論として、弊害が生じてくるという場合もままあるということだと思います。

緑川:特にこだわるわけではありませんが、同族関係者の中で法人税法施行令4条1項4号なる「生計を維持しているもの」という世界がありますが、生計を維持していることについて、相続税の評価というのは客観的交換価額を標榜する以上、客観性が必要だと思います。生計を維持しているかどうかというのは客観性の問題ではなくて、その時々の主観性の問題だと思うのです。ある時はあるかもしれないし、ないときはないかもしれません。問題は法人税法が定めているからですといって逃げられるかもしれませんが、これについてやはり問題点として残るのではないでしょうか。
品川:生計を維持しているというのは言葉遊びの問題ではなくて、結局は事実認定の問題です。事実認定について、法人税の世界、所得税の世界、相続税の世界を切り離して考えるのはなかなか難しいと思います。
緑川:法律に書いてあるものについて、事実認定を行うのならわかります。しかし、通達が法律を準用して事実認定だというのは逆だと思います。
品川:通達も相続税法22条の時価とは何かというのを想定して時価の解釈基準として発遣しているわけです。取引相場のない株式について、同族株主がいるのかいないのかということによって評価を区分すると、同族株主とは何かということについて、本来の法の趣旨に照らして相続税法では同族株主とはこういう概念を導入するのだと独自に決める方法もあります。
しかし、他の国税の中ですでに概念が確立されていることであれば、もともと法人税法の同族会社という概念が法人税法が制定されたときからあるわけですから、それにしたがって評価通達で定義を明確にするというのは、評価通達でも独自にその概念を導入したことになります。法人税法の取り扱いと同じにしたということとは少し違うのです。
緑川:単純に評価通達は画一的処理が求められるのだから、事実認定してはならないと思っているわけです。
品川:たとえば、最近問題になっている広大地の評価も、最後は事実認定です。
緑川:それはあくまでも評価の適正についてだと思います。ところが、個人のプライベートなことを誰が事実認定できるのでしょうか。
品川:たとえば、最近の裁判で一番問題となったのは、所得税法56条の生計を一にしている親族等に支払った役務提供の対価の額が必要経費になるかどうかです(最高裁平成16年(行ツ)第23号 平成16年11月2日第三小法廷判決、本誌135号参照)。夫である弁護士が税理士である妻に申告書を書いてもらった場合、その税理士費用について争われたものです。生計を一にするかどうかということで、それぞれの報酬で生活しているのだから認められるというものと、夫婦である以上、区分することはできないだろうと、そういう非常に人様の生活、内情にまで首を突っ込み、生計を一にしているか否かが争われましたが、結局、最後は事実認定の問題となりました。
緑川:中小企業の事業承継税制でも、措置法であるのに法人税法を準用せずに別に定めているわけです。法律のレベルでさえそうです。
品川:もともと措置法も法人税法も独立した法律ですので、全く違います。措置法にいたっては、所得税法の特例、法人税法の特例、相続税法の特例などがあって、その特例ごとに概念が違うわけです。
緑川:意味はわかります。付け加えれば、中小企業事業承継税制は、役員給与の過大の判定は法人税法と同様となっているものの、組織再編成税制は、別途規定しています。わかりやすいところは準用して、わかりづらいところは準用しないというのがおかしいと思います。
品川:その点は、立法政策的に妥当かどうかという問題は残ると思います。
大中小の計算方法を同じにした理由は?~昭和47年改正
緑川:昭和47年の税制改正により、大会社の50%ウェイトをはずして「小会社」と「中会社」と同じ計算方法にしました。この点はたしか中小企業事業承継税制が騒がれた初めの頃だったと思いますが、その経緯はどうだったのでしょうか。
品川:「大会社」「中会社」「小会社」に区分して評価方法を変えるという流れが昭和39年から続いていたわけですが、同じ大中小に区分する意味合いが地価の上昇に伴って変わってきました。
もともと大会社というのは、いつでも上場できるだけの一定規模の会社であって、ただ政策的に上場していないだけだとされてきました。したがって、課税時期では上場していないけれども、いつ上場するかもしれない会社の株式の評価については、少数株主に関しても上場すれば市場価格が明らかになるわけですので、類似業種比準価額なり純資産価額なり、その同族株主に課せられる評価方式も当然、同じように考慮せざるを得ません。そういう意味で当初の大会社を区分したときには、いずれは上場することを考慮して少なくても半分は原則的評価方式を反映させる必要があるということで50%基準を導入したと思うのです。
ところが、ご指摘のように、昭和47年というのは、列島改造ブームなど、要するに会社が所有する土地の値段が値上がりしたことで中小企業の事業承継問題が非常に深刻になってきたわけです。売ることのできない株式が、土地の値段の上昇とともに評価が上がり、相続税の負担が厳しくなって、何とか事業承継を円滑化にできる方法を考えざるを得ないということがありました。
何とか中小企業の株式承継が円滑にできるようにするためには、どのような理屈で評価減ができるかということを考えたわけです。そのような背景の中で大会社なるものは、いつでも上場する、上場したら少数株主もきちんと上場株価が保証されるという概念から、大中小の概念は本来の考え方を引き継ぎながらいかにして取引相場のない株式の評価を穏便にすまして事なきを得ようといういわば時代の走りであったわけです。結局、大会社と区分されたとしてもいつ上場するかわからない場合が多いし、そうであれば小会社、中会社と同じように配当還元だけでよいのではないかということになったわけです。仮に近々上場するのであれば、その時に然るべく評価方法でやればよいということです。ここは本来の理屈があって改正したというよりも基本的には事業承継対策について、株の評価のうえで対応せざるを得なかったということです。それが最も顕著に現れたのが昭和58年の改正だったと思うのです。
緑川:時代の走りと言いましたけれども、あえて言うなら評価通達が時価から離れた走りといえるのではないでしょうか。
品川:ご指摘のとおりです。
緑川:評価通達が時価を標榜しながらも時価ではないといった走りであり、その後の評価通達は、時価ではなく課税価格を定めるものとなっています。
品川:この時期から時価とは何かというよりも事業承継等その政策手段として、評価通達が使われ始めたということです。
配当還元方式の適用範囲の拡大~昭和53年改正
緑川:昭和53年改正で配当還元価額の適用できる範囲が拡大されました。これについてはどのように理解したらよいのですか。
品川:先ほど指摘した事業承継対策問題や地価の上昇といった背景の中で、単純に同族株主以外の株主、すなわち少数株主の概念で配当還元が従来どおり適用されるものと、同族株主といえども非常に支配力のない株主が現れてくるわけです。同族関係者の括りの問題にも関係しますが、その同族関係者を親族、すなわち6親等以内の親族で括るというのはある意味で相当無理があります。
緑川:6親等以内の親族のすべてを知っているわけではありません。
品川:そのとおりです。そのような括りに無理があったことに加えて、同族株主の間では支配層と非支配層が存在するという問題がありました。直接のきっかけは、同族株主だからといってひと括りに評価するのはおかしいということが国会で問題になったわけです。これを踏まえ国税庁は実態調査を行い、その結果、配当還元方式が適用される株式が拡大されたわけです。
緑川:昭和53年改正では中心的な同族株主を作り、血の濃さの括りを狭くしたわけですが、同族関係者は変わりませんでした。
品川:そもそも同族関係者の範囲を親族で区切るのが無理だと思うのです。せめて4親等内の血族とか3親等内の姻族などの範囲でしないとならないと思います。その矛盾は今でもずっと引きずっているわけです。
緑川:やはりどこかで見直さなければならない問題であると思います。
商法改正による額面株式の廃止~昭和58年改正
緑川:商法の改正で無額面株式が出来ました。これを受け、昭和58年の改正では計算式の改訂がされましたが、なぜ50円で割り戻すことになったのでしょうか。やはり配当利回りにこだわっていたのですか。
品川:このときの改正については、この前年に税制調査会で事業承継税制の小委員会が出来ました。結論的には事業承継対策の税制は、この段階は採用する必要がないとの結論に至りました。
しかし、同じ会社であっても儲かっている会社と儲かっていない会社があるわけですので、一律に小会社に純資産価額方式を適用するのはおかしいとなりました。収益力を加味する評価方式にすべきだということで小会社に対しても類似業種比準方式を半分認めるべきという結論が出ました。いうなれば税制調査会の委員会でわざわざ時価の認定方法である通達を直すというレベルの低い答申を出すというナンセンスなことが行われたわけです。
緑川:全く同感です。
品川:昭和47年から先ほどのご指摘のとおり、評価通達の取扱いは本来の時価の理念から乖離し、さらに昭和58年はその乖離に拍車がかかってしまったのです。大幅に政策の手段として使われてしまったわけです。その中でご指摘の50円で割り戻すという話がありましたが、配当還元方式の評価に関しては、あまり関心が持たれなかったように思います。
もともとは昭和56年の商法改正において額面が廃止されました。ただ、なぜ50円で割り戻したかというと、戦後額面というのは50円というのが支配的であったわけです。支配的であったがゆえにそれは無額面株式になったところで1株に対する配当をいくらにするかというのは、ほとんどの会社において、額面とのバランスを考えて50円株で1割配当1株5円であれば、無額面でも1株5円にするといった配当政策上の慣行を重視したと思うのです。
ただ、ここで留意しなければならないのは、このような配当慣行を平成18年改正のときには全く無視しているわけです。評価通達上の流れの中で昭和58年にその配当慣行を考慮したことと平成18年に評価通達を改正したときには、これを考慮せずにある意味では無謀な通達改正をやってしまったということなのだと思います。昭和58年改正と平成18年改正をもう少しきちんと対比させる必要があると思います。
緑川:配当ということについて50円換算であれ、実施していた時代であったと思いますし、受け取った方も1株当たり50円換算でいくらになるかというようなことをやっていた時代だったと思います。それをなぜやるかというと、配当の利回り計算ということです。そこには何もありません。配当を10%で還元するだけです。10%がいいかどうかは別にして、少数株主は受け取った配当を還元すればよいということについて対応していたのだろうと思います。付け加えますと、平成13年の商法改正で額面株式も廃止されました。廃止になっても評価通達には何も手を入れず、受け取った配当を10%で還元すればよいというスタンスをとっていたと思います。このような理解でよろしいでしょうか。
品川:そう思います。これは昭和58年の改正の延長線上の問題で額面が廃止されても、もとは50円株、500円株、5万円株だという考え方でそれ以前に出資している人たちは、1株50円で出資したり、1株500円で出資したりという額面概念で所有しているわけです。その出資に対して何%の配当がもらえるかということであれば、配当を払う会社の方としても本来の2割配当であれば1株当たり10円になるということを慣例的に置き換えて配当しているはずだと思います。
緑川:平成25年の現在も配当利回りと同じ考え方だと思います。
「資本金等の額」への変更による影響~平成18年改正
緑川:問題の平成18年改正、ここが今日の一番のテーマとなりますが、平成18年度の税制改正で法人税法は資本の区分を整理し、資本金と資本積立金を一本化。資本金等の額にしました。これを受けて、法人税の世界では、別表五の(1)資本金等の額の計算に関する明細書により、資本金とそれ以外とを分けています。法人税法は、貸倒引当金設定対象法人や交際費の限度額計算、留保金課税などはこれをすべて資本金の金額で行っています。別表五の(1)を直して分かるようにしています。
ところが、財産評価基本通達は配当還元価額の計算式を、「資本金の額」から「資本金等の額」に変更してしまいました。これについてはどう思われますか。
品川:結論的には、これまでの配当支払いの慣例を非常に無視したことになると思います。国税庁は、評価通達の改正の趣旨について、平成17年の会社法により資本金制度において資本金がゼロでも会社が設立できるとか、いうならば資本金という概念はなくなったということで評価通達もそれに対応する必要があるという説明で終始しているわけです。しかし、その結果、実務的に様々な不都合が生じてきていると思いますが、その例について、緑川先生から事例を説明していただければと思います。
緑川:たとえば、これがどういう場合に影響が出てくるかということで事例の1と2を作成しました。簡単に事例の1と2を説明させていただきます。まず、事例1というのは単純な場合です。第三者割当により10億円増資しました。それは当然に時価純資産価額を基準として発行しています。そうしますと増資後、図のようになります。増資前の配当還元価額の計算は50円です。しかし、時価発行増資を実施しますと、その10億円全額が資本金等の額になり、これを受けて、増資後の配当還元価額は500円と10倍になります。
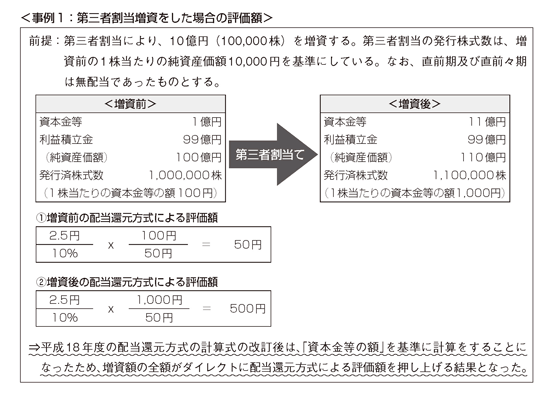
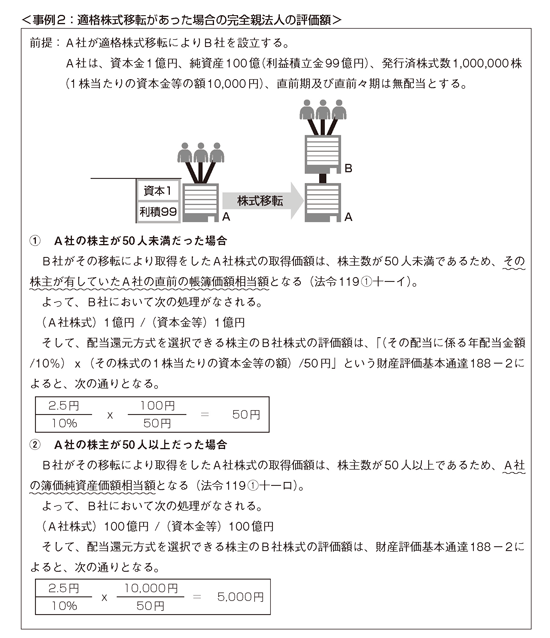
ある程度、第三者割当時価発行増資を考える場合というのは会社支配に関するものであり、少数株主には全く関係ありません。配当が上がるわけではありません。逆に下がるかもしれません。にもかかわらず、配当還元価額が資本金等の額のベースになったことによって、まったく資本金等の額を知らない、申告書を見ることができない少数株主にこれほどの影響を与えることになります。
さらにおかしいと思うのは事例2です。適格株式移転があった場合をここで示しています。特に組織再編の場合というのは、配当還元価額の計算に非常に影響を及ぼします。なぜなら、再編が資本金等の額に非常に大きな影響を及ぼしているからです。再編をしますと、少数株主の配当還元価額は上がるというのが現在の実務だと思います。それを典型的に表すのが株式移転だと思います。
事例2は、A社の上にB社を株式移転で設立します。株式移転の場合、B社の資本金等の額は、A社株式の取得価額となりますが、これが株主数50人未満と50人以上の場合とで異なります。まず、50人未満だった場合のB社の資本金等の額は、A社の株主が有していたその帳簿価額相当額です。したがって、資本金等の額は1億円のままなのです。ところが、株主が50人以上だった場合、B社の資本金等の額となるA社株式の取得価額は、A社の簿価純資産価額相当額と定められています。B社の資本金等の額は、A社の株主が50人未満ですと1億円ですが、50人以上だと100億円になってしまいます。この場合、②のケースの配当還元価額は5,000円と①のケースの100倍になります。これを普通に考えますと、50人未満というのは少数株主の方も少し影響力があるような気がしますが、50人以上、たとえば話題になっているのは500人といったケースです。株主が500人規模の会社なんて、少数株主は全く経営に関与できません。そのような人たちの配当還元価額が、50円から5,000円になってしまうのです。少し血の色の濃い50人未満の遠くの親戚のような会社には都合がよくて、本来の意味での少数株主が5,000円になってしまいます。これは、法人税法の資本金等の額に評価通達が変更したことのおかしさだと思っています。組織再編というと中小ではあまりなく、大体が株主50人以上なのです。
品川:事例1を考えた場合、増資をした場合に、商法改正でその出資をした場合に2分の1以上は資本金に組み入れなければならないとされています。また、増資しなくても問題が生じます。昔は特に有限会社というのは100億円出資しても、資本金は1億円で資本積立金額を99億円にするということがよく行われていました。その方が登録免許税も少なく済みますので、そのような会社ばかりを作っていたのではないかと思います。このような会社は、今まではこの50円で評価できたのに、通達が変わった途端に500円になってしまう。

緑川:何もしていないにもかかわらずです。
品川:何も経済環境に変更がなくて、なぜ評価通達の改正で500円に変える必要があったのかというのは説明ができません。会社法や法人税法が変わったら株価が上がるのかというとそういうわけではありません。100億円出資して50億円を資本金、50億円を資本剰余金で処理したような場合でも、10倍とは言わなくても何倍かは跳ね上がってしまいます。そういう意味で、平成18年の評価通達改正というのは相当矛盾を抱えています。
結果的に、資本金等の額(50円)で割り戻すという考え方は、限りなく純資産価額の半分で評価をしなさいということに近づきます。無配当でもその純資産価額が全部資本金等の額に反映されているような場合には、純資産価額の半分で評価されるということになりかねない。これは本来の配当還元方式の趣旨に反します。だから、国税庁が平成18年に通達を改正した際に、会社法が改正されて資本金がゼロでもよいことになった、法人税法が改正されて全部資本金等の額に組み込まれたからという説明は全く的を得ていないわけです。
しかも、昭和58年の評価通達改正の時には、わざわざ配当還元価額が額面を意識して1株当たりの配当金額を決定しているということを考慮した通達改正をしているわけです。平成17年に会社法が変わり平成18年に法人税法が変わったからといって、現在でも、会社が配当するときには、額面に相当する金額に対応した、500円とか50,000円に対して何%配当する必要があるというところから1株当たりの配当金額を決定しているはずです。そういう慣行をも無視しているわけで、平成18年改正というのは、配当還元方式の性格というのを非常に変えてしまった。変える必要が本当にあるのかないのかということを、通達を改正した側がもう少し丁寧に説明しないと、ご指摘の事例があるように、納税者は納得できないのではないかと思います。
緑川:私も実務で組織再編をよく行いますが、少数株主の方にこの評価はおかしいとはいえないのが実際です。少数株主の方には税理士もいますし、逆に迷惑をかけてしまいます。配当還元価額というのはそもそもこういうものであり、資本金等の額になったことは誤りだから、裁判しましょうよと言いたいのですが、なかなか争ってくれません。多くの方が評価通達どおりに何の抵抗もなく受け入れていますので、これについて明確にして欲しいというのが一番です。この事例は1も2もあえて無配当としました。無配当でも2.5円が残っているわけです。
品川:無配当なら2.5円というのは、額面株式当時の考え方からいえば、額面の半分の価値はあるだろうという推定にすぎません。たとえば従業員持株会の場合、取引がないとしても、その持株会において額面相当額の売買は可能です。無配当だからゼロとすると評価額がゼロになるが、いくらなんでもゼロということはないだろう。結局は、半分くらいは会社に対して請求権(請求する価値)があるだろうということです。持株会等の存在を考えた場合には、この額面の半分で評価するという考え方にはそれなりの合理性がありました。ところが、本件のように片方は純資産価額に近い価格で割り戻しておいて、この無配当でもその2分の1に近づけるというのは、そもそも2円50銭とした当初の制度の趣旨にも反することになります。
緑川:利益があっても無配当にするから2.5円だというのはわかりやすいのですが、それはあくまでも10%還元しているからです。資本金等の額にしたのは、10%の還元を捨てたということです。捨てたのにこの2.5円が相変わらず残っているというのは非常にバランスを欠いているということだと思います。
品川:通達上の問題は、個別には指摘できますが、指摘できたからといって見直してくれるかというのは別の問題です。国税庁としては、通達は職員に対する行政上の命令手段であるから、外野の人に何か言われる筋合いはないといえます。納税者サービスのために情報公開して、これで申告をしたら認めますというだけの話です。それがいやであれば時価をきちんと算定して申告すればよいということです。これも当局の1つの考えだと思います。
ただ、通達の実質的な法規範性を考えた場合、納税者側から積極的にこの通達はおかしいから見直したらどうですかというのは、結局訴訟しかありません。裁判で平成18年の改正はその趣旨から外れて本来の少数株主の経済価値を測定する評価方式として合理性があるとは認められないという判断があって、初めて国税庁としては直すということになるわけです。
もう1つは、最近色々事例があるようですけれど、週刊T&Amaster423号(2011年10月17号)4頁でも紹介された評価通達186-2のように、問題のある通達に関する課税処分については通達を直さずに、減額処理して個別案件として処理されてしまうこともあります。この場合には、納税者として争うこともできなくなってしまいます。
会社法上の問題は?
緑川:株式保有特定会社かどうかで争われた東京地裁平成24年3月2日判決(本誌445号4頁参照)をみても、たしかに評価通達は税務職員のマニュアルと書かれています。マニュアルに対して訴訟をするしかないというのはわかりますし、納税者が従う必要はないということもわかります。しかし、この問題は、少数株主が保有している株式の評価について、事例1で、たとえ平成17年にその出資額の2分の1を資本金として第三者割当をしていたとしても、平成18年改正で「資本金の額」ではなくて、「資本金等の額」で配当還元価額の計算を行うことにより、平成18年になると500円の評価になってしまうのです。会社法上、収益還元方式における配当還元価額は、ともに50円なのです。自己株式を取得する場合、会社法上許されるのでしょうか。
品川:会社法上、株式を引き取るような場合には、株主平等の原則がありますが、これは会社法の中での話であって、課税上不平等に扱われても会社法としては別に関係はありません。
緑川:評価通達の評価により500円で自己株式を取得したら会社法上の問題がでると思います。高額買取ですので、会社法上、株主に対する利益供与という取締役の問題がでます。
品川:高額であればということです。
緑川:会社法上は高額だと思います。
品川:会社法上は当事者が買い取れば別に問題はありません。実質的な資本払い戻しとか取締役の注意義務違反がなければ、いくらで買い取ってもいいわけです。
緑川:会社法上、少数株主で争いがあった場合に鑑定書を書きます。少数株主であれば、収益還元方式としての配当還元価額を算出しますが、これは利回り計算です。したがって、2.5円にもこだわっていませんし、資本金等の額にこだわらず、単純に利回りで割り戻すだけです。平成17年のときと平成18年のときに鑑定書を書く際、利回りを計算するとやはり50円は50円なのです。納税者を拘束するものではありませんが、国税庁から何か言われたくないために、仮に会社が評価通達のとおりに500円で買ったのであれば、やはり株主に対する利益供与になると思います。
品川:本来、会社法上は特に500円に引きずられることはありませんが、500円で買取りをしないと課税問題が生じることであればそうなると思います。
緑川:課税問題を起こすことを助長していると思います。評価通達は、株主に対する利益供与を認めていることと同じです。課税上問題がなければ、利益供与をしても構わないということと違いはありません。
品川:この点、先ほど言ったように組織再編前後で比較した場合、再編を行ったのだから価値も変わったのではないかとカモフラージュされてしまいます。そもそも資本準備金に99億円積み立てていたものが平成18年の通達改正で突然、50円だったものが500円になるというのは、本当に相続税法22条の時価を反映しているのかというと、合理性があるとは言い難いのではないでしょうか。
緑川:事例1や2が特殊なものと言われるかもしれませんが、そもそも論として間違っていると思います。評価通達はマニュアルだから当局の思うとおりにやればいいのではないかとは思いますが、実務的に会社法違反を助長するのはいかがなものかと思います。
品川:結果的にはそうかもしれませんが、会社法の運用上、自主性がないためにそうなるのではないかと考えます。
緑川:さらに言いますと、組織再編成税制の平成18年までは資本金と資本積立金と一緒にしただけですので明確ですが、平成22年のグループ法人税制については損出し規制であり、損を資本金等の額に振り替えるわけです。損を認めず、譲渡損を認めないがために相手科目に資本金等の額を持ってきています。資本金等の額は滅茶苦茶になっているのです。
品川:そう思います。
緑川:そうなったときに評価通達をマニュアルとしている人たちが正しい資本金等の額を算出できるかどうかは疑問が残ります。
品川:評価通達は、同族株主の範囲の問題について、これまで是々非々で法人税法に対応していたわけですから、法人税法が資本金等の額にしたからと言って評価通達もそれに合わせる必要性は全くなかったと思います。平成18年の通達改正は勇み足だったのではないかと思います。
緑川:グループ法人税制の問題点をあげたらキリがありませんが、資本金等の額で調整したことによって、会社の計算の問題が少数株主の配当還元価額の計算に影響するわけです。本当に少数株主の贈与税の問題にまで影響させてよいのでしょうか。
品川:本来はそうあってはいけないと思います。評価通達は淡々と少数株主が持っている株式の価値とは何かということを前提に評価方法を組み立てているわけであり、ご指摘のような矛盾したケースをどこまで想定したかというのは疑問です。少なくとも国税庁の公式的見解と言われる財産評価基本通達逐条解説にはそういうことは一切説明されていませんし、その後の国税庁の説明でも何も言われていません。
緑川:今までの配当還元価額というのは安すぎたということで、資本金等の額にして通達レベルで課税ベースを拡大しましたということであればまだ納得がいきます。確かに、擬似的な配当還元価額も実務的にはあるようですが、それは別途対応すればいいのです。
品川:そのように開き直るのも一つの見解かと思いますが、世間的な相場から考えると、純資産価額が100であれば、類似業種比準価額は平均的には20~30前後なのです。それを配当還元価額を純資産価額の最大5割まで持っていけるという発想自体がナンセンスだと思います。
緑川:そうであれば少数株主は、原則的評価より高い。
品川:昭和39年改正よりもまだ厳しくなる可能性はあります。
緑川:類似業種比準価額との選択も認めてもらわないとおかしな話になります。
品川:これまでの個別事例の中でも、この配当還元方式で評価する評価額がその会社の類似業種比準価額の倍くらいになっている事例がいくつもあります。
緑川:少数株主が中心的な同族株主の評価額よりも高くなってしまいます。
品川:現にこのような会社の事例について、私は意見書を書いたことがあります。
緑川:極端な例ではありますが、争うしかなくなります。
品川:昭和60年前後から平成の初めにかけて、持株会社を作って節税策を講じた際に設立された会社というのがいまでもまだ多く存在しています。100億円を出資しても資本金は1億円で99億円は全部資本積立金にしておき、配当は無配当でずっと何十年も継続して、少数株主の場合、今までは額面の半分で評価すればよかったわけですが、それが純資産価額の半分で評価することになると、何のために通達改正をしたのか理解できません。ただ単純に会社法が資本金ゼロでもいいという制度をつくり、翌年に法人税法が改正されて資本金等の額に統一されたので、それに合わせたということであれば、そもそも取引相場のない株式の時価とは何かということについて、配当還元方式が導入された当初の趣旨あるいは昭和58年の通達改正の趣旨等と相当乖離してしまっています。
問題提起は専門家の役割
緑川:品川先生が担当された株式保有特定会社で封じ込められましたが、平成2年の改正からすでに20年以上経過しています。現在の実務は何か事業を付加して株特を外しにかかっているわけです。そうして、類似業種比準価額で評価できる会社をつくるわけです。配当還元価額が50%で類似業種比準価額が30%とすると、配当還元価額の方が支配株主よりも高くなってしまいます。そうであれば、純資産価額との選択ではなくて、類似業種比準価額の選択を認めるべきとしか言えません。
品川:ご指摘のとおりだと思います。しかし、通達のいろいろな矛盾点というのは、外野が騒いでいても難しいのが実情です。訴訟を提起するしか手段はないかもしれません。
緑川:通達は税務職員のマニュアルですから、実務界で何か言っても直らないと思います。
品川:しかし、問題提起をしていくのは専門家の役割でもあると思います。やはり税の専門家は通達に盲従してはいけません。通達について、理論的におかしいところがあれば指摘することが必要です。
緑川:最後になりますが、先ほど述べた東京地裁平成24年3月2日判決は大賛成で、納税者側からすると、評価通達が税務職員のマニュアルでないと困るわけです。ただ、納税者は、マニュアルのおかしな点があれば争わなければいけないと思うのです。マニュアルであることは、人によって課税価額が違いませんので一番安全なわけです。25%の株特の割合についても25%があるから安全なのです。これが事実認定ですと言われたら実務ができなくなってしまいます。したがって、25%という割合がおかしいのではなくて、25%の杓子定規での適用は間違っている、と納税者は争うということになるのだと思います。
配当還元価額についても同様ですかね。しかし、原則と例外とが逆の気もしますが。
本日は、配当還元方式の改正の変遷とその問題点について議論させていただき、ありがとうございました。
(了)
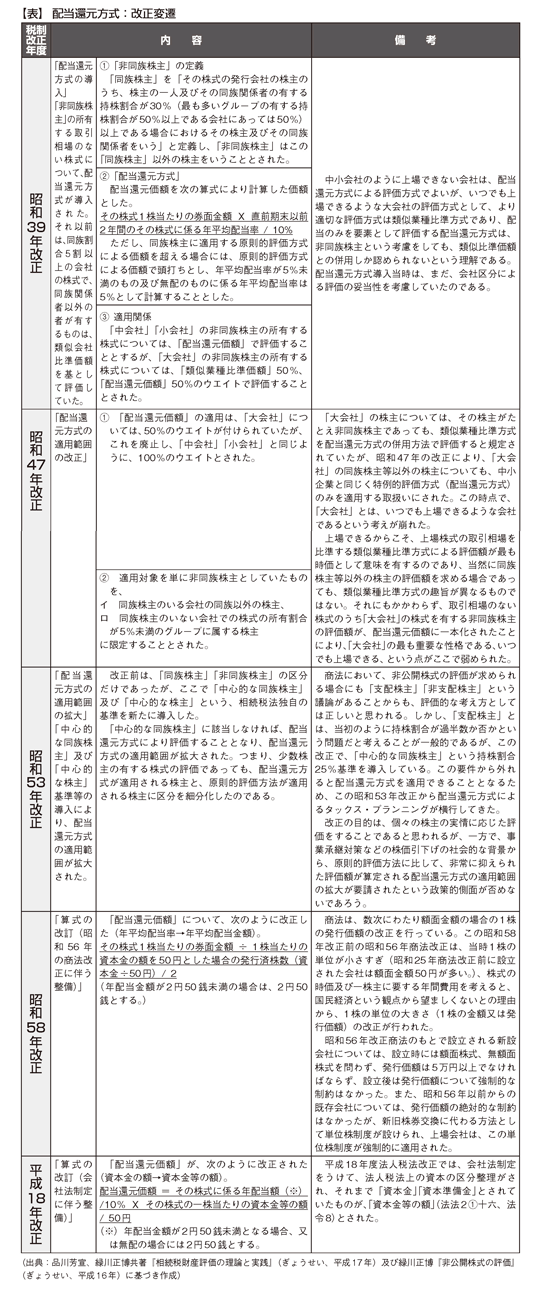
「資本金等の額」への変更により配当還元価額が急騰
平成18年度改正で生じた配当還元方式の問題点
品川芳宣(筑波大学名誉教授/弁護士)
緑川正博(公認会計士/税理士)
平成18年度税制改正により、法人税法は、資本金と資本積立金を一本化し、資本金等の額に変更した。これを受けて財産評価基本通達は、配当還元方式の計算式について、「資本金の額」から「資本金等の額」に改正した。その結果、少数株主の評価額である配当還元価額が、改正前の取扱いに比べてかなり上昇することになるという問題が生じている。対談では、国税庁在職中には財産評価基本通達の策定に携われた品川芳宣先生をお招きし、緑川正博先生とともに財産評価基本通達における配当還元方式の改正の変遷(32頁の表参照)を辿りながら、その問題点について論じていただいた。
配当還元方式が導入された経緯とは?~昭和39年改正
緑川正博氏(以下、敬称等は省略)
本日は品川芳宣先生をお招きして、財産評価基本通達における配当還元方式の問題点について議論していきたいと思います。配当還元価額は、所得税および法人税の通達にそのまま準用されています。また、平成18年の評価通達の改正でこの評価方法の計算が「資本金の額」から「資本金等の額」に見直されたことにより、配当還元価額がかなり上昇するという問題が生じています。特に、組織再編成を行う場合には、顕著に影響が生じています。そもそも配当還元価額とはどのようなものであるのかという点について、ご意見をお伺いしながら、最後に平成18年改正の資本金等の額についての議論をしていただければと思っています。
まず、昭和39年に配当還元方式が導入された経緯というのはどうだったのでしょうか。
品川芳宣氏(以下、敬称等は省略)
もともと取引相場のない株式の評価方法というのは、基本的には3つあります。純資産価額方式、比準方式、収益方式です。このうち、収益方式に関しては、本来、配当を基準にするやり方とその会社の収益力を反映して評価する方法の2つに分けて考えることができますが、実際の収益力を反映した評価方式というのは、将来の収益力の見込みや還元率をどうするかなど、非常に難しいものです。むしろこれは企業会計などで対応されています。
税法は、その収益方式の中の最も簡便な配当還元方式を伝統的に採用しているわけです。収益方式は本来、少数株主だけではなくて、原則的評価方式の1つとして考えられるのですが、通達は、配当に限って少数株主への配慮として配当還元方式を採用しているわけです。この場合、少数株主においては、株式を所有していることについて、配当しか期待できないという経済的価値を10%という還元率で現在価値として置き換えるのが基本的な考え方です。また、もう1つ言えば少数株主というのは、会社の決算書の中身がわかりませんので、評価の簡便方法として寄与してきたと言えます。
そういう意味で、昭和39年に導入された配当還元方式は、収益方式のワンオブゼム(one of them)の1つであり、少数株主に対する経済的価値の測定と簡便的な評価方式であるという2つの要素を兼ねているということだと思います。
緑川:昭和39年当時というのは、中小会社のほとんどが株主総会を開催していないのが現状だったと思います。このような状況で、配当だけを還元するというのは非常に理解できます。現在は、中小会社でも招集通知を出さないような会社はなくなってきていると思いますが、類似業種あるいは純資産にしても申告書を見ないとわかりません。申告書を見られない少数株主がどうやって配当還元価額を計算できるのでしょうか。
品川:実際の配当を基準に通達の定める方程式に当てはめ、10%還元することで実務は回っています。10%の率の是非はともかくとして、配当をもらうだけの少数株主にとっては簡単に評価できて申告にも支障がありません。また、従業員持株会のように、かつては額面価額で買い取るという売買が行われているという慣行もあるわけですので、株式を保有していればいずれは額面で買い取ってもらえるという意味で額面を基準とした配当還元方式というのは、それなりに説得力があったのではないかと思います。
緑川:1つの評価方式としてわかりやすかったと思います。
法人税法を準用する理由は?
緑川:もう1つ疑問なのは、財産評価基本通達が法人税法を準用したりしなかったりする点です。たとえば、法人税法施行令4条の「同族関係者」を株式の評価の中に持ってきて同族判定にそのまま使ったりしています。基本的に同族関係者の判定ということについて、法人税では留保金課税という年度・年度の判定だと思うのですが、相続税・贈与税というのは、個人のことでいつどうなるかわからないし、かといって個人のことは会社が知る由もありません。なぜ、法人税法の規定をそのまま持ってきているのですか。
品川:評価通達は、基本的に相続税や贈与税という特定の税目を対象に出来上がっています。通達自体は、相続税法の解釈として国税庁が発遣しているので、本来、法人税法とは独立した概念です。ただ、通達上用語の定義をするに当たっては、関連する会社法なり法人税法の規定を参酌し、取引相場のない株式の評価に有効な定義として借りてくるということはよくあることです。
法人税法施行令が定めている同族関係者の範囲なるものは、所得税法でも採用されておりますし、評価通達でも参考にしています。いわば同族関係者とは何かというようなことを議論する場合に、この概念を持ってくるのが最も無難といいますか、最も広く支持されているという意味で評価通達上もその範囲で同族判定をしようということにしているわけです。ただ、個々の結果論として、弊害が生じてくるという場合もままあるということだと思います。

緑川:特にこだわるわけではありませんが、同族関係者の中で法人税法施行令4条1項4号なる「生計を維持しているもの」という世界がありますが、生計を維持していることについて、相続税の評価というのは客観的交換価額を標榜する以上、客観性が必要だと思います。生計を維持しているかどうかというのは客観性の問題ではなくて、その時々の主観性の問題だと思うのです。ある時はあるかもしれないし、ないときはないかもしれません。問題は法人税法が定めているからですといって逃げられるかもしれませんが、これについてやはり問題点として残るのではないでしょうか。
品川:生計を維持しているというのは言葉遊びの問題ではなくて、結局は事実認定の問題です。事実認定について、法人税の世界、所得税の世界、相続税の世界を切り離して考えるのはなかなか難しいと思います。
緑川:法律に書いてあるものについて、事実認定を行うのならわかります。しかし、通達が法律を準用して事実認定だというのは逆だと思います。
品川:通達も相続税法22条の時価とは何かというのを想定して時価の解釈基準として発遣しているわけです。取引相場のない株式について、同族株主がいるのかいないのかということによって評価を区分すると、同族株主とは何かということについて、本来の法の趣旨に照らして相続税法では同族株主とはこういう概念を導入するのだと独自に決める方法もあります。
しかし、他の国税の中ですでに概念が確立されていることであれば、もともと法人税法の同族会社という概念が法人税法が制定されたときからあるわけですから、それにしたがって評価通達で定義を明確にするというのは、評価通達でも独自にその概念を導入したことになります。法人税法の取り扱いと同じにしたということとは少し違うのです。
緑川:単純に評価通達は画一的処理が求められるのだから、事実認定してはならないと思っているわけです。
品川:たとえば、最近問題になっている広大地の評価も、最後は事実認定です。
緑川:それはあくまでも評価の適正についてだと思います。ところが、個人のプライベートなことを誰が事実認定できるのでしょうか。
品川:たとえば、最近の裁判で一番問題となったのは、所得税法56条の生計を一にしている親族等に支払った役務提供の対価の額が必要経費になるかどうかです(最高裁平成16年(行ツ)第23号 平成16年11月2日第三小法廷判決、本誌135号参照)。夫である弁護士が税理士である妻に申告書を書いてもらった場合、その税理士費用について争われたものです。生計を一にするかどうかということで、それぞれの報酬で生活しているのだから認められるというものと、夫婦である以上、区分することはできないだろうと、そういう非常に人様の生活、内情にまで首を突っ込み、生計を一にしているか否かが争われましたが、結局、最後は事実認定の問題となりました。
緑川:中小企業の事業承継税制でも、措置法であるのに法人税法を準用せずに別に定めているわけです。法律のレベルでさえそうです。
品川:もともと措置法も法人税法も独立した法律ですので、全く違います。措置法にいたっては、所得税法の特例、法人税法の特例、相続税法の特例などがあって、その特例ごとに概念が違うわけです。
緑川:意味はわかります。付け加えれば、中小企業事業承継税制は、役員給与の過大の判定は法人税法と同様となっているものの、組織再編成税制は、別途規定しています。わかりやすいところは準用して、わかりづらいところは準用しないというのがおかしいと思います。
品川:その点は、立法政策的に妥当かどうかという問題は残ると思います。
大中小の計算方法を同じにした理由は?~昭和47年改正
緑川:昭和47年の税制改正により、大会社の50%ウェイトをはずして「小会社」と「中会社」と同じ計算方法にしました。この点はたしか中小企業事業承継税制が騒がれた初めの頃だったと思いますが、その経緯はどうだったのでしょうか。
品川:「大会社」「中会社」「小会社」に区分して評価方法を変えるという流れが昭和39年から続いていたわけですが、同じ大中小に区分する意味合いが地価の上昇に伴って変わってきました。
もともと大会社というのは、いつでも上場できるだけの一定規模の会社であって、ただ政策的に上場していないだけだとされてきました。したがって、課税時期では上場していないけれども、いつ上場するかもしれない会社の株式の評価については、少数株主に関しても上場すれば市場価格が明らかになるわけですので、類似業種比準価額なり純資産価額なり、その同族株主に課せられる評価方式も当然、同じように考慮せざるを得ません。そういう意味で当初の大会社を区分したときには、いずれは上場することを考慮して少なくても半分は原則的評価方式を反映させる必要があるということで50%基準を導入したと思うのです。
ところが、ご指摘のように、昭和47年というのは、列島改造ブームなど、要するに会社が所有する土地の値段が値上がりしたことで中小企業の事業承継問題が非常に深刻になってきたわけです。売ることのできない株式が、土地の値段の上昇とともに評価が上がり、相続税の負担が厳しくなって、何とか事業承継を円滑化にできる方法を考えざるを得ないということがありました。
何とか中小企業の株式承継が円滑にできるようにするためには、どのような理屈で評価減ができるかということを考えたわけです。そのような背景の中で大会社なるものは、いつでも上場する、上場したら少数株主もきちんと上場株価が保証されるという概念から、大中小の概念は本来の考え方を引き継ぎながらいかにして取引相場のない株式の評価を穏便にすまして事なきを得ようといういわば時代の走りであったわけです。結局、大会社と区分されたとしてもいつ上場するかわからない場合が多いし、そうであれば小会社、中会社と同じように配当還元だけでよいのではないかということになったわけです。仮に近々上場するのであれば、その時に然るべく評価方法でやればよいということです。ここは本来の理屈があって改正したというよりも基本的には事業承継対策について、株の評価のうえで対応せざるを得なかったということです。それが最も顕著に現れたのが昭和58年の改正だったと思うのです。
緑川:時代の走りと言いましたけれども、あえて言うなら評価通達が時価から離れた走りといえるのではないでしょうか。
品川:ご指摘のとおりです。
緑川:評価通達が時価を標榜しながらも時価ではないといった走りであり、その後の評価通達は、時価ではなく課税価格を定めるものとなっています。
品川:この時期から時価とは何かというよりも事業承継等その政策手段として、評価通達が使われ始めたということです。
配当還元方式の適用範囲の拡大~昭和53年改正
緑川:昭和53年改正で配当還元価額の適用できる範囲が拡大されました。これについてはどのように理解したらよいのですか。
品川:先ほど指摘した事業承継対策問題や地価の上昇といった背景の中で、単純に同族株主以外の株主、すなわち少数株主の概念で配当還元が従来どおり適用されるものと、同族株主といえども非常に支配力のない株主が現れてくるわけです。同族関係者の括りの問題にも関係しますが、その同族関係者を親族、すなわち6親等以内の親族で括るというのはある意味で相当無理があります。
緑川:6親等以内の親族のすべてを知っているわけではありません。
品川:そのとおりです。そのような括りに無理があったことに加えて、同族株主の間では支配層と非支配層が存在するという問題がありました。直接のきっかけは、同族株主だからといってひと括りに評価するのはおかしいということが国会で問題になったわけです。これを踏まえ国税庁は実態調査を行い、その結果、配当還元方式が適用される株式が拡大されたわけです。
緑川:昭和53年改正では中心的な同族株主を作り、血の濃さの括りを狭くしたわけですが、同族関係者は変わりませんでした。
品川:そもそも同族関係者の範囲を親族で区切るのが無理だと思うのです。せめて4親等内の血族とか3親等内の姻族などの範囲でしないとならないと思います。その矛盾は今でもずっと引きずっているわけです。
緑川:やはりどこかで見直さなければならない問題であると思います。
商法改正による額面株式の廃止~昭和58年改正
緑川:商法の改正で無額面株式が出来ました。これを受け、昭和58年の改正では計算式の改訂がされましたが、なぜ50円で割り戻すことになったのでしょうか。やはり配当利回りにこだわっていたのですか。
品川:このときの改正については、この前年に税制調査会で事業承継税制の小委員会が出来ました。結論的には事業承継対策の税制は、この段階は採用する必要がないとの結論に至りました。
しかし、同じ会社であっても儲かっている会社と儲かっていない会社があるわけですので、一律に小会社に純資産価額方式を適用するのはおかしいとなりました。収益力を加味する評価方式にすべきだということで小会社に対しても類似業種比準方式を半分認めるべきという結論が出ました。いうなれば税制調査会の委員会でわざわざ時価の認定方法である通達を直すというレベルの低い答申を出すというナンセンスなことが行われたわけです。
緑川:全く同感です。
品川:昭和47年から先ほどのご指摘のとおり、評価通達の取扱いは本来の時価の理念から乖離し、さらに昭和58年はその乖離に拍車がかかってしまったのです。大幅に政策の手段として使われてしまったわけです。その中でご指摘の50円で割り戻すという話がありましたが、配当還元方式の評価に関しては、あまり関心が持たれなかったように思います。
もともとは昭和56年の商法改正において額面が廃止されました。ただ、なぜ50円で割り戻したかというと、戦後額面というのは50円というのが支配的であったわけです。支配的であったがゆえにそれは無額面株式になったところで1株に対する配当をいくらにするかというのは、ほとんどの会社において、額面とのバランスを考えて50円株で1割配当1株5円であれば、無額面でも1株5円にするといった配当政策上の慣行を重視したと思うのです。
ただ、ここで留意しなければならないのは、このような配当慣行を平成18年改正のときには全く無視しているわけです。評価通達上の流れの中で昭和58年にその配当慣行を考慮したことと平成18年に評価通達を改正したときには、これを考慮せずにある意味では無謀な通達改正をやってしまったということなのだと思います。昭和58年改正と平成18年改正をもう少しきちんと対比させる必要があると思います。
緑川:配当ということについて50円換算であれ、実施していた時代であったと思いますし、受け取った方も1株当たり50円換算でいくらになるかというようなことをやっていた時代だったと思います。それをなぜやるかというと、配当の利回り計算ということです。そこには何もありません。配当を10%で還元するだけです。10%がいいかどうかは別にして、少数株主は受け取った配当を還元すればよいということについて対応していたのだろうと思います。付け加えますと、平成13年の商法改正で額面株式も廃止されました。廃止になっても評価通達には何も手を入れず、受け取った配当を10%で還元すればよいというスタンスをとっていたと思います。このような理解でよろしいでしょうか。
品川:そう思います。これは昭和58年の改正の延長線上の問題で額面が廃止されても、もとは50円株、500円株、5万円株だという考え方でそれ以前に出資している人たちは、1株50円で出資したり、1株500円で出資したりという額面概念で所有しているわけです。その出資に対して何%の配当がもらえるかということであれば、配当を払う会社の方としても本来の2割配当であれば1株当たり10円になるということを慣例的に置き換えて配当しているはずだと思います。
緑川:平成25年の現在も配当利回りと同じ考え方だと思います。
「資本金等の額」への変更による影響~平成18年改正
緑川:問題の平成18年改正、ここが今日の一番のテーマとなりますが、平成18年度の税制改正で法人税法は資本の区分を整理し、資本金と資本積立金を一本化。資本金等の額にしました。これを受けて、法人税の世界では、別表五の(1)資本金等の額の計算に関する明細書により、資本金とそれ以外とを分けています。法人税法は、貸倒引当金設定対象法人や交際費の限度額計算、留保金課税などはこれをすべて資本金の金額で行っています。別表五の(1)を直して分かるようにしています。
ところが、財産評価基本通達は配当還元価額の計算式を、「資本金の額」から「資本金等の額」に変更してしまいました。これについてはどう思われますか。
品川:結論的には、これまでの配当支払いの慣例を非常に無視したことになると思います。国税庁は、評価通達の改正の趣旨について、平成17年の会社法により資本金制度において資本金がゼロでも会社が設立できるとか、いうならば資本金という概念はなくなったということで評価通達もそれに対応する必要があるという説明で終始しているわけです。しかし、その結果、実務的に様々な不都合が生じてきていると思いますが、その例について、緑川先生から事例を説明していただければと思います。
緑川:たとえば、これがどういう場合に影響が出てくるかということで事例の1と2を作成しました。簡単に事例の1と2を説明させていただきます。まず、事例1というのは単純な場合です。第三者割当により10億円増資しました。それは当然に時価純資産価額を基準として発行しています。そうしますと増資後、図のようになります。増資前の配当還元価額の計算は50円です。しかし、時価発行増資を実施しますと、その10億円全額が資本金等の額になり、これを受けて、増資後の配当還元価額は500円と10倍になります。
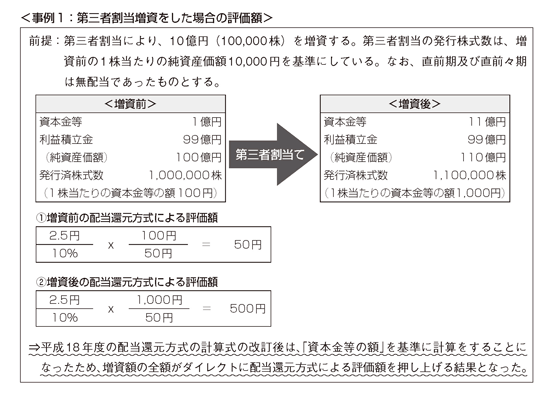
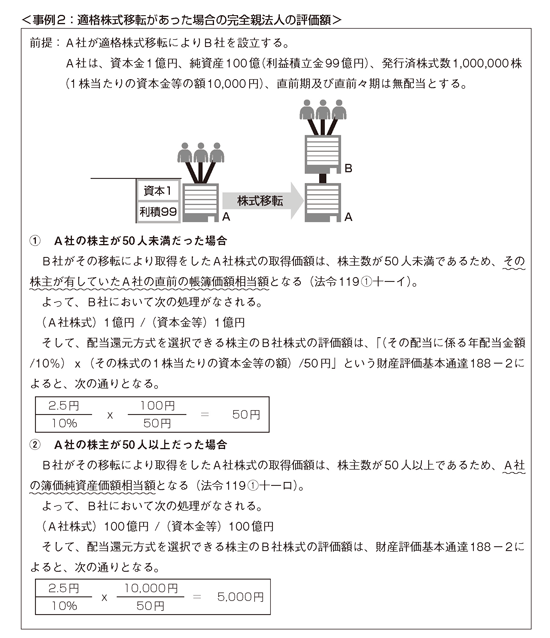
ある程度、第三者割当時価発行増資を考える場合というのは会社支配に関するものであり、少数株主には全く関係ありません。配当が上がるわけではありません。逆に下がるかもしれません。にもかかわらず、配当還元価額が資本金等の額のベースになったことによって、まったく資本金等の額を知らない、申告書を見ることができない少数株主にこれほどの影響を与えることになります。
さらにおかしいと思うのは事例2です。適格株式移転があった場合をここで示しています。特に組織再編の場合というのは、配当還元価額の計算に非常に影響を及ぼします。なぜなら、再編が資本金等の額に非常に大きな影響を及ぼしているからです。再編をしますと、少数株主の配当還元価額は上がるというのが現在の実務だと思います。それを典型的に表すのが株式移転だと思います。
事例2は、A社の上にB社を株式移転で設立します。株式移転の場合、B社の資本金等の額は、A社株式の取得価額となりますが、これが株主数50人未満と50人以上の場合とで異なります。まず、50人未満だった場合のB社の資本金等の額は、A社の株主が有していたその帳簿価額相当額です。したがって、資本金等の額は1億円のままなのです。ところが、株主が50人以上だった場合、B社の資本金等の額となるA社株式の取得価額は、A社の簿価純資産価額相当額と定められています。B社の資本金等の額は、A社の株主が50人未満ですと1億円ですが、50人以上だと100億円になってしまいます。この場合、②のケースの配当還元価額は5,000円と①のケースの100倍になります。これを普通に考えますと、50人未満というのは少数株主の方も少し影響力があるような気がしますが、50人以上、たとえば話題になっているのは500人といったケースです。株主が500人規模の会社なんて、少数株主は全く経営に関与できません。そのような人たちの配当還元価額が、50円から5,000円になってしまうのです。少し血の色の濃い50人未満の遠くの親戚のような会社には都合がよくて、本来の意味での少数株主が5,000円になってしまいます。これは、法人税法の資本金等の額に評価通達が変更したことのおかしさだと思っています。組織再編というと中小ではあまりなく、大体が株主50人以上なのです。
品川:事例1を考えた場合、増資をした場合に、商法改正でその出資をした場合に2分の1以上は資本金に組み入れなければならないとされています。また、増資しなくても問題が生じます。昔は特に有限会社というのは100億円出資しても、資本金は1億円で資本積立金額を99億円にするということがよく行われていました。その方が登録免許税も少なく済みますので、そのような会社ばかりを作っていたのではないかと思います。このような会社は、今まではこの50円で評価できたのに、通達が変わった途端に500円になってしまう。

緑川:何もしていないにもかかわらずです。
品川:何も経済環境に変更がなくて、なぜ評価通達の改正で500円に変える必要があったのかというのは説明ができません。会社法や法人税法が変わったら株価が上がるのかというとそういうわけではありません。100億円出資して50億円を資本金、50億円を資本剰余金で処理したような場合でも、10倍とは言わなくても何倍かは跳ね上がってしまいます。そういう意味で、平成18年の評価通達改正というのは相当矛盾を抱えています。
結果的に、資本金等の額(50円)で割り戻すという考え方は、限りなく純資産価額の半分で評価をしなさいということに近づきます。無配当でもその純資産価額が全部資本金等の額に反映されているような場合には、純資産価額の半分で評価されるということになりかねない。これは本来の配当還元方式の趣旨に反します。だから、国税庁が平成18年に通達を改正した際に、会社法が改正されて資本金がゼロでもよいことになった、法人税法が改正されて全部資本金等の額に組み込まれたからという説明は全く的を得ていないわけです。
しかも、昭和58年の評価通達改正の時には、わざわざ配当還元価額が額面を意識して1株当たりの配当金額を決定しているということを考慮した通達改正をしているわけです。平成17年に会社法が変わり平成18年に法人税法が変わったからといって、現在でも、会社が配当するときには、額面に相当する金額に対応した、500円とか50,000円に対して何%配当する必要があるというところから1株当たりの配当金額を決定しているはずです。そういう慣行をも無視しているわけで、平成18年改正というのは、配当還元方式の性格というのを非常に変えてしまった。変える必要が本当にあるのかないのかということを、通達を改正した側がもう少し丁寧に説明しないと、ご指摘の事例があるように、納税者は納得できないのではないかと思います。
緑川:私も実務で組織再編をよく行いますが、少数株主の方にこの評価はおかしいとはいえないのが実際です。少数株主の方には税理士もいますし、逆に迷惑をかけてしまいます。配当還元価額というのはそもそもこういうものであり、資本金等の額になったことは誤りだから、裁判しましょうよと言いたいのですが、なかなか争ってくれません。多くの方が評価通達どおりに何の抵抗もなく受け入れていますので、これについて明確にして欲しいというのが一番です。この事例は1も2もあえて無配当としました。無配当でも2.5円が残っているわけです。
品川:無配当なら2.5円というのは、額面株式当時の考え方からいえば、額面の半分の価値はあるだろうという推定にすぎません。たとえば従業員持株会の場合、取引がないとしても、その持株会において額面相当額の売買は可能です。無配当だからゼロとすると評価額がゼロになるが、いくらなんでもゼロということはないだろう。結局は、半分くらいは会社に対して請求権(請求する価値)があるだろうということです。持株会等の存在を考えた場合には、この額面の半分で評価するという考え方にはそれなりの合理性がありました。ところが、本件のように片方は純資産価額に近い価格で割り戻しておいて、この無配当でもその2分の1に近づけるというのは、そもそも2円50銭とした当初の制度の趣旨にも反することになります。
緑川:利益があっても無配当にするから2.5円だというのはわかりやすいのですが、それはあくまでも10%還元しているからです。資本金等の額にしたのは、10%の還元を捨てたということです。捨てたのにこの2.5円が相変わらず残っているというのは非常にバランスを欠いているということだと思います。
品川:通達上の問題は、個別には指摘できますが、指摘できたからといって見直してくれるかというのは別の問題です。国税庁としては、通達は職員に対する行政上の命令手段であるから、外野の人に何か言われる筋合いはないといえます。納税者サービスのために情報公開して、これで申告をしたら認めますというだけの話です。それがいやであれば時価をきちんと算定して申告すればよいということです。これも当局の1つの考えだと思います。
ただ、通達の実質的な法規範性を考えた場合、納税者側から積極的にこの通達はおかしいから見直したらどうですかというのは、結局訴訟しかありません。裁判で平成18年の改正はその趣旨から外れて本来の少数株主の経済価値を測定する評価方式として合理性があるとは認められないという判断があって、初めて国税庁としては直すということになるわけです。
もう1つは、最近色々事例があるようですけれど、週刊T&Amaster423号(2011年10月17号)4頁でも紹介された評価通達186-2のように、問題のある通達に関する課税処分については通達を直さずに、減額処理して個別案件として処理されてしまうこともあります。この場合には、納税者として争うこともできなくなってしまいます。
会社法上の問題は?
緑川:株式保有特定会社かどうかで争われた東京地裁平成24年3月2日判決(本誌445号4頁参照)をみても、たしかに評価通達は税務職員のマニュアルと書かれています。マニュアルに対して訴訟をするしかないというのはわかりますし、納税者が従う必要はないということもわかります。しかし、この問題は、少数株主が保有している株式の評価について、事例1で、たとえ平成17年にその出資額の2分の1を資本金として第三者割当をしていたとしても、平成18年改正で「資本金の額」ではなくて、「資本金等の額」で配当還元価額の計算を行うことにより、平成18年になると500円の評価になってしまうのです。会社法上、収益還元方式における配当還元価額は、ともに50円なのです。自己株式を取得する場合、会社法上許されるのでしょうか。
品川:会社法上、株式を引き取るような場合には、株主平等の原則がありますが、これは会社法の中での話であって、課税上不平等に扱われても会社法としては別に関係はありません。
緑川:評価通達の評価により500円で自己株式を取得したら会社法上の問題がでると思います。高額買取ですので、会社法上、株主に対する利益供与という取締役の問題がでます。
品川:高額であればということです。
緑川:会社法上は高額だと思います。
品川:会社法上は当事者が買い取れば別に問題はありません。実質的な資本払い戻しとか取締役の注意義務違反がなければ、いくらで買い取ってもいいわけです。
緑川:会社法上、少数株主で争いがあった場合に鑑定書を書きます。少数株主であれば、収益還元方式としての配当還元価額を算出しますが、これは利回り計算です。したがって、2.5円にもこだわっていませんし、資本金等の額にこだわらず、単純に利回りで割り戻すだけです。平成17年のときと平成18年のときに鑑定書を書く際、利回りを計算するとやはり50円は50円なのです。納税者を拘束するものではありませんが、国税庁から何か言われたくないために、仮に会社が評価通達のとおりに500円で買ったのであれば、やはり株主に対する利益供与になると思います。
品川:本来、会社法上は特に500円に引きずられることはありませんが、500円で買取りをしないと課税問題が生じることであればそうなると思います。
緑川:課税問題を起こすことを助長していると思います。評価通達は、株主に対する利益供与を認めていることと同じです。課税上問題がなければ、利益供与をしても構わないということと違いはありません。
品川:この点、先ほど言ったように組織再編前後で比較した場合、再編を行ったのだから価値も変わったのではないかとカモフラージュされてしまいます。そもそも資本準備金に99億円積み立てていたものが平成18年の通達改正で突然、50円だったものが500円になるというのは、本当に相続税法22条の時価を反映しているのかというと、合理性があるとは言い難いのではないでしょうか。
緑川:事例1や2が特殊なものと言われるかもしれませんが、そもそも論として間違っていると思います。評価通達はマニュアルだから当局の思うとおりにやればいいのではないかとは思いますが、実務的に会社法違反を助長するのはいかがなものかと思います。
品川:結果的にはそうかもしれませんが、会社法の運用上、自主性がないためにそうなるのではないかと考えます。
緑川:さらに言いますと、組織再編成税制の平成18年までは資本金と資本積立金と一緒にしただけですので明確ですが、平成22年のグループ法人税制については損出し規制であり、損を資本金等の額に振り替えるわけです。損を認めず、譲渡損を認めないがために相手科目に資本金等の額を持ってきています。資本金等の額は滅茶苦茶になっているのです。
品川:そう思います。
緑川:そうなったときに評価通達をマニュアルとしている人たちが正しい資本金等の額を算出できるかどうかは疑問が残ります。
品川:評価通達は、同族株主の範囲の問題について、これまで是々非々で法人税法に対応していたわけですから、法人税法が資本金等の額にしたからと言って評価通達もそれに合わせる必要性は全くなかったと思います。平成18年の通達改正は勇み足だったのではないかと思います。
緑川:グループ法人税制の問題点をあげたらキリがありませんが、資本金等の額で調整したことによって、会社の計算の問題が少数株主の配当還元価額の計算に影響するわけです。本当に少数株主の贈与税の問題にまで影響させてよいのでしょうか。
品川:本来はそうあってはいけないと思います。評価通達は淡々と少数株主が持っている株式の価値とは何かということを前提に評価方法を組み立てているわけであり、ご指摘のような矛盾したケースをどこまで想定したかというのは疑問です。少なくとも国税庁の公式的見解と言われる財産評価基本通達逐条解説にはそういうことは一切説明されていませんし、その後の国税庁の説明でも何も言われていません。
緑川:今までの配当還元価額というのは安すぎたということで、資本金等の額にして通達レベルで課税ベースを拡大しましたということであればまだ納得がいきます。確かに、擬似的な配当還元価額も実務的にはあるようですが、それは別途対応すればいいのです。
品川:そのように開き直るのも一つの見解かと思いますが、世間的な相場から考えると、純資産価額が100であれば、類似業種比準価額は平均的には20~30前後なのです。それを配当還元価額を純資産価額の最大5割まで持っていけるという発想自体がナンセンスだと思います。
緑川:そうであれば少数株主は、原則的評価より高い。
品川:昭和39年改正よりもまだ厳しくなる可能性はあります。
緑川:類似業種比準価額との選択も認めてもらわないとおかしな話になります。
品川:これまでの個別事例の中でも、この配当還元方式で評価する評価額がその会社の類似業種比準価額の倍くらいになっている事例がいくつもあります。
緑川:少数株主が中心的な同族株主の評価額よりも高くなってしまいます。
品川:現にこのような会社の事例について、私は意見書を書いたことがあります。
緑川:極端な例ではありますが、争うしかなくなります。
品川:昭和60年前後から平成の初めにかけて、持株会社を作って節税策を講じた際に設立された会社というのがいまでもまだ多く存在しています。100億円を出資しても資本金は1億円で99億円は全部資本積立金にしておき、配当は無配当でずっと何十年も継続して、少数株主の場合、今までは額面の半分で評価すればよかったわけですが、それが純資産価額の半分で評価することになると、何のために通達改正をしたのか理解できません。ただ単純に会社法が資本金ゼロでもいいという制度をつくり、翌年に法人税法が改正されて資本金等の額に統一されたので、それに合わせたということであれば、そもそも取引相場のない株式の時価とは何かということについて、配当還元方式が導入された当初の趣旨あるいは昭和58年の通達改正の趣旨等と相当乖離してしまっています。
問題提起は専門家の役割
緑川:品川先生が担当された株式保有特定会社で封じ込められましたが、平成2年の改正からすでに20年以上経過しています。現在の実務は何か事業を付加して株特を外しにかかっているわけです。そうして、類似業種比準価額で評価できる会社をつくるわけです。配当還元価額が50%で類似業種比準価額が30%とすると、配当還元価額の方が支配株主よりも高くなってしまいます。そうであれば、純資産価額との選択ではなくて、類似業種比準価額の選択を認めるべきとしか言えません。
品川:ご指摘のとおりだと思います。しかし、通達のいろいろな矛盾点というのは、外野が騒いでいても難しいのが実情です。訴訟を提起するしか手段はないかもしれません。
緑川:通達は税務職員のマニュアルですから、実務界で何か言っても直らないと思います。
品川:しかし、問題提起をしていくのは専門家の役割でもあると思います。やはり税の専門家は通達に盲従してはいけません。通達について、理論的におかしいところがあれば指摘することが必要です。
緑川:最後になりますが、先ほど述べた東京地裁平成24年3月2日判決は大賛成で、納税者側からすると、評価通達が税務職員のマニュアルでないと困るわけです。ただ、納税者は、マニュアルのおかしな点があれば争わなければいけないと思うのです。マニュアルであることは、人によって課税価額が違いませんので一番安全なわけです。25%の株特の割合についても25%があるから安全なのです。これが事実認定ですと言われたら実務ができなくなってしまいます。したがって、25%という割合がおかしいのではなくて、25%の杓子定規での適用は間違っている、と納税者は争うということになるのだと思います。
配当還元価額についても同様ですかね。しかし、原則と例外とが逆の気もしますが。
本日は、配当還元方式の改正の変遷とその問題点について議論させていただき、ありがとうございました。
(了)
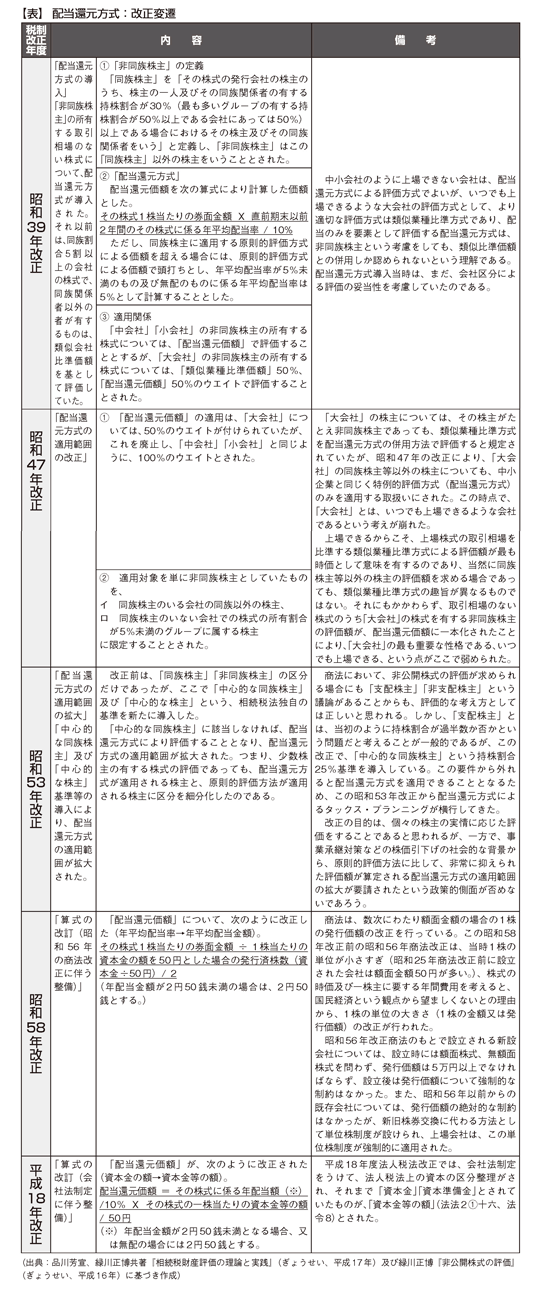
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -

Copyright (C) 2019
SHINNIPPON-HOKI PUBLISHING CO.,LTD.




















